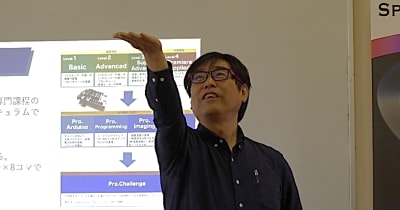学校教育の役割はプログラミングとの「良い出会い」をさせること 柏市が行うプログラミング教育とは?

2020年から小学校でのプログラミング教育が必修化されることが決まり、各自治体が様々な取り組みを始めています。中でも注目したいのは、2017年度から市内の全公立小学校でプログラミングの授業を行っているという柏市。なぜ、柏市は早い段階でスタートすることができたのでしょうか? その真相を明らかにするため、柏市教育委員会を訪れました。
30年前から全国に先駆けて行っている「情報教育」をルーツに持つという、柏市のプログラミング教育。学校教育部学校教育課の佐和伸明さんが、「別になにも隠してないですよ」と色々なお話を聞かせてくださいました。
ルーツは30年前?柏市のプログラミング教育誕生秘話

-なぜ柏市はプログラミング教育に早期から取り組むことができたんですか?
実は、柏市はもともと情報教育が盛んだったんです。小学校のコンピューター室が初めて作られたのは1986年で、日本では3本の指に入る早さでした。プログラミング教育に関しては1987年から行っており、当時は教材なんて何もなかったので、「ベーシック」というプログラミング言語を使って教えていました。日本語じゃないので教えるのがとても難しく苦労したみたいです・・・。
次の年に「LogoWriter(ロゴライター)」を使い始めました。これはコマンド(コンピューターへの実行指示)が全て日本語化されていて、「FORWARD」を「まえへ」、「RIGHT」を「みぎへ」など、日本語で打てるプログラミング言語です。これならアルファベットを知らない小学生でもわかるということで、これを使って図形を書いたりしていました。
その後10年ぐらいプログラミング言語を使った教育が続いていたのですが、パワーポイントや映像など、だんだんビジュアル化されたものが、世の中の教育に求められるようになっていったため、当時のプログラミング教育は忘れられていきました。
-そこから再び「プログラミング教育を実施しよう」となった経緯を教えてください
プログラミング教育が、文科省の学習指導要領に入るかもしれないという話が上がった時、「今ならまだ、30年前を知っている人もいるわけだし、時代が求めているならやるべきだ」と思いました。それで
この発表の翌月の8月に文科省が「次期学習指導要領に向けたこれまでの審議のまとめ」で、2020年からの小学校プログラミング教育の必修化が明らかになってきました。
-すんなり実施しようとなったのですか?
柏市が全国に先駆けてプログラミング教育を実施するために周りを説得するときに貫いたのが、「プログラミングは子どもがこれから生きていく上で必要な情報リテラシーですと伝えることでした。これから子どもが生きていく上で必要な資質能力で、誰にでも必要な能力です。」
だから、「学習指導要領に『載る』『載らない』は分かりませんが、柏市では子供たちにプログラミング的な思考力を育てていきましょう」と理解していただきました。もちろん、昔やっていたということも大きく、当時の生徒へのアンケート比較などを用いて、数字上の訴求も出来ました。
 画像実際に利用した約30年前の児童アンケート調査との比較
画像実際に利用した約30年前の児童アンケート調査との比較 学校教育におけるプログラミング教育の役割とは?
-柏市が行っている「プログラミング教育」の内容を教えてください
柏市ではICT教育(※)にも力を入れており、小学校1年生で「初めてのコンピューター」、3年生は「ローマ字入力」、5年生は「プレゼンテーション」、中学校では「情報モラル」を学びます。
その一環として小学校4年生で「プログラミング」を行うことにしました
また、4年生で取り入れることになったきっかけは、正直に言うと「ちょうど4年生のICT教育が空いていた」といった理由もあります(笑)。
でも本当は、それだけではなく、3年生でコンピューターの使い方、キーボードの使い方が終わっているという点、5年生の算数で正多角形、6年生の理科で電気のセンサーを授業で扱うことがあるので、4年生でプログラミングを学習することは理にかなっていることも理由です。
4年生で「プログラミングって何?」から始まり、「Scratch(スクラッチ)」というプログラミングツールを使って簡単な操作を身に付け、5年生で正多角形を教わった後、あらためて「Scratch」で正多角形を考えてみよう!ということが期待できます。それと、プログラミングの授業が終わった後に、授業の続きをやりたい学校があったときのことを考えて、夏休みの前の1学期にしました。
※ ICT教育とは・・・ 情報通信技術(Information and Communication Technology)に関しる知識を学ぶこと
-授業はどのように行われるのですか?
柏市ではICT教育を学校で実施するための支援として、「ITアドバイザー(ICT支援員)」事業を取り入れています。プログラミングの授業はICT教育の支援者2名とクラスの担任の合わせて3名で行っており、「ITアドバイザー」はプログラミングを教える人が1名とサポートに1名、と役割がわかれています。ただ、子どもが発表する段階になったら、メインは担任の先生に任せていますね。
-プログラミング教育において学校教育はどのような役割を担っていると思いますか?
一般的なプログラミング教育は、実際にプログラミングをやって、子どもたちが試行錯誤して多くのことを学ぶ、というのを理想としていますが、それをやるにはかなりの時間、テーマ、ツールが必要です。
柏市で行われるプログラミングの授業時間は、年間でたった2時間。その中で柏市教育委員会として目指しているプログラミング教育は「プログラミングといい出会いをしてもらう」ことです。
公立学校ですから、全ての子どもに平等に最初の一歩となる機会を与えなければいけません。もっとやりたいと思う子は、そこから自分でやることもできるので、教育委員会はプログラミングとの出会いのお手伝をしています。
自動販売機でジュースを買ったり、ゲームで遊んだりする時に、その機械はプログラミングによって動いているなんて、いちいち考えないですよね。でも、そこを考えさせることに教育の意味があるのです。
-2021年度から中学校でも「新学習指導要領」が施行されます。それについてはどう考えますか?
2021年に中学2年生になる子が、今現在小学校4年生です。 「新学習指導要領」では、技術の授業でプログラミングの指導内容、例えば「安全適切なプログラミングの制御、デバッグ」などが増えており、それを習う時に子どもたちが困らないように4年生の今から行うのが大切だと思っています。
小学校でこんな体験をしてきたから、中学校でこんなツールを使ってみようという風になるのが理想ですが、現段階では具体的には考えられていません。
 小学校での実証事業の様子
小学校での実証事業の様子 保護者から思わぬ反応が!「プログラミングの聖地」柏で起こっていることとは?
-プログラミング教育が始まって、保護者の方からどのような反応がありましたか?
これは僕が言っているわけではないのですが、柏市は「プログラミングの聖地」と呼ばれていて、それがステイタスになっています。
柏市には、大型の商業施設がいくつかあり、そこを使ってプログラミングのイベントや体験を何度も実施しているのですが、毎回応募は10倍を超えています。また,有料のプログラミング教室も常にいっぱいだと聞いています。
また、保護者から「柏市はプログラミング教育が進んでいると聞き、他市から引っ越ししたいのですが、どこの学区がいいですか?」と問い合わせが入ったことがありました。
そういう状況を見ていると、プロブラミングを学んでおくことがこれからの社会で役立つと、一般の人も気が付いているのでは、と感じています。
-柏市では、コラボイベントなども盛んだと伺いましたが?
柏市ではいろんなプログラミングのイベントが行われています。2017年10月から始まった、小学生のプログラミング教育を題材にした子ども向けTV番組「GP LEAGUE プログラミングコロシアム」は柏市教育委員会が後援していて、「日本初の小学生プログラミングバトル」の公開収録が9月に柏市で行われました。
3人の小学生がチームを組み、知識と技とチームワークを競い合う内容で、今はテレビがこんな番組やるくらいプログラミングが注目されているのです。主催者発表で5000人が集まったそうで、保護者はここまで期待しているのだなと感じました。
 平成29年8月22日に、ららぽーと柏の葉で「かしわプログラミングフェスタ」を開催①
平成29年8月22日に、ららぽーと柏の葉で「かしわプログラミングフェスタ」を開催① 平成29年8月22日に、ららぽーと柏の葉で「かしわプログラミングフェスタ」を開催②
平成29年8月22日に、ららぽーと柏の葉で「かしわプログラミングフェスタ」を開催② プログラミング教育を実施後の課題について
-これまでプログラミング教育を実施してきて課題に感じていることはありますか?
プログラミングを教える人を育てることです。先生はプロなので、自分で上手に出来なくてもポイントさえつかめば子どもに教えられますが、全くやったことがないとポイントがつかめない。
じゃあどうしたのかというと、プログラミングの授業にICT教育サポートの先生だけでなく、担任の先生も参加してもらい、ただ見ているだけではなく役割を与えます。
例えば、パソコン画面でのプログラムを作る活動場面は、ICT支援員が担当しますが、「このプログラムを作るためにはどんな命令が必要か」考えさせたり,話し合わせたりする場面は担任が登場するのです。
あと、柏市の教育委員会と一緒にやってくれる仲間を増やすことです。
「CoderDojo Kashiwa」の代表・宮島 衣瑛さんは大学生で柏市内で小中学生向けのプログラミング道場を運営しています。そこでボランティアしている学生さんは教育委員会のイベントなどにも参加してくれます。いろいろ手伝ってくれるんですね。企画も出してくれます。彼らのような仲間を増やしていくことが大事だと思います。いろんな人や組織のつながりを僕自身が楽しんでるし、今いる学校教育課のメンバーも楽しんで仕事する人が揃っています。開かれた教育委員会が柏市の目指す姿なんですよ。
-ロボットを使ったプログラミング教育にも関心が集まっていますが、今後行う予定はありますか?
ロボット(を使ったプログラミング)はいいと思うし、やらせたいのですが、現行の学習指導要領でいくと、どうにもその時間がとりにくいんですよ。
今の時間割では、新しく入れるものが多いのに、今までやっていたことを止めたり、大きく削ったりすることをしていないんです。これは非常に難しい課題です。
ロボットで「プログラミング」を学ぶ良さは、こだわることじゃないですか。例えば自動ドアを作るとすると、横にずれるドアとか、上に跳ね上がるドアとか、観音開きのドアとか、いろんなドアを作る子どもがいていいわけですよね。でも、1時間や2時間では「こうやって作るのよ」って先生が教える授業にしかなりません。それでは、あまりプログラミングの思考力を育てることにはならないんじゃないかと僕は思います。
柏市では、パソコン画面上のプログラミングが実際にモノを動かす様子を見せるために、「mBot」というロボットを使っています。プログラミングとモノが連動して動いていることを目の前で見るのは、子どもにとって面白いはずです。本当は、時間をとってロボットを触らせてあげることが出来たらいいんですが、時間的な問題とお金の問題の2つがありますよね。

プログラミング教育のこれから
-結局のところ、プログラミング教育は何に役立つのでしょうか?
柏市の子どもを全員プログラマーにするというわけではありませんが、これからIT業界の人材が何十万人も不足する時代と言われているのに、それを放っておく手はないと思いませんか? 職業として選択するかどうかは、子どもの自由ですし。また,世の中にプログラミングが役立っていることを理解し,プログラミング的な思考ができるようになることは,どんな職業に就いたとしても必要になると考えます。今授業で教えているプログラミング言語が、この先残るかどうかは分かりません。ただ、今の私たちがやっている仕事の大部分が無くなると言われていても、新しい仕事は生まれるわけで、きっとそれは情報技術系で、何かを作り出す仕事だと予測出来ます。であれば、「プログラミングと出会う」体験が子どもの頃にあったほうが絶対いいですよね。
―プログラミング教育の今後の展望を教えてください。
柏市を拠点にした人材育成が、プログラミング教育で出来るとよいですね。国がやる以上、全国でやるわけで、柏市だけでこうやりますと閉鎖的にやっても意味がないし、共有出来るところは一緒にやっていきたいです。昔は技術が発展すれば、国は潤うと思われていました。でも今は、技術はプラットフォームに過ぎず、プラットフォームをどう活用するかが経済成長の鍵と考えられています。
教育も覚えさせるだけではダメで、考えさせることが大事な時代です。すでに言われたことだけをやればいいっていうのは違うんじゃないかって、子どものほうは気が付いているんじゃないですかね。
だから、僕たちは子どもの変容や違いがどこに出るのかをこれから意識して、2020年を迎えなければなりません。その時のことを考え、仕組みを作ったり、能動的に動いたりすることが、僕ら教育委員会の仕事ですから。
そもそもプログラミング教育で日本一とかを意識してやってるわけじゃなくて、子供を持つ家族が住みたいと思うような,育に信頼のおける柏市を目指していたら、いつの間にか注目されて、聖地と呼ばれちゃった!それが、真相ではないかと思っています。
編集部コメント
1980年代、スパコンやパソコンの分野で日本企業が世界的に躍進したという時代背景から、プログラマーという職業が日本では注目されました。マイコン(マイクロ・コンピューター)がパソコンと呼ばれはじめ、企業のものから個人のものに移った時期でもあります。その当時にいち早くプログラミングの将来性に着目し、小学校の教育に取り入れていた柏市。一度は、カリキュラムを休止していましたが今またその実績を活かして、市内の全公立小学校でのプログラミング教育を実現した柔軟性に注目しました。
プログラミングは機械を動かす仕組みというだけでなく、人間と同じような脳を作る「人工知能=AI」の研究など、医療、環境、芸術、文化など様々な分野において必要とされるスキルです。日本の子どもたちの未来のために、柏市のような柔軟な公共教育が求められているのです。
柏市が「プロラミングの聖地」として呼ばれる理由には、そんな未来的思考を取り入れた教育への、期待が全国から寄せられているからではないでしょうか?
参考資料
柏市のホームページ「平成29年4月からのプログラミング教育」について
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/270100/p038654.html
(取材・文・撮影/松井紀美子、編集/コエテコ編集部)


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
民間教育だからこそのスピード感で日本のプログラミング教育を引っ張る!全国学習塾協会 会長安藤大作さん
学習指導要領の改訂に伴って、2020年から小学校でも導入されるプログラミング教育。学校教育が大きく変わろうとしている今、塾などの民間教育も大きな転換期を迎えています。これからの民間教育...
2025.05.26|工樂真澄
-
まち全体でクリエイターを応援する金沢市の魅力(副市長インタビュー後編)
人口約46万の中核都市・金沢では、2020年度から全小学校・全学年でのプログラミング教育を実施します。今回は細田大造副市長にインタビューし、クリエイターを応援するまち・金沢の魅力とビジ...
2025.06.24|夏野かおる
-
合宿は本物の科学に出会い、自分の可能性を見出す場!「子どもの理科離れをなくす会」春合宿レポート
まだプログラミング教育という言葉が広まっていなかった15年以上も前から、ロボットを通して科学教育を行っている『子どもの理科離れをなくす会(以下、理科会)』。今では全国に60教室、約60...
2025.05.26|工樂真澄
-
「全小学校・全学年でプログラミング」金沢市の取り組み(副市長インタビュー前編)
人口約46万の中核都市・金沢では、2020年度から全小学校・全学年でのプログラミング教育を実施します。今回は細田大造副市長にインタビューし、伝統と進取の共存する街・金沢の取り組みについ...
2025.06.24|夏野かおる
-
(取材)Mind Renderで3Dゲーム制作、高度なプログラミングに挑戦|聖光学院・特別授業のようすをお届け
プログラミング教育の高度化が進むなかで、「拡張性があり、中高生の興味を引く教材」として注目されているのがMind Render(マインドレンダー)です。この記事では、Mind Rend...
2025.09.10|大橋礼