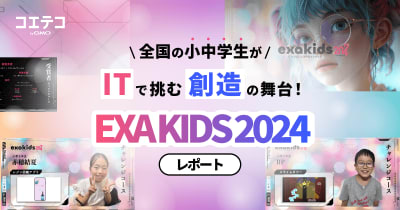九州初のプログラミングコンテストを開催 ITキッズフェスティバル「エクサキッズ」体験レポート

2018年2月25日(日)に福岡市中央市民センターで開催されたITキッズフェスティバル「エクサキッズ2018」。
イベントでは、九州で初めての開催となる小・中学生によるIT・プログラミングを使った「ITキッズコンテスト」の最終審査も行われ、応募のあった150作品の中から一次審査を突破した28作品が登場しました。
他にもプログラミングやIT、ものづくりに関するワークショップやブース展示なども行われており、会場は熱気に包まれていました。
多くの親子連れで賑わうイベント会場
イベント会場は、2Fがワークショップやブース展示、3Fがコンテストや講演が行われていました。
会場から溢れてしまい、階段で休憩している子どもたちがいるほど、会場は多くの親子で賑わっており、イベントの注目度の高さを感じました。
コンテストは、チャレンジコース①、チャレンジコース②、アイディアコース、エキスパートコース①、エキスパートコース②に分かれて開催されており、今回は、チャレンジコース①、チャレンジコース②のコンテストを見学してきました!
独創性の高い子供たちの作品
チャレンジコース①に登場する審査通過は6作品。それぞれ子どもならではの独創的な作品が揃いました。

秋穂 正斗さん『勇者ヒロトの冒険』
トップバッターとなった秋穂正斗さんは、Scratch(スクラッチ)というプログラミング言語を使って、オリジナルのRPG『勇者ヒロトの冒険』を作成。作ったきっかけは、「自分の”RPG”を作りたかった」ことと、「友達にもゲームを楽しんでもらいたいから」だそうです。
最初の発表ということで緊張している様子でしたが、プレゼンの練習もしていたそうで、時間制限の7分を使い切りしっかりと発表していました。

渡辺 拓海 『どうぶつレース』
2番目の発表者の渡辺 拓海さんは、動物がレースで競い合い、1位の動物を予想して所持金を増やしていくゲーム「どうぶつレース」を作成。どうぶつ毎の倍率が表示され、自分の掛け金を設定し、予想が当たると所持金が増えていきます。最近買ってもらったゲームが面白くて、自分でもゲームを作ってみたいと思っていたところ、友達が「こんなゲームがあったらいいな」という話を聞いて作ったそうです。
動物が同着にならないように変数を組み合わせたり、レースに勝った動物のリアクションをオリジナリティ溢れるものにしたりなど、様々な工夫が見られました。今後の課題としては、もっと動物の速さに差をつけたり、抜いたり抜かれたりの臨場感を出していきたいと言っていました。

山﨑 浩太郎 『 ゆうきの冒険』
3番目の発表者は、山﨑 浩太郎さんをリーダーとした5人組のグループでした。みんなで力を合わせて大きなゲームを作りたいと思い、グループでゲームの作成に取り組んだそうです。作成したのは「ゆうきの冒険」、主人公ゆうきがモンスターのいる世界を冒険するアクションゲームです。
スクリプト、バグ修正、キャラクター作成、ステージ作成などを、それぞれが分担しています。敵の強さを中ボス、ラスボスなどで変えたり、ステージの難易度を変えるなどしてゲームを楽しめる工夫していました。また、こだわったポイントとして、プレイヤーに合わせて敵が自動で追尾してきたり、効果音やBGMをつけた点を挙げていました。

安東 鷹亮 『ペットボトルロケットの自由研究まとめ動画』
4番目の発表は、安東 鷹亮さんによる「ペットボトルロケットの自由研究まとめ動画」でした。自由研究でペットボトルロケットを作って飛ばした様子を、まとめ動画としてYouTubeにアップしたことをプレゼンしていました。
動画の中で、ペットボトルロケットが水の量で飛ぶ飛距離が変わることを実験しており、ペットボトルの3分の1の水の量が一番飛距離が出ていました。が編集作業が大変で3日間ほどかかったそうですが、音楽を著作権フリーのサイトから選んだりすることは楽しかったそうです。一番嬉しかったこととして、チャンネル登録してくれた人がいたことを挙げていました。

フライア 瑠菜 『脱出せよ!闇の宮殿』
5番目の発表は、フライア 瑠菜さんによる「脱出せよ!闇の宮殿」でした。このゲームは、闇の宮殿から脱出するファンタジーゲームです。フライア瑠菜さんは読書が好きで、オリジナルのお話を作ってみたいと思って作ったそうです。独自の世界観が伝わってくるゲームでした。
また、自分でデザインすることも好きだそうで、登場するキャラクターのイラストも自身でで描くといったこだわりを見せていました。プログラミングの要素としてだけでなく、デザインの良さ、アメリカ映画のような作品名のタイトルなど、わくわくするゲームになっていました。

田村 天磨 「 最悪な誕生日」
チャレンジコース①の最後の発表者となった田村 天磨さんは、「最悪な誕生日」というシミュレーションゲームを発表していました。このゲームは、友達の誕生日にプレゼント代わりにゲームを作って驚かせたいという思いから作ったそうです。
ゲームのストーリーは、主人公が誕生日に突然逮捕され、部屋に閉じ込められてしまうところから始まります。その部屋の中にあるアイテムを使って、謎を解き、脱出を試みます。操作は、数字を入力したり、クリックなどで簡単に遊べるようになっており、無事にゲームをクリアすると、サプライズの誕生日パーティー会場にたどり着くことができます。
自分が形にしたいモノだけでなく、人が楽しめるモノを形に
チャレンジコース②に登場する審査通過も6作品、日常生活で困ったことや、友達にプレゼントしたいと思って作ったと言っていたのが印象的でした。
安東 鷹亮 『マイクラPEで音楽演劇ホールを忠実に再現!』
チャレンジコース②の最初の発表者に、チャレンジコース①で「ペットボトルロケットの自由研究まとめ動画」を発表した安東 鷹亮さんが再び登場しました。2度目の発表は、「マイクラPEで音楽演劇ホールを忠実に再現!」です。
マインクラフトを使って、実際にある建物を再現しています。今回の作品は、現実にあるものに似せて作りたいと思ったことから作ったそうです。舞台裏や音響のシステム、ホールの電気をつけたり消したりするなど、細かなところまで作りこみ、火事に備えて火災報知器を取り付けたり、水が溢れ出るシステムなども作っています。これから追加していきたいものとして、劇が始まる前に開け閉めされるカーテンやライトを増やしたい、火災のシステムをより忠実にしたいなどがあるそうです。今回の作品を作るにあたって、実際に建物の中に入って調べてきたと言っており、意気込みが伝わってきました。

前山 行雲 『~scradraw~(スクラドロウ)』
2番目の発表は、前山 行雲さんによる「~scradraw~(スクラドロウ)」でした。「~scradraw~(スクラドロウ)」は、簡単で誰でも無料で使うことができるイラストソフトです。
今回の作品を作った背景には、家にあったイラストレーターが使いづらく、もっと誰でも簡単に覚えられるようなソフトを作りたいと思ったから「scradraw」の名前は、プログラミング言語の「Scratch(スクラッチ)」と、描くという意味の「draw」を合わせた造語です。太字にしたり、色を変えたりなど、ぱっと見で誰でも使いやすいツールになっており、今後は消しゴム機能や保存機能、画像挿入機能などを追加していきたいと話していました。

入川 真愛 『おもしろランド』
3番目の発表者である入川 真愛さんは、「おもしろランド」を作成。「おもしろランド」は、遊園地に気軽に行きたいという思いから生まれた作品です。このゲームでは、ユーザーがゲームの中の遊園地に行くと、園長が出迎えてくれたり、ロボットや犬、お化けなどが登場します。最後には、遊園地でコンサートが開催され、女の子らしさが詰まった作品になっています。小さいお友達にも楽しんでもらえるように考えて、優しいイラストで絵を描くなど工夫されていました。

岩田 倖祈 『S660 3D-view』
4番目の発表者の岩田 倖祈さんは、Hondaの自動車「S660」を3Dで見ることができる「S660 3D-view」を作成。
自動車を見ることが好きだった岩田さんは、車の既存のWebサイトがグレードを変えたり、色を変えたりする時にフリーズしてしまうことがあり困っていたそうです。そこで、もっと操作性の良い3Dビューワーを作りたいと思い、「S660 3D-view」を作成たとのこと。そこで、今回作成した作品では、表示を早くしたり、拡大縮小することができる機能や、360°どの角度からも車を見ることができる機能を搭載しました。

松尾 蒼志 『 1年せいのさんすうのもんだい』
5番目の発表は、松尾 蒼志さんによる「1年せいのさんすうのもんだい」でした。「1年せいのさんすうのもんだい」は、作成した松尾さんや友達が勉強するために作られた3つのプログラムで、①どっちがおおいのもんだい②たしざんのもんだい③とけいのじかんあてクイズのパートに別れています。
「どっちがおおいのもんだい」と「たしざんのもんだい」には、可愛らしい動物たちが登場し、正解した時にはピンポンと効果音が鳴ったりするなど、楽しく算数に取り組む工夫がなされています。実際に松尾さんは、「1年せいのさんすうのもんだい」を通して、足し算や時計の読み方がわかるようになったそうです。

中村 侶唯 『 お絵かきマシーン』
最後の発表は、中村 侶唯さんで「お絵かきマシーン」でした。
元々絵に対して苦手意識のあった中村さんは、機械で絵が描けたらいいと思い、お絵かきマシーンを作成したそうです。お絵かきマシーンのパーツは3Dプリンターでプリントして作成、マシーンのコントローラーはイラストレーターでデザインし、レーザーカッターでカットし作られています。
縦、横、上下にそれぞれ動くボタンを作り、ボタンを押すことで絵を描くことができ、同時にボタンを押すことで斜めに描くことも可能です。将来的には手ボタンを使って動かすではなく、自動にできるようにしていきたいと話していました。
各ブースでプログラミングやゲームを体験
2Fは、ワークショップ・ブースのスペースとなっていました。
ワークショップで開催されるイベントは、午前中でチケットが配布終了するほどのイベントもあったほどなど大勢の親子で賑わっていました。
また、プロゲーマーと遊ぶことができる「eスポーツ体験ブース」は、中の様子を見るのも大変なほどの人気。子どもたちのeスポーツへの注目の高さが伺えました。

仮想通貨「NEM」を使った買い物体験ワークショップ、ウェアラブル楽器の体験など、子どもたちは最新のテクノロジーに触れていました。


他にも、ドローンを実際に動かすことができる「ドローン×プログラミング」ブース、子どもたちに人気のマインクラフトを学ぶことができるブースなどがありました。


編集部コメント
今回開催されたコンテストでは、子どもたちが考えたアイデアを子どもたち自身がプログラミングを使って形にし、プレゼンテーションを行っていました。このコンテストを通じて、プログラミングの技術だけでなく、考える力や失敗から学ぶ力、大勢の前で話す力など様々な力を身につけていたように思えます。また、多くの子どもが「このゲームやサービスで周りの人たちが楽しんでほしい」と話しており、自分が形にしたいモノだけでなく、人が楽しめるモノを形にする発想がとても素敵だなと感じました。参加された親子の方になぜ参加したのかを聞いてみると、「子どもが行きたいと言ったから一緒に来た」と話される方が多くいて実際にワークショップに参加した子どもたちを見てみると目を輝かせて参加していました。2020年から小学校でプログラミングが必修化となり、「今のうちからプログラミングをさせた方がいいのかな」という悩みをお持ちの保護者の方にとって、まずは気軽に参加出来るプログラミングに関する今回のようなイベントは、子どもたちの興味度合いを探るにはいい機会となります。
このようなイベントが開催された際は、参加してみることが子どもたちの刺激になり、成長につながるのではないでしょうか。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
MVPは小学6年生!ヒューマンアカデミーロボプロ全国大会レポート(2018年)
2018年10月27日(土)、ヒューマンアカデミー ロボプロ全国大会(第2回)が開催されました。ハイレベルなロボットが次々と登場した本大会。予想外の展開が連続し、終わりまで目が離せない...
2025.05.26|夏野かおる
-
【レポート】EXA KIDS 2024|ITキッズによる作品コンテスト 大人が嫉妬する才能が終結!白熱した大会の様...
全国の小中学生がITを駆使して制作したオリジナル作品を発表するコンテスト「EXA KIDS(エクサキッズ)」。2024年11月24日にオンラインで開催された第7回目の様子をレポートします。
2025.05.21|コエテコ byGMO 編集部
-
一足先にリュウグウへ?ロボ団×JAXA「はやぶさ2」イベントレポート
2018年9月23日(月・祝)、関西大学梅田キャンパス(KANDAI MeRISE)にてロボ団×JAXAイベント「ロボットプログラミングではやぶさ2ミッション!—軌道にのって小惑星リュ...
2024.11.06|夏野かおる
-
embot大展覧会2024|子どもたちの独創性あふれる作品が大集合!
2024年8月24日、台場フロンティアビルにて「embot大展覧会2024」が開催されました。 embot大展覧会2024では、子どもたちが出展者であり審査員!審査員の意見と子どもた...
2025.06.11|鳥井美奈
-
クリエイティブロボティクスコンテスト2026レポート|中高生25名のロボット創造力
2025年11月23日、「クリエイティブロボティクスコンテスト2025」の本戦が開催されました。予選を通過した25名の中高生が、ロボット工学の第一人者である古田貴之先生(千葉工業大学 ...
2026.01.02|大橋礼