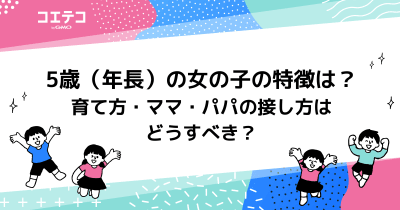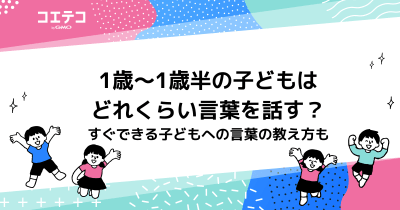イヤイヤ期はなぜ?いつからいつまで?理由と乗り越えるコツを紹介
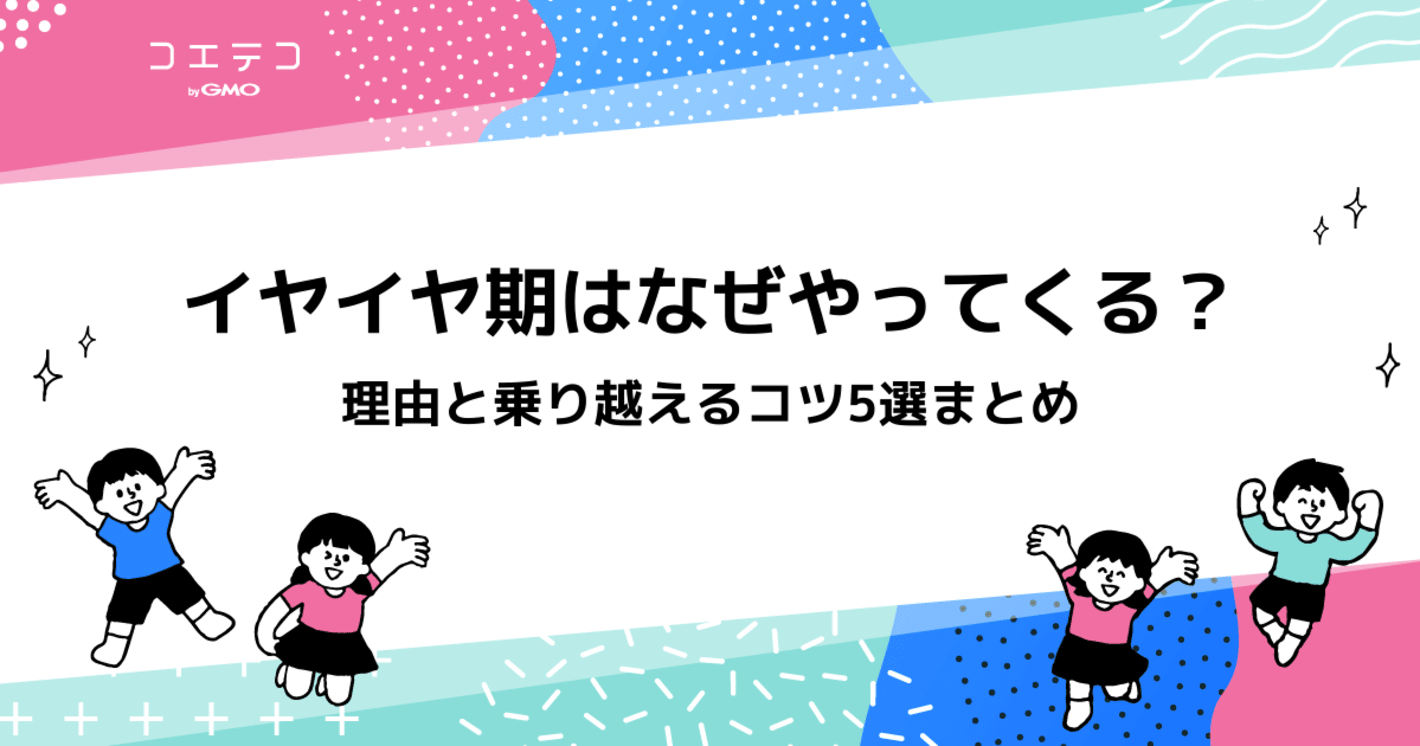
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
子どもの自我が芽生え始めると「イヤイヤ期」が始まります。
「イヤッ!」「違う!」と泣き叫ぶ我が子を前に、周りの目も気になり、パパ・ママは心身ともに疲れ果ててしまいますよね。
「一体なぜこんなにイヤイヤするの?」
「いつまで続くんだろう…」
そんなお悩みを持つあなたのために、この記事ではイヤイヤ期が起こる「なぜ」をわかりやすく解説し、親子で少しでも穏やかに、そして前向きにこの時期を乗り越えるための具体的な方法をまとめました。
イヤイヤ期への理解が深まり、心に余裕を持って子どもと接するためのヒントが見つかるはずなので、ぜひ最後までご覧ください。
イヤイヤ期はなぜ起こるの?原因は「脳の成長」という喜ばしいサイン

イヤイヤ期が起こる原因は、子どもの『脳』、特に感情や理性をコントロールする「前頭前野(ぜんとうぜんや)」がまだ発達の途中であるためだと言われています。
「やりたい!」気持ちにブレーキをかける機能が未熟なため、思い通りにならないことがあると、その感情をうまく処理できず「イヤ!」と爆発させてしまいます。
自我が芽生え、自分の意志で物事を進めたい気持ちが育っている証拠なので、決して悪いことではありません。
3歳頃になると前頭前野の機能が徐々に発達し、自分の気持ちをコントロールする力が身についてきます。
そのため、イヤイヤ期は「脳が順調に成長している!」と実感できる、子どもの発達の大切なステップとなります。
【イヤイヤ期の基礎知識】いつからいつまで?どのような行動が見られる?

イヤイヤ期の原因がわかっても、具体的な期間や行動パターンが気になりますよね。
ここでは、イヤイヤ期の基本的な情報を解説します。
一般的には1歳半~2歳頃に始まり、3~4歳で落ち着くことが多い
イヤイヤ期は「魔の2歳児」とも呼ばれるように、多くの場合、2歳前後にピークを迎えます。自我がはっきりと芽生え、これまでパパやママの言う通りにしていた状態から、「自分でやりたい!」という自立への第一歩を踏み出している時期です。
個人差は大きいですが、一般的には3歳を過ぎる頃から徐々に落ち着き始め、4歳になる頃には「そういえば、最近あまりイヤイヤ言わなくなったな」と感じるご家庭が多いようです。
「なんでもイヤ!」イヤイヤ期によくある行動パターン
イヤイヤ期の子どもは、基本的に自分の「やりたい」という本能的な気持ちに正直です。日常生活のあらゆる場面で「イヤ!」が頻発し、パパ・ママを悩ませます。
このように、家の中でも外でも、子どものイヤイヤと向き合う時間が増えるため、保護者にとっては精神的にも体力的にも大きな負担を感じやすい時期となるでしょう。
今すぐ試せる!イヤイヤ期を乗り越えるための具体的なコツ9選!

イヤイヤ期が成長の証だと頭では理解していても、毎日続く「イヤイヤ」に笑顔で対応し続けるのは大変です。
ここでは、少しでも穏やかにこの時期を乗り越えるための具体的なコツを9つご紹介します。
1. 写真や動画で記録してみる
「また始まった…」と感情的になりそうなときは、あえて一歩引いて、その様子を写真や動画で撮影してみましょう。「すごいエネルギーだな」「まさに本能のままに生きている!」と客観的に見ることで、不思議と気持ちが落ち着くことがあります。
後から見返すと、「こんなことで泣いていたんだな」と愛おしく思え、貴重な成長の記録になりますよ。
2. 時間と心に余裕を持つ
イヤイヤ期への対応で最も大切なのは、時間に余裕を持つことです。時間に追われていると、親の心にも余裕がなくなり、ついイライラしてしまいます。
子どもが「自分でやりたい!」と言い出したときは、可能な限り挑戦させてあげられるように、朝の準備や外出の予定は、いつもより15〜30分早めにスタートしましょう。
どうしても時間がないときは、「時計の長い針が6になったら終わりにしようね」など、事前に見通しを立てて伝えておくと、子どもも納得しやすくなります。
3. 遊びやゲームに変えて誘導する
何かに夢中になっている子どもに「ご飯だよ」「お片付けしよう」と声がけをしても、「イヤ!」と返ってくることもあるでしょう。そんな時は、次の行動を遊びに変えて誘ってみるのが効果的です。
楽しい雰囲気を作ることで、子どももスムーズに次の行動に移りやすくなります。
遊びながら学べる幼児向けタブレット学習などを活用するのも一つの手です。
4. 子どもの気持ちを言葉で代弁する
イヤイヤ期の子どもは、まだ自分の気持ちをうまく言葉で表現できません。「〜したかったんだね」「うまくできなくて悔しかったんだね」と、親が気持ちを代弁してあげると、子どもは「分かってもらえた」と安心します。
共感し、受け止めてもらえる経験は、子どもの自己肯定感を育む上で重要です。
まずは子どもの気持ちに寄り添い、「そうだね」と共感することから始めてみましょう。
5. 「できた!」をたくさん褒める
イヤイヤが続くと、つい叱ることが増えてしまいます。もちろん、危険なことやいけないことをしたときには毅然と叱る必要がありますが、それ以上に「褒める」機会を意識的に作ることが大切です。
いつもは嫌がることすんなりできたとき、小さなお手伝いをしてくれたときなど、些細なことでも「すごいね!」「ありがとう、助かったよ」と具体的に褒めてあげましょう。
褒められることで子どもの自尊心は育ち、親自身もポジティブな気持ちで子どもと向き合えるようになります。
6. 選択肢を与えて本人に選ばせる
「イヤ!」の一点張りで困ったときは、「AとB、どっちがいい?」と子ども自身に選ばせてあげるのが効果的です。自分で決める経験は、「自分でできた」満足感につながり、イヤイヤをポジティブな自己主張へと転換させるきっかけになります。
7. 周囲の力を積極的に借りる
「イヤイヤ期くらいで…」と、一人で抱え込んでいませんか。ワンオペ育児が常態化していると、誰かに頼ること自体に罪悪感を覚えてしまうかもしれません。
しかし、イヤイヤ期は本当に大変な時期なので、パートナーや両親、友人など、頼れる人には積極的に助けを求めましょう。
話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなります。
保育園や地域の支援センターの保育士さんに、具体的なアドバイスをもらうのもおすすめです。
8. 親自身が気分転換をする時間を作る
子どもと向き合う時間は大切ですが、四六時中向き合い続けていては、誰でも疲れてしまいます。時には、一時預かりやベビーシッターなどを利用して、意識的に子どもと離れる時間を作りましょう。
一人でカフェに行ったり、友人と会ったり、好きなことに没頭したりと、自分自身をリフレッシュさせることが、結果的に子どもへの穏やかな対応につながります。
参考:おすすめの幼児教室
9. 「今はこういう時期」と割り切る
いろいろ試しても、どうしてもうまくいかない日もあります。そんなときは、「今はこういう時期なんだ」と、ある意味で諦めることも肝心です。
すべてを完璧にこなそうとせず、「今日は食事を手作りしなくてもいいや」「部屋が散らかっていても仕方ない」と手を抜くことも大切です。
親のイライラは子どもに伝わり、悪循環を生んでしまいます。まずはパパ・ママが自分自身を追い詰めないことを最優先に考えましょう。
逆効果かも?イヤイヤ期の子どもにしてはいけないNG対応

心身ともに疲れていると、ついやってしまいがちなNG対応があります。
しかし、これらの行動は子どもの心を傷つけ、イヤイヤを悪化させる可能性もあるため注意が必要です。
NG対応1:無視・放置する
泣きわめく子どもを無視したり、その場に放置したりする行為は、子どもに「見捨てられた」という強い不安感と絶望感を与えます。自分の気持ちを受け止めてもらえない経験は、子どもの情緒をさらに不安定にさせ、イヤイヤをエスカレートさせる原因になりかねません。
また、放置は転倒や誤飲など、思わぬ事故につながる危険性もあります。
どうしても気持ちが収まらないときは、まず子どもの安全を確保した上で、少しだけ別の部屋に行くなど物理的な距離をとり、深呼吸して冷静さを取り戻しましょう。
NG対応2:感情的に強く叱りつける
大声で怒鳴ったり、強い口調で叱りつけたりする行為は、子どもに恐怖心を植え付けるだけです。近年の研究では、強い言葉による叱責(マルトリートメント)が子どもの脳の発達に悪影響を及ぼす可能性も指摘されています。
恐怖で行動をコントロールしようとすると、子どもは親の顔色をうかがうようになり、自分の気持ちを表現できなくなってしまう恐れがあります。
もし感情的に叱り過ぎてしまうと悩んでいる場合は、以下のことを試してみてください。
「叱る」と「怒る」は違います。
感情に任せて怒るのではなく、子どもの安全や成長のために、冷静に伝えるべきことを伝える「叱り方」を意識しましょう。
一人で悩まないで!子育ての悩みを相談できる窓口

「子どもへのイライラが止まらない」「つい怒鳴ってしまって自己嫌悪…」
そんな気持ちは、一人で抱え込まずに誰かに話すことで、楽になる場合があります。
身近に相談できる人がいない、あるいは話しにくいと感じる場合は、専門の相談窓口を利用するのも一つの方法です。
自治体ごとの子育て相談窓口
各自治体には、子育てに関する相談窓口が設置されています。名称はさまざまですが、「子育て支援課」「こども家庭センター」などで対応しており、電話や面談で相談に乗ってくれます。
お住まいの市区町村のホームページで確認するか、「〇〇市 子育て 相談」のように検索してみてください。
児童相談所相談専用ダイヤル(189)
「児童相談所」は、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に対応する専門機関です。児童福祉司や児童心理司、医師、保健師などの専門スタッフが在籍しており、より専門的な見地からアドバイスや支援を受けることができます。
電話番号「189(いちはやく)」にかけると、お近くの児童相談所につながります。
相談は匿名でも可能です。
子育てホットライン「ママさん110番」
日本保育協会が運営する電話相談窓口です。保育の現場に詳しい専門家が相談員を務めているため、特に乳幼児期の子育てに関する悩みに強いのが特徴です。
子どもの発達やしつけ、関わり方など、幅広い相談に対応しています。
保健センター
市区町村が運営する、地域住民の健康をサポートする公的機関です。乳幼児健診などでおなじみですが、保健師や助産師、栄養士などの専門家への育児相談も可能です。
地域の情報に詳しいため、必要に応じて子育てサークルや親子教室などを紹介してもらえる場合もあります。
まとめ

今回は、多くのパパ・ママが悩む「イヤイヤ期」について、その原因から具体的な対処法、NG対応、相談先までを詳しく解説しました。
イヤイヤ期は、子どもの自我が芽生え、脳と心が大きく成長している大切な時期です。
真っ最中はつらく、永遠に続くように感じられるかもしれませんが、必ず終わりはやってきます。
今回ご紹介したコツを参考に、完璧を目指さず、時には周りの力も借りながら、お子さんの「自分でやりたい」気持ちを温かく見守ってあげてください。
この記事が、あなたの心が少しでも軽くなるきっかけになれば幸いです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
2歳児の男の子はイヤイヤ期・大変?ママ・パパのお悩み解決策
赤ちゃんから幼児へと、身体も心も急速に変化する2歳児。イヤイヤ期をはじめ日々の接し方や声がけ、しつけに戸惑ったり、早期教育や習い事などに向けて悩むママ・パパに向けて、2歳児あるあるや、...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
3歳の男の子は第一次反抗期? 3歳児を持つママ・パパのお悩み解決策まとめ
東京都教育委員会の就学前教育カリキュラム改訂版ハンドブックによれば、3歳児は運動神経が発達し、手先が器用になり、語彙が増え会話を楽しむようになるなど、大きな成長を見せる時期です。同時に...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
5歳(年長)の女の子の特徴は?育て方・ママ・パパの接し方はどうすべき?
保育園・幼稚園の年長にあたる5歳の女の子。「中間反抗期」と呼ばれる時期に差し掛かり、小学校への入学準備を兼ねた習い事の検討やしつけや接し方に迷ったりと、育児が大変になる家庭も多いでしょ...
2025.05.30|コエテコ教育コラム
-
1歳~1歳半の子どもはどれくらい言葉を話す?発語や教え方も解説
子どもが1歳になると気になりがちなのが「言葉」について。つい周りの子と比べてしまいがちですが、この時期の言葉の発達は個人差が大きく、言葉が出てくるのが遅いと感じても過度に焦る必要はない...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
3歳~3歳半の子どもはどれくらい言葉を話す?三語文とは何かも解説
親など大人のまねをする「模倣」や、2つ以上の述語を組み合わせた「複文」にステップアップする3歳。言葉の発達には個人差が大きく出るため、目安の時期より遅れていても心配する必要はありません...
2025.11.17|コエテコ教育コラム