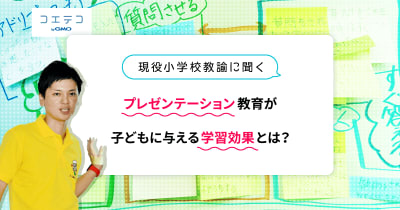プログラミング教材からIoTまで! 創造と挑戦のソリューション企業

小学校でプログラミング教育が本格的に始まるこれからの時代、エンジニアを目指すお子さんはますます多くなることでしょう。
でもエンジニアって、いったいどんなお仕事なのでしょうか?今回は兵庫県にある会社に伺い、お話をお聞きしました。
きっとどこかでお世話になってる!幅広い分野で活躍するフジ・データ・システム
兵庫県尼崎市にある株式会社フジ・データ・システムは、1978年にソフトウェア開発会社として創業されました。先代の社長であったお父様がご急逝された後、代表取締役社長として会社をけん引する藤嶋純子様にお話を伺いました。
――フジ・データ・システムはどのようなお仕事をする会社なのですか?
おもに大手メーカー様の下請けとして、さまざまなお仕事をさせていただいております。
たとえば身近なところでは、電車の改札システムやファミリーレストランの注文システム、カーナビゲーションシステムなどの開発も行っています。現在はソフトだけでなく、ハード、そしてシステムの開発も手がけています。
あまり目にすることはないかもしれませんが、プラスチック製品を形作る『射出成形機』という機械のコントローラーの開発も行っており、国内だけではなく海外でも広く使われています。
現在も多くのメーカー様からのご要望にそって、ありとあらゆる製品開発に携わっており、50名ほどいる社員の半数は、それぞれ担当のメーカー様に出向いて仕事をしています。
 『プラスチック射出成形機』の心臓部であるコントローラーを開発
『プラスチック射出成形機』の心臓部であるコントローラーを開発
――社長様ご自身もエンジニアご出身なのですか?
実はそうではないんです。あまり心の準備もできないまま、まったく異なる業種から飛び込んだものですから、最初は猛勉強の日々でした。業界のことや経営のノウハウ、もちろん技術やプログラミングも必死になって勉強しました。
でもあるとき、「自分の役割は、技術的なことよりもむしろ、会社の方向性を定めて、ここで働く皆さんが能力を発揮できるような環境を整えることではないか」と気づいたんです。それからは、少し余裕をもって仕事ができるようになったかもしれませんね。
――優秀なエンジニア集団を引っ張るお立場ですが、どんなことに気を配っておられますか?
手前みそになりますが、わが社には優秀なエンジニアが多く在籍しています。しかし、優秀であるからこそ、納得してからでないと動いてくれません。
「こういうアイデアを試してみてほしい」、「ああいう製品を開発してほしい」とお願いするときも、しっかり論理を立てて「どうしてそれが必要なのか」を明確に示すといった『論理武装』が欠かせないんですよ(笑)。
 社員の皆さんとのコミュニケーションを最も大切にしている藤嶋社長
社員の皆さんとのコミュニケーションを最も大切にしている藤嶋社長
プログラミング教材の開発が会社の起爆剤に
――お子さん向けのプログラミング教室を定期的に開催されておられますね。どのような経緯で始められたのですか?
2012年に『ロボカップジュニア』の日本大会を、尼崎の商工会議所が主催することになり、当時、商工会議所に所属していた私もお手伝いをさせていただきました。
そこで見たのは、少ないお小遣いからやりくりして部品を買い足し、試合で少しでも良い動きをさせようと、創意と工夫を重ねて根気よくロボットを作る子どもたちの姿です。
「これこそ今まさに会社に必要な姿勢なのではないか」と思い、会社を挙げてサポートを始めました。
わが社では同じメーカー様と長年にわたってお取引させていただくことが多く、一から新しいものを作るケースはそれほど多くはありません。
しかし、それに甘んじていたのでは、生き残ることはできません。
IT時代になり多くの需要があるこの業界でも、海外の安価なメーカーに押されて廃業に追い込まれる会社はたくさんあるのです。
このような時代だからこそ、つねに新しいモノづくりに挑まなくてはなりません。
ロボカップジュニアで目にした子どもたちの思考力や企画力、そして何より未知の世界へ挑戦する姿勢は、モノづくりメーカーとしての基本を思い出させてくれました。
――プログラミング教材の開発も行われていますね。
ロボカップジュニアジャパンで当時理事をされていた『子どもの理科離れをなくす会』の北原先生から、「もっと多くの機能をもったロボット教材を作りたいから、力を貸してもらえないでしょうか」とお話をいただいたのがきっかけです。
そこでわが社で独自に開発したマイコンが『C-cubic』です。ビジュアル言語のようにアイコンを操作するだけで楽しく簡単にプログラミングできるようになっているので、プログラミングは初めてというお子さんでも、すぐに慣れることができます。
また、ベースはC言語でできているので、上級クラスではC言語の習得教材としても使われています。
 フジ・データ・システムが教育用に開発したC-cubic
フジ・データ・システムが教育用に開発したC-cubic
フジ・データ・システムが教育用に開発したC-cubic
実は『C-cubic』は、わが社の製品として実際に工場などでも使われている『本物の』電子部品なのです。20のセンサーを取り付けることができ、Bluetoothという通信機能も搭載している工業製品です。 プログラミング教材『C-cubic』の中身は本物の工業製品
プログラミング教材『C-cubic』の中身は本物の工業製品
――プログラミング教材の開発は会社の利益にもつながるのですか。
直接の利益というのはそれほど多くはありませんが、そこから派生して新商品の開発につながることがあるのです。
わが社では『C-cubic』にクラウド接続機能などを付けた製品の開発に成功し、今年『FREEWIL』として産業向けに販売を始めました。
これも元はと言えば、展示会でC-cubicをご覧になったお客様から、「クラウド対応はしているの?」とお訊ねいただいたのがきっかけです。
たとえば『FREEWIL』を遠く離れた山奥の川に設置しておけば、都会の真ん中からでも水位や流量を把握することができます。
あちこちの川に設置しておけば、どんなたくさんの場所の情報でも、たった1カ所で把握することができます。
さらに『FREEWIL』を使えば、もし水位が上がり過ぎたらサイレンを流すとか、堰を開けて水位を下げるなど、遠隔操作を行うことも可能です。
最近、IoT(Internet to Things)という言葉をあちこちで耳にすると思います。
これは「あらゆるモノがインターネットにつながる」ということですが、『FREEWIL』はまさにIoTを可能にする製品で、これから多くの需要があると期待しています。
このような製品もプログラミング教育に関わったからこそ生み出せたものですから、人と人との縁とは大切なものだとあらためて感じます。
エンジニアとして大切なのは『質問力』
次に、フジ・データ・システムで27年にわたって、ソフトウェアの技師として活躍されている松谷健人さんに、お話をうかがいました。――エンジニアになられて最初のお仕事はどんなものでしたか?
わたしが仕事を始めたのは、ちょうどこれからコンピューター関連の人材が不足すると言われ始めた時期でした。会社に入って最初に手がけたのはワークステーションのUNIXで動くソフトウェアの開発です。
先輩技師について仕事を覚えながら、『X-Mate』という製品を開発しました。規模にもよりますが、1人で仕事をするよりは、他のエンジニアとチームを組んで行うことが多いですね。
 フジ・データ・システムの技師 松谷健人さん
フジ・データ・システムの技師 松谷健人さん
――エンジニアというお仕事がたいへんだと思うのはどんなことですか?
わが社は下請けをすることが多いのですが、他の会社様で開発していたものを途中から請け負うことが稀にあります。
そうすると開発途中のプログラムを渡されたりするのですが、他の方が作ったプログラムを1から解読するのはやはり苦労しますね。
また、変化が激しい分野ですから、勉強や情報収集は欠かせません。プログラミング言語にしても、人が使いやすいようにどんどんと新しい言語が生み出されています。
わたし自身が最初に習得したのはC言語でした。その後、いろいろな言語を使って開発に携わりましたが、基本的にはどの言語もC言語を発展させたものですから、理解するのはそれほどたいへんではありません。
プログラミングの根底にある考え方はどの言語でも同じですから、1つの言語をきちんと習得したら次は学びやすくなりますね。
――お仕事をしていてやりがいを感じるのはどのような時ですか。
やはりお客様に満足していただけたときですね。一生懸命に作ったものが、お客様の思い通りの製品に仕上がり、「ありがとう!次もよろしく頼みます」と言われると、この仕事をしていてよかったなと思います。
あと、もちろんプログラミングをする楽しみというのもありますよ。試行錯誤してやっと思い通りに動いたときは、やはり嬉しいものです。
これはプログラミングをされているお子さんなら、よくわかると思いますよ。
――お家でもプログラミングをされたりするのですか?
若い頃はそういうこともありましたが、最近はまったくしなくなりました(笑)。
仕事でずっとプログラミングしていることも多いので、家では気分転換して翌日の英気を蓄えるようにしています。
そうは言っても、家でぼんやりとしている時に、急に問題解決のアイデアを思いつくこともあるんですよ。
――エンジニアに必要な資質とはどのようなものでしょう。
ずばりコミュニケーション能力ですね。ソフトウェアエンジニアというと、ひたすらパソコンの画面に向かって黙々と仕事をしているイメージかもしれません。
でも、お客さまが求めている製品を作るには、まずそのお客さまが求めていることを正確に聞き出す必要があります。そういう意味では『質問力』と言ってもいいでしょう。
わが社で実際にあったケースなのですが、あるとき長い付き合いのあるメーカーさんから発注をいただきました。
本来ならばそこで発注内容の確認をするべきなのですが、よく知ったお客さまですし、いつものご要望だろうと勝手に解釈して、詳しい仕様をお聞きしなかったのです。
案の定、お客様の求めているものとはまったく違うものを作ってしまい、たいへんご迷惑をおかけしたことがありました。
そういうこともありますから、たとえ慣れ親しんだ相手であっても、正確なコミュニケーションをすることは何より大切だと思います。
――昨今のビジュアル言語を使った子ども向けのプログラミング教材は、将来的にプログラム言語の習得に役立つとお考えですか。
わたし自身は直接ビジュアル言語に触れたことはありませんが、どの言語もたいていC言語などを基礎にして開発されていますから、ベースとなる考え方は同じでしょう。
プログラミングが全く初心者というお子さんには、プログラムに対する感覚を習得するという意味でも役に立つと思います。
――将来エンジニアになることを目指して、頑張っているお子さんたちにメッセージをお願いします。
プログラミングの上達に必要なのは実践と経験です。せっかく勉強して新しい技術を習得しても、使ってみないと本当に自分のものになったとは言えません。
勉強したことを使って、ぜひいろんな課題にチャレンジしてほしいですね。
子どもが試行錯誤をする機会をたくさん与えてほしい
――最後に藤嶋社長から、保護者の方やお子さんにメッセージをお願いします。
この先ますます拡大するIoTやAIの分野では、世界的にも人材不足が深刻です。そんな中で中国やインドなどが目覚ましい発展を見せており、日本は追いやられてしまうかもしれません。
日本でも義務教育でプログラミング教育の必修化が始まることもあり、この分野の人材育成につながってほしいと思います。
学校の英語の授業でもネイティブの先生が教える機会があるように、本物のエンジニアがお子さんにプログラミングを教える機会があるといいと思います。
日本の技術力を底上げしたいと本当に思うのであれば、プログラミング教育を導入するということに満足しているだけではダメで、学校の先生を手助けする形で技術的なことをエンジニアが教えるなどして、しっかりとレベルを上げようという意識が必要だと思います。
そしてお子さんたちには、子どものうちにたくさんの試行錯誤をしてほしいと思います。
今は少子化でお子さんも少ないことから、どうしても子どもに目が行きがちで、ロボット教室でも親御さんがお子さんに口を出してしまう光景を見かけます。
でも、それではお子さんの成長する機会を奪っているのと同じです。いろんな経験ができる機会を与えると同時に、失敗をしても、お子さん自身が答えを出すのを見守ってあげてほしいですね。
編集部より
ソフト、ハード、そしてシステム開発まで、たくさんのお仕事をこなす『株式会社フジ・データ・システム』。多くの大手メーカーと長年にわたって取引を続けているのも、その技術力と信頼性があるからこそでしょう。藤嶋社長は業界の未来につながる、子どものプログラミング教育にも積極的に取り組んでいます。
また、コミュニケーションをとても大切にされていて、子ども向けの教室でも挨拶やプレゼンテーションの重要性を教えています。
今回の取材を通して、藤嶋社長はじめ、エンジニアの皆さんのモノづくりへのひたむきな姿勢こそが、日本の高い技術を支えているのだと感じることができました。
 取材協力:株式会社フジ・データ・システム
取材協力:株式会社フジ・データ・システム


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
『未来の先生』は大学でどんな勉強をしているの? 畿央(きおう)大学 教育学部の取り組み
2020年から小学校でプログラミング教育が始まることになり、学校ではその準備が急ピッチで進められています。その中でも急がれるのは、子どもたちの指導にあたる先生を中心とした人材の育成です...
2025.05.26|工樂真澄
-
現役小学校教諭に聞く、プレゼンテーション教育が子どもに与える学習効果とは?育つのは「話す力」だけじゃない!
プレゼンテーション能力はこれからの時代に生きる子ども達が今から身に付けておくべき重要なスキルです。今回の記事では子どものうちから身に付けたいプレゼンテーション力についてまとめ、茨城県の...
2025.07.31|大橋礼
-
『MADE IN SHIBUYA』の子どもたちを育てる街づくり―渋谷区 長谷部健 区長
『ちがいを ちからに 変える街。渋谷区』をコンセプトに新たな街づくりを目指している渋谷区。これからの時代を生きる子どもたちの育成への意欲的な取組みや渋谷区ならではの事例、今後の学校教育...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
ママだってプログラミングしてみたい!ITな女子会に行ってきた!
2020年からの小学校でのプログラミング教育必修化にともない、盛り上がりを見せるロボットやプログラミング教室。でも、そんな中でなんとなく取り残されているのがお母さんたち…。「いったい何...
2025.05.26|工樂真澄
-
小学生におすすめデジタルイラストの習い事!アタムアカデミーに取材!
絵を描くのが大好き!というお子さまにピッタリなのが、オンラインで本格的にデジタルイラストを学べるATAMACADEMY(アタムアカデミー)です。この記事では子どもたちの大好きな「お絵か...
2025.11.17|大橋礼