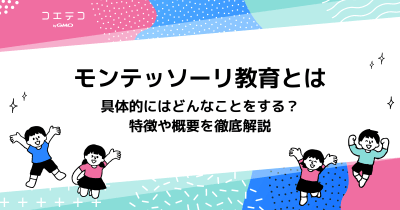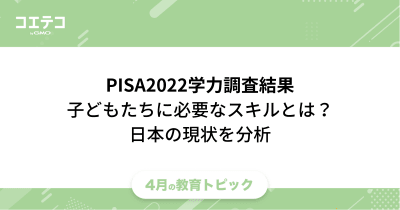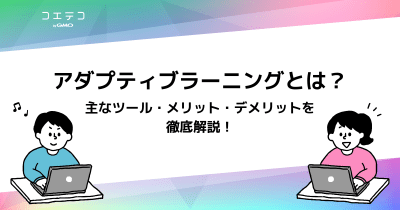協働学習とは?メリット・デメリットを徹底解説
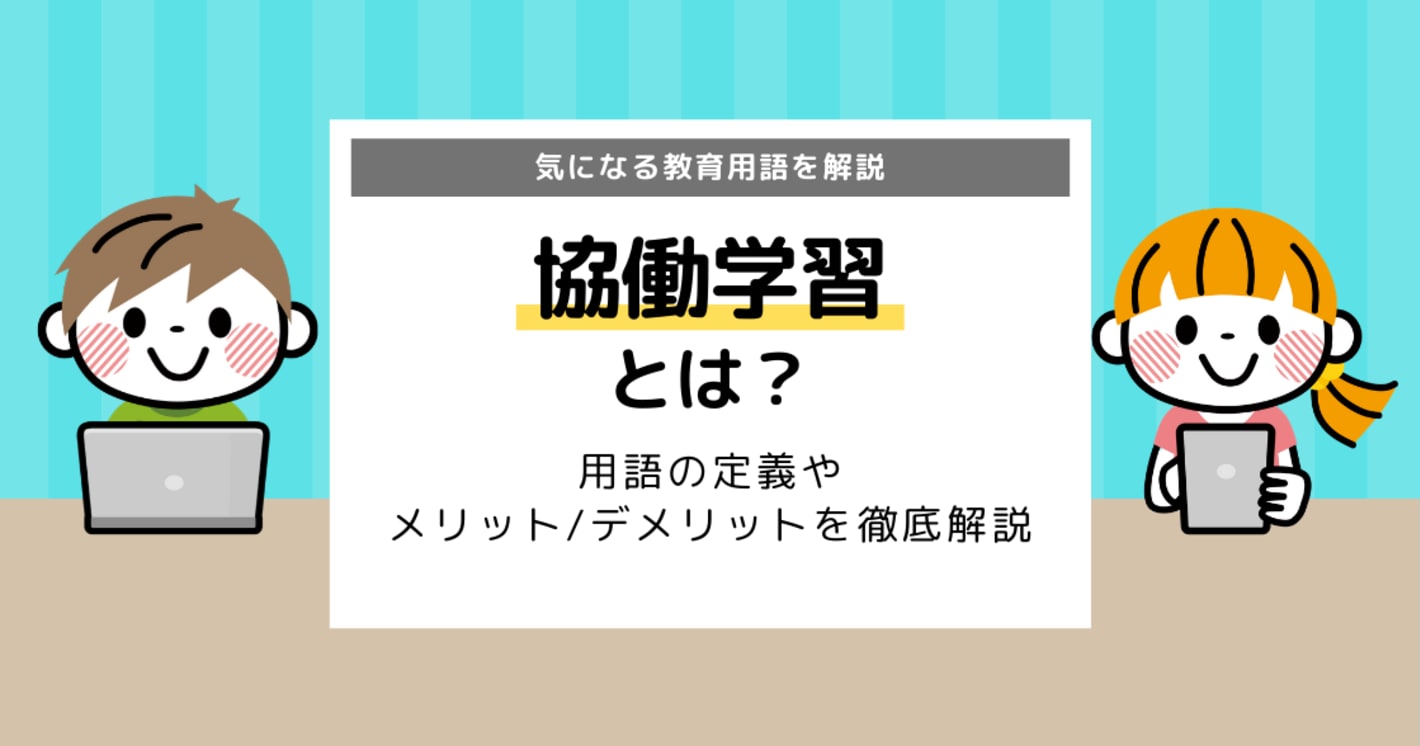
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
漢字を見ると何となく意味が想像できそうな気もしてきます。「子どもたちどうしで協力した学びなのかな……?」なんて。
たしかに間違いではありません。
ただ、この用語が使われる背景には、文科省が期待するこれからの新しい学び方への考え方などが盛り込まれています。
本記事では、言葉の意味を踏まえた上で解説していきます。
また、協働学習を行う上でのメリットやデメリットについても取り上げていきます。
講師や先生の方はぜひ授業づくりの参考にしてみてくださいね。
協働学習とは?
文科省の定義によると、協働学習とは「子どもたち同士が教え合い学び合う協働的な学び 」という意味合いになります。協働学習については、学びのイノベーション事業の「新しい学び」の中で提唱されていました。
学びのイノベーション事業では、2011~2013年に全国20校で実証研究がされています。
研究校は、1人1台の端末、電子黒板、無線LAN等が整備された環境となっています。
この事業ではICTの活用により下記のような新しい学びが実現可能であるとされました。
具体的には、電子黒板やタブレットを用いて生徒同士で意見交換をすることや、海外の学校との交流学習などの実施が想定されています。
- 子供たちが分かりやすい授業を実現
- 一人一人の能力や特性に応じた学び(個別学習)
- 子供たち同士が教え合い学び合う協働的な学び(協働学習)
これらの協働的な学習活動を通して子どもたちがお互いを高めあい、思考力・判断力・表現力などを育成することが狙いとなっています。
協同学習のメリット・魅力とは?
文科省は、「発表や話合い」「協働での意見整理」「協働制作」「学校の壁を越えた学習」といった場面で協働学習を行うことで、学習の幅が広がると発表しています。協働学習が適切に行われた場合には、他者との対話と積極的に授業に参加することが重要視されます。
チームでの作業ということで自分ごととして意欲的に授業に参加するきっかけとなりますし、チーム内での交流によって他者を思いやる場面も増えることでしょう。
さらに、他者の意見と触れる機会が多くなるので、自分とは異なる意見を目の当たりにする機会が増えます。
そのため、単に正解・不正解にこだわるのではなく、課題解決までの思考力が育成されます。
加えて、ICTを活用することで、海外の学校や他校との交流も容易に実現されます。
これまでは実現がむずかしかった授業形式であっても、ICTを用いた協働授業の導入によって学習の幅が広がることが期待されています。
なぜ今、協働学習が注目されている?
2020年から施行される新学習指導要領では、アクティブラーニングの考え方が引き続き注目されています。新学習指導要領では、「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も重視して授業を改善していくと発表されています。
アクティブラーニングの中に、協働学習的な視点が組み込まれているといえるでしょう。
そして、アクティブラーニングでは主体的かつ対話的に授業に臨むことのできる授業が目指されます。
そのため、チーム内での意見交換や制作物作成、発表をする…などという協働学習的な場面も増えていきそうです。
また、協働学習は、これまでICTの活用とともに実証研究がなされてきました。
これは、アクティブラーニングを意識した授業との親和性も高そうです。
言語活動が重点的に行われるアクティブラーニングでのICT活用は今後増えていくことでしょう。
遠隔地同士の協働学習も可能に
先にも触れたとおり、協働学習があらためて注目されている理由としては、ICTの活用で空間の制約がなくなったことが大きいです。これにより、教室内だけではなく、遠隔地にいる子どもたちとも協働学習を行うことができるようになります。同じ地域・文化の中で育っている子どもたちは、どうしても自分たちの地域のことを常識だと思ってしまいがちです。しかし協働学習を通じて勉強を行っていくことで、自分たちとは違った文化の存在を知ることができます。グローバル化が進む現代において、自分たち以外の他者に思いを馳せることのできる能力は、ますます重要になっていくでしょう。
協働教育でICTによる物理的制約からの解放
協働学習にICTを取り入れることは、遠隔地とのやり取りを行わない場合でも効果があります。従来の協働学習では、たとえば模造紙に意見を書き込んでそれを見てみる、といった方法が取られていました。しかし、模造紙に全員が同時に意見を書き込んでいくことは物理的に不可能です。そのため、どうしても「待ち」の時間が発生してしまい、効率的に授業を進められないという問題がありました。
ところが、タブレット端末でそれぞれが書き込み、電子黒板でそれらを表示する……という手法をとれば、全員が同時に作業を進めることができます。その結果、書き込まれた意見をを元にした議論を行うなど、より本質的な活動に時間を割けるようになります。
協働学習のデメリット・課題
学びのイノベーション事業の報告書では今後の改善点が挙げられています。その中には、協働学習に関連する項目もあります。
例えば、協働学習を一斉授業の中で効果的に行うにはICT環境の整備や教員の指導力の育成が課題となります。
環境面では、情報機器や学校や家庭をつなぐ環境を充実させることが求められます。
また、自治体によって取り組み具合が異なるため、指導方法や教材の共有、研修の実施などを通したさらなる教員のスキルアップも求められることでしょう。
また、その他の課題としては教員の力量が問われる場面が増え、体系的な指導法が確立されにくいことも課題なのではないでしょうか。
例えば、協働学習を行う場合はクラス内である程度協力しあえる環境づくりが構築されていることが前提となります。
そのため、教員の学級経営能力が協働学習の成功や失敗に直結することでしょう。
さらに、子どもたちの性質の差をどのようにカバーするのかという面も、教員の手腕が問われる部分となることでしょう。
例えば、クラスの中に特別な支援が必要な子がいる場合やグループの中で能力差が著しい場合に、協働学習を成立させるためのアプローチが必要となります。
このように、一斉授業以上に臨機応変に判断しなければならない場面が増えるため、教員の負担となることが予測されます。
協働学習におけるCSCL
協働学習(あるいは協調学習)は、CSCLという単語と共に語られることもあります。CSCLは「Computer Supported Collaborative Learning」の略称。協働学習を行うにあたって、コンピューターを活用していくことを指す概念になります。協働学習において、ICT技術が必須なわけではありません。そのような技術を用いない協働学習はこれまでも行われてきました。ではCSCLで何が変わるのかというと、前述してきたように協働学習をより実りのあるものにすることが可能です。
これは、現代的な知的創造を行う際に必要なツールの学習をすることに繋がるでしょう。従来はノートとペンを使って学習をすることが基本でしたが、大学生を中心にタブレット端末を利用して学習を進めていくスタイルが流行しています。教育現場にタブレット端末が普及するにつれて、これはどんどん当たり前の風景になっていくはずです。協働学習と共に情報機器の取り扱いに習熟することで、将来役に立つスキルを身につけることができます。
協働学習まとめ
本記事では、「協働学習」という教育用語を題材にメリットやデメリットなどを解説いたしました!ICTと組み合わせると、海外の学校との交流やクラス内の意見交換が簡単にできてしまうのは魅力ですね。
従来のアナログの教具だと時間がかかっていた授業展開を大幅に時間短縮し、その分子どもたちの対話の場面を増やすこともできそうです。
ただし、協働的な活動を行うためには、クラス内での人間関係がある程度構築されている必要があります。
また、話し合いのルールなどもしっかり子どもたちに教えておかないと、効果的な対話にならずに混乱してしまう可能性もあります。
かなり先生個人の腕前や学級づくりに頼る部分もありそうです。
さらに、教育困難校や特別支援学校での協働学習実施の場合は配慮すべき要素も増えることでしょう。
とはいえ、ICTを用いた協働学習により、受け身ではなく主体的に授業に参加しやすくなることや他の生徒の意見についても意識的に考える場面を増やすことができます。
学校でのICT環境の整備も徐々に進んでおりますし、今後は協働学習を意識した幅広い授業スタイルが増えていくのではないでしょうか。
参考資料
文部科学省「平成29・30年改訂学習指導要領のくわしい内容」
文部科学省「学びのイノベーション事業」


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
モンテッソーリ教育は後悔する?簡単にわかりやすく解説
「モンテッソーリ教育ってよく聞くけど、一体どんな教育なの?」など、疑問に感じる保護者も多いでしょう。 モンテッソーリ教育は、言わば「教育の基礎となる考え方」ともいえます。この記事では...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
学力は世界でもトップレベル!でも?…PISA2022学力調査結果から見えてくる「子どもたちに必要なスキルとは」
PISA学力調査とは、世界中で実施されている学習到達度に関する調査です。PISA学力調査を見ていくと、世界と比較した日本の教育に関する実情がわかります。 今回の教育トピックでは、...
2025.05.30|大橋礼
-
アンプラグドプログラミングとは?パソコンを使わないプログラミング学習!
アンプラグドプログラミングという言葉をご存知でしょうか?小学校での必修化に向け、パソコンを使わずにプログラミングを学ぶ方法が注目を浴びています。具体的な内容、メリット、デメリットをわか...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
アダプティブラーニングとは?主要な学習ツール、メリット、デメリットを徹底解説!
文科省は「アダプティブラーニング」を、主体的・対話的で深い学びである「アクティブ・ラーニングと」同様に推進しています。 この記事では「適応学習」とも訳されるアダプティブラーニングにつ...
2025.10.29|千鳥あゆむ
-
オルタナティブ教育(オルタナティブスクール)とは?特徴とメリット、デメリットを解説!
「オルタナティブ教育」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? オルタナティブ教育とは文科省が定めた学校外での教育のことで、独自の理念と教育方針によって行われる教育になります。 今...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部