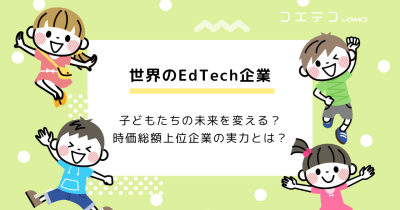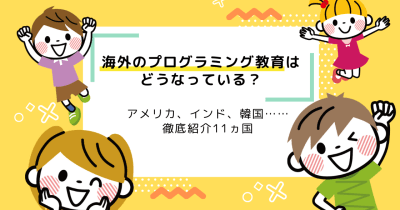アンプラグドプログラミングとは?パソコンを使わないプログラミング学習!
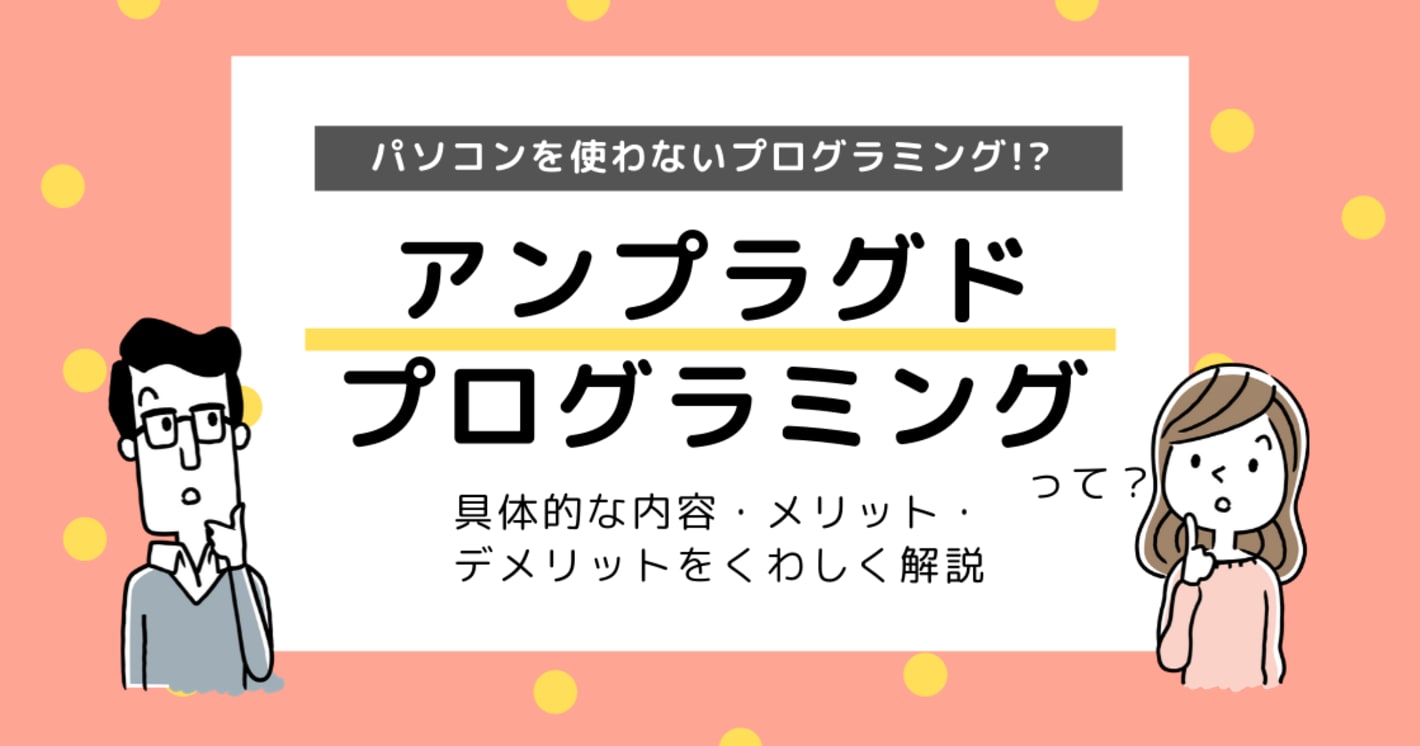
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
アンプラグドプログラミング(Unplugged=「電源プラグをつながない」の意味)とは、パソコンなどの端末を使わずに、プログラミングを学習すること。
「プログラミングの勉強なのに、パソコンを使わないの?」
「それって、ちゃんと効果があるの?」
と驚いた人も多いかもしれませんね。
でも、これはいま注目されている最新のプログラミング学習法。
その進め方とメリット、そして課題をわかりやすく説明します。
アンプラグドプログラミングとは?
アンプラグドプログラミングとは、パソコンやタブレットなどの電子機器を使わずにプログラミングの考え方を学ぶ学習方法です。小中学校でのプログラミング学習の目的は「実際にコンピュータを動かす力」以上に「ものごとを論理的にとらえて、解決法を組み立てていく能力の育成」にあります。つまり、プログラミングに関する「考え方」を学ぶのが「プログラミング学習」であり、そのためには、むしろコンピュータにふれる前の試行錯誤に意味があるとも言えるのです。
だからこそ、端末を使わずにグループワークによって進めていく授業=アンプラグドプログラミングが効果的になる。
このような考え方から、アンプラグドプログラミングを重視して教育方針に採用する教育委員会や学校が増えています。
アンプラグドでプログラミングを学ぶ目的は?
コンピュータを使わないアンプラグドプログラミング。どうしてこのやり方で学ぶのでしょうか?その答えは、プログラミングに取り組むために必要な論理的思考力を得ること。
ここでは、アンプラグドプログラミングで学ぶ目的と考え方について説明します。
コンピュータの仕組みを知る
たとえば、コンピュータは10進数でなく2進数を基礎としています。また、いろいろな色はRGB(Red、Green、Blue=赤緑青)の各色のレベルを0-256までの数字に置き換えて、その合成によってつくられます。
このようなコンピュータの基本的な仕組みを知ることなしに、プログラミングによって、動かしていくことはむずかしいでしょう。
そこでまずプログラミング学習の第一歩として「コンピュータとは何か」を学ぶ。
そのためには、アンプラグドプログラミングというコンピュータに直接ふれない学習方法が適していると言われます。
プログラミングの"基礎の基礎"を体験する
上にも書きましたが、最終的にコンピュータは、すべての命令を0と1に置き換えて動きます。小中学校ではもちろん、そこまで進むことはなく「楽しみながら、感覚的にプログラミングを学ぶ」ということが中心になります。
一方で、その基礎を理解していくことは非常に有意義でもあります。
たとえば、1バイト=8ビットであり、8桁の0と1で256通りの数字を示すことができる。
また、2進法でも10進法と同じように+-×÷の四則計算はできるということを体験的に学ぶことは、その先につづくプログラミング学習を理解するためにも大いに役立つことでしょう。
水泳の練習をするとき、まずはプールサイドで足の動かし方を練習しますよね。それと似ているかもしれません。
プログラミング的思考を身に付ける
プログラミング的思考の定義は「コンピュータの働きを理解しながら、何を使い、どう組み合わせて意図する処理にしていくかということを論理的に考えていく力」です。小学校や中学校の時点ではプログラミングそのものができることではなく、プログラミングに必要な論理的思考を身に付ける方がよいとも言われています。
この力は他の教科にも役立つだけでなく、大人になって何の職業についても必要とされる力でもあります。
そこでたとえば「掃除の手順」や「給食当番の決定の仕方」というような身近な課題を解決する手順(アルゴリズムといいます)をグループワークで話し合い体系化していくことは、将来のプログラミング学習にも、論理的思考を学ぶ上でも役立つものです。
実際のプログラミングでも紙を使う
仕事などでプログラミングを行う場合は、もちろんPCを使ってコードを書きます。しかし、プログラマーはずっとコードを書き続けているわけではありません。どのようにプログラミングをすれば問題を解決できるのか、頭の中でじっと考えている時間もかなり長いです。また、どのようにプログラミングをしていけば良いのか頭の中だけで考えても分からない場合は、紙に書いて論理構造を整理したりもします。数学の図形問題を解く時に、線を引いたり分かっている数字を書き込んでいったりしますよね。あれと同じような感覚です。それを元に、PCを使ってプログラミング・コーディングを行っていきます。
PCを使わないアンプラグドプログラミングの技術は、実際にプログラミングを行う上でも役に立つスキルなのです。
アンプラグドプログラミング学習の例
ここでは、実際にコンピュータを使わないでプログラミング学習を行う具体例を紹介します。2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子どもにおすすめのオンラインプログラミングスクールをまとめました。
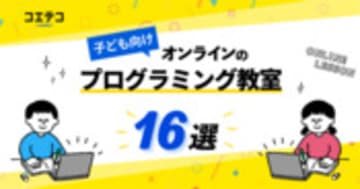

2026/02/03

2進数の学習
コンピュータのデータは0と1の列として保存されます。このことをグループワークを通して学んでいきます。
5人の子どもが5種類のカードを1枚ずつ持ちます。
そしてカードが裏返しで数が見えていないときは0、表になり見えているときは1と表します。
表になって見えているカードに示された数列の合計数を表します。
この実験を通し、0と1だけであらゆる数を示せると学びます。
画像を数で表す(画像表現)
コンピュータ上のすべての色は赤緑青3色の合成によってつくられ、色素・彩度・明度は3色それぞれ0から256までの数字によって示されます。また、黒は赤緑青が0-0-0、白は256-256-256で示すことができます。
そのことを理解するのが、この学習。
マス目のついたシートを使い、指示する数字に導かれるままにマスを塗っていくことによって目的とする画像が示されることを学びます。
数字によって画像を指示できることを理解して、将来の画像表示の知識につないでいきます。
出発進行(プログラミングのトライ&エラーの体験)
コンピュータが自分のイメージしたプログラム通りに動かないとイライラします。しかし、プログラミングでも意図したものとは違う結果になったのは、自分の指示が間違っているから。
トライ&エラーは、このことに気がつくよい経験になります。
そこで行われるのが「命令を細分化し、それにより期待される動作が行われるか」確認していく授業。
ひとりの子どもにある絵を見せます。
そしてその絵を言葉で説明していきます。
他の子どもたちはその言葉どおりに紙に点や線を描き、絵を仕上げていきます。
友だちを疑似コンピュータと見なし、命令を間違えると、正しい答えが出ないことを理解するために有効です。
アンプラグドプログラミングのメリット
アンプラグドプログラミングだからできること、期待される学習効果をまとめてみました。コンピュータの仕組みを楽しく理解できる
コンピュータの中身がわからなくてもソフトやアプリが使えればいいという意見もあります。が、将来、本格的なプログラムを行っていこうとするなら、出発点からコンピュータの仕組みを理解しておくといいのはいうまでもありません。
アンプラグドプログラミングを通じて、コンピュータの基本的な姿を学ぶことは、すべての原点として重要な学習となります。
2020年度、ついに小学校でプログラミング教育が必修化しました。コロナ禍の影響もあいまって、自宅からプログラミングが学べるオンラインスクールへの注目が集まっています。 この記事では子どもにおすすめのオンラインプログラミングスクールをまとめました。
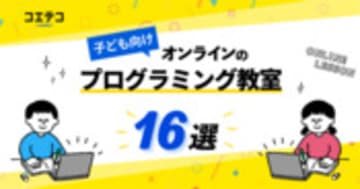

2026/02/03

コンピュータの扱いに慣れていない教師でもできる
残念なことに小中学校の教員のなかに、プロフェッショナルなプログラミングスキルを持っている人材はきわめて少数といえるでしょう。また、2020年のタイムリミットに向けて、全員にその知識を習熟させていくというのは、現実的ではありません。
しかし、日常の生活のなかで、たとえば掃除の進め方について、論理的に考えていく、ということなら、大きな困難はなく指導することができるでしょう。
アンプラグドプログラミングは、教師の負担を減らしながら、プログラミング的思考を育てるいい機会となります。
学校間のコンピュータ台数など格差を解決する
地域間の格差によって、生徒一人あたりの端末台数には差があります。一人一台が備えられているところもあればそうでないところもあります。
またプログラミング学習が必須となり全学年全クラスがコンピュータ室を利用するなら、時間割の調整は大変に困難となります。
端末がなくても授業ができるアンプラグドプログラミングは、端末などの設備が不足している学校にとって少なくとも今後数年間は有効な処方箋となるでしょう。
アンプラグドプログラミングの問題点
一方で、アンプラグドプログラミングの問題点も指摘されています。その代表的なモノをまとめてみました。
プログラミングをできたつもりになってしまう
アンプラグドプログラミングは、コンピュータの基礎を知るという上では、大変に有効な方法です。しかしもちろん、実際にコンピュータを使ってプログラムを動かさなくては、知識は完成したことになりません。
アンプラグドプログラミングは考え方を学ぶだけで、プログラミングそのものではない!
大きな意味でのプログラミング学習のなかでは、これらは単なる導入部分だということ、了解しあって進めることが大切ですね。
教師の力量が実は問われる
アンプラグドプログラミングは、全体が一つの「たとえ話」であるといえるでしょう。「毎日普通にやっていることを、コンピュータにさせようと思ったら、機械に対してこのように命令しなくてはいけない」
机の上で考えたり議論しながら、でも、それはじつはコンピュータの考え方のシミュレーションであること、きちんと理解させられないと、何のための授業か先生も生徒も見失ってしまうことになりそうですね。
コンピュータを使わないアンプラグドプログラミング学習は、簡単なようで実は教師の力量が問われます。
「いまやっている学習は、どのようなプログラミングのためか」きちんと説明しながら進めることが必要になってくるわけです。
グループワークが多いのでコントロールが難しい
一方的に教師が教えるのではなくグループワークを通してお互いに理解を深めていくのが、アンプラグドプログラミング。教員は、その司会役として横道にそれたりすることなく、議論をコントロールしていかなくてはなりません。
教員にとって事前準備がいままで以上に必要になり、その労働環境が過重にならないかということも心配されているところです。
アンプラグドプログラミングに関する保護者や教員の反応
プログラミング授業の必修化が発表されると同時に、さまざまな議論が起きました。アンプラグドプログラミングに関するものをいくつか紹介しましょう。
「将来、プログラマーになるわけではないのに、どうして?」
プログラマーになるわけでもないのに、プログラミング言語を学ぶ必要はないのではといった意見が保護者からありました。アプリケーションを使えれば、社会的な生活は十分だろうという考え方です。
もうひとつ懸念されることは、早くから学びわかった気になり興味を失ってしまったり、むずかしいという先入観を植え付けてしまうと、プログラミングをする楽しさ、おもしろさを見失ってしまうということでした。ただ、大学入試でプログララミング(情報科目)が必修科となる大学も出てきているため、学んで損はないでしょう。
参考:小学生や中学生がプログラマーになるには
「どう教えるのか、教える人材をどう確保するのか」
コンピュータのプログラミング自体、大人が皆できるものではなく、自分がどう覚えたかという経験をだれもがもっているわけではありません。また小学校の場合は一人の教員がすべての教科を教えるので、さらにプログラミングを教える負担は大変なものになります。
コンピュータを専門に教える教師が確保されている工業高校のように、プログラミングの専門家を招く必要がありますが、そういた人材をどう確保するのかという現場からの声もありました。
まとめ:課題も期待も大きい、それがアンプラグドプログラミング
2020年4月からのプログラミング学習必修化のなかで、教育現場ではその準備が着々と進められています。一方で教員の指導方法が確立していない、自由に使える端末が少ない……などの問題点も指摘されるようになってきています。
ここで紹介したように、アンプラグドプログラミングは正しく運用されれば、非常に効果的なものになるはずです。
しかし、軌道に乗るまでは、さまざまな場所で混乱が起きてしまうかもしれません。
家庭でも、ときどき授業について語り合う、必要な知識を補充するなどのバックアップが必要になるかもしれません。
必修化に向けて期待半分、課題半分。家庭でもできる対策をしておくのが有効かもしれませんね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
世界のEdTech企業|インド、中国、アメリカの注目企業をまとめて紹介!
小学校でのプログラミング教育必修化、そして新型コロナウィルスの影響によるオンライン需要の急拡大を受け、EdTech(エドテック)企業が注目を浴びています。EdTech業界は世界的に盛り...
2025.05.21|コエテコ byGMO 編集部
-
小中高で情報教育が大幅強化!2030年代に向けて親が知っておくべきこと
2025年9月、文部科学省が2030年代に向けた教育改革の方針を発表しました。注目すべきは「情報教育の抜本的強化」です。小学校から高校まで、子どもが学ぶ情報教育の内容が大きく変わります...
2026.01.02|大橋礼
-
協働学習とは?メリット・デメリットを徹底解説
今、「協働学習」が注目されています。背景には、文科省が期待するこれからの新しい学び方への考え方などが盛り込まれているようです。 この記事では「協働学習」のメリットやデメリットを分かり...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
ICT化で学校教育現場はどう変わる?メリット・効果・海外の事例まとめ
2020年、ついにプログラミング教育が小学校で必修化します。それに伴い、学校教育現場のICT環境整備も進められています。海外と比較して遅れていた日本のICT環境。整備が進むとどのような...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
海外のプログラミング教育はどうなっている?徹底紹介(11選まとめ)
小学校でプログラミング学習が必修化されます。そこで気になるのが一足早くプログラミング教育をはじめている海外の動向。世界の先進国や急速に発展している途上国では、どのような教育が行われてい...
2025.04.18|コエテコ byGMO 編集部