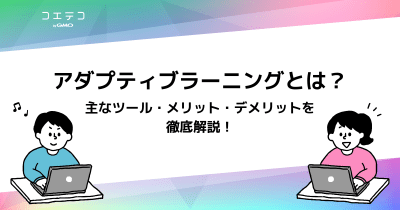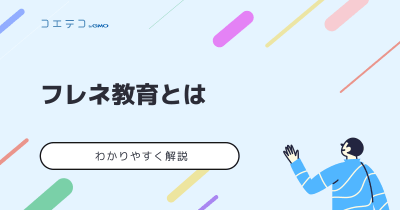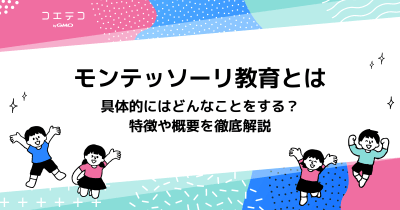アクティブラーニングはもう古い?文部科学省が推進する理由や事例を紹介

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
アクティブラーニングとは、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための学習方法です。
文部科学省も導入を推進してきましたが、「結局どのような授業なの?」「もう古いのでは?」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、アクティブラーニングの定義や背景、最新の教育現場での活用事例までわかりやすく解説します。
成功事例を通してアクティブラーニングの効果や魅力を紹介するので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
アクティブラーニングとは?基本概念と定義
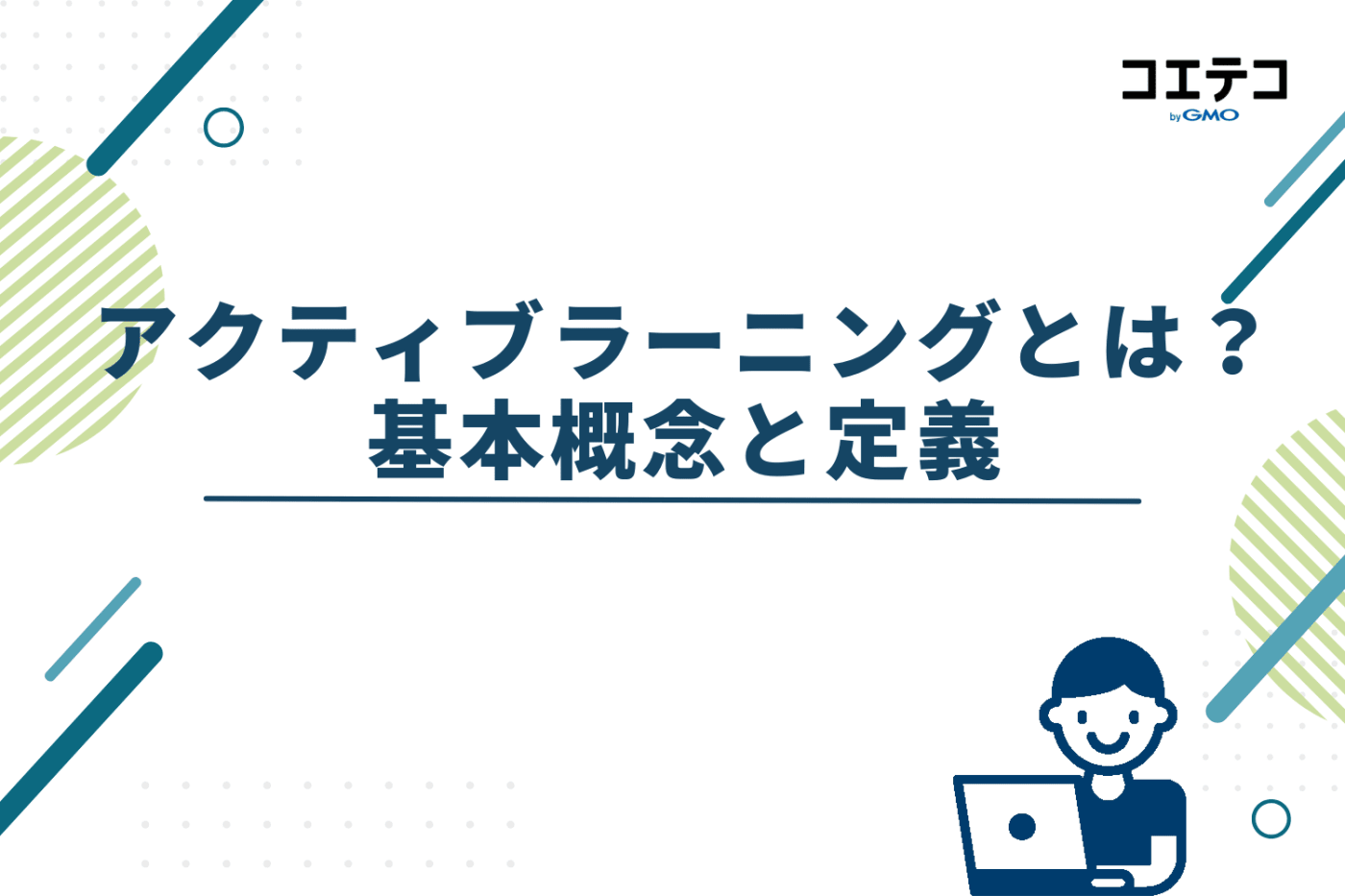
アクティブラーニング(Active Learning)とは、学習者が受動的ではなく能動的に学習に参加する学習方法の総称です。
従来の教師が一方的に知識を伝達する授業形態とは異なり、学習者自身が主体的に学習プロセスに関わることで、より効果的な学習を実現する教育手法として注目されています。
能動的学習としてのアクティブラーニング
アクティブラーニングは「能動的学習」と呼ばれ、学習者が自ら考え、積極的に授業運営に参加する手法を指します。
単に授業を聞くだけでなく、体験学習やグループ学習、ディスカッションなどを通じて、学習者が主体的に学習に取り組めるのが特徴です。
「何を学ぶか」よりも「いかに学ぶか」が重要視され、学習者の能動的な参加により、知識の定着だけでなく、思考力・判断力・表現力の向上も期待できます。
従来の受動的学習との違い
従来の日本の学校教育では、教師が教室で講義を行い、生徒は机に向かって受動的に授業を聞くスタイルが主流でした。
アクティブラーニングは、今までの受動的な学習方法と異なり、学習者の積極的な参加を促進します。
| 項目 | 従来の受動的学習 | アクティブラーニング |
| 学習者の役割 | 受動的な聞き手 | 能動的な参加者 |
| 教師の役割 | 知識の伝達者 | 学習のファシリテーター |
| 学習方法 | 講義中心 | 体験・対話・協働中心 |
| 評価方法 | 知識の暗記・再現 | 思考力・判断力・表現力 |
「主体的・対話的で深い学び」との関係
2020年から実施された新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」と表現されるアクティブラーニングの概念が導入されました。
アクティブラーニングの用語そのものは使用されていませんが、本質的な考え方は継承されています。
「主体的・対話的で深い学び」は以下の3つの要素から構成されています。
文部科学省の資料によると、従来の教育実践の蓄積を活かしながら、授業改善を進めることが重要とされているため、新しい指導方法の導入は必要ありません。
文部科学省がアクティブラーニングを推進する3つの理由
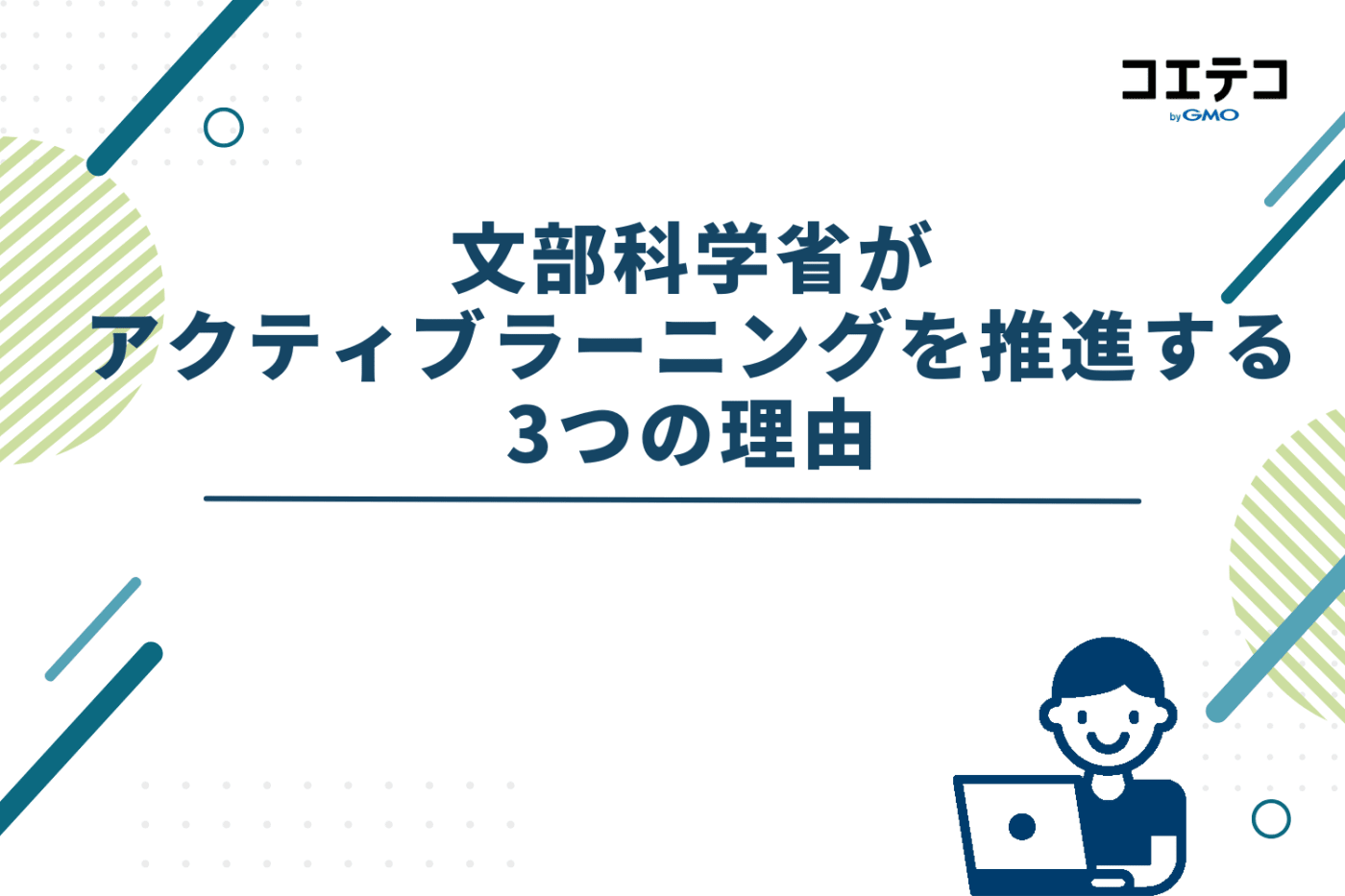
文部科学省が教育現場にアクティブラーニングの導入を推進する背景には、現代の教育や、将来に向けた人材育成の課題があります。
従来の一斉授業中心の教育から、生徒が主体的に学習に参加する教育スタイルへの転換が求められています。
新学習指導要領への導入背景
2020年度に全面実施された新学習指導要領では、アクティブラーニングの考え方が「主体的・対話的で深い学び」として位置づけられました。
従来の知識伝達型授業から学習者中心の授業への転換を意味しています。
学習指導要領の改訂では、単に知識を覚えるだけでなく、学んだ知識を活用して問題を解決する能力の育成が重要です。
文部科学省は、グローバル化や情報化が進む現代社会にて、受動的な学習では対応できない課題が増加していることを指摘し、能動的な学習スタイルの必要性を強調しています。
変化する社会への対応力育成
現代社会は急速な変化を続けており、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)などの技術革新により、従来の職業や働き方が大きく変わりつつあります。
既存の知識だけでは対応が困難な課題が次々と生まれるため、自ら学び続ける力が必要です。
文部科学省は、社会のグローバル化やIT産業の躍進により、知識が急速に陳腐化する現状を踏まえ、変化に対応できる柔軟な思考力と学習能力の育成を重視しています。
アクティブラーニングは、生徒が自ら問題を発見し、解決策を考え、実行する能力を養える教育手法として期待されています。
| 社会の変化 | 従来の教育の限界 | アクティブラーニングの効果 |
| グローバル化の進展 | 国内基準での知識伝達 | 多様な価値観への対応力 |
| 技術革新の加速 | 固定的な知識の暗記 | 新しい知識の習得能力 |
| 働き方の多様化 | 画一的な人材育成 | 創造性と協働性の育成 |
21世紀型スキルの必要性
21世紀型スキルとは、知識や技能だけでなく、思考力・判断力・表現力、さらには主体性・協働性・多様性を含む総合的な能力を指します。
文部科学省は、これらのスキルが現代社会で活躍する人材に不可欠と認識し、アクティブラーニングを通じて育成を図っています。
「育成すべき資質・能力の三つの柱」として挙げられているのは以下の要素です。
学びに向かう力・人間性など
知識・技能
思考力・判断力・表現力など
従来の講義中心の授業では十分な育成が困難であり、生徒同士の対話や協働学習を通じて効果的に身につけられます。
文部科学省は、アクティブラーニングが21世紀型スキルの育成に最も適した教育手法だと位置づけ、全国の学校現場での導入を推進しています。
アクティブラーニングで身につく能力と効果
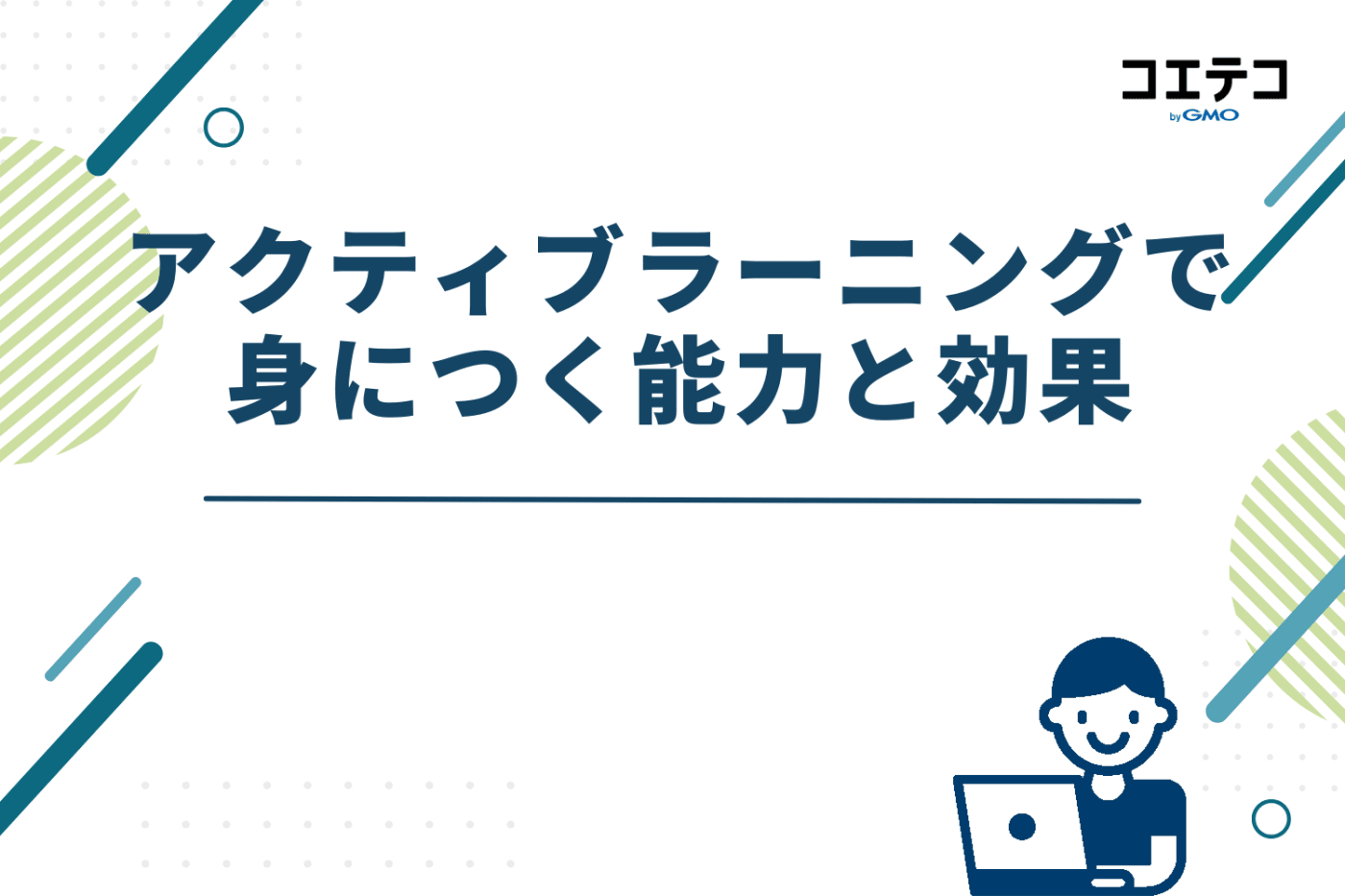
アクティブラーニングを実践すると、生徒たちは従来の座学中心の授業ではあまり身につけられない多様な能力を習得できます。
文部科学省が推進する新しい学習指導要領でも、能力育成が重要視されています。
思考力・判断力・表現力の向上
アクティブラーニングの重要な効果の一つが、思考力・判断力・表現力の3つの能力の総合的な向上です。
従来の知識を暗記する学習方法とは異なり、学習者が主体的に問題に取り組む過程で、自然に育成されます。
思考力は、与えられた課題に対して多角的に考察し、論理的に筋道を立てて問題を分析する力が身につきます。
ケースメソッドやPBL(課題解決型学習)などの手法を通じて、複雑な問題を構造化し、本質的な課題を見つけ出す能力が養われるでしょう。
判断力では、収集した情報を適切に評価し、最適な解決策を選択する能力が育成されます。
複数の選択肢がある中で、根拠を持って判断を下す力は、変化の激しい現代社会で特に重要な能力となるでしょう。
表現力では、自分の考えを相手に分かりやすく伝える能力が身につきます。
プレゼンテーションやディスカッションを通じて、論理的に説明する力や、相手の立場に立って伝える力が養われます。
主体性・協働性・多様性の育成
アクティブラーニングでは、主体性・協働性・多様性などの21世紀に求められる重要な資質が育成されます。
グローバル化が進む現代社会で、特に重要視されている能力です。
主体性の育成では、学習者が自ら学習目標を設定し、必要な情報を収集し、学習計画を立てて実行する能力が身につきます。
教員から与えられた課題を受動的にこなすのではなく、自分なりの問題意識を持って学習に取り組む姿勢が育つでしょう。
協働性では、他者と連携して課題に取り組む能力が養われます。
ジグソー法や協調学習などの手法を通じて、異なる意見を持つ仲間と建設的な議論を行い、よりよい解決策を見つけ出す力を習得可能です。
多様性の受容では、異なる価値観や文化的背景を持つ人々と協働する能力が育成されます。
さまざまな視点から物事をとらえ、多角的に問題を分析する力が養われると、包括的な解決策を見つけ出せるでしょう。
問題解決能力とコミュニケーション力
問題解決能力とコミュニケーション力は、アクティブラーニングを通じて身につく最も実践的な能力として位置づけられています。
学校教育だけでなく、将来の職業生活でも重要な役割を果たします。
問題解決能力の育成では、複雑な問題を分析し、適切な解決策を見つけ出す一連のプロセスを学習します。
問題の発見から解決策の実行、評価・改善まで、体系的なアプローチを身につけることで、さまざまな場面で応用できる汎用的な能力が養われます。
| 能力の分類 | 具体的な効果 | 育成される場面 |
| 認知的能力 | 思考力・判断力・表現力 | ディスカッション、プレゼンテーション |
| 社会的能力 | 協働性・多様性の受容 | グループワーク、協調学習 |
| 実践的能力 | 問題解決・コミュニケーション | PBL、ケースメソッド |
コミュニケーション力は、単に話す能力だけでなく、相手の意見を適切に理解し、建設的な対話を行う能力が身につきます。
ピア・インストラクションなどの手法を通じて、相手の理解度に応じた説明を行う力や、効果的な質問を投げかける力が養われるでしょう。
また、非言語コミュニケーションの重要性も学習し、身振り手振りや表情、声のトーンなどを適切に使い分ける能力も育成されます。
将来的に国際的な場面でも活用できる重要なスキルとなります。
アクティブラーニングの具体的な手法と実践方法
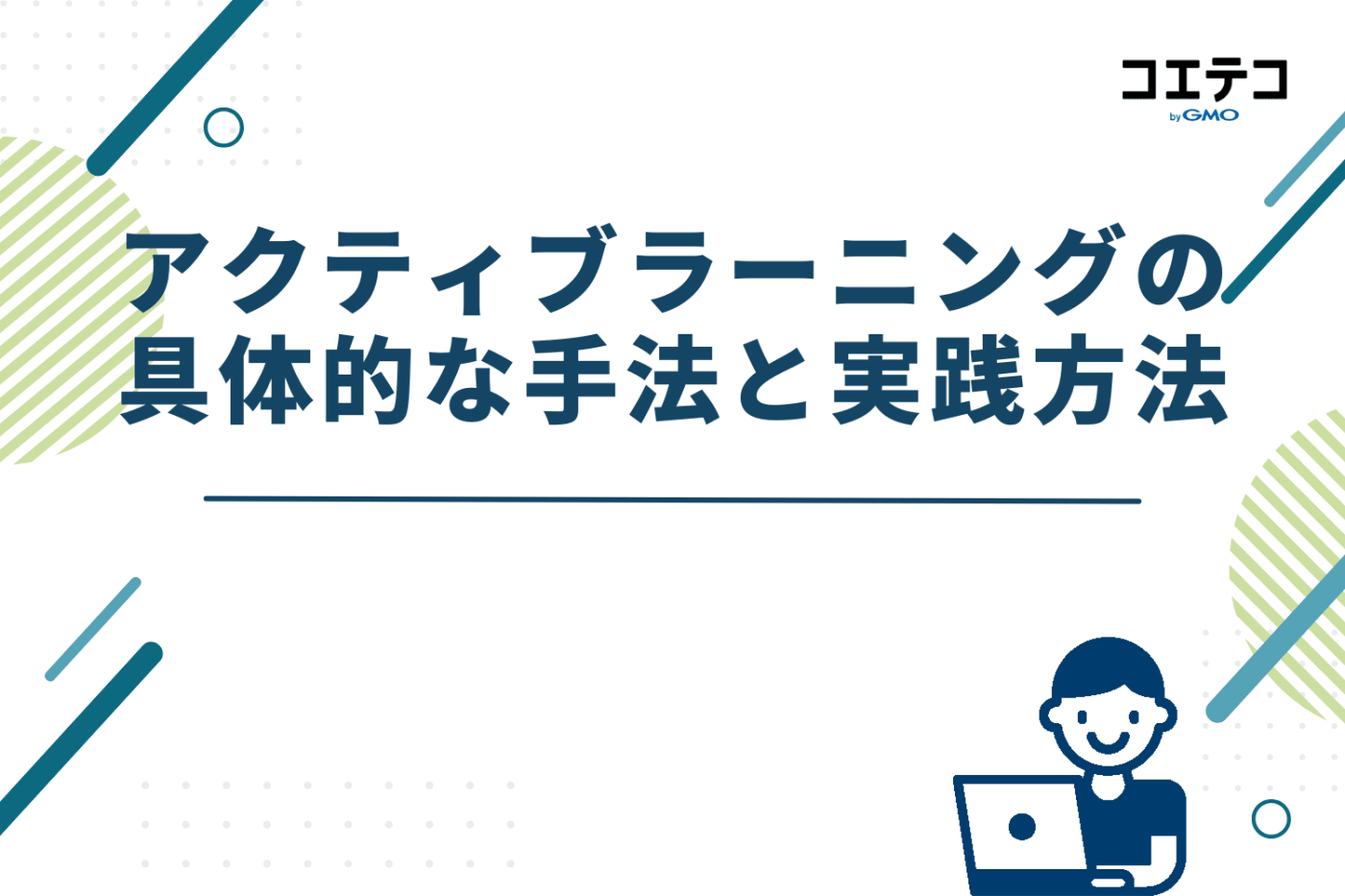
アクティブラーニングを効果的に実践するためには、具体的な手法を理解し、適切な場面での活用が重要です。
学習者の主体性を引き出し、協働的な学びを促進するための代表的な手法を紹介します。
ケースメソッド(事例研究法)
ケースメソッドは、実際に起きた事例を教材として活用し、学習者自身が問題の分析から解決策の提案まで行う学習手法です。
欧米のビジネススクールで広く採用されており、問題解決能力とリーダーシップ能力の向上が期待できます。
教員があらかじめ答えを用意するのではなく、学習者同士のディスカッションを通じて最適な解決策を導き出します。
たとえば、企業の経営判断に関する実際の事例を題材に、学習者が経営者の立場になって意思決定のプロセスを体験可能です。
ケースメソッドの特徴は、正解が一つではないことです。
多様な視点から問題をとらえ、根拠を持って自分の考えを発表すると、論理的思考力と表現力が向上します。
協調学習・協働学習
協調学習は、学習者同士が対話を通じて理解を深める学習形態です。
個別学習では得られない他者からの刺激を受けると、学習意欲の向上と知識の幅の拡大が可能です。
協働学習では、学習者が共通の目標に向かって役割を分担し、協力して課題に取り組みます。
それぞれの強みを活かしながら、お互いの不足を補い合うことで、より高いレベルでの学習成果を目指せるでしょう。
| 学習形態 | 特徴 | 期待される効果 |
| 協調学習 | 対話を通じた理解の深化 | 論理的思考力、コミュニケーション能力の向上 |
| 協働学習 | 役割分担による共同作業 | チームワーク、リーダーシップ能力の育成 |
ジグソー法
ジグソー法は、協調学習の一形態で、学習者がエキスパートグループとジグソーグループに分かれて学習を進める手法です。
知識構成型の学習方法として、多角的な視点から問題をとらえる能力の育成に効果的です。
まず、3つのエキスパートグループ(A・B・C)に分かれ、それぞれ異なる資料や観点から同一のテーマを学習します。
各グループは担当分野の専門家となるまで理解を深めます。
次に、各エキスパートグループから1名ずつが集まってジグソーグループを形成します。
このグループで、それぞれが学習した内容を共有し、統合的な理解を構築します。
最後に、全体でクロストークを行い、学習内容の統合と深化を図ります。
ジグソー法は、学習者全員が「教える側」と「学ぶ側」の両方の役割を経験できるのが利点です。
相互作用により、知識の定着と理解の深化が促進されます。
PBL(課題解決型学習)
PBLは「Project Based Learning」または「Problem Based Learning」の略称で、学習者が実際の問題や課題に取り組む学習手法です。
アメリカの教育学者ジョン・デューイの学習理論に基づき、問題発見から解決実行まで一連のプロセスを体験します。
PBLの特徴は、学習者自身が問題を設定し、解決策を考案・実行する点です。
与えられたテーマの中から疑問点や課題を見つけ出し、情報収集、分析、解決策の立案、実行、評価の一連の流れを経験します。
この手法では、結果の正確性よりも思考プロセスが重要です。
試行錯誤を通じて学習者の問題解決能力・創造性・自己主導性の育成を目指します。
医学部や工学部などの専門教育分野で特に効果的とされています。
ピア・インストラクション
ピア・インストラクションは、ハーバード大学で開発された講義型授業の中で行われるアクティブラーニング手法です。
学習者同士が教え合い、深い理解と定着を促進するのが特徴です。
授業では、コンセプトテストと呼ばれる概念理解を確認する問題が出題されます。
学習者は個人で回答した後、近隣の学習者と議論を行い、再度回答します。
理解が不十分な学習者は理解している学習者から説明を受け、理解している学習者は教えることでさらに理解を深めましょう。
クリッカーなどの回答システムを使用すれば、教員は学習者の理解度をリアルタイムで把握でき、授業の進行を調整可能です。
ピア・インストラクションの効果は、学習者が「分からない人の気持ち」を理解している点にあります。
同じレベルの学習者同士だからこそ、より分かりやすい説明ができる場合があります。
学校教育現場での導入状況と変化
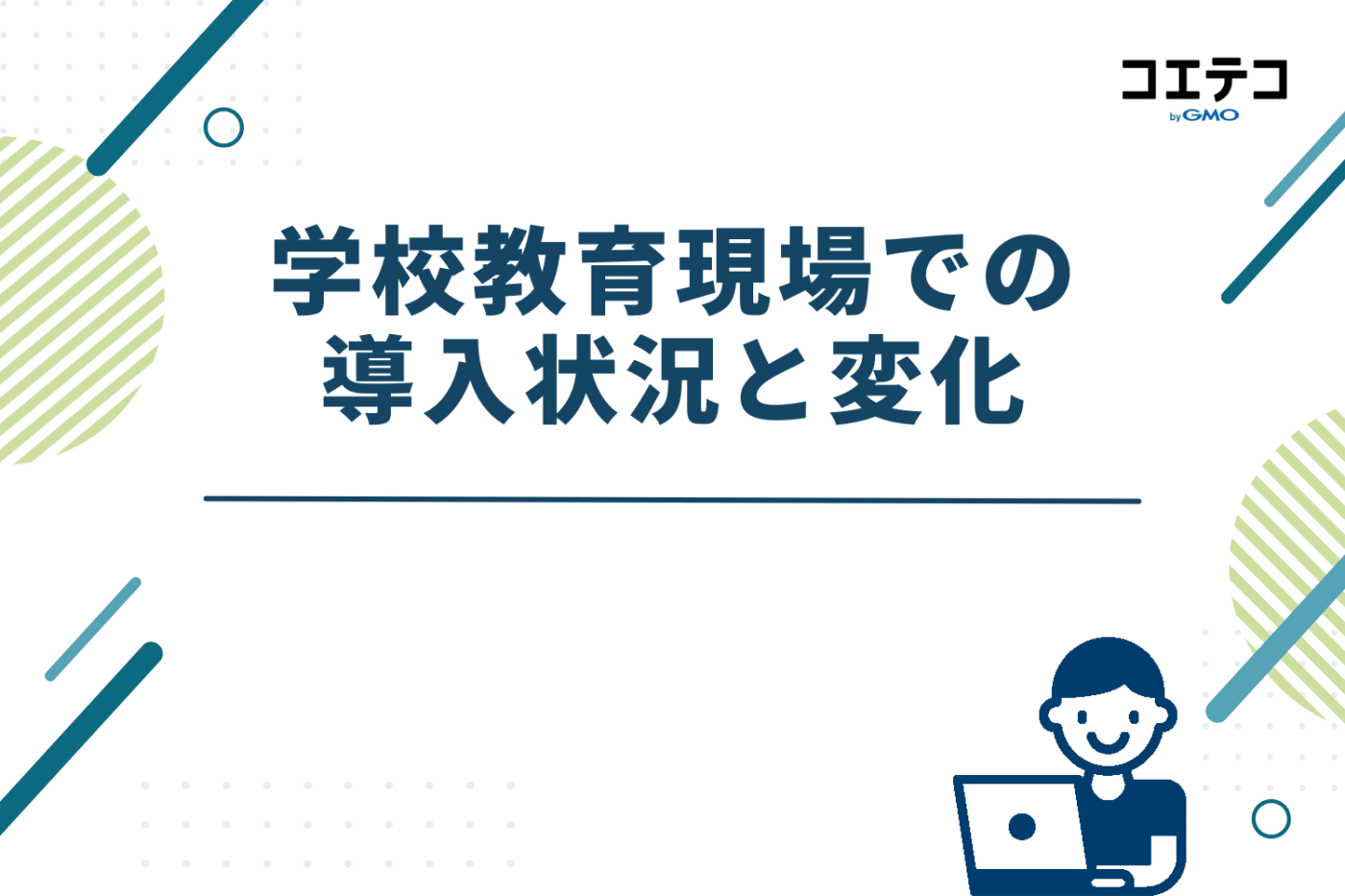
2020年度に全面実施された新学習指導要領により、日本の学校教育現場は大きな変化を迎えています。
アクティブラーニングの用語は学習指導要領から削除されましたが、その理念は「主体的・対話的で深い学び」として引き継がれ、教育現場での実践が進められています。
新学習指導要領での位置づけ
新学習指導要領では、アクティブラーニングに代わって「主体的・対話的で深い学び」の表現が採用されました。
文部科学省は改定のポイントとして、「小・中学校においては、これまでとまったく異なる指導方法を導入しなければならないと浮足立つ必要はなく、これまでの教育実践の蓄積を若手教員にもしっかり引き継ぎつつ、授業を工夫・改善する必要」と示しています。
学習指導要領解説では、「単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善を進めること」と明記されており、従来の教育実践を基盤としながら、学習者主体の授業改善を推進する方針が示されています。
育成すべき資質・能力の三つの柱
新学習指導要領では、学習者に育成すべき資質・能力として「三つの柱」が定められています。
能力育成では、主体的・対話的で深い学びが重要な役割を果たすとされています。
| 柱 | 内容 | 学校教育法での表現 |
| 第一の柱 | 何を理解しているか、何ができるか | 知識・技能 |
| 第二の柱 | 理解していること・できることをどう使うか | 思考力・判断力・表現力 |
| 第三の柱 | どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか | 主体的に学習に取り組む態度 |
この三つの柱は、学校教育法第30条第2項にも対応しており、知識の習得だけでなく、知識を活用して主体的に学習に取り組む姿勢の育成が重要です。
教員の役割変化と授業改善
主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、教員の役割は大きく変化しています。
従来の知識伝達型の授業から、学習者の主体性を引き出し、対話を促進するファシリテーター的な役割への転換が求められています。
具体的に変わったのは以下の点です。
一方向的な講義形式から双方向的な授業形式への変更
学習者同士の対話や協働学習の促進
課題解決型の学習活動の導入
学習者の思考過程を重視した評価方法の採用
教員には、学習者の多様な考えを引き出し、深い学びにつなげる指導技術が求められており、研修機会の充実や指導方法の改善が継続的に行われています。
また、授業改善では、学習内容以上に学習の仕方の変化が重要視されており、教員と生徒、生徒同士の関わり方にも大きな変化が生じています。
「アクティブラーニングは古い」と言われる理由
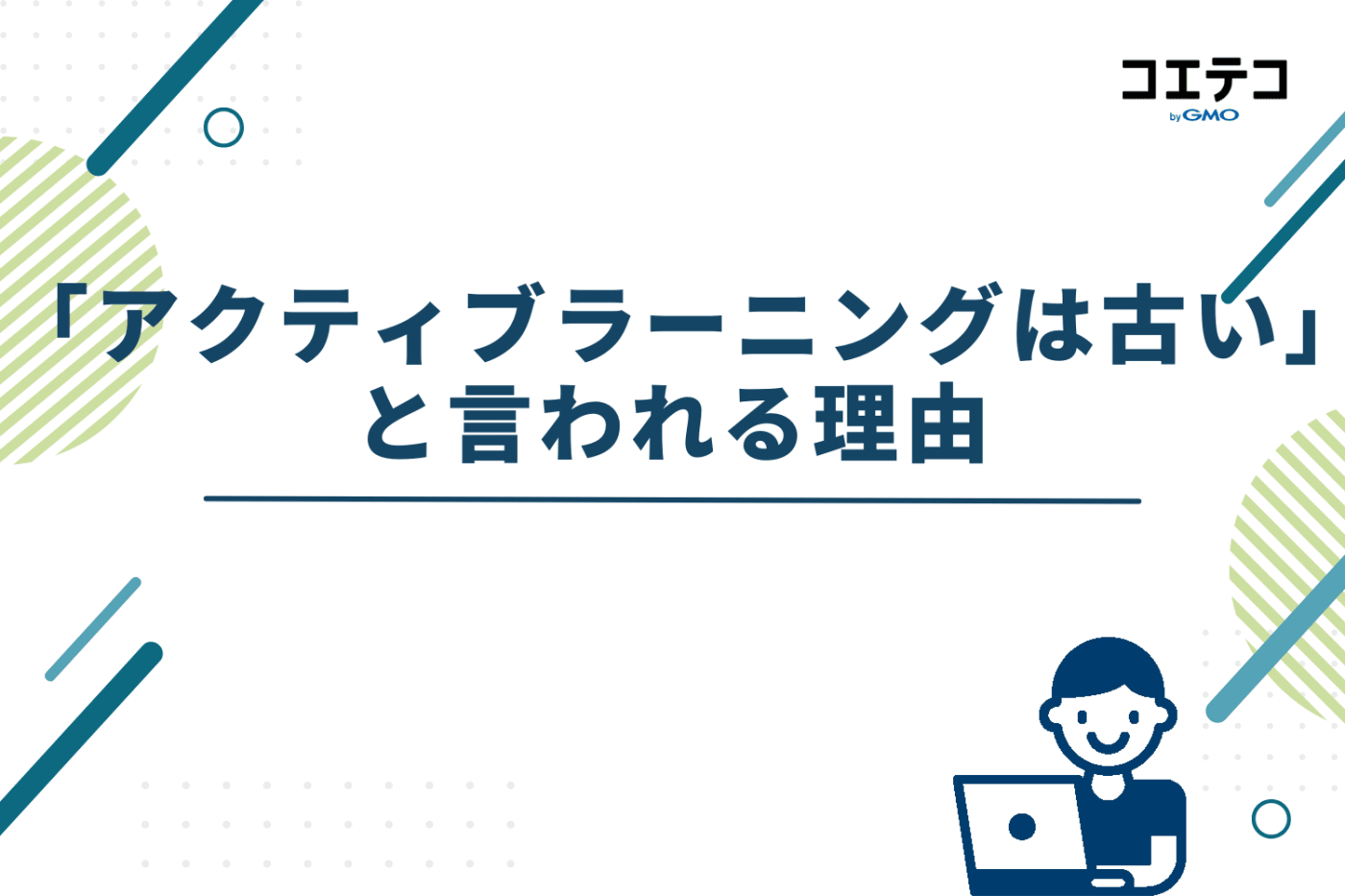
アクティブラーニングの言葉は、教育界で一時期大きな注目を集めていましたが、現在では「古い」と言われることが増えています。
教育政策の転換、技術の進歩、実践の際の課題など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
学習指導要領からの表現変更
2015年に中央教育審議会の答申で注目されたアクティブラーニングは、2017年告示の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」の表現に変更されました。
文部科学省は、アクティブラーニングの言葉が手法のみに焦点を当てがちなので、学習の質を重視する表現に改めました。
この変更により、教育現場ではアクティブラーニングの用語そのものが使われなくなり、結果として「古い概念」のイメージが定着しました。
しかし、本質的な理念は継承されており、単なる名称の変更にとどまらず、より本質的な学習改善への転換を意味しています。
デジタル技術の発展と教育手法の進化
ICT教育の急速な普及により、タブレット端末やAI教材を活用した個別最適化学習が注目されています。
特に新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン学習が一般化し、デジタル技術を活用した学習手法が「新しい」教育として認識されています。
GIGAスクール構想の推進により、1人1台端末環境が整備され、従来のグループワークを中心としたアクティブラーニングよりも、デジタル技術を活用した学習が現代的とみなされるようになりました。
アクティブラーニングは相対的に「古い手法」の印象を持たれやすいです。
本来の教育効果が発揮されない課題
日本の教育現場では、アクティブラーニングの形式だけを真似て、本来の教育効果を発揮できない事例が多く見られました。
グループワークの実施が目的化し、深い学びに至らないケースや、教員の指導力不足により効果的な実践ができない状況が指摘されています。
| 課題 | 具体的な問題 | 影響 |
| 形式化 | グループワークの実施が目的化 | 深い学びに至らない |
| 指導力不足 | 教員の研修不足 | 効果的な実践ができない |
| 評価方法 | 従来の評価基準のままで実施 | 学習成果が適切に測定されない |
また、欧米で発展したアクティブラーニングの手法を日本の教育文化に適応させる際の困難さも指摘されています。
集団主義的な文化の中で、個人の主体性を重視する学習スタイルを定着させる難しさが、アクティブラーニングの効果を限定的にしてしまう要因となっています。
これらの課題により、アクティブラーニングは期待されたほどの成果を上げられず、教育界では「古い」「効果が限定的」と評価を受けることが多くなりました。
しかし、根本的な理念の主体的な学習の重要性は変わらず、現在も「主体的・対話的で深い学び」として教育現場で実践され続けています。
日本の学校でのアクティブラーニング成功事例
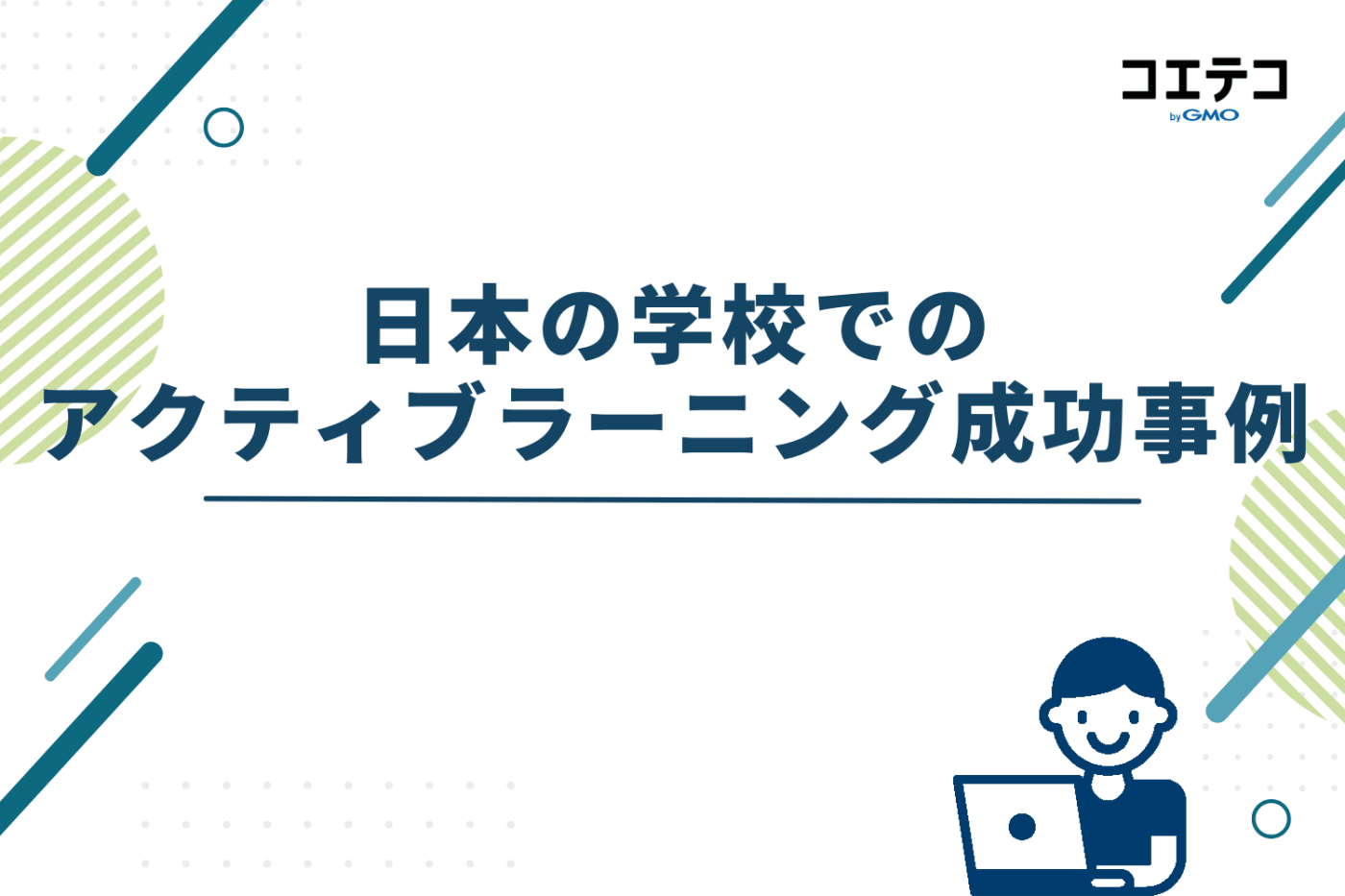
アクティブラーニングの導入により、日本の学校教育現場では多様な実践が展開されています。
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた具体的な取り組みとして、以下の事例を紹介します。
渋谷教育学園渋谷中学高等学校の取り組み
「自調自学」を校訓とする渋谷教育学園渋谷中学高等学校は、SGH(スーパーグローバルハイスクール)に選定された学校として、早期からアクティブラーニングを導入しています。
自主性を重視した教育方針のもと、ノーチャイム制度や校則の自由化などの特徴的な取り組みを実践しています。
| 取り組み内容 | 実践方法 | 期待される効果 |
| 自調自考論文 | 高校1年から2年間かけて制作 | 自主的な研究力・表現力向上 |
| 校外研修 | 行先・テーマを生徒が決定 | 主体的な学習姿勢の育成 |
| プレゼンテーション | 研修成果の発表・共有 | コミュニケーション能力向上 |
自調自考論文の制作プロセス
同校の特徴的な取り組みの自調自考論文は、生徒が自らテーマを設定し、必要な資料収集から執筆までを一貫して行う長期プロジェクトです。
教員はアドバイザーとしての役割に徹し、生徒からの求めに応じて助言を提供する形式を採用しています。
論文制作では、問題発見から解決策の提案まで、生徒の主体性を尊重した指導が行われており、思考力・判断力・表現力の総合的な育成を図っています。
校外研修での実践的学習
校外研修では、事前学習・フィールドワーク・プレゼンテーションの一連の流れを通じて、実践的な学習方法を展開しています。
生徒が研修先やテーマを自主的に決定するため、主体的に学習に取り組めます
岩手県立盛岡第三高等学校の参加型授業
岩手県立盛岡第三高等学校では、2006年に学校改革を実施し、従来の詰め込み型教育から参加型授業のアクティブラーニングへの転換を図りました。
SSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業の一環として、地域の特性を活かした教育実践を展開しています。
被災地復興を考える授業実践
東日本大震災の被災地の地域特性を活かし、「SD総合」カリキュラムで被災地復興をテーマとした授業を実施しています。
被災地見学、がれき処理体験、復興特別講座、街づくり提案など、多角的なアプローチで学習を進めています。
生徒は現地での体験学習を通じて問題を発見し、復興に向けた具体的な提案をレポートとして制作・発表するため、社会課題に対する理解を深められるでしょう。
学校改革による効果と成果
アクティブラーニングの導入により、保健室利用者数や教育相談の訴え数が激減するなど、学力向上以外にも多面的な効果が確認されています。
生徒の学習意欲向上と精神的な安定が同時に達成されている事例として注目されています。
大分県佐伯市立木匠小学校の日常授業改善
大分県佐伯市立木匠小学校では、特別なカリキュラムを新設するのではなく、通常の授業内容をアクティブに変更し、アクティブラーニングを実践しています。
通常授業のアクティブ化
既存の授業内容に対して、取り組み方を変更したり、少しアレンジを加えたりすると、実質的にアクティブラーニングとして授業が機能します。
新聞づくりなどの活動も、従来の手法でありながらアクティブラーニングの要素を含んだ実践として位置づけられています。
身近な題材を活用した学習
普段使用している道具の仕組みを探究するなど、身近な題材を活用した発想の転換によって、児童の主体的な学習姿勢を引き出しています。
日常的な疑問から学習への関心を高め、探究心を育成する取り組みが評価されています。
アクティブラーニングの課題と今後の展望
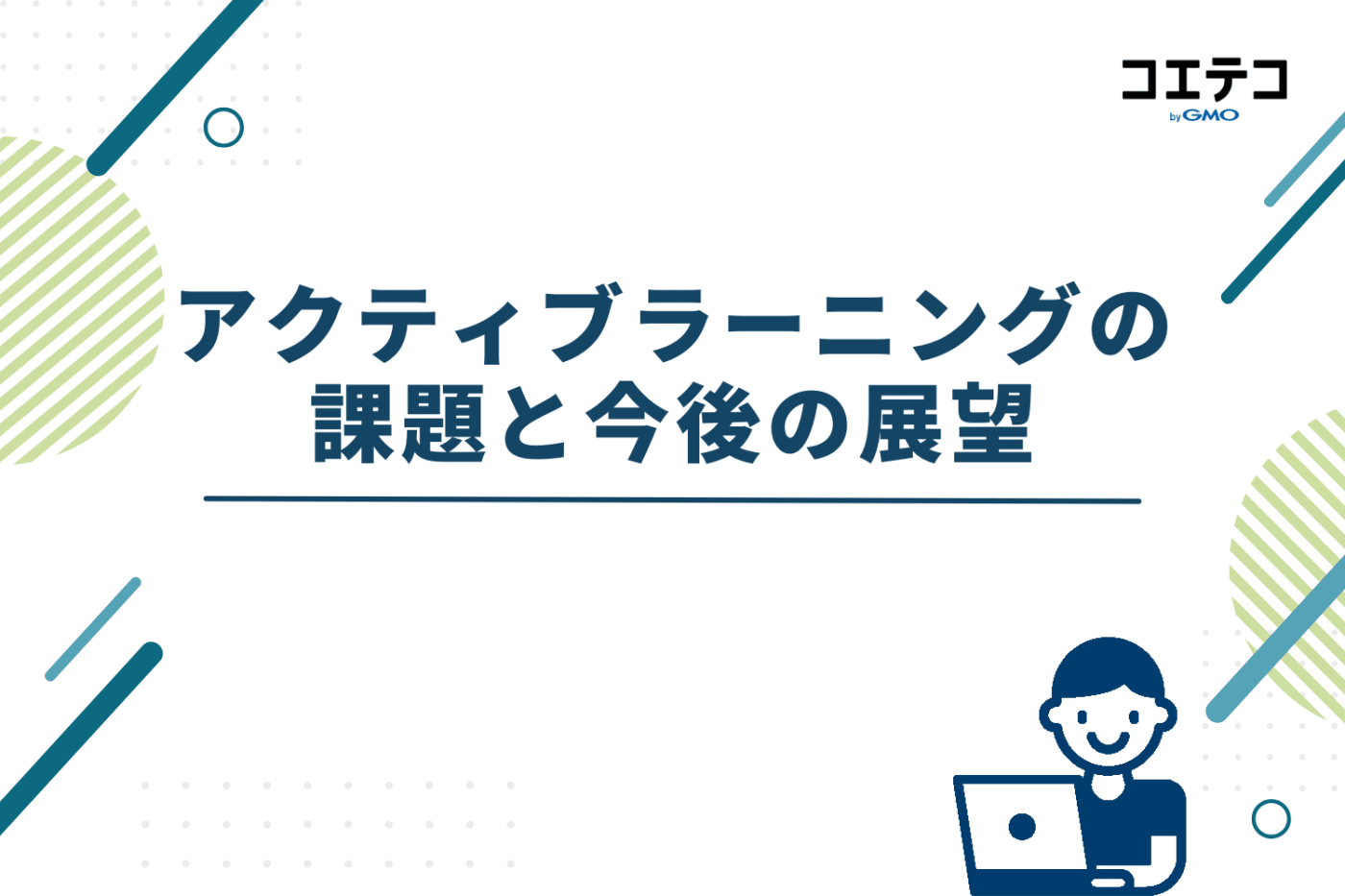
アクティブラーニングの普及が進む一方で、教育現場ではさまざまな課題も浮き彫りになっています。
課題を解決し、より効果的な学習環境を構築するために、今後の展望を含めて詳しく解説します。
導入の障壁と解決策
アクティブラーニングの導入には、従来の教育システムに根ざした複数の障壁が存在します。
最も大きな課題は、教育現場での意識改革と体制整備です。
| 主な障壁 | 具体的な課題 | 解決策 |
| 時間的制約 | 授業時間内での実施が困難 | 単元全体を通した計画的な実施 |
| 設備・環境不足 | グループワークに適した教室環境の欠如 | 段階的な設備改善と既存環境の活用 |
| 評価方法の未確立 | 従来のテストでは測れない能力の評価 | ルーブリック評価やポートフォリオ評価の導入 |
| 保護者・地域の理解不足 | 新しい学習方法への不安や反発 | 説明会や成果発表会による理解促進 |
特に重要なのは、学校全体としての取り組み体制の構築です。
個々の教員の努力だけでは限界があり、管理職のリーダーシップのもと、組織的な改革が求められています。
教員研修と指導力向上の必要性
アクティブラーニングの成功は、教員の指導力に大きく依存します。
従来の一斉授業とは異なるファシリテーションスキルが必要となるため、体系的な教員研修プログラムの充実が急務です。
効果的な研修には以下の要素が重要です。
実践的なワークショップ形式での研修により、教員自身がアクティブラーニングを体験し、効果と手法を理解できます。
また、授業観察とフィードバックを通じて、実際の授業改善につなげられます。
教員同士の学び合いの場の創出も重要です。
校内研修や授業研究会を通じて、成功事例の共有や課題解決に向けた協働が促進されます。
新任教員への指導体制も整備し、経験豊富な教員のノウハウを継承していく仕組みが必要です。
評価方法の見直しと改善
アクティブラーニングで育成される能力は、従来のペーパーテストでは測定が困難な場合が多く、新しい評価方法の開発と実践が求められています。
パフォーマンス評価では、実際の課題解決過程や発表内容を通じて、思考力や表現力を評価します。
ルーブリック評価により、評価基準を明確化し、学習者にとって分かりやすい評価システムの構築が可能です。
また、形成的評価の重視も重要な観点です。
学習過程での継続的な評価により、学習者の成長を支援し、教員も授業改善のためのフィードバックを得ることができます。
ポートフォリオ評価やピア評価の導入により、多角的な評価が可能です。
デジタル技術の活用も評価方法の改善に貢献します。
学習管理システムやデジタルツールを活用すると、学習過程の記録や分析が効率化され、より精緻な評価が可能になります。
今後の展望として注目されているのは、アクティブラーニングとデジタル技術の融合です。
AI技術を活用した個別最適化された学習支援や、VR・AR技術を用いた没入型学習体験など、新しい可能性が広がっています。
課題解決には時間と継続的な努力が必要なので、文部科学省や教育委員会、学校、そして教員の連携による、持続可能な改善システムの構築が求められています。
まとめ
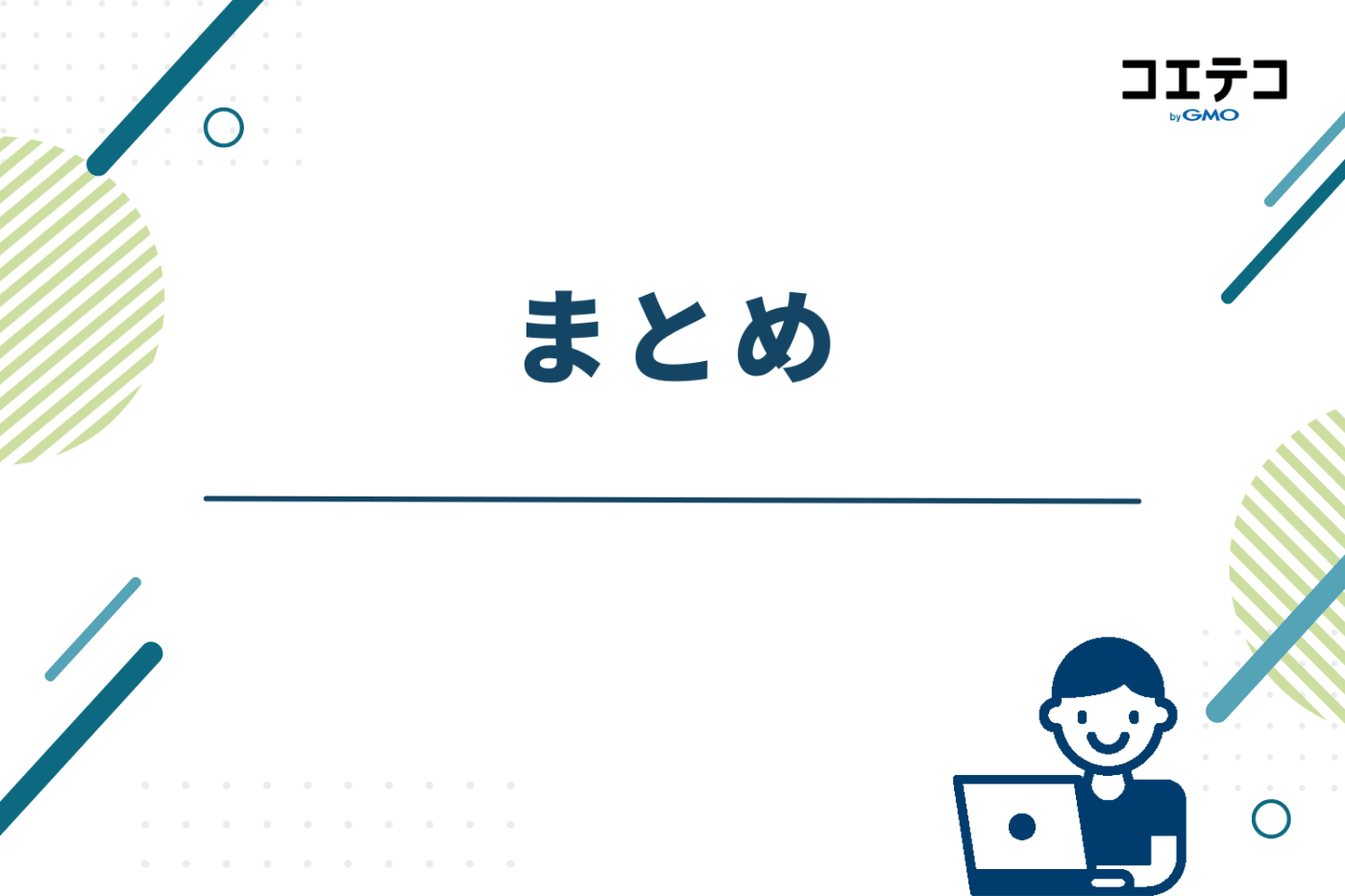
アクティブラーニングは古いのではなく、「主体的・対話的で深い学び」と呼び方を変えて現代も教育現場で活用されています。
子どもたちの思考力・判断力・表現力、そして主体性・協働性を育成するためには、アクティブラーニングの手法が必要です。
現場への導入での課題は残っていますが、学校での成功事例をヒントにして、授業の改善につなげられるとよいですね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
アダプティブラーニングとは?主要な学習ツール、メリット、デメリットを徹底解説!
文科省は「アダプティブラーニング」を、主体的・対話的で深い学びである「アクティブ・ラーニングと」同様に推進しています。 この記事では「適応学習」とも訳されるアダプティブラーニングにつ...
2025.10.29|千鳥あゆむ
-
ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説
教育現場で、新たな評価方法として注目を集めるルーブリック。アクティブ・ラーニングが授業に導入されるようになり、ルーブリックが採用される大学や高校も増加傾向にあります。この記事では、ルー...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
フレネ教育は子どもの自由な思想を育む教育メソッド!導入されている学校は?
フランスで誕生した教育メソッドであるフレネ教育は、子どもが自発的に学ぶ姿勢を育めることが特徴です。自由作文が教材となるため、文章力や探求心を伸ばせるメリットも。この記事では、フレネ教育...
2023.11.14|コエテコ byGMO 編集部
-
モンテッソーリ教育は後悔する?簡単にわかりやすく解説
「モンテッソーリ教育ってよく聞くけど、一体どんな教育なの?」など、疑問に感じる保護者も多いでしょう。 モンテッソーリ教育は、言わば「教育の基礎となる考え方」ともいえます。この記事では...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
【小学校】ALT/JTEって何の職員?授業での役割とは
「ALT」や「JTE」は英語の授業に関わる先生たちのことを指します。 この記事では、ALTとJTEの意味、必修化した小学校英語、ALTとJTEの勤務体系をご紹介します。
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部