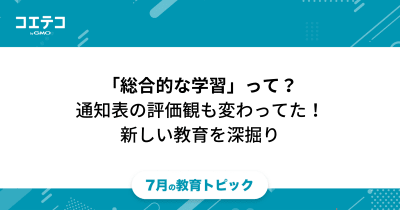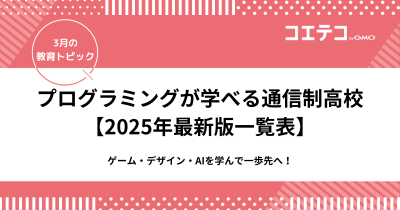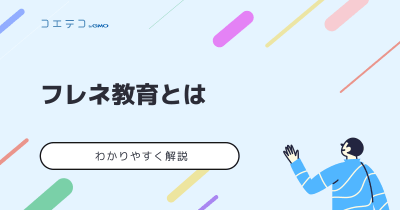探究学習とは何のこと?学習内容や事例を徹底解説!
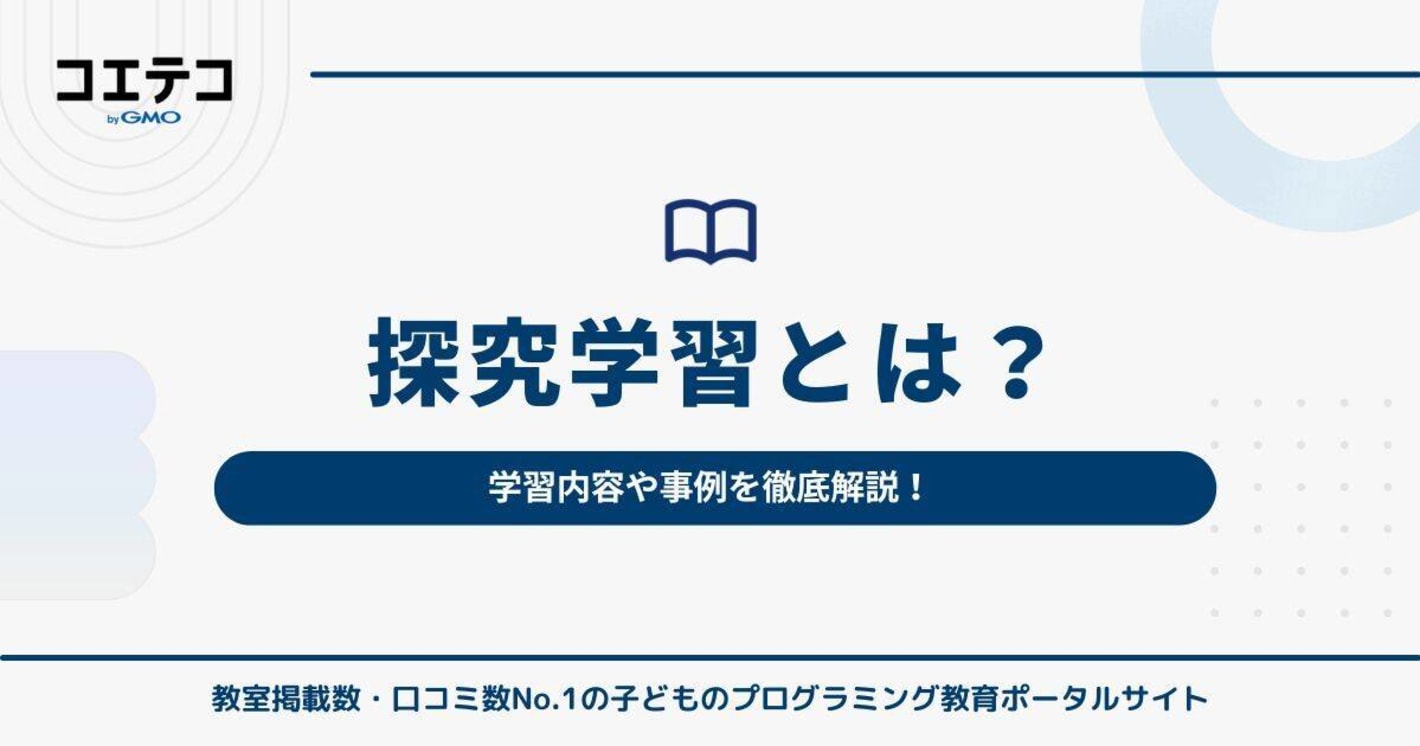
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
2022年度から高校生の新科目として追加された「探究学習」という言葉をご存じでしょうか?AIの進化やデジタル化が推し進められる時代のなかで、昨日は正解だったものが明日は不正解になる日もやってくるかもしれません。
めまぐるしい変化がある時代のなかで、自分で考え、答えを出すことの重要性が注目されるようになりました。学生には受け身ではなく、主体性のある人格を求められるようになっています。
この記事では、主体性を育む探究学習の特徴や実際に探究学習を導入している学校の代表例をわかりやすく紹介します。
探究学習とは?
学習指導要領の改訂に伴い、高等学校の「総合的な学習の時間」は、2022年度から「総合的な探究の時間」に変更されました。・高等学校においては,名称を「総合的な探究の時間」に変更し,小・中学校における総合的な学習の時間の取組を基盤とした上で,各教科・科目等の特質に応じた「見方・考え方」を総合的・統合的に働かせることに加えて,自己の在り方生き方に照らし,自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら「見方・考え方」を組み合わせて統合させ,働かせながら,自ら問いを見いだし探究する力を育成するようにした。引用:文部科学省
探究学習とは、教科や科目の枠を超えた横断的、かつ総合的な学習を指します。具体的には、地域活動を通して、自分が住む地域の問題点や課題を発見し、解決策を探究するなどがあります。
探究学習では地域活動のほかにも、自然環境や社会貢献など幅広いテーマを用いて学習が進められます。従来の授業では問いに対して答えが用意されていますが、探究学習では自らで課題を見つけ解決策を探し出します。探究学習を通して、自身の新しい考えや個性が発見できることもあるでしょう。
探究学習をすることで、身近な地域の問題やグローバルな環境問題まで考えるきっかけにもなります。探究学習で得られた情報はまとめて、他の生徒にも内容が伝わるよう発表します。
AI時代における探究学習の位置づけ
2025年5月、中央教育審議会において「質の高い探究的な学びの実現」について議論が行われました。生成AIをはじめとするデジタル技術が飛躍的に発展する中で、小中高等学校を通じた情報活用能力の抜本的向上を図る必要性が指摘されています。特に注目すべきは、探究的な学びが生成AIの苦手とする部分と高い親和性を持つという点です。自ら課題を設定すること、批判的思考、創造的思考、他者との対話や協働といった能力は、AIには代替できない人間の強みとなります。
文部科学省では、生成AI等の先端技術の特性理解を基盤としながら、情報モラルやメディアリテラシーを併せて育む方向性を検討しています。探究的な学びと情報活用能力の一体的な充実をめざし、以下のような方向性が示されました。
小学校
総合的な学習の時間に情報活用能力を育む領域を付加する方向
中学校
技術分野を充実させ、生成AI等の先端技術を含めた適切な取扱いや特性の理解を学ぶ方向
高等学校
情報科の内容を充実し、探究的な学びとの連携を強化する方向
参考:文部科学省「質の高い探究的な学びの実現(情報活用能力との一体的な充実)」
「子どもにもAIを学ばせた方がいいの?」といった疑問については、下記記事で解説しています。
プログラミングスクールで実施されているAIコースの内容についても詳しく解説紹介しているので、気になる方はあわせてご覧ください。
うちの子でもAIがわかる!アルスクールの楽しく学べるAIコースが注目を集める理由
探究学習の授業内容とは?
探究学習は、以下のようなステップで進められます。- 体験活動を通して課題を設定する
- 必要な情報を収集する
- 情報を整理して分析する
- 気付きや考えをまとめて発表する
すべてのステップにおいて、生徒自身が主体的に行動を起こす必要があります。自身で立てた問いの答えを見つけるために、必要だと思われる情報を収集することも探究学習において大切な要素になります。
また、最も重要なステップといえるのが、学んだ内容をまとめて最後に発表することです。学びをアウトプットすることで、生徒同士で議論しあったり学びをより深められたりします。
なお、下記記事では子どもが主体的に学ぶまでの過程について触れています。
発表会からAI学習まで、時代に対応した学習機会を提供するプログラミングスクールに直接話を伺っているので、ぜひご覧ください。
小学生が夢中になる!コードオブジーニアスジュニア・オンライン校の魅力に迫る
探究学習が必要な理由
探究学習の目的は学び方を身に付けることです。全く知らないものに出会ったとき、対応の仕方が分からなければ理解が進みませんし問題を解決するのも難しいでしょう。探究学習で知らないものに対する接し方を身に付けることで、どのようなアプローチで課題を解決できそうか道筋をつけられます。
たとえば卒業後の進路を考えるとき、探究学習の経験があれば「何をしたいか」「どう生きるべきか」などを自発的に考えられます。
小学生の探究学習とは
小学校の探究学習は「総合的な学習の時間」になります。課題の設定、情報の収集、整理と分析、まとめ・表現といった探究学習のプロセスを授業の中で学びます。小学生では、身近な環境から課題を見つけることが推奨されています。関心を持って身の回りを観察し、課題を見つけて探究することは、地域や周辺の人々と関わることにもつながり、学校だけでなく地域へと広がる学習となっています。
参考:今求められる力を高める総合的な学習の時間の展開(小学校編)/文部科学省
中学生の探究学習とは
中学生においても探究学習は「総合的な学習の時間」に位置づけられていますが、小学校よりもさらにプロセス(課題の設定、情報の収集、整理と分析、まとめ・表現)を深く理解し、実践するスキルを身につけることが求められます。自ら課題を見出し、課題解決のためにフィールドワーク等も取り入れて情報を収集し、それらをまとめていく過程で生徒はさまざまなことを学びます。
高校生の探究学習とは
高校では「総合的な探究の時間」となり、生徒たち自身が主体的に課題を設定し、成果や研究結果を発表します。高校における探究学習の特徴は、教科や科目の枠を越えた横断的・総合的な学びとなっている点です。また、総合的な探究の時間だけでなく、「古典探究」「地理探究」といった科目も始まっています。たとえば地理探究は、高校で必履修である地理総合の後に選択できる科目で、地理総合で得た知識をベースにより広く深く探究する授業になります。
探究学習のメリット
探究学習に取り組むと、思考力・判断力・表現力などの向上につながります。これらは他の教科を学ぶときにも欠かせない汎用的なスキルです。学習する上で必要な基礎的な能力が高まることで、国語や数学など教科の学力アップを期待できます。また探究学習に取り組む過程では、課題を設定する力や、課題解決に役立つ情報収集力、集めた情報を整理し課題解決に活用する力も養われます。探究学習で培ったスキルは、生徒の考えを問う出題の多いAO入試にも役立つでしょう。大学入試の結果を左右する可能性のあるスキルです。
探究学習のデメリット
デメリットとして挙げられるのは指導の手間や難しさです。探究学習に効果的に取り組むには生徒の主体性が欠かせませんが、教科の学習方法に慣れている生徒はどのように取り組めばよいか分からず積極的になれないケースもあります。また地域や企業との連携が推奨されていますが、時間や人的リソースが不足している中で実行するのは難しいと考えている学校が多いでしょう。指導計画を立てても関わる先が多ければイレギュラーが発生しやすく、想定より時間がかかることも考えられます。
探究学習での教員の役割
探究学習を実施するとき教員に求められている役割は、コーチング・ティーチング・メンタリングの3種類です。生徒の段階によって教員が果たすべき役割が異なる点も理解しておきましょう。コーチング
生徒が自分の探究するテーマを見つけられていないときに必要なのがコーチングです。コーチングで教員は生徒のテーマ作りをサポートします。このときのポイントは教えるのではなく引き出すことです。生徒が自発的に探究したいと感じることが重要なため、「どんなことについて探究してみたい?」といった問いかけで、生徒の中にある興味や関心を引き出していきます。
ティーチング
テーマについての探究を進めるとき、情報収集の仕方や集めた情報の取り扱い方を知らなければ、生徒は探究学習を正しく実施できません。探究学習を効果的に進めるために必要な技術やスキルを、教員から教わるティーチングの必要があります。例えば信頼できる情報を集めるための方法や、集めた情報の整理の仕方などを教員が伝えられれば、生徒はスムーズに探究学習を進めやすくなるでしょう。
メンタリング
メンタリングでは生徒が行っているテーマに関する学びに対し、「もっと他の方法は試した?」というように問いかけながら、より良い答えを目指します。ただし指導し過ぎると、教員の学習成果になってしまいかねません。生徒が自ら情報をまとめあげ、自分なりの答えを見出すためのサポートです。
探究学習の進め方

探究学習は、以下の4つのステップを踏んで進めていきます。
- 課題の設定
- 情報の収集
- 整理・分析
- まとめ・表現
まずは、生徒が自分で課題設定を行います。次に、課題の解決に、なにが役に立つのかを考慮しながら情報を収集します。
情報を集めるだけでは課題解決に繋がらないため、集めた情報を整理・分析します。最後に、探究学習の一年の流れをまとめて発表・表現します。
下記記事ではAI時代に"考える力"を育む方法を詳しく解説しています。
ソニー・グローバルエデュケーションが主催する「思考力チャレンジ」の例題も掲載しているので、ぜひお子さんと挑戦してみてください。
「思考力ってどう育つ? 生成AI時代の"考える力"を育む方法とは」〜Sony Global Educationの『思考力チャレンジ』と『LOGIQ LABOⓇ』から考える〜
探究学習における注意点
生徒が受け身の姿勢である場合、探究学習に抵抗を感じてしまうケースもあります。先生が授業を引っ張っても、生徒にとって「受験勉強に必要がない」「自分にはできることがない」と考えれば、探究学習が実を結ばないこともあるでしょう。そのためにも、探究学習をするうえで最も大切なのは課題設定です。生徒のモチベーションを上げるためにも、フィールドワークを早期に取り入れても良いでしょう。地域活動に実際に参加して目にすることで、課題が見つけやすくなることもあります。
また、探究学習をする際に、先生が正解を用意しておかないことも重要なポイントです。そもそも、探究学習における課題には、正解がありません。先生がアイディアを出すのではなく、生徒が意欲的に意見を出し合える環境を用意したいですね。
探究学習の代表事例
国内の高校では、すでに探究学習を取り入れている学校もあります。ユニークな取り組みをしている学校もあるので、参考にしてみましょう。兵庫県芦屋市 甲南高等学校
兵庫県芦屋市の甲南高等学校は2016年にスーパー・グローバル・ハイスクールに選ばれ、探究学習が取り入れられるようになりました。生徒達が選ぶテーマのなかには、下層通貨の成り立ちや企業誘致の失敗例などがあります。甲南高等学校では学校外でのフィールドワークを積極的に取り入れており、体験や地域の人達との交流を通して探究を深めています。
参考:日本教育新聞
東京都世田谷区 駒場学園高等学校
駒場学園高等学校では、同校の卒業生であるシェフが在校生にジビエ(野生鳥獣肉)調理実習を行った探究学習で注目を集めました。実際にジビエの肉をさばいてもらうことで、命や食の大切さを実感する生徒もいました。調理師や栄養士などの仕事を志す生徒に理解を深めてほしいとの卒業生の思いから、この探究学習は行われました。この取り組みは、信濃毎日新聞にも取り上げられています。
参考:駒場学園高等学校
宮城県仙台市 仙台白百合学園高等学校
仙台白百合学園高等学校では「家庭の意識の改善で食品ロスは減らせるか」をテーマに、2018年から2020年にかけて継続的な探究活動を行いました。この取り組みは消費者庁の事例集にも掲載されています。参考:消費者庁「生徒・学生の取組事例」
おすすめの探究学習教材
続けて、おすすめの探究学習教材をご紹介します。探求学習の土台となる思考力や集中力を育みたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。
下記記事では小中学生におすすめのプログラミング教材や人気ツールをご紹介しています。
【最新版】小学生・中学生におすすめ!子ども向けプログラミング教材・ツール徹底ガイド|Scratch・マイクラ・ロボット・AI教材まで一挙紹介
すらら

すららは、学年を横断して学習に取り組める無学年式を採用したeラーニング教材です。教材には映像・音声・アニメーション・クイズなどインタラクティブな要素が盛り込まれており、楽しみながら自分のペースで学びを深めることができます。
またすららでは、2023年4月より高校生向けの探究学習ICT教材「すらら Satellyzer(サテライザー)」をリリース。すららSatellyzerは、レクチャー・グループワーク・自己評価・相互評価で構成されたストーリー仕立てになっているため、本コンテンツを通じて基礎的な探究スキルを身に付けることができます。
天神

天神は、幼児・小学生・中学生向けの家庭学習用オンライン教材です。探究学習に向けた効果的な基礎力の習得を叶えられる、超スモールステップのコンテンツが特徴です。
2023年4月に大幅なバージョンアップを実施し、新機能『レクチャー』が搭載されました。やる気がない・勉強しない・集中力もないという悪循環を断ち切った学習環境作りを可能にし、多くのお子さまの学力向上・学ぶ意欲喚起に寄与しています。
おすすめの探究学習スクール
探究学習塾エイスクール
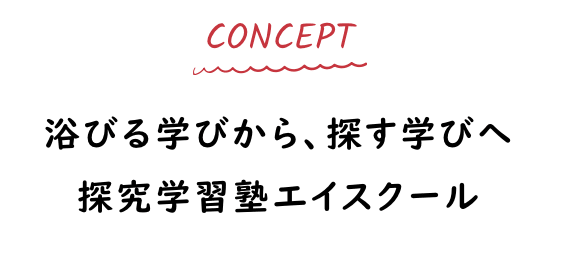
小学生から高校生までを対象とした探究学習専門の塾です。オンラインと教室の両方で授業を実施しており、生徒一人ひとりの興味関心に基づいた学びを提供しています。
探究学舎
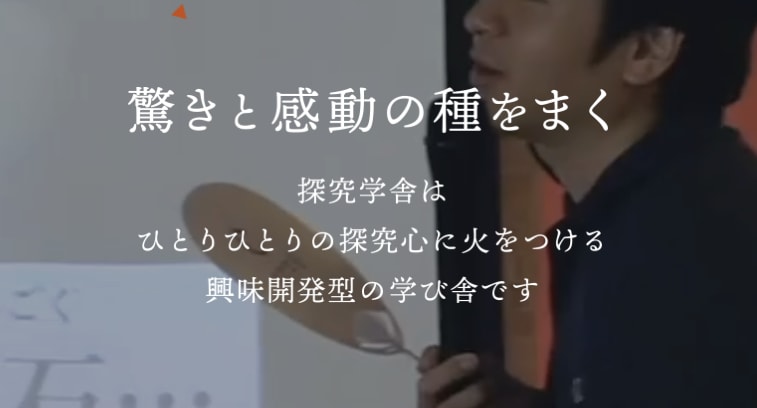
受験も勉強も教えない教室として、子どもたちの「もっと知りたい!」「やってみたい!」という興味の種をまき、探究心に火をつける興味開発型の学び舎です。算数・理科・社会など、いろいろな分野で、驚きと感動に満ちた授業を展開しています。
RAKUTO(ラクト)
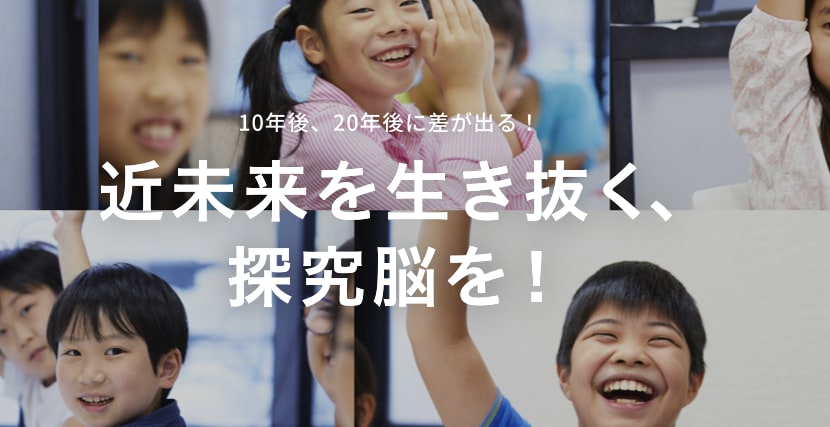
アクティブラーニング型学習塾で、脳科学と長年の経験に基づいた独自のメソッドで探究脳を育成します。記憶術や速読など、学習効率を高める技術も併せて指導しています。
ベネッセ チャレンジスクール オンライン探究学習

オンラインで受講できる探究学習プログラムです。自ら問いを探し答えを見つけようと試行錯誤を繰り返す学びを提供しており、全国どこからでも参加できるのが特徴です。
探究学習によって社会で活躍できる人間性を育む
探究学習では、教科書には載っていない問題について学べるチャンスだといえます。探究学習を通して、用意されている答えに対して疑問を持ち、自ら考えるきっかけにもなります。自ら考える力を育むことで、枠組みにとらわれない自由な発想力を身に付けられるようになるでしょう。

Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
総合的な学習って何をするの?“生きる力を育む教育”「え?通知表の評価観点も変わってた!?」
2022年度より高校では新たな科目として「総合的な探求の時間」が実施されています。中学では名称こそ変わりませんが、高校と同様の内容変更が行われました。ちなみに、小学校でも以前から総合的...
2025.10.29|大橋礼
-
必修科目「情報Ⅰ」に備えよう!共通テストや定期テスト対策も詳しく解説
2020年に小学校、2021年に中学校でプログラミング教育が全面的に実施されました。一方高等学校では既に2003年から「情報」が導入されましたが、2022年度には科目が再編され「情報Ⅰ...
2025.11.27|コエテコ byGMO 編集部
-
プログラミング通信制高校おすすめ一覧【2026年最新版】
通信制高校はこれまでの教育システムでは居場所を見つけられなかった方や、自分のペースで学びたいと考える方にとって、新たな選択肢となっています。そして今、多くの通信制高校がプログラミング教...
2026.01.02|大橋礼
-
ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説
教育現場で、新たな評価方法として注目を集めるルーブリック。アクティブ・ラーニングが授業に導入されるようになり、ルーブリックが採用される大学や高校も増加傾向にあります。この記事では、ルー...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
フレネ教育は子どもの自由な思想を育む教育メソッド!導入されている学校は?
フランスで誕生した教育メソッドであるフレネ教育は、子どもが自発的に学ぶ姿勢を育めることが特徴です。自由作文が教材となるため、文章力や探求心を伸ばせるメリットも。この記事では、フレネ教育...
2023.11.14|コエテコ byGMO 編集部