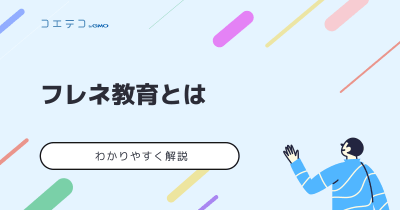反転授業とは?メリットとデメリットを徹底解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
近年、教育現場で注目を集めている「反転授業」。
従来の「授業で学び、家で宿題をする」というスタイルとは逆のアプローチで、生徒と教員の双方に多くのメリットをもたらす可能性を秘めています。
この記事では、反転授業の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、導入時の注意点まで、わかりやすく解説します。
反転授業の理解が深まり、新しい学びの形にスムーズに対応できるため、ぜひ参考にしてくださいね。
反転授業とは?従来の授業との違いを解説
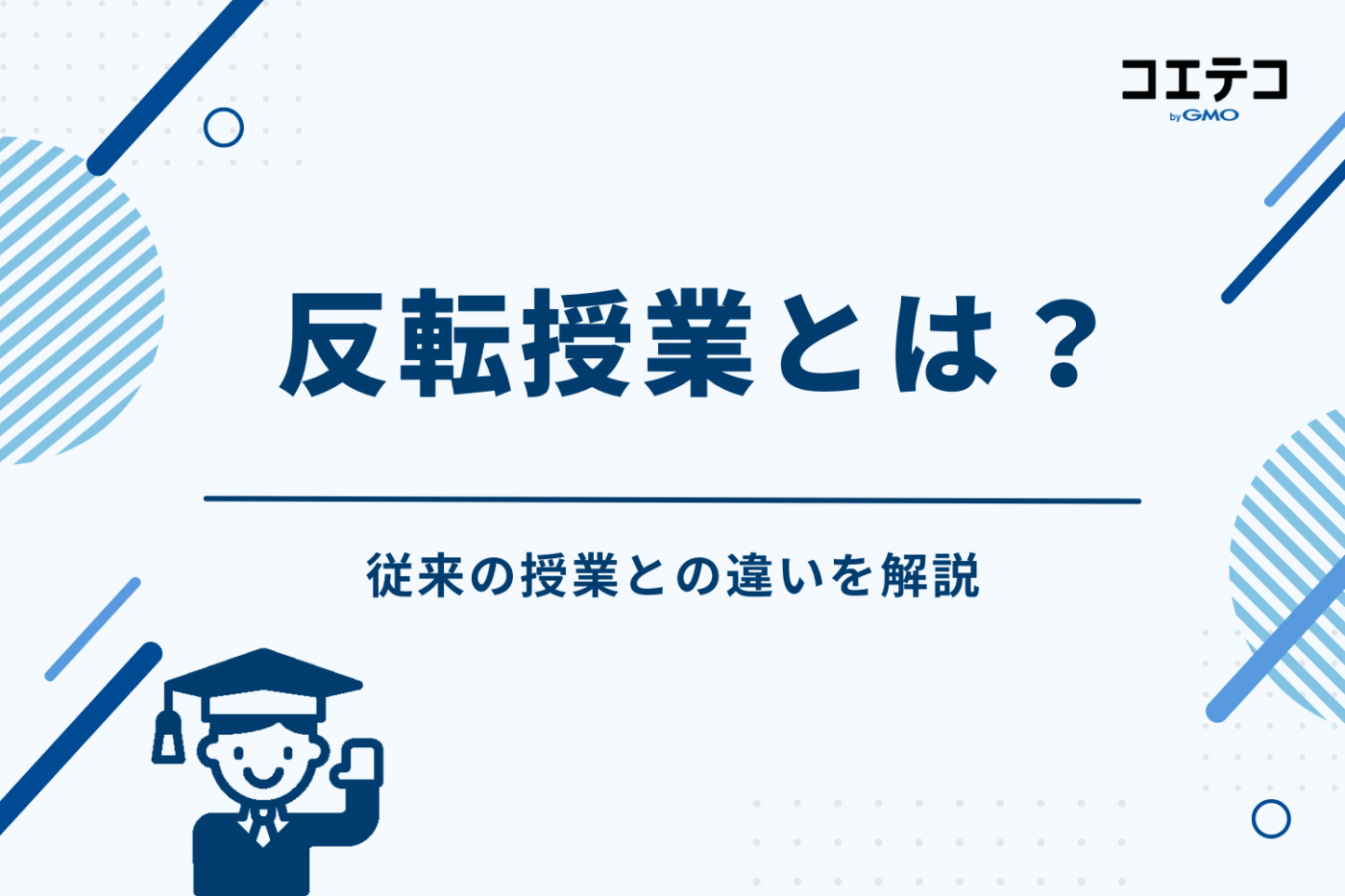
反転授業とは、自宅などで事前に動画教材などを使って予習(インプット)を行い、授業ではその知識を前提とした演習や議論(アウトプット)に取り組む学習スタイルを指します。
従来の授業が「授業でインプット→宿題でアウトプット」だったのに対し、反転授業は「自宅でインプット→授業でアウトプット」と、学習の順番を「反転」させているのが特徴です。
この学習スタイルは2007年頃にアメリカで始まり、日本では2013年頃から導入が進んでいます。
最近では、企業の新人研修など、学校教育以外の場でも効果が期待され、活用されるケースが増えています。
反転授業が注目される背景
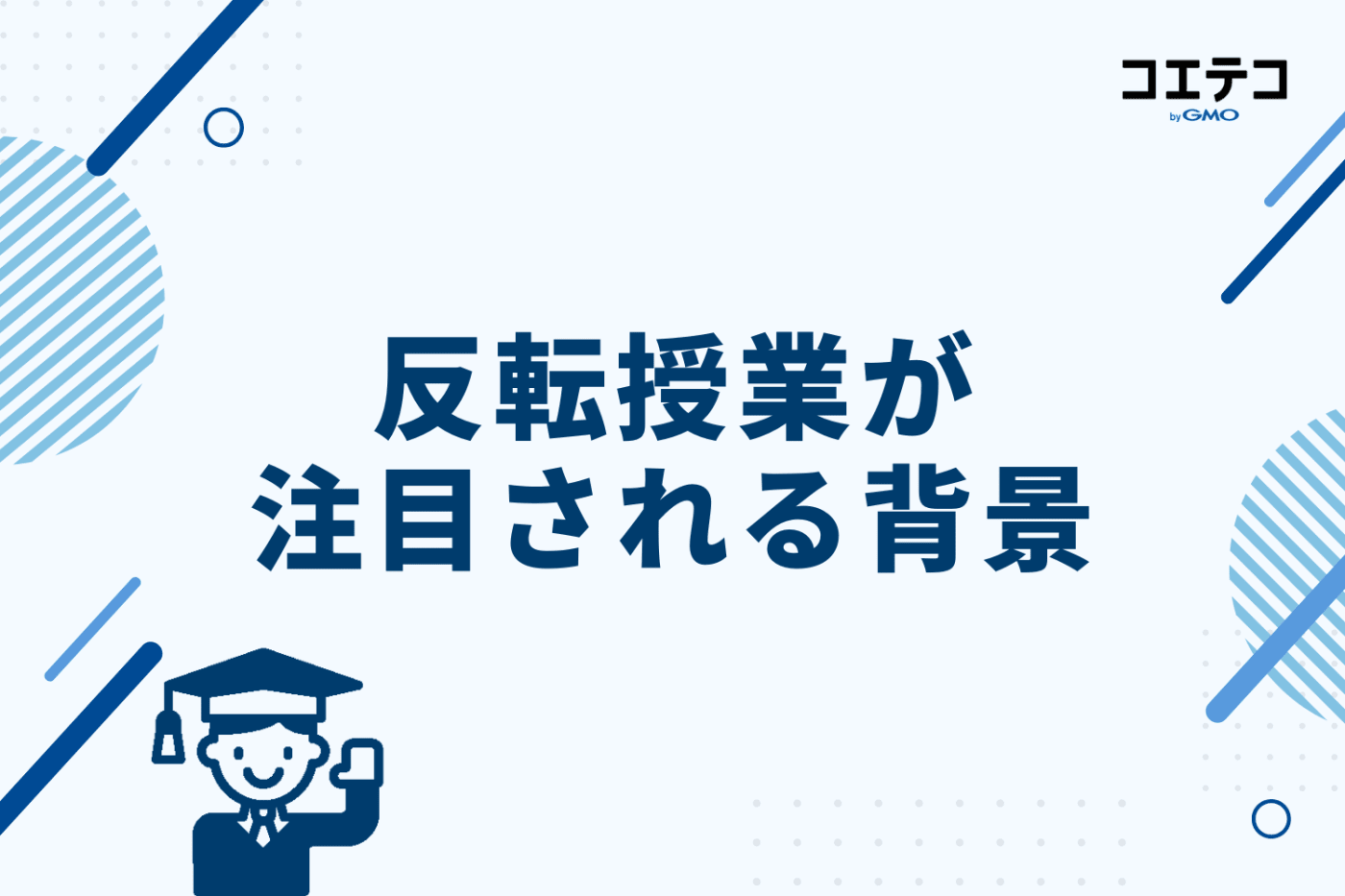
なぜ今、反転授業がこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。
その背景には、教育現場を取り巻く環境の大きな変化があります。
オンライン教育の普及とICT環境の整備
大きな理由の一つが、学校や各家庭にパソコンやタブレットが普及したことです。特に、文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」により、生徒1人に1台の学習者用端末が整備され、高速ネットワーク環境も整いつつあります。
1人1台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たち一人一人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現する。これまでの我が国の教育実践と最先端のICTのベストミックスを図り、教師・児童生徒の力を最大限に引き出す。引用:GIGAスクール構想による 1人1台端末環境の実現等について
生徒は自宅で動画教材を視聴したり、デジタル教材に取り組んだりできるようになりました。
教員側も、オンラインで予習用の動画を配信したり、AIやツールを使って生徒の学習状況を把握したりと、テクノロジーを活用して効率的に反転授業を実践できる環境が整いました。
国内外で学習効果が実証されている
たとえば、アメリカの研究では、反転授業によって生徒の学習意欲が向上し、従来の暗記中心の授業をより先進的な内容に進化できると期待されています。
また、日本の研究論文でも、反転授業は従来型の講義と比較して、予習の質を高め、知識の定着に貢献する可能性が示唆されています。
特に、生徒にとって身近な動画視聴を用いた予習は、有効な手段として認められています。
引用:J-STAGE『基礎科目に対する反転授業の効果』
反転授業の5つのメリット【生徒・教員別】
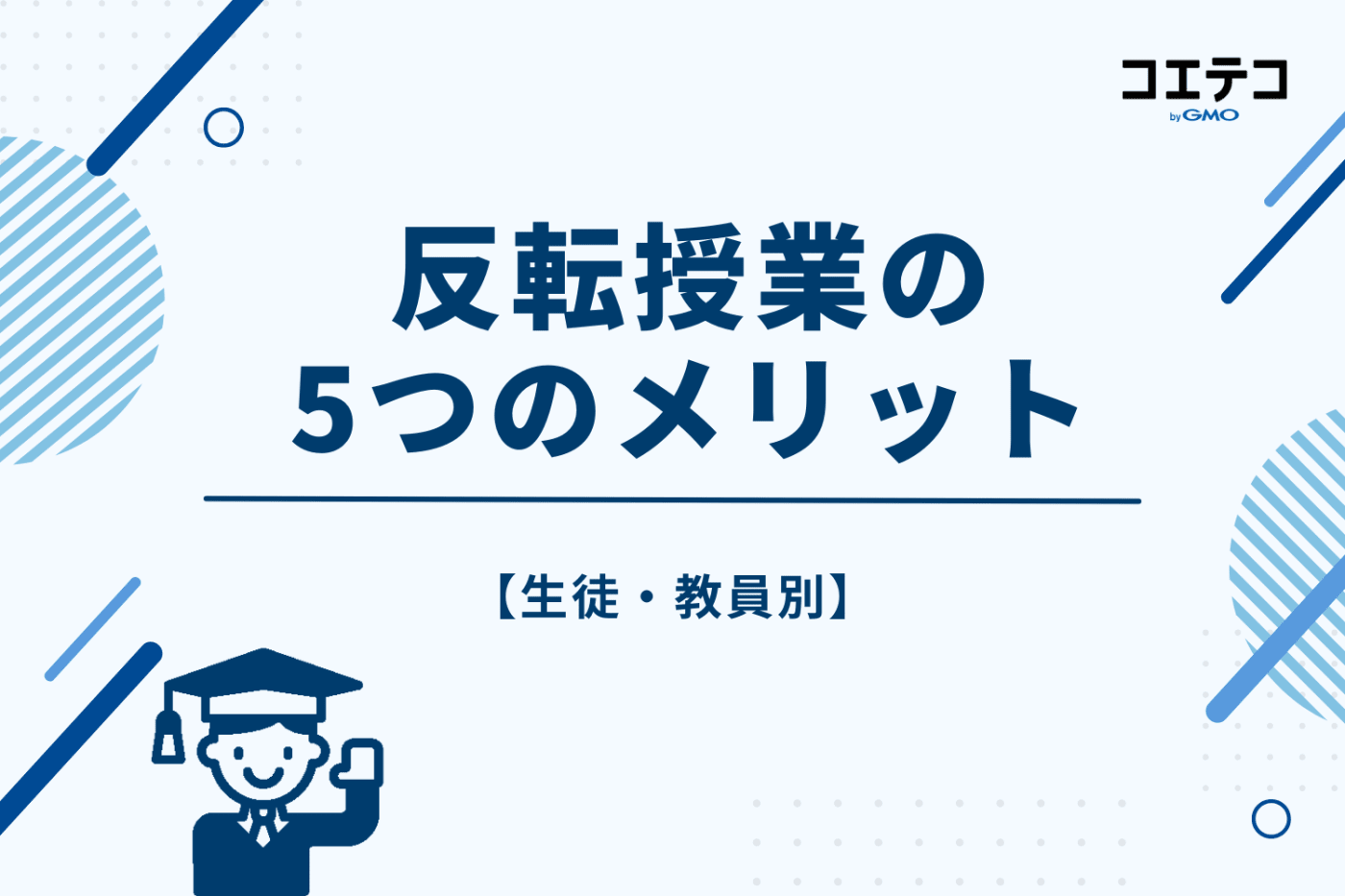
反転授業は、生徒と教員の両方にメリットをもたらします。
ここでは、主なメリットを5つ紹介します。
メリット1:学習効率が高まる(生徒)
反転授業では、予習にeラーニングや動画教材を用いるのが一般的です。何度でも繰り返し視聴できるため、自分のペースで、分からない部分の納得がいくまで学習できます。
事前に内容をしっかり理解して授業に臨めば、授業中の演習や議論にもスムーズに参加でき、学習効率が格段に向上するでしょう。
メリット2:問題解決能力が身につく(生徒)
反転授業は、生徒の問題解決能力を育成する効果も期待されています。予習の段階で「なぜこうなるんだろう?」と疑問を持ち、自分で調べたり考えたりするプロセスが、主体的に学ぶ姿勢を育みます。
さらに授業では、グループワークなどを通じて他の生徒と協力しながら課題に取り組むため、多様な視点に触れ、より深い解決策を見出す力が養われるでしょう。
メリット3:知識をアウトプットする力が伸びる(生徒)
従来の授業では、インプットが中心でアウトプットの機会は限られていました。反転授業では、授業時間が丸ごとアウトプットの場になります。
ディスカッションやプレゼンテーションなどを通じて、予習で得た知識を自分の言葉で表現する練習を重ねることで、「何を、誰に、どう伝えるか」というアウトプットのスキルが自然と磨かれていきます。
メリット4:生徒同士の協働学習が生まれる(生徒)
反転授業では、生徒が主体的に学習を進めるため、学習意欲が高まりやすいです。実際に、海外の大学で行われた調査では、反転授業の導入によって学業成績が向上したというデータも報告されています。
欧米で実証された学習効果引用:Education Career
the Atlantic「The Post-Lecture Classroom: How Will Students Fare?」によると、ノースカロライナ大学のRussell Mumper副学部長が基礎薬学の課程で反転授業を2012年と2013年に導入し、年度末試験において結果が向上しました。つまり、2年間で計5.1%向上しています。
- 2012年は前年度+2.5%
- 2013年は前年度+2.6%
意欲の高い生徒同士が授業で議論を交わすと、互いに教え合い、学びを深める「協働学習」の効果も生まれやすくなります。
メリット5:生徒の理解度を把握しやすい(教員)
教員にとっての大きなメリットは、生徒一人ひとりの学習状況や理解度を正確に把握しやすくなる点です。授業での発表や課題への取り組みを見れば、誰がどこでつまずいているのかが一目瞭然になります。
理解が不十分な生徒に対して、きめ細やかなフォローや個別指導を実施しやすいでしょう。
反転授業の4つのデメリットと対策
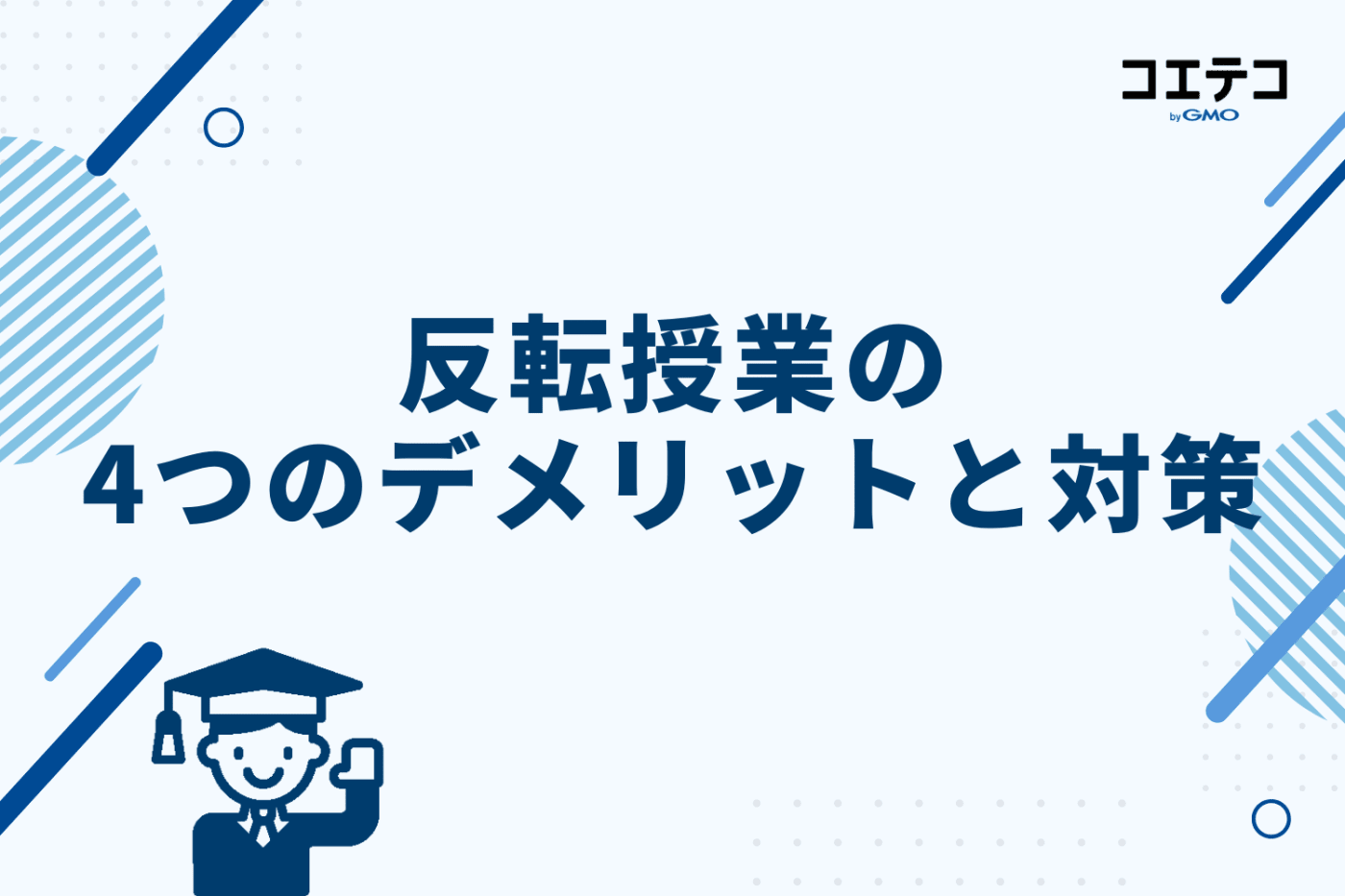
多くのメリットがある一方で、反転授業にはいくつかのデメリットや課題も存在します。
あらかじめ対策を理解し、備えておきましょう。
デメリット1:予習時間の確保が難しい場合がある
反転授業は、事前の予習が前提です。しかし、部活動や他の習い事で忙しい生徒や、家庭での学習習慣が身についていない生徒にとって、安定して予習時間を確保するのは簡単ではありません。
予習ができていないと、授業の内容がまったく理解できず、学習から取り残されてしまう懸念があります。
対策として、予習の範囲をコンパクトにしたり、予習期間を十分に設けたりするなど、生徒が無理なく取り組める工夫が必要です。
家庭での学習が難しい場合は、学習塾やオンライン家庭教師など、外部のサポートの活用も検討しましょう。
デメリット2:生徒の学習意欲に成果が左右される
反転授業がうまく機能するかは、生徒の学習意欲に大きく依存します。特に、自分で学習計画を立てて実行するのが難しい年齢の生徒や、学習意欲が低い生徒が多いクラスでは、導入しても期待した効果が得られない可能性があります。
また、保護者が予習をサポートする必要が出てくる場合もあり、家庭への負担が増えることも考えられるでしょう。
対策として、生徒の知的好奇心を刺激するような魅力的な教材を用意したり、予習の進捗をゲーム感覚で確認できる仕組みを取り入れたりするなど、学習意欲を引き出す工夫が求められます。
デメリット3:ICT機器による健康面への影響
予習で動画教材などを使用するため、パソコンやタブレットに触れる時間が増え、視力低下や肩こりなどの健康への影響が懸念されます。特に、長時間同じ姿勢で画面を見続けるのは避けましょう。
対策として、予習動画の時間を短くしたり、30分に一度は休憩して遠くを見たりするなど、ルールを決めることが大切です。
また、画面と目の距離を30cm以上離し、目線が下がりすぎないように端末の高さの調整も推奨されています。
デメリット4:教員側の負担が増加する
反転授業の導入期は、教員側の負担が大きくなる傾向があります。予習用の動画教材の作成はもちろん、授業での演習やグループワークの設計、生徒の学習状況の管理など、新たな業務が発生します。
また、一度作成した教材も、よりよい授業にするために、定期的な見直しや改善が必要です。
対策として、教材作成を効率化するツールや、生徒の学習管理システムなどの積極的な活用が重要です。
また、すべての教材を自作するのではなく、質の高い外部サービスや教材をうまく組み合わせれば、負担軽減につながります。
反転授業と混同しやすい学習方法との違い
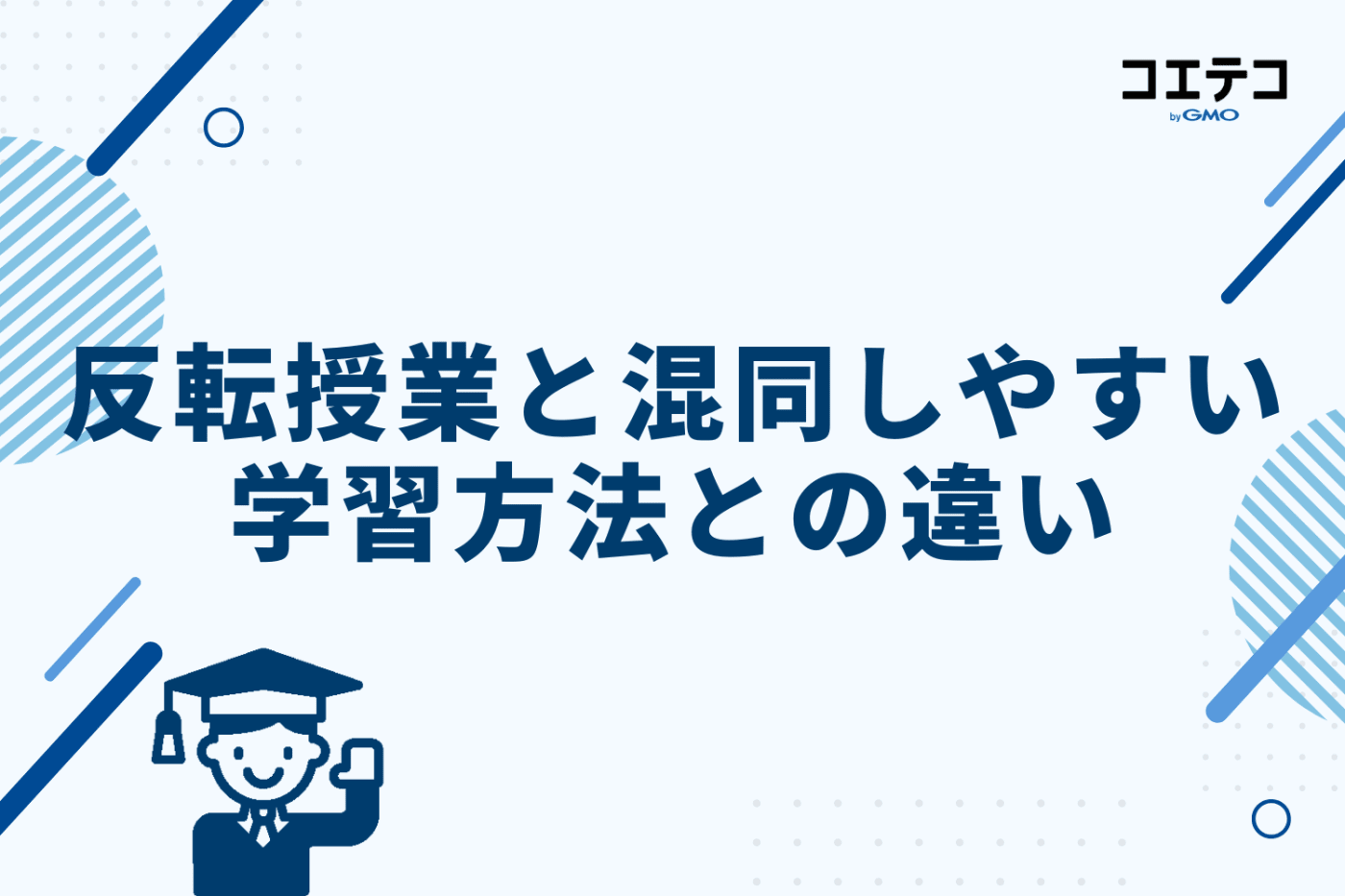
反転授業としばしば混同される学習方法に「アクティブラーニング」と「MOOC」があります。
それぞれの違いを理解しておきましょう。
反転授業に関するよくある質問
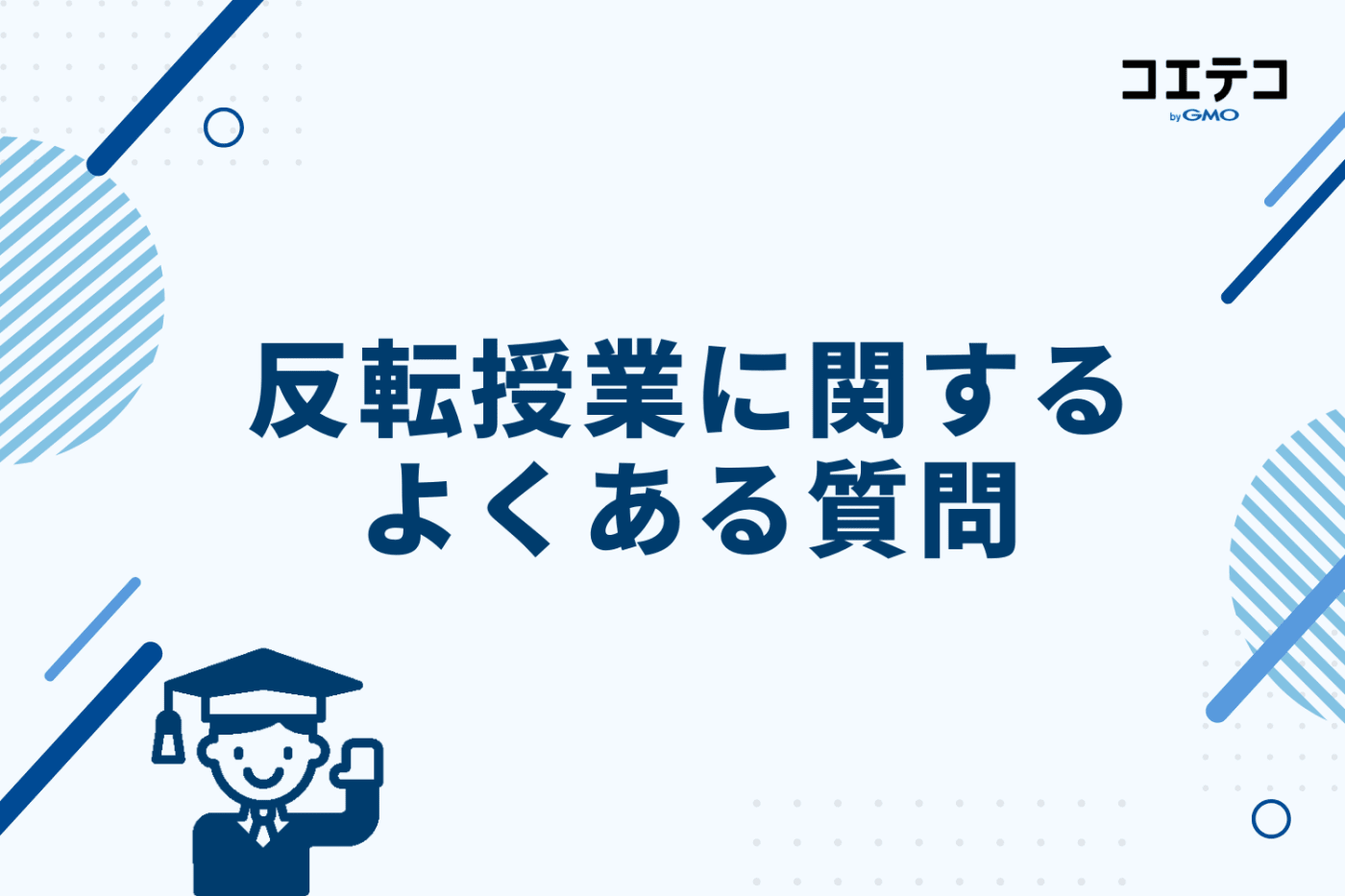
ここでは、反転授業に関するよくある質問にお答えします。
大学の反転授業はどのようなものですか?
大学の専門的な学びでは、反転授業は非常に有効です。従来は講義で基礎知識を学び、応用問題は各自で取り組むのが一般的でした。
反転授業では、自宅で講義映像などを用いて基礎を固め、授業では教員や他の学生と対話しながら、より難易度の高い応用課題に取り組みます。
この方法を導入した多くの大学で、学生の学習意欲や成績の向上、さらには落第率の低下などの成果が報告されています。
まとめ:反転授業を見すえた学習スタイルを確立しよう
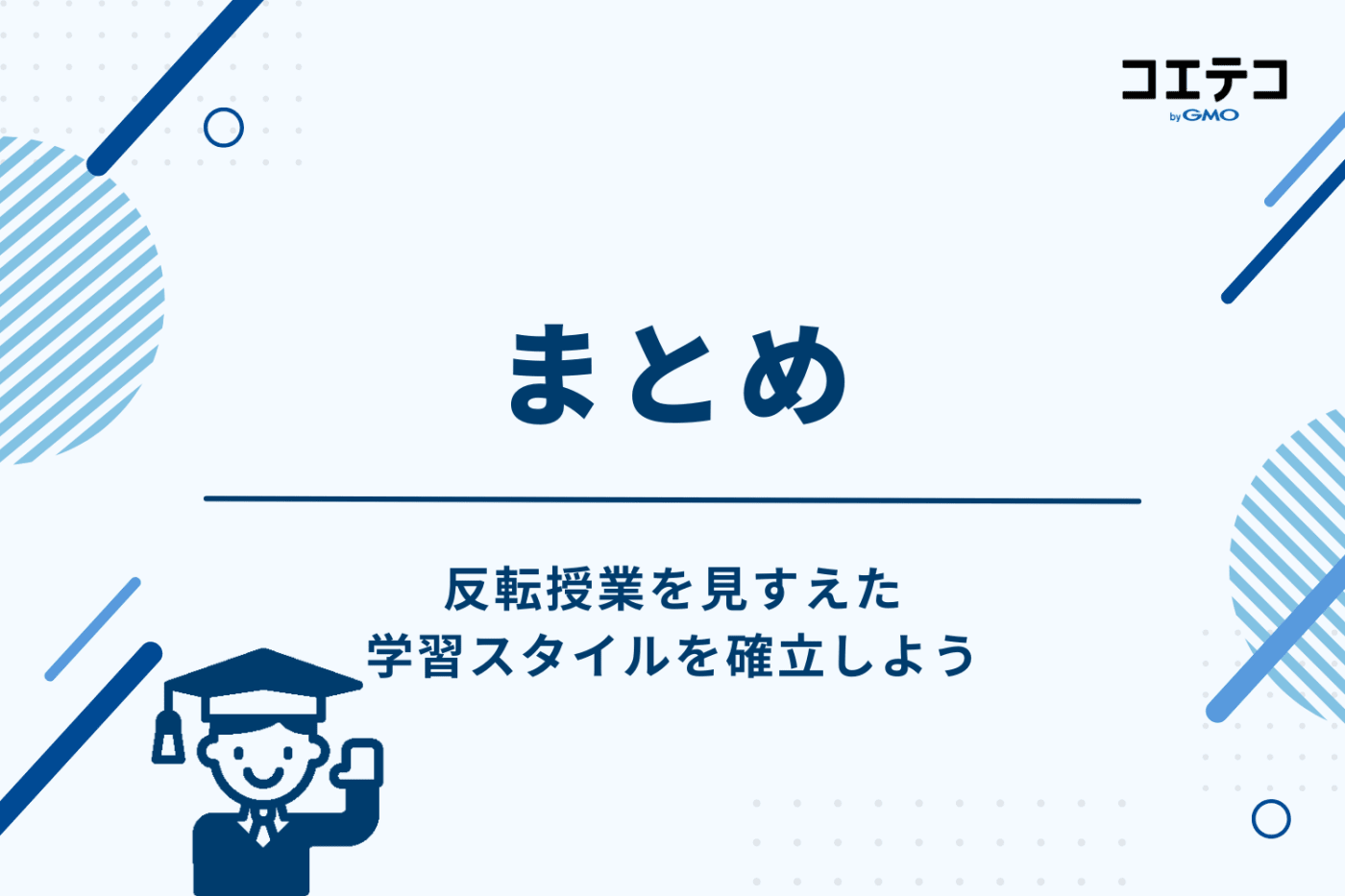
この記事では、新しい学びの形の反転授業について、その仕組みやメリット・デメリットを解説しました。
今後、反転授業はさらに多くの教育現場で導入が進むと予想されます。
この変化に対応するためには、日頃から予習を習慣づけ、主体的に学ぶ姿勢を身につけておくのが大切です。
もし、「一人で予習を進めるのが不安」「もっと効率的に学習したい」と感じるなら、学習塾やオンライン教材の学習相談や無料体験授業を受けてみるのも一つの手です。
まずは気軽に試してみて、自分に合った学習スタイルを見つけることから始めてみてくださいね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説
教育現場で、新たな評価方法として注目を集めるルーブリック。アクティブ・ラーニングが授業に導入されるようになり、ルーブリックが採用される大学や高校も増加傾向にあります。この記事では、ルー...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン授業を受けるのにおすすめの場所5選|集中力が高まる場所の選び方を紹介
オンライン授業を受ける際に、家の中では集中力が持続しづらいという人もいるでしょう。その場合には、家以外の場所でオンライン授業を受ける方法もあります。この記事では、オンライン授業を受ける...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
ICT化で学校教育現場はどう変わる?メリット・効果・海外の事例まとめ
2020年、ついにプログラミング教育が小学校で必修化します。それに伴い、学校教育現場のICT環境整備も進められています。海外と比較して遅れていた日本のICT環境。整備が進むとどのような...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
シュタイナー教育とは?メリット・デメリットもわかりやすく解説
「シュタイナー教育って日本の学校教育と何が違うの?」と疑問を感じる方も多いでしょう。この記事では、シュタイナー教育の基本理念から具体的な学習内容、モンテッソーリ教育との違い、メリット・...
2025.08.06|コエテコ byGMO 編集部
-
フレネ教育は子どもの自由な思想を育む教育メソッド!導入されている学校は?
フランスで誕生した教育メソッドであるフレネ教育は、子どもが自発的に学ぶ姿勢を育めることが特徴です。自由作文が教材となるため、文章力や探求心を伸ばせるメリットも。この記事では、フレネ教育...
2023.11.14|コエテコ byGMO 編集部