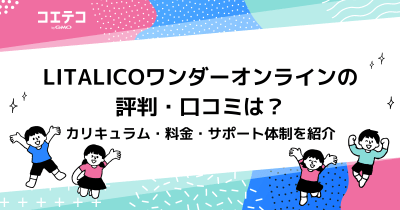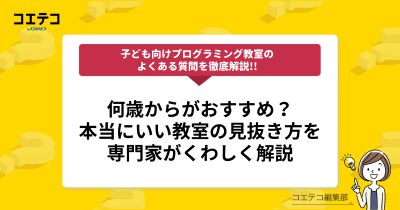「みんなでプログラミング」ってどんなプログラミング教材?特徴や構成を詳しく紹介
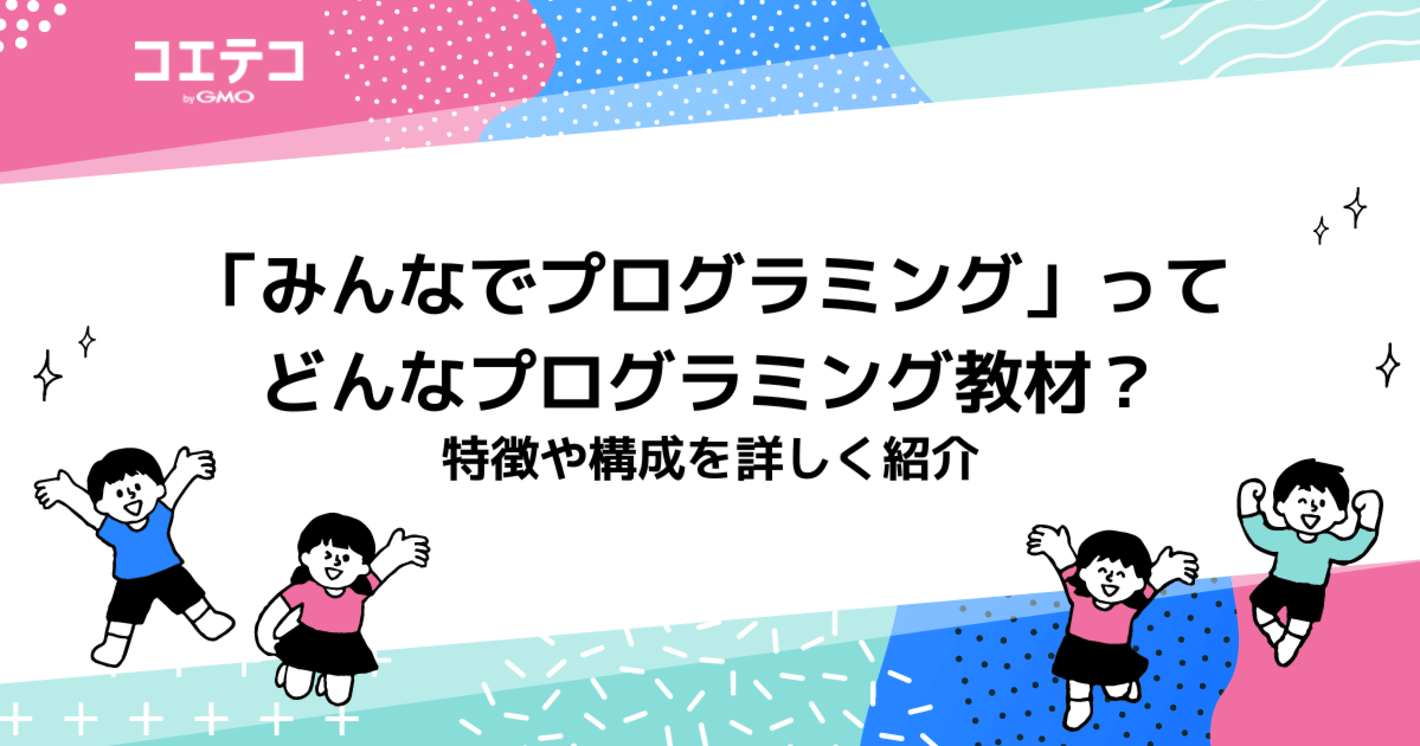
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
「みんなでプログラミング」の魅力は、家庭向けの個人用もリリースされていること。有償ではありますが、家庭でも学校と同等の質の高い学びを得ることが可能です。
この記事では、「みんなでプログラミング」の特徴や構成について詳しくご紹介します。
「みんなでプログラミング」とは?

プログラミング学習の必修化を受け、子どもが楽しくプログラミングを学べる教材が数多くリリースされています。
「みんなでプログラミング」も、そんな学習コンテンツの1つです。概要や特徴について、詳しく見ていきましょう。
学校現場でも使われるプログラミング教材
「みんなでプログラミング」は、電子機器メーカー「レノボ」と教科書販売の大手「東京書籍」によって開発された子ども向けのプログラミング教材です。ブラウザ型でダウンロードが不要なため、OSやデバイスを問わず利用できます。「みんなでプログラミング」はもともと、NTTコミュニケーションズが提供するクラウドプラットフォーム「まなびポケット」に含まれる無償コンテンツの1つとして提供されていました。利用者から「より充実したコンテンツを提供してほしい」との声が上がり、有償版がリリースされることとなったのです。
家庭で利用できる個人向けパッケージもリリース
有償版のリリースに伴い、中学生・高校生向けのコンテンツが追加されました。学校用だけではなく個人用もリリースされ、家庭でも学校と同じ教材を使ってプログラミングを学べます。個人向けパッケージでは、自由に問題を作れる「オリジナル問題作成機能」、オンラインワークショップイベントに参加できる「オンラインクラス機能」、分からない問題を質問できる「添削機能」などを利用することが可能です。
小中高のプログラミング学習を網羅
有償版「みんなでプログラミング」は、小中高のプログラミング教材を1パッケージで提供しています。ビジュアルプログラミング(小中コース)からより本格的な「Python」(高校コース)までを1つのプラットフォームでに学べるのは、大きな魅力といえるでしょう。
文部科学省の新学習指導要領に対応
「みんなでプログラミング」は、文部科学省の新学習指導要領に対応しています。小学校ではビジュアルプログラミングや創造性・自主性を伸ばすコンテンツが提供されているほか、情報モラルに関する学びを得ることも可能です。中学生向けになると、上記に加え「技術分野」やより実践性の高いコンテンツがプラスされます。さらに高校生向けでは「情報Ⅰ」に準拠したデータサイエンスやコンピューターの仕組みが追加され、コンテンツの充実度はかなりのものです。
低コストで効率的な学習が可能
個人向けの有償版「みんなでプログラミング」は、月額396円(税込)で利用できます。コスト面の負担が少ないのは、大きな魅力といえるでしょう。「情報」が大学入試科目に組み込まれるとはいえ、「プログラミングをどのように学ばせたらよいのか分からない」というご家庭は少なくありません。
学校現場でも使われている「みんなでプログラミング」なら、質の高さは折り紙付き。コストをかけず、家庭でも効率的にプログラミングを学べます。
「みんなでプログラミング」を構成するコンテンツ
「みんなでプログラミング」は学校での使用を想定した「教員用」と、家庭での個人利用が可能な「個人用」があります。教員用は先生の授業準備の負担を軽減する機能が実装されていますが、コンテンツの内容に大きな違いはありません。ここからは、小中学校用「みんなでプログラミング」の構成について紹介します。
ブロックプログラミング
「みんなでプログラミング」では、ブロックプログラミングのコンテンツが搭載されています。ブロックプログラミングとは、ブロックを組み合わせてコンピューターに命令を出すビジュアルプログラミングです。タイピングスキルがない子どもでもつまづきが少なく、遊び感覚でプログラミングのカンを養えます。
中学生向けの「技術・家庭」コンテンツでは、ブロックプログラミングでチャットボットの制作にチャレンジ。これにより子どもたちは、新学習指導要領に掲載されている「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題解決」についての学びを得られます。
タイピング
テキストプログラミングでは、タイピングスキルが必須です。小学生コースでは、タイピングスキルを鍛えるコンテンツが配信されています。タイピングコンテンツでは「ホームポジション」から学ぶため、タイピングスキルゼロの子どもも心配はいりません。問題の難易度はさまざまあり、スキルに合わせて文字タイピング、単語タイピング、短文タイピングにチャレンジできます。
情報モラル動画コンテンツ
情報モラル動画とは、子どもたちが適切な情報活用力を身に付ける上で必要な知識や情報をまとめた動画コンテンツです。動画を視聴してデジタル社会ならではのリスクとメリット・心構えを学ぶことで、子どもたちは社会で生きていく上で必要なデジタルリテラシーを身に付けることができます。
プログラミングをより深く学ぶなら。おすすめのオンラインプログラミングスクール
「みんなでプログラミング」に挑戦するうちに、「もっとプログラミングを学びたい」と感じる子どもも出てくるかもしれません。子どもがプログラミングに興味を持ったら、より本格的な学びを得られるオンラインプログラミングスクールがおすすめです。
ここからは、子どもの興味を引き出せる、人気の高いオンラインプログラミングスクールをご紹介します。
デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン)

サブスクリプションサービス型のオンラインプログラミングスクールです。マインクラフトやScratchといったさまざまな動画コンテンツから、子どものレベルや興味にマッチしたカリキュラムを選択できます。コンテンツは100以上あり、月額料金だけで受け放題です。
全てのコースには分かりやすいレクチャー動画が付いており、初めての子どもでも操作に迷う心配はありません。作った作品をほかの受講者と共有できるコミュニティ機能・リアルタイムでフィードバックを受けられるLive配信などもあり、オンラインでも充実した学びを得ることが可能です。
| コース名 | Scratchコース |
| 対象学年 | 小学校3年生から中学生 |
| 入会金 | 無料 |
| 授業料 | 4,980円/月(月々プラン)・3,980円/月(年間プラン) |
| 授業形態 | 動画教材による自己学習 |
| 無料体験 | 14日間 |
テラコヤエッジ

現役プログラマーの講師から、きめ細かなフォローを受けられるオンラインプログラミングスクールです。講座では子どものレベルに合った小中学生専用教材が使用され、プログラミングスキルを効率的に底上げできます。
選択できるコースは「スクラッチゲームプログラミングコース」「Unityゲームプログラミングコース」「HTML,CSS,Javascript WEBアプリ開発コース」の3つです。プログラミングを学び始めたばかりの子どもは、「スクラッチゲームプログラミングコース」で基礎を固めるのがおすすめです。
レッスンは少人数制で行われるため、講師の目が子ども1人ひとりにきちんと行き渡ります。ほとんどの子どもが初心者なので、「うちの子にできるかな?」という心配は不要です。
| コース名 | スクラッチゲームプログラミングコース |
| 対象学年 | 小学校1年生から中学校3年生 |
| 入会金 | 4,980円 |
| 授業料 | 3,980円~ |
| 授業時間 | 50分 |
| 無料体験 | 水曜日・土曜日・日曜日(週により変動) |
まとめ
「みんなでプログラミング」は、レノボと東京書籍が共同開発した子ども向けのプログラミング教材です。新学習指導要領に準拠しており、小中学校のプログラミング授業で活用されています。「家庭でもプログラミングに触れさせたい」と考えるご家庭は、有償版を利用すると学校と同じ環境でプログラミングを学べるでしょう。
また「みんなでプログラミング」でプログラミングに興味を持ち始めた子どもは、よりレベルの高い学びにチャレンジするのもおすすめです。オンラインプログラミングスクールなら、本格的なプログラミングを家庭で楽しく学べます。
「みんなでプログラミング」やオンラインプログラミングスクールを活用し、子どものプログラミング学習をサポートしましょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
LITALICOワンダーオンラインの評判・口コミは?カリキュラム・料金・サポート体制を紹介
ロボット作りやアプリなどに興味があるお子様から人気があるプログラミングスクールは、LITALICOワンダーオンラインです。豊富なコンテンツが用意されており、お子様が飽きることなく学習を...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
デジタネ(旧 D-SCHOOLオンライン)の評判・口コミは?カリキュラム・料金・サポート体制を紹介
デジタネは、小・中学生に向けたプログラミング講座を提供しています。マインクラフトやディズニーなど、親しみやすいコンテンツが充実しているから、小学校低学年から利用できます。この記事では、...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
Z会プログラミングシリーズとは?講座の内容やメリットを紹介
Z会プログラミングシリーズは、通信教育の大手・Z会が提供するプログラミング学習サービスです。学習対象は年長から中学生で、子どものレベルに合わせて3種類の講座が用意されています。この記事...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
Playgram(プレイグラム)は小学生のプログラミング学習におすすめ。特徴や機能を詳しく紹介
Playgram(プレイグラム)とは、Preferred Networks(PFN)が開発・運営するプログラミング学習サービスです。プログラミング学習教材としての評価は高く、2021年...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
【第4回】「本当によい教室の見抜き方は?」「何歳からがおすすめ?」事業責任者の沼田直之氏に聞く!
保護者が子どもに習わせたい習いごとで、書道や体操にならんで4位にランクインしているプログラミング。一方で、「よくわからない……」と一歩引いて見ているご家庭も多いかもしれません。コエテコ...
2025.09.10|原 由希奈