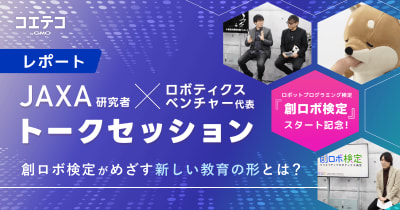科学実験教室から生まれたプログラミング教室『プロ・テック倶楽部』

プログラミング教育への関心が高まる中、他とは違った環境で2016年からプログラミングスクールをスタートさせた『プロ・テック倶楽部』 この教室は、子どもたちに科学の楽しさを伝えたいと、1992年から始まった『サイエンス倶楽部』が新たに展開したもので、科学実験とプログラミングの相性の良さから誕生したそうです。しかし、その相性とは具体的には一体どういうものなのでしょうか? そんな「ナゼ?」を探りに、『プロ・テック倶楽部』の本部を訪ね、様々な質問を投げかけてみました。
 プロ・テック倶楽部の授業風景
プロ・テック倶楽部の授業風景 広永雅史さんは、大卒後、大手学習塾を経て、現在の『サイエンス倶楽部』の運営に携わり、2016年度から『プロ・テック倶楽部』の展開にも尽力している
広永雅史さんは、大卒後、大手学習塾を経て、現在の『サイエンス倶楽部』の運営に携わり、2016年度から『プロ・テック倶楽部』の展開にも尽力しているモノの仕組みに疑問を持たない子どもたちへの危機感
「『サイエンス倶楽部』は、『自然科学教育を通じて、未来を担う子どもたちの創造性、社会性を育み、社会的価値を最大限に発揮出来る人材を輩出』することを理念に掲げた子どものための学習教室です。
子どもたちが日常生活で見つけた『なぜだろう?』どうしてだろう?』を、実験したり、調べたりすることで、自然に学習への理解や興味を深めていくことが狙いです」と、この『サイエンス倶楽部』の立ち上げに携わり、また新しくできた『プロ・テック倶楽部』の事業展開にも関わっている、専務の広永雅史さんは言います。
25年以上子どもたちを見つめてきた広永さんですが、数年前から気になっていた変化がありました。
それは、日常生活の中で「ナゼ?」と思わない子どもたちが増えてきていること。「ナゼ?」は子どもの持って生まれた、知りたいという欲求で、学習の本質的な部分です。自然科学の実験教室である『サイエンス倶楽部』には疑問を解決することに興味のある子どもたちが多いはずなのに、その疑問を持つ子どもが少なくなっている現象は無視できないと思い始めたそうです。
「便利さ」が当たり前の現代、子どもの「ナゼ?」をどう育てる?
「例えば、『エアコンってすごいね』って子どもに言うと、『だって最初からそうなっているでしょ?』という感じで、『どうしてそんなことを聞くんだろう?』という顔をするんですよ。
エアコンの中で起こっていることに、疑問を持たないんです。もちろん、すべての子どもというわけではありませんが、ここは『サイエンス倶楽部』で仮にも理科や実験に興味のある子どもが通っているわけです。
そんな子どもが疑問を持たないということは、いろんな意味でまずいと思いました。『ナゼ?』がなければ、行う実験もすべて結果を見るだけの受け身になってしまい、その先にある想像力や理解力も育まれません。これでは『サイエンス倶楽部』の理念に反します。
そして、その原因を突き詰めると、世の中のIT化など、環境の変化が大きく関係しているのではないか?
不便さを知る大人は便利になったと感じることが出来ても、子どもたちにとっては、快適な暮らしは当たり前の世界になっている。だから無関心なのでは?という考えに至りました」と広永さん。子どもの無関心は、『サイエンス倶楽部』の問題というよりも、世の中全体の変化からもたらされており、デジタル社会で生きる子どもたちが、自らの力で新しい発見が出来るようなプログラミング教育が必要だと確信したそうです。
物理や数学的要素が盛りだくさんの『プロ・テック倶楽部』誕生!
『サイエンス倶楽部』で行っている実験の中には回路やセンサーなど簡単なプログラミングを必要とし、そのプロセスを検証するようなものもすでに存在していました。「プログラミング教育のノウハウや環境はすでに整っているではないか」と、広永さんはこれまでのやり方にITとの接点を持たせた新しいプログラミング教室が子どもたちの未来への教育につながると感じたそうです。
『サイエンス倶楽部』の科学実験教室が行ってきた『観察をし、問題を見つけ、テストをして、失敗したら新しいやり方を考える』といったトライ&エラーを通じて問題を見出すトレーニングは、モノつくりの基本。そこに、プログラミングの知識が加われば、もっと新しい教育価値が生まれる可能性は十分にあります。
プログラミング『を』学ぶのではなく、プログラミング『で』学ぶというキャッチコピーは、そういった教育現場の目指すべき方向性を表したものといえるでしょう。
 サイエンス倶楽部が展開するプログラミング教室「プロ・テック倶楽部」
サイエンス倶楽部が展開するプログラミング教室「プロ・テック倶楽部」『サイエンス倶楽部』と『プロ・テック倶楽部』のセット受講が人気
広報担当の鈴木里美さんは「『プロ・テック倶楽部』をスタートして約1年ですが、すでに生徒は小・中学生合わせて約500人と定員を十分に満たしています。現在
『サイエンス倶楽部』は中野本校だけで600人ほどの生徒がいますが、8割くらいが『プロ・テック倶楽部』とセットで通っているお子さんです。興味の対象が増えたことで、子ども同士のコミュニケーションも活発になっているようですね」と、『プログラミング×ものづくり』を掲げた『プロ・テック倶楽部』の誕生以降、子どもたちの視野の広がりが実感出来るそうです。
『プロ・テック倶楽部』のコースは、2016年に始まった初級と中級、2017年10月からは上級にあたる『アドバンストコース』、11月からは幼児向けの『はじめてのプログラミング講座』が加わっています。
年齢別のクラス編成ではなく、学習に必要なことが出来る出来ないを見極めた能力別での『プログラミング×ものづくり』は、子どもたちに刺激を与えているとのことでした。子どもたちの能力ややる気に合わせ、C言語までしっかり学ばせたい、というアクティブラーニングへの取り組みは期待できそうです。
『プロ・テック倶楽部』は、『サイエンス倶楽部』と基本は同じ
「私たちの目指すプログラミング教室の教育方針は、科学実験教室と同じ考え方です。子どもたちの『ナゼ?』を大切にするために、ロボットにしてもゲームにしても、その動作制御を理論的に学ぶこと、すなわちプロセスを重視したいと考えました。
そこで、『プログラミング×ものづくり』と明文化したのです。そこには、物理や数学的要素がたっぷりと盛り込まれていますから、子どもたちの学習能力を高めることにも影響するはずです」と広永さんは自信を持って『プロ・テック倶楽部』の実践が子どもたちの将来に役立つといいます。
このように『機械に操られるのではなく、機械を操る側に立つ』を目指した方針は、新しいことにチャレンジすることが出来る子どもの姿として、保護者側からも支持されているそうです。
『プログラミング×ものづくり』を教える先生はどんな人?
しかし実際にこのような授業を行うには、教える側のスキルが問われます。また、プログラミングは2020年から小学校での必修科目化が決定し、どこのプログラミングスクールでも教える先生が不足していると聞きます。
この先生問題をどうするのか、広永さんにザクっと切り込んでみました。すると「そこが、この教室のもう一つの強みなんです」と、力強い声。その自信は、『サイエンス倶楽部』の四半世紀に渡る長い歴史から導かれたものでした。『サイエンス倶楽部』の卒業生が講師として、またはアルバイとして戻ってきてくれるというのです。教室の質と信頼性を強く感じられるコメントでした。
 「常に五感を働かせ、物事をとらえる力とそれを効果的に伝えていく力を養うには、
「常に五感を働かせ、物事をとらえる力とそれを効果的に伝えていく力を養うには、『有名大学合格率何%』なんて看板がなくても、子どもが集まる学習塾
「『サイエンス倶楽部』は一般的には学習塾の種類に入るのですが、子どもの成績アップを狙う教科指導を行う所ではありません。ですから、有名中学入学何人、高校入学何人というような看板が宣伝として出せません。
ただ、ここに通う子どもたちの、その後の進路を見ていると、結構すごかったりするんです。もう25年やってますから、初期の頃に通っていた小学生が、今は30歳を超えています。IT関係の仕事をしていたり、大学で研究をしているなど、この分野で働いているOB・OGは珍しくないのです。そういうわけで、ありがたいことに人材には恵まれていて、『プロ・テック倶楽部』で教える内容やコース設定を一緒に考えてもらったりしています。
『サイエンス倶楽部』に通っていた子どもは、プログラミングのリテラシーにつながる論理的に考えることの意味を理解していますし、何よりもここの雰囲気をよく知っている。自分の後輩の面倒を見るような気持ちで接してくれますから、子どもを預ける保護者の信頼も厚く、こちらも安心して任せられます。『サイエンス倶楽部』もそうですが、アルバイトの声掛けをすると150人くらい応募があって、逆にこっちが驚いたりするんですよね」と広永さん。この教室の特長として、「先生は元生徒」という点が挙げられるでしょう。
 広報の鈴木さん(左)は、「作りながらモノの原理を理解するのが『サイエンス倶楽部』でアイデアを形にするのが『プロ・テック倶楽部』」と取材した子どもに即答されたそうです
広報の鈴木さん(左)は、「作りながらモノの原理を理解するのが『サイエンス倶楽部』でアイデアを形にするのが『プロ・テック倶楽部』」と取材した子どもに即答されたそうです幼児から中学生までのステップアッププログラムを見てみよう!
現在用意されているコースは4つ。基本的には年齢別ではなく能力別にステージが用意されていますが、文字が読めるか? キーボードで英字が打てるか? といった一般的な発達状態を目安にした年齢がホームページなどの案内に表記されています。
幼児のための『はじめてのプログラミング講座』は2017年11月から募集を始めたばかりだそうですが、保護者の口コミですでに250人の定員に達するなど、プログラミング教育への関心の高さが伺えます。
「こんな小さな子どもが、プログラミングを理解出来るのか?」とよく聞かれるそうですが、小さなロボットがセンサーを利用して線の上を走るライントレースの授業では、横にいる友だちとアイデアを出し合いながら自然にプログラミングを覚えていったそうです。大人の目線で判断するのではなく、まず子どもに体験する機会を与えることが大切なのかもしれませんね。
<コースの内容>
『プロ・テック倶楽部』は主に幼児、小学生、中学生を対象に一都三県と兵庫県で17教室を展開中。今後は高校生に向けた本格的なプログラミングコースの開設や、フランチャイズ化などによって、もっとたくさんの子どもが参加出来るような教室の組織作りにも取り組んでいきたいそうです。
 プロ・テック倶楽部 授業の様子
プロ・テック倶楽部 授業の様子編集部コメント
保護者の立場からすれば、学習塾に求めるのはやはりテストの点数UPという目に見える結果だと思います。しかし『サイエンス倶楽部』では、子どもの進路や合格実績ではなく、子どもに本質的な「ナゼ?」から学ぶことの楽しさを伝えてきました。その結果、基本的な学習能力がしっかりと備わった大人になって塾に顔を出してる。そこからプログラミング教室が誕生しているのですから、説得力があります。ここに通う子どもの父親には、IT系やモノづくりに携わる理系の方が多いとのこと。現場の最前線で働く父親が「プロジェクトをまとめる力やプロセスを組み立てる力を子どもの頃から養うことも大事。科学実験とプログラミングの組み合わせは悪くないのではないか」と『プロ・テック倶楽部』を高く評価しているそうです。
塾や習い事を選ぶ時には、保護者の納得感も大事なポイント。保護者が教室の考え方に共感することで、子どもにとっても満足度の高いプログラミング体験になるのではないでしょうか?
※基本情報
●はじめてのプログラミング講座(幼稚園年中~小学2年生程度)
プログラミングによってモノが動くということを理解する
期間:2017年11月~2018年3月 月1回 計5回
所要時間:90分
定員:1クラス10名
入会金:¥10,000(税別)会費:¥3,800/月(税別)
●初級コース(小学3年生~6年生)
※事前にタイピングテストやアンケ―トでスキルチェックプログラミングと電子工作の基礎を学ぶ
期間:1年間 月1回 計12回
所要時間:2時間
定員:1クラス10名
入会金:¥10,000(税別) 会費:¥6,000/月(税別)
●中級コース(小学5年生~中学生)
※事前にタイピングテストやアンケートでスキルチェック
マシン製作と制御プログラムの基礎、応用を学ぶ
期間:1年間 月2回 計24回
所要時間:2時間
定員:1クラス10名
入会金:¥10,000(税別) 会費:¥11,000/月(税別)
●アドバンストコース(小学5年生以上)
モノが動くために必要なセンサーについて理解を深める
期間:半年間 月1回 計6回
所要時間:150分
定員:1クラス10名
入会金:¥10,000(税別)会費:¥7,000/月(税別)
※入会金は入会時のみ
※『サイエンス俱楽部』既存会員は、入会金不要
※参考リンク
https://protech-club.com/
プロ・テック倶楽部の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社サイエンス倶楽部
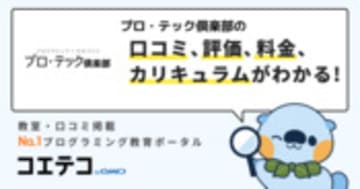
https://coeteco.jp/brand/protech-club >
(取材・文・撮影/松井紀美子、編集/コエテコ編集部)


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
(取材)プロ・テック倶楽部|プログラミングの基礎からPythonによるIoT開発、大会へのチャレンジも!実力派スク...
今回ご紹介するプロ・テック倶楽部は、プログラミング的思考の基礎からPython(プログラミング言語)によるIoT開発、さらには仲間とチームを組んで大きな大会へ挑戦するなど、小学生から高...
2025.05.30|大橋礼
-
(教室取材)ヒューマンアカデミーサイエンスゲーツとは?|科学など「STEM教育」への入り口となる実験教室!
今回ご紹介するのは、理科実験教室の新定番となりそうなヒューマンアカデミーサイエンスゲーツ。毎月設定されるテーマに沿った実践を通し、科学のさまざまな分野を幅広く学べるスクールです。 こ...
2024.11.06|夏野かおる
-
(レポート)JAXA研究者とロボティクスベンチャーが語るSTREAM教育の可能性と新しい検定制度「創ロボ検定」
子どもたちに学びの機会を提供するため2023年6月に設立された、一般社団法人未来創生STREAM教育総合研究所(以下、RISE)。同法人が展開する新しいロボットプログラミング検定「創ロ...
2025.05.30|大橋礼
-
(取材)横浜・戸塚に新規オープン!ロボット科学教育Crefus(クレファス)|小2在籍生と保護者にインタビューしました
ロボット科学教育Crefus(クレファス)は、小学校低学年から算数や理科の領域にも踏み込んだカリキュラムを展開し、子どもたちの「好き」を伸ばすスクールです。そんなクレファスに2023年...
2025.05.30|大橋礼
-
ひとりひとりの個性を伸ばす!小中学生向けプログラミング教室「CodeCampKIDS(コードキャンプキッズ)」
コードキャンプ株式会社が新たに展開する子ども向けプログラミングスクール事業「CodeCampKIDS(コードキャンプキッズ)」。2018年4月からはCodeCampKIDSオンラインス...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部