Scratch非対応問題は「オフライン版で解決」でいいのか?阿部和広先生に聞く

ところが今年1月、こんなニュースが世間を騒がせました。
渋谷区で配布しているタブレットでscratchが使えなくなった件について対処

http://www.s-kenpo.jp/archives/2541 >
渋谷区の学校で使用するタブレットではブラウザがInternet Explorer(略してIE)に限定されており、バージョンアップしたScratchが動かなくなってしまったのです。
「Scratchも動かないのに、プログラミング教育必修化なんて本当にできるの?」
「今どきIEを使っているなんて、学校のICT環境はどれだけ遅れているんだ!」*
SNS上には怒りや疑問の声が上がり、ついに渋谷区議会の鈴木けんぽう議員にまで届いたのでした。
*Windows 10標準のブラウザは「Edge」へ変更されており、Microsoft社もIEを使わないよう求めている。
とはいえ、学校のパソコン・タブレットの標準ブラウザがIEに限定されている問題は、Scratchの件が話題になる前から指摘されてきたところです。
今回はScratch日本語版の翻訳者であり、Eテレ『Why!? プログラミング』プログラミング監修者でもある青山学院大学大学院・阿部和広先生に、広い視点から「渋谷区Scratch非対応問題」について解説していただきました。

青山学院大学大学院で教鞭を執りつつ、プログラミング教育に関して常にアンテナを張られている阿部先生。
この日は大学の入学式で、構内には桜が咲いていた
「誰が悪い」ではない
—さっそく本題に入ります。今年1月、渋谷区にお住まいの保護者の方から「Scratchが3.0にバージョンアップし、学校のタブレットでは使えなくなった」という問題が提起されました。いわゆる「学校IE問題」* について、分かりやすく教えていただけますか。
IEは一般に普及している「モダンブラウザ(Google Chrome、Safari、Edge等)」と比較して「レガシーブラウザ(古い技術のブラウザ)」とよばれる。
まず確認しておきたいのは、「学校のパソコンでScratch 3.0が使えない」という事実だけに着目すると、問題の本質を見誤ることです。
今回はたまたま①渋谷区の親御さんが ②Internet Explorer(IE)で ③Scratch 3.0が動かない という問題を提起され、それが”バズった”わけですが、問題の本質はもっと根深いんです。
誰が悪いとか、こうすれば良いと一概に言えないことを頭に置いてください。
込み入った話になりますが、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

阿部先生は15年ほど前から子どものプログラミング教育に強い関心を寄せておられ、毎日の情報収拾は欠かさない。
今回もいろいろなニュースを踏まえつつ、さまざまな角度から問題を解説していただいた
①渋谷区だけの問題ではない
繰り返しますが、今回の問題は渋谷区に限定された話ではありません。「学校でIEしか使えない」というのは、全国的な話なんです。そもそも、コンピュータの管理権限は一般には各学校ではなく、教育委員会が持っています。学校が独自の考えで新しいブラウザを使いたくとも、簡単にはできない構造だといえるでしょう。
個人的には、各学校に権限を委譲すべきだと考えますが……話はそう簡単ではありません。
この件に限らず、プログラミング教育をとりまく問題を紐解こうとするとおのずと社会の構造の問題になっていきます。法改正なども含めて包括的に問題を捉える必要があるのです。
②なぜ学校ではIEしか使えない?
「どうして学校ではInternet Explorer(IE)しか使えないのか?」という問題については、Z会の野本さんが書かれた記事にまとまっています。昨今、各所で話題になった「学校のブラウザがIEであることでプログラミング学習が充分にできない」という課題に端を発した論争。この件について、各所の記事や筆者の周辺から集めてきた情報をもとに、解決策を考えてみたいと思います。 ...
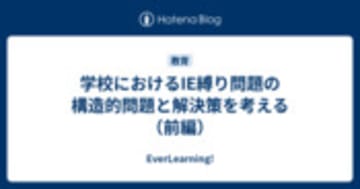
http://it-education.hatenablog.com/entry/2019/03/12/021022 >
複雑なので、ひとまず3点に絞って話しましょう。
大半の学校パソコンはWindowsで動いている
野本さんの指摘をなぞる形になりますが、学校に導入されているパソコンはWindowsが大半です。Windows 10からは標準ブラウザが「Edge」に変わりましたが、それ以前のOSではIEが標準です。だからIEを使う、というのが前提としてあります。
「特定のソフトが確実に動く」のが大事
これも野本さんの記事にあるように、学校のパソコンは家庭とは違い特定の目的のために使われます。授業では決められたソフト、決められたアプリが確実に動くことが大事とされているのです。そうなると、わざわざ他のブラウザを導入するよりも、アプリの動作が保証されている標準ブラウザ(=IE)を使っておくのがもっとも簡単で、サポートコストが低くなります。
授業と関係のないことはタブー
学校の先生はパソコンに詳しい方ばかりではありません。良いか悪いかの議論はさておき、子ども達が授業と関係のない操作をするのを止めたい気持ちがあるんですね。だから、余計な操作ができないように制限された「IE以外は使用禁止」ルールができてしまう。
パソコンに詳しい子がイタズラをすると、先生は困っちゃうわけです。

③動かないのはScratch 3.0だけではない
「学校IE問題」をエンジニアの観点でみると、「なんでIEなんだ?」と眉をひそめたくなります。IEはレガシーな(古い)ブラウザで、最新のHTML5の仕様にも対応していません。けれども、先ほどまとめたように、サポートコストの面を考えると簡単には乗り換えられない。
その摩擦が「Scratch 3.0が動かない」という形でたまたま表面化したのです。
「仕方ない」で済ませてはいけない
—こうして見ると「IEしか使えませんよ」と言われても仕方ない気がしてきました。とはいえ、学校以外でもIE問題は国会で議論されるレベルになってしまいました。
さまざまな事情があるにせよ「仕方ない」で終わらせるべきではないと考えます。
26日の衆議院財務金融委員会で、Internet Explorerを巡る論争があった。「日銀ネット」のOSがWindows限定で、ブラウザーがIEに限られているという。IEを巡っては、マイクロソフト社自体も使用をやめるように声明を出している

http://news.livedoor.com/article/detail/16079565/ >
たとえScratch 3.0の問題が片付いても、セキュリティやアプリの互換性など別の形で表面化することは避けられません。
問題を先送りするのではなく、これをきっかけにして、子どもたちにとって何が一番大切なのか考えた上で、学校内のICT環境を整える動きが生まれて欲しいですね。

—お話を聞いて、あっちを立てればこっちが立たず……という印象を持ちました。
「じゃあGoogle Chrome入れたらええやん」で解決する話ではないんですね。
渋谷区の話には続報があるんですよ。どういうオチがついたのか、見てみましょうか。
渋谷区のオチ「オフライン版を使う」
3月25日に渋谷区議会議員の鈴木けんぽう氏がこのような報告を出されました。渋谷区のICT教育、課題を一つ解決できそうです。

http://www.s-kenpo.jp/archives/2630 >
結論として「Scratch 3.0のデスクトップ版を使う」* ことになったわけですね。
—えええ。局所的な解決策のように思えるんですが……
もちろん、鈴木氏も「 原因となったブラウザのインターネットエクスプローラーは近いうちに変更しなくてはならない」と課題を認識されています。
とはいえ膨大なコストや人的な負担がかかりますから、とりあえずScratchの話は「デスクトップ版を使う」ことで解決、という結果になったわけです。
—必修化も迫っていることだし、まずは手近な落としどころで、と。
学校IE問題に関しては未来の学びコンソーシアム* にも多数の問い合わせがあったようで、このような「お願い」が出されました。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://miraino-manabi.jp/content/388 >
「学校及び教育委員会におかれましては、(中略)適切なブラウザ環境をご用意ください。」とかなり踏み込んだ言い方をされています。
強制力があるわけではありませんが、はっきりと言い切ったのが大きいです。
—「ご用意ください。」とはっきり言い切られたら「早めにやらなきゃ」って気持ちになりますもんね。
ただ、「Scratchには、ブラウザを利用しないオフライン版も用意されています。」と書かれているのがミソです。
モダンブラウザを用意して欲しいけど、無理ならオフライン版を……という「逃げ道」を用意した格好です。
—現場の先生方にしてみれば、「そんなこと言われても無理だよ!」というケースが多々あるんでしょうね……。
ええ。この「逃げ道」を書かなければならなかった事情も、痛いほどよく分かります。

「結果平等」から「機会平等」へ
—様々な問題が絡み合ったScratch 3.0非対応問題ですが、プログラミング教育必修化においてScratchはどういう役割を果たすでしょうか。これまで、日本の公教育は公平性を重視してきました。それも、どちらかといえば「出口の公平性(=結果平等)」です。「学校を卒業した子ども達は全員、ある一定水準の能力を有している」という状態を目指してきたんですね。
それが今後は「入り口の公平性(=機会平等)」に変わっていくのだろうなと。
—「すべての子どもがプログラマになる(結果平等)」のではなく、「すべての子どもがプログラミングに触れる(機会平等)」を目指すことになると。
そうなると、設備や先生方のスキルの面で「教育格差」が生まれやすくなるのでは?
そうですね。これまでも教育格差はあったけれども、今後はより表面化してくるのではないかと思います。
アメリカの話をすると、チャーター・スクール* やマグネット・スクール* というものがあります。
これらの学校では魅力的な教育を受けられる一方で、そこへ通えない子どもとの格差を生み出しているのでは?と批判されています。
ただ、同じようなことは実は日本でも起きているんです。たとえば、魅力的な公立学校に通わせるために住民票を移すケースなどがありますよね。
—そういえば「公立の小学校でアルマーニの制服が……」という話がありましたね。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://www.huffingtonpost.jp/2018/02/07/schooluniform_a_23355576/ >
ええ。プログラミング教育に関係なく、教育格差はすでに生まれてしまっている。
となると、プログラミングにおける入り口の平等(=機会平等)を考えたときに、「Scratch 3.0を誰もが使える環境を用意する」のがミニマムな解決策ではないか。
ベストではないにせよ、ベターであろう、が私の意見です。
まとめ
「Scratch 3.0が動かない」という形で表面化した学校ICT環境の問題。コエテコでも、平成29(2017)年8月に出された「学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議 最終まとめ」を引用しつつ、「一人一台タブレット」とは程遠い現実をお伝えしました。
小学校でプログラミング教育が必修化されて以降、中学校や高校にも広がり、子どもたちがプログラミングに触れる機会は確実に増えています。一方で、保護者の中には「何を学んでいるのか」「将来にどう役立つのか」といった関心や不安を抱く方も多いはず。本記事では、小学校におけるプログラミング教育の内容や目的をわかりやすく解説します。


2025/11/17

阿部先生のおっしゃった通り、この問題を解決するには社会や学校組織の構造から変えていかなければなりません。
どれくらい本気で変化を望み、現実を動かしていけるのか……我々一人ひとりが問われているのかもしれませんね。
コエテコでも引き続き、プログラミング教育に関する情報発信を続けていきます。阿部先生、ご解説ありがとうございました!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
東急電鉄と大手IT企業4社、渋谷区教育委員会と「プログラミング教育事業に関する協定」を締結
2019年6月17日(月)、東急電鉄とサイバーエージェント・DeNA・GMOインターネット・ミクシィの渋谷区IT企業4社が渋谷区教育委員会と渋谷区の小・中学校におけるプログラミング教育...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
Scratchで実演!プログラミングの授業を成功させるポイントとは
プログラミング教育必修化を目前に控え、効果的な授業実践の方法を求める方が増えています。今回は『Why!? プログラミング』監修の阿部和広先生にお伺いし、実際にScratchを動かしなが...
2025.06.24|夏野かおる
-
(インタビュー)熊本市教育センター主任指導主事 前田康裕先生|タブレットを「ゲーム機」にしないために、今できること
コロナ禍により前倒しされたGIGAスクール構想。1人につき1台の学習用端末が配られたものの、活用の度合いはまちまちで、トラブルの声も絶えません。OECDの調査によると、2018年時点で...
2025.05.21|夏野かおる
-
自民党、民間EdTech事業者に「学校休校要請に関連した対応状況等ヒアリング」を実施
2020年3月3日15時、自由民主党本部にて学校休校要請に関連した対応状況についての関係省庁・関係企業・団体に対するヒアリングが行われました。 参加の自民党議員からは多くの質疑・要望...
2025.06.03|コエテコ byGMO 編集部
-
(イベントレポート)Kids VALLEY プログラミングサマーキャンプ2022 渋谷のITキッズが語る!プログラ...
2022年8月、東急と渋谷に拠点のあるIT企業5社によるKids VALLEYのプログラミングイベントが開催されました。オフライン・オンラインイベントに加えて「渋谷区プログラミングコン...
2025.09.10|安藤さやか






