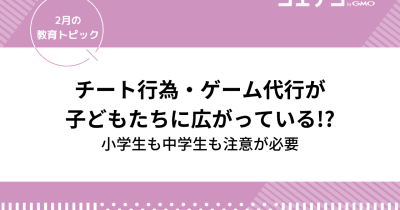課題解決力を家庭で育てるには? | 問題解決型学習(PBL)も解説!

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。
問題を把握し解決する力は、勉強にかぎらず「生きていくうえで必要なスキル」といえますね。今回は子どもの課題解決力をテーマに、わかりやすい例をあげながら解説します。
小学校の課題解決学習について
小学校では課題解決学習を問題解決型学習(Project Based Learning、略称PBL)と呼ぶ場合もあります。・問題の認識理解はできますがわかりづらいですね。では具体的な例をあげていきましょう。
・情報の収集と分析
・方策の決定
・実行
引用:問題解決能力育成のためのガイドブック/神奈川県立総合教育センター
コインの裏返しでは意味がない!課題解決力とは
みなさん、こんな場面を見たことがありませんか?上司「売上が悪いな!」
部下「はい…」
上司「とにかく売上を伸ばせ!」
家庭なら、こんな感じです。
親「算数の成績がヒドイじゃない!」
子ども「うん…」
親「だったら算数の成績をあげなさい!」
上司も親も「売上が悪い」「成績がヒドイ」ことにたいして解決の方法をアドバイスしていません。ただ「伸ばせ!上げろ!」と言っているだけです。これでは言い方を変えただけ、つまりコインを裏返したただけで何ひとつ解決していません。
課題を正しく見つけることが大事
「算数の成績がヒドイ」のは本当の課題ではありません。課題解決力でもっとも重要なのは、何が問題/課題なのか見極めて把握することです。「算数の成績」の場合だと、なぜ「ヒドイ」結果につながっているのか親子で課題を把握しなくてはなりません。テスト結果やノートを見て「計算での間違いが多い」など、具体的な問題を把握していきます。
問題解決型学習で「問題の認識」と呼ばれるステップがこれにあたります。

課題・問題は「計算間違いが多い」とわかったので、次は「情報の収集と分析」です。ノートを見ると筆算での間違いが多い。乱暴に字を書くから0が「6」に見えて間違えたり、桁がずれて計算ミスをしている。テストでは計算にとても時間がかかっていたことを思い出します。
ここで親が「どうしたらいいんだろうね」と投げかけてみましょう。子どもは
- 数字を見間違えないようにきれいな字で書く
- 桁をそろえて凡ミスをしないように計算する
- 時間があれば試し算をして答えを確かめる
次には「算数の成績をあげる」結果を出すために計算間違えをなくす方法を決めます。「方策の決定」ですね。
- 計算ドリルで毎日練習する
- きれいな字で書いてミスを減らす
- 続けていくことで計算のスピード力もつける
学習でも生活でも「問題を解決する力」が必要
考えてみると、わたしたちは日常的に問題や課題と向き合い、日々解決を試みています。しかし、わたしたち大人が「問題を発見し解決していける」のは幼少期から積み重ねてきた経験や知識が土台となっているのです。これからはもっともっと「課題解決力」が必要とされるでしょう。
グローバル化が進む世の中で外国語が必要だからこそ「小学校から英語必修化」となりました。パソコンの仕組みを理解し、どう使えばよいのかを学び、論理的思考力を育むために「プログラミングの必修化」も始まりますね。
加えて、人と人とを結びつけるコミュニケーション能力が円滑な社会生活を支えます。
どれをとっても、そこに必ず出てくるのが「課題や問題がでてきたときの解決力」です。何をするのでもトラブルや課題は生じるからです。
プログラミング教室は「子どもの課題解決力」を育てる
プログラミング教室やロボット教室では「試行錯誤」という言葉がよく出てきます。先生が一方的に「こうしなさい」と教えたりマニュアル通りに行ったりしません。教室では「課題」に対して子どもひとりひとりが考え、実践し、うまくいかなければもう一度改善して実行します。プログラミング教育では試行錯誤のなかで「論理的思考」を育むのが第一とされています。同時に失敗した、うまくいかなかったときもあきらめず、粘り強く課題を解決し成功するよう取り組む経験を積むことも教育の一環です。
課題解決力は「問題がおきたとき、あきらめちゃダメです!」と言うだけでは身につきません。うまくいかないときは誰でも落ち込みます。今度は大丈夫だろうとトライしたのに失敗したら、やる気が失せます。当然のことです。
プログラミング教室では、先生が「失敗したなら次はこれをやりなさい」と指導しません。「どうしてうまくいかなかったのかな?」「これを解決するには、どんな方法があると思う?」と子どもたちが自ら考えるよう声かけをします。時には小さなヒントを与え、さらに「よく考えてるね」「すごいアイデアだね!」と子どもの気持ちを引き立てます。
答えを教えるほうが簡単です。でもそれでは、いつまでたってもドリルの後ろの回答ページを見て答えを写しているだけの勉強と同じです。
神奈川県立教育センターによる「問題解決能力育成のためのハンドブック」では、ロボット教材による問題解決能力の育成についても言及しています。ここでは「論理的な試行錯誤のプロセスが最大のポイント」としています。
家庭で育てる課題解決力は「対話がカギ!」
日頃から親子の対話を心がけましょう。といっても、実はみなさん普段から行っていることです。会話での注意点をまとめましたので参考にしてください。【幼児期~小学校低学年】
-
なぜ?どうして?になるべく答える
一緒に答えを探す。 -
できない!と投げ出しそうになったら具体的に答えられるような問いかけをする
できないに「やりなさい!」ではコインの裏返し。「いま、どこをやってるの?」「これか、それでなんで怒ってるの?」「どれどれ一緒に考えてみよう」と声かけをしましょう。 -
無理矢理に答えを求めない
小さな子はなかなか理論的に物事を考えられません。
親の問いかけに突拍子もない返事をしたり、まるで関係のないことを口にするかもしれません。親としては予測している、あるいは「こう答えるはず」と思っている回答でないと「はぁ?なんでそうなるの?」とつい呆れてしまったり、怒ってしまいがちです。でもそこは子どもなのですから、とにかく怒らずに聞いてあげたいところです。
-
問題が何なのかハッキリさせる
課題を把握させるために漠然とした話ではなく「いったいどこが問題なのか」を会話しながら子どもに見つけさせるのが大事です。 -
対話のなかで子どもに考えさせる
建設的な質問をします。「算数の成績をあげるにはどうしたらいいのか」ではなく「計算ミスをしている理由は見つかった?」「そのミスをなくすためにはどうしたらいいのかな」と順序立てて問いかけをしてみましょう。
まとめ
課題解決力というと難しく聞こえますね。こんな風に考えてみたらどうでしょう。課題解決力学習のプロセスは大事です。でもそれだけではありません。家庭では、できなくてイライラしている子どもに「ちょっと休憩したら?」行き詰まっていたら「今日は切り上げて、外で遊んで気分転換してみたら?」とトラブルにめげないようにいろいろな方法を示してあげることができます。
子どものうちにこうした体験を積み重ねていけば「それでもやればできる」過去の体験がモチベーションアップにつながるでしょう。失敗は誰にでもあるとわかれば社会人なって壁にぶつかったときも「だったらもういいや、この仕事やーめた!」ではなく「別の方法はないかな」「うまくいかないときは、他に楽しいことをやって気分転換してまた取り組もう」とこれまでの経験値が支えてくれることでしょう。
子ども時代に親が与えてあげられる「失敗と成功の体験」「問題を解決するプロセスの経験」「突発的におきた出来事に対応してきた実績」が、子どもの糧となり、将来を支えてくれるのではないでしょうか。
少々のことではへこたれない強いハートと、変化や進化にも対応できる柔軟性はこれからの時代を生き抜くのに大きな強みになるはずです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どものうちから身に付けたい!社会人に求められる問題解決スキルって?
社会人になると、仕事上で問題に直面したときに慌てず冷静に問題を解決する力が必要となります。ですが、問題解決スキルを学ぶ機会は少なく、大人になってからスキル不足に気づく人も多いでしょう。...
2022.12.08|横山まなみ
-
チート行為・ゲーム代行が子どもたちに広がっている!?小学生も中学生も注意が必要
みなさんは「チート行為」「ゲーム代行」をご存知でしょうか?親世代では知らないケースも多いでしょう。ゲームで「強くなりたい」と考えた子どもが検索すると、いとも簡単に出てくる「チート」「ゲ...
2024.04.01|大橋礼
-
クレヨンから「肌色」が消えた? 子どもも大人も考えたい、 多様性と差別意識|4月の教育トピック①
多様性、ダイバーシティ、ジェンダーニュートラルにインクルージョン、なんとなく耳にしたことはあるけれど、きちんと意味を把握している人は意外と少ないのではないでしょうか。 これからの時代...
2022.01.17|大橋礼
-
リモート・オンライン工場見学|おうちで楽しむ社会科見学を一挙に紹介!【12月の教育トピック】
ステイホームに外出自粛、大人でもストレスがたまる環境ですが、子どもだってどこにも出かけられず息が詰まる!今回の教育トピックは、大人にも人気の「社会科見学」をオウチで体験しよう!のテーマ...
2024.03.31|大橋礼
-
音読の効果5選!子どもの学習力を上げる方法や注意点も詳しく紹介
子どもが行う音読の脳科学的な効果が注目されています。ただ読解力や語彙力を養うだけでなく、記憶力・集中力アップ、感情コントロールやストレス解消にも効果があるようです。今回は音読の効果や学...
2024.11.06|コエテコ byGMO 編集部