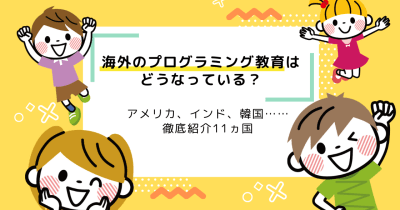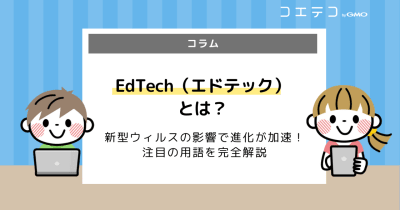ICT化で学校教育現場はどう変わる?メリット・効果・海外の事例まとめ

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
それに伴い、学校現場のICT環境整備も進められています。
インターネット時代とともに、世界をものすごいスピードで変えてきたICT(情報&コミュニケーションの技術)。いよいよ学校教育のなかでも本格的に活用されようとしています。
ICTにはどんな可能性があるのでしょうか。そして、教育をどのように変えていけるのでしょうか?
くわしく紹介していきます。
そもそも「ICT」とは?
まず最初に、「IT」に代わってよく使われるようになった「ICT」(Information and Communication Technology)という言葉の意味を解説します。ICTとは……情報と通信の技術!
直訳すると「情報と通信の技術」という意味になります。以前は情報技術を示すIT(Information Technology)という言葉がよく使われていましたが、SNSの普及などにより、情報だけではなくコミュニケーションの重要性が増していることを受けて、C=Communicationが付け加えられました。
パソコンやタブレット端末を使い、インターネットを介して知識や情報の伝達を行う=ICTと理解しておけばいいでしょう。
ITとICTには、厳密な定義の違いはありません。
とはいえ国際的には、ITよりもICTのほうが一般的に使われている、という説もあります。
ICTとIoTの違いは?
ICTによく似た響きの言葉に「IoT(アイ・オー・ティー)」があります。でも、この二つはまったく違う言葉です。
IoTは、Internet of Thingsの略語で、日本語では「モノのインターネット」と訳されています。
呼んで字のごとく、インターネットによりさまざまなモノ(家電、通信機器)などを操作して、作業をさせたり情報を集めたりすることです。
外出先からテレビ番組を録画予約する/スマートフォンを使って自宅のペットのようすをチェックしエサを与えるなどの作業をする/ウェアラブル端末から生体情報を取得し医師による健康チェックを受けられるなど、我々の生活を便利にしてくれる技術がIoTです。
ICTはどこで利用されているの?
現在の社会、そのすみずみまでICTが生かされていない場所はない、というぐらいの広がりを見せています。超高齢化社会でより安全性向上と効率化が求められる医療・介護分野/地方の人口減少を抑止するための地域活性化分野/頻発している巧妙なサイバー攻撃から機密情報を守るためのサイバーセキュリティ分野/迅速かつ正確な災害情報伝達手段の普及拡大の推進のための防災分野……など。
たとえば、会社の経理事務は、紙の帳簿から、ホストコンピュータにつないだ端末により操作するようになり、現在は多くの企業でインターネット上のWebブラウザ上にアプリケーションを起動して入力管理するように変化しています。
手書きからコンピュータへ。
さらには、インターネットの利用へ。
すなわちこれが、ICT化されたということです。
そのなかで、教育分野は比較的ICT化が遅れていた分野といえるかもしれません。
従来は試験問題、プリントなどの印刷、試験結果の集計など、ネットワークを利用しない用途が中心でした。
だからいっそう、ネットワークの利用により極端な変化が訪れると予測されている分野でもあります。
どうして教育現場でICTが注目されている?理由は?
教育現場で導入が急がれるICTについて、その背景を説明します。少子高齢化が進み、遠隔で授業を受けられるシステムが必要
少子高齢化に起因して、生産年齢人口の減少、社会保障費の増大、介護負担の増大といった課題が浮き彫りになっています。その課題の中、日本が目指すべきビジョンとして、総務省ではICTを活用した次の3点を掲げています。
1.すべての国民が、可能な限り長く健康を維持し、自立して暮らすことができ(健康寿命の延伸)、また、病気になっても住み慣れた地域で、質の高い医療・介護サービスを享受することができる社会の実現出典元:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/index.html (総務省ホームページ)
2.健康で意欲のある高齢者が、その経験や知恵を活かし、現役世代と共生しながら、生きがいを持って働き、コミュニティで生産活動や社会参加ができる社会の実現
3.世界に先駆けて超高齢社会を迎えた我が国が、課題解決先進国として、その解決方策となるICTシステム・サービスの日本モデルをいち早く確立し、新産業の創出とグローバル展開を実現
たとえば、地方においては児童数の減少、先生の不足などを背景にして、学校の統廃合が急ピッチで進んできました。
このために長時間かけて登校を強いられるような子どもたちも増えています。
学力に関する地域格差も問題で、一部地域では学歴低下が無視できない状況になっています。
これを解決するために、たとえば、東京の有名講師の授業をネットワークを介して、全国で受講できるようにならないか……など、さまざまな取り組みがはじまっています。
ネットワーク環境が充実して、ICTがより便利になった
WiFiなどのネットワークの整備が進み、センサー、AI(人工知能)といったロボットを作成する上で必要となる技術、タブレット端末やスマートフォンといった通信媒体が進歩したことにより、それらを組み合わせて様々なことに応用できるようになりました。さらに、それらから収集したデータを蓄積・分析するビッグデータ技術などが発展したことで、より高度な技術を生み出すことが可能となっています。
教育に関するさまざまな課題が、ICTの積極的な導入によって解決できるのではないか。
この発想が、いま教育現場を一変させようとしています。
ICTで教育現場がどう変わる?
学校教育にICTが導入されるといっても、具体的に何がどう変わるのでしょうか?デジタル教材が気持ちも体も軽くする!
かつての子どもたちは、教科書、ノート、筆記具などを詰め込んだ重いカバンを背負って学校に行ったものでした。重過ぎるカバンを背負いつづけると、子どもの体に悪影響を及ぼすのでは?といった指摘もあります。でも、iPadなどのタブレット端末を使うようになれば、これだけ持って学校にいけばいいことになり、子どもの負担が軽くなります。
また、教科書の枠を超えて、インターネットから情報収集しながら学習でき、よりアクティブな授業が可能になります。
それだけではなく、たとえば……
・数学では、3次元モデルを使って図形をさまざまな立体的に表示できるため、直感的な理解をしやすくなるでしょう。
・体育では、見本となる動きを動画で確認したあと、生徒の動きを撮影して動画と照らし合わせることで伝わりやすい指導ができます。
・英語や国語では文章の音声データを可変速度で再生することができ、自身の習熟度に合わせた学習ができます。
また、教科に関わらずテストを実施する際、タブレット上で回答すれば、先生は瞬時にクラスの何%が理解できたかがわかり、指導しやすくなるでしょう。
(正解の子と、典型的な間違いをした子のどちらが正しいか、クラス全員で議論すれば理解も高まっていくはずです)
デジタル教材は、紙の教科書・ノートをを必要としないため、省資源化の観点からも意義があると言われています。
カリスマ先生の授業がどこでも受けられる!
人口の一極集中が進み、離島や過疎地では各教科の専門知識を有する教員を確保できない問題が発生しています。不登校になってしまったり、病気の療養等で学校に来ることができない生徒もいます。
ネットワークを利用した遠隔授業を利用することで、過疎地における学力低下を最小限にできるでしょう。
また、みんなが同じ先生から同じ内容を学ぶという従来のスタイルから脱して、じぶんの興味・関心に合った授業を選ぶ・・・と選択肢も拡大していきます。
事務作業がなくなれば、先生が授業準備に時間を割ける!
教員は、生徒の成績・出欠・体調等の情報を日々の校務で管理しています。それらの作業は教員の負担になるだけでなく、生徒と教員のコミュニケーションを阻害する原因にもなります。
そこで、生徒の情報をICTを用いて一元管理することで校務を削減する取り組みがなされています。
生徒管理のための事務作業がなくても、自然に情報が蓄積されて、それを見れば指導できる。
それにより、先生の時間を授業内容の研究など、より本質的な作業に使うことができます。
いろいろな子どもにバリアフリーな環境を!
ICTの活用は、さまざまな不自由をもった子どもたちの問題も解決するかもしれません。・読むことが困難な生徒は、電子化された教科書の文章を音声で聞けます。
・書くことが困難な生徒は、タブレット端末で文字を入力できます。
・意思を伝えるのが困難な生徒は、電子化された絵カードを使って自分の意志を選択して音声出力できます。
・話を聞くことが困難な生徒は、字幕付きの映像を見ることで話の内容を理解できます。
このように、不自由であることがハンディキャップでないような教育におけるバリアフリーな環境が実現していきます。
プログラミング学習の素地づくりに
小学校、中学校、高校の授業の中でプログラミング教育が取り入れられてきています。少し前までは授業でパソコンなどの情報機器に触れるのは情報の時間くらいでしたが、最近では様々な教科の中で情報機器やプログラミングの活用が進んでいます。プログラミング的思考力を身につけるために情報機器が必須というわけではありませんが、やはり切っても切り離せない関係にはあります。今後もどんどんプログラミング教育が拡充されていくことが予想されるので、小さいうちからタブレットやPCに触れる機会が多いのは良いことでしょう。
今の子どもたちにとって、スマホやタブレット端末は当たり前の存在になってきています。しかし、それはYouTubeなどを見るのが主な用途となっており、どうしても受動的に使っている感が否めません。授業の中で、それらの機器を能動的に使っていく意識を育んでいきたいですね。
だけど、ICTで子どもたちの学力は本当に伸びるの?
ICT化された授業が子どもたちの学力に与えるメリットを考えてみます。情報社会で役に立つ基礎力を得られる
現在の社会で活躍していくために、コンピュータを使いこなす力(リテラシー)は、基本的なものとなっていきます。タッチタイピングができない。Google検索が上手にできないというような人は、それだけで大変な弱みとなってしまいます。
現行の学習指導要領では、小・中・高等学校の各学校段階を通して情報教育を体系的に実施することが義務付けられています。
ICTを導入することで、ICT機器に関して机上の空論ではなく実体験としてより深い理解を得ることができるようになります。
また、パソコンやタブレット端末を日常的に利用することで、セキュリティに対する警戒心を高め、ネットワークのさまざまなリスクを防ぐこともできます。
じぶんから進んで学習するアクティブ・ラーニングが容易になる
生徒が能動的に学習に参加することを、アクティブ・ラーニング(Active Learning)と言います。押しつけの学習ではなく、好奇心を持ってみずから進んで学習する。
それより、負担も少なく学力の向上も早くなると言われています。
ICTを導入することで、わからない問題に直面したときインターネットの検索サイトなどを利用してスピーディに「わかる」。
そのくりかえしが、学業に関する楽しさと学習効果を高め、アクティブ・ラーニングを実現します。
世界には、ICT学習が普通になっている国も!
海外では、早い段階から積極的に教育にICTを導入している地域があります。シンガポール/1万を超えるデジタル教材を無料でダウンロード可能
シンガポールは、最もICT教育に力を入れている国のひとつです。スクールコックピットシステムが全学校に導入されています。
これは、子供が小学校入学から社会に出るまでの期間、基本情報・成績・体力・出欠情報をすべて一元管理するもの。
子供一人一人がそれぞれのレベルで一貫した教育を受けられるようになっています。
また、Eduma112.0&The ICT Connectionというシステムにより、1万を超えるデジタル教材の中から無料でダウンロードして、活用できる仕組みがあります。
その結果、シンガポールはOECD(経済協力開発機構)が実施している国際学習到達度調査で2015年度世界1位を獲得しました。
デンマーク/教育ポータルEMUを積極活用
デンマークも、早期段階から国家戦略としてICT教育を掲げた国として有名です。すべての文書を電子化し、すべての学校と保護者、児童・生徒とのコミュニケーションをデジタル化することを目標としています。
注目すべきは、EMUという教育ポータル。
これは、2つの機能を備えています。
1.教員らが授業のための教材等に関して意見交換ができるコミュニケーションサイトとしての機能。
2.過去25年間分の新聞記事、ブリタニカ・オンラインなどの百科事典など、教育にかかわる多種多様なコンテンツが一元的に閲覧可能な教育コンテンツ・データベースとしての機能。
運営費は、将来に向けて投資としてすべて国が負担しています。
日本/アップルの認定を受けた学校も!
日本にも、すでにICT教育の取り組みを行っている学校があります。近畿大学附属高等学校/生徒はすべての校内活動をiPad1台で完結!
校内全域にWiFi環境が完備していて、生徒は1人1台iPadを所有しています。そのiPadは、授業やプレゼンテーション、テストをはじめ、あらゆる場面で用いられています。
特色は、サイバーキャンパスという教育ツールを導入していること。
出欠確認から生徒とのコミュニケーション、学習時間の管理にいたるまで、iPad1台で完結できる仕組みになっています。
その取り組みは、2016年11月 Apple Distinguished Schoolという革新的で魅力的な学習環境を整備している学校を対象にしたApple社の認定を日本で初めて受けたほどに高水準なものです。
出典元:http://www.jsh.kindai.ac.jp/hs/education/ict/(近畿大学附属高等学校ホームページ)
まとめ:遅れていた日本にもついにICT化の波が!
コンピュータというと「非人間的なもの」という印象を与えた時代もありました。しかし、いまでは人間が人間らしくあることの強い味方が、パソコン、タブレット、ネットワークというICT技術となってきています。
教育分野でのICTへの取り組みは比較的遅れていましたが、いよいよ本格化していくことでしょう。
子どもたちが好奇心を持って、学力をぐんぐん伸ばしていける時代へ。
保護者の皆さんも、積極的な情報収集は欠かせませんね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
海外のプログラミング教育はどうなっている?徹底紹介(11選まとめ)
小学校でプログラミング学習が必修化されます。そこで気になるのが一足早くプログラミング教育をはじめている海外の動向。世界の先進国や急速に発展している途上国では、どのような教育が行われてい...
2025.04.18|コエテコ byGMO 編集部
-
EdTech(エドテック)とは?なぜ注目されているのかを解説
EdTech(エドテック)とは、教育現場にテクノロジーを取り入れ、さまざまなイノベーションを起こす動きやサービスのことです。学校現場のICT化が急速に推し進められ、EdTechへの注目...
2025.07.17|コエテコ byGMO 編集部
-
NEXT GIGAとは?GIGAスクール構想の課題と文部科学省・学校の取り組みを解説
NEXT GIGAは、文部科学省が推進するGIGAスクール構想の第2期として、日本の教育現場でのICT活用をさらに深めるための重要な取り組みです。本記事ではGIGAスクール構想の課題や...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
文部科学省提供「プログラミン」と学校現場でのリアルなプログラミング教育に迫る!
『プログラミン』は文部科学省が無料提供しているブラウザでプログラミング作成ができるサイトです。今回筆者の5歳の子どもが実際に『プログラミン』を体験しました。2020年プログラミング教育...
2025.05.30|Yukiko
-
次世代の科学技術系人材をはぐくむ「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」
科学技術系人材の育成を目的とし、2002年から開始されたスーパーサイエンスハイスクール(SSH)。響きからなんとなく「理系に強い学校なのかな?」とは分かるものの、実際にどのようなことを...
2022.04.12|コエテコ byGMO 編集部