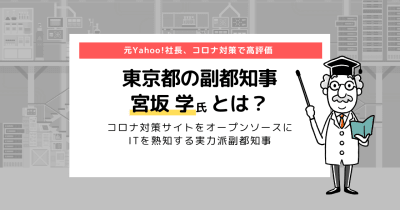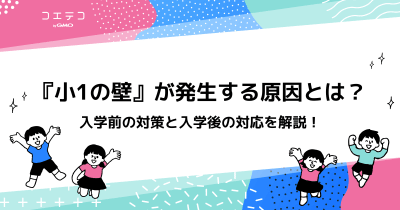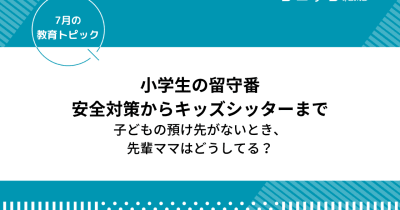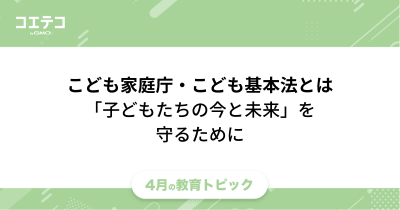幼児教育・保育料無償化の対象とは? 所得制限や手続きについても解説
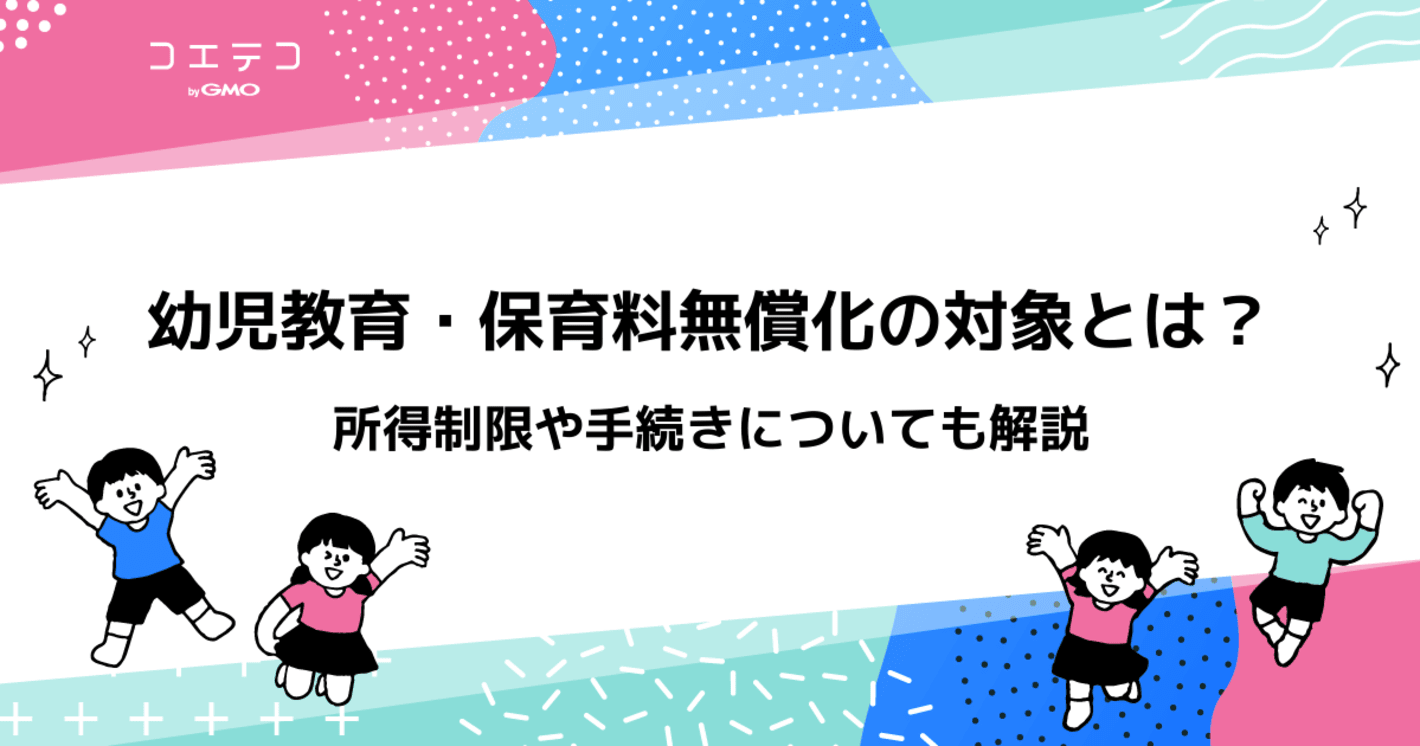
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
2019年10月1日から実施された幼児教育・保育料の無償化。幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育など、さまざまな施設に適用されます。
この記事では、幼児教育・保育料の無償化について、対象児童や対象の施設、手続きの方法について解説します。
幼児教育無償化の対象となる子ども
無償化の対象となる子どもは、満3歳から5歳までの子どもです。対象となる施設は、幼稚園、認定保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育です。公立や私立は関係ありません。
認可外保育施設等に含まれる事業・サービスも対象となり、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、病児保育、ベビーシッターなども、3歳の誕生日以降は月額3万7000円まで補助が受けられます。
また、住民税非課税の世帯の場合は、4万2000円までを上限に補助されます。
対象となる保育の必要性認定区分
1号認定、2号認定、3号認定、認定の必要性なしに分けられます。就労状況などにより、保育の必要性が認定される制度です。無償化の対象となるのは、幼稚園においての1号認定、認可保育所においての2号認定、認定こども園においての1号・2号認定、地域型保育1号・2号認定、企業主導型保育(認定なし)です。
認定区分によって、施設の利用可能時間などが異なります。
1ヶ月あたりの就労時間については48〜64時間以上とされており、市町村によって違いがあります。
| 認定区分 | 対象 | 利用施設 | 施設利用時間 |
| 1号 | 満3歳以上の教育を希望する子ども、あるいは2号認定以外の子ども | 幼稚園、認定こども園 | 1日4時間(標準時間認定) |
| 2号 | 保育を必要とする満3歳以上の子ども | 保育所、認定こども園 | 1日最長11時間(保育標準時間)/1日最長8時間(保育短時間認) |
| 3号 | 保育を必要とする満3歳未満の子ども | 保育所、認定こども園、地域型保育 | 1日最長11時間(保育標準時間)/1日最長8時間(保育短時間認) |
| 認定の必要性なし |
ー | 一時預かりなどの支援サービスを利用できる | ー |
一般的には、フルタイム勤務なら最長11時間預けることができ、パートタイムや短時間勤務の場合は、最長8時間預けることができます。
0〜2歳の子どもは対象になる?
無償化の対象となるケースがあります。住民税非課税世帯で保育の必要性があると判断された場合は、無償で利用できます。
第2子、第3子は対象になる?
第2子、第3子の場合も、満3歳を迎えれば無償化の対象です。満0〜2歳の子どもは、第2子であれば半額負担、第3子以降は無償となります。この第2子や第3子の無償化について注意したいのが、第1子の年齢です。無償化の対象となるのは保育所を利用している最年長の子どもを第1子とカウントします。
第1子が小学生などの場合は、以下のように、幼保無償化の制度上は第1子とカウントしません。
- 第1子 小学生(8歳)ー制度上は第1子にカウントしない(制度対象外)
- 第2子 保育園児(5歳)ー制度上の第1子としてカウントする(無償)
- 第3子 保育園児(2歳)ー制度上の第2子としてカウントする(半額負担)
ただし、年収が360万円未満相当の世帯においては、第1子が小学生であっても第1子とカウントします。例のような兄弟構成の場合、第2子と第3子は無償です。
- 第1子 小学生(8歳)ー制度上の第1子としてカウントする(制度対象外)
- 第2子 保育園児(5歳)ー制度上の第2子としてカウントする(無償)
- 第3子 保育園児(2歳)ー制度上の第3子としてカウントする(無償)
認可外保育施設の場合
認可外保育施設などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合は、保育の必要性認定が必要です。幼児教育無償化の気になる所得制限は?
幼児教育・保育料無償化に、所得制限は設けられていません。逆に、住民税非課税の世帯や年収360万円未満相当の世帯は、さらに補償や補助が受けられるようになっています。住民税非課税世帯
認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育に預ける場合、0歳~2歳児の利用料が無償となります。認可外保育施設等を利用する場合は、合計で月額4万2,000円までの利用料が補助されます。
年収360万円未満相当世帯
おかずやおやつなどの副食費が無償化されます。教育費や保育料が無償化になるかどうかは一般世帯の条件と同じです。幼保無償化の対象とならないもの
給食費、通園送迎費、行事費、教材費、制服費、PTA会費、入園料などは、幼保無償化の対象とはなりません。各家庭で負担する必要があります。ただし、第3子以降の子どもの副食費用は免除の対象です。
入園料
幼稚園などの入園料は無料ではありません。各園によって定められた入園料を支払う必要があります。延長保育
保育園やこども園などの延長保育は幼保無償化の制度対象外です。基本的には、利用する際に実費を負担しなければなりません。ただし、保育所や認定こども園などでは、預かり保育が無償化されて費用が免除となるケースがあります。
預かり保育無償化について
月内の預かり保育利用日数×450円をかけた額と預かり保育の利用料とを比較し、少ない額の方を月額1.13万円までを上限に補助する制度です。満3歳児で保育の必要性があり、かつ市町村民税非課税世帯の子どもなら、支給額上限は月額1.63万円です。
各種学校
「森のようちえん」などの各種学校は、幼保無償化の対象になりません。学校教育法に定める施設に当てはまらないためです。インターナショナルスクールなども自動車学校と同じ法律上の各種学校と定められており、無償化の対象にはなりません。
幼保無償化のために必要な手続き
幼保無償化の手続きについて解説します。保育園や幼稚園などでは申請不要
保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育であれば、自動的に無償の対象となります。必要書類の提出が必要なケース
企業主導型保育事業を利用する場合、企業主導型保育施設に対し必要書類の提出を行います。また、認可外保育の場合は、無償化される費用を各自で請求しなければなりません。認可外保育施設を利用している場合は、支払いが確認できる書類を市区町村へ提出することで利用費の補助が受けられます。
保育の必要性の認定について
無償化に対しては申請は必要ありませんが、入園の手続きなどと同時に、保育の必要性の認定を受けるための書類を提出が必要です。地域等にもよりますが、入園願書などを配布するタイミングで申請書を受け取り、市町村へ提出します。
幼稚園などの預かり保育を無償で利用する場合も、お住まいの市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
おすすめの幼児教育3選
お子様に遊びながら学習の習慣を身に付けてもらいたいなら、幼児教育を利用してみましょう。ここでは、おすすめの幼児教育をご紹介します。こどもちゃれんじ

幼児教育の大手として長年高い人気を得ているのは、こどもちゃれんじです。0歳から年長向けまで、幅広い教材を取り揃えていることが特徴。遊びのなかから、学習の基本を楽しんで学べます。お子様一人でも取り組める教材だから、共働きのご家庭からも選ばれています。
こどもちゃれんじでは、言葉や数、生活習慣や自然科学など、さまざまなテーマに触れられることがメリット。たとえば、1~2歳向けの教材では音の出るリトミックドラムやお風呂でも使える教材で、身体を使いながら言葉を覚えられます。それに対し、年長向けの教材では、プログラミングや英語、ひらがなや時計が学べる「じゃんぷタッチ」が教材となっています。
カリキュラムが決められていないので、お子様の気が向いたときや隙間時間に無理なく教材を活用できます。使用時間については、公式サイトで以下のように案内されています。
特に決まった使い方はありません。ご家庭のリズムや、お子さまの興味に合わせて、好きな時に10分~15分程度、毎日取り組まなくても、十分に力が身についていきます。引用:こどもちゃれんじ
年齢に合う必要なテーマの教材だけをバランスよく届けてもらえるから、保護者が教材を選ぶ必要もありません。
受講費は、1~2歳向けコースと2~3歳向けコースが27,360円(税込)、年少コースは27,960~28,160円(税込)、年中コースは29,760円(税込)、年長コースが36,360~36,560円(税込)となっています。入会金は無料で途中退会も可能であるため、まずは気軽に無料体験教材を申し込みたいですね。
スマイルゼミ幼児コース

小学校入学までに学習習慣を身に付けたいなら、スマイルゼミがおすすめです。ひらがなやカタカナ、英語や生活などをタブレット1台で学習できることが特徴です。毎月、約220問を配信しているから、学ぶたびに新しい知識を吸収できます。さらに、無学年学習を採用しており、小学校や中学校レベルまで先取りで学習することも可能です。
タブレットには、お子様の学習をサポートする機能が搭載されています。これによって、お子様が一人で学習する習慣が身に付きやすいことがメリット。タブレットを起動すれば、「きょうのミッション」で取り組む課題が表示されます。そのため、偏りなく学習を進められるようになっています。
タブレットに搭載されている機能は、以下の通りです。
- 文章読み上げ機能
- 自動丸付け機能
- 間違い指摘
- 書き順ナビゲート
- 筆圧検知システム
受講料は、年中~年長コースで、12ヵ月分一括払いで月々3,278円~(税込)となっています。気になる場合は、約2週間のお試し入会を利用したいですね。
幼児ポピー

2歳児から年長までの学習意欲を高められる教材は、幼児ポピーです。幼児期の「好きになること」を尊重する教材だから、お子様の学習に対する意欲を育めます。幼児ポピーには、「株式会社新学社」の学習教材が盛り込まれていることが特徴。そのため、小学校入学後もスムーズに学習を継続できることがメリットです。
幼児ポピーでは、以下のようにコースが分けられています。
- 2~3歳児:ももちゃん
- 3~4歳児:きいどり
- 4~5歳児:あかどり
- 5~6歳児:あおどり
月会費は、2~3歳児コースと年少コースが980円(税込)、年中コースと年長コースが1,100円(税込)となっています。幼児教育のなかでは比較的安いため、教育費を抑えたいご家庭からも人気を得ています。
まとめ
保育園や幼稚園の利用料は、毎月数万円から十数万円にものぼります。子育て世代にとっては、これらの利用料無償化はありがたいものです。基本的には利用する施設等に従って書類を提出すれば制度を利用できます。預かり保育の利用料も無償化される可能性があるため、少しややこしさを感じても、制度をきちんと理解しておいた方がいいでしょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
東京都の副都知事 宮坂学とは? 元Yahoo!社長、コロナ対策で高評価! なぜ注目されているの?
新型コロナウィルスの対策で、東京都副知事の宮坂学氏が注目されています。 宮坂学氏は、元々はヤフー株式会社の代表取締役社長の経験がある実業家で、2019年9月に東京都の副知事に就任しま...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
小1の壁が発生する原因とは?入学前の対策と入学後の対応を解説
まもなく入学を迎える多くのお父さま・お母さまは『小1の壁』という言葉を聞いたことがあるかと思います。幼稚園や保育園の時とは違い、小学校入学後の方が育児と仕事の両立が難しくなったという声...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
小学生の留守番「安全対策からキッズシッターまで」子どもの預け先がない時の対処法
今回の教育トピックは「子どもひとりでお留守番」の方法についてです。 預け先が見つからない急な外出や、どうしても子どもひとりで「まるまる1日過ごさせなくてはならないとき」もあるでしょう...
2025.10.29|大橋礼
-
こども家庭庁・こども基本法とは?知っておきたい「子どもたちの今と未来」を守る権利と国の組織
2023年4月に「こども家庭庁」が発足しました。同時にこども基本法も施行されたことは、ニュースなどでご存知の方もいるかもしれません。“こども家庭庁”は「こどもまんなか」を謳っていますが...
2025.09.10|大橋礼
-
「おうちモンテ」とは?簡単アイデアや基礎知識を知ろう!
子育て世代の間で話題の「おうちモンテ」。モンテッソーリ教育は世界的企業の創始者や芸術家などが受けた教育方法で、子どもの自己教育力を育むことができます。近年は家庭で気軽に試せるおうちモン...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部