小4の壁の壁とは?勉強への対策・乗り越え方も解説
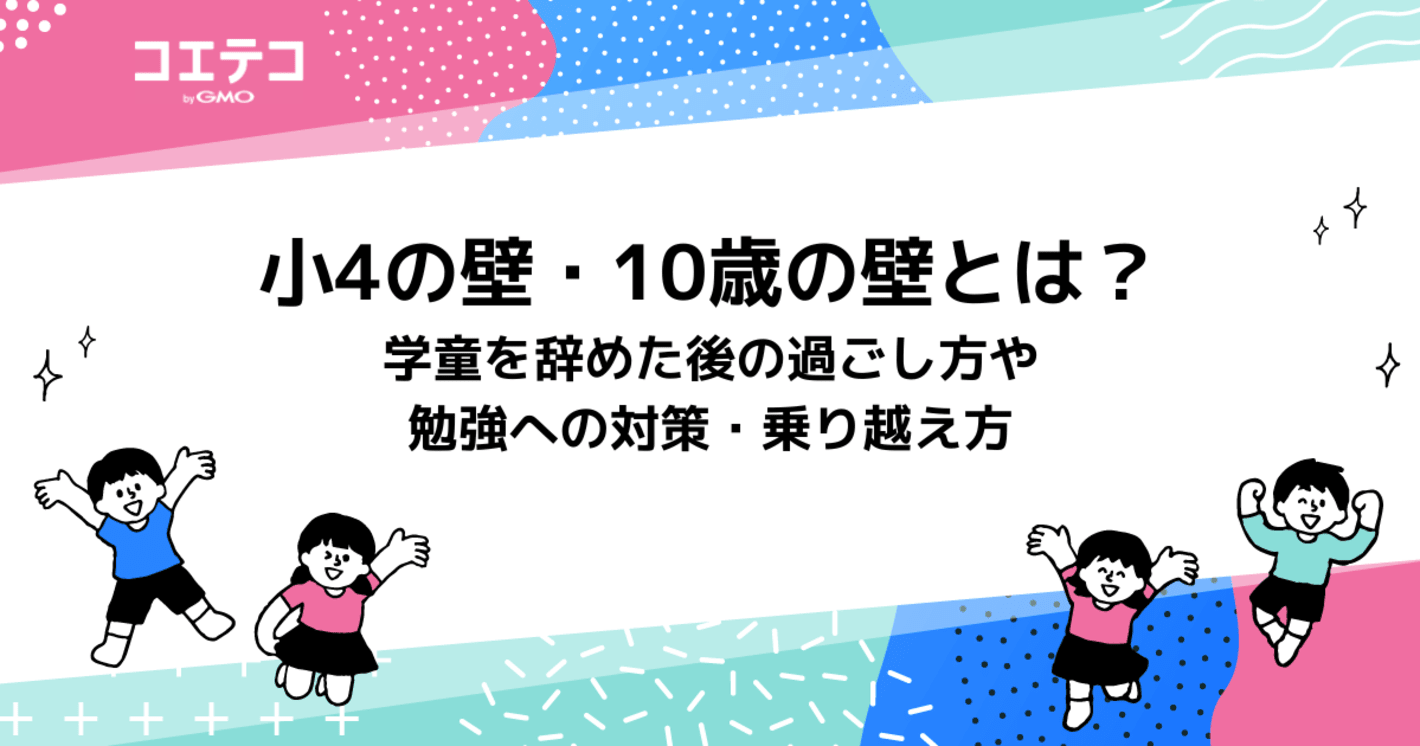
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
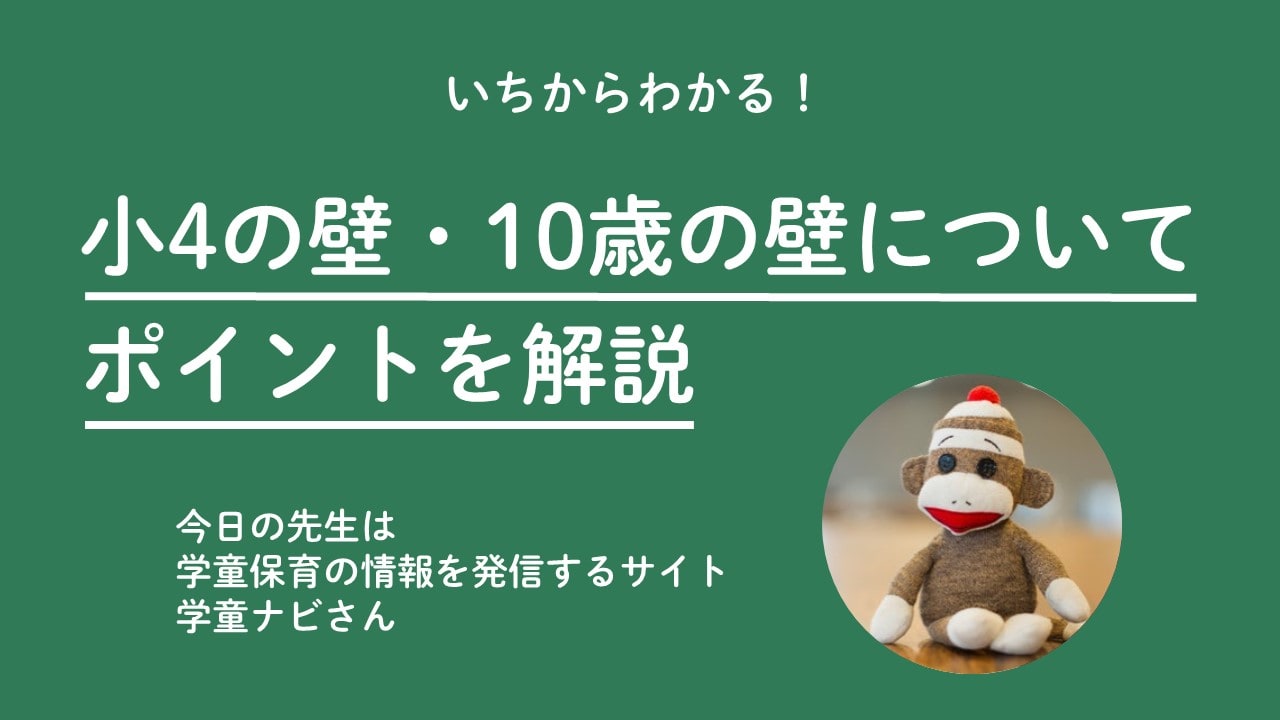
「小4の壁」は「小1の壁」とはまったく違います。「一番辛かったのは小4の壁だった。あの頃のことは思い出したくもない」と筆者の周りには強烈な体験をした人が少なくありません。早めに対策することで防げる問題も多くあります。実態や対策について解説します。
- 1. 小4の壁・10歳の壁とは?
- 2. 【小4の壁の課題1】学習でつまずく子どもが増える
- 3. 【小4の壁の課題2】親の仕事と子育ての両立が難しくなる
- 4. 【小4の壁の課題3】友達同士でのトラブルが増えやすくなる
- 5. 【小4の壁の課題4】子どもが親に反抗するようになる
- 6. 小4の壁の実態 どんな問題が起きるのか
- 7. 厚労省も「小4の壁」を問題視
- 8. 小4の壁で退職するメリット・デメリット 良かったことや後悔したことは?
- 9. 小4の壁への親ができる対策方法
- 10. 【小4の壁の対策】ギャングエイジへの対応
- 11. 小4以降の子どもも対象のおすすめ民間学童・習い事
- 12. 小4の壁に関するよくある質問
- 13. 小4の壁まとめ
小4の壁・10歳の壁とは?
「小4の壁」は、小学校4年生前後の時期に子どもが直面するであろう幅広い問題のことを意味しています。「9歳の壁」「10歳の壁」とも呼ばれており、問題は大きく分けて2つあります。- 年齢に応じた子どもの発達段階の問題
- 社会全体における子どもの放課後の居場所の問題
例えば、内面的成長の変化や勉強面でのつまずき、学校生活での困難、共働き家庭の子どもに必要な放課後の居場所の確保、仕事と家庭の両立などがあります。「小1の壁」と比べると、子ども同士の交友関係の影響も大きいです。
文科省は、「子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」で、9歳以降の小学校高学年の時期に起きることについて、下記のような事柄を紹介しています。
「集団の規則を理解して、集団活動に 主体的に関与したり、遊びなどでは自分たちで決まりを作り、ルールを守るようになる 一方、ギャングエイジとも言われるこの時期は、閉鎖的な子どもの仲間集団が発生し、付和雷同的な行動が見られる」
「付和雷同的」とは、他人の言動にすぐ同調してしまうようなことを意味しています。このように、「小4の壁」には様々な要素が含まれています。
【小4の壁の課題1】学習でつまずく子どもが増える
小4の壁は「学習でのつまずき」が原因となることが多いようです。算数などで抽象的な思考を求められるようになる時期でもあり、これまでの学習の積み重ねの不足が顕在化してくるとも言われています。積み重ねの不足は、計算だけでなく文章の読解力にも大きく影響しています。経済協力開発機構(OECD)が2018年に実施した国際学習到達度調査(PISA)で、日本は「読解力」の成績が落ち込み、2012年世界4位、2015年世界8位、2018年は15位へと落ち込みました。テストで何を問われているのかを理解できない子どもが増えていると言われています。
【小4の壁の課題2】親の仕事と子育ての両立が難しくなる
小4の壁を理由に、仕事を辞める保護者も少なくありません。何が理由なのか?具体的な問題をご説明します。「小4」は学童待機児童数が最も多く居場所がない
厚生労働省発表によると、2020年に学童保育を利用したくても利用できなかった児童数(学童待機児童数)は、1万5995人です。学年別内訳をみると、下記の通りです。- 小学1年生(1982人)
- 小学2年生(1904人)
- 小学3年生(3648人)
- 小学4年生(4632人)
- 小学5年生(2714人)
- 小学6年生(1115人)
学童待機児童数は「小4」が最も多いのです。
子どもが社会的な問題を起こすようになる
学習でのつまずきなどがきっかけとなり、勉強以外のことに興味が出てくることに加え、ギャングエイジとも言われる子どもの発達段階の特徴のひとつである「閉鎖的な子どもの仲間集団が発生し、付和雷同的な行動が見られる」ことが重なり、生活や心身の発達における問題へと発展することがあります。「塾の帰り道に親に無断で買い食いや寄り道をするようになる」このようにエスカレートして、警察のお世話になるまで問題が発展することもあります。
「塾をたまにさぼるようになる」
「友だちとつるんでコンビニで万引きをした」
警視庁の統計によると、少年に占める学識別割合の経年比較によると、2017年と2018年は、それまで万引きする割合が最も大きかった中高生の数を抜き、小学生の数が最も多くなりました。
子どもが自立しているように思えたからといって安心せず、しっかりと見守る必要があるのが「小4の壁」なのです。
1日2回の塾弁+塾の宿題+中学受験……小4は保護者の負担が急増する
中学受験は他人事ではありません。首都圏模試センターの推計によると、2021年は首都圏の小学6年生の約6人に1人が私立や国立の中学を受験していました。
全国的にみても、小学生の10人に1人程度は、中学受験をして私立・国立中学や公立中高一貫校に進学すると言われています。
中学受験こそ、親のサポートなしではできません。学習のつまずきを克服しながら、塾に課せられた課題を子どもひとりの力でこなしていくのは厳しいでしょう。
一般的に、小学生の家庭での勉強時間の目安は学年×20分と言われていますが、学びに熱心な家庭の場合、平日の学習時間は3時間、土日は6~8時間ほどかけている、という子どももいます。
塾で授業がある日は、20~21時まで勉強するため、わずか休憩10分間の時間にお弁当を差し入れる、いわゆる「塾弁」と呼ばれる問題も、中学受験をサポートする保護者の間では有名です。
自分の子どもだけコンビニ弁当ではかわいそうだと、塾のお弁当づくりのために残業を断り仕事を切り上げる保護者も多いのです。
これまでの問題をまとめましょう。
- 学童保育という安全地帯が少ない
- 学習のつまずきをフォローする必要がある
- 塾の宿題をフォローする必要がある
- 塾のためにお弁当をつくる必要がある
- 子どもの生活、交友を見守る必要がある
途中で保護者が仕事との両立を断念し、仕事を辞めることは決して珍しくないのです。
【小4の壁の課題3】友達同士でのトラブルが増えやすくなる
小学4年生になると、仲間意識がより強くなります。グループができ、グループ内独自のルールを守ることや共有する価値感が彼らにとって何よりも重要なことになります。仲間内での結束が強くなる分、うまくいかなかった時のトラブルも大きくなりがちです。低学年と違い、精神的な成長も少しずつ見られるために、いざこざの内容もだんだんと複雑になっていきます。
「◯◯さんが、△△さんのことをこう言ってたよ」と間を介した告げ口や、5人の仲良しグループがふたつに分かれた上に、他方のグループの悪口を別のグループに言い、新しいグループが派生するなど、日々、子どもたちの輪は変化し、変化に対応しきれない子も出てきます。
こうしたトラブルも最終的には落ち着いてくるものですし、悪口も結局は順番に巡り巡って、また元の鞘に収まるように仲良くなるものもよくあることです。いずれにしても、低学年の頃よりも友だち同士のトラブルが増え、その原因もわかりづらくなってくる傾向があります。
子どもが学校でトラブルを起こして、先生から連絡をもらうことが増えるのもこの頃です。
【小4の壁の課題4】子どもが親に反抗するようになる
子ども同士のトラブルが増えるのは、それだけ仲間・グループの意識が高まるからです。この年代ではグループや仲間の影響を受けやすく、その結果として親の言うことを素直に受け取れなくなる面も出てきます。親の言うことにいちいち反抗的になり、ああ言えばこう言う状態で、親の苛立ちがマックスになるのも珍しいことではありません。また、乱暴な言葉づかいや態度がかっこいいと思える年頃でもあり、眉をひそめるようなことを口にします。
「勉強したの?」と聞けば「今からやるとこ」、「早く始めなさいよ」には「うっせーな」なんて偉そうにため息などをつくものですから、そこから親子喧嘩になるのもよくあることです。
こうした小さな親とのもめごとが日常的に起きうるのが「小4」なのです。
小4の壁の実態 どんな問題が起きるのか

小4の壁の実態について、2人のワーキングママに話を聞きました。
【小4の壁の実態】警察から職場に電話がかかってきた
Aさんは、製薬メーカーでリーダー職として働くワーママです。子どもが3歳の時に離婚しましたが、元パートナーや両親との関係性はよく、それぞれのサポートを借りながら、小学校4年生の息子を育てていました。孫には良い教育機会を与えたい、という両親からの教育資金一括贈与を利用した手厚いサポートもあり、保育園時代はインターナショナルスクールが運営する英語型保育園に、小学校に入ってからは民間学童で様々な習い事をし、小学1年生からは進学塾にも通わせてきました。
ある日、進学塾に通っている時間に、警察から職場に電話がかかってきました。コンビニで万引きをしたため保護しているということでした。
頭が真っ白になりながらも警察署に駆けつけ事情を聴くと、この日はひとりで入店して今に至っているものの、これまでにも友だちとお菓子を万引きした疑いがあるということでした。
いったい、どこで間違えたのか?Aさんは日常を振り返りました。些細なことですが、予兆はありました。
例えば、学童で学習するためにワークブック一式を持たせたはずなのに、施設の指導員から「今日はワークブックを持っていなかったので、何もできませんでした」とフィードバックをもらうことが何度かありました。
ピアノ教室に行っているはずなのに、先生から「〇〇くんが来ていないのですがお休みですか?」と電話があったこともありました。子どもに連絡して聞くと、「教室に向かう途中で友だちと会い、立ち話しをしていた」と言われたようです。それも一度だけではありませんでした。
Aさんは、もっと子どもの言い分にごまかされず丁寧に向き合っていたら……と自問自答を繰り返しました。ショックは大きかったため、今気づけて良かったのだ、と思えるようになるまでしばらく時間がかかったそうです。
【小4の壁の実態】子どもと向き合うために1年間休職した

Bさんは、国際線でも勤務をしていたため、出張のために家を空ける日が珍しくありませんでした。夫も出張が多かったため、息子が1歳半のときからお世話になっている馴染みのベビーシッターがおり、当時は自宅に泊まってもらうことも含めて子育てのサポートを依頼し、なんとかやりくりしていました。
仕事が休めたときは意識的に子どもと過ごす時間を作り、子どもの観たい映画や展覧会へ行ったり、年に1回は必ず家族旅行に行ったりしていました。
最初に問題が起きたのは、Bさんの息子が小学3年生だったときです。学童保育の指導員から「言動が少し暴力的になっている」とやんわり指摘されました。
しばらくすると、馴染みのベビーシッターから「担当から外して欲しい」と相談を受けました。Bさんの息子がまったく言うことを聞かなくなったというのです。
そしてある時、学童施設から、「年下の女の子のお腹を蹴った」と報告を受けました。Bさんは驚き、息子に深刻な問題が起きていることを重く認識するようになりました。
Bさんの息子は、保育園時代から周りの子どもに頼りにされるお兄ちゃん的な存在でした。自分から進んで年下の面倒を見るタイプだったため、学童で起きた問題は信じられない出来事でした。Bさんは会社と相談して泊りの仕事を止め、息子との時間をつくりました。しかし、改善の兆しは見えません。
専門家にも相談しましたが、具体的な原因や問題があるというよりは、子どもの発達段階のひとつで「大人」と「子ども」の狭間で自立のためにもがいているため、長い目で見守る必要がある、という話でした。また、母親の精神的な心のゆとりは、子どもにも影響がある、ともアドバイスを受けました。
Bさんは、中途半端な立場で仕事を続けながらストレスを溜めている自分自身の言動が、息子に悪い影響を与えているのだと考えました。そして、会社に休職を申込み、完全に仕事から離れることにしました。
約1年間、何か特別なことをしたわけではありませんでした。
朝になったら息子を起こし、朝ごはんを食べさせ、学校に送りだし、家事をして、16時前に帰ってくる息子を迎え、軽食を食べさせて、塾や習い事へ行かせて、20時前後に帰ってきたら一緒に夕食を食べ、22時には就寝させる。この繰り返しです。
するとある時、Bさんの息子がこう言いました。
「お母さん、もうぼくは大丈夫だから、仕事してもいいよ」
それからは、中学受験のことや、進学や将来についてのこと、放課後の過ごし方など、いろいろなことを親子で話し合いました。民間学童やベビーシッターの利用も、お試し利用から少しずつ始め、少しずつBさんの職場復帰を進めていきました。
民間学童は、息子が問題を起こした施設にもう一度利用をお願いしました。Bさんの息子は、無事に頼もしいお兄ちゃんへと戻っていったそうです。
「1年生の勉強も見てくれて、本当に助かりました」
「1~2年生の友だちに人生ゲームを教えてくれて、一緒に遊んでくれました」
学童からの連絡ノートには、毎日感謝のコメントが綴られるようになりました。かつて施設で一番の問題児だったBさんの息子は、一番頼もしいお兄ちゃんになり、無事に卒業することになりました。Bさんはこう振り返ります。
「あんな苦しい時期はもう二度と過ごしたくありませんが、それでも息子が大人になるために必要な成長のプロセスだったのだと思っています」
厚労省も「小4の壁」を問題視
2008年6月19日付の社会保障国民会議中間報告では、小4の壁について下記のような指摘がありました。- 小学3年生までしか利用できないクラブが多い
- 放課後児童クラブ(厚労省)と放課後子ども教室(文科省)の連携が不十分
- 施策が実際に利用される場面において使いやすいものとなっておらず、利用者にとって 各種施策の推進による改善が実感できない状況となっている」
改善は進んでいる?
2015年4月から施行された「子ども・子育て支援新制度」では、公設学童の対象児童が「おおむね10歳未満」から「小学6年生まで」と変更され、明確化されました。学童待機児童数は年々減少しています。また、毎年、厚労省は、毎年各自治体別の取り組み状況として、小3以上の学童保育の実施の有無の確認・報告をしています。改善が進んでいることは間違いないでしょう。
小4の壁で退職するメリット・デメリット 良かったことや後悔したことは?

小4の壁で退職した際の「メリット」「デメリット」を紹介します。
【メリット】子どもの安全・安心を見守ることができる
「ひとりで、自宅に帰るのが怖い」小学4年生だった娘の一言で退職を決意したCさんの話を紹介します。
Cさんの娘は、小学1年生の下校で不審者に後をつけられた経験があったため、退職に迷いはありませんでした。
マンションのエレベーターで乗り合わせた子どもの後ろをつけて、自宅に入る際に押し入る、この類の事件は後を絶ちません。どんなにセキュリティの高いマンションに住んでも、乗り合わせや家に入る瞬間など、盲点は必ずあります。子どもの安全・安心に勝るものはありません。娘がひとりで自宅に帰り、安心して過ごせるようになるまではしっかりと見守っていく、とCさんは話します。
【メリット】希望の中学に合格!子どもとの絆が深まる
Dさんは、息子が小学5年生になったタイミングで、中学受験のために退職を決意しました。進学塾から持ち帰ってきた宿題の量が、小学4年生のときの約2倍になっていたのです。このまま息子ひとりで頑張らせるわけにはいけない、と考えました。息子は夏休みをほとんど塾で過ごしていたため、Dさんは毎日2回、朝晩と「塾弁」を差し入れに行きました。1日勉強をしている子どものために、せめてこれくらいはしてあげたいという思いからでした。もし働き続けていたら、絶対にできなかったことです。
宿題のフォローは、国語や社会などの問題はDさんが、算数や理科など理系問題は夫が、と、家族分業でなんとか取り組んでいました。
「合格発表は忘れられません!家族みんなで嬉し泣きです」
【デメリット】世帯収入が減少した
娘の中学受験のために退職をしたEさんは、あまりにも高い塾代に、仕事を辞めたことを後悔しています。有名進学塾だけでは成績が伸び悩み、家庭でもうまくフォローができないため、系列の個別学習塾にも通い始めたのが誤算でした。
毎月の講習費や、夏休みの夏期講習、個別学習塾も合わせると、年間150万円以上は払っています。せっかく仕事を辞めたものの、Eさんがサポートできることは多くありませんでした。かといって、中学受験中に自分が仕事に復帰するのはどうなのか……とも。悶々とした日々を過ごしています。
【デメリット】心にゆとりがなくなった
「なんで分かんないの!昨日もやったでしょ!」Fさんは、ついつい子どもにきつく当たってしまう自分に反省する毎日を送っています。
子どもが小学3年生のときに、子どもが学習の遅れを指摘されたこともあり、家族で相談をして仕事を辞めることになりました。Fさん自身は仕事を続けたいと思っていましたが、「お前がもっと面倒を観てあげたらいいじゃないか」と、パートナーにも両親にも言われ、辞めざるを得ませんでした。
「どうやったら子どもに算数の概念を理解してもらえるのでしょうか?子どもに勉強を教えるのは本当に難しい」
小4の壁への親ができる対策方法

小4の壁の対策方法を5つご紹介します。いつ始めても、早すぎることも遅すぎることもありません。じっくりとお子様と一緒に取り組んでみましょう。
【小4の壁の対策】①復習と反復学習で乗り越えよう
小4の壁の一番の原因は「学習のつまずき」です。つまずきには復習と反復学習が重要です。とくに算数は積み上げ式の教科ですから、どこかでつまずくと、わからないことがどんどん増えてしまいます。
まずは、どこまで理解をしているのか?を確認しましょう。
つまずいた箇所が分かったら、理解を定着させるまで、類似問題や関連問題に繰り返し取り組みましょう。
【小4の壁の対策】②読書と対話で日本語力を育もう
今からすぐにでもおすすめしたいのは、家庭でたくさんの本を読むことです。子どもの年齢は問いません。本には書かれていない主人公の気持ちを探ったり、物語の続きを一緒に考えたりして、親子で対話をしながら「論理的思考力」を地道に育みましょう。どんなジャンルの勉強をするにも、「小4の壁」を乗り越えるためにも役立つ、一番の土台となるでしょう。
【小4の壁の対策】③子どものやる気と自信を高めよう
子どもが自信を失っていたり、やる気がないのにイヤイヤ取り組んでいたら、まったく効果はなく時間の無駄になっていると思ってください。そんな子どものやる気と自信を高めるのは、保護者の声掛けです。
「こんなに今日も勉強したの。頑張ったね!」
「この問題、解けるようになったんだ。すごいね!」
ポイントは、子どもが元々持っていた能力ではなく、頑張った努力を肯定するよう言葉をかけることです。
子どもの性格によっては、声掛けをネガティブに捉える子もいます。その際は、子どもの抱えている不安や悩みに共感をしてから、子どもの努力をしっかりと見守っていることを伝え、子どもの努力を誉めて、自信をつけてあげてください。
【小4の壁の対策】④放課後の居場所づくりをしよう
1.中学受験をする場合、小4からはとても忙しくなります。塾がない日は宿題をこなすことに大忙しです。2.中学受験をしない場合は、習い事と併用して、公設学童や民間学童で過ごすことになるでしょう。
では、中学受験しない場合で、公設学童や民間学童の利用が期待できないケースについてはどうでしょうか。先に考えたいのは、小学4~6年生の3年間を、子どもにどう過ごして欲しいかです。
子どもが熱中できるスポーツや文化活動などに関する地域のサークルやクラブ、習い事教室など、何かひとつでも子どもが好きで通いたいと思える場所を、家庭以外につくりましょう。
毎日は通えなくても、好きなものがあれば良いでしょう。それ以外の日は練習や準備をして前向きに過ごすことで、ほかの問題が発生することを防げるはずです。
【小4の壁の対策】⑤教科別に子どもの学習のサポートをする
算数
算数は小学校4年生から一気に難しくなり、成績の差が顕著になっていきます。まず基本となる四則計算(たし算・ひき算・かけ算・わり算)をしっかり身に着けさせましょう。算数に限りませんが、1年生から積み上げてきた学習が土台になります。大きくつまずく前に、簡単な掛け算や割り算など戻れるところまで戻って、高学年の算数に無理なく進めるように、基礎をつけるようにしましょう。やる気が失せないように「できるところから」始めるのがコツです。
国語
国語は漢字と読解力のふたつに分けて考えましょう。漢字は2年生〜3年生で覚えたものが定着していない場合、過去の漢字ドリルなどに戻って練習するようにしましょう。読解力は短期間では身につきません。しかし高学年になると「読む力」が国語以外の勉強でも影響してきます。算数の文章題も読解力がなくては、そもそも答えを導き出せません。本を読む機会を作るだけでなく、短い文章を呼んで問いに答えるようなドリルなどを使ってトレーニングを続けましょう。
理科・社会
小学校3年生から「理科」「社会」と分かれての学習がスタートしています。小学校時代はあまり重視されない傾向がありますが、中学・高校を視野に入れると、実は小学校時代に学ぶ理科と社会は非常に重要です。高校で、物理や日本史、地理で苦労する原因は、さかのぼって小学校時代の「理科・社会嫌い」が要因となっているケースはよくあります。
苦手意識を持ってしまうと後々まで影響するので、理科なら実験や観察、社会なら工場見学や調べ学習など、子どもが興味を持ちそうな領域から入るとよいでしょう。
理科も社会も、動画やイラストでの解説がわかりやすいので、図鑑やマンガで学んだり、面白い理科実験や社会のニュース解説など動画を選んで視聴させてみるのも良い方法です。
【小4の壁の対策】⑥子どもの考えを尊重する
自立心が芽生える頃でもあるので、なるべく本人の意思を尊重し、何かを決める前に「あなたの考えはどう?」と聞いてみましょう。その答えが、たとえ親が思っていることと違ったとしても、頭ごなしに否定するのではなく、「そうなんだ」「そういう考えもあるね」と共感を示すことが大切です。小学校4年生の子どもたちは、プライドを傷つけられることに敏感、失敗を恐れるようになります。しかし、この時期こそ、さまざまなことに挑戦し、失敗と成功を繰り返して経験値を上げていきたいですね。
失敗をして1番傷ついていたり、ガッカリしたりしているのは子ども自身です。親は子どもに寄り添いながら、前向きな気持ちになっていけるよう導いていきましょう。
【小4の壁の対策】ギャングエイジへの対応
保護者はあまり感情的にならないことが大切です。ムキにならないということがポイントです。小学3~4年生の子どもに厳しく対応しても、親の思いは伝わりません。最低限必要なことを伝え、その後はその話題に触れることなく、切り替えていくこと、そして、長い目で見ることことが必要となります。
子どもの行動には意味があり、そこに学びがあるのだということを保護者が理解しておくことで、ゆとりをもったコミュニケーションを取ることができるでしょう。
小4以降の子どもも対象のおすすめ民間学童・習い事
ここからは、編集部がおすすめする民間学童・小学4年生におすすめの習い事を紹介します。スマイルゼミ

スマイルゼミには、お子さまのやる気を引き出す工夫がいくつも用意されています。例えば、お子さまの学習状況に応じた個別のアドバイス。お子さまのためだけの適切なアドバイスにより、苦手な部分は改善しやすく、できた部分はより達成感を感じやすくなるでしょう。
無学年式の学びができるのも、スマイルゼミの強みの1つです。どの学年の教材も自由なペースで好きなだけ学べるので、学力を無限大に鍛えられます。
子どもの家庭学習の教材として従来のドリルやテキスト型の通信教育から、オンライン学習に主流が移り変わりつつあります。今回はスマイルゼミについて、リアルな口コミ・評価をご紹介すると共に、口コミから考察するメリット・デメリットやコース・料金まで徹底解説いたします。


2026/01/02

東進オンライン学校

日本一の東大現役合格実績を持つ「東進」と、シェアNo.1の予習シリーズで有名な四谷大塚がタッグを組むことで、実力講師陣による楽しくてわかりやすい授業を実現。子どもの「わかった!」が引き出されることで、学ぶ楽しさを味わうことができ、学習の定着化につながります。
日々の授業以外にも、確認テストや月例テストで学習を振り返るため、わからないところがそのままになりません。基礎学力の定着を目指す方は標準講座が、中学・高校につながる応用力を身につけたい方は演習充実講座がおすすめです。
東進オンライン学校 小学部・中学部は、授業+テスト(理解+確認)の繰り返しで学習習慣をつけ、学力アップへとつなげるオンライン塾です。今回は東進オンライン学校の運営ご担当者に、東進オンライン学校 小学部・中学部カリキュラムの特徴やこだわり、具体的なサービス内容についてくわしくお話を伺いました。


2025/11/17

キッズ・デュオ
学童保育と習い事のいいとこどりをしているのが、キッズ・デュオです。オールイングリッシュ環境で過ごす学童保育なので、自然と英語が身につくでしょう。長時間英語のシャワーを浴びることで、無理なく習得できます。英語の授業では経験できないようなバラエティに富んだ200種類以上のプログラムが用意されており、楽しみながら英会話スキルを身につけることが可能です。豊富なテーマに触れて熱中することで、英語力の飛躍的な成長につながるでしょう。
送迎専用バスがあり、月~金の最大20時30分まで預けられるので、共働き世帯でも安心して預けられます。長期休暇中は、午前中から預けることも可能です。全国210教室以上が展開されているので、興味のある方は公式ホームページからお近くの教室を探してみてください。
ウィズダムアカデミー

「第三の家」をコンセプトに、1人1人がゆったりとくつろいで過ごせるスペースで、時代の先端を行く人気の習いごとを多数取り揃え、学びと遊びをバランスよく採り入れた豊かな時間を過ごします。
多種類の習いごとが1箇所で受けられるのが特徴で、一部の個人レッスンを除き、どの習いごとも1回ずつは無料体験できます。送り迎えが大変な方には、学童利用の追加で前後のお預かりと送迎付き添いサービスも利用可能。
ラボ・パーティ

全国各地に教室がある人気のスクールで、特徴は英語を「語学」として机上だけで学ぶのではなく、英語劇や国際交流などを通して複合的に学べる点です。
週に1回の教室は「パーティ」と呼ばれ、自宅で聞いてきたCDをベースに、仲間といっしょに劇活動を楽しみます。歌やダンスをはじめ,物語をみんなでごっこ遊び、時には工作やキャンプなどもあり、英語が苦手な子でも構えずに楽しみながら英語でのコミュニケーションを身につけます。兄弟姉妹で同じクラスに参加することもでき、異年齢を混ぜて学び合うことで、協調性や思いやりを育んでいきます。
小4の壁に関するよくある質問
小4の壁に関して、よくある質問をふたつピックアップしました。4年生の学習の特徴は?
小学校4年生は、すべての科目において、一気に勉強が難しくなります。もちろん低学年の頃から地道に基礎的な学力を積み上げていればいいのですが、実際にはなかなかそうはいかないもの。特に算数は、分数やおおよその数(四捨五入)、また作図や面積の問題も出てくるので、ここでつまずく子どもは少なくありません。
また、応用力や、自分の考えをまとめる力、それを表現する力なども求められます。ただドリルを繰り返していれば覚えられることではない「学習」が増えてくるのも特徴のひとつです。
小学4年生の発達の特徴は?
社会性と自立心が大きく育つのが小学4年生です。仲間との関係構築がより重要になり、小さな社会の中で自分の立ち位置を決めるのに模索する時期です。
また、自分でできる、親の助けはいらないと思い、子ども扱いをされるのを嫌がります。おとなが使うような言葉遣いや、少々乱暴な言い方も「一人前」になったような気持ちでよく使うようになります。
発達の差が広がる特徴もあるので、わが子が他の子と比べて幼いと感じたり、勉強の差が気になったり、あるいは体格や身長が気になるかもしれません。しかし長い目でみれば、きちんと成長しているわけですから、親があまり神経質にならないようにしましょう。
小4の壁まとめ
小4は、とかく親子間の軋轢も多く、さらに子どもの言葉や行動に不安を感じることも多々ある時期です。共働き家庭にとっては学童の終了と共に、留守番や勉強のフォローなど新たな課題も生じます。いずれにしても、小4の壁はやがて必ず乗り越えられるものです。
そのために親としてできる対策は行い、子どもに寄り添いながら一方で自立を過度に信用せずにしっかりと目を離さないでいることが大事です。「振り返ってみると大変だったなぁ、でもあの時期があったからこそ成長したんだな」と思える時がくると、まず保護者自身が前向きに「小4の壁」を捉えていきたいですね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小1の壁が発生する原因とは?入学前の対策と入学後の対応を解説
まもなく入学を迎える多くのお父さま・お母さまは『小1の壁』という言葉を聞いたことがあるかと思います。幼稚園や保育園の時とは違い、小学校入学後の方が育児と仕事の両立が難しくなったという声...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
(教育トピック)小一の壁|退職?転職?朝はどうする?7つの壁と対策
「小1の壁」はご存知ですか?小学校入学と共に、働くお母さん・お父さんが新たにぶつかる壁。今回の教育トピックでは、時には転職や退職を余儀なくされることもある小1の壁について詳しく解説。先...
2025.05.30|大橋礼
-
小学4年生におすすめの習い事16選 !月謝は?
「小4の壁」と言われるように、個人の能力や体力の差が大きく見えてくることで、精神面や学習面などで壁に当たることもある小学4年生。中学受験を考えている家庭にとっては学習塾や進学塾と習い事...
2025.11.17|コエテコ教育コラム
-
4歳の勉強おすすめ10選!教え方やできることも徹底解説
保育園や幼稚園の年少にあたる4歳ごろになると、周りに読み書きができる子が増えてきて「あれ?うちの子もそろそろ教えなきゃダメ?」と心配になることもあります。同じクラスでも月齢差や個人差が...
2025.12.26|コエテコ教育コラム
-
英語長文が苦手な人向けの勉強法3選!対策を徹底解説
英語の試験のなかで、長文読解が苦手な人は少なくありません。英語長文を克服したいなら、効率的な勉強法を覚えておきたいですね。この記事では、英語長文が苦手な人向けの勉強法や対策を解説します。
2025.12.19|コエテコ byGMO 英語編集部


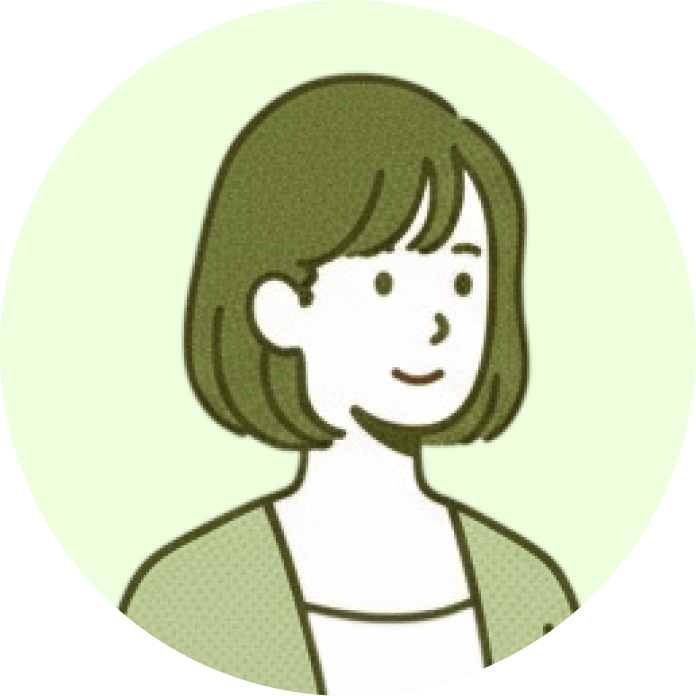
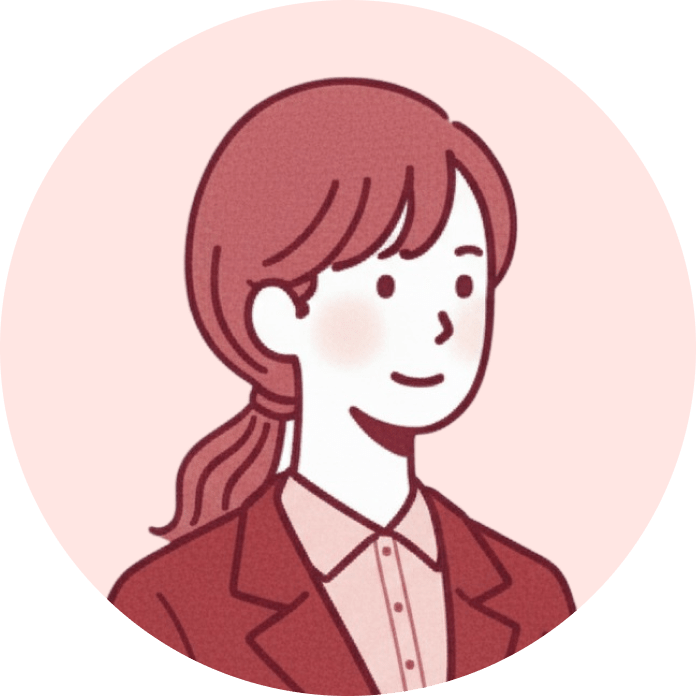
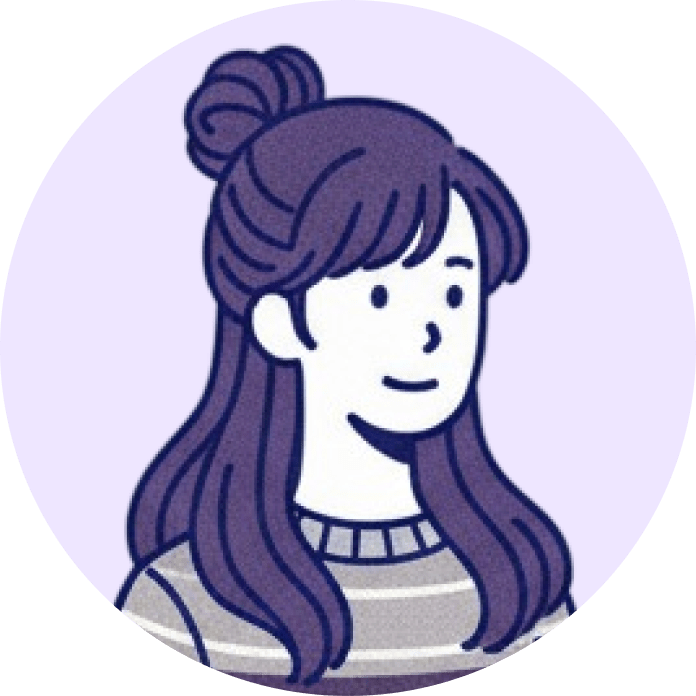

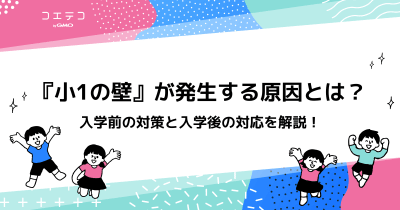
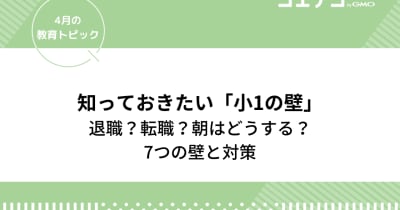
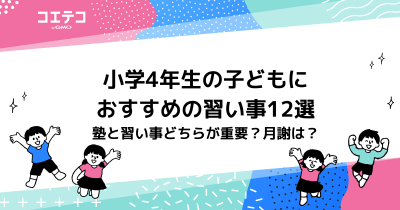
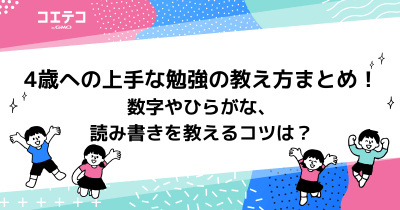
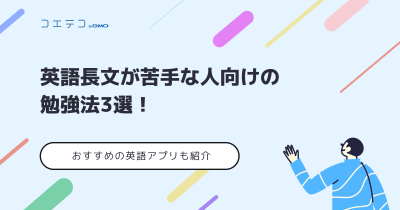
「安易に子どもに自立させてはいけない、小さな嘘を見逃してはいけない、子どもが抱えているストレスや内なる課題にしっかりと向かっていきたい」