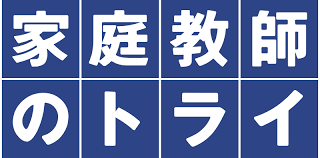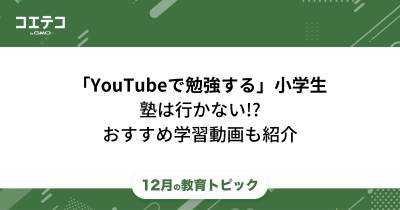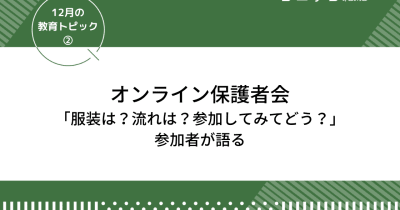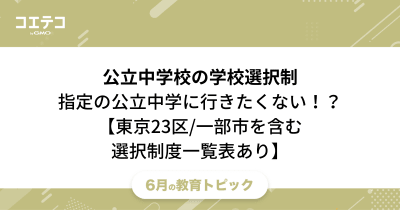仮想空間の学校に通う!?東京都のバーチャル・ラーニング・プラットフォーム|メタバース学校や塾という新しい選択肢
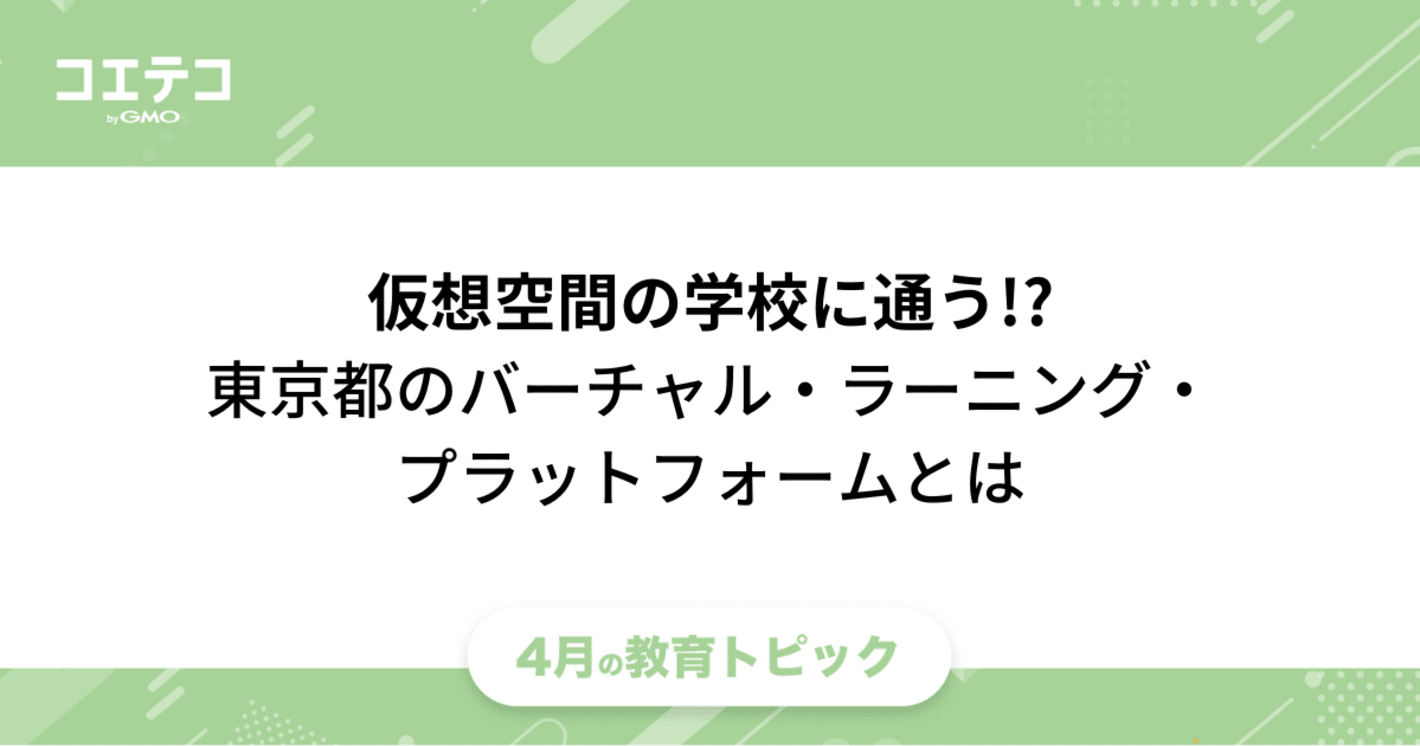
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
東京都教育委員会の仮想空間を活用した新たな児童・生徒支援を開始します 「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」について(12月)のページです。

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2022/release20221202_01.html >
インターネット上の仮想空間で、自分の分身であるアバターを操作しながら、たとえば他のアバターと話したり、授業に参加したりできるのが「バーチャル学校」「バーチャル塾」あるいは「メタバースの学校」と言われるものです。
今回の教育トピックでは「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」のほか、自治体が行っているメタバースによる支援プラットフォーム、仮想空間キャンパスを持つ民間のオンライン高校や小学生から受講できるオンライン塾、フリースクールなどをご紹介します。
さまざまな理由から学校に行けない・行かない子どもたちの新しい選択肢のひとつとして、また最先端のIT学習環境として、保護者もぜひ知っておきましょう!
「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」(東京都教育委員会)とは

東京都教育委員会が仮想空間上に「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」を用意し、区市町村に提供する取り組みがスタートしたのは2022年。2023年度は、順次、バーチャル・ラーニング・プラットフォームを広げていくとしています。
この仮想空間(メタバース)では、インターネット上の仮想スペースに自分の身代わり(アバター)を作ることで、仮想空間を歩いたり、他のアバターと話したりできるようになります。
仮想空間には友人と交流できる交流スペースやオンライン支援員に相談できる相談スペース、授業スペースもあり、会議ツールを使用し授業を受けることも可能です。

アバターなら自分の顔を映さずに、分身として自由に仮想空間を動けます。人と交わることが苦手でも、「自分が実際にそこに行くわけではない」仮想空間なら、無理なく外と交流できるメリットがあります。また日本語を習得していないケースなどにも対応しやすいとされています。
バーチャル学校は「支援が必要な子どもたちにとっての新しい学びの場所」になると期待されています。
バーチャル学校のメリットとデメリット

バーチャル(メタバース)学校のメリット
- 学校になじめない「登校しぶり」「不登校」の子どもが人との接点を持ち学習ができる
- 病気などで学校に通えない子どももバーチャル学校で仲間や先生との時間を共有できる
- 遠隔地や僻地での利用
- 学習などの記録が容易である
仮想空間の学校における一番のメリットは、実際に学校に行かなくても「通っているような」感覚で、いろいろな人と交流ができる点です。
なかなか学校になじめないお子さまでも、あるいは病気や僻地で通学が難しい状況でも、アバターが自分の代わりに自由に歩き回り、話をしたり授業を受けたりもできます。また、学習等の記録が自動的にでき、それらを分析し、さまざまに活用できる点もメリットと言えるでしょう。
バーチャル(メタバース)学校のデメリット
- お金がかかる
- あくまで「アバター」を通しての交流であり「リアルな体験」との違いはある
- 学校で学ぶレベルの学習量の確保が難しい
まずバーチャルな学校やスペースを作るのに、そもそもお金がかかります。また基本的には義務教育の一環ではありませんから、自治体の支援などではない場合には利用者はそれなりの負担が必要です。
たとえば小学校の代わりになるか?となると、すべての授業内容をカバーするというよりも、学校に行けるようになるまで「隔離された気持ちや孤立感を持たないように」バーチャルな空間で仲間やスタッフ・先生などと交流することがメインとなるため、同等の勉強量を確保するのは現実的には難しい面があるようです。
社会へつながるアプローチの手段として、バーチャル学校は大きな意味を持ちます。
しかし同時に「本当の意味でのリアルな体験」とは違う部分があるのも事実です。その「差」を少なくとも保護者や支援者が理解し、子どもたちへどう対応するのが良いのかを常に見守っていく必要はあるでしょう。
ちなみに、義務教育が終わってからの高校・大学レベルになると、バーチャルキャンパスはITスキルや専門的なジャンルを学んだり、効率的に時間を活用して学べるといった利点もあります。
バーチャルな学習機関の現状について

昨今はバーチャル塾も増えつつあり、こちらは学習を主目的としています。
オンラインによる学習に加えて、バーチャルな教室に自分のアバターを存在させることで、リアルタイムのチャットで友だちと話したり、先生と気軽に「立ち話」をする感覚で質問できたりします。何らかの理由で学校に登校できない子どもたちにとって、しっかり学習面をカバーできるため、上手に利用することで学習の遅れを取り戻すことも可能でしょう。

またフリースクールとして運営される民間のバーチャル学校は、所属する小学校の規定などにそった上で「出席」とみなされるケースもあります。フリースクールの形態もさまざまで、お子さまの資質に合う・合わないがありますから一概には言えませんが、ひとつの選択肢として検討してみるといいかもしれません。
高校レベルでは仮想空間やオンライン授業を積極的に取り入れている教育機関もあります。ITスキルを身につけ「いつでもどこでも」学べる環境を活かし効率的な学びを求めて、自ら選んでインターネットの教育機関を選ぶケースも多くあります。
年齢や個々のバックグラウンドによって違いますが、オンライン授業・メタバースでの学校・インターネットスクール等々、学ぶ場が多様化していることは、決して悪いことではないのではないでしょうか。
バーチャル空間の「教室」「学校」

三重県教育委員会 不登校の子どもたちに向けたメタバース空間での交流

三重県教育委員会はネット上の仮想空間(メタバース)を活用し、不登校の中高生や高校を中途退学した人などを対象に、社会につながる「場」を始めています。
この「場」には、勉強のスペースや、動画を一緒に見たり、おしゃべりを楽しめるスペースが設けられているそう。自分の分身であるアバターを操作しながら、ほかの参加者や、サポーターである大学生などと交流ができます。
熊本市 フレンドリーオンライン「バーチャル教室」

熊本市教育委員会は、すららネット、 Inspire High、NTT コミュニケーションズと共同で、学校に登校できない子どもたちの勉強や自立をオンライン上でサポートする「フレンドリーオンライン」を行っています。
2023年1月からは、フレンドリーオンラインに、新たな取り組みとして「バーチャル教室」を設置。アバターを操作し、仮想的な教室で、チャットや音声ツールなどでコミュニケーションがとれます。
※この取り組みは、文部科学省「令和4年度 次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの 利活用推進事業(実証地域)」の一環です。
N校「インターネット上のスクール先駆者」新しい高校のカタチ

N校は、KADOKAWA・ドワンゴが創るネットと通信制高校の制度を活用したネットの高校です。高校資格が取得でき、大学合格実績も豊富で、生徒数は実に24,000人以上(2022年12月時点)となっています。

バーチャル授業では自宅にいながらにして、非同期コミュニケーションにより、同じ授業を受けた仲間のクラスメイトが登場。バーチャルでも、ノンバーバルコミュニケーション(言葉を使わず、人の五感を使ったコミュニケーション、一例として表情や声の調子で相手の意思を感じ取ることが挙げられる)がとれる最先端の学習環境が整っています。
「出席扱い」の対応可能なバーチャル・オンラインフリースクール

SOZOWスクール

SOZOWは小学校4年生から中学生を対象としたフリースクールです。
AI教材を利用して勉強を進めるほか、自習室ややりたいテーマに合わせたバーチャルクラスに入り、アバターをコントロールしながら、さまざまな体験ができます。ライブイベントなどもあり、盛りだくさんの内容。いくつかの条件や所属する小学校との話し合いは必要ですが、出席認定を得ることも可能です。
オンラインフリースクールWIALIS

主に不登校の中学生を対象としています。アバターを使って部活動の参加もでき、バーチャルキャンパスは「玄関ラウンジ」「スタッフルーム」「面談・雑談ルーム」「動画視聴ホール」「カフェテリア」「自習室」「図書室」「イベント広場」と実にさまざまなスペースが用意されており、生徒はそれぞれのスケジュールを立てて、学習やフィールドワークにも携われるようになっています。
こちらも学校との連携が必要ですが、状況に応じて出席認定をとることが可能とされています。
バーチャル塾「自宅でガッチリ勉強できる!」

学研ON AIR(学研オンエア)

「学研」によるオンライン学習については、コエテコでも過去に取材させていただいています。
この「学研ON AIR」もメタバース空間のキャンパスをスタート!
これまで通りの充実したオンライン学習に加え、学研オンエアバーチャル校ではアバターを使って同じ空間にいる友だちや先生と話をしたり相談したりできます。他の習い事などで塾に行く時間がとれない場合や、通塾時間をなくし効率的に学習したい方、しっかり勉強を学びたい人に向いています。
創造学園エディックオンライン校

自宅にいながらにして、さながら塾にいるような感覚で学習できるのが、創造学園エディックオンラインです。
バーチャルのエディックオンライン校では、アバターが職員室に行けば先生に質問することができます。コミュニティルームでは、他のアバターとディスカッションができ、クラスルームに入ると自動的にzoomが起動するなど、バーチャル塾内を行き来しながら自分なりの学習ペースで勉強が行なえます。
「バーチャルなサードプレイス」外へとつながる“きっかけ”になることに期待

バーチャルな学校や勉強について調べていると「バーチャル転校生」なるものが出てきました。バーチャル転校生は、停滞した授業に刺激を与えるような「新たなアイデアや意見」を出してくれる仮想空間上の転校生です。たとえば、みんなが同じ意見しか出てこないとき、バーチャル転校生は「わたしは違う考えです!」と、みんなが「おお?」となるような発言をしてくれるそう。
ちょっと想像がしづらいのですが、人と違うことを回避する傾向がある日本人にとって、カンフル剤のように「ビシっ」とモノ言う転校生の存在で、授業の雰囲気がガラリと変わることもありえるかも?……などと想像をふくらませると、仮想空間というのはなかなか興味深いですね。
いずれにしても、学校になじめみづらい、教育を受ける環境が整っていない、さまざまな条件を抱えた子どもたちがバーチャルな学校で少しでも「誰かと出会い、社会になじむ感覚」を育て、それが外へとつながる一歩になればと思います。
仮想空間における学校がすべての問題を解決してくれるわけではありません。しかし、学校に行けない子どもたちのこころが少しでも新たな興味や意欲に結びつく「きっかけ」になるのであれば、もっともっと活用される場面が増えるといいかなと思います。さらには、高校大学では、授業やカリキュラムの幅を広げる新しいツールとして、活用していけるといいですね!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
YouTubeで勉強する小学生!おすすめ勉強動画や面白くてためになる解説
今、YouTubeで勉強する子どもたちが増えています。「ねぇ、これ見て!すっごくわかりやすいんだよ!」今回の教育トピックでは、YouTubeで勉強する小学生の実態に迫り、人気がある小学...
2026.01.05|大橋礼
-
オンライン保護者会「服装は?流れは?参加してみてどう?」参加者が語る|12月の教育トピック②
オンライン保護者会に参加したことはありますか? 学校はもちろんですが、塾の保護者向け説明会や、受験関連では学校説明会などもオンラインで開催されたところも多いですね。これからはコロナ禍...
2025.09.10|大橋礼
-
グローバルサイエンスキャンパス(GSC)とは?代表例と応募方法を解説
科学が好きな高校生ならグローバルサイエンスキャンパス(GSC)という言葉を耳にしたこともあるでしょう。大学が開催しているグローバルサイエンスキャンパスは、大学内で研究を行ったり学会で発...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
私立中高一貫校とは?中高一貫には種類がある!メリット・デメリットを解説
中高一貫校は、その名前のとおり「中学と高校」が一体化した学校です。そして、中高一貫校の一種である大学の附属校と、高校までの一貫校では、いろいろと違う点があります。今回の教育トピックでは...
2025.09.10|大橋礼
-
公立中学校の学校選択制【東京23区/一部市を含む選択制度一覧表あり】|指定の公立中学に行きたくない時の対処法も解説!
公立中学校は公立小学校と同様に「学区域」が決められており、進学する中学も定められています。しかし、最近では学区域外であっても自由に学校を選べる「学校選択制」も広まっています。 学...
2025.05.30|大橋礼