私立中高一貫校とは?中高一貫には種類がある!メリット・デメリットを解説
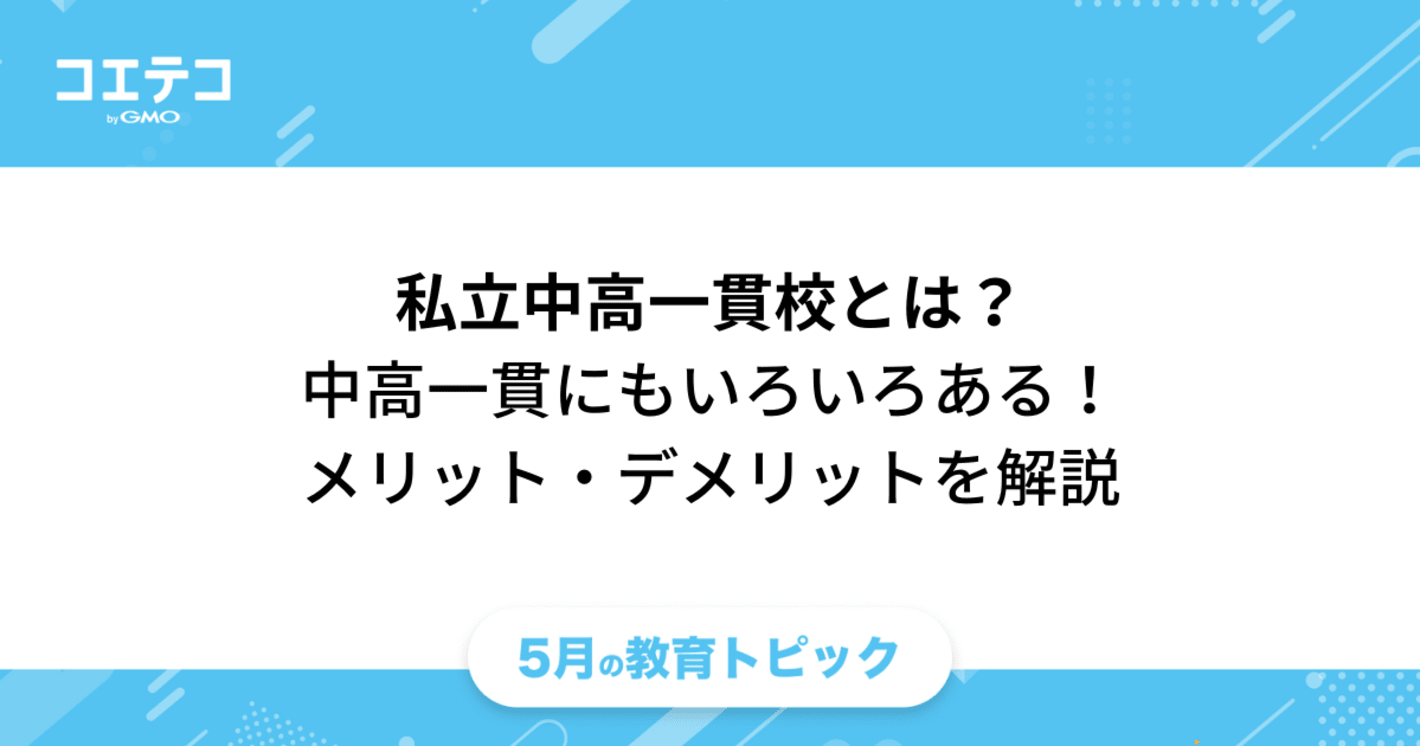
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
また、中高一貫校の一種である大学の附属校と、高校までの一貫校では、いろいろと違う点があります。
今回の教育トピックでは、中学受験を含め、これからの進路について考える中、
- 中高一貫校って?
- 大学付属と何が違うの?
中高一貫校とは

中高一貫校は、中学校と高等学校が一体化した、6年間を通じて通うことを前提とした学校です。中学から高校へは特に大きな問題がなければ進学できるのが一般的です。
中高一貫校は大きく「国公立」と「私立」に分けられます。
公立の中高一貫校は数が少なく、独自の試験により難易度も高い傾向があります。入学はなかなか高いハードルですが、私立の中高一貫校と比べて学費がかなり安く抑えられるため人気もあります。

国公立の中高一貫校の人気は高いが、そもそも数が少ない…
一方で私立は、やはり学費は高くなる傾向があります。学費についてはこの記事の後半で取り上げますが、無償化であっても私立だからこその出費もあります。「義務教育のようにお金がかからない」わけではありません。
この記事では、私立の中高一貫校にしぼって解説していきます。
私立中高一貫校の種類

私立中高一貫校にも、いくつか種類があります。
- 大学付属系
- 大学連携系
- 独立した進学校系
また、それぞれに細かく分類はありますが、ここではまず上の3つについて取り上げます。
①中高一貫校「大学附属系」

「大学附属系」中高一貫校は、系列の大学へ進学できる、いわゆる「附属」です。
ちなみに附属といっても、一定の成績であればほぼ100%大学に入れるところもあれば、そうでないところもあります。
成績順に希望学部が決まる附属校は多いですから、人気の学部に入るためには、やはり相応の成績が必要となります。附属の大学には入れるけれど、思っていた学部に入れない……というのも珍しいことではありません。
また、在籍生徒数の半数程度しか大学付属に試験なしでは入れない、規定に達していないと内部進学は認められないといった学校もあります。
なお、幼稚園や小学校から大学まである附属は「中高のみの一貫校」ではありませんが、大きくみると「大学附属の中高一貫校」と捉えられています。
大学付属の中高一貫校
大学付属の中高一貫校も、いろいろあります。(1)大半が付属大学へ進学するタイプ
卒業生の多くが、系列大学に推薦で進学します。
「附属進学」タイプは、遅刻や欠席数が多い、成績が非常に悪いといった大きなマイナス要素がない限りは、内部進学ができ、在籍している生徒の多くがそのまま附属の大学へと進みます。
評定に届かない場合には、内部進学ではないけれど、一般入試よりは優遇された推薦制度で進学できるケースもあります。
(2)附属校+進学校タイプ
「附属校+進学校タイプ」は、外部進学にも力を入れており、同時に付属大学への進路も開いているタイプの中高一貫校です。一定の成績であれば付属大学への推薦を保持しつつ、国立など外部受験も可能な学校は、人気が高いと言われています。
(3)ほぼ進学校タイプ
そもそも附属大学への進学希望が少なく、学校も外部受験のサポートを積極的に行っているのが、ほぼ進学校タイプの中高一貫校です。附属校もいろいろなレベルがありますが、系列の大学よりも難易度の高い大学への進学率を誇る附属の中高一貫校もあります。

大学付属で受験がないから楽とは限らない…。
大学によっては「附属・係属・系列」など多種類
日大がわかりやすい例ですが、日大鶴が丘(にっつる)、日大櫻丘(にっさく)、日大豊山、日大三高などのほか、千葉日本大学第一高等学校・中学校や、札幌日本大学高等学校・中学校など、公式サイトを見ると、25校を超える附属があります。これらは、日大の直属附属校もあれば、もともと違う学校法人で日大と提携したところもあります。
東海大も、直属・系列の中高一貫が多い大学です。数で言うと多くはありませんが、たとえば明大明治は直属系で、明大中野と明大中野八王子は系列校となります。附属校でも、大学への内部進学率がとても高い学校と、外部受験が4割程度はいる学校など、それぞれ違いがあります。「◯◯大学附属」とついていても、学校によってカリキュラムや内部進学率が違うということは知っておきましょう。
②中高一貫校「大学連携系」

大学連携系は、大学と連携した中高一貫校のことです。たとえば麹町女子学園には「東洋大学グローバルコース」があり、基準を満たしていれば東洋大学への進学が可能です。
大学側にとってこうしたシステムは、少子化が進む中で、早い段階から生徒を確保できるメリットがあります。生徒・保護者側からすれば、試験を避けて進学できるメリットがありますし、中高一貫校としては「大学まで進める」ことで生徒募集のアピールもできます。
三方よしとは言い過ぎかもしれないけど、だから、中高一貫校と高大連携のカリキュラムや進学を行っているところが増えているのですね!
③中高一貫校「独立した中高一貫校」

特に大学との連携はない中高一貫校も、たくさんあります。
中でも難関大学をめざす、いわゆる進学校の代表例が開成や麻布や灘校、桜蔭や女子学院です。こうした難関校は、中学から先取り学習を行い、高校では大学受験に照準を合わせたカリキュラムを行うのが一般的です。
中高一貫校「中学入試のみか、高校入試もありか」
中高一貫校の種類として、次のように分けることもできます。- 中学受験のみ(中学からの入学者のみ)
- 高校受験もあり(高校からの入学もあり)
最近の中高一貫校では、高校からの入学を受け入れるところは減っているようです。
中学高校と連続したカリキュラムのため、高校から入ってきた生徒と内部進学生との間にギャップが出るという意見もあります。
いずれにしても、義務教育である中学は地元の公立で、高校は「一定レベルの中高一貫校、大学附属がいいかな」と漠然と考えている場合には、学校案内などを見比べて、高校入試枠があるかどうかも確認しておいたほうがよいですね。

私立中高一貫校だけでなく、さまざまな進路についてまずは知っておこう!
志望校については繰り返すようですが、中学受験にせよ高校受験にせよ、学校や塾などがサポートしてくれますから、心配しすぎる必要はありません。ただ、後から「え?あの学校いいなと思っていたけど、高校入試はなくなっちゃったんだ!」なんてことがないように、親が関心を持ってリサーチしておくことは大切です。
私立中高一貫校のメリット

- 連続した教育カリキュラム
- 6年間あるので総合的かつ幅広い教育が行いやすい
- 中学から高校への移行がスムーズ
- 特色ある教育に力を注げる
- 充実した設備
私立中高一貫校では、中学から高校を6年間の継続した期間として教育プログラムを設計しています。そのため、中学から高校への受験勉強も必要がなく、高校へもスムーズに移行できるメリットがあります。
また長い期間を過ごせるので、それぞれ独自のカリキュラムを展開しています。
たとえば英語に力を入れ希望者全員が留学できる、課外活動が盛んで強豪校としてスポーツや文化部で活躍できる、プログラミングやAIなどの本格的な学びを提供している、といったように特徴がはっきりしている学校も少なくありません。

私立の中高一貫校ではスポーツや文化部における「強豪校」と呼ばれる学校も多い
高校受験がないので、6年間を通じて課外活動に熱中できる、研究プロセスのような勉強もできる、あるいは先取り学習で大学受験に向けた一貫したカリキュラムで勉強できるといったメリットもあります。
設備が非常に充実している私立の中高一貫校も多くあります。
大学や小学校も同じ敷地内にある附属校は、中学生が大学のグラウンドを利用できたり、高校生が大学の講義を受けられたり、小学生の教室で交流を行ったりといった「ワンキャンパスならではの良さ」もあります。
私立中高一貫校のデメリット

- 学費が高く、付随する出費も多い
- カラーが合わないと学校生活になじめないケースもある
- 必ずしも希望の大学に簡単に入れるわけではない
公立の学校よりも学費の負担は重くなるでしょう。確かに高校無償化がありますが、あくまで「学費の無償化」であって、たとえば交友関係の出費や部活動の費用などは含まれません。
附属だからといって必ず大学に入れるとは限りませんし、入れたとしても学部は成績優秀者から決まるので、希望する学部を選べるかもわかりません。学校の方向性やカラーに合っていない場合には、学校生活そのものがうまくいかないこともないわけではありません。
現実的なこととして、中学受験を経て中高一貫校に入学しても、毎年数名の転校(中学は義務教育なので公立に入るなど)や退学はありますよ……。
入試で入ってきた生徒は少なからず「似たような成績」であるために、入学してみたら、成績が思ったように上がらないことも珍しくありません。
上位レベルの中高一貫校をあきらめ、ひとつレベルを落とした中高一貫校に入って、トップをキープして希望の推薦をとるといった進路方針をとる場合もあります。ギリギリで入った生徒が奮起して周囲から良い影響を受けてグングン成績を伸ばす子もいれば、その逆で「無理」と挫折することもないわけではありません。
要するに、中高一貫校だから、あるいは附属だからと「大学も安心」「指定校推薦* がたくさんあるから大丈夫」と勉強を怠っていれば、後であわてふためくことにもなり得るということです。
私立中高一貫校の費用について
文部科学省の令和5年度子供の学習費調査によると、私立の中学・高校の費用は6年間の総額で約775万円です。公立中学と私立中学の費用

中学の出費を比べると、公立中学は約15万円なのに対して、私立中学は約112万円と大きな差があります。グラフを見てわかるように、このうち「学費」の無償化が適用されたとしても、その他もろもろの出費もかなりの額にのぼります。
また、ここには出てきませんが、友だちと遊ぶにしても広範囲から生徒が集まる私立では「毎期の交通費が高い」とか、部活が盛んなのはいいけれども「部活費用にプラスして毎試合ごとの交通費や帰りがけに食べる軽食代、道具なども周りに合わせると高額になる」といった声も……。
私立の中高一貫校は、学費とは関係のない出費も大きくなりがちです。
よく中学受験の「塾の費用が高い」と話題にのぼりますが、塾が終わったところで学費関連は続きます。
無償化の制度は地域によってさまざまです。そもそも「高校無償化」なので、私立中学への助成金はほとんどありません。
学校は入学時だけでなく、毎年のように教育費がかかることを念頭に置いて、しっかりと中高、その後の大学と「教育費をどこまで出せるのか」をプランすることも大切です。
少しずつ「中学・高校・大学」と進路について考えていこう
中学・高校・大学あるいは専門学校など、進路について親も少しずつ学んでいきましょう。小学生はもちろんですが、実は中学生でも「進路」と言っても明確にはわかっていないことがほとんどです。
「将来は◯◯になりたい、だから◯◯大学に行って◯◯を勉強したい、そのためには◯◯大学への合格者をたくさん出している◯◯高校へ行きたい」とまで考えている子どもはそういません。
そもそも、将来なりたいものやめざすものが明確ではない子どもの方が多いですよ!
「大きくなったら何になりたいの?」と聞いても、「う〜ん」「わかんない」と答えるのは、まったく普通のことなんです。
大学受験も親世代の頃とはシステムも変わっています。
まだずっと先のことであるように感じるかもしれませんが、中学受験をするにしろ、しないにしろ、学校の種類やどんな学校があって特色があるのか、いくらくらい費用がかかるのかは知っておいて損はありません。
中高一貫校について、本記事ではごくごく基本的なことのみを取り上げています。
まずは、いろいろな学校の受験の条件や教育理念、ここ数年の合格者数や大学進学実績を公式サイトで見ておくことをおすすめします。「プログラミング入試があるんだ」とか「高校からも入学はできるけど、ほんの数人しかとっていない。ここに行きたければ中学受験をしないと難しいかも?」と、さまざまな情報が得られます。
子どもがどうしようかな?と思ったら、いろいろな選択肢を教えてあげられるように、親であるわたし達も日々勉強ですね!
参考:
中高一貫教育の概要と設置状況/文部科学省
中高一貫教育/文部科学省


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
私立の中高一貫校の学費は?先輩ママたちの費用一覧表も解説
私立の中高一貫校・大学付属校では、いったいどれくらいお金がかかるのでしょうか?今回の教育トピックでは、現在「私立中高一貫・大学付属校」に通学中、あるいは卒業して数年以内のお子さまがいる...
2025.11.12|大橋礼
-
【倍率8倍!!】公立中高一貫校入試の適性検査に「プログラミング的思考」が関係ある?
近年人気が上昇中で、倍率は8倍にも昇る公立中高一貫校入試。公立中高一貫校は適性検査という独自の入試問題を出題しますが、「プログラミング教育必修化」の背景もあり、「プログラミング的思考」...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
初の公立・小中高一貫校が2022年開校!東京都立小中高一貫教育校【8月の教育トピック】
今回取り上げるのは公立では全国初めてとなる「小中高一貫校」2022年に開校のニュースです。公立の中高一貫校はそれぞれ特色があり、また最近ではレベルの高い進路実績からも人気があります。さ...
2025.09.10|大橋礼
-
シュタイナー教育とは?メリット・デメリットもわかりやすく解説
「シュタイナー教育って日本の学校教育と何が違うの?」と疑問を感じる方も多いでしょう。この記事では、シュタイナー教育の基本理念から具体的な学習内容、モンテッソーリ教育との違い、メリット・...
2025.08.06|コエテコ byGMO 編集部
-
大学入試・評定アップで「情報Ⅰ」が鍵に!? 高校「情報Ⅰ」はしっかり学んでおけば将来役に立つ!
大学受験に向けて「総合型選抜(旧AO入試)」や「学校推薦型選抜」「指定校推薦」をめざすなら、大きなポイントになるのが評定です。指定校推薦は学習成績概評(評定平均値など)が出願条件となっ...
2025.10.31|大橋礼










大学名がついているといっても、違う学校法人が運営していたり、内部進学率がまるで違ったりするのね!