好きなことが見つからない!子どもの好奇心を引き出すコツとNGな声かけ(体験談)
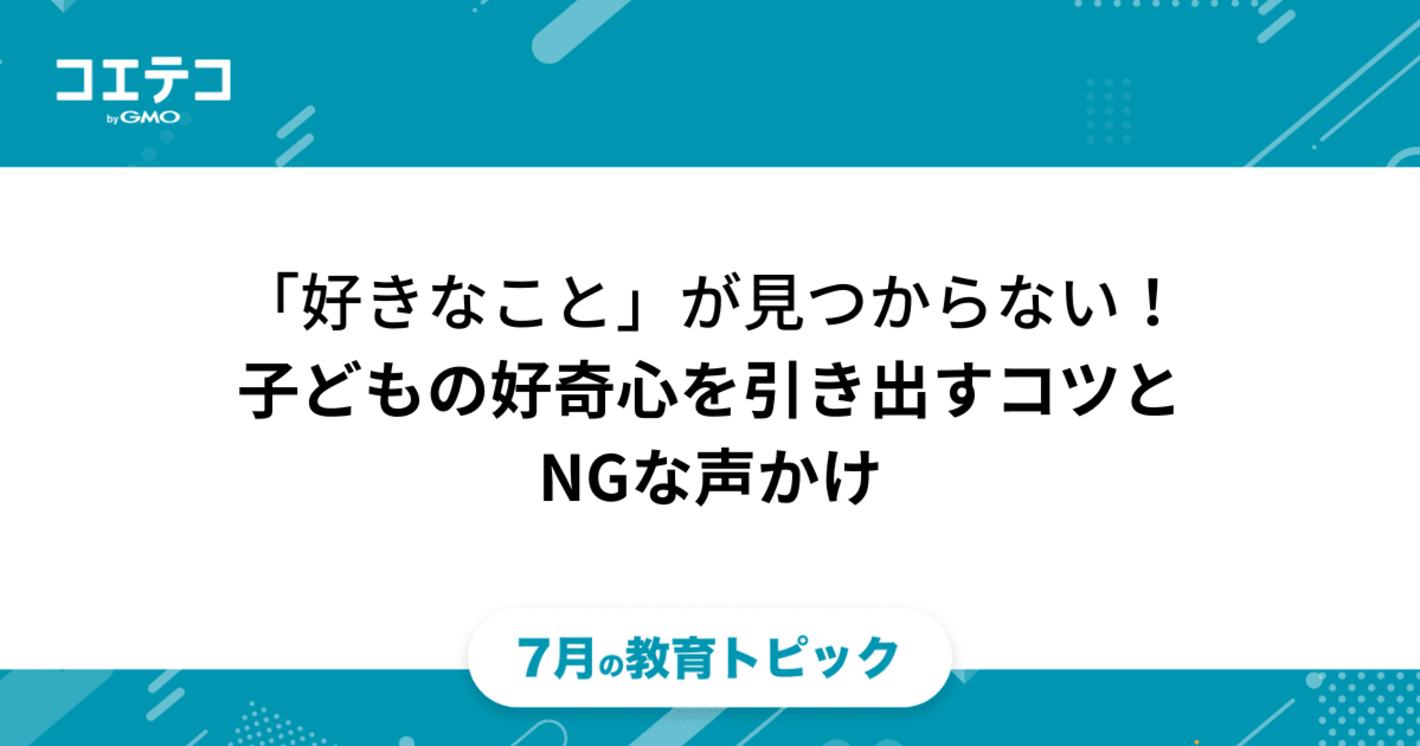
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
親としては、子どもの好きなこと・やりたいことを見つけて、それを伸ばしてあげたいと思うもの。今回の教育トピックでは「子どもの好きなこと・やりたいこと」の見つけ方について、先輩ママ・パパたちの経験談も交えながらご紹介します。
子どもの好きなことの見つけ方4つ

子どもの好きなことの見つけ方
- 「初めての◯◯」に挑戦してみよう
- 習い事の体験をしてみよう
- 子どもが見せる「興味の芽」を要チェック!
- 興味を持ったことに楽しく没頭する姿を親が見せる
子どもがやりたいことを見つけるためには「いろいろな体験をさせること」とよく言われます。
やってみたら面白い!見てみたら興味がわいた!実際に行ってみたら好きになった!なんていうのはよくあることですよね。でも問題は「何を体験させたらいいのか、わからない」こと。
そこで「やりたいこと・好きなこと」が見つかるヒントを得られる方法4つを解説します。
「初めての◯◯」に挑戦してみよう
とりあえず、今の時点でやりたいことや好きなことが見つかっていないのだとすれば、「これまでにやったことがない活動」、つまりまったく新しいジャンルを切り開いてみましょう。
川遊びだって「体験」のひとつ。自然と触れ合う機会も作りたい。
スポーツにしても、「サッカーもテニスも野球も興味ナシ」であきらめるのはまだ早い!スケートボードやボルダリング、殺陣(刀を使ったアクション)、ブレイクダンス……実にいろいろな種類があります。子どもがまだ体験したことがない「◯◯」にどんどんチャレンジしてみましょう!
習い事の体験をしてみよう
好きなこと・やりたいことがわからないから「習い事が見つけられない」という声もよく聞かれます。それなら、まずいろいろな習い事の体験会に参加してみましょう。この時、せっかくだから英語を学べるところがいいなとか、団体競技でチームワークを経験してほしいなとか、ついつい親の希望が浮かんでくるものですが、あまり決めつけないようにしたいところ。
「こんなチラシが入ってたよ」「すぐ近くだから行ってみる?」と気楽に誘い、誘いに乗ってこなかったら「そっか〜」でいったん終わりましょう。
(スポーツ系はあまり好きじゃないみたい。でも工作や実験は夢中になっている)(運動は嫌いだと思っていたけどチアリーディングは衣装も可愛くて興味津々になっているな)と体験会での反応を見ていると、より子どもの関心度が高いものが明確になります。
実際にやってみないとわからないのが子どもの興味。無料体験やワークショップがあったらぜひ参加してみてください。
子どもが見せる「興味の芽」を要チェック!
忙しい親としてはどうしても見逃してしまいがちですが、子どもはよく「これって何?面白そうかも」というサインを出しています。ニュースでマウンテンバイクを見て「かっこいいね」と言ったり、オープンキッチンのお店でシェフの動きをじっと見つめていたり、子どものノートを見るとカラフルなイラストがあちこちに描かれていたり。
それってもしかしたら、子どもが気になっているものの「マーク」かもしれません。

お花を育てるのに一生懸命な子もいる。何気ない日常にも「子どもが夢中になっていること」はあるかも。
見つけた途端に「これ好きなの?やってみる?」と聞くと意外と「いや、いい」なんて答えがちですから、それよりも「あら、マウンテンバイク? 日本人の選手が活躍しているらしいね」と話題をつないでいくのがベター。
子どもがいきいきと話しだしたら、一緒に興味を持ってあげると「好きなこと・やりたいこと」へと結びついていきやすいようです。
公園から帰ってくるたびにセミの抜け殻でポケットをパンパンにしてくるのにウンザリしていたわたし。
それを見ていた夫が「昆虫展をやっているから見に行こうか」と子どもを誘ったら、もうずっとへばりついて展示を見ていたんですね。
それからは昆虫図鑑を購入し、休みには昆虫ツアーに!(わたしは苦手なので夫担当)。
あまりおしゃべりな方ではないのですが、昆虫のことになると夢中になるし、パパと楽しそうに公園に「虫観察」に出かけるので、好きなことなら思いっきり楽しんで!と見守っています(Kさん・子ども小3)
興味を持ったことに楽しく没頭する姿を親が見せる
親が楽しそうに何かに没頭している姿を見ていると、子どもも自然と自分も楽しいことを見つけようという気持ちになります。逆に言うと「なんか最近つまらないな」「やることないしね」なんて会話をしていたら、子どもも同じくだら~んとしがち。無理をする必要はありませんが、ご自身が興味があることや好きなことはエネルギッシュに楽しみしょう。親の背を見て子は育つですよ!
夫はトレーニングが大好き。ジムにも通っていますし、家でも筋トレしているし、週3日は走ってるし。
そんなパパを見ているせいか「僕も走ってみようかな」と息子が言い出しました。
今は夫が走る横で自転車に乗っていますが、格闘技のジムにも興味が出てきたようでこの前は「親子でトレーニング」というジムのイベントにも一緒に参加しました。
いろいろと習い事に誘っても「やりたくない」の一点張りだったのが嘘みたいです。
思い返すと、わたしの母は裁縫が好きでよく子供服やバッグを作ってくれていたのですが、その横でわたしもチクチク刺繍とかしていたんですよね。今も手芸好きでそれが趣味になっています。
親の影響って意外にあるのかな、と感じます(Mさん・子ども小5)
好きなこと・やりたいことが見つからない子ども「家庭での注意点」

「うちの子は◯◯が好き」と決めつけていませんか?
親は赤ちゃんの時から成長を見続けています。子どもがどんなことに興味を持ってきたかをつぶさに見ているので「うちの子は◯◯が好き」「この子はこういうタイプ」と思い込んでしまっていることもあります。
「絵が大好き」と思っているけど、他にも好きなことがあるのかも?
子どもの興味や好奇心は変化します。学校に行けば友だちから新たな情報も得てくるでしょう。
親のフィルターで子どもの興味を分別しないこと!否定しないこと!
「え?劇団に入ってみたい?無理無理。それよりあなたは小さい時からサッカー得意だったじゃないの、サッカーに入ったら?」と、こんな風に最初から子どもの提案をはねつけてしまうのは避けましょう。
自分の希望を知らずと押し付けていませんか?
誰にでも叶わなかった夢がありますが、無意識のうちに子どもにその夢を押し付けていることがあります。確固たる信念があってすべてを集中するくらいのレベルなら(オリンピック選手を育てようとするように)別ですが、一般的にはあまりおすすめできません。自分がやりたいこと、あるいは子どもにやらせたいこと、ではなく、子どもが自分で「やりたいこと」を見つけられるような手助けをしてあげたいですね。
「別に」「わかんない」の返答に怒っていませんか?
子どもに「何かやりたいことはないの?」「好きなことは何?」とついつい聞いてしまいがちですが、子どもが「別に~」「わかんない」とあっさり答えて終わり、というのもよくあります。会話の流れによっては「なんでわからないのよ?」「好きなことがないの?」と畳み掛けてしまうのもよくあること。でも、子どもは本当にわからないから「わからない」のです。
答え方が反抗的だったり、やる気のなさ丸出しだとイラッとしますが、そこで怒ってしまうと子どもが心の根っこに持っている好奇心を押しつぶしてしまう可能性もあります。

いつもと違った環境になると会話がはずむことも!キャンプや旅行先、親子散歩で語り合う時間を持とう
家庭でも、さまざまな話題を投げてみて下さい。スポーツの結果でもニュースで見聞きしたことでも、隣町に新しくできた映画館のことでも、「こんなことがあってね」と話をしていると、子どもが積極的に会話に入ってくることもあるでしょう。
それが小さな「関心の芽」です。むやみに摘み取らず、自然な会話の流れで子どもの好奇心を高めていきたいですね。
疑似体験・間接体験と実際に自分がやってみることの違い
体験することがとても重要ではあるのですが、最近ではメディアやデジタル機器(つまりスマホやインターネット)を通して、擬似的な体験をしてそれで「やってみた」感覚を持ってしまう子どもも増えています。魚釣りをゲームで体験すると、釣り上げる瞬間の手応えさえ再現されています。
でも実際に湖に釣りに行くとどうでしょう。足元が滑らないように気をつけながら、餌をつけ、投げる練習をし、なかなか魚が釣れなくて、ふてくされたりして。みんなに励まされ、立ち直って粘って魚を釣り上げた瞬間の喜び。
体中で感じる「体験」と模擬体験は、やはり違います。

疑似体験も悪くはない。でもリアルな体験から生まれる「はじける笑顔」が見たい!
一概に疑似体験が悪いわけではありません。しかし幼児期から小学校時代までは特に、「ビックリした!」「焦った!」「すげ~っと思った!」とリアルに感じる体験が本当の経験値として残るのではないでしょうか。
参考:各発達段階における子どもの成育をめぐる課題等について/文部科学省
得意なこと=好きなこととは限りません
足が速いので運動神経がいいんだな、何かスポーツをやれば夢中になるに違いない、と思うのはちょっと早計かもしれません。一般的に得意なことは子どもにとって「好きなこと」であるケースは多いのですが、それはたくさん褒められたり、親が喜ぶことによって感じている場合も多いのです。周囲からすごいねと言われたり、結果を残したりすると、親としても「得意なことを伸ばそう」と力が入ります。
でも、得意なこと=本当に子どもがやりたがっていることなのか、必ず本人の意志を確認しましょう。
学校で描いた絵がコンクールで表彰されて(実際にとても上手だった!)、「絵が得意なんだわ」と思って絵画教室に通わせることに。
ある時、わたしの母から「◯ちゃんは、絵のお教室は好きじゃないんだって言ってたわよ。猫が大好きで猫の絵を一生懸命描いたら表彰されちゃった、って」と指摘されビックリ。
そこで娘を猫カフェに連れていくと、もう夢中でずっと猫と遊んでいるのです。
なんだ、そういうことなんだと自分が見ていたものが間違っていたことに気づきました。
今は本人がお世話をする、家族と同じように大切にする約束で猫を飼っていますが、掃除から何からきちんと行っています。
猫を中心に親子の会話も広がり、中学になった今では「獣医さんかトリマーになりたい」と進路に対する希望にもつながりました。あの時、勘違いしたままでなくてよかった(Aさん・子ども中3)
ワクワクと好奇心が大事!親子でいろいろなことにチャレンジ

純粋に好きなことに打ち込む姿は素晴らしいものです。でも、まだまだ経験値の少ない子どもにとっては、打ち込めるものを見つけるのは簡単ではありません。
そして夢中になるものは、いずれにしても変化していきます。成長と共に自分の興味の方向は定まってきますから、あまり心配することはありません。
ですから、無理に好きなものを見つけようとするのではなく「将来につながる土台」として、幼児期から学童期にかけてさまざまな体験をさせてあげませんか。体験したことが「きっかけ」になり、新たな発見をし、興味の方向がだんだんと見えてくることもよくあります。
子どもの目が輝いたり、ワクワクしていたり、そんな表情がたくさんたくさん見られるように、親子でいろいろなことに挑戦してみましょう。
世の中にはたくさんの面白いことがあります。わたし達「親」も好奇心を忘れずにいたいですね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どもが話してくれない!相談してくれない!親子のコミュニケーションについて考えてみよう|2月の教育トピック②
「ふさぎこんでいるので、どうしたのと聞いても何も話してくれない」「学校や友だちのことを聞いても〝別に〟〝わかんない〟しか答えない」子どもが悩みや学校のことを話してくれないと気をもんでい...
2025.09.10|大橋礼
-
あなたの家の教育方針は?先輩ママ・パパの体験談「夫婦で意見が合わない」「あわや離婚に!?」「ママ友とトラブル勃発」
教育方針と聞くと「小学校受験するわけでなし、改めて考えるほどのことでもない」と考えるご家庭も多いようです。でも、実は家庭内で互いの「子育て論」を勘違いしていることは少なくありません。 ...
2025.05.30|大橋礼
-
塾の先生の言い方がきつい・高圧的な場合の対処法4選と体験談を解説|教育トピック
「塾の先生との相性」問題は、親にとってはなかなか困ったことですね。 今回の教育トピックでは、子どもが塾の先生と合わない場合、親がとるべき対処法を4ステップで紹介。さらに先輩ママ・...
2025.11.12|大橋礼
-
「どうして?なぜ勉強しなくちゃいけないの?」子どもの問いに先輩ママ・パパたちはどう答えたか
「なぜ勉強するのか?」と問いかける子どもは実に多いものです。パパママ自身も小さい頃、親に聞いたことがあるかもしれません。 その答えはさまざまですが、今回は「なぜ勉強するのか」に先...
2025.09.10|大橋礼
-
小学生から始める理科好きに育てる方法とは〜理科嫌い・リケジョ・文理選択を考える〜
理科嫌い・理科好きは、まだずっと先のことと思っている進路の「文理選択」にまでつながっています。 今回の教育トピックは、理科嫌い・理科好きの子どもの特徴や育った背景を探りつつ、「うちの...
2025.09.10|大橋礼

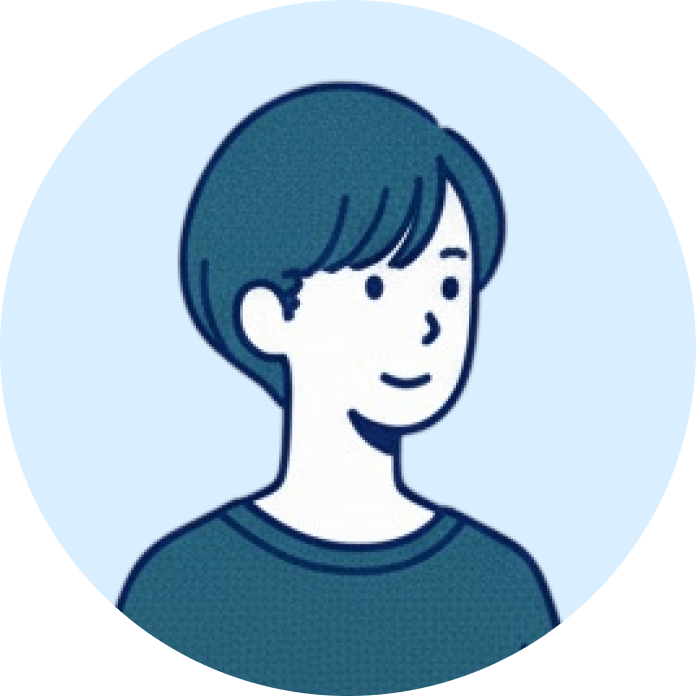
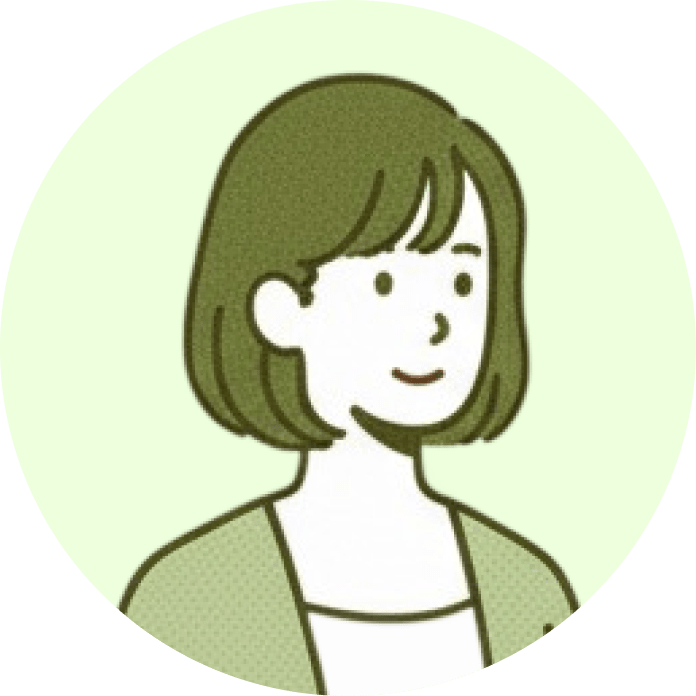
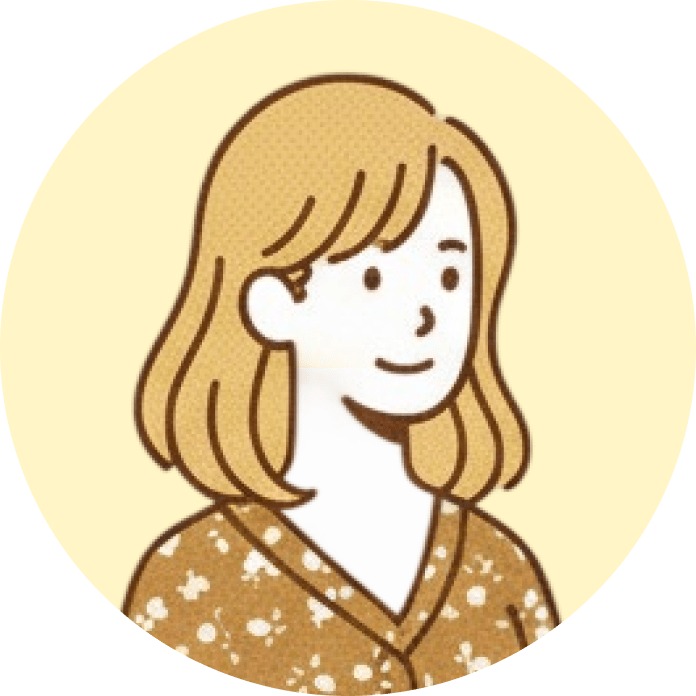

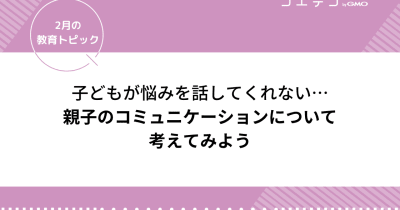
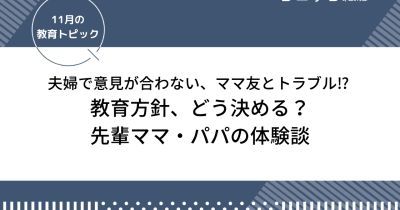
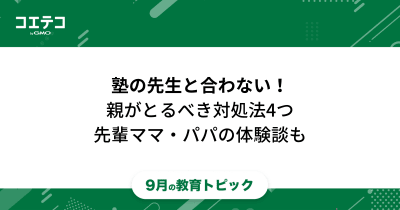
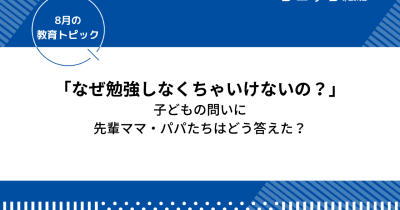

グイグイ攻め込んでも、引くだけの子どもも多いんですよね。子どもをその気にさせるのって難しい〜