塾の先生の言い方がきつい・高圧的な場合の対処法4選と体験談を解説|教育トピック
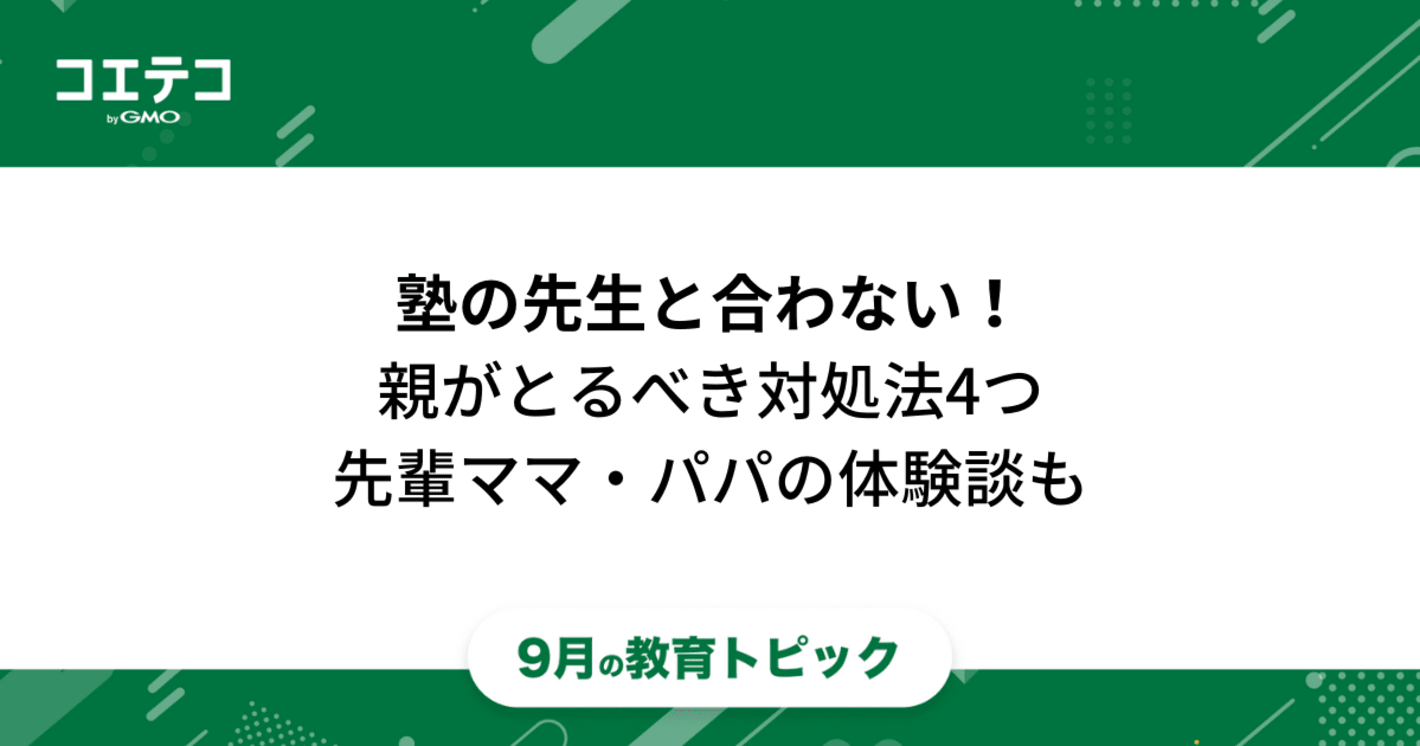
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
「塾の先生と合わない」
という悩みは本当によく耳にします。合わないという言葉はとても幅広い意味があって、先生が嫌いなのか、塾自体が嫌なのか、先生の態度に不信感を持っているのか、生理的にどうしても好きになれないのか……。
「塾の先生との相性」問題は、親にとってはなかなか困ったことですね。
今回の教育トピックでは、子どもが塾の先生と合わない場合、親がとるべき対処法を4ステップで紹介。さらに先輩ママ・パパたちが「塾の先生と合わない場合、どうしたか」体験談もピックアップしましたので、参考になればと思います。
塾の先生と合わない!対処のステップ4つ

塾の先生と合わないときの対処法・ステップ4つ
1:子どもの話をよく聞く
2:子どもの話を踏まえた上で塾長などトップと相談する
3:クラスやコースを変更する
4:塾を変える
では、4つのステップをさらに詳しくご紹介します。
塾の先生と合わないとき「最初に子どもの話をよく聞く」

まず、子どもの話を聞いてみましょう。先生のどこが嫌なのか、何が不満なのか、具体的に聞き出すことが大切です。とはいえ、子どもはそう簡単に本音を語りません。根底には(きっとお母さんやお父さんが怒り出す)と思っているからです。
親としては、「え?先生が嫌?なんで?どこが嫌なの?っていうか、塾に行きたくないからって、そんなこと言い出したの?」と、ついつい畳み掛けて問いただしてしまいがち……。
そうではなく、
「先生と合わないことってあると思うよ」
「ママも子どもの頃、苦手な先生がいて、その科目は成績が悪かったことがあるな」
「なんとなく気に入らない相手っているよね」
と、最初に子どもの気持ちに共感を示してあげたいところです。子どもがいったい「何が嫌なのか」を見極めなくては、適切な対処ができません。
もしかしたら、勉強そのものではなく、自分がしてもいないことで怒られたとか、成績が同じように上がったのに、別の子は褒められて自分は何も言われなかった、といったような、単純な出来事がきっかけとしてあるかもしれません。
ひとつ嫌なことがあると、他のことまですべて「自分にとっては悪いように思える」こともありがちです。
子どもがぽつりぽつりと話しだしたら、途中で「えええ?そんなこと?」と決して口をはさまないように!
私もつい「そんなことで嫌がるの?もっと世の中、嫌な人なんていっぱい出てくるよ!」みたいに言ったことがある。その後、何度聞いても子どもは答えてくれなかった……
子どもの感覚は大人よりも繊細なことが多く、同時に人生経験の積み重ねがないのですから、「こういう人もいる、しかたない」と割り切る考え自体がまだ持てないことも多いのです。
子どもが自分で理由を見つける手助けをしながら話を聞く
あえて「話し合う」と書かなかったのは、子どもと塾の先生が合わないことについて親子で話し合うのは次の段階であって、最初は「聞くことに徹する」のが大切だからです。なかなか核心にたどりつかないときは次のようなことを念頭に置いて、話してみるといいかもしれません。
- 先生の教え方が合わなくて「授業がよくわからない」のか
- 先生の話し方が嫌いだったり、自分(子ども)に対する態度が嫌なのか
- 過去に子どもにとって「とても嫌だと思うこと」が先生を介してあったのか
- おとなしい子、逆に明るい子が先生の「お気に入り」で、自分はあてはまっていないと感じているのか
- 何がではなく生理的にどうしても嫌でしょうがないのか
塾の先生が合わないときに「塾に対してするべきこと」

もし、子どもの話を聞いて、これはどうも「家庭内では解決しそうにない」と思ったら、塾と話し合いましょう。
塾と学校は違います。
塾は、料金を支払い、子どもの学習指導をお任せしています。お金を払っているから何を言ってもいいわけではありません。しかし必要なら、相談することをためらう必要もありません。
塾長などトップに相談する
子どもが「合わない」としている先生と直接お話をしてもいいのですが、客観的な立場で話し合えるように、先生方を取りまとめている立場の人や塾長など、いわゆる管理職にある人に話をしてみましょう。とりとめない話になってしまわないように、簡単なメモを書いておくと安心です。
- 子どもが嫌がっていると思われる理由
- 今の状況
- 子どもが言っていること
- 親の意見、気持ち
有り体に言えば、塾もビジネスの部分はありますから、なるべく穏便にすませようとするはずです。また同時に、もちろん塾としても、子どものことを考えていますから「この子の成績を伸ばすためには、○○先生でないほうがいい」とか、先生のやり方に問題があると判断すれば、先生に指導を行うはずです。
この時点で塾長や教室長から、担当の先生に話をしてくれたり、子供の不安をとりのぞくよう配慮してくれたりしたら、改善の成果を期待しつつ、子どもの変化を見守るようにしましょう。
クラスやコースを変更する
実際に先生が対応を変えてくれたとしても、困ったことに、子どもは一度嫌になると(状況が改善しても、「なんとなく」で)嫌がるというのも、これまたありがちです。塾に限ったことではないので、一度は親から「先生も考えてくれているから、一度だけ受け入れてみたら」と教えることは必要でしょう。とはいえ、別の視点で考えると、もっとも簡単な解決法は先生から離れることです。曜日によって先生が違う場合には、別の日にちにしてみるといいでしょう。あるいはコースを変える方法もあります。
もし塾に個別指導があるのならば、そちらに変える。個別指導は比較的、先生の変更がしやすいので、お子さんに個性があって「好き嫌い」が激しいのなら、個別指導で性格を考慮してもらい、合いそうな先生を選んでもらうとうまくいくかもしれません。
仮に個別指導で何度か先生を変えたが「合わない」とお子さんが言い続けるのなら、個別指導というスタイル自体が合わない可能性もあります。
個別指導でもマンツーマンもあれば1対2もあり、若いお兄さんやお姉さんのような先生を慕う場合もあれば、少し厳しいくらいのベテラン先生だとうまくいくこともあります。
先生を変える場合には、子どもの性格と「今、なぜ嫌なのか」を把握して、同じことの繰り返しにならないよう気をつけたいですね。
塾の先生と合わないなら「転塾」の選択肢もあり

塾によっては先生を変えられないケースもあります。塾を変えるのは大きな決断ですが、学校を転校するのとは違います。先生が嫌で嫌で、塾でストレスがたまるようでは本末転倒です。
いっそのこと、新しい塾を提案し、子どもと一緒に探してみましょう。こちらは、塾に通わせている小学生の子どもがいる親のアンケート調査結果です。
転塾を検討しているか?

塾を変えることについて検討している、あるいは既に転塾したケースを合わせると約2割近くになります。多くはありませんし、他の理由もあるでしょうが、かといって転塾が非常に珍しいケースというのでもありません。
体験授業をいくつか受けて、子どもに印象を確かめさせます。ひとつだけだと比較できないので、できれば複数の塾で体験してみるといいですね。
成績向上を目指し、学校以外でも学習しようと考えたときに塾の利用を検討する人は多いと思います。その中でも、講師のサポートが手厚い「個別指導塾」は非常に人気。しかし個別指導塾にも数えられないほど種類があるため「どれを選んだら間違いないんだろう...」ときっと悩んでしまうはず。当記事ではそんな悩みを解消すべく、数ある中でも特に実績豊富で人気度の高い、おすすめ個別指導塾を5つ厳選しました。
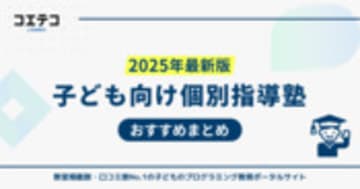

2025/12/15

また、オンライン塾であれば授業の様子を親御さまが自宅にいながら見ることも可能です。選択肢に入れてみても良いですよね。
この記事ではおすすめのオンライン塾について、講座内容や料金、講師の質、授業方式、サポート体制などを分かりやすく一覧で比較しています。オンライン塾のメリット・デメリット、各塾の口コミ、向いている子どもの特徴や対面式の塾との併用など、オンライン個別指導塾ランキングの気になるポイントがすべてわかります。
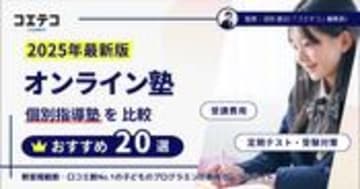

2026/01/24

先輩ママ・パパ体験談「子どもが塾の先生と合わないとき」どう対処した?

周りの評判に振り回されず「我が子と合うかどうか」が大事
ある時から塾に行き渋るようになったので、何度か話を聞きました。子どもは「できる子につきっきりで教えるけど、自分のことは適当にあしらう」と言うわけです。「そんなの思い込みだよ」と答えると不機嫌になって、さっさと部屋に戻ってしまいました。数日後、塾から「来ていませんが欠席ですか」と連絡がきて驚きました。戻ってきた娘に怒り心頭で怒鳴っていると、帰宅した夫が「学校ならともかく塾なのだから、そんなに嫌がるなら、別の塾にすればいいじゃないか」とあっさり言うので今度は夫婦げんかに。

しかし夫に「嫌いな塾にお金を落とすのも無駄なら、娘の大事な時間も無駄にしている」と言われ、最終的に納得して娘とも話しをし、別の塾を体験してから転塾しました。
わたしとしては、良い塾という評判で小3からでないと入れないと言われていた分、もったいないと思ってしまっていたんですよね。いくら「良い塾」と評判でも、良いかどうかは我が子に合うかどうかなので、周りの評判に振り回されないのも大切だと学びました(Mさん)
塾の先生とどうしても合わないなら、塾を変えればいいだけ!
最初に「あの先生が嫌いだから国語だけは変えてほしい」と言われた時は、子どものわがままを簡単に通していいのか悩みました。夫婦でかわるがわる話を聞き、つなぎ合わせていくと、どうやら「話し方とかが嫌い。聞いているだけでイライラする」ことが判明。ひとまず私が「進路の相談」という名目で該当の先生と面談をしたのですが、あっ!と思いました。
なぜなら、私もその先生の話し方とか、何かちょっとした仕草や言葉の端々が気になったからです。なるほど、親の私が(こういう人は苦手だな)と思うのだから、「そりゃ子どもも苦手なはずだよな」と思って、他の習い事もあるという理由で曜日を変更しました。
生理的に合わないというのは実際にあるし、それはもう解決の方法がないので、塾であれば普通に変えてしまえばいいと思います(Aさん)
この記事ではおすすめのオンライン家庭教師について、料金や授業形式、手元カメラのレンタル、サポート体制などを分かりやすく一覧で口コミも比較しています。オンライン家庭教師の料金相場やメリット・デメリットなどおすすめのオンライン家庭教師をランキングで紹介します。
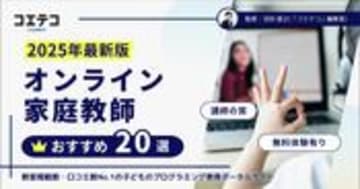

2026/01/15

塾に「先生と合わないようです」と率直に相談すべき
塾を嫌がるのは勉強したくないからだと思って、毎回、「早く行きなさい」とせっついても無言で時間稼ぎをするので困っていました。買い物に一緒にでかけた時、たまたま同じ塾の子と会ったのですが「先生はあーいう子が好きなんだよ」と言うのでビックリしました。

娘は引っ込み思案のところがあり、なかなか手を挙げて発言することもない様子で、「いくら勉強できても、しっかり発言もできない子はこれから成績が伸びない」と言われたのだと話してくれました。
先生の言葉にも一理はあると思いましたが、中学受験といっても名門校をめざすレベルではなく、おとなしい娘が過ごしやすい中堅レベルの女子校を考えていたので、ちょっと方向性も違うと感じました。手を打つなら早い方がよいと思い、受験指導の担当者と面談。最終的に違うコースへ変更しました。
また、子どもの性格についてもよく説明し、考慮して指導してほしいともお願いしました。
教室長からも「合う合わないは珍しいことではありません。相談して下さってよかった。○○先生とはうまくいくと思いますが、もし少しでもお子さまが不安に思うようなら、またすぐに連絡をください。必ず対応します」と言われ安心しました。
塾には遠慮せずにきちんと要望を出すべきです。それで改善してくれないのなら、別の塾にしたほうがいいのではと思います(Oさん)
結果が出ている塾なら、先生と合わなくても続けさせる手段を考える方がいい
先生が自分を見下している、と息子が訴えるので気になり、教室長と面談をしました。教室長は「それはうちの方針です。見下したというのは受け取り方だと思いますが、大事なのは成績アップという結果を出すこと。そのためには厳しい言い方もしますし、お子さんにとっては耳の痛い話をすることもあります。お子さまをバカにするような言い方であったら、私のほうから先生にも厳しく指導しますが、しかし基本的にうちの先生方は熱心です。実際に○君の成績はアップしていますよね」とデータを見せられました。

確かに成績は上がっている、成果が出ているということは「合う・合わない」でいえば、実際には「合っている」とも考えられます。
そこで子どもの文句というか、「最悪」「あの先生って~」みたいな話は「そりゃきついねえ」などと受け流しつつ、本人のストレスのはけ口になるよう、何度でも聞き、決して反論はせず、「うん、わかる」と答えるようにしました。
時には「まぁでも塾の先生だからね、一生付き合うわけじゃないから」とか「それはムカつくわね!」と一緒に憤慨し、「イライラしている時には甘いものがいいよ」と話の方向を変えて気分転換になるよう気をつけました。
結局、その先生とは小4の間だけで学年が上がると担当も変わったのですが、後から考えると辞めなくてよかったなと思います。結果が出ているなら、子どものストレスや愚痴を親が受け止めてあげながら、うまく通わせるのも親の役目かなと思います(Yさん)
子どもの意見を尊重してあげて
けっこう乱暴な話し方をするが塾では有名な名物先生がいて、その先生のクラスに入れた時には周囲から「いいわね」と言われたほどです。ところが、生真面目な息子はこの先生と合わず……。
「無駄話が多くてうざい」「くだらない冗談でウケてると思ってる」「僕が答えると、お前はマジメ人間すぎるな~って笑う」……正直、その程度のことはどこでもあるし、悪い先生ではないのだからと何度か話したのですが、どうしても先生を変えるか塾を変えたいと言い張るので根負けして塾を変えました。
すると息子が「ママごめん、でもありがとう」と謝るので困惑しました。どうやら、塾を変えるとなればきっとお金もかかる、迷惑をかける、親を落胆させると思っていたようです。
「ママごめんね」と言われて、そんなことじゃないのに!と、息子を抱きしめたくなりました。繰り返し子どもが主張したら、やはり子どもの意見を尊重する方向が良いのかなと個人的には思います(Oさん)
子どもが気持ちを伝えられないのが一番良くないこと
合う・合わないとは少し違う話ですが……。うちの娘の場合は中学受験はしないので、地元の個人塾に通っていました。小学校の成績が落ちることはなかったけれど、上がることもありませんでした。それでも中学入学後のためになると思い、通っていましたが、後から「あそこの先生って気分にムラがあって、不機嫌だとわからないところを聞いても、参考書みたいのを指さして黙ってた。それに喋り方とかハッキリ言って気持ち悪かった。でも塾さえ行っていればママも機嫌いいから、あきらめて、なるべく先生と関わらないようにしてた」と告白されて呆然。
親に「塾が嫌だ」とは話しづらいような雰囲気を当時のわたしが作っていたのでしょう、それこそ娘の時間を無駄にしてしまった。親として反省しています。

子どもが素直に自分の気持ちを話せる親子関係を築くことが何より大事。わたしは、娘の塾帰りの様子や表情とか、何もちゃんと見ていなかったんだなぁと後悔しています。
嫌がるという態度を示したら、それは絶対に見逃さずに、しっかり話を聞いてあげてください!子どもが「合わない」と話してくれるだけマシなのです!(Sさん)
親に相談してよかったと子どもが思えるように行動しよう!

塾の先生と合わない場合、できるだけの対処はしてみた上でそれでもうまくいかないのなら、塾を変えるという選択肢もありえます。
子どもが我慢に我慢を重ねて、大きなストレスを抱えて塾に通っても、良い成果も出ないでしょう。
塾に通うのは、受験であったり成績アップであったり、あるいは中学進学を見据えて学力を蓄えるなど、各家庭の目的があります。その目的を達成するために、塾一択ではないことも頭の片隅においておきましょう。
「先生と合わない」ことから、苦手なタイプや嫌な相手と思う人とどうつきあえばいいのか、どう対応すればいいのかを学ぶ機会ともなりえます。
しかしあくまで塾であることを考えると、何が何でも辞めさせないという態度も微妙です。
親がその時に相談相手となってくれて、自分の為を考えて行動してくれることを、ぜひ、お子さまにストレートに見せてあげてください。
子どもの意見に耳を傾けつつ、人生の先輩としてアドバイスもし、「何が一番よいか」を一緒に考えて必要なら子どものために行動をする、「やっぱり親に話してよかった」と思える結論が出るように、親も努力したいですね。
オンライン塾を検討するときに「本当に小学生は授業に集中できるのか?」「オンライン学習塾に通って学力は上がるのか?」と不安になることもあるでしょう。 この記事では、小学生におすすめのオンライン塾やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。


2026/01/15



Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どもが話してくれない!相談してくれない!親子のコミュニケーションについて考えてみよう|2月の教育トピック②
「ふさぎこんでいるので、どうしたのと聞いても何も話してくれない」「学校や友だちのことを聞いても〝別に〟〝わかんない〟しか答えない」子どもが悩みや学校のことを話してくれないと気をもんでい...
2025.09.10|大橋礼
-
(教育トピック)小一の壁|退職?転職?朝はどうする?7つの壁と対策
「小1の壁」はご存知ですか?小学校入学と共に、働くお母さん・お父さんが新たにぶつかる壁。今回の教育トピックでは、時には転職や退職を余儀なくされることもある小1の壁について詳しく解説。先...
2025.05.30|大橋礼
-
あなたの家の教育方針は?先輩ママ・パパの体験談「夫婦で意見が合わない」「あわや離婚に!?」「ママ友とトラブル勃発」
教育方針と聞くと「小学校受験するわけでなし、改めて考えるほどのことでもない」と考えるご家庭も多いようです。でも、実は家庭内で互いの「子育て論」を勘違いしていることは少なくありません。 ...
2025.05.30|大橋礼
-
好きなことが見つからない!子どもの好奇心を引き出すコツとNGな声かけ(体験談)
子どもに「やりたいことはないの?」「好きなことは何?」と聞いても、「別にぃ~」「特にない」なんて薄い反応しか返ってこなくてガッカリしたことはありませんか? 親としては、子どもの好...
2025.09.10|大橋礼
-
「どうして?なぜ勉強しなくちゃいけないの?」子どもの問いに先輩ママ・パパたちはどう答えたか
「なぜ勉強するのか?」と問いかける子どもは実に多いものです。パパママ自身も小さい頃、親に聞いたことがあるかもしれません。 その答えはさまざまですが、今回は「なぜ勉強するのか」に先...
2025.09.10|大橋礼




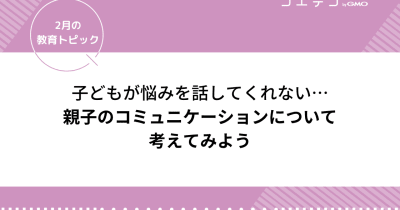
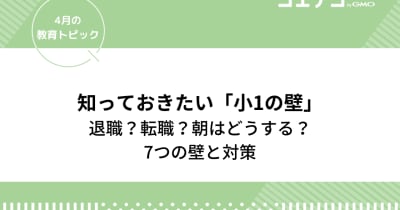
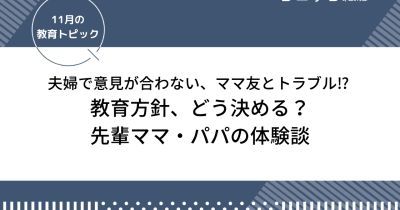
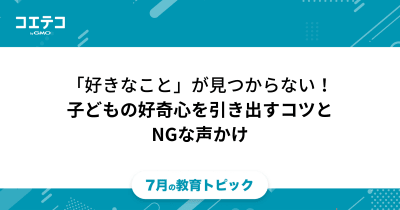
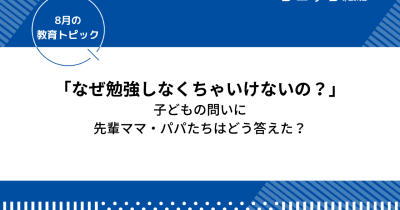
それが難しいんですけどね。だって子どもの言い分を聞いていると、ただのわがままだったりすることもよくありますから!