子どもの話、聞いてますか?聞く力・話す力・コミュニケーション力は親が伸ばす!
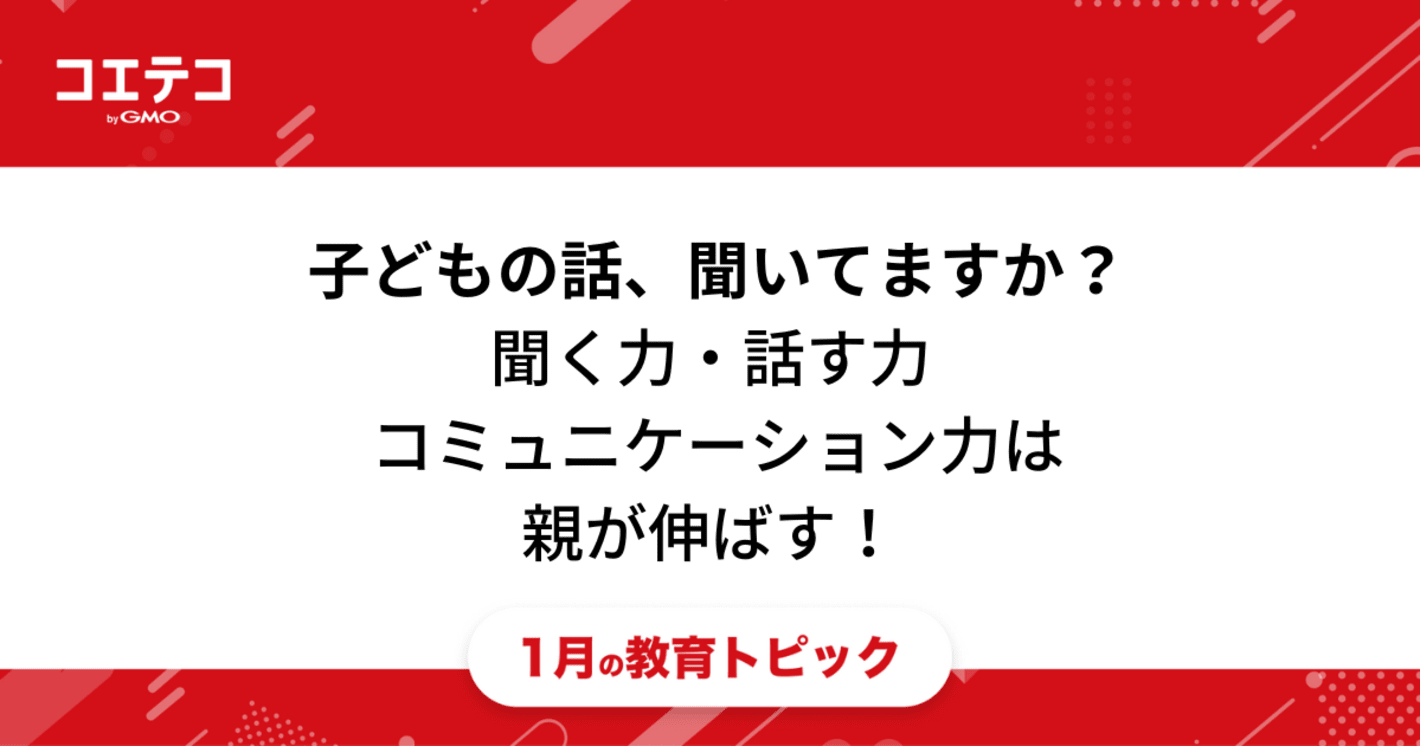
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
「うんうん(スマホを見ながら)」
「それで?(作業をしながら)」
こんな経験、ありませんか?
子どもが話しかけてくるたび、ついついその場しのぎの対応をしてしまう。気がつけば、子どもの話を心から聞いていない自分がいる……。
気になっているのは、あなただけではありません。
共働き世帯が増え、時間に追われる毎日。子どもとゆっくり向き合う時間を作ることは、誰もが難しさを感じている課題なのです。
そこで今回は、忙しい毎日の中でも実践できる、子どもの話の「聞き方」のコツをご紹介します。難しく考える必要はありません。ちょっとした工夫で、子どもとの会話はもっと楽しく、もっと深くなっていくはずです。
まずは、なぜ今、子どもの「聞く力・話す力」が重要なのか、そして親である私たちにできることは何なのか。具体的なテクニックとともに、一緒に考えていきましょう。
10人にひとりは「親にもっと話を聞いてほしい」と思っている

上記は日本財団による、子ども1万人の意識調査報告書の一部です。子どもの視点から、「家庭でこうあってほしい」希望のランキングですが、勉強へのプレッシャーをあまりかけないでほしい、など、親からすると痛い指摘ですね。
この中で、「親にもっと話を聞いてほしい」が10%いることがわかります。つまり、10人にひとりは親がちゃんと話を聞いてくれない、もっと自分の話を聞いてほしいと願っているわけです。
なぜ今、子どもの「聞く力・話す力」が重要なのか

将来を左右するコミュニケーション能力
私たちの子どもたちが社会に出る頃、どんな能力が求められているでしょうか。AI技術の進展により、暗記や計算といった従来型の学力の重要性は低下する一方、「人と関わる力」の価値が急上昇しています。
文部科学省が2023年に発表した調査によると、企業が新卒採用時に重視する能力の上位に「コミュニケーション能力」が20年連続でランクインしています。さらに、グローバル化が進む中、異なる価値観を持つ人々と協力し合える力も不可欠となっています。
わが子が小学生くらいだと、なかなか先の未来までは考えられないものです。でも、就職をしてからのことを想像してみてください。
多くの仕事は、ひとりではできません。それは仕事だけでなく、生きる上でも同様です。つまり、誰かと会話をし、意思疎通ができるかどうか、コミュニケーション能力は、とても重要な力なのです。
小学生の親子のコミュニケーション、実は今が大切な時期!
子どもの言語発達において、6歳から12歳までの小学生時代は特に重要な時期です。この時期には、次のような大切な力が育まれていきます。- 論理的思考力の基礎が形成される
- 相手の立場に立って考える力が芽生える
- 抽象的な概念を理解できるようになる
- 言葉を通じて感情をコントロールする力が育つ
わが子が赤ちゃんの頃を思い出してみませんか?

まだ言葉を話せない我が子に、「おむつ替えるよ」「お腹すいたね」と、一生懸命語りかけていたはずです。幼い子どもへの言葉かけの大切さは、多くの親が自然と理解しています。
ところが、子どもが成長するにつれて、その大切な会話の機会が少しずつ減っていくことがあります。特に小学生になると、子どもが面倒くさそうな表情を見せたり、時には親の話を聞き流したりすることも。そんな反応に、つい諦めてしまいがちですね。
東北大学加齢医学研究所の研究によると、就学前の子どもへの言葉かけが重要なのは広く知られていましたが、実は小学生以降の発達期においても、親子で多くの時間を過ごし、会話を重ねることが、子どもの言語関連脳神経機能の発達に重要な影響を与えることがわかってきました。
小学校6年間という時期は、子どもにとって大きな変化の時期です。「小学校」という新しい社会に飛び込み、親子関係以外にも、友達や先生など、さまざまな人々との関係を築いていきます。新しい経験や発見、時には困難に直面することもあるでしょう。
だからこそ、この時期の親子の会話はとても大切なのです。子どもの話に耳を傾け、その思いに寄り添うことは、子どもの心の成長を支える大きな力となります。たとえ反抗期のような難しい時期を迎えても、日々の何気ない会話を大切にしていきたいですね。
参考:親子で過ごす時間が子どもの言語理解と関連脳領域に影響/東北大学加齢医学研究所
子どもの話をしっかり受け止める!親の「聞き方」3つの基本

良い聞き手になるためには、意外とシンプルなコツがあります。今回は、すぐに実践できる3つの基本をご紹介します。
- アイコンタクトで「あなたの話を聞いているよ」を伝える
- 相づちで会話を広げる
- オウム返しで「ちゃんと聞いているよ」を示す
アイコンタクトで「あなたの話を聞いているよ」を伝える
子どもが話しかけてきたら、できるだけ隣に座り、目を合わせて話を聞くことが理想的です。でも、仕事から帰宅して家事の真っ最中に、ゆっくりとした時間を作るのは難しいですよね。そんな時は、キッチンからちょっと顔を出して、いったん子どもと視線を合わせ「うんうん、それで?」と声をかけるだけでもOK。たった数秒のアイコンタクトでも、「今、あなたの話を聞いているよ」というメッセージは伝わります。
相づちで会話を広げる
相づちは、子どもの話を引き出す魔法の言葉です。場面に応じて使い分けることで、より深い会話につながります。| 共感を示す相づち |
| 「そうだったんだ」 「うんうん、そう感じるのは当然だよね」 |
| 関心を示す相づち |
| 「それでどうなったの?」 「もっと聞かせて」 「そうかぁ、いろいろあるんだね、それで?」 |
| 理解を示す相づち |
| 「なるほど」 「そういうことだったのね」 「その気持ちよくわかるなぁ」 |
| 励ましの相づち |
| 「すごいね!」 「がんばったねえ」 |
| 質問を交えた相づち |
| 「それでどう思ったの?」 「どんな感じだったのかな?」 |
オウム返しで「ちゃんと聞いているよ」を示す

子どもの話したことを簡潔にまとめて返す「オウム返し」も効果的です。
オウム返しによって、子どもは自分の言葉が親にしっかり理解されたと感じ、安心して話を続けることができます。
【親子の会話「オウム返しの具体例」】
子ども:「今日、学校で跳び箱4段飛べたよ!」
親:「へぇ!今日、跳び箱が4段も飛べたんだ」
このオウム返しから、「すごいね」と褒めたり、「できた時はどんな気持ちだった?」と質問を投げかけたりすることで、会話をさらに広げていくことができます。
【兄弟姉妹がいる場合のポイント】
兄弟姉妹がいる家庭では、子どもの名前を先に呼んでからオウム返しをするのがおすすめです。
親:「お兄ちゃん、跳び箱4段跳べたんだね!」
こうすることで、親が誰に向かって話しているのかが明確になり、自分への関心をしっかり感じ取ることができるでしょう。
これらの基本を踏まえた上で、より深い親子の対話を育むための注意点についても学んでおきましょう!
要注意!子どもの話を遮ってしまう親の「聞き方」とその改善法

私たち親も、つい陥ってしまいがちな「よくないな」と思う対応があります。でも、それに気づくことができれば、改善することもできます。特によくある3つのNGパターンと、その改善方法についてお話しします。
スマートフォンを見ながらの「ながら聞き」
「うん、うん」とスマートフォンを見ながら返事をする。私たちの多くがどこかで後ろめたさを持ちつつも、ついやってしまう行動ではないでしょうか。スマホを片手に子どもの話を聞くことの影響
- 「自分の話より、スマートフォンの方が大事なんだ」と感じてしまう
- 親に話しかけることを諦めてしまう
- 自分の話の価値を低く感じてしまう
改善のポイント
- スマートフォンを一時的に裏返しにする
- 「今ちょっと手が離せないから、5分後に話を聞かせて」と正直に伝える
- 食事中はスマートフォンを別の部屋に置くルールを作る
つい始まってしまう「一方的な説教」
子どもの話をきっかけに、親の経験や教訓を延々と語ってしまう。過去にさかのぼって、子どもの悪い点をあれこれ指摘してしまう。これも多くの親が思い当たる場面ではないでしょうか。一方的な説教をしてしまうことの影響
- 話す意欲が失われる
- 自分で考える機会を奪われる
- 親に話すと説教が始まると思い、話すのを避けるようになる
改善のポイント
- まずは子どもの話を最後まで聞く
- 「どうしてそう思ったの?」と子どもの考えを引き出す
- 説教したくなったら「どうしたらいいと思う?」と子どもに考えを委ねる
思わず出てしまう「否定的な反応」
「だから言ったでしょ!」「それじゃダメじゃない」など、つい否定的な言葉を投げかけてしまうことはありませんか?否定的な反応がおよぼす子どもへの影響
- 自己肯定感が低下する
- 失敗や困ったことを話せなくなる
- 親に相談することをためらうようになる
改善のポイント
- まず子どもの気持ちに共感する
「そうだよね、そう思っちゃうよね」 - 否定から始めず、まず受け止める
「そうか、そんなことがあったんだね」 - 建設的な提案をする
「次はこうしてみたら?」
明日からできる!子どもの話を聞くための改善アクション

1. スマートフォンを見ながらの会話をしていることに気づいたら、すぐに画面を伏せる
2. 説教したくなったら「深呼吸」を心がける
3. 否定的な言葉が出そうになったら、まず「そうだね」と言ってみる
完璧な親なんていません。でも、こうした「よくないな」と思う対応に気づき、少しずつ改善していくことで、子どもとの会話はきっと変わっていきます。とにかく意識することです。
親であっても、仕事もすれば家事もする、些末な用事をこなしながら生活をしています。だから、やっぱり、子どものためと思っても、常に完璧に子どもの話を聞くのは難しいことです。
それでも、少しでも意識して、たとえば「後でね」と言ったまま、時間が過ぎてしまったとしても「ごめん、あの時、後でねと言って話を聞けなかったよ」と伝えてあげましょう。
あるいは、話を聞けなかったとしても、次の機会は(この前、流し聞いてしまったな、今日はちゃんと聞くようにしよう)とすればいいのです。タイミング的には、夕飯時やお風呂から出た後とか、ちょっとしたスキマ時間に「そういえばさ」と話しかけてみてはどうでしょうか。
子どもの話を上手に聞くためのコツとテクニック

「子どもの話をもっとちゃんと聞きたい」。そう思っていても、具体的にどうすればいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。ここでは、実践的なテクニックをご紹介します。
まずは「話しやすい環境」を整えましょう
子どもには、心を開きやすい時間帯があります。- お風呂上がりのリラックスした時間
- 寝る前のちょっとした会話
- 休日の車の中
- 二人きりで過ごせる休日の朝食時

忙しい毎日の中で、「話しやすい時間」を意識的に作っていくことが大切です。
適切な「距離感」を保つ
物理的な距離も大切なポイントです。- 視線の高さを合わせる
- 適度な距離を保つ(近すぎず、遠すぎず)
- 体の向きを子どもの方に向ける
ちなみに、思春期に差しかかる高学年の場合は、距離を取りすぎず、かといって近すぎず、というさじ加減が必要になってきます。それに子どもの性格や、その時の気分もありますね。甘えて寄りかかってくるような時もあるし、自分から話すのが苦手なタイプもいます。
親としては、話をしてほしくて、あれこれ問い詰めてしまうこともあるでしょう。でも、「問い詰める」と「会話」は違います。ぽつり、ぽつりと話すのでも、それに対して「うんうん」と聞くのも、その子にとっては重要な会話になるかもしれません。
子どもの様子、表情、仕草や態度を見極めながら、それに合わせて、距離感をうまくとって話を聞けるといいですね。
「開かれた質問」で話を引き出す
「はい」「いいえ」で終わってしまう質問をクローズドクエスチョンと言います。その逆で、具体的な回答を引き出すのが「開かれた質問」です。NGな質問例
「学校は楽しかった?」
「宿題は終わった?」
「お友達と遊んだ?」
こんな問いかけだと、口数の少ない子は特に「うん」とか「まぁね」で終わってしまいます。
効果的な質問例
「今日の学校でどんなことがあった?」
「休み時間は何して遊んだの?」
「給食のメニューで何が一番おいしかった?」
上記のような問いかけには、子どもは「今日はカレーライスだったよ」とか「ドッジボールした」と何らかの答えを言いやすくなります。自然な親子の会話が、子どもの心の成長を支えていくのです。
わたしの経験談「会話の引き出しを持つこと」
わたしの個人的な経験もひとつ、お話しますね。ちょっと長いので、興味のない方、飛ばしちゃってください!子どもとの会話で、夕飯の時や外食時、旅行先などでよく行っていた方法です。それは「みんなに質問タイム」。小学校低学年くらいまでは、「じゃ、みんなに質問するからね!」と、イベント風にしていました。
「これまでで一番楽しかったこと」
「今までママが作った料理でベスト!って思ったものは?」
「マジでつまらないと思ったドラマやアニメは」
こんな質問を投げかけて、まず私が話します。そうすると子どもも、けっこう話し出すことが多かったです。聞いているだけの時もありましたが、途中で会話に入ってくるんですね。
子どもが高学年になってくると、イベントっぽい感じをわざとらしく感じるのか、「ふーん」と関心を示さないこともありました。そのときは、子どもが今いちばん興味を持っていることについて聞くようにしていました。
たいていはゲーム、次男の場合は幼少期から車が好きだったので、その手の新しい話題やニュースに取り上げられているようなことを事前になんとなく集めておいて、(それを、わたしは引き出しにしまっておく、とよく言っていました)、ぽんぽんと「話題の種」を投げかけます。
これ、実は夫婦の会話でも使っています。
「会話力は学ぶべきスキル」留学時代に教わったこと
アメリカに15歳でわたった時に、「会話」がいかに重要であるかを覚えました。日本人の「阿吽の呼吸」「察する力」も素晴らしいのですが、言葉にしないと伝わらないこともあるというのを肌身で感じたのです。ある時、ホームステイ先のママが、テーブルセッティングをしながら、こんな話をしてくれました。
「アイスブレイクとか、カンバセーションピースって大事なのよ」
指をさしたのは、古い犬の陶器の置物と、わたしがお土産で渡した和紙でできた小さな箱。
「これを見て、あらきれいね、から、それはね、日本から持ってきてくれたのよ、とか、わたしのひいおばあちゃんは陶器の犬をコレクションしていたの、なんて話をするわけ。みんなの会話のきっかけになるでしょ?」
「みんなで集まるのは楽しくおしゃべりしながら食事をすること。だから、ホストは会話のきっかけをみんなに投げかけるし、ホストがいなくてもちょっとした話題になるようなモノを出しておくわけ」
カンバセーション(会話)を活発にするための小道具を用意する。話題を投げかける。楽しく会話をして、相手のことを知り、自分のことを知ってもらう。「黙っていたら通じないから。あなたもたくさん会話してね」そう言われたのです。
英語も上手ではなく、初対面の人とにぎやかに盛り上がるなんて難しいと思っていたものですが、これも経験。こうしたホームパーティーに参加するうちに、どう話しかければいいのか、相手がどんなことに興味を持っているのかを捉えて話す、ということを覚えました。
そのママは、こんな話もしてくれたのです。
「普段から、面白そうなこととかびっくりしたこととか、ニュースや話題をためて、心の中の引き出しにしまっておくの。夫は無口な方だけど、わたしがどんどん『こんな話があるのよ』と話し出せば、新しい会話が始まるからね」
わたしもそのママに教わったことを、今でも実践しています。話題の引き出しをたくさん作っておいて、今日はなんだかみんな静かだな、なんていう時には「そういえばね」と話し出します。
長くなりましたが、わたしはあの時に「会話とコミュニケーション」についてたくさんのことを教わってよかった、大きな財産になっていると思っています。
聞く力と話す力。それは生涯、必要となるスキルなのです。
親が子どもの話をきちんと聞くことから始めよう
もともとおとなしい子もいますし、おしゃべりが苦手でも、だからコミュニケーションがとれないわけではありません。子どもは大きくなると一時的に極端に会話が減ることもあります。でも、そんな時も焦らないでくださいね。大学生や社会人になると、今度は対等に話もできるようになるものです。
コミュニケーション能力とは、日々、少しずつ伸ばしていくものではないでしょうか。学校や友達関係でも身についていくものですが、まずは親が子どもの話をきちんと聞く、そこから始めてみませんか?


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学生の子どもがショート動画ばかり見ている!親が知っておくべき影響と対策
最近の調査によると、小学生の67%がテレビよりも動画配信サービスを視聴しており、その中でもショート動画の人気は急上昇しています。子どもたちの生活の一部となったショート動画ですが、その影...
2026.01.19|大橋礼
-
子どもが話してくれない!相談してくれない!親子のコミュニケーションについて考えてみよう|2月の教育トピック②
「ふさぎこんでいるので、どうしたのと聞いても何も話してくれない」「学校や友だちのことを聞いても〝別に〟〝わかんない〟しか答えない」子どもが悩みや学校のことを話してくれないと気をもんでい...
2025.09.10|大橋礼
-
中学受験対応の民間学童5選【一覧表】共働きでも大丈夫!手厚い学習環境で受験をめざそう
共働き夫婦にとって「子どもの中学受験」でひとつの壁となるのが、放課後の過ごし方です。今回の教育トピックでは中学受験に対応している民間学童をご紹介します。民間学童は独自のカリキュラムや有...
2025.05.30|大橋礼
-
在宅フリーランスママの働き方|子育てと仕事の両立・稼働時間の変化・3大ピンチの乗り越え方
フリーランスとして働きながら子育てをする毎日は、想像以上に大変。小1の壁、夏休み、急な体調不良――フリーランスママが直面しやすい3大ピンチをどう乗り越えるか。保育園と小学校、中学まで各...
2025.07.31|大橋礼
-
小1の壁が発生する原因とは?入学前の対策と入学後の対応を解説
まもなく入学を迎える多くのお父さま・お母さまは『小1の壁』という言葉を聞いたことがあるかと思います。幼稚園や保育園の時とは違い、小学校入学後の方が育児と仕事の両立が難しくなったという声...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部











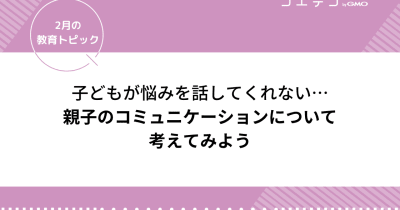
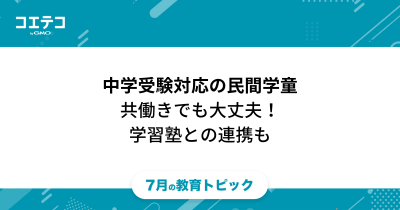

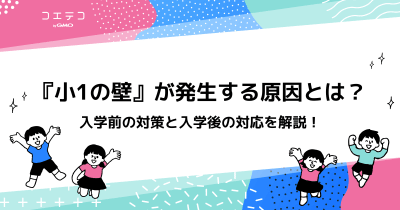
「別にぃ〜」なんて答えることもありますが、そこで『なによ〜、ママが聞いているのにちゃんと教えてよ』と返したら、ますますかたくなになることも。
今日は話す気分じゃないのね〜、とサラリと流すことも必要なのかも。