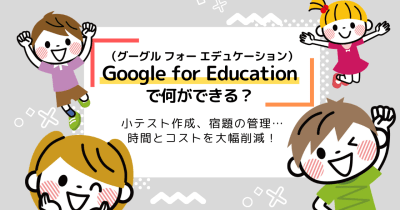オーダーメイド教育が可能?アダプティブ・ラーニング

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。
それもそのはず、2018年現在、1学級の標準人数は40人となっています。40人もの生徒がいれば、理解度にばらつきが出るのは当たり前のことですよね。
ある程度は仕方のない面があるとはいえ、このばらつきは生徒のやる気を損ない、学習への意欲を下げてしまうことが大きな問題となっています。
この状況を解決するのがアダプティブ・ラーニング(日本語では『適応学習』)です。アダプティブ・ラーニングとは、平たく言えば、それぞれの生徒のレベルに合わせた学習内容を提供すること。
ICT(情報通信技術)を活用することにより、先生にかかる負担は極力抑えたままでオーダーメイドの学習を提供できる可能性が出てきました。今回はそんなアダプティブ・ラーニングについて解説します。
理解度のばらつきを抑え、効率のよい学びを
アダプティブ・ラーニングについて説明する前に、学校で起こりがちな理解度のばらつきについて掘り下げてみましょう。たとえば、『小数』自体の理解があやふやな生徒に『小数の足し算』を指導しても、うまく理解することができませんよね。
一方で、小数くらいなら簡単に理解できてしまう生徒にとっては、足し算の時間は退屈になってしまい、授業に対する興味を失ってしまうかもしれません。
これを解消するためには、うまく理解が進まない生徒には数ステップ戻った内容(小数とは何か? という段階)を指導し、すでに理解できている生徒には発展的な内容を与えればよいと言えるでしょう。
こうした工夫をすることにより、モチベーションを損なうことなく学習に取り組んでもらうことができるのです。
また、人には思考のくせ(どのような考え方をしがちなのか)があります。思考のくせを把握しておけば、問題につまずく前の段階で予防することができます。
このように、個人に合わせた学習内容を提供すれば効率のよい学びが可能になるという考え方・システムがアダプティブ・ラーニングなのです。
なぜ今アダプティブ・ラーニングが注目されているのか
もっとも、アダプティブ・ラーニングの考え方自体は珍しいものではありません。これまでの学校でも、いわゆる補習やレベル分け授業などの形で行われてきました。それが改めて注目を浴びているのは、学校現場にICTの導入が進んできたためです。
これまでのアダプティブ・ラーニングでは、生徒の成績分析・内容のレベル調整を先生の力でやらなければなりませんでした。
しかし、日々忙しい先生の時間には限りがあります。40人もの生徒をまんべんなくフォローして内容を調整するのは、現実的に考えて難しいでしょう。
実際に学校現場では、先生の長時間労働・過重労働が問題視され、教育の担い手が不足してきています。
「生徒一人ひとりに合わせた教育が理想」とは言えど、先生の負担をこれ以上増やすのは……ということで、細やかな実施が難しい側面がありました。
教育ICTを利用することにより、先生の負担も軽減
そこで登場するのが教育ICT(EdTech)です。たとえばデジタル教材では、生徒が問題を解けたかどうかが初めからデータとして記録されていきます。紙のテストを先生が採点し、エクセルなどに入力して……という手間も必要ありません。つまり、生徒それぞれの学習状況や点数、つまずいたポイントなどを瞬時に把握することができるわけです。
さらに、多数の生徒のデータが集まれば、そもそも子どもがどのあたりでつまずきやすいのか(時間をとって学習させた方がよいのか)、つまずいた場合、どのような教材でフォローすればいいのかなどを事前に予測できるかもしれません。
教育ICTを導入すれば、先生の負担を極力増やさないように配慮しながらアダプティブ・ラーニングを実践できる可能性があるのです。
教育内容の標準化
従来の教育では、先生の経験や主観に沿った授業が多く、若手の先生とベテランの先生との間では教育内容に差が出ることもありました。教育ICTを利用したアダプティブ・ラーニングでは、過去のデータなどに基づいて客観的な観点から教材を用意して指導を行うことが可能です。そのため、先生の能力を問わずに高いレベルでの教育を行うことができます。
もちろん、教室に立って指導を行う先生が必要ないわけではありません。むしろ、実際の教育の現場での気づきや改善点をどんどん見つけていき、客観的なデータを溜め、ICT教育の質を高めていくためには現場の先生方の力が必要です。また、例外的な指導を行わなければならない場合などは、長年の経験が生きることもあります。
従来の指導法とICT教育によるアダプティブ・ラーニングの両方を取り入れていくのが肝要といえるでしょう。
まとめ
少し前に『分数ができない大学生』という本が話題になったことがありました。どこかで学習につまずいてしまい、それが解消されないままカリキュラムが進んでしまうと、広い範囲を後からやり直す必要が出てきます。
そうはいっても、5年生の子どもに「3年生の内容からやり直そうね」とアプローチするのは容易なことではありません。
つまずきは、発生した段階ですぐに発見・対処することが大事だと言えるでしょう。そうした観点からも、アダプティブ・ラーニングの導入・普及に期待が高まっているのです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
アクティブラーニングはもう古い?文部科学省が推進する理由や事例を紹介
教育が変わろうとしています。先生が一方的に授業をし、生徒は受け身で聞くだけ……というパッシブ(受動的)な学びではなく、生徒がみずから学ぶアクティブ(能動的)な授業に変わろうとしているの...
2025.01.24|コエテコ byGMO 編集部
-
【小学校】“SSS””CS”って何のこと?「先生」以外の学校スタッフ
小学校の職員と言えば、校長先生、副校長先生、担任の先生たちは想像がつくでしょう。実は、それ以外にも学校スタッフはたくさんいます。中には、略称になっていて、職名だけでは仕事内容がよく分か...
2024.06.06|コエテコ byGMO 編集部
-
Google for Educationって何?機能やメリットを詳しく解説!
学校の業務は多岐に渡ります。先生の勤務時間も増加傾向にあるのが現実です。 よけいなコストを削減して、生徒と向き合う時間を増やす。今回はそんな学校教育のためのツール「Google fo...
2022.06.03|コエテコ byGMO 編集部
-
仮想空間の学校に通う!?東京都のバーチャル・ラーニング・プラットフォーム|メタバース学校や塾という新しい選択肢
東京都教育委員会では、仮想空間上に「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム」を用意し、区市町村に提供する取り組みを開始しました。 今回の教育トピックでは自治体が行っているメタバース...
2024.04.01|大橋礼
-
探究学習とは何のこと?事例や学習内容を徹底解説!
多様なテーマについて、自分で考え答えを導き出す探求学習。探求学習の多くは、フィールドワークを行い生徒自身が情報を得るスタイルになっています。この記事では、2022年から高校の授業で導入...
2024.12.18|コエテコ byGMO 編集部