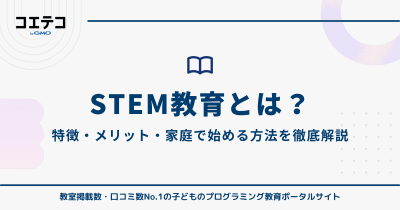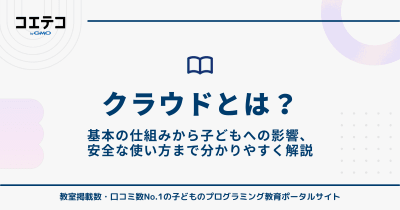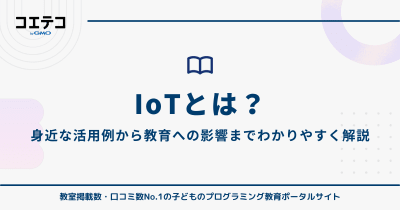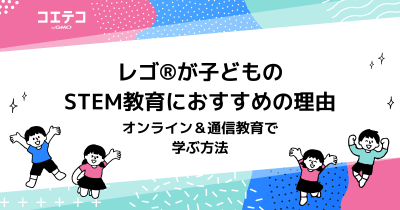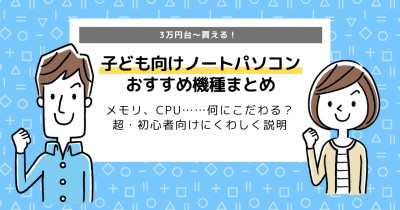EdTechとは?子どもの学びを支える最新教育技術を紹介!

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
これは、IT技術を活用して子どもの学びを進化させる新しい教育の形です。
この記事では、EdTechの基本から注目される理由、教育現場での活用事例までを保護者向けにわかりやすく解説します。
EdTech(エドテック)とは
EdTechとは「Education(教育)」と「Technology(技術)」を組み合わせた言葉です。簡単に言えば、「最新のテクノロジーを活用した教育」のこと。経済産業省も推進している新しい教育の形です。従来の教科書やプリントだけでなく、タブレットやパソコン、インターネット、人工知能(AI)などを活用して、子どもたち一人一人に合わせた効果的な学習を実現します。
単なるデジタル化ではなく、テクノロジーを使って「より良い学び」を実現することが目的なのです。
EdTech(エドテック)で変わる教育現場
「学校の勉強道具」と聞いて、何を思い浮かべますか?黒板、チョーク、ノート、鉛筆……。保護者の世代にとって、これらはとても懐かしい学校の風景ですよね。
そう、これまでの学校教育は、先生が黒板に書いたことをノートに写して覚える「一斉授業」が基本でした。

インターネットやパソコンが普及していなかった時代、この方法は多くの生徒に同時に教えられる点で、とても効率的でした。しかし、時代とともに、この従来型の授業にはいくつかの課題が見えてきました。
たとえば、先生から生徒への一方通行になりがちな点。「自分で考える力」や「創造性」が重視される現代において、子どもたちが受け身になってしまうのは大きな課題です。
また、先生が説明するスピードについていけない子もいれば、もっと進んだ内容を学びたい子もいるでしょう。一斉授業では、各自の学習ペースの違いに対応するのが難しいのです。
さらに、学校教育には別の課題もあります。先生方の長時間労働は深刻な問題ですし、都会と地方での教育の格差も気になるところ。
「うちの地域には学習塾が少ないから…」と不安を感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。また、グローバル化が進む中、海外の子どもたちとの学力差も無視できない問題です。
EdTechは、こうした様々な課題をテクノロジーの力で解決しようという新しい試みなのです。個人の理解度に合わせた学習、時間や場所を選ばない学習環境の提供、先生の業務負担の軽減など、テクノロジーには多くの可能性があります。
もちろん、テクノロジーだけで全ての教育課題が解決できるわけではありません。でも、子どもたちにより良い学びの機会を提供するための、大切なツールの一つとして、EdTechは注目されているのです。
EdTech(エドテック)4つの特徴
お子さんの「もっと勉強したい!」「ここがわからない…」といった声に、テクノロジーがきめ細かく応えてくれる。それがEdTechの大きな特徴です。EdTech(エドテック)4つの特徴
- 時間や場所を選ばず学習できる
- 先生や友達と双方向でやり取りができる
- AIが個人のペースに合わせてサポート
- ゲーム感覚で楽しく学べる
特に注目なのは、ひとりひとりの理解度や興味に合わせた「個別最適化」という点。「うちの子、授業についていけているかな……」という保護者の心配も、テクノロジーの力で解決できるかもしれません。
「EdTech」って具体的にはどんなもの?
ここでは、EdTechの具体例をまとめました。どこでも授業が受けられる!オンライン講義(e-Lerning)

教育現場とテクノロジーと聞いて、はじめに思い浮かぶのはオンライン授業や「e-Lerning(e-ラーニング)」でしょう。
学校だけでなく、会社の研修などでも採用されているので、「これなら知ってる!」「受けたことがある」という方がいるかもしれません。
オンライン講義の利点は何と言っても「先生と生徒が同じ場所にいなくてもいい」点。
欠席時の補習という形でも使えますし、人気の先生の授業をどこでも受けられるため、学習塾でも活用されています。
また、最近では世界中の大学がMOOC(Massive Open Online Course、大規模オープンオンライン授業)を開講し始めており、日本にいながらハーバード大学の授業を受ける、といったことも可能になりました。
わざわざ海外に行かなくても「留学」ができるということで、大人向けの教育方法としても注目を集めています。
プリントも採点も、もう要らない!学習管理システム(LMS)

先ほどのe-Lerningと同時に用いられるのがこのLMS(Learning Management System、学習管理システム)です。
これは、教材の配布をオンラインで行ったり、それぞれの生徒がどこまで学習を終えているかを管理したりするためのシステムです。
教材の配布をオンラインで行うことができれば、毎回プリントを用意する必要もありません。経費も手間も、資源も節約できます。
また、生徒の学習状況を把握しやすくなることで、それぞれの生徒に適切なカリキュラムを組み直すことも簡単になり、学習効率を高めることができるのです。
デジタル時代の「連絡網」、教育SNS

教育SNSとは、教師と生徒、そして保護者のコミュニケーションを取りやすくすることに特化したツールです。
少し前までは「クラスの連絡網」があり、AさんからBさんへ、そしてBさんからCさんへ……と電話で内容を伝えるのが一般的でした。
現代では、電話番号が個人情報にあたること、共働き家庭が多くなり電話に出られない保護者が多くなったことから、連絡網を教育SNSに切り替えた学校も多くなっています。
教育SNSでは、日々の連絡や宿題の管理、災害時の安否確認などを行うことができます。連絡網よりスピーディ、かつ簡単にさまざまな情報をやりとりできるので便利ですね。
他にも、先生同士のコミュニケーションをはかる教員用SNSもあります。
他のクラスや、場合によっては他の学校の先生ともコミュニケーションが取りやすくなるため、学校間の連携や先生同士の助け合いが活発になります。結果的に、教育の質が高くなるというわけです。
EdTechで先生の負担が減り子どもたちに良い影響が!
EdTechの導入は、子どもたちだけでなく、先生方にとってもメリットがあります。例えば、埼玉大学附属小学校では、EdTechの活用により、先生方の残業時間が年間587時間も減ったそうです。- 保護者への連絡をデジタル化し、プリント配布の手間を削減
- 欠席連絡や学校評価アンケートをアプリで処理
- 教材作成や授業準備の効率化
- 先生同士で授業改善について相談しやすくなる
これらの取り組みにより、先生方は子どもたちと向き合う時間や、より良い授業の準備に時間を使えるようになります。
「先生の仕事は大変」と言われがちですが、EdTechによって働く環境が改善されれば、より多くの優秀な先生が教育現場に集まってくるかもしれません。大切な子どもたちを預ける親として、これはとてもうれしいことですね。
まとめ
EdTechは、決して「デジタル機器を使えばいい」という単純なものではありません。テクノロジーの力を借りて、子どもたち一人一人により良い学びを提供すること。そして、先生方がより子どもたちと向き合える環境を作ること。それが、EdTechの本当の目的なのです。まだ発展途上の分野ですが、子どもたちの未来のために、私たち保護者も関心を持って見守っていきたいですね。
参考:
未来の教室〜learning innovation〜/経済産業省
東京すくすく/東京新聞


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド
-
文科省のGIGAスクール構想とは?小学校に1人1台タブレットはいつから?
文部科学省が進める「GIGAスクール構想」により、小学校では1人1台のタブレット端末が当たり前の時代に。本記事では、GIGAスクール構想のねらいや導入の背景、学校教育にどんな変化がある...
-
STEM教育とは?特徴・メリット・家庭で始める方法をわかりやすく解説
21世紀型の新しい教育「STEM(ステム)教育」が世界各国で導入され始めています。その具体的な内容は?STEAM(スティーム)教育とは何が違う?日本のSTEM教育の現状は?くわしく解説...
-
ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説
2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説...

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
クラウドとは?基本の仕組みから子どもへの影響、安全な使い方まで徹底解説
スマートフォンやタブレットが普及し、子どもたちの生活にも「クラウド」が自然に入り込む時代になりました。家庭や学校で活用される一方、仕組みや安全性がよくわからず不安に感じる保護者も少なく...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
IoTとは?身近な活用例から教育への影響までわかりやすく解説
IoTは「モノのインターネット」と呼ばれ、家電や車、学校の設備などがネットにつながることで暮らしや学びを便利にしています。実は教育現場でも、IoTが子どもたちの学習環境づくりに役立って...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
レゴ®が子どものSTEM教育におすすめの理由 オンライン&通信教育で学ぶ方法
組み合わせや工夫次第でいろいろな物を作って遊べる「レゴ®ブロック」。知育玩具として選ぶ保護者も多く、STEM教育に最適な教材として、教育の現場でも活用されています。この記事では、STE...
2024.11.06|コエテコ教育コラム
-
子ども向けノートパソコン|選び方、注意点からからおすすめ機種まで
タブレットの方が割安でも、本格的に学ばせたいならパソコンがいい?と考える保護者も多いのでは。 ここでは子ども向けノートパソコンの選び方からおすすめ機種までご紹介! 「パソコン選びは...
2025.05.21|コエテコ byGMO 編集部
-
Blenderとは?基本の使い方や特徴、活用事例3つを徹底解説
Blenderは、無料で利用できる高性能な3DCGソフトとして、初心者からプロフェッショナルまで幅広いユーザーに支持されています。モデリングやアニメーション、レンダリングといった多彩な...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部