デジタル・シティズンシップ教育とは?デジタル社会でより良く生きる「新しい学び」へ

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
これまでは「こんな危険があるよ!約束を守らないと危ないよ!」と、どちらかといえば抑制する教育を行ってきました。しかし、最近は「きちんと使い方を知った上でデジタル社会で自分の能力を発揮し、より良い社会を担っていきましょう」というデジタル・シティズンシップ教育への注目度が高まっています。
情報モラル教育からデジタル・シティズンシップ教育へ。今回の教育トピックでは、親であるわたし達も知っておきたい「新しいポジティブなデジタル教育の流れ」について見ていきましょう!
デジタル・シティズンシップとは

デジタル・シティズンシップとは、デジタル技術の利用を通じて、社会に積極的に関与し、参加する能力のこと。
デジタル・シティズンシップ教育とは、優れたデジタル市民になるために、必要な能力を身につけることを目的とした教育。引用:安心安全な利活用とデジタル・シティズンシップ教育/文部科学省/豊福晋平
なぜ今「デジタル・シティズンシップ教育」が注目されているのか

多くの親が、子どもひとりに1台の端末配布が進む中で「ネットで変なものを見ないか」「ネットいじめが起きないか」と不安を持っているのは事実です。
これまでも、子どもにいつからスマホをもたせるか、SNSを使わせるかは家庭の悩みでした。ところが学校から端末が配布されたことで、家庭の問題だけでなく「学校の教育はどうなっているのか」きちんと管理し、子ども達の安全を守れるのかへと関心が広がりました。
学校も情報モラルとしてインターネットの危険性を子ども達に教え、たとえば警察署からサイバー犯罪対策の担当者がきて「SNSのリスク」などを話す授業も行われています。

禁止するだけでは本当に必要な力が育たない面も……
すべての情報モラル教育がそうだと言うのではありません。しかし、「危険がひそんでいるよ」と警告し、だから次のことを守りなさいとルールを提示し、約束は守りましょうという「情報モラル教育」が実際にはとても多いんですね。
もちろん、危険を教えるのは何より大切なのですが、「(インターネットやオンラインに)さわるな危険!」とまで恐れてしまうことになると、ちょっと微妙です。「規則で規制する」やり方のみでは、学びに広がりがありません。
危険について教えるだけでなく、いっぽうでデジタルツールの良い面を知り、上手に活用する方法を知ること、さらには「善き社会の善き担い手になるために」という背景まで子どもたちに教えたいのです。
そこで注目されているのが、抑制する指導から、より積極的で前向きにデジタルツールを使おうという考え方です。
これまでの情報モラル教育とは

これまで教育現場で行われてきた情報モラル教育について少し見ていきましょう。
情報モラルとは、情報化社会で適切な活動をするための倫理。特にインターネットの利用によって自らを危険にさらしたり、他者を害したりしないようにするための考え方や道徳上の規範を指す。情報倫理。引用:デジタル大辞泉/小学館
たとえば、文部科学省では令和2年に情報モラル教育のひとつとして「インターネットにつなぐとき、守ってほしいこと、大切なこと」というリーフレットを出しています。

実際に、こうした知識を得ることはとても大切です。家庭でも「パスワードは、どんなに仲良しでも、友達に教えてはいけないんだよ」と繰り返し教える必要はあります。
これまでの情報モラル教育は、基本的にはこのように「○○は危険だからやめましょう」と抑制の面が強くありました。でもリスク管理をするだけでは子どものデジタルスキルは伸びない、自ら考えてデジタルツールを活用するところまで進まない……悩ましいところです。
情報モラルからデジタル・シティズンシップ教育へ

デジタル・シティズンシップはアメリカで始まり、2015年には国際教育テクノロジー学会が定義を発表。情報モラル教育の内容に「これからはちょっと違うんじゃない?もっとデジタルを上手に使おうっていう教育も必要なのでは?」という声が少しずつ日本でも広まりました。
「情報モラルは個人個人が気をつけること、安全に利用できるように守るべきことを知ること」であるのに対して、デジタル・シティズンシップ教育は少し違います。
「正しく理解して、もっと便利で、楽しく、幸せな社会生活ができるように活用する力をつけよう。その力を社会に役立てよう」というポジティブで積極的なデジタルの学び、それがデジタル・シティズンシップ教育です。
危険を回避する、健康とのかかわりを理解する、という安全の倫理としての認識が示されている「情報モラル」と、ICTの善き使い手となり、情報社会を構築する善き市民となることを目指す「デジタル・シティズンシップ」少しわかりづらいかもしれません。そこで、日本で情報モラルの教育を受けた子がアメリカのデジタル・シティズンシップ教育を見た感想を載せるので、ぜひ見てください。
引用:デジタル・シティズンシップとメディアリテラシー/スマートニュース
日本の情報モラルの授業は”大人が”決めた約束を守ることを教えているのに対して、アメリカのデジタル・シティズンシップ教育では”自分で”行動するスキルを獲得させるものだと感じました。日本の授業では当事者意識が育たないと感じますし、自分で考えて行動することを想定出来ていないと思います。引用:デジタル・シティズンシップとは何か/GLOCOMワークショップ:法政大学
今の情報モラル授業では多くの子どもたちが上記と似たような印象を持つでしょう。
それは家庭でも同じです。「LINEは友達とのトラブルにつながるから禁止!」とすれば、いわゆるSNSのトラブルは避けられるかもしれません。でも、子どもの年齢が上がれば、親がどう言おうとLINEは使うでしょうし、Twitterも見るでしょう。見るだけでなく発信する側にもなるでしょう。

ごく幼い頃からデジタルツールに触れて育っているデジタルネイティブ世代
ソーシャルメディア(You Tubeや口コミサイト、TwitterやFacebook、Tik Tokなど)をコミュニケーションツールとして「日常的に利用する」デジタルネイティブ世代の子どもたち。それらの危険性だけを指摘し抑制する、制約をかけるだけの教育では足りないのかも?と少しずつ、みんなが気づいてきているのではないでしょうか。
だからこそデジタル・シティズンシップへの関心が高まっているのです。
デジタル・シティズンシップ教育の実践
デジタル・シティズンシップ教育では、「デジタル環境に積極的、批判的、人間の権利と尊厳を尊重した社会参加を実践する」となっています。「人間の権利と尊厳を尊重した社会参加」はわかりづらい・・・。どうやって子どもに教えるの?
若者は「デジタルネイティブ」でも、新しいテクノロジーが生活にもたらす影響について、市民・社会 の一員として理解しているとは限りません。また、テクノロジーの恩恵を受ける人と、中途退学やいじめ、ネット荒らし、過激化の犠牲になる人との間に格差が広がっています。シティズンシップは市民性、とか市民権という意味があります。デジタル・シティズンシップは、デジタル能力を適切に使用するだけでなく、社会の一員としてより良い生活や社会をめざして力を発揮していこう!という意味も含んでいます。
教育は、若者がインターネットのリスクや落とし穴から身を守るだけでなく、有能なシティズンとして、社会のためにデジタル技術を積極活用する方法を理解させ、若者たちの能力習得を支援する重要な役割を担っています。
デジタル・シティズンシップ教育を実践している学校はまだまだ少ないようですが、たとえば岐阜市ではすでに取り組みが始まっています。

このような取り組みをスタートしている自治体や学校も少しずつですが増えてはいます。とはいえ、デジタル・シティズンシップ教育はまだまだ認知度も低いですね。
学校が行動を起こしてくれるのを待っている間に、子どもはどんどん成長していきます。
親であるわたし達も、デジタル・シティズンシップを体系的にきちんと子どもに教えることはできなくても、考え方の一端を知ることが大事ではないでしょうか。
そして、危険だから使わせないのではなく、親がまだ子どもを見守ることができる年齢のうちに「使ってみて失敗して危ないなと感じて、どう使うのが良いのかを考えて覚える」ようにできたらいいですね。
家庭でもデジタル・シティズンシップが学べる教材
米国Comonnsense Education財団が制作したデジタルシティズンシップ教材動画に日本語字幕をあわせた教材を紹介しましょう。デジタル・シティズンシップ教育の普及に力を注いでいる豊福晋平さんにより公開されています。【個人情報とその人らしさの情報】

「あなたの好きなものの情報をネットで共有すれば楽しい。面白いことを共有すれば楽しい思い出を残すことができる」

「でも共有する前にちょっと考えよう。名前や住所、誕生日であなた自信を見分けられる。これは個人情報だからネットで共有してはダメ」
非常によくできていて、4〜5歳の幼児から思春期の子どもたちまで広く対象としています。
たとえば、上記は「個人情報とその人らしさ」の動画です。その人らしさの情報はいいけど、個人情報を共有することはダメなこと。情報を友達と共有するのか、周囲の人と共有するのか、それとも世界中の人と共有するのか「さぁ、よく考えて!」と問いかけています。
インターネットで発信する楽しさも示した上で、危険なことについても指摘し、なぜダメなのか、何はよいのか、最後に「考えてみて!」と問いかけているところがポイントです。
いくつかの動画は日本語字幕や吹き替えにも対応しています。ぜひ親子で視聴してみてください。
CCライセンスに基づき、米国Comonnsense Education財団が制作したデジタルシティズンシップ教材動画に日本語字幕をつけています。オリジナルの教材はこちらにあります。なお、こちらの教材群は授業研究用に限って提供しているものです。リンクや二次配布はご遠慮ください。 https://www.common...

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNoOLCJNPgDdox0vBJ-V4FMyDLWUob829 >
変化していく社会と子どもたちの未来に向けて

最後に、こちらの表をご覧ください。

これからデジタルは日常であり、デジタルツールは文具であるとしています。
親であるわたし達も「ネットは危ない」と言うだけでなく、危険性は充分に子どもと共有しながらもデジタルツールをどう使っていくかを共に考える時間を持つべきなのかなと感じます。
善き社会の担い手になる、とは社会性を育むことでもあります。
他人を尊重することや、自分たちの権利・義務・責任や、多様性を受け入れること。社会の中で生きる「ひとりの人間」としてどうあるべきか、どうなりたいか、どうしたらいいのかを、保育園や幼稚園から小学校などで教育を受け、仲間と協働しながら身につけていくものです。家庭でも教えていくべきことです。
その中に、デジタル能力も含まれている。欠かせないスキルとなっているのです。
社会は常に変化しています。今は凄まじいスピードで変化する時代と言われています。そんな時代であっても、子どもたちが未来に向けて、変化を追い越すくらいに大きく育ってほしい。そのためのデジタル教育が進んでいくことに期待したいですね!
参考資料
欧州評議会「デジタル・シティズンシップ教育研修資料集」坂本旬
安心安全な利活用とデジタル・シティズンシップ教育/文部科学省/豊福晋平
日本デジタル・シティズンシップ教育研究会(Facebook)
デジタル・シティズンシップとメディアリテラシー~情報モラル教育との違い~今度珠美(前篇)


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学校「宿題の量が多い!」いつやる・どうやる・どうしてる?|4月の教育トピック④
最近はドリルやプリントに加えて「タブレット端末でやる宿題」もプラスされ、新しい学習方法に親が戸惑うことも少なくありません。今回の教育トピックでは主に小学校1年〜6年のお子さんがいる保護...
2025.09.10|大橋礼
-
小学校の授業参観・学校公開「注意点は?服装は?見るべきポイントも教えて!」先輩ママの回答も紹介
今回の教育トピックでは、授業参観/学校公開で親が見るべきポイントや、場にふさわしい服装など「知っておくと役立つ情報」を詳しく解説します。 先輩ママたちの体験談も紹介するので、ぜひ...
2025.11.12|大橋礼
-
YouTubeで勉強する小学生!おすすめ勉強動画や面白くてためになる解説
今、YouTubeで勉強する子どもたちが増えています。「ねぇ、これ見て!すっごくわかりやすいんだよ!」今回の教育トピックでは、YouTubeで勉強する小学生の実態に迫り、人気がある小学...
2026.01.05|大橋礼
-
学力は世界でもトップレベル!でも?…PISA2022学力調査結果から見えてくる「子どもたちに必要なスキルとは」
PISA学力調査とは、世界中で実施されている学習到達度に関する調査です。PISA学力調査を見ていくと、世界と比較した日本の教育に関する実情がわかります。 今回の教育トピックでは、...
2025.05.30|大橋礼
-
小6の今からできる!先輩ママの「後悔」から学ぶ中学入学前に準備しておくべきこと
今中学生のお子さんがいるママたちに「中学入学前にしておけばよかったと思うことを教えて」と聞いてみました。それをもとに今回の教育トピックでは「小6で中学に入る前にしておくとよいこと」をま...
2025.12.25|大橋礼




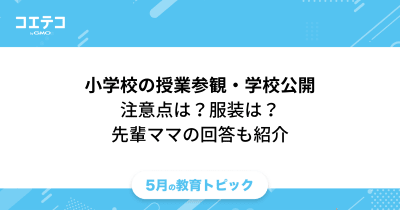
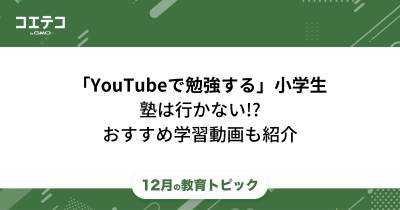
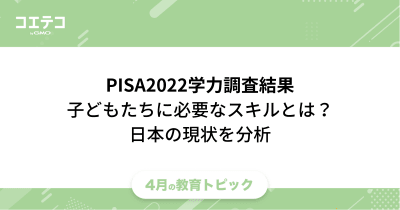

うーん難しい…。そもそもなぜ、デジタル・シティズンシップ教育が注目されるようになってきたのでしょうか?