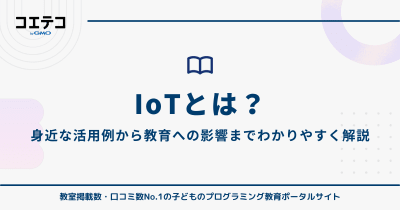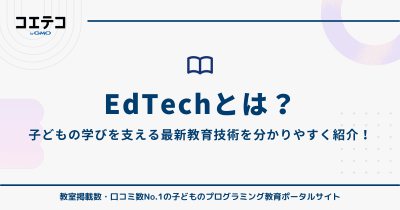デジタルネイティブとは?意味や特徴を徹底解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
彼らは情報を得る手段、コミュニケーションの取り方、消費行動など、あらゆる面でそれ以前の世代とは異なる価値観を持っています。
「どの世代がデジタルネイティブなの?」「デジタルネイティブの特徴は?」など気になる方も多いでしょう。
この記事では、デジタルネイティブの基本的な意味から、世代ごとの特徴、職場での関わり方まで、わかりやすく解説するので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
デジタルネイティブとは?【意味と定義をわかりやすく解説】

「デジタルネイティブ」とは、アメリカの教育思想家であるマーク・プレンスキー氏が2001年に提唱した言葉です。
物心ついたときから、インターネットやデジタルデバイスが当たり前に存在する環境で育った世代を指します。
彼らにとってインターネットは、特別なツールではなく、電気や水道のようなライフラインに近い存在です。
日本では、一般家庭向けにインターネットサービスが普及し始めた1990年代以降に生まれた世代が、これにあたると考えられています。
Windows 95の登場や、画像を表示できるブラウザの普及が、インターネットを身近なものにした大きな要因です。
この環境の違いが、後述する「デジタルイミグラント」世代との間に、テクノロジーに対する考え方や価値観のギャップを生んでいます。
デジタルネイティブに含まれる主な世代(ミレニアル世代・Z世代・α世代)

デジタルネイティブは、生まれた年代によってさらに細かい世代に分けられます。
ここでは代表的な「ミレニアル世代」「Z世代」そして、その次の「α世代」について解説します。
ミレニアル世代(Y世代)
ミレニアル世代は、一般的に1980年代から1990年代半ば頃までに生まれた世代を指します。2000年代に成人や社会人を迎えた世代なので、「千年紀の」を意味する「ミレニアル」と呼ばれています。
上の世代が主にパソコンでインターネットに触れていたのに対し、ミレニアル世代は思春期から青年期に携帯電話(ガラケー)やスマートフォンの普及を体験しました。
価値観としては、組織への帰属意識よりも「個」の成長を重視する傾向があるとされています。
終身雇用が崩れ始めた時代背景もあり、スキルアップのための転職や副業、独立を選ぶ人が増えました。
また、モノを「所有」することよりも、旅行やイベントなど、SNSで共有できる「体験」にお金を使う「コト消費」を好むのも特徴です。
Z世代
Z世代は、1990年代半ばから2010年代初頭頃に生まれた世代を指します。高速なインターネット通信が当たり前となり、情報収集はテキストから動画へとシフトしました。
ニールセンデジタル社の調査によれば、ソーシャルメディアへ「積極的に投稿している」と答えた割合は、ミレニアル世代が18%だったのに対し、Z世代は37%にのぼります。
この結果からも、Z世代が情報の発信や自己表現に積極的だとわかります。
一方で、幼い頃からスマートフォン中心の生活を送ってきたため、パソコンの操作に不慣れといった新しい世代ならではの課題が指摘される場合もあります。
参考:Z世代とのコミュニケーションでは、動画とソーシャルネットワークの活用方法の把握が重要~ニールセン Z世代とミレニアル世代のメディア消費状況を発表~
α(アルファ)世代
α(アルファ)世代は、およそ2010年代初頭から2020年代半ばにかけて生まれる世代を指し、Z世代の次に続きます。スマートスピーカーに話しかけたり、タブレットで動画を見たり、オンラインで学習したりするのが日常の一部となっています。
学校教育でもプログラミングが必修化されるなど、幼少期からデジタル技術を創造的に活用するスキルを身につける機会が増えています。
今後、社会の中心となっていくα世代が、どのような新しい価値観やサービスを生み出していくのか注目されるでしょう。
デジタルネイティブと何が違う?対義語「デジタルイミグラント」とは

デジタルネイティブの対義語として使われるのが、前述のマーク・プレンスキー氏によって提唱された「デジタルイミグラント」です。
「イミグラント(immigrant)」は「移民」を意味し、成人してからインターネットやデジタル技術に触れるようになった世代を指します。
デジタルイミグラントにとって、デジタル技術は後から学習した「外国語」のようなものです。
一方、デジタルネイティブにとっては生まれながらに話す「母国語」となります。
この感覚の違いが、コミュニケーションや仕事の進め方の世代間ギャップの要因と考えられています。
デジタルネイティブの7つの特徴【価値観・行動様式】

デジタルネイティブには、これまでの世代とは異なるいくつかの特徴的な価値観や行動様式が見られます。
ここでは代表的な7つの特徴を紹介します。
特徴1:情報収集は「検索」が当たり前
何かを知りたいとき、まずスマートフォンやパソコンで検索するのが基本です。彼らは「まず自分で考える」よりも「まず調べて情報を集め、それから考える」方が効率的と考えています。
情報の正確性を見極めるリテラシーは必要ですが、このスピード感は大きな強みです。
特徴2:オンラインでのコミュニケーションに抵抗が少ない
デジタルネイティブは、SNSやチャットツールを通じて、オンライン上で人間関係を築くことに抵抗がありません。「春から〇〇大学」のようなハッシュタグで入学前に友人を作るなど、上の世代から見ると大胆に思える行動をとる場合もあります。
特徴3:SNSでの情報発信や自己表現に積極的
自分の意見や体験をSNSで発信し、他者からの「いいね」やコメントを通じて承認欲求を満たす傾向があります。単なる自己満足ではなく、社会とのつながりを確認する重要な手段となっています。
特徴4:「所有」より「体験(コト消費)」を重視
高級なモノを所有することよりも、旅行やフェス、グルメなど、その場でしか得られない体験を重視します。体験をSNSで共有するまでがセットになっている場合が多く見られます。
特徴5:多様な価値観を尊重し「個」を大切にする
インターネットを通じて世界中の多様な文化や価値観に触れて育ったため、自分と異なる考え方を受け入れられます。組織のルールよりも個人の働きやすさやライフワークバランスを重視する傾向があります。
特徴6:コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを重視
限られた時間やお金を有効に使いたいという意識が強く、コストパフォーマンス(コスパ)やタイムパフォーマンス(タイパ)を重視します。動画を倍速で視聴したり、要約サイトで情報を得たりするのも、この価値観の表れです。
特徴7:社会問題への関心が高い
SNSを通じて社会問題に関する情報に触れる機会が多いため、環境問題やジェンダー、人権問題などへの関心が高い傾向があります。共感した活動には、SNSでのシェアやクラウドファンディングへの参加などの形で、気軽に参加するのも特徴です。
企業が知っておくべきデジタルネイティブとの接し方【職場編】

デジタルネイティブ世代が社会人となり、職場でのコミュニケーションに悩む管理職や先輩社員も少なくありません。
「指示待ちで動かない」「報連相がない」などの声も聞かれますが、それは彼らの価値観を理解していないと誤解が生まれます。
デジタルネイティブとの円滑なコミュニケーションのために、企業や上司が知っておくべきポイントを3つ紹介します。
ポイント1:テキストベースのコミュニケーションを基本にする
彼らは電話や対面の会話を「相手の時間を一方的に奪うもの」ととらえる場合があります。急ぎでない用件はビジネスチャットなどを活用することで、彼らは自分のタイミングで確認・返信でき、心理的な負担が減ります。
ポイント2:指示は具体的かつ明確に
曖昧な指示では、何をどこまですればよいのか分からず、動けなくなってしまう場合があります。業務の目的、背景、具体的なゴール、期限などを明確に伝えて、彼らが安心して業務に取り組めるようにしましょう。
ポイント3:1on1など対話の機会を設ける
テキストコミュニケーションを好みつつも、対話を軽視しているわけではありません。定期的に1on1ミーティングなどを設定し、キャリアの悩みや業務の相談に乗ることで、信頼関係を築けます。
その際は、一方的に話すのではなく、彼らの意見に耳を傾ける姿勢が重要です。
デジタルネイティブ世代の子どもの強みを伸ばすには?

これからの社会を生きるデジタルネイティブ、α世代の子どもたちは、生まれながらにして優れたITスキルや情報収集能力を持っています。
強みをさらに伸ばし、将来に活きる力に変えるために注目されているのがプログラミング教育です。
プログラミングを学ぶことは、単にコードが書けるようになるだけではありません。
目的を達成するためにどうすればよいかを考える「論理的思考力」や、エラーを乗り越えて新しいものを創り出す「問題解決能力」「創造力」を育めます。
これらは、デジタルネイティブ世代が持つ情報収集能力やITツールへの適応力とかけ合わせることで、大きな相乗効果が期待できるスキルです。
オンライン学習との親和性が高いデジタルネイティブ世代にとって、プログラミングは楽しみながら未来の可能性を広げられる、最適な学びの一つと言えます。
デジタルネイティブにおすすめのオンラインプログラミング教室3選

デジタルネイティブはネットを駆使する能力に長けているため、オンライン学習やオンライン教室との親和性が高いという特徴もあります。
ここでは、デジタルネイティブにおすすめの子ども向けオンラインプログラミング教室を紹介します。
多くのスクールで無料体験が用意されているので、まずはお子さまに合うかどうか試してみるのがおすすめです。
N Code Labo

未経験者は基本的なPC操作やタイピング、プログラミング基礎、中級者はコードを書くプログラミングや3Dゲーム制作、上級者はオリジナルゲーム制作や高度なスマホアプリ、AI・機械学習などを学習できます。現役エンジニアが監修するオンライン教材を活用して自宅で学べるため、自分のやりたいことに合わせて学習を進められるのが魅力です。
なお「自宅でなく教室で指導を受けたい」という人のために、新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・天王寺の5教室では通学コースも開講されています。
LITALICOワンダーオンライン

スタッフ1人に対して生徒は1人という少人数制を採用しており、操作方法やプログラミングで分からないところがあればすぐに質問できる環境が整っています。自宅に居ながら楽しく学べるだけでなく、もっと取り組みたい場合はそのまま自宅で活動制作を続けられるため、学びが深まりやすいでしょう。
受講できるコースには、ゲーム&アプリプログラミングコース、ゲーム&アプリエキスパートコース、ロボットテクニカルコース、3DCGコース、マインクラフトクリエイトコースがあります。
デジタネ

1つの動画は5分~10分程度で、実際にゲームを作る体験を通じて学習を進めていくのが特徴。自ら創造し、形にしていく体験を通じて「好きだ」「得意だ」と感じるところを伸ばし、生きるために必要な考える力・造る力・伝える力を育んでくれます。
またゲームからさらにステップアップしたい子ども向けに、JavaScriptやHTML&CSS、ネットリテラシーに関する学習教材も提供されています。
まとめ:変化を理解し、世代間の強みを活かそう

デジタルネイティブ世代は、生まれたときからデジタル技術に囲まれて育ちました。
その価値観や行動様式は、上の世代から見ると、理解しがたいかもしれません。
しかし、彼らはグローバルな視点を持ち、変化への適応力も高いなど、多くの強みを持っています。
一方的に評価するのではなく、その背景にある社会の変化を理解し、お互いの強みを活かすことで、よりよい未来を築けるでしょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どもに教えたいフェイクニュースの見分け方
インターネットの世界は信憑性が低いものや、中にはいわゆるフェイクニュースもあり、情報を選択するスキルが必要とされています。 今回の教育トピックでは特にフェイクニュースにフォーカスし、...
2025.09.10|大橋礼
-
IoTとは?身近な活用例から教育への影響までわかりやすく解説
IoTは「モノのインターネット」と呼ばれ、家電や車、学校の設備などがネットにつながることで暮らしや学びを便利にしています。実は教育現場でも、IoTが子どもたちの学習環境づくりに役立って...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
ビッグデータとは?基礎知識から教育分野での活用事例まで徹底解説!
ビッグデータとは?SNSの普及により耳にすることの多くなった「ビッグデータ」。この記事ではビッグデータの具体的な活用法方法やメリット、デメリット、リスクなどを分かりやすく解説します。
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
デジタル教科書とは?2025年から本格導入がスタート!メリット・デメリットや今後の展望も解説
デジタル教科書とは、紙の教科書の内容をデジタル化し、タブレットやPCで閲覧できるようにしたものです。単に紙の内容を電子化するだけではなく、動画や音声など多様なメディアを掲載したり、書き...
2025.09.10|大橋礼
-
EdTechとは?子どもの学びを支える最新教育技術を紹介!
オンライン授業やタブレット学習など、教育現場で急速に広がる「EdTech(エドテック)」。これは、IT技術を活用して子どもの学びを進化させる新しい教育の形です。この記事では、EdTec...
2025.06.11|プログラミング教室ガイド