【小学生】テストの点数が良くても「通知表の成績・評価が低い!?」その理由

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
「テストの点数は良いのになぜ?」
「通知表の基準がよくわからない」
「テストが良くても通知表の成績が上がらない、じゃあどうしたらいいの?」
こうした話題は親同士でよく聞かれるところです。
今回の教育トピックでは「テストの点数が良くても、なぜか通知表の評価はイマイチ」な理由を探ります。
テストの点数が良くても通知表・成績表の評価が上がらない理由5つ
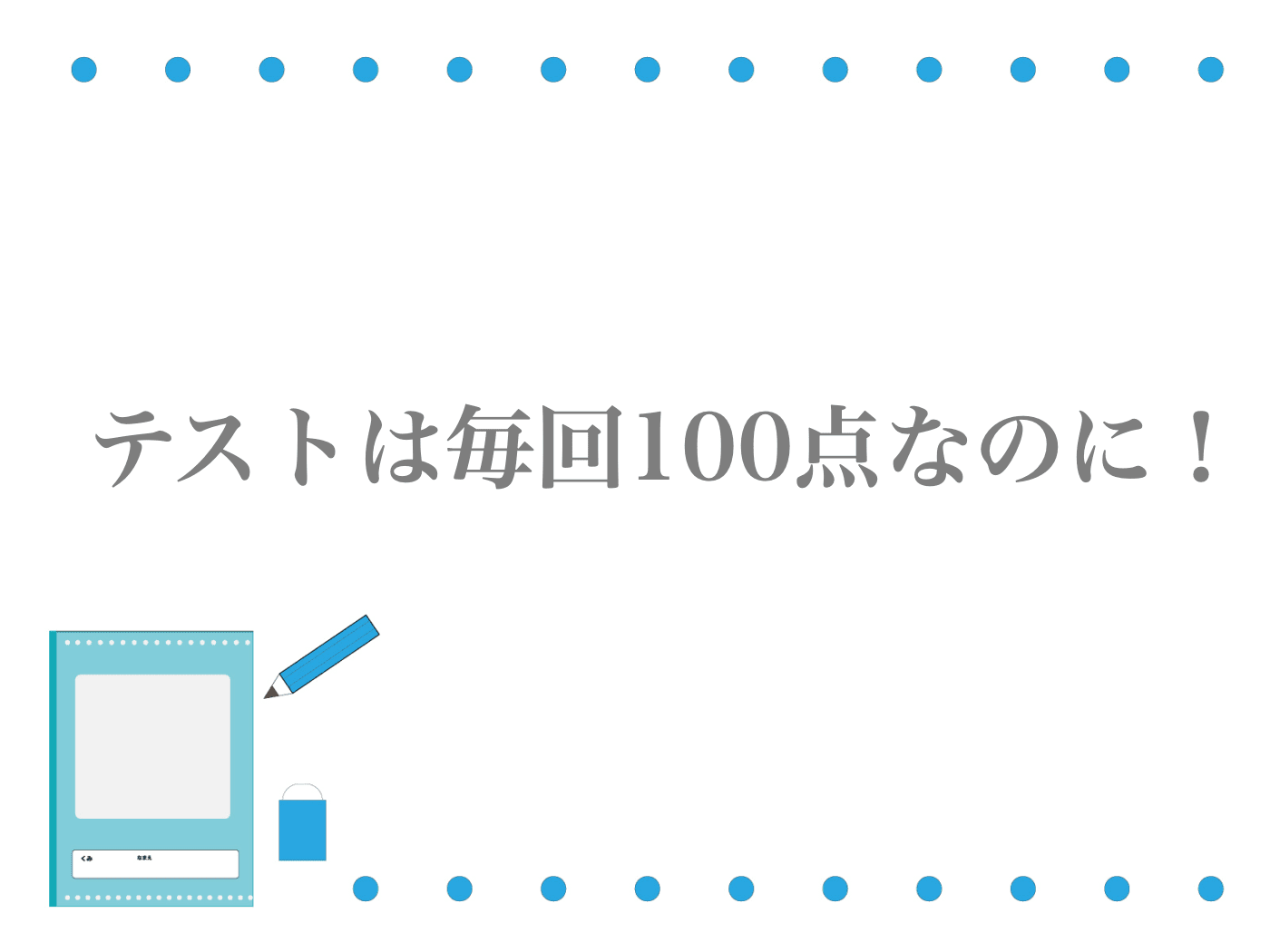
- 宿題をやっていない(出していない)
- 忘れ物が多い・提出物を出していない
- 小テストなどの結果が良くない
- 授業態度が悪い
- 消極的で挙手や発言の回数がほぼない
これらの理由は後ほどひとつずつ説明します。その前に、そもそも小学校通知表の基準や評価方法について少し学んでおきましょう!
小学校「通知表」の評価について
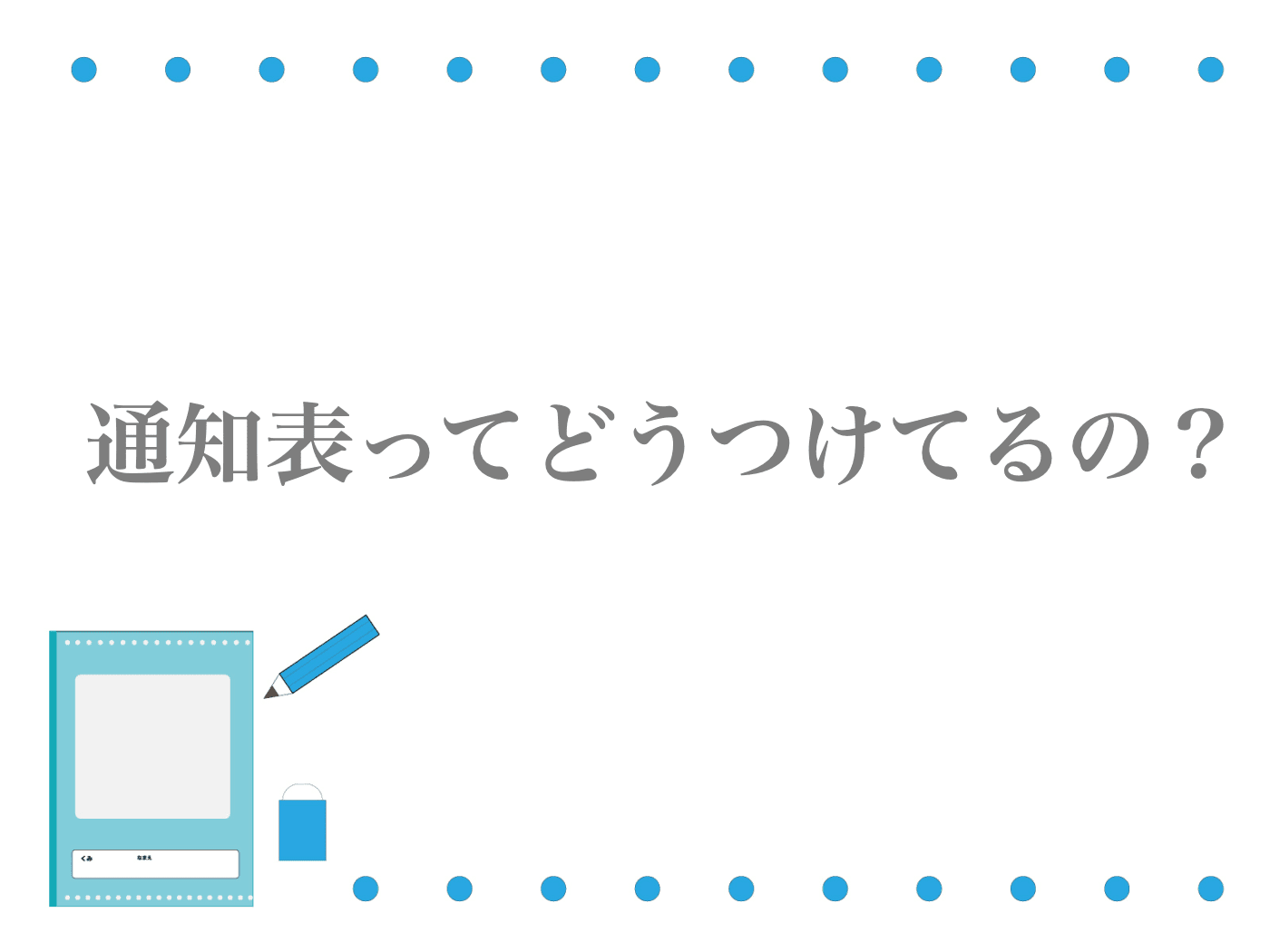
通知表の評価についてはなかなか複雑で、しかも各学校や教員によって「評価の付け方」に違いがあるのも事実です。というわけで、保護者としては大きなポイントだけ押さえておきましょう!
通知表は各学校の裁量に任されている
学校には指導要録と呼ばれる、国が定める「成績や学校の様子の記録」があります。これはたとえば転校すれば引き継がれ、中学へ入学の際には写しが提出されます。しかし基本的に保護者に開示されることはありません。いっぽうで通知表は保護者に「お子さんの学習はこんな感じですよ」と伝えるためのもので、法的な規定はありません。ですから、評価も「ABC」もあれば「◎○△」もあるし、「通信簿」「あゆみ」など名前もバラバラです。
通知表は「絶対評価」である

以前、通知表は相対評価(集団の中でどの位置にいるか)でしたが、今は絶対評価(目標に達成したか)* に変わっています。
相対評価では、クラスの上位○○%が「よくできる」、「できる」は○○%、「もうすこし」が○○%と割り振っていました。一方で絶対評価は「目標に達成したかどうか」で成果を評価します。
ですから極端なことを言えば、全員に「よくできる」がついてもいいわけです。しかし実際には、◎○△なら「○」が一番多くなる傾向があるのだとか。要するに、相対評価が多少なりともまじった状態ですね。
また、絶対評価になってからは逆に「クラスの10人は“よくできる”にする」とは決めていないために、目標のおきどころによってはなかなか「よくできる」がとれない傾向もあるようです。
通知表における3つの観点
通知表は、次の3つの観点から評価されています。- 知識・技能
- 思考・判断・表現
- 主体的に学習に取り組む態度
ざっくり言うと、知識や技能というのは、テストで言うところの「基本問題」です。各教科の基本を理解できているかどうかを、テストあるいはノートや提出物、授業中の発言などから判断します。
思考・判断・表現は、基本的な知識や技能を活かし、自分で考え、判断し、表現する力を評価します。ですからテストなら応用問題の範囲になります。教科にもよりますが発表や調べ学習のレポート、グループでの作品制作なども対象となります。
さらに主体的に学習に取り組む態度は、端的に言うと「自ら学ぶ意欲」となります。
文部科学省では「自らの学習状況を把握し、学習の進め方について試行錯誤するなど自らの学習を調整しながら、学ぼうとしているかどうかという意思的な側面を評価することが重要」としています。たとえば小学校の国語を一例に挙げて、次のように解説しています。

よく挙手をして発言する子が意欲的とみなされるのか、ノートをしっかりとり自分なりにまとめている子が主体的なのか。教科によっても違うでしょうし、先生の考え方にもよるでしょう。
ただ、こうした評価が「担任の先生だけの判断」に偏りすぎないよう、小学校では指導要録などを参考にしながら他の先生方や校長先生なども通知表を確認しています。
ですから評価を見て「担任の先生はウチの子が嫌いだから評価も厳しい」と考えるのはちょっと行き過ぎているのではないでしょうか。先生も人間ですから、多少なりとも主観による評価はあるにしても(そこが親としては気になるのですが!)、基本的にはテストの点数のほか、さまざまな観点から客観的に評価を決めています。
参考:児童生徒の学習評価の在り方について(報告)/文部科学省
テストは良くても通知表の成績は真ん中!子どもの学習を見直してみよう

ではテスト結果は良いのに、なぜか通知表の評価が上がらない、成績が良くならない理由を見ていきましょう!
宿題をやっていない

宿題は、たまに忘れるくらいならともかく、「この子はよく宿題を忘れるな」と先生に印象づけてしまうとマイナス要素になります。また宿題の内容も、先生によっては「雑にやっているか、きちんとやっているか」を見ている場合もあります。
いずれにしても小学校の多くで宿題はほぼ毎日出ており、それらを提出していないとテストの結果がいくら良くても「◎」をつけないケースはよくあります。
| CHECK★宿題は必ず行い期限どおりに提出しよう! |
宿題をするのは、小学校のうちに身に着けたい基本中の基本ともいえる学習習慣です。きちんと宿題は行い、そして期限通りに提出することが大切です。中には「算数ドリルの宿題は提出した」けれど、「間違いを直して、翌日に再提出」を忘れてしまうこともあるので、親の声がけと宿題チェックは必須ですね!
最近はドリルやプリントに加えて「タブレット端末でやる宿題」もプラスされ、新しい学習方法に親が戸惑うことも少なくありません。今回の教育トピックでは主に小学校1年〜6年のお子さんがいる保護者に「宿題の量はどれくらいか、いつ、どのようにやらせているか」を聞いてみました。 さらに先輩ママたちに「こんな方法で宿題をやらせた」というアドバイスも貰いました!
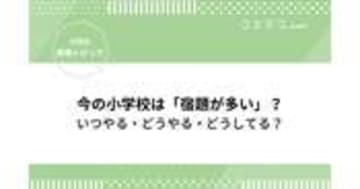

2025/09/10

忘れ物が多い・提出物を出していない
提出物を重視する先生は少なくありません。宿題に限らず、たとえば「日記」だとか「家庭科で終わらなかったところは次の授業までに家でやってくる」といったことをきちんと達成しているかどうかも「評価に対する影響」があると考えておきましょう。学習と関係はないように思えますが、忘れ物が多いこともマイナス要素になります。教科書を忘れた、図工で絵の具セットを忘れた、体育で体操着を忘れた、では授業に参加できません。授業に「意欲的ではない」と判断されてしまうかもしれません。
忘れ物の多さや提出物を期限どおりに出さないといったことは、学校生活のルールを守れていないことになります。いくらテストの結果が良くても「あの子はだらしがない」という印象が強ければ、評価が厳しくなるでしょう。
|
CHECK★時間割と明日の持ち物について確認しよう! |
低学年のうちは一緒に、しばらくたったら本人に任せるとしても「時間割は揃えたの?」「お手紙はない?」と声をかけ、時々はノートを見てみましょう。先生が「見ました」というハンコやシールを貼っているページがあるのに、途中が抜けていたりしたら「あれ?ここは?」と聞いてみてもいいかもしれません。
学校からのお便りには、今月に必要な持ち物や準備するものが載っているはずですから、要チェック。子どもと一緒にカレンダーなどに書き込むなど家庭ごとに工夫をしてみるの良い方法です。
小テストなどの結果が良くない
テストは、いわゆる市販のプリントテストがすべてではありません。中学年から高学年になると、朝テストだとかドリルの単元ごとの小テスト、先生手作りの復習テストなどが増えてきます。プリントテストの成績は良くても、日頃の「漢字テスト」で点数が悪いと、良い印象は与えられません。

|
CHECK★小テストについて子どもに聞いてみよう! |
プリントテストは親に見せますが、毎日のようにある小さな紙に書くテストなどは年齢と共に親に見せない子も増えてきます。
ランドセルをチェックしたら、底の方にクシャクシャの紙がいくつも見つかったことがありますよ。開いてみると「漢字テスト」「計算マラソンテスト」といった10問程度のミニテストでした!
周囲のママ友から「毎朝、漢字テストやっていて、満点をとると教室に貼ってある表にシールを貼るのよ、うちの子はシール少ないから怒っちゃったわよ。この前の公開授業で見なかった?」なんて話を聞いて、あわてて子どもを問いただすなんてことも実際にはよくあります。
小テストは基本、前日にちょっと復習をすれば満点をとれることがほとんどです。親の声がけと10分の復習だけで結果が変わるので、ぜひ声がけをしてみてください。
オンライン塾を検討するときに「本当に小学生は授業に集中できるのか?」「オンライン学習塾に通って学力は上がるのか?」と不安になることもあるでしょう。 この記事では、小学生におすすめのオンライン塾やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。


2026/01/05

授業態度が悪い
教科書も出さずに机の上に足を乗せているなら、わかりやすく「態度が悪い」ですよね。しかし、教科書は開いていても上の空だとか、グループ学習で周囲と協力しないとか、鉛筆をぐるぐる回して「先生が写しなさいといった文章を書いてもいない」といった行為も、授業態度が悪いと判断されることが多々あります。その程度や状況にもよりますが、いくらテストの点数が良くても「授業に集中していないのは困ったこと」としてマイナス評価につながります。
逆に言うと、たとえば「進められる子は進めていいよ」と言われているドリルだとか、宿題ではなく本人に任せている「読書ノート」だとかをどんどん行っていると「この子はよくがんばっているな」と学習意欲として評価されやすい面はあります。
|
CHECK★面談で先生に聞いてみよう! |
授業の様子は親にはわかりません。子どもはおおむね「良いようにしか伝えない」ですから、本当のところがわかりませんね。
面談の時を利用して授業態度についても聞いてみましょう。家ではそうでもないけれど学校では落ち着きがないということもありえます。「家庭でどの辺りを注意したほうがよいですか?」「授業の様子で先生が気になる点はございませんか?」と聞くことで、具体的に何がいけないのか、どこを気をつけたらよいのかがわかります。
あわせて家庭の様子も伝えることで、先生もお子さまの行動への理解が深まります。
消極的で挙手や発言の回数がほぼない
性格的な問題なので、挙手や発言の回数をあえて評価の基準にはしないという先生も実際にいます。しかし、印象としては積極的に授業へ参加しようとする姿勢を「良し」とする先生が多いのもまた、事実です。親の視線で考えると、授業参観などで(なんでウチの子は手を挙げないのかしら!問題はわかっているのに!)なんてヤキモキすることがありますね。授業に限らず、係ぎめがあると聞くと「学級委員に立候補してみなよ」などと子どもをせっつくようなことも口にしがちです。
どこかで「積極的なタイプ=リーダーシップがありデキるタイプ」というイメージを持っていませんか?そして同じことが先生にも言える傾向はあります。前述した通知表の話で「主体的に取り組む」評価の観点がありましたが、積極的な行動はとてもわかりやすく「主体的」な印象を与えます。
でも、おとなしくても粘り強く勉強する子もいるでしょう。グループ学習では目立たたないけれども時間のかかる地道な作業をきっちりこなす縁の下の力持ちもいます。
このような姿勢をよく観察している先生もいます。とはいえ、やはりわかりやすいのはよく発言する子や質問をする子、グループをまとめている子の姿です。
|
CHECK★「発表が上手だね」と褒めて自信をつけさせよう! |
なかなか難しいところですが、消極的な子に無理強いするよりは、良い部分を褒めて自信をつけさせるほうが、遠回りのようで近道かもしません。
小中高を通じて、教育現場ではプレゼンテーション力の育成により力を注いでいます。自ら挙手することは少なくても、普段は恥ずかしがり屋さんでも、発表が上手にできると「表現」の評価が高まる可能性もあります。
おうちで練習してみて「とてもわかりやすいよ、うまいと思う!」と褒めてあげてください。「人前で話すと緊張するよね、ママもそうだよ」と励まし、たとえば、人の字を3回書いて飲み込むなど、昔からある「緊張ほぐし」の技を教えてあげたらどうでしょう。
もともとの性格によるところも大きいですし、おとなしく引っ込み思案だからといって将来困るというわけでもありません。それぞれの良さに気づき、良いところはいっぱい褒めましょう。加えて、これからは自分の意見を伝える力が必要な時代ですから、少しずつ無理なくそのスキルが身につくように導いてあげたいですね。
点数や偏差値だけではない「評価」について関心を持とう!
親としては、まずテストの点数が気になるものです。受験をする子や中学へ入学すれば、偏差値という数字も気になることでしょう。通知表における観点のひとつとしてご紹介した「主体的な学び」のように、最近は自ら考え、課題を見つけ、試行錯誤をしながら解決策を求めることや、周囲と協働して答えを見つけていき、みんなにわかるように発表をするといった「教科書だけにおさらまない体験学習」の重要性が高まっています。
「教科書の内容を理解し、応用した問題が解ける」ことは、小学校のように基礎を固める時期には必須です。しかし同時に、思考力やコミュニケーション力、プレゼンテーションスキルも求められています。デジタル化が進み、時代が大きく変化する中で、子どもたちが生き抜く力や自ら歩む力をつけるために、新しい取り組みがどんどん始まっています。
「テストの点数は良いのに成績が上がらないなんて、おかしいなぁ」
そう思ったら、子どもの生活習慣や学校での様子などにより一層、気を配って見守ってみましょう。そして授業の内容や評価も含めて、学校自体も「時代」に合わせて、バージョンアップをしながら変化していることに関心を持って見ていきましょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学校のカラーテスト・業者テストは「100点が普通」って本当?平均点は?
業者が教科書の単元ごとに作成したカラープリントのテスト。巷ではカラーテスト・プリントテスト・業者テストなどと呼ばれ、「小学校低学年ならカラーテストは100点とって当たり前、高学年でも9...
2025.11.12|大橋礼
-
小6の今からできる!先輩ママの「後悔」から学ぶ中学入学前に準備しておくべきこと
今中学生のお子さんがいるママたちに「中学入学前にしておけばよかったと思うことを教えて」と聞いてみました。それをもとに今回の教育トピックでは「小6で中学に入る前にしておくとよいこと」をま...
2025.12.25|大橋礼
-
小学校の授業参観・学校公開「注意点は?服装は?見るべきポイントも教えて!」先輩ママの回答も紹介
今回の教育トピックでは、授業参観/学校公開で親が見るべきポイントや、場にふさわしい服装など「知っておくと役立つ情報」を詳しく解説します。 先輩ママたちの体験談も紹介するので、ぜひ...
2025.11.12|大橋礼
-
小学生の国語の教科書に出てくる懐かしい物語6選!
お子さんが音読の宿題に取り組んでいるとき、「このお話、懐かしいな」「ん?この話、初めて聞いた。これってどういうお話なの?」と感じたことはありませんか。 実は、国語の教科書に載って...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説
教育現場で、新たな評価方法として注目を集めるルーブリック。アクティブ・ラーニングが授業に導入されるようになり、ルーブリックが採用される大学や高校も増加傾向にあります。この記事では、ルー...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部





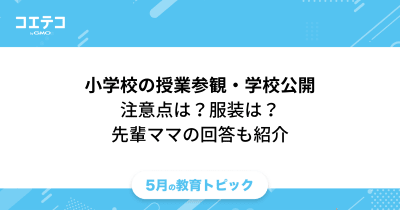


「主体的に学習に取り組む態度」というのが、イマイチわからないんですよねぇ。