小学校のカラーテスト・業者テストは「100点が普通」って本当?平均点は?
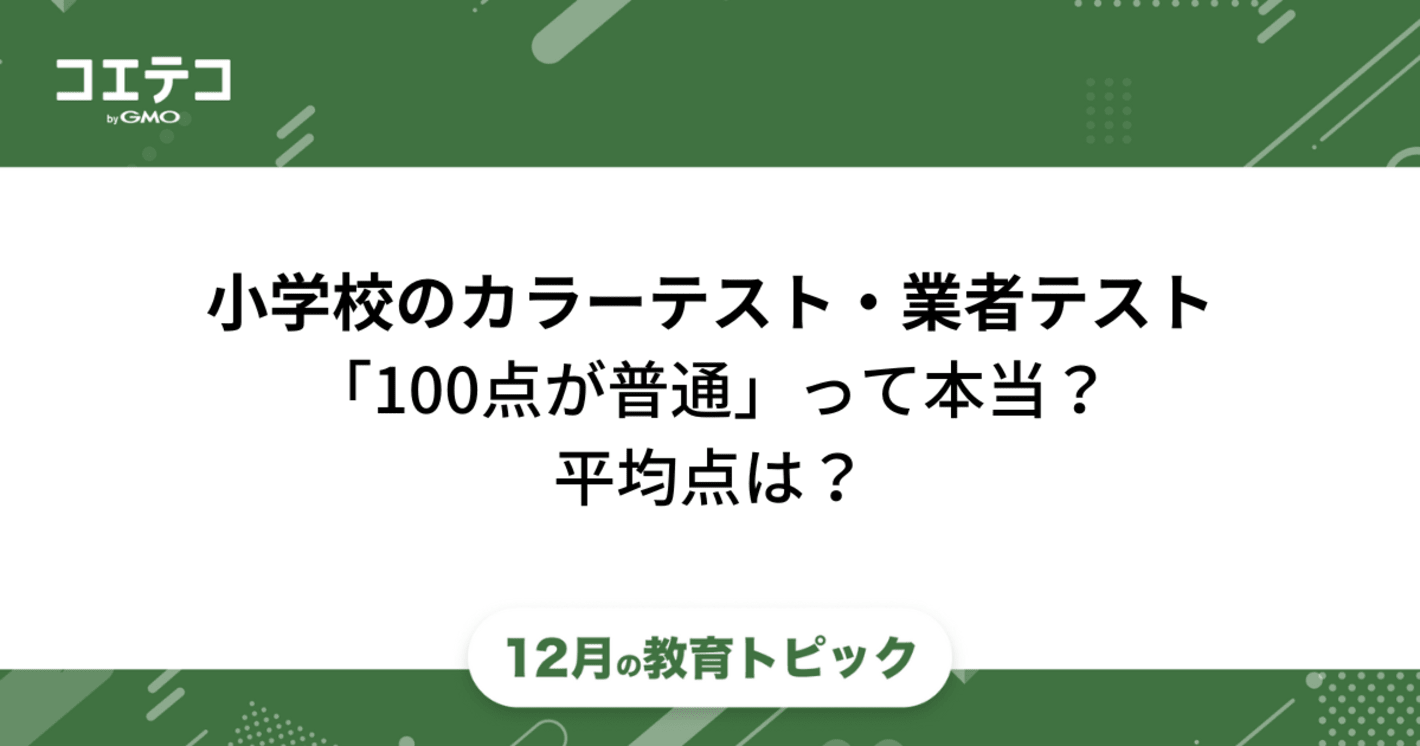
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
小学校から子どもが持ち帰ってくるカラーテスト「うーん、70点……って、どうなんだろう?」と微妙に悩むことがありませんか?
業者が教科書の単元ごとに作成したカラープリントのテスト。巷ではカラーテスト・プリントテスト・業者テストなどと呼ばれ、「小学校低学年ならカラーテストは100点とって当たり前、高学年でも90点くらいはとっていないと」なんて母親同士の会話でも話題になります。
本当に小学校のカラーテストは100点満点が当たり前なのでしょうか?何点以下だったら「ちょっとやばいよ」のレベルなのでしょうか?
今回の教育トピックは、小学校のカラーテストについて深掘りしていきます。
カラーテスト/業者テストとは

カラーテストとは、小学校で学ぶ各教科の単元が終わるごとに行われるテストです。先生手作りのプリントではなく、専門の業者が作成する文字通りカラー印刷されたテストで、目的は学んだ単元の理解度や到達度をはかるためのものです。
小学校のカラーテスト「100点」が当たり前なの!?

結論から言うと、カラーテストは100点が「当たり前」ではありません。
しかし小学校1年生から2年生くらいまでだと、90点以上をとってくる子どもが多い傾向があるのも事実です。
低学年のうちは一斉スタートで、ひらがなや簡単な計算など、入学前からある程度なじんでいる子どもが多いため、そもそも、あまり差がでません。
しかし勉強は積み上げていくものですから、算数などの難易度が上がってくる小学校3~4年生あたりから、テストの点数差に幅が出てくるようです。学年が上がるごとに少しずつ勉強に遅れが出て、追いつけずに一気にテストの点数も悪くなる子が出てくるので、平均点が下がることも多くなります。
業者のテストは普通に授業を受けていれば、単元が終わった直後に行うテストのため、8割くらいは解けることが目安となっています。そのため、一般的には「80~85点」がカラーテストのボーダーラインと言われています。
カラーテストには種類がある
カラーテストには各社が出していますが、それぞれ複数の種類があります。ここでは新学社の例を見てみましょう。基礎・基本重視の「Aテスト」

思考重視の「α(アルファ)テスト」

基礎・基本重視はテストの配点を見ると、基本問題に重点を置いています。いっぽうでαテストは思考や判断、表現への配点と基本となる知識・技能ともに100点ずつの配点です。
光文書院も見てみましょう。


基礎・基本を理解しているかを評価できる「Aテスト」、基礎・基本からチャレンジ問題も含まれる「Vテスト」、配当時間が少ない2単元を1枚におさめ、テストの実施回数を減らすことができる「Cテスト」などがあります。
このようにカラーテスト・業者テストも各社でレベルや内容が少しずつ違うものがあるのですね。
一般的には、公立小学校では基本の理解度・到達度を見る、いわゆる「難易度が低い」テストを選ぶと言われていますが、どのテストを選ぶのかは学校や先生によって違います。
カラーテストの平均点は?

カラーテストの「100点当たり前」という声は実際に多くありますし、中学受験向けの塾ではハッキリと「学校のテストは全部100点とるぐらいじゃないとダメ」と明言するところもあるようです。
カラーテストで100点を毎回とる子も、公立小学校だとクラスに数人いるのも珍しくありません。
中学受験をする子が多い地域の小学校は、高学年になってからもカラーテストで100点をとる子の割合が多くなります。そうなると平均点も上がり、(みんな100点が普通みたいに言うけど……ウチの子はだいたい70点から80点だし、算数は時々65点なんていうのもあるなぁ)なんて思うと、不安になってきますね。
お子さまが通っている小学校・クラスで、どのレベルのテストを選んでいるかによって、また学級編制によって、平均点数も変化します。
学校の授業をきちんと聞いて宿題を行っていれば、カラーテストは一定のレベルまで点数がとれる構成にはなっています。ですから一般的に平均点としては「80〜85点」と言われます。
実際に80点以上をとる子が多いのですが、先生が独自のカリキュラムで授業を行うとカラーテストの内容が必ずしも一致しない(実は根本的には学ぶことは網羅されているはずですが、出題傾向や出題の仕方が違う)と、業者テストの点数がクラス全体で少し低くなるということもあります。
カラーテストは80点以上をとっていれば「ひとまず安心」なわけですが、地域差や学校、先生によって幅はあるので注意は必要です。
テストの間違えの内容をよく見て!
単元テストは1つの問題に対する点数配分が大きいことがよくあります。ちょっとしたミスで思わぬ点数になるのもよくあります。テストが戻ってきたら「80点だからOKね」ではなく、マイナス20点の間違えた内容を親子でチェックしておきたいですね。

特定の教科で点数が悪いことが続いたら「苦手なのかな?」と少し意識をして、子どもが宿題やドリルを行う様子を見守りながら、何につまずいているのか、何がうまくいかないのかを親子で紐解いていくといいかもしれません。
テストは点数よりも「間違えた内容を分析すること」が重要です。暗記が弱いのか、時間が足りなかったのか、問題の文章をきちんと読んでいるか……間違えの内容を親子で確認することがポイントです。
テストの点数と成績の関係性

親としては、テストの点数=成績と考えがちです。文部科学省は上記のように、
- 知識技能
- 思考判断表現
- 主体的に取組む
この中で、「知識・技能」はテストの点数が影響するところです。ただしカラーテストのみではなく、日頃のミニテストや先生手作りのテストなども評価の対象となっています。
テスト等の結果に加えて、積極的に授業に参加するとかノートの内容とか宿題への取組など、さまざまな視点で「主体的に取り組む」や「思考や判断、表現の力」を評価しています。
「80点以下はヤバいから」フリマでカラーテストを購入!?

小学校のカラーテストはどうやら「みんなが満点」は大げさですが、かといって80点以下の割合が多いのは、あまりよろしくない状態といえることはわかってきました。
成績の付け方には他の要素も重要なこともわかりましたが、やはり単元ごとの業者テストの点数は親としては気になります。そのせいでしょうか、「カラーテストの点数が悪い!」と悩む保護者の中には、「それなら去年のテストを参考に勉強させたら、すぐに点数アップしそう!」と考えることもあるわけです。
というわけで、フリマやオークションで「◯◯(教科書等の業者名)令和◯年度テスト一式」と、子どもが持ち帰ってきたテストをまとめたものが売られていることもあります。
こうした販売の良し悪しや法的な解釈についてはここでは触れませんが、実際に売られていることもあるし、年の近い兄弟姉妹だと「お兄ちゃんのテストを残しておいてあるから、あれを参考にして勉強させよう」というケースもあるかもしれません。
業者のテストは教科書の内容が大幅に変わらない限りは、テスト内容も大きくは変わりません。
もちろん同じ問題は出ませんが、似たりよったりの問題がでます。ですから、去年や一昨年の「誰かが実際に小学校で受けたテスト」を譲り受けて、その問題を解けるように練習すれば、たしかにある程度、点数が上がる可能性はあるかもしれません。
でも……ちょっと待って!
単元テストは1つの問題に対する採点が大きいので、1~2つの問題を落とすと、80点くらいになることはあります。たまたま、勘違いしたり焦っていたりでミスをしたのならいいのですが、本当にわからなくて問題が解けないこともあるでしょう。

間違えた問題を見ることで、子どもが理解できていないことがわかれば、「ちょっとわからなくなってきているみたい。家でも勉強させたほうがいいかも」と早めに対応ができます。
でももし、去年のテストを参考にして「問題の内容を本当に理解はしていないけど、練習したから、そっくりの問題はみんな解けた」となったら、どうでしょうか。
テストの点数は良かったとしても「理解していないまま」であれば、積み上げていくはずの学びが抜け落ちてしまう可能性もあります。
中学に入って、小学校の基礎が実は確立されていなかったら、難しくなる教科についていけなくなるかもしれません。
小学校のうちは「基本の学力をつけること」を重視したいので、「わからないところが見つかる」テスト本来の意図を考慮すると、おすすめの方法とは言えないところです。
参考:小学生の家庭学習
大切なのは勉強のサイクルを身につけること

カラーテストは、教科書や授業の「単元」が終わるごとに行われます。つまり、その単元をきちんと理解できたかどうかをチェックするものです。
点数が悪いとつい叱りたくもなりますが、叱られた記憶から今度は子どもがテストを隠したり親に見せなくなったりすることもあります。ランドセルの底から、くしゃくしゃになったテスト用紙を発見して、「なにこれー!」とテストを握りしめて子どもを問い詰める……というのも、よくある話です。
テストで間違ったところを見つけて、直して、きちんと取りこぼしなく勉強を続けていくことが、最終的に成績アップにつながります。
授業をきちんと聞く
↓
宿題をする(復習をする)
↓
テストを受ける
↓
間違いを直し、理解できていないところを学び直す
確かに、「うわ、なにこの点数!」みたいなテスト用紙を見たら、怒りたくもなります。「だからちゃんと勉強しなさいって言ってるじゃないのよっ」とついつい声を荒らげたくもなります。
でも、ちょっと落ち着いて、とりあえず怒る前にひと呼吸してみましょう。
そして、学校と家庭学習のサイクルをしっかり小学生のうちに身につけることを第一に考えてみませんか?
参考:小学生向けタブレット学習
カラーテスト「100点」じゃなくても大丈夫!だけど
カラーテスト・業者テストは、100点をめざしたいところですが、基本的には80点以上であれば「間違えたところ」を見直す習慣をつければ大丈夫です。しかし、毎回80点以下、たとえば50点ということであれば、まず授業そのものをきちんと聞いていない、ノートをとっていない、宿題もやっていないなど他の問題もありそうです。
全体的に点数がよくないのであれば、問題文を読み取れていない可能性もあります。
80点以上がとれない「原因」を見つけて、解決していくことを親が導いてあげられたらいいですね。
カラーテストの点数をひとつの目安にしながら、しっかり勉強の基礎・基本の土台を築いていきましょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
【小学生】テストの点数が良くても「通知表の成績・評価が低い!?」その理由
テストは毎回90点以上なのに、通知表を見ると「あれ?“よくできる”じゃないの!?」と戸惑ったことはありませんか? 「テストの点数は良いのになぜ?」 「通知表の基準がよくわからない」...
2025.09.10|大橋礼
-
小学校「教科担任制」のデメリットは?最新の現状についても解説
2022年度より「小学校での教科担任制」導入の指針が発表されたことはご存知でしょうか。2019年4月、当時の文部科学大臣から諮問があったことで一部では話題にのぼった「小学校教科担任制」...
2026.01.02|大橋礼
-
ジェンダー教育とは?小学校から学ぶ意味と家庭の役割
小学校ではどのようなジェンダー教育が実践されているのでしょうか?ジェンダー教育によって、子どもたちの「何が」将来的に変わるのでしょうか? ママやパパも知っておきたい「ジェンダー教...
2025.09.10|大橋礼
-
小学校「宿題の量が多い!」いつやる・どうやる・どうしてる?|4月の教育トピック④
最近はドリルやプリントに加えて「タブレット端末でやる宿題」もプラスされ、新しい学習方法に親が戸惑うことも少なくありません。今回の教育トピックでは主に小学校1年〜6年のお子さんがいる保護...
2025.09.10|大橋礼
-
公立中学校のメリット「中学受験を選ばなかった理由」とは
小学校高学年になると、「中学受験」という言葉が気になり始める保護者も多いのではないでしょうか。同時に地元の中学に通うのもいいのではないか、それが自然なのでは?とも思いますよね。 ...
2025.05.30|大橋礼















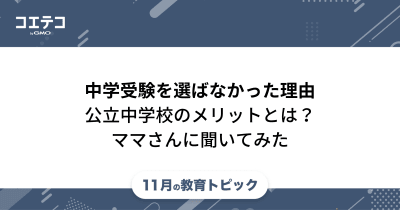
主体的に取り組むっていうのが、ちょっと抽象的で親からすると何を基準に判断されているのかがわかりづらいですね。でも実は現場の先生方も戸惑う面はあるみたいですよ。
たくさん発言する子はわかりやすく主体的に取り組んでいると捉えやすいのですが、発言は少なくてもノートがきちんと整理され自分の考えをしっかりと書いている子も、グループ学習でテーマについて地道に調べて資料をまとめる子も、主体的に取り組んでいると言えるからです。
学校の成績に関しては親にとってはテストの点数しか見えてきづらいのが難しいところですね。