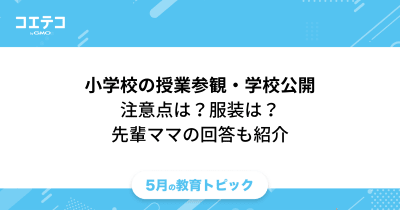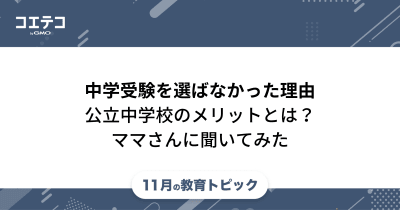小1プロブレムを防ぐ!小学校入学前後の「架け橋期」を家庭はどうサポートするか

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。
小学校の入学前後について、過度に心配する必要はありません。しかし、幼児期(保育園・幼稚園)と小学校ではギャップがあるのも事実です。ご家庭では小学校入学前後をどのようにサポートしたらよいのでしょうか?
文部科学省による「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について」を参考にしながら、先輩ママたちの体験談もまじえて、家庭でできることをチェックしていきましょう!
小1プロブレムとは

小1プロブレムとは、保育園や幼稚園の手厚い見守りや保護の中で過ごしてきた子ども達が、小学校へ入学し集団行動や授業を受けるスタイルにうまくなじめない状態のことを言います。
文部科学省の資料では小1プロブレムを「入学したばかりの1年生で集団行動がとれない、授業中に座っていられない、話を聞かないなどの状態が数ヶ月継続する」としています。

上記のような調査結果が出ていますが、これを見ると小1プロブレムの発生理由としては「家庭の教育(しつけ)に原因がある」とされているようにもとれます。
自分をコントロールするとか、自己中心的傾向が強いというのは、子どもが持つパーソナリティでもあるので一概に「家庭で対応する」とも言えないのですが、いずれにしても、保護者や家庭の役割は大きいと言えます。

この調査結果では、保護者が我が子を幼稚園や保育園に通わせる理由として、「集団の中で」ルールを学んだり、コミュニケーションをとれるようになったりすることを望んでいることがわかります。
親からすれば「お友だちと仲良くできる」(自己中心的ではなく、相手のことを思いやれる)とか「思い通りにいかなくても我慢したり意見を伝えたりする力をつける」(自分をコントロールできる)といったことは、集団の社会で体験しながら覚えてほしいところです。
では次に、小学校入学前に家庭でできることをご紹介します。
小学校入学前に家庭でやっておきたいこと4つ

- 早寝早起き・生活習慣を整える
- きちんと話を聞いてルールを守ることを教える
- 自分の気持ちを言葉にする経験を積む
- 数字やひらがなを学ぶ
早寝早起き・生活習慣を整える
遅く寝てなかなか起きない子どもを、たった1週間程度で「早寝早起き」にするのは難しいです!ついつい親の生活に合わせた就寝をさせており、朝は幼稚園ギリギリセーフが当たり前だったわが家は、入学翌日から毎朝大騒ぎで、怒鳴りつづけるうちに「もう学校休む!」などと言い出して大変でした。早寝早起きもそうですが、ご飯は集中して食べる(遊び食べや、食事中の立ち歩きはしない)、自分で洋服の着替えをする、あいさつをするといったことは、いわば「家庭で行う“しつけ”」のひとつ。保育園や幼稚園くらいだと「まぁいっか」なんてこともありがちですが、早めに「基本的な生活習慣」を整えておきましょう。
少しずつ早寝早起きのサイクルにするべく、少なくとも入学の数ヶ月前からしっかり「学校ペース」にシフトしていくことをオススメします!(Nさん)
基本的生活習慣とは
基本的生活習慣と呼ばれる食事、排泄、睡眠、清潔、着脱衣、お手伝い、あいさつといった習慣が年齢相応にきちんと身に付いているということは、子どもの心と体の 健やかな育ちにとってとても大切なことです。
出典:家庭生活(生活習慣)/教育力向上福岡県民運動
きちんと話を聞いてルールを守ることを教える
保育園や幼稚園にはそれぞれの園のカラーがあります。年長さんになると、椅子に座って先生の指示を待つとか、お話を聞くように徹底的に指導されるところもあれば、全体的に自由な雰囲気のところもあります。でも、小学校に行くと時間割があって、ルールを守って集団行動をすることになります。自由な園で長く過ごしてきた場合は、最初は戸惑うかもしれません。おうちでも、お約束を作って守ることを少しずつ始めていきましょう。
幼児向けのドリルやお絵描きなどでもいいので、「椅子に座って、机(テーブル)で集中して行う」経験をさせてあげるのもいいかもしれません。「学校ごっこ」みたいな感じで、小学校ではこういう風に勉強するんだよと遊びにまじえて体験させてあげましょう。
自分の気持を言う経験を積む

保育園や幼稚園では、先生から「どうしたの?」「トイレに行きたいの?」と声をかけてもらえたかもしれません。しかし小学校では先生はそこまで手厚く子どもに声がけをすることは少ないと思っておきましょう。
長女はもともとのんびり屋でおとなしくてモジモジするタイプ。そんな子を保育園の先生はとてもおおらかに見守ってくださって、親子ともにとても居心地がよかったんですね。小学校低学年のうちは、実際に子どもが自分の気持ちや状況をしっかりと言葉で伝えるのは難しいものです。それでも、小学校に入学したら、自ら行動する必要性が出てきます。
子どもも「言わなくてもわかってもらえる」みたいな感覚があったようで、小学校入学後は、上履きを忘れたとか、友だちといざこざがあっても先生に何も言えずに、次第にストレスになっていたようです。「先生嫌い」とか「保育園に戻りたい」と泣くこともよくありました。
下の子は「ママー」と言ってきたら、(ジュースのことだな)とは親としてわかっちゃうんだけど、あえて「どうしたの?」「何がほしいのかちゃんと教えて」と言葉で伝えることを教えるようにしています(Hさん)
入学直前に「ちゃんと先生に言うんだよ!」と諭しても、子どもの性格にもよりますが、なかなか言い出せません。年長さんになったら日頃から「それで?」「どう思ったの?」「どうしたいの?」と子どもの口から自分が思っていることや、やろうとしていることを話せるような会話を意識したいですね。
数字やひらがなを学ぶ
幼児期は遊びが中心ですが、小学校に入ったら「勉強」をします。結論から言えば、家庭で何もしていなくても、いずれ学校で学ぶわけですから問題はありません。とはいえ、周りはスラスラと取り組む中で子どもが焦りを感じたり、勉強がイヤになったりしないように、多少なりとも数字やひらがなを学んでおくほうが安心ではあります。「小学校できちんと習うから大丈夫」と言われたけど、入ってみたら周りは簡単な足し算くらいできるし、中には漢字が書ける子もいて焦った。お風呂に五十音表を貼って「ひらがな」を指さして教えるとか、おやつを分けるときに一緒に数を数えるとか、時計を見て時間を確認するなど、普段の生活の中で「数字・数の概念・ひらがな」にふれる機会を増やしていきましょう。
とりあえず1から10までの数字がわかり書ける、ひらがなで自分の名前が書ける、五十音がわかるくらいまでは入学前にやらせておいたほうが安心だと思う。
実際に何もしてなくても何とかはなるけど、本人が気にするタイプだと1年生でも「勉強できない!」と落ち込んだり、早々に勉強嫌いになることもあります(Nさん)
小学校について楽しく話す
子どもにとって小学校は未知の世界。期待ばかりではなく、不安があって当然です。ランドセルのコマーシャルのように、瞳をキラキラさせて「早く小学校に行きたい!」という子ばかりではありません。「もうすぐ1年生になるんだから」とアレコレ言い続けたら、もともと心配性の娘は入学式も嫌がるようになってしまいました(汗)。ランドセルや新しい文房具を揃えながら、楽しみだね~!と明るく話すくらいがちょうどよさそうです(Yさん)
小学校の目の前に公園があるので、幼稚園の帰りに少し寄りました。延長保育で16時お迎えでしたが、公園に行くと小学生の姿もチラホラあり、学校の校庭も見えるので、少しでも気持ち的に慣れてほしいと思ったからです。小学校を一緒に外から見たり、もし未就学児もOKな「校庭開放」などをしていたら遊びに行ってみてもいいですね。登下校の道を確認し慣れるためにも、休みの日には散歩がわりに親子で歩きながら「ここは車がいっぱい通るよ」と危ない箇所を教えるのも大事なことです。
上に小学生のいる、同じ幼稚園のママとも顔見知りになり、親もいろいろと小学校の情報が聞けてよかった。親が安心すると子どもも安心するし、「早く小学校行きたい」と言い出すようになったので、特に初めてのお子さんの場合、親子で「小学校を知る」のは大事かなと感じました(Kさん)
小学校入学後に気をつけたいこと4つ

- いつもと様子が違うか変化を見逃さない
- 理由がわからなくても追い詰めずに「寄り添う」
- 癇癪を起こす子どもを怒鳴りつけない
- 「ウチの子は○○なタイプ」と決めつけない
いつもと様子が違うか変化を見逃さない
子どもにとって「小学校」はまったく新しい環境です。普段と同じように見えても、食事の量が減るとか、夕方ウトウトしているとか、いつもよりは口数が少ないなど、ちょっとした変化があれば注意して見守るようにしましょう。小学校に入りフルタイム勤務に戻ったので、自分自身もへとへとでした。少しの変化に気づいて「子どもの気持ちに共感する」ことが大事。何事も早め早めの対応が良いようです。
2ヶ月くらいたった頃に小学校の保健の先生から「給食もほとんど食べていなくて、よく保健室に来ます。ご家庭ではいかがですか?」と連絡があり、ハッとしました。そういえば、夕飯もよく残すようになった……。
忙しくて子どもの話も聞いてあげず、子どもの体調に「不安」が形となって出てきていたのかなと思います。
夕飯後にはなるべく一緒に宿題を見ながら話をし、朝食もパパが一緒にテーブルについて食べながら話すようになって、しばらくしたら元通りになりました。早めに気づいて早めに対処するのが大事!(Eさん)
理由がわからなくても追い詰めずに「寄り添う」
「学校イヤだ」と通いだして2週間もしないうちに娘が言いだしたので、焦りました。いろいろ聞いても、理由がわからない。実は、入学後に登校したがらない「登校しぶり」は珍しくありません。そして、その原因がわからないことも珍しくありません。
先生にもご相談しましたが、しばらく玄関では泣いているけれど用務員さんなどに話しかけられ教室へ行くと、あとは休み時間もお友だちと遊んでいるし、まったく問題なく過ごしているそうで、ますます私としては困惑。
理由がわからないまま、職場がフレックスだったのを幸いに、子どもの登校に毎日付き添い、玄関で養護の先生や用務員の方にお迎えしてもらって、なんとか教室に連れていってもらっていました。
結局、半年以上付き添い登校を続け、その後はお友だちと登校する日が徐々に増えたり、途中までで大丈夫と言うようになって、2年生になる前にはすっかり平気になりました。
今だになぜあの時、あれほど登校を嫌がったのかはわかりません。
でも、とにかく、そういうことがあるし、子どもは何が嫌なのかをうまく口に出せないこともあるようなので、これといった原因がわからないことも珍しくないそうです。
みんなが元気に登校している中、わが子を連れて毎日登校するのはとても辛い。心折れそうになりましたが、「学校に慣れるのに、ちょっとだけ他の子より時間がかかったんだ」ということだったのかな、と今は思います(Aさん)

「なんでイヤなの?いじめられてるの?誰か嫌いな子がいるの?先生に何か言われたの?」と問いただしても、あまりうまくいきません。学校のことでなくても、子どもが何か話しだしたら、関心をもって聞いてあげられるといいですね。
癇癪を起こす子どもを怒鳴りつけない
小学校では、約束が多く、授業も時間通りに決まっており、慣れていない子にとっては「キーッ!」とイライラが爆発することもあります。理不尽なことをしたら叱るのは当然ですが、園の頃みたいに先生に甘えたり、自由に遊んだりできずにイライラがたまっている子どもを頭ごなしに怒鳴りつけるのは良い対策とは言えないですね。
はじめのうちは、わが家に帰ってきたら甘えてくる子どもをしっかり受け止めてあげたいところです。「いつでも、どこにいっても、おうちに帰ってきたら安心、安全」と思えるように、家庭は常に子どもの帰れる場所であると温かく見守っていきましょう。
とはいえ、共働きも多いですし、多忙なママが多い現代。「こっちも大変なのに、そこまでできない……」というのが本音かもしれません。ママが疲れているときはパパが、あるいは祖父母とビデオ電話で話す、習い事など子どもが好きなことがある、どこでもいいのですが「もうひとつの居場所」サードプレイスがあると安心です。
「ウチの子は○○なタイプ」と決めつけない
親ですから、わが子の性格や行動はよくわかっています。「少々ヤンチャだから」
「引っ込み思案」
「優しすぎて人に流されやすい」
「リーダータイプだけどちょっと頑固」
たぶん、きっと、その認識は正しいのです。性格はいきなり変るものではありませんが、とはいえ大きく環境が変わると、「あれっ?」と思うような行動をすることもあります。
最初から自分をうまく出せる子どもはそう多くありません。
だからこそ、「うちの子はああ見えて、けっこう神経太いから大丈夫」とか「おとなしいから、誰かの言いなりになっているに違いない」と決めつけるのは避けましょう。
本質的なことは変わらないとしても、環境に合わせて行動も変わるのは当たり前のこと。時には「何があったの?前はそんな子じゃなかったよね!」と詰め寄りたくなるこがあったとしても、グッと我慢して「成長しているんだな、子どもも頑張っているんだな」と応援する気持ちで見守っていきましょう。
スタートカリキュラムとは?幼保小の連携で安心

文部科学省では、小学校1年生が学校に早くなじめるような取り組みのひとつとして、スタートカリキュラムを推奨しています。
スタートカリキュラムとは、小学校へ入学した子供が、幼稚園・保育所・認定こども園などの遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り出していくためのカリキュラム教育現場も小1プロブレムを注視し、少しでも子どもたちがスムーズに学校生活になじめるような「幼保小連携」を進めています。親の目で見守り、学校現場も力を尽くす。幼保小連携と同様、保護者も学校の状況を理解し、小学校や先生方と「一緒に」連携して、子どもが楽しく小学校に通えるようにしたいですね。
引用:スタートカリキュラムスタートブック/文部科学省
小学校入学前後の「架け橋期」をみんなで乗り越えていきましょう!

幼稚園や保育園から小学校入学への「架け橋期」は、なかなか難しいですね。
小1プロブレムについて触れましたが、働く親にとっては園よりもお迎え時間が早いなど、さまざまな環境の問題もあって「小1の壁」などとも言われています。
しかし、架け橋は「つなぐ」こと。子どもの成長は、つないでいくことの連続です。節目節目で、あらゆる問題がふりかかってくるように感じますが、ひとつ橋を渡って、次の景色が見えてくれば、どんどん子どもの世界が広がっていきます。
家庭という小さな、あたたかくて安全な場所から踏み出していく子どもたちの勇気をぜひ応援していきましょう!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学校の授業参観・学校公開「注意点は?服装は?見るべきポイントも教えて!」先輩ママの回答も紹介
今回の教育トピックでは、授業参観/学校公開で親が見るべきポイントや、場にふさわしい服装など「知っておくと役立つ情報」を詳しく解説します。 先輩ママたちの体験談も紹介するので、ぜひ...
2024.06.03|大橋礼
-
小学校の担任と子どもが合わない!「担任の先生を変えて欲しい」ときの対処法|教育トピック
わが子と先生の関係は保護者にとっては大きな悩みのタネになりがちです。悩みを抱えていても、「モンスターペアレンツ」扱いをされたらと思うと、どう話をしたらよいのか対処法に迷いますね。 今...
2024.04.01|大橋礼
-
公立中学校のメリット「中学受験を選ばなかった理由」とは
小学校高学年になると、「中学受験」という言葉が気になり始める保護者も多いのではないでしょうか。同時に地元の中学に通うのもいいのではないか、それが自然なのでは?とも思いますよね。 ...
2024.12.10|大橋礼
-
文部科学省提供「プログラミン」と学校現場でのリアルなプログラミング教育に迫る!
『プログラミン』は文部科学省が無料提供しているブラウザでプログラミング作成ができるサイトです。今回筆者の5歳の子どもが実際に『プログラミン』を体験しました。2020年プログラミング教育...
2024.03.31|Yukiko
-
小学校「宿題の量が多い!」いつやる・どうやる・どうしてる?|4月の教育トピック④
最近はドリルやプリントに加えて「タブレット端末でやる宿題」もプラスされ、新しい学習方法に親が戸惑うことも少なくありません。今回の教育トピックでは主に小学校1年〜6年のお子さんがいる保護...
2024.03.31|大橋礼