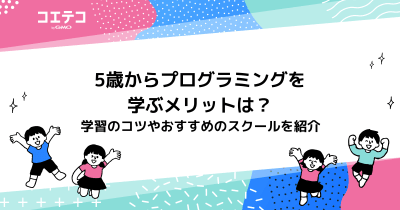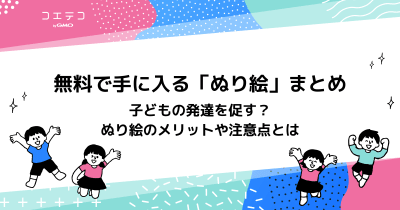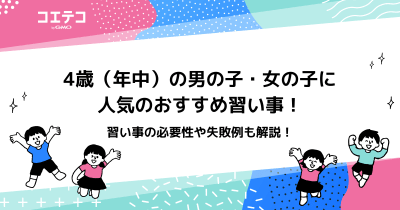生成AIで学びを楽しく!小学生でも使える生成AIの活用方法と注意点
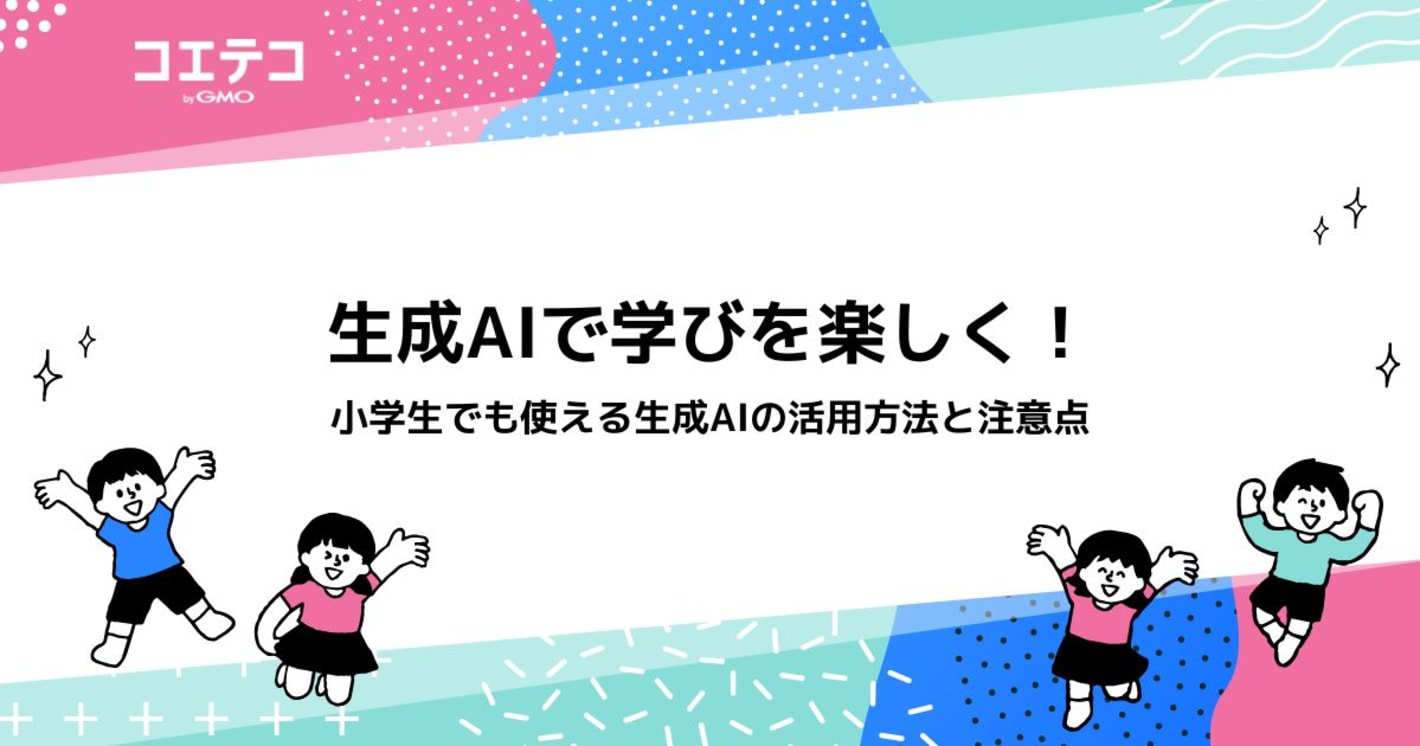
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
生成AIの進化が目まぐるしい中、小学生の間でもAIへの関心は高まりつつあります。
「小学生にAIなんて早すぎる!」と感じる大人もいるかもしれません。しかし、未来を担う子どもたちにこそ、最先端技術であるAIをもっと身近に感じ、適切に使いこなすスキルを学ぶ機会が必要です。
この記事では、小学生が楽しく学びながら生成AIを活用する方法をはじめ、おすすめツールや利用する際の注意点、学校での活用事例などをご紹介します。
この機会にAIの有用性と特徴を正しく認識し、お子さんと一緒にAI教育を始めましょう。
小学生でも使える生成AIの活用手順
生成AIを小学生が活用するには、いくつかのステップを順番に進めることが大切です。ここでは、小学生が分かりやすい形で生成AIを学ぶための具体的な手順を詳しく見ていきましょう。手順1:生成AIとは何かを理解する
まずは、生成AIが何なのかを理解することが大切です。そもそも生成AIとは、大量のデータを学習して、人間のように文章や絵、音楽などを作り出す人工知能のことを指します。例えばAIが人間の質問に答えたりオリジナルの絵を描いたりするのは、学習した情報をもとに新しいものを作る「生成」という仕組みがあるからです。
このことを小学生に説明するときは、「AIは先生や本からたくさん学んで、そこから新しい答えや作品を作れる頭の良いコンピュータ」のようなものをイメージしてもらうと分かりやすいでしょう。
基本的な仕組みを理解することで、生成AIを楽しく使いこなす第一歩を踏み出せます。
手順2:小学生に適した生成AIツールを選ぶ
小学生が生成AIを使うには、年齢や目的に合ったツールを選ぶことが重要です。ツールを選ぶ際には、子ども向けに安全性が確保されているものかどうかを優先して選びましょう。例えば、簡単な操作でイラストを作れるアプリや、子ども専用のチャットAIなどが挙げられます。
学校の課題や自由研究に活用したい場合には、テキスト生成AIを使って文章を作成したり、調べ学習をサポートしてくれるツールが便利です。
実際に選ぶ際には、保護者が事前にツールの内容を確認し、操作のサポートをすることで、子どもが安心して使える環境を整えましょう。適切なツールを選ぶことで、AIの楽しさをより実感でき、学びが深まります。
手順3:生成AIでできることを体験してみる
生成AIの魅力を知るには、実際に使ってみるのが一番です。たとえば、絵を描くAIを使って好きなキャラクターを作ったり、文章生成AIでオリジナルの物語を考えたりすることで、創作活動の幅を広げられます。また、AIに質問をして自由研究のテーマを見つけるといった学習にも役立ちます。
ChatGPTをはじめとする生成AIの普及が進むにつれて「プロンプトエンジニアリング」に注目が集まっています。AI業務を効率的かつ正確に進めるうえでは欠かせなくなっている状況です。この記事では、そんなプロンプトエンジニアリングのスキル習得におすすめの生成AIスクールやオンラインで学習可能な生成AI講座を厳選してご紹介します。
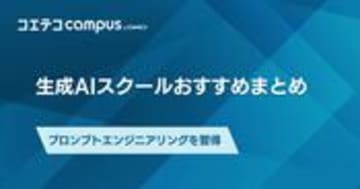

2026/01/02

初めは保護者が一緒に操作をサポートし、AIが生成した結果について話し合うことで、子どもが正しく理解しながら使えるようになります。実践を通じて、AIの可能性を楽しく体感してみましょう。
小学生におすすめの生成AIツール紹介
生成AIは難しいというイメージがあるかもしれませんが、実は小学生でも簡単に使えるツールが増えています。遊びながら学べるものから自由研究・宿題に役立つものまで、小学生が楽しみながら生成AIに触れられるツールを詳しく見ていきましょう。ChatGPT:文章作成や質問回答が得意なツール
ChatGPT(チャットジーピーティー)は、文章を作成したり、質問に答えたりするAIツールで、例えば作文のアイデアを出したり、自由研究のテーマを決めたりするのに役立ちます。また、分からないことを日本語で質問するだけで分かりやすい説明が得られるので、宿題のサポートとしても活用可能です。遊び感覚で物語を一緒に作るなど、創造力を育むツールとしても利用できます。
一方で、その便利さゆえに、宿題の答えをそのまま丸写ししたり、AIが作った作文をそのまま書いて提出したりと、学びの本質を損ねる使い方につながる可能性もあります。ChatGPTを利用する際には、正しい使い方を親子で確認することが重要です。
DALL-E3:画像生成で創造力を育むAI
DALL-E3(ダリ・スリー)は、テキストから画像を生成できるAIツールです。ChatGPTに組み込まれているため、ChatGPTのプロンプトで「絵を描いて」と入力するだけで簡単に利用できます。例えば「未来の学校の絵を描いて」や「宇宙をテーマにしたキャラクターを作って」と依頼すると、生成された画像がすぐに表示されます。
このように、特別な操作を必要とせず文章だけでイラストを作成できるため、小学生でも気軽に楽しめるのがメリットです。自由研究や創作活動に役立てながら、親子でAIの可能性を探求してみましょう。
Gemini:調べ学習やアイデア出しに最適
Googleが提供する生成AIツールGeminiは、Googleの検索エンジンとの連携により、検索に強みを持っているAIツールです。テキストだけでなく、画像、音声、動画など、様々な形式の情報を理解してコンテンツを生成できます。活用方法としては、宿題のテーマについて質問して分かりやすい情報を提供してくれたり、自由研究や作文のネタ探しをしてくれたりと、学習の幅を広げる活用が可能です。
ネット検索よりも簡単で具体的な答えが得られるため、小学生でも無理なく使えます。さらに、調べた情報を整理したり、新しいアイデアを得るためのヒントとして活用するのもおすすめです。
その他の無料で使える生成AIツール
生成AIはChatGPTやDALL-E3、Gemini以外にも、多くのツールが存在します。小学生におすすめのものとしては、例えば絵を描くAIアプリの「Canva AI」や、アニメ風の画像を作成できる「Toonify」、音楽を生成する「Soundraw」などがあります。
それぞれ特徴が異なるため、子どもの興味や目的に合わせて選んでみましょう。新しいツールを試してみることで、AIの可能性を広げる楽しい体験ができます。
小学生が生成AIを利用する際の注意点
生成AIは便利で楽しいツールですが、小学生が利用する際には注意が必要です。正しいルールと環境を整えることで、子どもたちが安全に活用できるようになります。ここでは、保護者や教師が押さえておきたい重要なポイントについて見ていきましょう。保護者や先生が見守る環境を整えよう
小学生が生成AIを使う際には、保護者や先生が見守る環境を整えることが大切です。AIは便利なツールですが、子どもだけで使うと、誤った情報を信じてしまったり、適切でない内容にアクセスしたりするリスクがあります。このため、ツールの使い方を保護者や先生が事前に確認し、安全性を把握することが重要です。
また、子どもがどのようにAIを利用しているかを一緒に確認し、適切なアドバイスを行いましょう。例えば、宿題や創作活動に活用する際は、AIが生成した結果をただ受け取るのではなく、自分で考えを加えることをサポートするのがポイントです。
大人の見守りがあれば、子どもたちはAIを安全かつ効果的に活用できます。
個人情報を守るためのルールを作ろう
生成AIを安全に使うためには、個人情報を守るルールを作ることも重要です。生成AIに名前や住所、学校名、電話番号などの個人情報を入力すると、意図せず外部に漏れる可能性があります。これを防ぐために、「絶対に入力してはいけない情報」にどのようなものがあるか、あらかじめ親子で話し合っておきましょう。またAIを使う際には、入力内容を親が確認する習慣をつけると安心です。
ルールを守ることで、子どもたちは安心して生成AIを使いながら、創造力や学ぶ意欲を育てることができるでしょう。
「AIは間違える場合がある」ことを理解する
生成AIは便利なツールですが、必ず正しい情報を提供するわけではありません。AIが誤った情報や不正確な答えを生成する場合があることを、子どもたちにしっかり伝えることが大切です。例えば、宿題や調べ学習でAIを使う際には、「AIの答えが本当に正しいかどうか」を確認する習慣を身につけるよう指導しましょう。本やインターネットの他の信頼できる情報源と照らし合わせたり、大人に相談したりすることで、誤情報に惑わされるリスクを減らせます。
AIはあくまで補助ツールであり、最終的な判断は自分で行うことを学ぶことで、正しい使い方を身につけられます。
AIスキルも学べる!おすすめプログラミング教室3選
ここでは、AIスキルも学べる!おすすめプログラミング教室を3つ紹介します。N Code Labo

N Code Laboは、AI・プログラミングスキルを実践的に学べる子ども向けプログラミング教室です。
ゲーム制作を通して、プログラミングの基礎から応用までを楽しく習得できるカリキュラムが特徴であり、深層学習の概念を身近な事例を交えて分かりやすく学ぶことができます。
さらに単に知識を教え込むだけでなく、自分で課題を見つけ、解決する学習スタイルを重視しており、自律的に学ぶ力を養えるとのこと。
また、メンター制度が充実しており、現役のエンジニアやクリエイターが個々の進捗に合わせて丁寧に学習をサポートしてくれます。
加えて、個々の理解度に合わせた少人数制指導を採用しているため、質問や相談もしやすい環境が整っている点も魅力。
将来的にAI開発やゲームクリエイターを目指す学生や、論理的思考力を身につけたいと考えているお子さんにおすすめの教室です。
HALLO オンラインプログラミング教室

HALLO オンラインプログラミング教室は、ゲーム感覚で楽しみながらAI時代に必要なプログラミング思考を身につけられる学習サービスです。
専用アプリを活用し、子どもが自ら挑戦しながら問題解決力を養えるカリキュラムが用意されています。
例えば、ロボットやセンサーを使った学習では、AIがどのように私たちの生活を便利にしているかを体験しながら理解できるとのこと。
レッスンはオンラインで完結するため、自宅で気軽に学習を続けられる利便性も大きな魅力。
さらに、学習の進捗状況は専用システムで保護者も確認できるため、子どもの成長を見守りながら適切なタイミングで最適な声掛けもできるようになるでしょう。
加えて、コーチによるサポートも充実しており、つまずいたポイントは個別にアドバイスを受けられます。
プログラミングを通じて、AIをはじめとする最先端技術に触れたいと考えているお子さんや、将来の選択肢を広げたいと考えているご家庭は、HALLO オンラインプログラミング教室の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
Z会プログラミング講座

Z会プログラミング講座は、論理的思考力や問題解決能力を養うことを目的としており、単なるプログラミングスキルの習得に留まらない、総合的な学習を提供している点が特徴です。
Scratchを活用した入門編からスタートし、徐々にPythonを使った本格的なプログラミングやAIの仕組みに触れられるカリキュラムが用意されています。
Z会が長年培ってきた教育ノウハウを活かし、子どもたちが無理なく、かつ確実に理解を深められるように設計されており、AIの基礎概念から実際にプログラムを動かす演習まで、段階的にスキルを積み上げていくことができるとのこと。
加えて、課題提出に対して丁寧なフィードバックを提供してくれるため、理解を深めながら着実にスキルを習得できます。
受験指導に定評のあるZ会が監修しているため、プログラミングを単なる趣味にとどめず、学習の延長として将来のキャリアや学問に結びつけたい家庭に最適といえるでしょう。
学校教育における生成AI活用事例
生成AIは学校教育の現場でも活用が進んでおり、学習の効率を高めたり、子どもたちの創造力を引き出したりと、多くの可能性を秘めています。ここでは、実際に学校で取り入れられている生成AIの活用事例を紹介します。参考:初等中等教育段階における生成AIに関するこれまでの取組み|文部科学省
AIの正しい知識を身に付ける(小学校)
大阪市立高殿小学校では、生成AIに関する情報モラル教育の一環として、生成AIで作成された記事と実際の記事を比較し、それぞれの違いを確認する授業が行われました。この活動を通じて、AIが生成する情報をそのまま信じるのではなく、他の資料や自身の経験と照らし合わせて考えることの重要性を学んでいます。
生成AIを正しく活用するためには、正しい知識を身につける情報モラル教育が欠かせません。生成AIが誤った情報を提供する可能性を理解し、その真偽を確認する習慣を養うことで、子どもたちはAIを活用する際の適切な判断力を身につけられます。
話し合いで問題を検討する(中学校)
茨城県つくば市立学園の森義務教育学校では、国語科の授業で、グループごとに設定した問題について話し合いを行い、生成AIを活用して意見を深める活動が実施されました。生成AIは、新たな視点や生徒たち自身の意見に対するアドバイスを提供し、議論をさらに広げる役割を果たします。生徒たちは生成AIから得たアドバイスをもとにグループ内で再度話し合いを行い、内容を洗練させた上で最終的な結論を導き出しました。
このような活動を通じて、AIを活用しながら考えを深める力や協働的な学びを体験できます。
画像生成で美術の苦手をサポート(高校)
鹿児島県立鹿児島玉龍高等学校では、美術科の授業で生成AIを活用した創作活動が行われています。まず何も参考にせずにスケッチを行い、その後、AIを使って画像を生成し、さまざまなパターンを作成。その後、生成された画像を参考に、自分の構図にアレンジを加えることで、より豊かな表現につなげられました。
生徒たちは、発想段階で生成AIを活用することで、予想外のイメージが得られ、それをきっかけに自身の発想を広げることができたという感想を抱いています。
このような取り組みは、美術が苦手な生徒でも新しいアイデアを得やすくする効果があり、創作のハードルを下げると同時に、個性豊かな作品作りをサポートできます。
アンケートの集計・分析での活用(校務利用)
沖縄県嘉手納町立嘉手納中学校では、生成AIを校務利用としてアンケートの集計・分析に活用しています。記述回答式のアンケートを迅速に分析し、結果を5つのグループに分類して職員間で共有。その後、生成AIが示した分析結果をもとに、成果や課題、対応策について議論を深める場を設けました。生成AIによるデータの分類が議論をスムーズに進める手助けとなり、教員たちは「議論の効率が向上した」と手ごたえを感じているようです。さらにアンケート設計やプロンプトの改善を重ねることで、より効果的なデータ活用が可能になるとされています。
学校教育でこのような生成AIの活用が進むことで、教員の負担を軽減しつつ、迅速かつ正確な意思決定が実現できる未来が開けるでしょう。
小学生と生成AIが共存する未来へ
生成AIは、小学生にとって学びや創造の幅を広げる強力なツールです。作文や自由研究、絵画制作など、さまざまな分野で可能性を広げてくれるだけでなく、子どもたちの好奇心や創造力を刺激します。一方で、正しい使い方や情報モラルを学ぶことも大切です。親や先生と一緒に生成AIを活用することで、小学生たちは未来の技術を楽しく安全に身につけられるでしょう。
進化し続ける生成AIと共存しながら、新しい挑戦や学びをどんどん楽しんでいきましょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
利用率急上昇中!小学生のAI活用実態と家庭でできる正しい対策
今や小学生はおろか、幼児でさえ、知らず知らずのうちに「AI」に触れています。AIについて、なんとなくはわかっていても、きちんと子どもに仕組みを説明し、正しい使い方を教えている保護者はど...
2025.09.22|大橋礼
-
理科実験教室おすすめ12選!子どもの科学的思考力を伸ばす教室の選び方
理科実験教室は、子どもたちが実際に手を動かして学ぶことで、科学的思考力や問題解決能力を育てる絶好の機会です。しかし、数多くある教室の中から、わが子に合った教室を見つけるのは簡単ではあり...
2025.10.15|コエテコ byGMO 編集部
-
5歳からプログラミングを学ぶメリットは?学習のコツやおすすめのスクールを紹介
5歳からプログラミングを学ぶことは、小学校教育の先取り・プログラミング学習の習慣付けなどに有益です。保護者が子どもにしっかりと寄り添って、楽しく学習を進めましょう。5歳からプログラミン...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
【無料の塗り絵まとめ】子どもの発達を促す?
塗り絵は人気の高い室内遊びのひとつ。枠の中に色を塗るというシンプルな作業ですが、自由に色を塗る過程に夢中になる子どもが多いようです。 そんな塗り絵は子どもたちが楽しんで取り組める...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部
-
4歳(年中)の男の子・女の子におすすめ習い事19選【2026年最新版】
幼稚園や保育園で年中にあたる4歳児は、習い事を始めるには早すぎるという見方もあるかもしれませんが、4歳から始められる習い事は数多くあり、レッスンを楽しむ子どもはたくさんいます。心と体が...
2026.01.02|コエテコ教育コラム