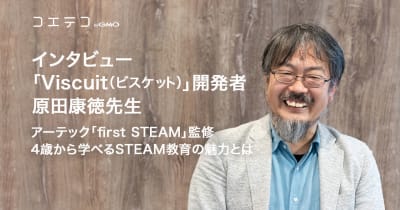中高生向け本格プログラミングスクール始動!TechAcademy×アーテック

2018年には子ども向けのTechAcademyキッズもスタートさせ、プログラミング教育の裾野をますます広げていると言えるでしょう。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://coeteco.jp/brand/tech-academy-kids >
一方、子ども向けプログラミングスクールを多数展開するアーテックは大人気ロボット教材をパワーアップした「アーテックロボ2.0」を発売。
たて・よこだけでなくナナメにもブロックを繋げられるのが「アーテックロボ」の特長ですが、「2.0」ではさらにWi-Fiを搭載し、プログラミング授業の幅を大きく広げました。
エジソンアカデミーの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック
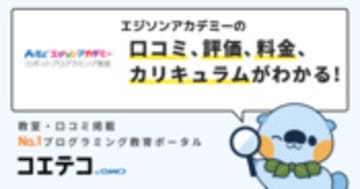
https://coeteco.jp/brand/edisonacademy >
そんな2社が今回業務提携を発表。Pythonを活用してロボット制御を行う、中高生向けのプログラミングスクールをスタートします。
TechAcademyの実践的なカリキュラム、アーテックの教育的知見。二つが合わさったスクールはどのようになるのでしょうか。
今回はTechAcademyキッズを運営するキラメックス株式会社の代表取締役社長・樋口隆広さん、株式会社アーテックの企画室 教育コンテンツチーム課長・濵田大地さんにお話を伺いました。
オンラインスクール「TechAcademy(テックアカデミー)」が手がける、子供向けプログラミングスクール「TechAcademyキッズ」。全国各地の子どもたちのために、教室を展開することになった背景や教材の特長、そしてカリキュラムに込めた想いなどをインタビューしてきました。


2025/05/26

全国700以上の教室を展開する、ロボットプログラミング教室「エジソンアカデミー」。教材とカリキュラムの開発を手がける株式会社アーテックは、大阪府八尾市に本社を置く、学校教材・教育玩具メーカーです。


2025/05/26

「小学生向け」「大人向け」の架け橋に

—さっそくですが、キラメックスさん自体もTechAcademyキッズを運営される中、アーテックさんとの業務提携にはどのような思いがあるのでしょうか。
樋口:
小・中学生対象のTechAcademyキッズがスタートしてから1年が経ちました。
大人中心のTechAcademyと同じく本格的なプログラミングを学んでもらうのがねらいで、Scratchを使ったアプリケーション制作に取り組んでもらいます。

キラメックス株式会社 代表取締役社長 樋口隆広さん
でも、プログラミングを学ぶ方法はアプリ制作以外にもあるし、学びの選択肢はたくさんあるべきだと考えたんです。中でも「ロボットを動かしたい!」という子は多いので、ぜひ始めたいと。
そこで「アーテックロボ2.0」の開発元であり、ロボットプログラミングに知見をお持ちのアーテックさんと業務提携させていただき、お互いの強みを生かしたカリキュラム開発を行うことにしました。
—アーテックさんのほうはどうでしょうか。
濵田:
我々はいくつかのプログラミング教室ブランドを展開しており、ロボットプログラミングですとエジソンアカデミーを運営しています。
スタートから数年経ち、卒業生が出る時期になって「続編が欲しい!」のリクエストを多くいただくようになりました。
生徒さんからは「もっと本格的なコーディングをしてみたい」の声もあり、プロ志向のキラメックスさんとタッグを組むことでリクエストに応えたいと考えたんです。

株式会社アーテック 企画室 教育コンテンツチーム課長 濵田大地さん
—なるほど。入門からステップアップした内容が求められているんですね。
樋口:
TechAcademyは大人中心とは言え、中高生、ときには小学生のお子さんも受講してくださっています。どうしてだろう?と考えてみると、入門レベルと本格レベルの間に溝があると分かりました。
ご自宅の近くにある入門スクールやキャンプイベントで興味を持っても、次のステップが近くにない。それでTechAcademyに入学してくださると。

小学校での必修化を前に、入門レベルのスクールは盛り上がりを見せています。でも「次」となるとまだまだ選択肢が少ないんです。
今回アーテックさんと始めるスクールではその溝を埋め、入門から実用への架け橋となるカリキュラムを提供する予定です。

開発中のカリキュラム。入門編のカリキュラムはLesson1~9まであり「プログラミングとは」「Pythonのデータを学ぶ」といった座学的な内容をカバーしている。そこから制作に入っていき、本格的なエディタを使ってPythonのコードを書く
アーテックロボ2.0でPythonコーディング

アーテックロボ2.0
—新スクールでは「アーテックロボ2.0」を使うそうですが、「2.0」になって大きく変更されたのはどこですか。
濵田:
一番のポイントはWi-Fiを搭載した点です。ロボット同士で通信したり、インターネット上にある情報を取得してロボットの動きに反映させられるようになりました。
アーテックロボはブロックで遊びながらかたちを組み立て、プログラミングをして思い通りの動きを与えるプログラミングロボットキットです。

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/ >
ロボット同士で通信できると、たとえば「信号機」「自動車」を組み立てて自動運転をシミュレーションできます。信号機が青になっていたら進む、赤なら止まる、といった感じですね。
他にも、インターネットから天気の情報を取得して、雨が降りそうだったら玄関先で傘を渡してくれるロボットなどが作れます。
分かりやすい例を挙げましたが、子ども達に渡してみると大人が思いつかないアイディアがどんどん出てくるので、実際の授業ではもっともっと幅が広がると思いますよ。

搭載されたMicroPython(マイクロパイソン)というインタプリタでコードを読み取るそう。ちなみにこれは、手を入れるとランダムで噛みつくワニ
大人向け・子ども向けスクールの違い

—日本e-Learning大賞 プログラミング教育特別部門賞を受賞するなど大人気のTechAcademyさんですが、大人向けスクールで得たノウハウはありますか。
樋口:
TechAcademyがスタートした当初は、教室に集まってもらい、スライドを見ながら学ぶオーソドックスなスクール形式をとっていました。
この形式にもいいところはたくさんあるのですが、プログラミングの学習に関して言えば学習効果が思うように上がらない場面がありました。
受講生のバックグラウンドがそれぞれ違うので、キャッチアップの速度にズレが出てしまうんです。「ここはもう知っているから、飛ばしてほしい」「もっとゆっくり説明してほしい」という感じで。
それで大人向けに関しては、自分のペースで勉強し、分からないところをメンターに聞く現在のスタイルが効果的と判断しました。

—なるほど。一方で新スクールは教室に集まってオンライン教材を受講するスタイルですね。通塾スタイルにした理由は何でしょうか。
樋口:
教育効果を上げるには、講師やコンテンツの質だけでなく学習が継続できるしくみづくりが大切です。
大人の場合「オンラインブートキャンプ」のような短期集中コース、キャリアに直結するコースが効果的だと分かりました。
子どもの場合は、飽きのこないコンテンツや「場」が大切になります。仲の良い先生に会いに行く、ロボットを触りに行くといった「場」づくりがモチベーションの維持に欠かせないんです。
—カリキュラムは現在設計中だそうですが、体験会等はされたのでしょうか。
(キラメックス 加藤):
新スクールの開校に向けて、カリキュラムの体験イベントを行いました。「難しいかな?」と危惧していたのですが、子ども達はなんなくこなしてくれて驚きました。

参加してくださったのは小6から高1のお子さんで、2日間で計10時間のイベント。大人でも集中が続くかどうか、ちょっと不安なペースですよね。でも皆さんは休憩もあまり取らず、本当に楽しんで取り組んでくださったんですよ。
これまではScratchでプログラミングをしていた方が多く、テキストでコーディングするだけでも新鮮味があったようです。

黒い画面にカタカタ……という、いかにもなプログラミング画面。これを「カッコいい!」と感じる子はどんどんのめり込んでいく

「コントローラー」の試作品。アーテックロボ2.0なら自作のゲーム機が作れる
中高生の保護者へのメッセージ

—では最後に、中高生のお子さんをお持ちの保護者に向けてメッセージをお願いいたします。
樋口:
TechAcademyに中高生の受講者がいる状況からも分かるように、中高生向けの選択肢はまだ多いとは言えません。
小学生向けが盛り上がる一方で、現段階で中学生、高校生のお子さんを持つ保護者は「やっておかなくていいのかな?」と不安に思われています。
濵田:
学校も同じですよね。今でも中学校の「技術」には「(3)プログラムによる計測・制御」の内容があるのですが、なかなか深くまでは扱われません。
2021年度からは、中学校でも新学習指導要領が「全面実施」となります。今回は文部科学省 上野耕史(うえの・こうし)さんにインタビュー。中学校でのプログラミング教育について詳しいお話を伺いました。


2025/06/24

樋口:
そのギャップを、私どものような民間のスクールでカバーしたい。
TechAcademyのプロ志向、アーテックさんの教育的知見の両輪でテクノロジーを理解した人材を育て、将来につながる場を提供したいと考えています。
ぜひこれを機会に、中高生の方もプログラミングにチャレンジしてみてください。
濵田:
中高生になると学習塾に通われる方も増え、費用面でハードルを感じる保護者の方も多いでしょう。
ただ、キャリア形成は大きく変わってきています。高校へ行き、大学へ行き、就職活動をする……という直線的なキャリアパスはいずれ変化するでしょう。

自分の強みやスキルがキャリアにつながる場も増えてきます。確かに費用面は気になるところですが、効果的な投資ではないかと思うのです。
中高生のお子さんが少しでもプログラミングに興味があるなら、ぜひ背中を押していただければと考えております。
—ありがとうございました。

とても雰囲気のよいお二人。新スクールのカリキュラムも楽しみだ
新ブランドは10月スタート
樋口・濵田:新ブランドは10月スタートで、通塾スタイルは受講料1万6千円/月、教材費が別途3万円です。
通塾スタイル以外にも短期集中講座を準備しており、費用は2日間で3万円です。
中高生になると部活動や受験勉強で忙しくなる方も多いと思うので、スケジュールの繰り合わせが難しい方は短期集中講座をおすすめします。

開発中のカリキュラム。「次」が欲しい人はぜひチャレンジ
幼・小・中学生向けスクールへはこちら
キラメックス株式会社
TechAcademyキッズ
小学3年生〜中学3年生を対象とし、Scratchでプログラミングを学ぶスクール。「これからプログラミングを始めてみようかな?」というお子さんはこちらへもどうぞ。リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://coeteco.jp/brand/tech-academy-kids >
株式会社アーテック
Hop STEAM Jump(ホップ スティーム ジャンプ)
年少〜小学生が対象。ブロックパズルやロボット、プログラミングを複合的に学びます。Hop STEAM Jumpの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック
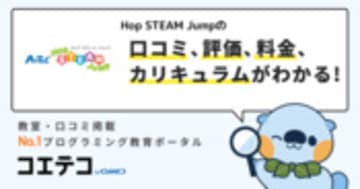
https://coeteco.jp/brand/hop-steam-jump >
自考力キッズ(じこうりょくキッズ)
小学1年生〜小学3年生が対象。パズル×ロボット×プログラミングを合わせた独自カリキュラムで、低学年でもやさしくプログラミングが学べます。アーテック自考力キッズの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック
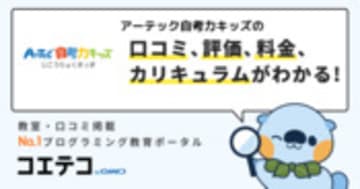
https://coeteco.jp/brand/jkids >
エジソンアカデミー
小学3年生〜が対象のロボットプログラミング教室。毎年、国際ロボット競技会『URC』へ出場するチームが多数輩出されているそう。エジソンアカデミーの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック
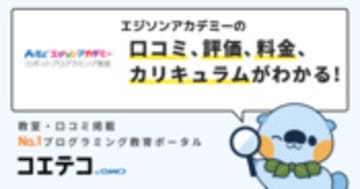
https://coeteco.jp/brand/edisonacademy >


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
Pythonが学べる!個別指導Axisロボットプログラミング講座「アドバンス」の内容とは
個別指導Axisロボットプログラミング講座がPythonを学べる新コース〈アドバンス〉を開講します。その内容とは?株式会社ワオ・コーポレーションの野々宮さん、株式会社ソニー・グローバル...
2024.11.06|夏野かおる
-
ITロボット塾 総合IT力育成教育教室授業をのぞいて見ました|静岡県浜松市
小学校2年生から高校生を対象としたITロボット塾。ロボットプログラミング講座の開発経緯やカリキュラムの特徴について、株式会社CAIメディアの代表取締役社長であり株式会社ITロボット塾の...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
本格派ロボットプログラミング教室「エジソンアカデミー」と「自考力キッズ」。未来を生き抜く力を養うカリキュラムとは?
全国700以上の教室を展開する、ロボットプログラミング教室「エジソンアカデミー」。教材とカリキュラムの開発を手がける株式会社アーテックは、大阪府八尾市に本社を置く、学校教材・教育玩具メ...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
「Viscuit(ビスケット)」開発者・原田康徳先生 | アーテック「first STEAM」監修
株式会社アーテックが4歳から学べるSTEAM教育スクール「first STEAM(ファーストスティーム)」を新規開講します。今回は「デジタルアート」のカリキュラムを完全監修された「Vi...
2025.06.24|夏野かおる
-
個性を育むひよこパソコン教室!P検・Jrプログラミング・MOS資格取得が目指せる
全国に68教室を展開する「ひよこパソコン教室」。運営するのは「ケーズデンキ」を展開するケーズHDの子会社、株式会社テクニカルアーツです。 保護者から厚い信頼を寄せられる「ひよこパソコ...
2025.05.21|夏野かおる