小中高で情報教育が大幅強化!2030年代に向けて親が知っておくべきこと
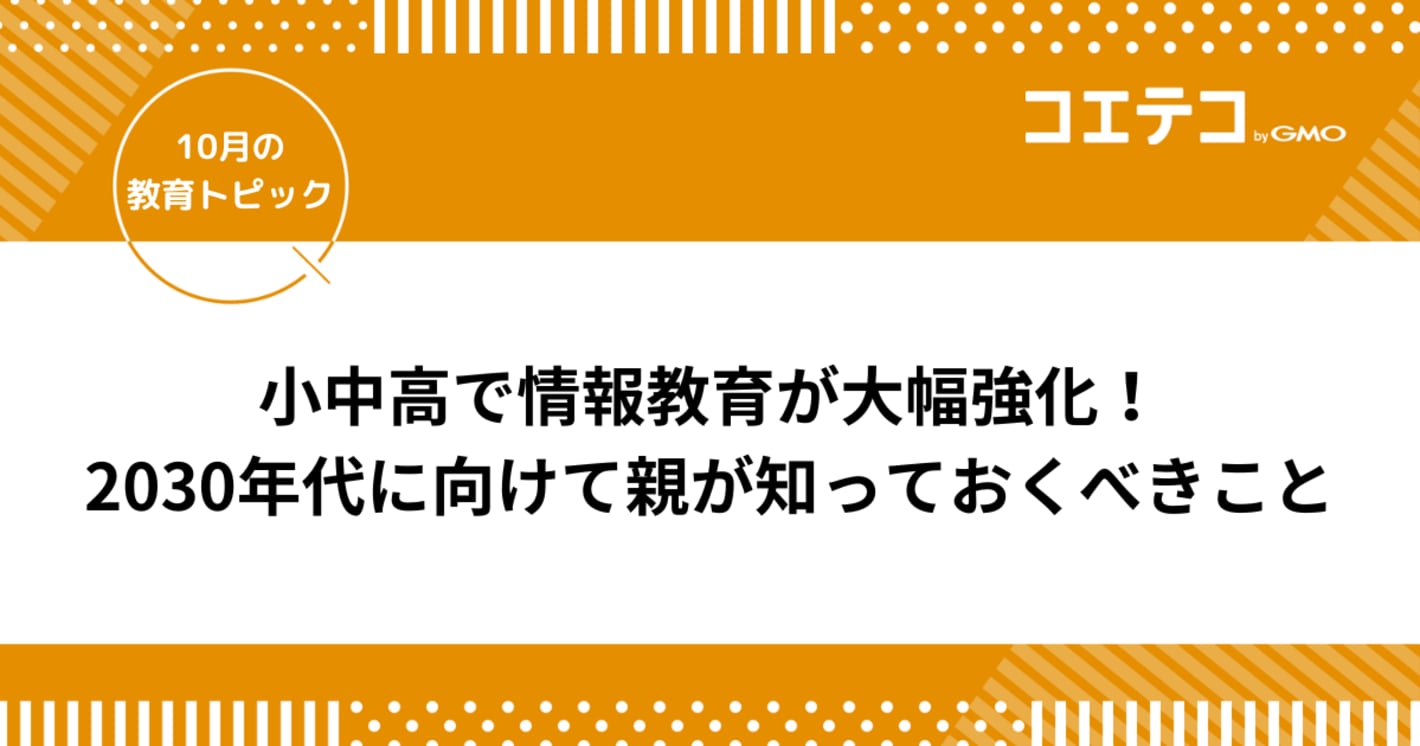
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
小学校から高校まで、子どもが学ぶ情報教育の内容が大きく変わります。
生成AIやデジタル技術が日常となる時代を生きる子どもたちに、今、何が必要とされているのでしょうか。
単なるパソコン操作の習得だけではない、これからの情報教育の本質を、保護者として知っておくべきポイントとともに解説します。
2030年代の学習指導要領改訂に向けた流れとは
 出典:論点整理/文部科学省
出典:論点整理/文部科学省文部科学省は2030年代に向けて、新しい学習指導要領の準備を進めています。
学習指導要領というのは、簡単にいえば「学校で何をどう教えるか」を定めた教育の設計図。約10年ごとに見直されていて、次の改訂では、子どもたちが自分で考え、学び続ける力をより育てていく方向に進みます。
特に注目したいのが「情報活用能力」です。2021年に始まったプログラミング教育は、まだ序章。これから先、情報を扱う力はさらに重視され、すべての学びの土台になっていきます。
2030年代というと先のように感じますが、幼児なら小学生に、小学生なら中学生に、中学生なら高校生になる頃。つまり、今のお子さんが実際に体験する未来です。
私たち親世代が学生だった頃とは、学校で学ぶ内容が大きく変わっています。だからこそ、わが子が小学校・中学校そして高校で何を学ぶのかを知っておくことが、家庭でのサポートを考える第一歩になります。
なぜ今、情報教育の強化が必要なのか?

子どもたちを取り巻く環境が急速に変化している
スマートフォンで写真を撮れば、AIが自動で加工してくれる。わからないことがあれば、生成AIに質問すれば答えが返ってくる。子どもたちの日常を振り返ってみると、ほんの数年前には想像もできなかった技術が、当たり前のように使われています。この変化のスピードは、私たち保護者世代が子どもだった頃とは比較になりません。
情報技術の進展により、子どもたちが将来就く職業の半分以上は、今はまだ存在していないとも言われています。
予測困難な時代を生きる子どもたちには、単に情報機器を「使える」だけでなく、情報技術を自在に活用し、自ら課題を発見して解決できる力が求められています。
現在の情報教育には大きな課題がある
では、今の学校教育で十分な準備ができているかというと、実は課題が山積しています。現在の情報教育の主な課題
- 小学校では「総合的な学習の時間」などで断片的に扱われているだけで、明確な位置づけがない
- プログラミング教育は導入されたものの、体系的なカリキュラムが不十分
- 生成AIなど新しい技術への対応が追いついていない
- デジタル機器の長時間利用や情報の真偽判断など、マイナス面への対応が不十分
- 諸外国と比べて、情報技術の仕組みを理解する学習内容が少ない
具体的な話をすると、たとえばタッチタイピング。政府は、小学生で「1分間40字」を目標として掲げていますが、実態は以下の通りです。

今の子どもたちは、それこそフリップ入力は幼児期から慣れていますが、パソコンを扱う基礎スキルであるタイピングは実際にはこのレベルであるわけです。
単なる「使い方」ではなく「理解して活用する力」を
2030年代の学習指導要領改訂でめざすのは、情報技術を「道具として使える」だけでなく、「仕組みを理解し、適切に判断しながら活用できる」力の育成です。- 生成AIが作った文章や画像の特性を理解し、どう活用すべきか自分で考えられる
- 情報の信頼性を見極め、自分の頭で判断できる
- デジタル技術を活用して、実社会の課題を解決できる
このような力は、文系・理系を問わず、すべての子どもに必要な「基礎力」として位置づけられます。
小学校の情報教育はどう変わる?

「情報の領域(仮称)」が導入予定
小学校では、総合的な学習の時間に「情報の領域(仮称)」が新たに設けられるとされています。年間で一定の時間を確保し、体系的に情報教育を行う計画です。最大の特徴は、体験的な活動を重視していることです。
座学で知識を詰め込むのではなく、実際に手を動かしながら、探究的な学びと一体的に情報活用能力を育てていきます。
小学生が学ぶ「情報」の具体的な内容とは
「小学生にどこまで教えるの?」と驚かれるかもしれませんが、内容を見ると「確かにこれは必要だ」と納得できるはずです。小学校で学ぶ主な内容
- 基本操作
→写真や動画の撮影、簡単な編集、インターネット検索、表やグラフの作成 - プログラミング体験
→ブロック型プログラミングなどで、コンピュータに意図した処理をさせる体験 - 情報技術の特性理解
→生成AIの特性(間違った情報を生成することもある)、デジタル情報の特徴 - メディアリテラシー
→インターネット上の情報の信頼性を見極める方法、写真や動画の加工の可能性 - 適切な取扱い
→個人情報保護、著作権の基礎、長時間利用による健康への影響、ネット上のコミュニケーションマナー
「え、うちの子が小学生になったら、こんなにいろいろと学ぶわけ!?」
って、正直、ちょっと焦りませんか?
とはいえ、わが子がこれから、小学校、中学校と進む中で、親も「知らない、わからない」というわけにもいきませんよね。さぁ、ここから、一緒にもっともっと学んでいきましょう!
「自分で課題を見つけて解決する力」が核心

たとえば、「地域の環境問題について調べよう」という探究学習で、子どもたちはタブレットを使って情報を集め、整理し、プレゼンテーション資料を作って発表します。
この過程で、次のような力を育みます。
1:どんな情報が必要か考える
2:検索して情報を集める
3:情報の信頼性を判断する
4:表やグラフにまとめる
5:相手にわかりやすく伝える
探求学習+情報技術で学ぶサイクルを繰り返すことで、課題解決力が定着します。情報技術は「探究の道具」として、子どもたちの学びを深めるために活用されるのです。
探求ってなんのこと?という方へ、こちらの記事も参考にしてくださいね。
探究学習とは何のこと?事例や学習内容を徹底解説!
中学校では新教科「情報・技術科(仮称)」が誕生
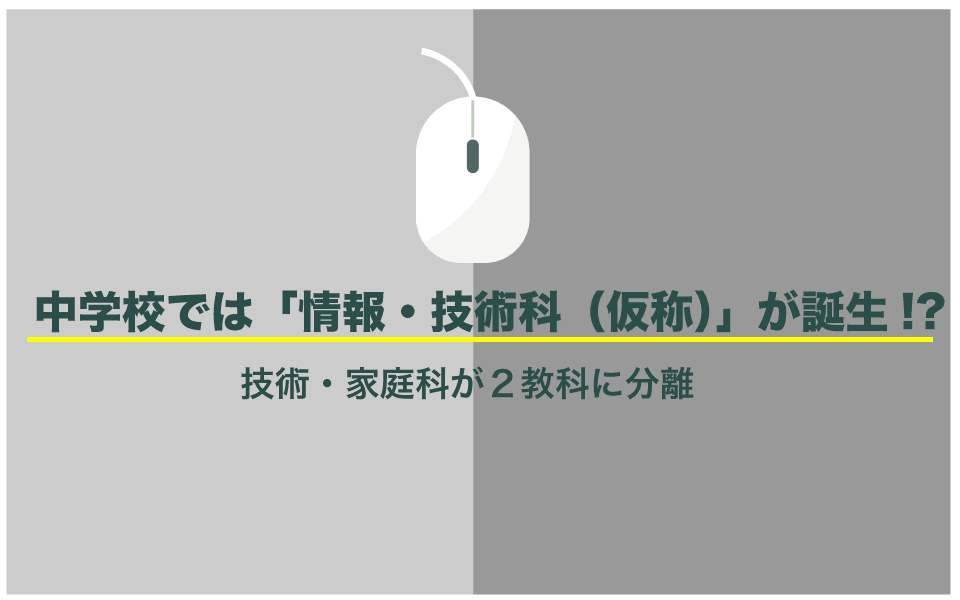
技術・家庭科が2教科に分離
中学校では、より大きな変化が起こります。現在の「技術・家庭科」が分離され、「情報・技術科(仮称)」と「家庭科」の2つの独立した教科になる予定です。これにより、情報技術の内容が大幅に充実します。授業時間も増え、より専門的な内容を学べるようになります。
中学生が学ぶ内容は高度化・体系化
小学校での学びを土台に、中学校ではさらに深く、専門的に学びます。情報・技術科(仮称)で学ぶ主な内容
| 分野 | 具体的な学習内容 |
| コンピュータとネットワーク | コンピュータの仕組み ネットワークの基礎 クラウドの概念 |
| データ活用 | データ分析の基礎 統計的な見方 データに基づく意思決定 |
| プログラミング | テキスト型プログラミング アルゴリズムの理解 簡単なアプリ制作 |
| 生成AI | 生成AIの仕組み 活用方法 限界や注意点の理解 |
| 情報セキュリティ | サイバー攻撃の種類と対策 個人情報保護 著作権 |
| ものづくりと情報技術 | 3Dプリンタ ロボット制御 IoT機器の活用 |
実社会の課題解決につながる学び
「こんな専門的な内容、うちの子についていけるかしら」と心配される方もいるかもしれません。でも、中学校での学びも、実生活や実社会の課題解決と結びついています。中学校での学びの一例
「地域の防災マップを作ろう」というプロジェクト
→データを収集・分析し、プログラミングで避難経路を示すアプリを作る。
「省エネ家電を設計しよう」という課題
→センサーとプログラミングを組み合わせて自動制御の仕組みを考える。
実際に手を動かし試行錯誤しながら、課題を解決する経験を通じて、情報技術が社会でどう役立つのかを実感できます。
将来の職業選択の幅が広がる
情報技術をしっかり学ぶことは、子どもの将来の可能性を広げます。IT企業だけでなく、医療、農業、製造、サービス業――どんな分野でも、デジタルを使いこなせる力が求められる時代です。
もはや情報は、国語や算数と同じように「誰もが学ぶべき基礎」となっています。文系でも理系でも、どんな仕事をめざすとしても、必要な力なのです。
高校、そしてその先の学びにつながる体系

小中高と段階的に深まるカリキュラム
2030年代の情報教育は、小学校から高校まで、一本の筋が通った体系的なカリキュラムになります。情報教育の体系的な流れ
- 小学校
体験を通じて情報技術に触れ、基礎的な活用方法と適切な使い方を学ぶ - 中学校
仕組みを理解し、実社会の課題解決に情報技術を活用できる力を育てる - 高校
専門性を高め、データサイエンスやAI、プログラミングなどを本格的に学ぶ
小学校で芽生えた興味が、中学校で深まり、高校で専門的な学びへとつながります。早い段階で「情報技術って面白い」と感じた子どもは、高校でさらに探究を深められます。
文系・理系を問わず必要な「情報技術の特性理解」
高校の情報科では、文理を問わず、すべての生徒が生成AI時代に必要な「情報技術の特性」を理解します。AIが得意なこと、苦手なこと。データに基づく判断の重要性と限界。情報セキュリティの本質。こうした知識は、どの分野に進んでも必要です。
法学部に進む生徒には、AIと法律の関係を考える視点が必要です。経済学部に進む生徒には、データ分析の基礎が役立ちます。医学部に進む生徒には、医療データの扱い方が重要になります。
探究的な学びを支える基盤として
情報活用能力は、各教科での探究的な学びを支え、駆動させる基盤です。- 理科の実験データを分析する
- 社会科で統計資料を読み解く
- 国語でプレゼンテーション資料を作る
- 数学で数式処理ソフトを使う
あらゆる教科で、情報技術を活用した深い学びが展開されます。
大学入学後も、レポート作成、データ分析、プレゼンテーションなど、情報技術を使いこなす場面は無数にあります。社会に出れば、どの職業でもデジタル技術との関わりは避けられません。
小中高で培った情報活用能力は、生涯にわたって役立つ「基礎力」になるのです。
保護者として何を知っておくべきか

2030年代に向けて、今から準備が進む
2030年代からの本格実施に向けて、今後数年間で準備が進められます。教材開発、教員研修、環境整備などが段階的に行われていきます。
お子さんが小学校に入学する頃、あるいは中学校に進学する頃には、新しい情報教育が始まっている可能性があります。保護者として、学校からの情報に注目しておきましょう。
情報教育強化の本質を理解する

「プログラミングができるようにならないと」「生成AIを使いこなせないと」と焦る必要はありません。情報教育強化の本質は、次の3つです。
情報教育がめざす3つの力
-
情報技術を活用した課題解決力
→情報技術を道具として使いこなし、自ら課題を見つけて解決できる力 -
デジタルとの適切な付き合い方
→情報モラル、メディアリテラシー、健康への配慮など、デジタル技術と上手に付き合える力 -
情報技術の仕組み理解
→生成AIなど先端技術の特性を理解し、活用の判断ができる力
こう書くとなんだか難しそうですが、要するに「なぜそうなるのか」「どう使うべきか」を考える力を育てることが重視されているのです。
私たち親は、「情報という科目の重要さ、なぜ重視されているのか、どういうことを小中高と学んでいくのか」を、ざっくりでいいので認識しておく、少なくとも関心を持っておくことが大切です。
家庭でできることは意外とシンプル
「学校で情報教育が強化されるなら、家でも何かしないと」と気負う必要はありません。家庭でできることは、実はシンプルです。家庭でできる情報教育サポート
- 子どもがタブレットやパソコンを使って調べ物をする機会を認める
- 興味を持ったことを、デジタル機器を使って深掘りする時間を見守る
- インターネットで見つけた情報について、「本当かな?」「誰が書いたのかな?」と一緒に考える
- スマートフォンやゲームの利用時間について、子どもと対話しながらルールを決める
- 生成AIを使ってみて、「便利だね」「でも間違いもあるね」と気づきを共有する
特別なことをする必要はありません。日常の中で、デジタル技術との向き合い方について、親子で対話することが大切です。
学校と家庭の連携が子どもを支える
学校で情報技術の活用方法を学び、家庭でそれを実践する。家庭での経験を学校で振り返る。学校と家庭が連携することで、子どもの学びはより深まります。「宿題でタブレットを使っているけど、何をしているのかわからない」という状態では、連携が難しくなります。日常的に、子どもがどんな学びをしているのか関心を持ちましょう。
授業参観や保護者会で、情報教育の取り組みを見る機会があれば、ぜひ参加してみてください。「学校でこんなことを学んでいるのか」という発見があるはずです。
不安よりも期待を持って
「デジタル機器ばかり使って、視力が落ちないかしら」「ネットいじめにつながらないかしら」
親としては心配は尽きませんよね。
でも、デジタル技術をただ遠ざけるのではなく、適切に活用する力を育てることが、これからの時代には必要です。
学校での情報教育強化は、子どもたちが安全に、賢く、創造的にデジタル技術と付き合える力を育てるためのものです。
不安よりも期待を持って、子どもたちの成長を見守っていきましょう。新しい時代を生きる子どもたちは、私たちが想像もできない方法で、情報技術を活用していくでしょうから!
今後の情報に注目を
2030年代の学習指導要領改訂に向けて、文部科学省や各自治体から、今後も詳細な情報が発信されます。学校からの配布物やウェブサイトなどで、最新情報をチェックしてください。情報教育の強化は、決して「学校だけの問題」ではありません。
子どもたちが生きる社会全体の変化に対応するための、大きな教育改革です。保護者として、その意義を理解し、子どもの学びを温かく見守り、支えていきたいですね。
「よし!ママやパパも一緒に学ぶよ」くらいのスタンスで、親子で共にデジタル化・IT化の大波小波をスイスイと泳いでいきましょう!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
文科省のGIGAスクール構想とは?小学校に1人1台タブレットはいつから?
文部科学省が進める「GIGAスクール構想」により、小学校では1人1台のタブレット端末が当たり前の時代に。本記事では、GIGAスクール構想のねらいや導入の背景、学校教育にどんな変化がある...
2025.08.27|コエテコ byGMO 編集部
-
小学校「教科担任制」のデメリットは?最新の現状についても解説
2022年度より「小学校での教科担任制」導入の指針が発表されたことはご存知でしょうか。2019年4月、当時の文部科学大臣から諮問があったことで一部では話題にのぼった「小学校教科担任制」...
2026.01.02|大橋礼
-
2020年の教育改革とは?3つのポイントをわかりやすく解説!
2020年は教育改革の年といわれています。 なんとなくニュースなどで耳にしたことがあっても、具体的に何が変わるのかまでは想像がつきにくいのではないでしょうか。 実は、コエテコで...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
アンプラグドプログラミングとは?パソコンを使わないプログラミング学習!
アンプラグドプログラミングという言葉をご存知でしょうか?小学校での必修化に向け、パソコンを使わずにプログラミングを学ぶ方法が注目を浴びています。具体的な内容、メリット、デメリットをわか...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
文部科学省提供「プログラミン」と学校現場でのリアルなプログラミング教育に迫る!
『プログラミン』は文部科学省が無料提供しているブラウザでプログラミング作成ができるサイトです。今回筆者の5歳の子どもが実際に『プログラミン』を体験しました。2020年プログラミング教育...
2025.05.30|Yukiko







大昔は、それこそ「女子は家庭科、男子が技術」なんて分かれていたのですから、隔世の感があります。