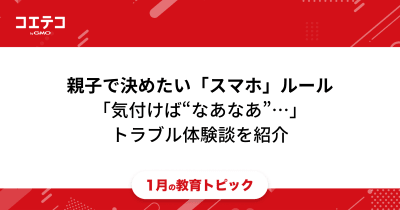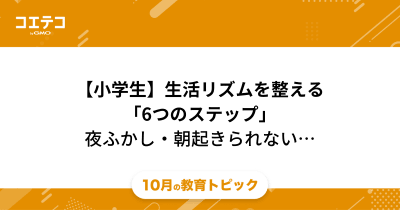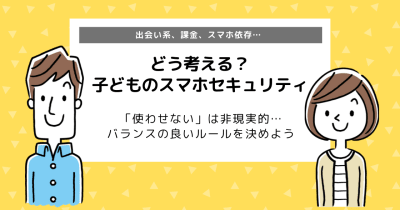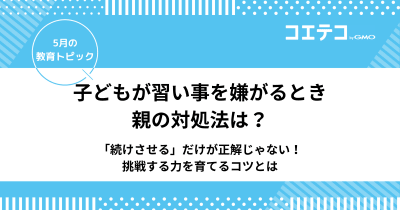子どものスマホは何歳から持たせる?平均やいつからなのか解説
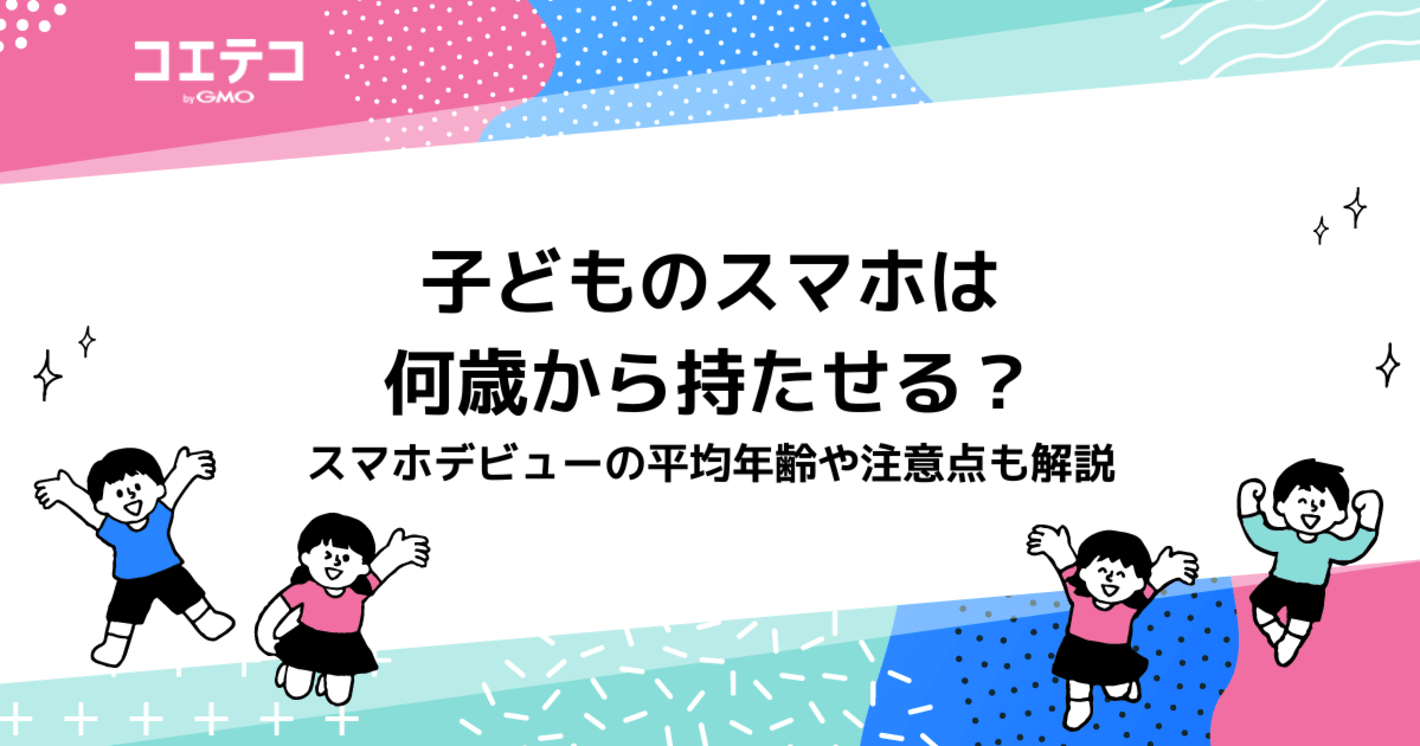
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
スマートフォンは、子どもの友人関係や行動範囲を広げるための重要なツールですが、デジタルデバイス特有のさまざまな課題があります。
「いつかは必要になる」「周りの子どもも持っているから仕方ない」と感じつつも、スマートフォンを何歳から子どもに持たせるべきか悩む保護者も多いでしょう。
この記事では、最新の調査データや専門家の視点を交えながら、子どもがスマートフォンを持つメリット・注意点、そして家庭で決めるべきルールを解説します。
何歳からスマートフォンを持つべきか親子でじっくり話し合い、スマートフォンデビューの時期を検討してみてくださいね。
子どものスマホデビュー、平均は何歳?【調査データ】

「周りの子は何歳からスマートフォンを持っているの?」というのは、多くの保護者が気になる点でしょう。
モバイル専門のマーケティングリサーチ機関であるMMD研究所の調査によると、子どもが初めてスマートフォンを持つ時期として最も多かったのは小学6年生で14.9%でした。
次いで中学1年生が12.7%、中学3年生が10.0%と続きます。
この調査では、初めてスマートフォンを持つ年齢は小学生が全体の51.0%を占めており、半数以上の子どもが小学生のうちにスマートフォンデビューしていることがわかります。

もちろん、ご家庭の方針やお子さんの生活スタイルによって最適な時期は異なります。
これらのデータは一つの目安として、小学校高学年頃から検討を始め、中学生のうちには持たせるイメージで、柔軟に考えていくのが良さそうです。
スマホを子どもに持たせる5つのメリット
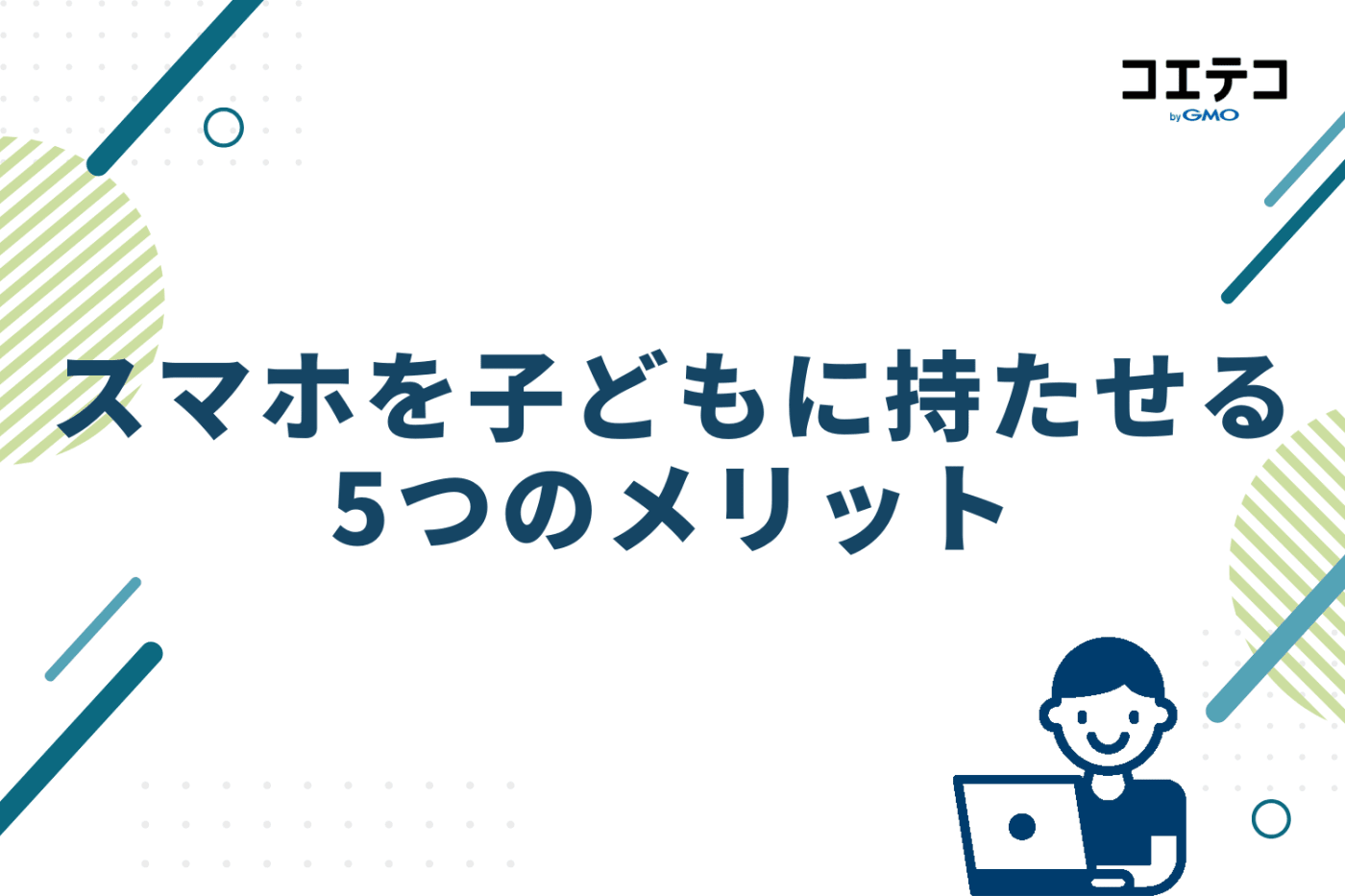
子どもにスマートフォンを持たせると、心配な面だけでなく、多くのメリットもあります。
ここでは、主なメリットを5つご紹介します。
メリット1:緊急時の連絡手段になる
共働きの家庭が増え、子どもが塾や習い事で遅くまで外出するライフスタイルが一般的になりました。スマートフォンがあれば、急な予定変更や災害時など、必要な時にいつでも親子で連絡を取り合える安心感があります。
これは、2000年代に携帯電話が普及した大きな理由の一つであり、スマートフォンが主流となった現代でも変わっていません。
メリット2:GPS機能で見守りができる
現在のスマートフォンには、位置情報(GPS)を追跡する機能が標準で搭載されています。保護者のスマートフォンから子どもの居場所を確認できるため、登下校中や遊びに出かけている時も安心です。
万が一、子どもが何らかのトラブルに巻き込まれた際にも、迅速な対応につながる可能性があります。
メリット3:友人とのコミュニケーションを円滑にする
「スマートフォンがないと仲間はずれにされる」という言葉は、現代の子どもたちが直面する現実の一つです。小学生の高学年にもなると、LINEなどのアプリを使ってグループで連絡を取り合うのが日常的になります。
友人関係を円滑にするためのコミュニケーションツールとして、スマートフォンが重要な役割を担っている側面は無視できません。
もちろん、スマートフォンが原因のいじめやトラブルも懸念されます。
この問題については、各家庭だけでなく、学校やPTAなどを通じて日頃から使い方を議論することが大切です。
参考:家で話さない子ども
メリット4:学習ツールとして活用できる
スマートフォンには、子どもの学びをサポートするポジティブな側面もあります。最近では、小学生からできるタブレット学習や学習アプリが充実しています。
小学生向けの通信教育がタブレットを取り入れ始めています。 情報を視覚的にとらえやすいタブレット学習は、印象に残りやすく、紙よりも手軽で場所を選ばずに勉強できるため、大きな注目を集めています。 今回はコエテコ編集部おすすめの小学生向けタブレット学習教材ランキングについてまとめました。
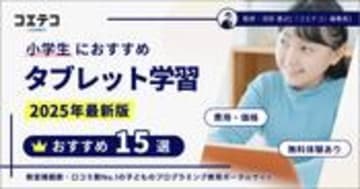

2026/01/28

通学の電車内や少しの空き時間に、ゲーム感覚で英単語を覚えたり、苦手な科目を復習したりと、スマートフォンは手軽な学習ツールとして大変役立ちます。
スマートフォンをただの遊び道具で終わらせないためにも、親子で一緒に学習アプリを探してみるのもおすすめです。
メリット5:ネットリテラシーを高めるきっかけになる
社会のデジタル化が進む現代では、インターネットの危険性から子どもを完全に隔離するのは現実的ではありません。ネット詐欺や個人情報の流出のリスクから身を守るためには、インターネットを正しく安全に使いこなす能力、すなわちネットリテラシーが不可欠です。
ネットが生活に欠かせない今こそ、身につけたいのが「ネットリテラシー」=「インターネットを適切に使いこなす能力」です。知っておかないと、意図せず加害者になってしまったり、身に危険が及んでしまうかも。分かりやすく解説します。
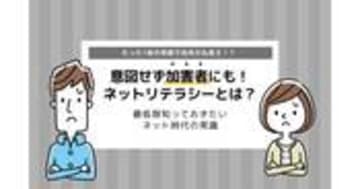

2026/02/07

高校生になってから自由にスマートフォンを使わせるよりも、小学生のうちから保護者の目の届く範囲で一緒に使い方を学び、危険な点や注意点を教えていくほうが、将来にわたって安全なネット利用につながるという考え方もあります。
知っておきたい!子どもにスマホを持たせる際の注意点と危険性
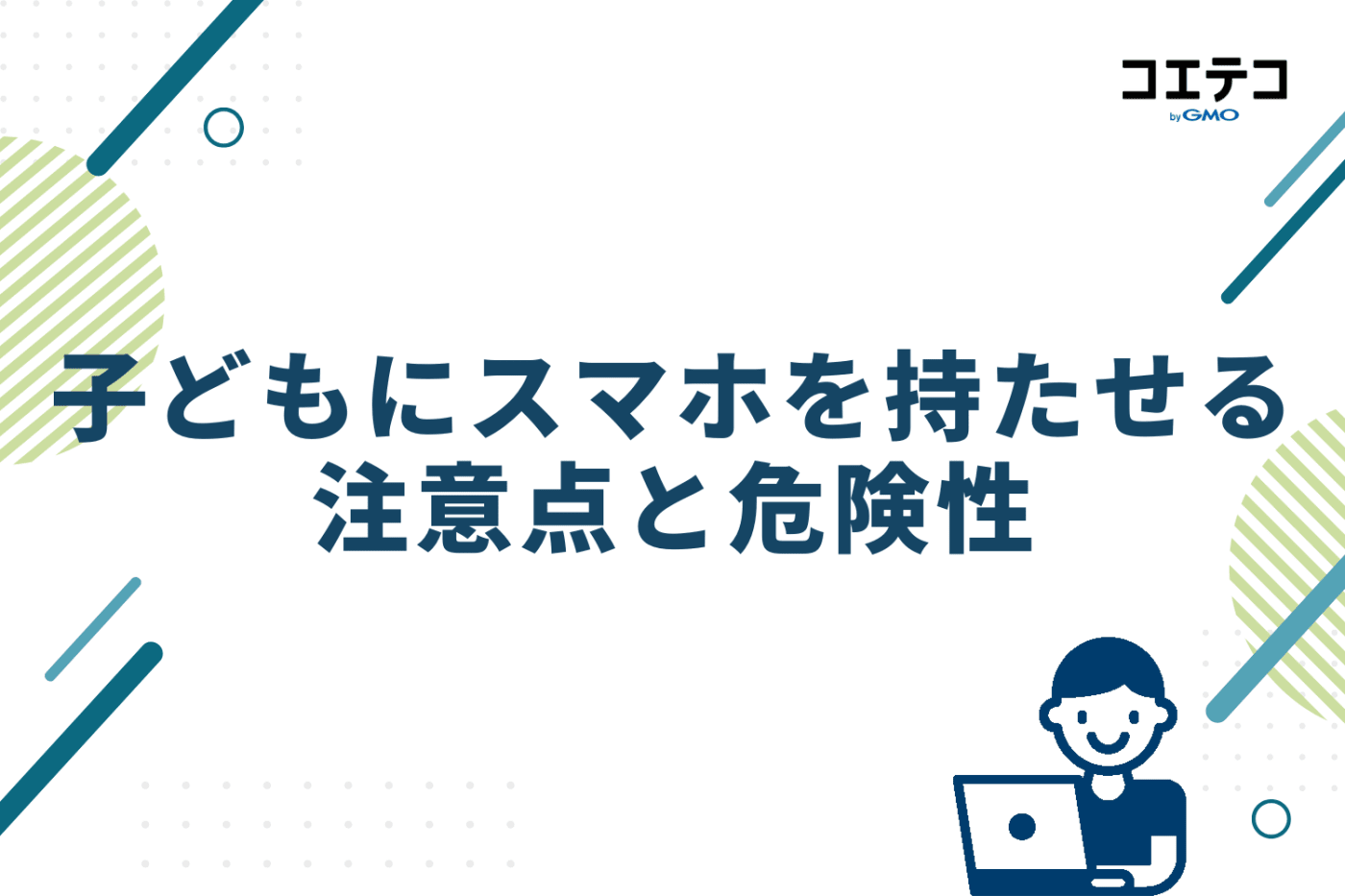
便利なスマートフォンですが、無条件に与えてしまうことには多くの不安がともないます。
スマートフォンを持たせる前に知っておきたい注意点や危険性を解説します。
注意点1:SNSの利用には年齢制限がある
LINE、Instagram、TikTokなどは、子どもたちがスマートフォンを持ったら真っ先に使いたがるアプリかもしれません。しかし、多くのSNSには利用規約による年齢制限が設けられていることをご存じでしょうか。
- 13歳以上が対象: Facebook, Instagram, X (旧Twitter), TikTok など
- 12歳以上を推奨: LINE (推奨年齢であり、保護者の判断に委ねる方針)
これらの制限は、子どもをトラブルから守るために設定されています。
利用を開始する前に、親子で各サービスのルールを確認しましょう。
注意点2:スマホ依存と睡眠不足のリスク
かつては深夜ラジオが学業の敵とされていましたが、現代ではスマートフォンによる夜ふかしと睡眠不足が深刻な問題となっています。夜遅くまで動画を見たり、友人とメッセージを送り合ったりすると、睡眠時間が削られ、翌日の授業に集中できなくなります。
スマートフォンの使いすぎを防ぐため、フィルタリングサービスやペアレンタルコントロール機能の活用がおすすめです。
たとえばiPhoneのスクリーンタイム機能を使えば、アプリの使用時間や夜間の利用を制限できます。
注意点3:アプリの課金トラブル
ゲームアプリなどでの高額課金は、子どもにスマートフォンを持たせる際に特に注意したいトラブルの一つです。子どもが悪意なく課金を繰り返してしまい、後から高額な請求に驚くケースは少なくありません。
対策として、アプリのインストールや課金は必ず保護者の許可をえるというルールを徹底しましょう。
iPhoneのスクリーンタイムやGoogle Playの承認機能を使えば、保護者のパスワードなしでは課金できないように設定できます。
後悔しないために!スマホを持たせる前に決めるべき家庭のルール

スマートフォンによるトラブルを防ぐには、購入前に親子でしっかりとルールを話し合い、合意しておくことが何よりも大切です。
ここでは、ルール作りのポイントをご紹介します。
口約束だけでなく、ルールを紙に書き出して、親子で署名するのもよい方法です。
ルール作りの参考として、アメリカのブロガーが作成し、世界中で賞賛された「スマートフォン18の約束」という動画があります。
親子で一緒に見て、家庭のルールを考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
日本語訳はこちらのサイトなどで確認できます。
2012年のクリスマス。アメリカで、母親が13歳の息子にスマホを与えるときに交わした「18の約束」が話題になりました(原題は「Gregory's iphone ...

https://act.fukoku-life.co.jp/club/contents/comic/detail/mamaletta/2021fall >
子どもに初めて持たせるスマホの選び方
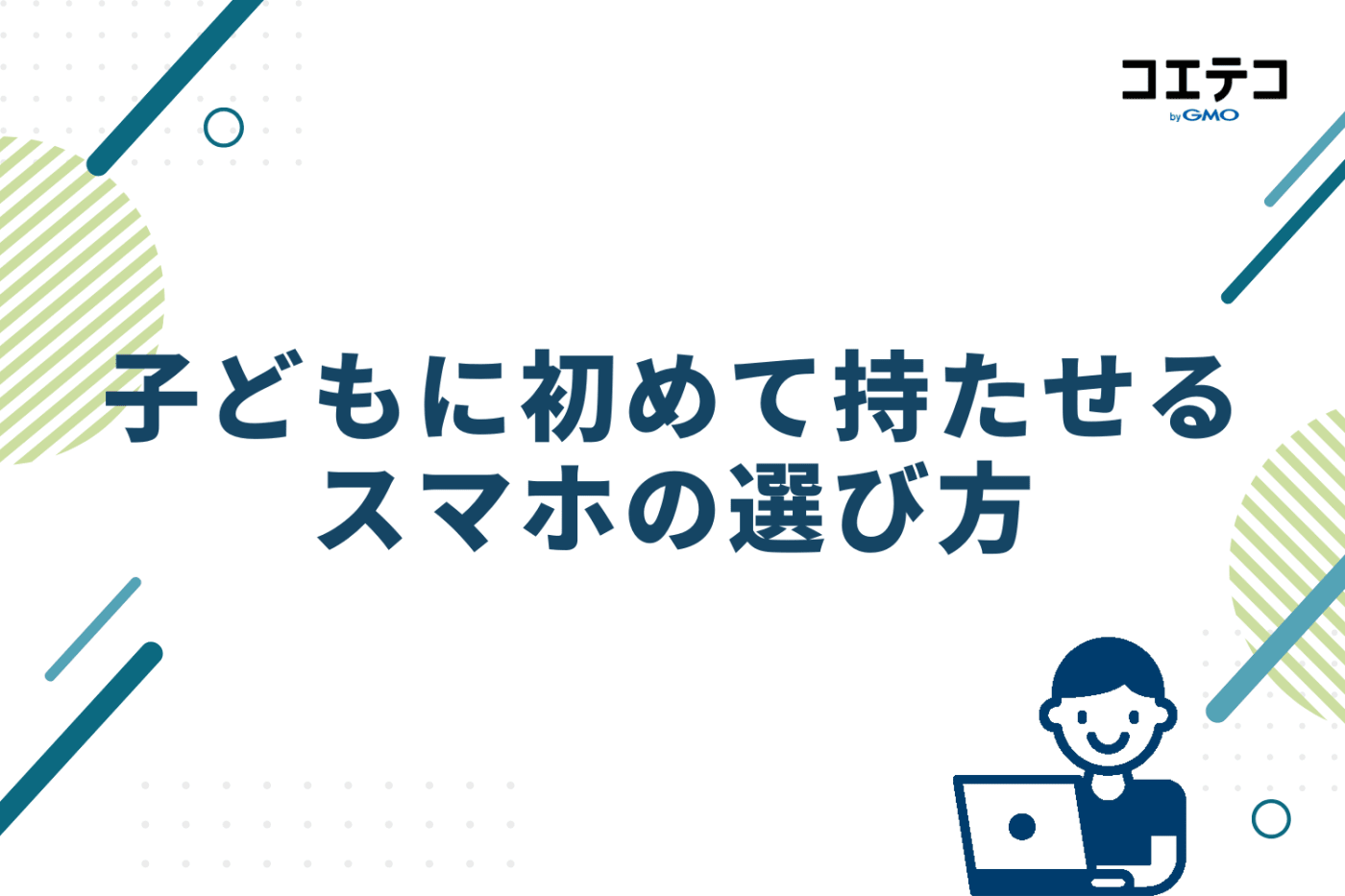
いざスマートフォンを購入するとなっても、どの機種やプランを選べばよいか迷うかもしれません。
ここでは、子ども向けの代表的な選択肢をご紹介します。
選択肢1:キッズケータイ
機能を絞って安全性を重視したい場合は、キッズケータイがおすすめです。通話やSMS、GPS機能など、必要最低限の機能に限定されている機種が多く、インターネットやアプリの利用ができないため、ネットトラブルの心配がありません。
主に小学生低学年〜中学年のお子さんに選ばれています。
選択肢2:格安SIMと通常スマホ
LINEでのやり取りや学習アプリの利用もさせたい場合は、通常スマートフォンと格安SIMの組み合わせが人気です。大手キャリアよりも月額料金を安く抑えられるのが大きなメリットです。
最近の格安SIM会社は、子ども向けのフィルタリングや利用制限などの見守り機能をオプションとして提供している場合も多いので、契約前に確認してみましょう。
iPhoneとAndroid、どちらを選ぶ?
保護者が使っているOS(iPhoneかAndroid)と同じものを選ぶと、操作方法を教えやすく、設定の管理もしやすいのでおすすめです。現在ではほとんどのアプリが両方のOSに対応しているため、機能面で大きな差はありません。
もし子どもが違う機種を希望した場合は、その理由をしっかり聞き、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら親子で話し合って決めるとよいでしょう。
まとめ:スマホは何歳から?という悩みは、親子の対話を深めるきっかけに

「スマートフォンは何歳から?」の問いに、唯一の正解はありません。
調査データによれば小学生のうちに半数以上がスマートフォンデビューしていますが、最終的には各家庭の方針とお子さんの成長に合わせて判断するのが大切です。
また、スマートフォンは便利なツールであると同時に、多くのリスクも潜んでいます。
買い与えるときに親子でじっくり話し合えば、インターネットの賢い使い方や自己管理の大切さに気づけるでしょう。
一方的にルールを押し付けるのではなく、子どもの意見に耳を傾けながら一緒にルール作りを行い、親子の信頼関係を深められるとよいですね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
スマホ依存症対「スマホ制限アプリ」が人気!ペアレンタルコントロールも活用しよう|1月の教育トピック②
年齢に関わらず、スマホを片時も放せない「スマホ依存」の問題が取り上げられています。特に子どもとスマートフォンの関係は、保護者にとって大きな関心事ですよね。今回の記事では、最初にお子さん...
2025.09.10|大橋礼
-
スマホのルールを守らない小学生・中学生!勉強しない!を解決しよう
最近はスマホを持つ小学生も増えました。購入前には親子で話し合いをし、使い方のルールを決めているご家庭がほとんどです。 しかし、約束やルールを守らずに親子喧嘩になってしまうのも、これま...
2026.01.30|大橋礼
-
小学生の生活リズムの乱れを整える「6つのステップ」夜ふかし・朝起きられないを改善しよう!
「最近、子どもがどんどん寝るのが遅くなっている」 「朝はなかなか起きてくれない」 多くの親が直面する悩みですよね。「ちゃんとしなきゃ」と思っても、実際は難しいのが現実。今回の...
2025.05.30|大橋礼
-
どう考える?子どものスマホセキュリティ|間違いのないセキュリティ設定とは?
どもがスマホを持つ年齢は年々低年齢化しているといわれます。 ゲームだけではなく学習ツールとしても使えるようになり、SNSを通じたコミュニケーションが友人関係で大事になるなど保護者とし...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
子どもが習い事を嫌がるときの親の対処法は?挑戦する力を育てるコツ
子どもが習い事を嫌がるとき、親はどう対応すべきでしょうか?「やめさせる」「続けさせる」どちらの選択にも、メリットとデメリットがあります。正解がないからこそ、悩むのは当然です。この記事で...
2025.05.30|大橋礼