塾にする?習い事を続ける?迷うママ・パパへの"納得できる"選び方

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
親子で話し合って「塾にするか、習い事を見直すか」を決められるのが一番いいのですが、小学生の子どもと将来や進路を見据えて話し合うといっても、なかなかうまくいきません。
結果として、親の考えだけで決めてしまいがちですが、たとえコロコロ気分が変わる小学生であっても、何度でも話をして、なんとか「互いに納得」した選択にしたいですね。
今回は、そんな悩みを抱えるママ・パパの気持ちに寄り添いながら、選択のヒントになるポイントを一緒に見ていきましょう。
「うちの子、このまま習い事だけで大丈夫…?」と感じたら

入学時は「元気で1年生になった!よかったな!」と思っていたのも束の間で、だんだんと勉強も気になってくるのが小学校時代です。
お子さんが成長するにつれて、周りのお友だちが塾に通い始めたり、中学受験の話が出てきたりすると、「このまま習い事を続けていていいのかな」「そろそろ塾に切り替えたほうがいいのかな」と迷うことがありますよね。

テスト結果が芳しくないと不安も増すというもの…。
特に3年生から4年生になるあたりは、学校の勉強の内容も少しずつ難しくなり、保護者としては将来のことも考え始める時期。学童が終わるタイミングでもあり、放課後の過ごし方に悩む方も多いでしょう。「このままでいいのかな」という不安が頭をよぎるのも自然なことです。
そんな迷いを感じているママ・パパに向けて、最初に習い事を続けるメリットとデメリットを見ていきましょう。
習い事を続けるメリット・デメリット

習い事を続ける【メリット】
- 自己肯定感が育つ
- 集中力や継続力が身につく
- 好きなことに夢中になれる時間がある
特に低学年のうちから続けている習い事であれば、「できた!」という成功体験や「頑張れば上手になる」という継続力を培ってきた可能性が高いです。何より、お子さんが「楽しい」と感じられる時間があることは、心の成長にとても大切な要素になります。
習い事を続ける【デメリット】
- 時間や体力に余裕がなくなり、勉強との両立が難しくなることも
- 長く続けていても、惰性になっているケースもある
習い事を長く続けることで、「本当に楽しんでいるのか」「何のために続けているのか」がわからなくなることもあります。なんとなくやめるタイミングがないまま、続けてしまうのもよくあること。
また高学年になるにつれて学校の勉強が増えてくると、時間的な余裕がなくなってくることも考えられます。習い事の量や日数が多く負担になり、宿題さえも後回しになって、家庭学習のペースが乱れてしまうようだと、マイナス面の方が大きいケースもあります。
塾に切り替えるタイミング、どう見極める?

では、「そろそろ塾かな?」と考えるきっかけには、どんなサインがあるでしょうか。
習い事から「塾へ」切り替えタイミングは3つ
- 学校の勉強についていけていない様子がある
- 苦手な教科を克服したいという気持ちが見える
- 中学受験など、目標が明確になってきた
こうしたケースでは、塾という選択肢が適切なこともあります。具体的には、たとえばテストの点数が毎回60点以下ともなると、腰を据えて子どもの勉強を見直す必要があります。
ただし大切なのは、「親が不安だから」という理由だけではなく、「子どもの気持ち」が出発点になっているかどうか。
お子さん自身が「なんか勉強わからなくなってきて不安だな」と思い始めたタイミングで、「通信教育とか塾とか、勉強の方法っていろいろあるよ」と選択肢のカードを見せてあげられるといいですね。
高学年になったら、中学進学を考えて、親子で勉強や進路について少しずつ、話し合うように意識することも大切です。

子ども自身に「勉強」や「成績」を意識させることも大事。
中学受験の選択肢も同様です。
もちろん、幼児期からしっかり「進路計画」をたてているご家庭もあるでしょう。
でも、実際には、「まぁ成績が良くて、学費が払えそうなら中学受験もありなのかな」とか「中学受験は無理。あとは公立中学に進んでから、高校とか大学とか考えていこう」と漠然と進路を捉えているご家庭の方が多いのではないでしょうか。
中学受験の決断は今回のテーマとは外れますが、目標として明確に受験をするとなれば、習い事との両立は可能であるにしても、塾に通うのはほぼ必須となります。
受験の選択肢も親だけで決めるのではなく、子どもと話し合うのが大切です。とはいえ、まだまだ小学生、「自分の意見」を伝えられないかもしれません。それでも、どんな風に思っているのかを聞いてみましょう。
いずれにしても、お子さんの気持ちに寄り添いながら、一緒に考えていくことが大切です。
迷ったときは、こんな視点で考えてみて

塾か習い事か、迷ったときのチェックポイントとして、次のようなことを意識してみましょう。
- 子どもが今、何に意欲を持っているか
- 習い事が子どもの将来の夢や関心とつながっているか
- 子ども自身が勉強と進路への意識を持つようになっているか
たとえば、ピアノが大好きで「もっと上手になりたい」と練習に打ち込むお子さんの場合、その情熱を大切にした選択ができるといいですね。一方で、「なんとなく続けている」という状態であれば、本人の気持ちを聞いてみる良い機会かもしれません。

子どもの興味はいろいろなところにある。
子どもの"今"を大切にしながら、数年後の姿にも思いを馳せてみましょう。
もし、子どもなりに「大きくなったら…」と希望や夢を描いているなら、それを奪い取るのは少し酷な気がします。たとえ大人目線では「プロ野球選手は難しいだろう」「ピアニストになりたいと言いながらも、遊びに誘われると練習をほったらかしにするくらいだから真剣ではない」と思うとしても、です。
いったん期間を区切って、「そろそろ勉強も頑張らないとね。でも、やりたいことなら応援するよ。とりあえず冬休みまでは今の状態で、お休みに入ったら一緒にまた考えてみようか」と声をかけるのもひとつの方法です。
こうすることで、子どもに将来の選択について考える時間を与えつつ、勉強の大切さも自然と意識させることができます。
保護者の不安や願いも大切ですが、子どもの目線に立って考えることで、納得のいく判断につながります。
「もうみんな塾に行ってるよ!この成績だと中学行ってから苦労するからね」と親が結論を先に出すのではなく、子どもが「塾に行ったほうがいいのかな」「でも今やっているサッカーはやめたくないんだよな」と自分の考えをまとめられるよう導いてあげたいですね。
上手に親子で話し合うには?

塾か習い事か、と悩む時期は、子どもが小学校4年生あたりから増えてくるのですが、この頃はちょうど自我が芽生えて、親のいうことは聞くには聞くけど、自分の気持ちも強くなってくる、難しい時期でもあります。
そのためか、習い事や塾についてどう思うか、話し合おうとしても「別に〜」とか「なんでもいい」とか、モヤモヤするような答えしか返ってこないこともあります。
親子で話し合うのは、いざとなると難しいもの。ここでは2つの「上手に親子で話し合うヒント」を紹介します。
(1)質問の仕方を変える
「塾に行ったほうがいいよね?」「サッカーは続けたいってことだよね?」とイエス・ノーの問いかけにすると、子どもは親の期待に合わせた回答をするか、逆に「別に、どっちでもいい」と無関心な様子を見せやすいようです。「サッカーって、どんなときが一番楽しい?」
「塾って言われて、ちょっと嫌だなって思うとしたら、どんなところかな?」
はい・いいえ、では答えられない質問にして、子どもが少しでも話しだしたら、否定せずに聞く姿勢を保つのがポイント。「もし」と仮定で聞いてみるのも良い方法です。
「もし、サッカーじゃなくて、他のスポーツなら何がいいと思う?」
「友だちが塾に行ってて、楽しそうだったら、自分も行きたいと思う?」
仮定の状況で想像する形にすると、子どももリアルに捉えやすく、そこで話し出すこともあります。親が知りたいすべての回答を一度に得ようとせずに、きっかけを作りながら、子ども自身も自分の本音を探り出して、言葉にして伝えていけるようにできるといいですね。
実際、子ども自身も本当にまだ「よくわからない」ことも、「よくある」ことだからです。
(2)ちょっとしたタイミングに「おしゃべり弾」を投げてみる
向かい合ってきちんと話し合う時間を持つことも必要ですが、うまく子どもと話せない時は焦らず、別のタイミングを待つのも大事。「さぁ話し合いましょう!」というスタンスに構えてしまう子どもも多いですよ。
たとえば、休日で買い物に行く途中に歩きながら、とか、夜、電気を消して「おやすみ」を言う前に少しだけ聞いてみるとか。
夕飯の後、果物をむきながら「そういえばさ」と話しかけるとか。
塾も習い事もどちらも行う、そんな決断もありますね。次では、塾と習い事の両立について考えてみましょう。
塾と習い事、両立はできる?併用のヒント

「塾か習い事、どちらかを選ぶのではなく、両方続けたい」と考えるご家庭も多いと思います。
塾と習い事を両立させるためのヒント
- 習い事は「週1〜2回」など頻度を見直す
- 塾と習い事の「主軸」を決める(どちらを優先するか)
- 定期的に「今のバランスで負担がないか」を見直す
実際、両方を無理なく続けている家庭も少なくありません。「月曜と木曜は塾、水曜は習い事」というように、スケジュールを固定化することで生活リズムを作ることもひとつの方法です。
また、好きな習い事を続けることで、勉強に対するモチベーションが上がる、集中できるという面もあります。
ただし、お子さんの表情や言動から「疲れていないか」「楽しめているか」を見守ることを忘れないでくださいね。どちらも精一杯がんばろうとすると、それこそ学校に行ったら眠くなってしまうなど本末転倒のことにもなりかねません。主軸を決めておくことも大事です。
中学受験でも習い事をやめないパターンも実際にありますよ!こちらの取材記事で先輩ママ・パパがインタビューに答えてくれているのでぜひ参考にしてください。
ロボット科学教育「Crefus(クレファス)」に通うお子様を持つ保護者の方に、習い事と中学受験を両立する秘訣について伺いました。ハードな中学受験と習い事の両立をどう乗り越えたのか、クレファスで得た知識・スキル・体験が中学受験にどう役立ったのか。経験者だからこそのリアルな声をお届けします。


2025/05/30

先輩ママに聞いてみた!「やっぱり塾か習い事か、悩んだ結果は?」
塾か習い事か、私も悩みました。息子が小4になると、周りの子が次々と塾に通い始め遊び相手が減り、オンラインゲームに夢中に。「習い事も塾も詰め込んで忙しくさせたほうがいいかも」と考えました。「これが絶対正解」という選択はなかなか見つからないものです。その時々の状況や子どもの様子を見ながら、試行錯誤しながら進んでいくことが大切なのかもしれません。
息子が唯一夢中になっていたのはバスケで、学校の体育館で卒業生やボランティアが教える週1のスポーツでしたが、その日を楽しみにしていました。スイミングはあまり乗り気な様子ではなかったので、結局スイミングをやめて英語塾に通わせることに。小5の4月からです。
中学の教科書を先取りするタイプの塾を選んだのは正解でした。英語で苦労する子が多い中、息子は英語が苦にならず、得意科目になったので良かったと思っています。
夏休みからは近所の補習塾にも通わせましたが、こちらは単なる自習室のようなもので、宿題をやりに行くだけの状態に。サボっていた日もあったようで、そもそも「近いし、安いし、とりあえず通わせてみるか」と適当に選んだのがよくなかったのかもしれません。
大切なのは、「なぜそれを学ぶのか」「どうしてそこがいいのか」をきちんと考えることだと実感しました。
これからを考えて必要なことは何か、それが塾なのかどうかを考え、目的に合った塾を選ぶこと。同時に、子どもが夢中になっているものには理解を示して、一緒に応援することが大切なのではないでしょうか。と言っても、当時はそこまで考えていませんでした。
振り返ると、むしろ息子が好きだったバスケを本格的なチームでやらせてあげれば良かったかもしれません。一緒にチーム見学や体験会に行ってあげればよかったな、と思います。体力がないと決めつけていましたが、週末も試合があるチームに入れば、忙しく充実した時間を過ごせたでしょうし、オンラインゲームから離れる時間も増えたはず。
今、中学のバスケ部で生き生きと活動する息子を見ると、そう思わずにはいられません。(Tさん/子ども・中1)
『子育てって、真っ只中は悩んだり迷ったりばかりしているし、後から、こうしておけばよかったのかも、の連続ですよね』と、Tさんは話していました。
子どもの成長とともに、手がかかることは減るのに、気を揉むことは増えてくる。悩んでいるのは、みんな、一緒なんですね。
子どもに合った"今の選択"を大切に「まずは小さな会話から」
習い事を続けるにしても、塾に切り替えるにしても、両方を併用するにしても、お子さんにとって意味のある選択になります。どの選択が「正解」ということはなく、その子に合った「今の選択」があるだけなのです。大切なのは「続ける意味」と「子どもの気持ち」を一緒に考えること。「このままでいいのかな?」と迷った時こそ、お子さんとじっくり向き合う良いきっかけになるはずです。
まずは今日、帰宅したお子さんに「習い事、楽しい?」「学校の勉強はどう?」と、何気ない会話から始めてみませんか?きっと、これからの道筋が少しずつ見えてくるはずです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
中学生の進路選択「迷う子どもに親ができること」
「うちの子、将来のことを全然考えていなくて心配」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。しかし、中学生が進路について明確な目標を持っていないのは、実は珍しいことではありません。...
2026.01.08|大橋礼
-
子どもが習い事を嫌がるときの親の対処法は?挑戦する力を育てるコツ
子どもが習い事を嫌がるとき、親はどう対応すべきでしょうか?「やめさせる」「続けさせる」どちらの選択にも、メリットとデメリットがあります。正解がないからこそ、悩むのは当然です。この記事で...
2025.05.30|大橋礼
-
小学生から始める理科好きに育てる方法とは〜理科嫌い・リケジョ・文理選択を考える〜
理科嫌い・理科好きは、まだずっと先のことと思っている進路の「文理選択」にまでつながっています。 今回の教育トピックは、理科嫌い・理科好きの子どもの特徴や育った背景を探りつつ、「うちの...
2025.09.10|大橋礼
-
小学生「将来の夢ランキング」!子どもの夢と親の役割
「大きくなったら何になりたい?」親なら一度は子どもに聞いてみるセリフですね。4~5歳の子どもは元気に「ウルトラマン!」「プリンセス」なんて答えて微笑ましいものですが、だんだんと子どもの...
2025.11.12|大橋礼
-
家事代行サービスおすすめ5選|塾や習い事の送迎に使えるかも?
子どもを習い事に通わせるとなると、保護者のスケジュールにも大きな影響がありますよね。 そんなときに役立つかも知れないのが家事代行サービスです。 今回は、おすすめ業者や費用の目安、頼...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部













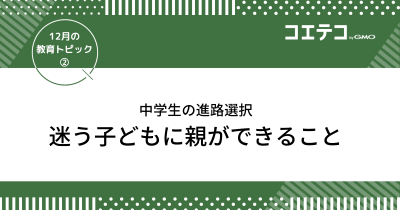
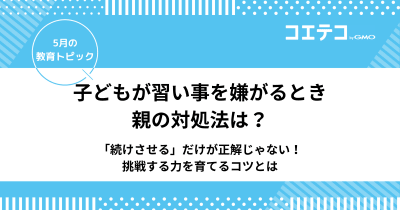

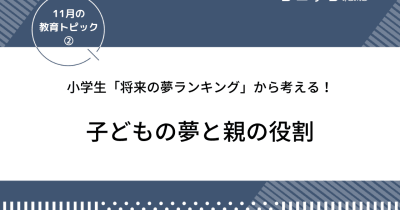

ついつい、「だってさ、◯ちゃんだって塾行き始めたじゃない?」なんて言ってしまいがちですが、そこはグッと我慢です!