プログラミング教育必修化目前、ネガティブ意見に経産省・浅野大介氏が答える(インタビュー)

「コエテコ」は子どものプログラミング教育を考えるメディアとして、過去数回にわたって保護者の意識調査を行い、レポートを発表してきました。
(最新)2019年9月9日〜12日の調査結果
小学生向けのプログラミング・ロボット教室情報掲載数が業界No.1のプログラミング教育ポータルサイト「コエテコ byGMO(以下、コエテコ)」は、2020年の小学校での「プログラミング教育必修化」まで約半年と迫る中、小学生の子どもがいる保護者920名を対象に「小学校でのプログラミング教育に関する保護者の意識調査」を実施いたしました。


2025/06/03

テレビや新聞で取り上げられる機会も増え、必修化に関する記事は大きくアクセスを伸ばしています。
小学校でプログラミング教育が必修化されて以降、中学校や高校にも広がり、子どもたちがプログラミングに触れる機会は確実に増えています。一方で、保護者の中には「何を学んでいるのか」「将来にどう役立つのか」といった関心や不安を抱く方も多いはず。本記事では、小学校におけるプログラミング教育の内容や目的をわかりやすく解説します。


2025/11/17

今後の動きについての関心が高まるとともに、SNS上ではさまざまな疑問や批判の声も。
「受験や就職に関係があるの?」
「どうして必修化するのか分からない」
「また学校の先生の負担を増やすのか」
「スター校ばかりが取り上げられ、『普通の学校』の取り組み内容が見えてこない」
地域格差や経済格差、先生の過重労働など教育環境をとりまく問題は注目を集めています。プログラミング教育の「なぜ?」「どうなる?」は保護者だけでなく、すべての人の関心事となっているのです。
今回、コエテコは経済産業省 教育産業室長である浅野 大介(あさの・だいすけ)さんにインタビュー。
「未来の教室」実証授業など教育改革の最前線で道を切り拓く浅野さんにあえてネガティブな意見をぶつけ、詳しくお答えいただきました。

プログラミング教育が「盛り上がらない」のはなぜか
—プログラミング教育の必修化を前に、民間のプログラミング/ロボット/STEMスクールの数も増えてきました。ところが、思うように認知が広がっていないとか、生徒を獲得できず撤退する事業者も少なくありません。英語(英会話)スクールと比べると苦戦している印象ですが、どうしてこのような状況になっているのでしょうか。
きっと、「必修化の意図」が保護者に伝わりきっていないでしょうね。
プログラミング教育が新学習指導要領に盛り込まれること自体は認知されてきました。とはいえ、多くの親御さんにとっては「受験に関係がない」「一教科増えるだけでしょ?」程度のインパクトでしょう。
プログラミングとは何か、プログラミング教育を受けさせてどうしたいのか。意義、意図が充分に伝わっていないと感じます。
—なるほど。では改めて、プログラミング教育の意義、意図を教えていただけますか?
今や、人間社会のあらゆるところにプログラミングあり、です。介護や福祉の現場もそうだし、スマート家電や自動運転もそう。もはやコンピュータサイエンスと無縁の場などほとんどない。
未来を生きる子ども達には、社会の誰かを幸せにできる、様々な課題が解消された便利で面白い世の中を創れる大人に育って欲しい。それが必修化の本来の意図です。
保護者の間には、それが伝わりきらないまま「プログラミング教育」という言葉だけが一人歩きしている側面があるのかもしれません。
民間のプログラミングスクールもそうで、意義、意図に関する議論が抜けたまま事業だけをスタートさせた教室も中にはあるでしょう。
そうしたスクールでは保護者の「どんな意味があるの?」にしっかりと答えられませんから、思うように事業が伸びないのも納得できます。
とはいえ、プログラミング教育市場は黎明期ですから、今後もいろいろな事業者が参入し、多種多様なサービス・教材が生まれるでしょう。しばらくすれば自ずと良質な教育だけが残っていくことと思います。
「自社教材での囲い込み」を問題視する向きも
—教材に関しては、「自社教材の枠内に囲い込むスクールが目立つ」「Scratchの見た目を変えただけでオリジナルと言うのはどうなのか」などの批判もあります。
黎明期なので、色々な企業が参入し、さまざまな教材が生まれること自体は喜ばしいと考えます。
とはいえ、プログラミングを含むSTEAM教育全体の本質である「『創る』と『知る』の循環」が伝わるかどうかが大切です。これを理解していない教材は子どもにとっても手応えがありませんから、スクールと同様、いずれ良質な教材だけが生き残るでしょう。
それから、教材はどこまで行っても教材ですから、どのみち入口しか提供できません。むしろ、教材をきっかけに本気でプログラミングを学びたいと考えた子が活躍できる場をどう作るかを今後は真剣に考えるべきでしょうね。
避けては通れない、中学受験との兼ね合い
—子ども向けプログラミングスクールは年齢/予算ともに中学受験市場とバッティングしやすい業界です。「受験に関係がないのに習わせる意味はあるのか」と迷う保護者も多いですが、浅野さんはどう考えますか。
私立学校の魅力は、通う生徒の意識レベルがある程度揃っているところにあります。そうした集団にわが子を置いて好影響を受けさせたい、と願うのは親の性ですから、否定することはできないでしょう。
とはいえ、今後は「名門校へ入学したから安心」という時代ではもはやなくなっています。有名校を卒業したか否か、ではなく「あなたは何を生み出せるのか」「あなたは何者なのか」をずっと問われる時代が来るのです。
そう考えると、子どもに無理をさせてレベルの合わない学校に入れるよりも、将来的に必要になる論理的思考力や情報編集力を早いうちに身につけさせるほうがよい。
論理的思考力や情報編集力の基礎さえできていれば、短い時間でも勉強にしっかり取り組むだけでその子の適性に合った学校に入学できるのではないかと思います。

保護者の方には目先のことに囚われないでいただきたいですし、事業者は保護者の不安にしっかりと回答できるスクールであって欲しい。
「遠回りに見えるかもしれませんが、こちらのほうが近道なんですよ」と胸を張って言える教育を提供して欲しいですね。
スター校ばかり取り上げられる現状の是非
—「教育改革に関して調べると、スター的な学校の取り組みばかりが目立つ」という意見があります。確かに、麹町中学校(千代田区)* の取り組みなどは私もよく目にしますが、こうした意見をどうお考えになりますか。
表紙に躍るセンセーショナルなタイトル。スマートなスーツ姿の著者――。私はてっきり、本書は先進的改革を行う民間人校長のサクセスストーリーかと先入観を持ってしまった。 しかし、ある意味ではこれは「嬉しい...
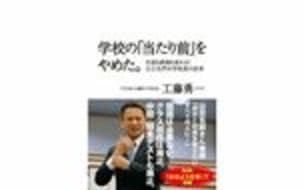
https://bunshun.jp/articles/-/10831 >
教育現場を変える困難さはもちろん我々も分かっています。ただ、あえて言いますが、そうした学校も、あくまで「普通の公立」です。
私たちの実証モデル校のひとつである千代田区立麹町中について言えば、施設は確かに立派ですし、有名な工藤校長もリーダーシップがあってビジョナリー(先見の明を持つ人)です。
けれども、彼らは学校教育法や学習指導要領をしっかりと理解した上で、その合理的解釈の中で、なにより、教育の最上位目標を常に保護者と合意しながらやれることを精一杯やっているだけ。「公立中学校でもここまで自由なやり方ができるんだ」と示してくれているんです。
教育の最上位目標をしっかりと学内や保護者と議論し共有する。目標に照らし、本当にベストな解か?と考える。その過程で不要なルールや行事は廃止する。
あの学校の改革の本質は、現行法令内で、常に原点に立ち戻って議論する文化を学内に作り上げたというシンプルな話ですから、同じやり方は全国どこでもできるはずです。

もしもそれが難しいというのであれば、学校設置者や管理者がそれを許していないか、現場の先生方に議論や改革の経験が不足しているか、のどちらかではないでしょうか。
中には、自分の置かれた環境を自力で変えていくトレーニングを受けないまま先生になった方もいます。そうなると、「学校現場を自力で変えられる」と信じられないのかもしれません。
管理職がこのタイプだと若手の提案を受け入れる環境にはなりません。そもそも入り口の教職課程全体の課題かも知れませんね。
語学(英語)教育は中国を参考にすべき
—小学校の学習内容に英語やプログラミング教育が加わり、教員の負担増を懸念する声があります。英語教育に関しては中国を参考にすべきですね。私は中国に留学したことがあるのですが、EdTechがフル活用されていました。
たとえば英語の発音は、正しいか、間違っているかの二択でしょう。まさにAIの得意分野です。先生がみんなの前で「リピートアフターミー(繰り返して言ってみましょう)」なんて言わなくとも、スマホを持たせてAI相手にトレーニングすればいい。
いわばスポーツの感覚で、反復練習は完全にEdTechの範疇でした。「ツールはツール」と割り切っているんです。
ただし、英語を実際に使ったり、議論したりする場面はAIには任せられませんから、そちらはネイティブスピーカーの力を借りるべきでしょう。
オンラインでネイティブと繋がり、ライティングやスピーキングの指導をしてもらう。学校の先生がすべてを担う必要はありません。「先生も一緒に勉強しているよ」くらいの姿勢でいいと思います。

プログラミング教育は地域・民間との連携がカギ
—プログラミング教育に関してはどうでしょうか。外部の力を借りるべき、という点ではプログラミングも同じです。学校でのプログラミング教育をどうデザインしていくかは非常に重要なポイントですね。
外部の人を呼んでくるのは、「本物感」を子ども達に見せるためです。どんな風にお仕事をされていて、どのように社会の役に立つのかを子ども達に知ってもらう。
我々経産省も、業界団体を動かしながらプログラミングを指導できる方を学校現場に送っていただけるよう協力しています。
—とはいえ、エンジニアの就職は買い手市場です。IT企業でも採用に苦しむ時代、教育現場に一線のエンジニアを呼び込むのは難しいのでは。
一線の方に来ていただくのはときどきでも構わないと思います。リアルに現場に来ていただく必要もなく、オンラインで対応していただければ充分。
そもそも、学校の限られた時間では入り口程度しか扱うことができませんから、普段の授業運営は民間の講師や情報工学系の大学生に任せても良いんです。
—「大学生にボランティアで働いてもらう」方法は各所で強い批判を浴びていますが……。
いえいえ、もちろん正当な対価は支払うべきです。タダでやらせるとか、自腹を切って来させるというのはすべきではありません。各自治体や地場のIT関連企業から予算面でのサポートがあるのが望ましいでしょう。

地方の人手不足は深刻な問題です。それぞれの自治体や地場のIT関連企業には、教育への先行投資をするのだという意識を持っていただきたい。
もしかすると、指導に携わる大学生自身がその地域に根付いてくれるかもしれません。プログラミング教育を地域にとっての死活問題と捉え、協力していただきたいと考えています。
我々経済産業省も、民間の事業者であるLife is Tech!(ライフイズテック)と協力して「『未来の教室』実証事業」を進め、地元の大学生がメンターになって子ども達を指導するような授業スタイルを計画・実証しています。今後はこのような活動が全国に広がっていくことが理想です。
プレスリリースや各種取り組みを紹介するお知らせなど、ライフイズテックの最新情報を掲載しています。

https://life-is-tech.com/news/pressrelease/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%95%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e3%80%81%e7%b5%8c%e7%94%a3%e7%9c%81%e3%81%ae%e3%80%8e%e3%80%8c%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%80%8d%e5%ae%9f >
新しい学びは「モチベーション格差」を拡大する?
—アクティブ・ラーニングについて、「活発な子ばかりが活躍し、内気な子が萎縮するのでは」と心配する保護者がいます。アクティブ・ラーニングの本来の意味* とはズレるかもしれませんが、学習へのモチベーション格差はどう考えるべきでしょうか。
「モチベーション格差」の問題はもっと深刻に捉えられるべきです。これからの社会では、モチベーションの有無が他の格差をより拡大していくのですから。
今の学校教育ではモチベーションの低い子への対応が手薄です。「やる気が起こらない」と訴える子に「いいから座っておけ」なんてナンセンスでしょう。理由も目的地も知らせないまま何かをやらされるのは苦痛でしかありません。
アクティブ・ラーニングは生きた知識を学び、活用する学習方法ですから、モチベーション問題を解決する糸口になる可能性があります。
—具体的な事例を教えていただけますか。
長野県に、「総合学習」で有名になった伊那市立伊那小学校という学校があります。自分たちで動物や野菜を育てたり、味噌や醤油を作って販売したりまでする。こうした総合学習を中心に据えて一年中の授業が組み立てられており、プロジェクトの中に教科の単元が見事にちりばめられているカリキュラムが大きく取り上げられたのです。
長野県の伊那市立伊那小学校は、60年以上も通知表がない。さらに時間割やチャイムもない。熊本大学教育学部の苫野一徳准教授は「公立小学校でもここまでできるのかと多くの人は驚くだろう」という。なぜそんなことができるのか――。

https://president.jp/articles/-/28207 >
「プロジェクトを進める」という目標がありますから、学ぶ目的も明確です。正確に計算をして土の配合や施肥をしなければ、野菜は量産できません。チーム内の誰しもが理解できるように日々の観察記録や伝達をできなければ、動物の健康状態を損ないます。算数や国語や理科を生きた知識として学ぶカリキュラム設計は見事なものでした。
もちろん、課題がないわけではありません。教科内容の深掘りや、クラスのプロジェクトに興味を持てない子への対応など、もっと改善していく余地はあるかもしれません。
それでも、現行の学習指導要領の範囲内でこういう学校づくりができるんだなと、アクティブ・ラーニングってこういうことなんだなと感銘を受けましたね。

ベンチャーと老舗の「スピード感摩擦」をどうするか
—ベンチャー(新興)企業がEdTech分野に参入する中、教育業界大手からは「短期間でやめてしまうところも多く、ベンチャーとは安心して取引ができない」と聞いたことがあります。老舗とベンチャーの事業スピードの摩擦について、どう思われますか。
学校現場や老舗企業がベンチャーのスピード感に合わせる側面もあって欲しいのですが、一方でベンチャー企業が落ち着いて事業を続ける基盤が足りていないのかも知れません。
3年、5年のスパンで事業を続けるための安定した出資や支援体制がないのだとしたら、国がさらなる環境整備を進める必要があります。
経産省も創業支援を行なっています。ただ、最終的な融資決定は民間の金融機関ということもあり、単純な問題ではありません。
いずれにせよ環境の問題は大きいですから、ベンチャー企業=信頼できない、と簡単に結論しないでいただければと思います。
日本には「足を引っ張る文化がある」?
—「日本ではイノベーターが育ちにくい」という意見があります。新しいことを忌避したり、非難したりする空気がある……と聞きますが、浅野さんはどう思われますか。非難までされるかどうかは分かりませんが、新しいこと、面白いことをストレートに称賛する文化はまだ育っていないかもしれませんね。
—「新しいことに取り組もうとしたら、職場で白眼視された」という方もいます。
イノベーターを育てるには、すぐ近くの人は賛同してくれなくとも、誰かは応援しているのだと伝えることが重要です。
他の場所で評価されれば職場でのポジションも変わっていくかもしれません。逆に、ますます浮いてしまう可能性もあるのが難しいところですが。
—この連載のテーマであるEdvation x Summitは教育イノベーターの育成をねらいとしたイベントですが、たとえばこういう場に来ていただいて、イノベーターが勇気付けられるのが理想だと。
Edvation x Summit 2021 Online は、国内における教育イノベーションの加速を推進するために企画された、世界初のEdTechグローバルカンファレンスオンラインイベントです。

https://www.edvationxsummit.jp/ >
そうですね。
Edvation x Summitは「教育にイノベーションを起こす」を明確にメッセージとして発信している唯一のイベントです。現場で日々苦労されている先生方が集う象徴的なイベントとして発展していくことを期待しています。
ICT機器展などのイベントは多く行われていますが、イノベーションを打ち出したイベントはEdvation x Summitのみです。
佐藤先生のご尽力もあり、この数年でイベントは順調に成長しています。今後は多言語対応を進めるなど国際色を強め、アジア圏で存在感のあるイベントになれば嬉しい。そのポテンシャルはあるでしょう。
Edvation x Summitについては、我々経済産業省もスポンサーを務めています。ともにEdvation x Summitを発展させていきたいと考えていますので、ぜひご注目ください。
—浅野さん、ありがとうございました。
Edvation x Summit 関連記事はこちら
今回インタビューするのはデジタルハリウッド大学大学院教授 佐藤昌宏先生。実務家教員として指導を担当されるほか、教育イノベーターのためのお祭り「Edvation x Summit」を主宰されています。日本の教育にEdTecchがもたらすものとは?詳しくお伺いしました。


2025/07/31

"教育のノーベル賞"グローバル・ティーチャー賞には、偉大な先生が世界中から選ばれます。ところが、日本人初のトップ10・高橋一也先生の反応は「ほっといてほしい」!?日本の教育イノベーションについて語っていただきました。
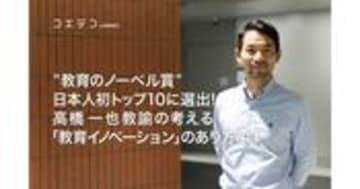

2025/07/31

教育系YouTuber・葉一(はいち)さん。幅広い学年をカバーした分かりやすい授業動画で有名です。そんな葉一さんの徹底した動画作りとは?独自のフォントを開発、結婚指輪も外す!?ストイックなお人柄をロングインタビューでお届けします。


2025/07/31



Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
『チェンジ・メーカー』を作ろう!日本の教育現場をもっと贅沢に―経済産業省 教育産業室長 浅野大介さん
驚くべきスピードで変化し続ける現代社会において、今の日本の教育は改めてその在り方を問われている中、将来の日本を背負って立つ子どもたちの育て方や今後の教育の在り方などを経済産業省商務・サ...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
小学校プログラミング教育必修化まであと少し!未来の学びコンソーシアム体制強化で教育現場を全力サポート
未来の学びコンソーシアムは、文部科学省、総務省、経済産業省、そして教育関係者や関連企業・団体など官民一体となって生まれました。組織が誕生した背景や目的、今後の官民連携のあり方などを文部...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
(文部科学省取材)高校「情報Ⅰ」必修化、大学入試「情報」新設どうなる?高校情報科教科調査官 鹿野利春氏に聞く
コエテコでは小学校・中学校でのプログラミング教育必修化について、さまざまな取材を行なってきました。今回はいよいよ高校での「情報Ⅰ」必修化、大学入試「情報」新設について、新学習指導要領を...
2025.06.24|夏野かおる
-
自動運転を体験!小学校プログラミング教育の推進月間「みらプロ」公開授業レポート
2020年からの小学校におけるプログラミング教育の実施に向けて、さまざまな取り組みが見られます。文部科学省、総務省および経済産業省は、2019年9月を「未来の学び プログラミング教育推...
2025.06.03|小澤志穂
-
(取材)天才クリエータを育成・発掘する「未踏事業」とは?|経産省主導、若者の夢とアイディアを応援するプロジェクト
突出したIT人材の発掘と育成を行うため、経済産業省が2000年から展開しているのが「未踏事業」です。これまでに約2000人を排出し、産学の第一線で活躍している人材も多数に上ります。未踏...
2025.06.24|まつだ







