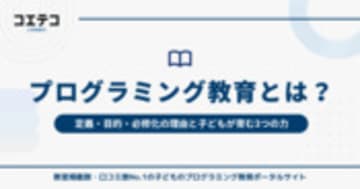PISAとは?日本の順位と最新動向をくわしく解説
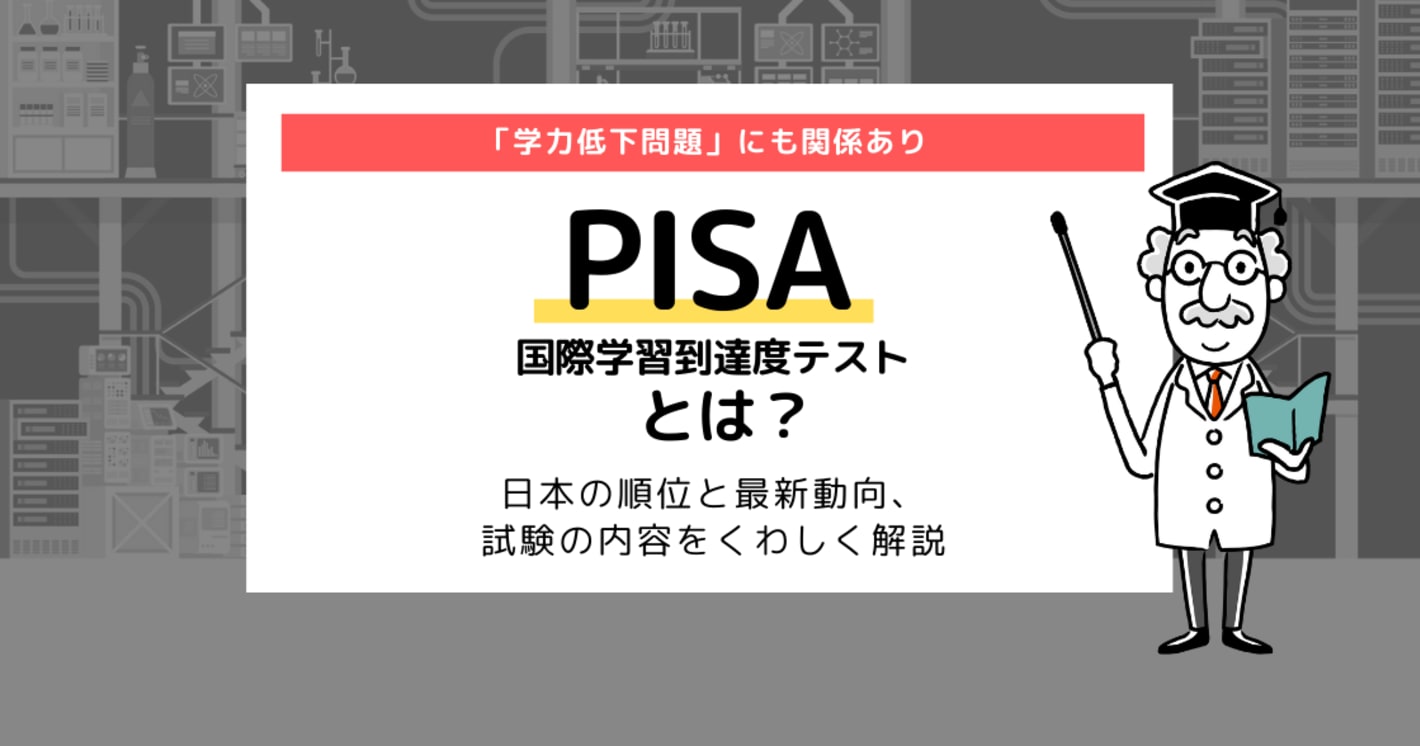
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
この「PISA」とは、OECD加盟国を中心として3年毎に実施される15歳を対象とした国際的な学習到達度テストです。
読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野を中心とした試験で、義務教育修了時点で学んだ知識を実生活にどの程度応用できるのかを測ります。
文部科学省の「新学習指導要領」にも影響を与えると言われている「PISA」とは一体どのような試験なのでしょうか?
この記事では気になる試験の内容や日本の順位などを紹介します。
PISAとは?国際的な学力テスト!
PISAは「Programme for International Student Assessment」の略称で呼ばれる国際的な学習到達度調査です。OECD(経済協力開発機構)加盟国を中心として実施されます。
日本では、PISAは2000年より導入されました。それ以降3年ごとに実施されています。
7回目(数学分野)は2021年に実施される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2022年に延期・実施されました。
引用:国立教育政策研究所
引用:文部科学省 国際学力調査(PISA、TIMSS)
世界81ヵ国、生徒約69万人が参加
PISAの2022年調査では、世界の81か国・地域の15歳の生徒約69万人を対象にして調査が行われました。日本では、高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校の1年生のうち、183校(約6,000人)が調査に参加しました。
| 年 | OECD加盟 | OECD非加盟 | 合計 |
| 2000年 | 28か国 | 4か国 | 32か国 |
| 2003年 | 30か国 | 11か国・地域 | 41か国・地域 |
| 2006年 | 30か国 | 27か国・地域 | 57か国・地域 |
| 2009年 | 34か国 | 31か国・地域 | 65か国・地域 |
| 2012年 | 34か国 | 31か国・地域 | 65か国・地域 |
| 2015年 | 35か国 | 37か国・地域 | 72か国・地域 |
| 2018年 | 37か国 | 42か国・地域 | 79か国・地域 |
| 2022年 | 37か国 | 44か国・地域 | 81か国・地域 |
試験は3分野に分かれている
読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野の習熟度を調査する試験です。実施年ごとに3つの中から中心分野が設定されて、その分野が特に重点的に調査されます。
PISAでは、学校で習得する基本的な知識に加えて、それらを自分たちの生活に活かすことができるような発展的な内容も出題されます。
これにより、思考力や応用力が問われる自由記述問題が比較的多く出題されることが特徴的です。
普段の学力試験や学習ドリルの問題形式とは異なるように感じるお子さんも多いと思います。
2022年のPISAでは、3分野に関する学習到達度調査の以外にも、革新分野としてクリエイティブ・シンキング調査が導入されました。2025年にはデジタル社会での学習能力調査も行われる予定です。この革新分野について、日本では2018年以降の参加を見送っています。
試験には高校1年生が参加
PISAは調査段階で15歳3か月以上16歳2か月以下の学校に通う生徒が対象となります。日本では通常は高等学校1年生にあたります。また、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーを調査する問題に加えて、生徒の学習環境や生活の背景などの情報を収集する生徒質問紙での調査が行われます。
さらに、生徒以外にも学校長に向けられた学校質問紙による調査も実施されます。
どちらも、およそ、20~30分の回答時間で完了すると想定されている調査です。
生徒と学校長への質問紙調査を行うことによって、各国での生徒の実態と学校での教育の実態の差異を比較することができます。
高校生になると勉強がグッと難しくなることはもちろん、大学受験に向けた準備も必要になります。このタイミングで通塾を考えるご家庭も多いのではないでしょうか。しかし、いかんせん塾サービスは各社ひしめき合っており「どの塾を利用したらいいんだろう...」と迷ってしまうこと必至です。そこの記事では、「学力を向上させたい」「大学受験を成功させたい」と考えている高校生におすすめの学習塾を厳選してご紹介します。


2026/01/02

2022年のPISAのランキング(2023年12月発表)
2022年のPISAランキングは、81か国中で、日本の読解力は3位(日本平均516点/OECD平均476点)、数学的リテラシーは5位(日本平均536点/OECD平均472点)、科学的リテラシーも2位(日本平均547点/OECD平均485点)と、いずれもOECD平均を大きく上回る結果となりました。また、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野全てにおいて前回調査より平均得点が上昇したことが話題になりました。
今回の結果には、新型コロナウイルス感染症のため休校した期間が他国に比べて短かったことが影響した可能性があることが、OECDから指摘されています。
このほかに、文科省の国立教育政策研究所は、学校現場において現行の学習指導要領を踏まえた授業改善やICT環境の整備が進んだことが影響していると考察しています。
授業でのICT機器の活用調査について、2018年の時点で日本はOECD加盟国で最下位の利用率でしたが、2022年調査ではOECD平均を上回り5位まで上昇しています。
参考:文部科学省 OECD生徒の学習到達度調査(2022年)
2021年は新型コロナウイルスの影響で1年開催が延期
PISAは、3年ごとのサイクルで数学・読解・科学の各分野で思考プロセスの習得や概念の理解を問います。2000年から始められ、7回目(数学分野)は2021年に実施される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、2022年に延期・実施されました。
また2024年実施(科学分野)も2025年に延期することが決定しています。
2022年調査ではより高い精度で能力を図ることを目的に「多段階適応型テスト」を導入
2022 年調査では、数学的リテラシーと読解力において、生徒の解答結果に応じて出題内容が変わる「多段階適応型テスト(Multi Stage Adaptive Testing : MSAT)」手法が導入されました。これにより、“生徒の能力をより高い精度で測る”ことができ、生徒の能力の高低差についての実態が把握しやすくなるでしょう。
多段階適応型テストの特徴は次の通りです。
•「コア」「ステージ1」「ステージ2」の三段階
•自動採点の正答数に応じて、続く「ステージ」では難易度の異なる(高い/低い)問題群が出題される
•同じ調査時間では、従来の方式「大問固定方式」に比べ、より高い精度で生徒の習熟度を推定できる
引用:文部科学省 生徒の学習到達度調査
引用:OECD-PISA調査プロジェクトチーム
2018年のPISAのランキング
2019年12月4日にPISA2018の結果が発表されました。2018年調査では、読解力が中心分野に設定されています。今回のPISAでは、全参加国・地域内での日本の読解力の順位が8位から15位に下がったことが話題になりました。
読解力の試験では日本は504点を獲得しており、OECD平均得点の487点を大きく上回っているのですが、前回と比べて順位が下がってしまう結果となりました。
これに関して、文科省の国立教育政策研究所は、自分の考えを他者に伝える能力に課題があると考察しています。
さらに、2015年調査からコンピュータを導入した調査が行われています。
この形式では大問ごとに解答をする必要があります。次の問題に進むと前の問題に戻ることができない設計であるため、冊子での試験のように、設問を先に把握したり解答後に見直しをすることができない仕組みになっています。
このような試験形式に日本の子どもたちが不慣れであった可能性も指摘されています。
また、数学的リテラシーは6位(日本平均527点/OECD平均489点)、科学的リテラシーは5位(日本平均529点/OECD平均489点)でした。
前回の調査と比べて若干順位は落ちているものの、OECD平均を大きく上回る結果となりました。
さらに、授業でのICT機器の活用調査について、日本はOECD加盟国で最下位の利用率であることもわかりました。
まだまだ学校現場でのデジタル活用の普及には課題が残るようですね。
参考:文部科学省 OECD生徒の学習到達度調査(2018年)
2015年のPISAのランキング
ちなみに、前回の2015年のPISA参加国別ランキングは以下のとおりです。2015年度調査では科学的リテラシーが中心分野に設定されました。
| 順位 | 科学的リテラシー | 数学的リテラシー | 読解力 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール |
シンガポール |
シンガポール |
| 2 | 日本 | 香港 |
香港 |
| 3 | エストニア | マカオ | カナダ |
| 4 | 台湾 | 台湾 | フィンランド |
| 5 | フィンランド |
日本 |
アイルランド |
| 6 | マカオ | 北京・上海・江蘇・広東 |
エストニア |
| 7 | カナダ | 韓国 | 韓国 |
| 8 | 香港 | スイス |
日本 |
| 9 | 北京・上海・江蘇・広東 |
エストニア | ノルウェー |
| 10 | 韓国 | カナダ |
ニュージーランド |
2015年度調査だと、参加国内での日本の順位は、72か国中で科学的リテラシー:2位、数学的リテラシー:5位、読解力:8位でした。
2012年度調査では、日本は65か国中で科学的リテラシー:4位、数学的リテラシー:7位、読解力:4位という結果でしたので、科学的リテラシー・数学的リテラシーの順位は上昇、読解力の順位は低下したといえます。
PISAの結果が学習指導要領に影響を与えるって本当?
国際的な試験であるPISAの結果は日本の教育に影響を与えるのでしょうか。2003年PISA調査では日本の読解力分野は参加41カ国中14位でし た。
2000年の試験の8位から14位へと順位が大幅に下がったことが話題となりました。
この順位下落の要因の一つには、日本の子どもたちの自由記述問題への無回答率が高かったことが関係すると分析されています。
このような結果を受け、2005年12月には読解力向上プログラムがはじまりました。書かれたテキストを読むだけではなく、理解・利用・塾考する能力の育成が目標とされます。このようにPISAの結果を課題として、文科省によってPISA型「読解力」の育成が推進されるようになりました。
さらに、2006年のPISAの結果を受けて、2008年の学習指導要領改訂ではPISAの枠組みに基づいて「思考力・判断力・表現力等の育成」が盛り込まれています。過去の改定では、PISAの結果が学習指導要領改訂に大きな影響を与えていると考えられます。
また、2020年から実施される新学習指導要領においても、単なる知識習得の学習ではなく、主体的・対話的・深い学びを実現するために、アクティブ・ラーニングの観点が重視されています。アクティブラーニングではPISAで重視するような知識の活用が求められます。
プログラミング教育との関連は?
2022年に実施するPISAの数学に関するテストでは、論理的な考え方や問題解決能力を重視する「コンピューテーショナル・シンキング」に関する問題が追加されました。コンピュータサイエンス分野に関する学力が重視される国際的な調査はPISAが初となっています。
このような動きにより、プログラミングを含むコンピュータサイエンス分野の学力が、今後、国際的にもさらに重視されていく可能性があります。
参考:高校生向けプログラミングスクール
国際数学・理科教育調査「TIMSS」とは?
PISA以外の国際学力調査の例としてTIMSSを紹介します。TIMSSは、「Third International Mathematics and Science」 の略称で「国際数学・理科教育調査」とも呼ばれており、算数・数学と理科の理解度を国際的な調査で測定する試験です。
この試験は、IEA(国際教育到達度評価学会)により、1964年から開始されました。1995年からは4年ごとに実施されています。
日本の場合、TIMSSは、小学校4年生と中学校2年生を対象に実施されます。
また、算数・数学、理科の試験に加えて、児童・生徒質問紙、教師質問紙、学校質問紙といったアンケート調査も実施されます。
引用:文部科学省 国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)の調査結果
まとめ:次のPISAではプログラミング的思考が問われる!
今回の記事では国際学習到達度テストのPISAについて紹介しました。過去を振り返ると、PISAの結果が今後の教育の指針ともなりうる学習指導要領へ影響を与えているようです。
また、国際的にもコンピュータサイエンティスト的な思考を獲得するコンピュテーショナルシンキング の学習が求められているようです。
日本でも2020年からプログラミング教育が小学校で必修化されます。
プログラミング教育は、PISAが重要視するコンピュテーショナルシンキングで求められる論理的なものの考え方や問題解決能力の育成にも共通する部分がありそうですね。
参考
「全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等)」(文部科学省)
「OECD生徒の学習到達度調査(PISA)」(国立教育政策研究所)


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
日本の教育水準はどうなっている?PISA・TIMSS・PIRLSなど
現代社会においてITに対する知識、英語力などが海外より遅れていると言われている日本。 少し前にはゆとり教育や学力低下という話も問題になり、近年では教育格差という言葉もよく耳にするよう...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
私立と公立の違いは?格差は本当か、コロナの影響と中学受験を考える【教育トピック】
新型コロナウイルスの影響をうけて中学受験や高校受験の動向が変わるのではないかといったニュースを見かけるようになりました。比較的多いのが「経済状況が悪化する中、公立人気が高まる」という推...
2025.09.10|大橋礼
-
1億人以上の人口の国では強い!日本の教育の強い点は?
日本の学力は一般的には高いといわれていますが、実際のどうなのでしょうか? 日本だけでなく、他の国がどのような教育を行っているのかも気になるところですね。すべての分野で1位を獲得してい...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
次世代の科学技術系人材をはぐくむ「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」
科学技術系人材の育成を目的とし、2002年から開始されたスーパーサイエンスハイスクール(SSH)。響きからなんとなく「理系に強い学校なのかな?」とは分かるものの、実際にどのようなことを...
2022.04.12|コエテコ byGMO 編集部
-
シュタイナー教育とは?メリット・デメリットもわかりやすく解説
「シュタイナー教育って日本の学校教育と何が違うの?」と疑問を感じる方も多いでしょう。この記事では、シュタイナー教育の基本理念から具体的な学習内容、モンテッソーリ教育との違い、メリット・...
2025.08.06|コエテコ byGMO 編集部