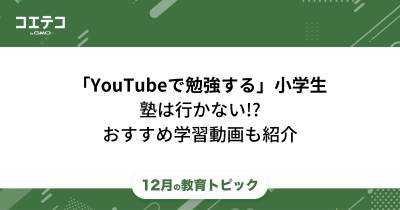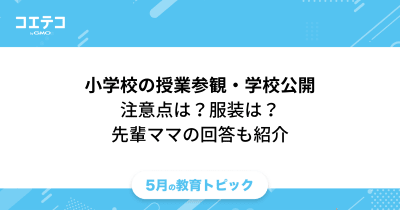小学生の不登校の原因は?親のNG行動や勉強方法も詳しく紹介
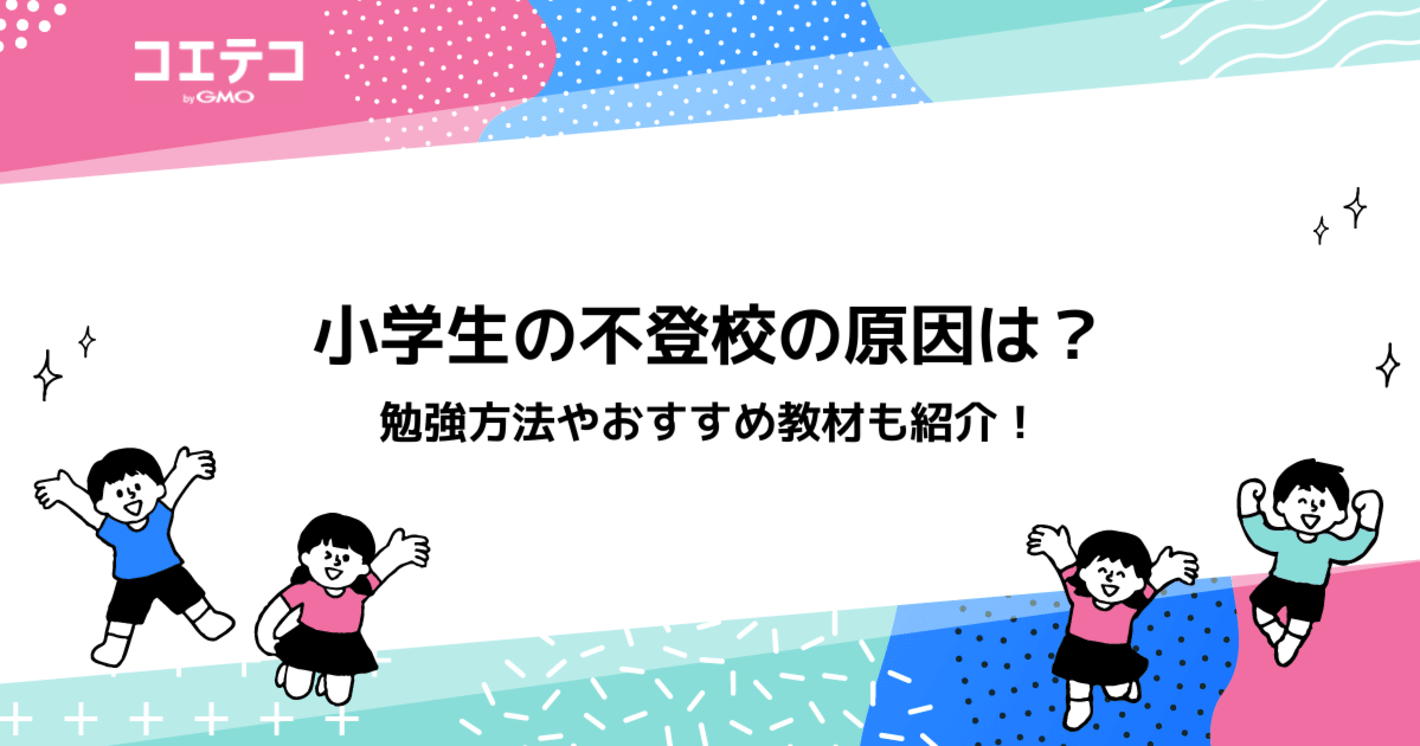
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
近年、小学生の不登校児童は年々増加傾向にあります。2023年の文部科学省の調査によると、不登校児童の数は過去最高を更新し、全体の約6.5%に達しています。このデータは、教育現場が抱える深刻な問題を浮き彫りにしています。
不登校自体は珍しいことではありませんが、いざ自分の子どもがある日から学校に行かなくなってしまったら、突然のことに戸惑ってしまうかもしれません。このような状況では、まず現状を理解し、冷静に対処することが重要です。
本記事では、小学生の不登校についてデータを用いて実態を紹介するとともに、不登校になる主な原因や親が取ってはいけないNG行動や勉強方法、おすすめの教材などを詳しく解説していきます。
不登校の小学生におすすめの勉強方法
学校に通わない期間があると、その分学習が遅れてしまいやすいでしょう。これまでできていた問題も、間が空くと忘れてしまうかもしれません。分からないことが増えてしまい、自信をなくしてしまうこともあるでしょう。不登校の小学生が勉強に取り組むには、以下の方法がおすすめです。オンライン家庭教師
不登校の小学生向けの勉強方法の1つに、オンライン家庭教師があります。オンライン家庭教師は、全国からお子さまに合った講師を選べるため、お子さまの性格に合った講師を見つけることができるでしょう。
また直接相対することなくマンツーマンで指導を受けられるため、周囲や社会とのコミュニケーション機会が減ってしまった不登校のお子さまにとっても心的ハードルが低い勉強法と言えるでしょう。
一方でマンツーマン指導ということで、料金が高額になることもあります。
オンライン塾
オンライン塾の中には、不登校児対応の塾もあります。集団授業の場合は、集団に馴染む練習にもなるでしょう。
また集団で授業を行う塾の場合、家庭教師よりも費用を安価に抑えられます。
他の生徒がいることに抵抗を感じることがないようであれば、選択肢として検討してみるのも良いでしょう。
不登校の生徒の学習方法や、受験対策の方法として注目されているのがオンライン塾です。 この記事では、不登校の生徒の学習にオンライン塾を利用するメリット、不登校の生徒向けのオンライン塾を選ぶポイントとおすすめのオンライン塾を紹介します。不登校の子どもの勉強方法でお悩みの際には、ぜひ参考にしてください。
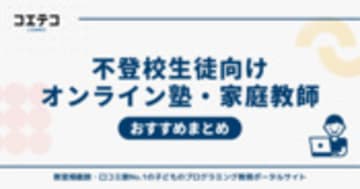

2026/01/05

通信教材
自分のペースで勉強に取り組みたい・費用面が気になるという場合は、通信教材がおすすめです。小学生向けには、学年の制限なく取り組める教材やゲーム感覚で楽しめる教材など、色々な教材が展開されています。
まずは勉強への興味・関心喚起に向けて、お子さまの志向に合った教材を選んでみると良いでしょう。
子どもの教育には学費だけでなく、習い事や塾の費用など何かとお金がかかるもの。 小学生のうちは、家庭学習に「費用がリーズナブルで内容が充実した通信教育を取り入れたい」と考えるご家庭も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、失敗しない通信教育の選び方と教材選びの際に注目したいポイントを解説すると共に、安い通信教育の中でも充実したコンテンツを提供するおすすめの教材を紹介します。


2026/01/02

フリースクール
学校以外の学びの場として、近年フリースクールも注目を集めています。ただし“フリースクール”と一口にいっても、学校への復帰を目指すタイプや自然の中で共同生活をするタイプ、子どもの居場所を提供するタイプなど様々です。また運営媒体も個人・NPO法人・ボランティア団体など、色々あります。
スクールによって教育理念や方針が大きく異なるため、お子さまとよく相談した上で通うスクールを決める必要があります。
小学生の不登校実態
文部科学省による不登校児の定義は次の通りです。何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者まずは、文部科学省の最新データから小学生の不登校の実態をご紹介します。
引用:文部科学省『不登校の現状に関する認識』
小学生の不登校児童の人数と割合
全国の小学生児童数は6,262,256人で、そのうち不登校児と言われる児童は81,498人です。不登校児童の割合は小学生全体の1.3%となっており、1.5~2クラスに1人ぐらいの割合で不登校児童がいる状態です。

引用:文部科学省初等中等教育局児童生徒課 『令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果(P.69)』
不登校児童数の推移
令和2年度の同調査では不登校児童数が63,350人であったことから、1年で2万人近く増えていることが分かります。小学生全体数は少子化とともに年々減少傾向にあるため、不登校児の割合は年々右肩上がりに増加の一途を辿っている実態が伺えます。

引用:文部科学省初等中等教育局児童生徒課 『令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果(P.71)』
小学生が不登校になる原因
小学生が不登校になる理由は、さまざまな原因があります。本項目で紹介する原因が全てではありません。いくつかの原因が複合的に絡み合うことで不登校になるケースもあります。
ここでは、不登校になる主な原因を紹介いたします。
無気力・不安
初めての集団生活によるストレスや環境の変化に対する不安などから、やる気を失ってしまい不登校に至るケースがあります。決定的なきっかけがないため、本人も親もなぜ学校に行けないのか分からず悩むことが多い傾向にあります。心理学的な観点から、無気力や不安は子どもにとって非常に厳しいストレス要因となることが知られており、これが不登校に繋がることが多いとされています。
親の過干渉・過保護
親の過干渉や過保護が不登校の要因になる事例もあります。子どもへの関わりが過剰になりすぎると、子どもが親に依存し自己解決能力が育たなくなってしまいます。
その結果、分離不安などから学校に行き渋るようになる様子が現れ始めるようになり、最終的に不登校に至ってしまうケースがあります。
最近の研究では、親の育て方が子どもの心理的な健康に大きな影響を及ぼすことが確認されており、過保護が子どもの自主性を妨げる要因となることが指摘されています。
生活リズムの乱れ・あそび・非行
長期休み中などにゲームや友人との出歩きに夢中になり、昼夜逆転になってしまう子どもも少なくありません。長期休み明けの登校時間に起きられなかったことから、不登校が始まってしまうケースなどが当てはまります。特に自分の意志が強くなり始める、小学校高学年に多くなる傾向があります。生活リズムの乱れは学業に影響を与えるだけでなく、社会的なつながりにも影響を及ぼすことが研究により示されています。
いじめを除く友人関係をめぐる問題
常にたくさんの同級生と共に過ごす小学校生活では、クラスに馴染めない・気の合う友人がいないなどの理由から学校に足が向かず、不登校になる事例もよくあります。いじめなどの決定的な事象が発生しているわけではないため、親や学校も原因が分からず解決策を導き出せず、不登校期間が長引くケースも多いようです。
友人関係の問題は、特に小学校高学年の児童にとっては深刻な影響を及ぼすことがあります。研究によると、子どもたちが友人関係のストレスを抱えることは、心理的健康にも大きな影響を与えるとされています。
家庭の生活環境の急激な変化
両親の離婚・再婚・転居など、大きな生活環境の変化に対するストレスから不登校になる場合もあります。環境の大きな変化が伴う場合、親自身も余裕がなく子どもの様子に気づけないこともあるでしょう。このような家庭環境の急変は、子どもにとって非常にストレスフルで、心の健康に影響を与える可能性があります。
不登校の小学生の親ができる子どもへのサポート
近年、不登校の問題が深刻化しており、子どもが学校に行かない原因は多岐にわたります。大きなストレスを抱えたまま学校へ行くのは難しいでしょう。このようなとき、親にできるサポートを紹介します。学校を休んでもよいことを伝える
学校を休みたい気持ちはあるけれど、学校を休むのはよくないといわれています。子どももそのことを知っているため、休むことに対して悩むことが多いです。子どもの気持ちを軽くするには「休んでも大丈夫」と伝えるのがよいでしょう。親が今の状態を受け入れていると分かれば子どもは安心できますし、相談しやすくなることも期待できます。実際、研究によれば、親が子どもの感情を受け入れることで、子どものメンタルヘルスが改善されることが示されています。
子どもの話をちゃんと聞く
「学校に行かないなんて甘えだ」と感じることもあるかもしれませんが、子どもの話には真剣に耳を傾けましょう。子ども本人にとっては、学校に行けないことは深刻な問題です。真剣に打ち明けた気持ちを軽く聞き流されれば傷つきますし、「次は話さないようにしよう」と考えてしまうかもしれません。話を聞いてくれる人がいることで、悩みやイヤな気分が晴れることもあるでしょう。親が子どもの感情を受け止めることは、心理的な安定感をもたらし、子どものコミュニケーション能力の向上にも寄与します。具体的には、子どもが「自分の気持ちを言葉にする」ことで、感情の整理ができ、問題解決能力が高まることが期待されています。
第三者に相談する
不登校に関する悩みを第三者へ相談することも重要です。主な相談先をチェックしましょう。- 学校
- 自治体の相談窓口
- 親の会
- フリースクール
まずは子どもが在籍している学校へ相談します。学校での子どもの様子を把握している担任の先生はもちろん、心のケアを行うスクールカウンセラーへの相談も有効です。特に、スクールカウンセラーは専門的な知識を持っており、具体的なアドバイスやサポートを提供できます。
どこへ相談するのがよいか分からず相談できずにいることがあるなら、自治体の相談窓口へ連絡してみましょう。各自治体には教育相談窓口が設置されており、適切な相談先を紹介してもらえるかもしれません。
親の心理的な負担軽減につながりやすいのは親の会です。同じ悩みを持つ親同士での相談や、有益な情報の交換ができることが期待されます。特に、地域に根ざした親の会では、具体的な体験談やアドバイスを得ることができるでしょう。
民間の団体が運営するフリースクールにも、不登校に関する相談ができます。フリースクールによって、学習を重視しているところ、心理的なサポートを重視しているところなど方針はさまざまです。子どもの状態や今後の方針に合わせたフリースクールを選び、相談すると良いでしょう。フリースクールでは、個別のニーズに応じたプログラムが提供されているため、特に役立つことがあります。
別室登校を勧める
学校へ行き教室に入るのは難しいけれど、同級生のいない別室なら通えそう、という子どももいます。そのような場合には別室登校できることを伝えるとよいでしょう。子どものペースで登校できるようになることも期待できます。教室には入れないけれど別室でも学校に通えているという状況が、子どもの悩みや罪悪感の軽減につながることも期待できます。例えば、別室登校をすることで、少しずつ学校に慣れていくことができ、最終的には教室に戻るきっかけになる場合もあります。また、教職員からのサポートを受けることで、個別の学習プランを設けることも可能です。
さらに、別室登校を行う際には、学校とのコミュニケーションが重要です。教職員と連携し、子どもの状態を定期的に確認しながらサポートしていくことが大切です。このようにして、子どもが無理なく自分のペースで学校生活に戻れる環境を整えることが求められます。
オンライン塾や家庭教師などを検討する
学校に通えないことで勉強が遅れてしまうのではないかと心配な場合には、オンライン塾やオンライン家庭教師を検討するとよいでしょう。自宅で学んでいれば、学校へ復帰するときに学力で苦労しにくくなります。オンライン塾や家庭教師は、特に不登校の子どもに対応したコースを提供している場合が多く、自宅での学習をサポートします。これにより、学校に通えていなくても出席扱いになるケースがあり、正式に授業を受けたことにカウントされることがあります。このため、学力維持だけでなく、学校復帰時の不安を軽減する手段ともなります。
また、オンラインであれば、自分のペースで学ぶことができ、気になる科目や単元に集中しやすくなるメリットもあります。プログラムや教材は多様であり、学習内容に対する理解を深めるためのリソースも豊富です。
参考:不登校生徒におすすめのオンライン家庭教師
参考:不登校の出席扱い制度とは?
不登校の小学生におすすめのオンライン塾・通信教材
学習面への不安から学校への復帰のハードルが高まったり、復帰できても不登校になることがあります。オンライン塾や教材を活用し、自宅で学習を進めていれば、勉強が学校復帰の妨げになる自体を防げるでしょう。不登校に対応しているコースを提供している、おすすめのオンライン塾や教材を紹介します。参考:オンライン塾小学生
参考:小学生向け通信教育
トライのオンライン個別指導塾

マンツーマンで行われる授業は、教師と会話をしながら進みます。子どものペースに合わせた丁寧な指導を受けられます。専任の教育プランナーがいるのもポイントです。担任の先生のようにサポートを行う役割で、学校復帰へのアドバイスも受けられます。
| コース | オンライン個別指導塾 オンラインLIVE集団塾 |
| コース別料金 |
■オンライン個別指導塾 10,000円台〜(税込)/月額 ※トライ式 AI教材も無料で利用可能 ■オンラインLIVE集団塾 小学生 6,980円(税込)/月額 |
| 授業形式 | オンライン・対面 |
| サポート体制 | ・子どもに合う専任の教師を全国33万人の登録教師から厳選 ・マンツーマンの双方向授業で理解できるまで指導 ・AIが単元の理解度を診断し学習をサポート |
| 運営会社 | 株式会社トライグループ |
| 公式HP | トライのオンライン個別指導塾 |
すらら

目標達成で受け取れるポイントを使い、マイページのカスタマイズができるトークンエコノミー方式を採用しているのも特徴です。「頑張ると良いことがある」という経験を通し、学習習慣を無理なく身につけられるでしょう。
| コース | 3教科コース 4教科コース 5教科コース |
| コース別料金 | ■3教科コース 毎月支払いコース:8,800円/月額 4ヶ月継続コース:8,228円/月額 ■4教科コース 毎月支払いコース:8,800円/月額 4ヶ月継続コース:8,228円/月額 ■5教科コース 毎月支払いコース:10,978円/月額 4ヶ月継続コース:10,428円/月額 |
| 授業形式 | タブレット教材 |
| サポート体制 | ・トークンエコノミー方式を採用 ・無学年方式で得意を伸ばし、基礎を固めて苦手を克服 |
| 運営会社 | 株式会社すららネット |
| 公式HP | すらら |
メガスタ
メガスタは、長年のオンライン指導実績を持つ、老舗オンライン塾。1対1の完全個別指導を徹底しているため、オンラインであっても小さな躓きや悩みのタイミングを見逃しません。
また長年の運用実績もあり、在籍講師の数も他のオンライン塾と比較して群を抜いています。
多くの講師の中から子どもに合った講師を選べるため、不登校環境下にあるお子さまの心情を汲んだ指導をしてくれる講師とも巡り合えるでしょう。
| コース | 80分コース 100分コース |
| コース別料金 |
■80分コース(週1回×月4回) 学生教師:5,896~6,336円 大学院生・社会人教師:7,656円 若手プロ教師:9,416円 プロ講師:11,704~14,784円 ■100分コース(週1回×月4回) 学生教師:7,370~7,920円 大学院生・社会人教師:9,570円 若手プロ講師:11,770円 プロ講師:14,630~18,480円 |
| 授業形式 | オンライン |
| サポート体制 | ・手元カメラと表情カメラの利用 ・授業採点AIによる質の高い授業 |
| 運営会社 | 株式会社バンザン |
不登校の小学生にしてはいけないNG行動
続けて、子どもが不登校になった時に親としてしてはいけない行動とその理由を紹介・解説します。不登校は珍しくないと分かっていても、自分の子どもがいざ不登校になった場合、無理やり登校させたり子どもを問い詰めたりしてしまうかもしれません。
どのような行動を控えるべきか理解し、子どもとの接し方を考えてみましょう。
無理やり学校に行かせる
学校に行きたくない子どもを、宥めたり脅したりして無理やり学校に行かせることは絶対にしてはいけません。無理に登校させようとすることは、子どもにとってさらなるストレスとなり、最終的には不登校が長引く結果につながります。
子どもが学校に行きたい気持ちがあっても、さまざまな理由から行けない状況に置かれている場合が多く、その状態を理解してあげることが重要です。無理に登校を促すと、親に対する信頼感が損なわれ、家庭内での関係も悪化する恐れがあります。これは、最終的に自宅引きこもりに繋がることもあるため、注意が必要です。
研究によれば、子どもが感じるプレッシャーが強ければ強いほど、学校への不安感が増すことが示されています。子どもが自ら学校に戻れるようになるためには、安心できる環境を整えることが求められます。
子どもを問い詰める
子どもの姿に冷静になれず、つい学校に行けない原因を聞き探ってしまうかもしれません。親からすると何気なく聞いているつもりでも、「問い詰められている」「責められている」と思い込んでしまう子どももいます。
また口調や聞き方によっては、子どもをさらに追い詰めることになりかねず、親子の信頼関係にも影響が生じてしまう懸念が考えられます。無理に聞き出すのではなく、子ども自ら話し出すタイミングを辛抱強く待つことも大切です。
実際、心理学的な研究では、子どもに対する強いプレッシャーが逆効果になることが指摘されています。問い詰める行為は、逆に子どもが話しにくくなる要因となるため、適切なコミュニケーションを心がけることが求められます。
今の学校に登校することにこだわる
元の生活に戻ることを前提として、通っていた学校に登校できるようになることにこだわりすぎるのも良くありません。不登校になった原因によっては、他の学校への転校やフリースクールへの通学などを検討することも視野に入れておくべきでしょう。
可能性や選択肢を広げることで、お子さまにとってよりベストな選択ができるようになります。教育専門家の意見でも、選択肢を持つことがストレス軽減に繋がるとされています。子どもが自ら進んで新しい環境に慣れ親しむことで、心の負担が軽くなることが期待できます。
親が自分を責める
「子どもが不登校になったのは自分の育て方や接し方が悪かったのかも…」などと、親が自分を責めるのも良くありません。また夫婦間で責任を押し付け合うのも、状況を建設的に改善する手立てとは言えません。
親が自分を責めている様子や親同士が責任転嫁し合う様子を子どもが目の当りにすることで、新たなストレスの原因が発生してしまう可能性も考えられます。決して簡単なことではないかもしれませんが、子どもとはできるだけ普段通りに接することを心がけましょう。心理的なサポートを受けることも効果的であり、必要に応じて専門家に相談することが推奨されています。
小学生が不登校になりやすい家庭の特徴
子どもが不登校に成りやすい家庭には特徴があるといわれています。代表的な5つの特徴は以下のとおりです。子どもに無関心
子どもは、親とのコミュニケーションを基盤に社会や周囲とのコミュニケーションを取るようになります。しかし、コミュニケーションの初期形成とも言える親とのコミュニケーションが不足していると、子どもは社会や周囲とのコミュニケーション方法が分からず孤立してしまうことがあります。また時には社会や周囲との距離感が分からず、踏み入った言動をしてしまうこともあるかもしれません。
結果的に、周囲と上手にコミュニケーションが取れないことで集団に馴染めず不登校へと至ってしまうことも起こり得ます。実際、子どもの社会性の発達において、親との関係性は非常に重要であることが研究からも示されています。
子どもへの接し方が過保護
反対に子どもへの接し方が過保護な家庭のお子さまも不登校になりやすい傾向があるようです。この場合、親が先だしで指示や用意をしてしまうため、子どもは自分で考えて行動することができなくなってしまいます。結果的に何事も親に依存してしまう癖がついてしまい、小学校では1人で登校できず母子登校になるケースもあります。
さらに小学校では、集団の中で自分で考えて行動することを求められるようになります。過干渉を受けた子どもは年相応の自立が養われていないため、「優しいパパやママが居る家のほうが良い」と、学校に行きたがらなくなり不登校に至ってしまう場合もあります。このような親の影響は、子どもの社会的スキルや自己肯定感に悪影響を及ぼすことがあります。
親同士が不仲
子どもの世界は大人よりも狭く、特に家庭で過ごす時間は子どもにとって大きな割合を占めます。両親が不仲であり、絶えず喧嘩の声が聞こえたり殺伐とした環境下に身を置くことになると、子供の精神も揺らぎやすくなります。家庭は本来、子どもの心を休め育む場です。しかし、そのような環境下では子どもの心が休まることなく疲弊してしまいます。
この心の疲弊が積もると、不登校という形で子どものストレスや不安が実態化してきてしまいます。実際、家庭内の不和が子どもの心理的健康に与える影響は多くの研究でも示されており、特に不登校と関連していることが指摘されています。
父母いずれかが不在
父母いずれかが不在であることが不登校の直接的な原因になるわけではありません。しかし両親が揃っている場合と比較し、父母いずれかが不在である家庭のほうが不登校の割合が高いというデータもあります。父母いずれかが不在である場合、親と子どもとのコミュニケーションが不足する、経済的に不安定な状況が続く、また親も日々の生活や子育てに対して不安を抱いているなど、子どもにとって健全な環境を作れない状況に陥りがちです。不登校の背景にはこうした家庭環境が深く影響していることが多く、社会的なサポートが重要だとされています。
その他様々な要因が絡み合い、不登校に至る場合もあります。
親子間のコミュニケーション不足
親子間のコミュニケーション不足が不登校という結果を招くこともあります。子どもは親とのコミュニケーションを通じて愛情や安らぎを感じますが、親子間のコミュニケーションが極端に不足していると、子どもは愛情や安らぎを感じられなくなります。実際、専門家の調査でも、親子の密接なコミュニケーションが子どもの心理的健康に与える影響が強調されています。
また親子間のコミュニケーションは、子どもの助けを求める声を拾う大切な行為の1つです。親子間でのコミュニケーションが足りないばかりに、学校での困りごとなども子ども自身で抱えることになります。このような状況が続くと、子どもは孤独感や不安感を増幅させることがあり、最終的には不登校につながる可能性が高まります。
不安な状況・欲求が満たされない状態が続いた結果、子どもが自身のキャパシティを超えてしまい不登校になってしまいます。親が子どもの声に耳を傾け、感情や状況を理解しようとすることが、子どもの心理的な安全基地を形成する鍵となります。
小学生の不登校に関するよくある質問
ここでは、小学生の不登校に関するよくある質問を紹介します。小学生が不登校になるきっかけは?
文部科学省が公表したデータによると、小学生の不登校の原因には次の3つの項目が上位に位置しました。- 無気力・不安 ……46.3%
- 親子の関わり方 ……14.6%
- 生活リズムの乱れ・遊び・非行 ……14.0%
「何となく学校に行きたくない」「友人との関係もしくは勉強への理解度などに対し不安を感じる」など、ちょっとしたネガティブな気持ちが様々な要因と絡み合って不登校に至ってしまうケースが約半数の割合を占めました。
2位には親子の関わり方が起因となり不登校になってしまった事例が続き、生活リズムの乱れ・遊び・非行を起因とする不登校もほぼ同じ割合で3位に続く結果となりました。
参考:文部科学省初等中等教育局児童生徒課
不登校の子どもに親ができることは?
不登校の子どもに対し親ができることは、お子さまの心的状況に合わせ1つずつ次のステップを用意してあげることです。あくまでも次のステップを用意するだけに留めることが大事であり、次のステップに進むよう催促するようなことがあってはいけません。
また、なぜ不登校に至ったのかその背景を探ることも大切です。
不登校の原因は様々な要因が絡み合っていることが多いですが、不登校に至った要因を1つひとつ紐解き、お子さまの気持ちに寄り添い改善や理解に努めていく姿勢も持っておきましょう。
加えて、広く情報を収集しておくことも大切です。進級・卒業など勉強に関することはもちろん、不登校児へのケアの方法、お子さまが興味・関心を示すようなモノ・コトなど多角的に情報を収集しておきましょう。
事前に情報を集め心づもりや用意をしておけば、多様な選択肢が取れるようになります。お子さまにとって最適なタイミングで新しい道を用意してあげることができるでしょう。
小学生の不登校の実態まとめ
近年増加の一途をたどる小学生の不登校。いつ誰が不登校になっても、おかしくない時代といえるでしょう。我が子が不登校になったとしても、広い心で受け止めてあげることが大切です。特に、子どもの気持ちに寄り添いながら、彼らが求める学びやコミュニティを用意する環境を整えていくことが重要です。
さらに、学校以外での活動を促進し、心身の回復を図ることが、最終的には学校復帰につながる可能性があります。地域のサポート団体やフリースクールなどの利用も考えながら、子どもの成長を見守る姿勢が求められています。
子どもの気持ちを理解し、柔軟な対応をすることで、彼らが再び社会に戻れる道を一緒に切り拓いていきましょう。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
YouTubeで勉強する小学生!おすすめ勉強動画や面白くてためになる解説
今、YouTubeで勉強する子どもたちが増えています。「ねぇ、これ見て!すっごくわかりやすいんだよ!」今回の教育トピックでは、YouTubeで勉強する小学生の実態に迫り、人気がある小学...
2026.01.05|大橋礼
-
ルーブリックは子どもを正しく評価できる方法?特徴と導入例を解説
教育現場で、新たな評価方法として注目を集めるルーブリック。アクティブ・ラーニングが授業に導入されるようになり、ルーブリックが採用される大学や高校も増加傾向にあります。この記事では、ルー...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
小学生の嫌いな科目ランキング|1位は「算数」過去の結果は?
子どもが学校に通い始めると、いつの間にか好きな科目と嫌いな科目ができてしまいます。今回は、実際に小学生の嫌いな科目のランキングのデータをもとに、今児童にどのようなことが起きているのかを...
2022.05.13|コエテコ byGMO 編集部
-
小学校の授業参観・学校公開「注意点は?服装は?見るべきポイントも教えて!」先輩ママの回答も紹介
今回の教育トピックでは、授業参観/学校公開で親が見るべきポイントや、場にふさわしい服装など「知っておくと役立つ情報」を詳しく解説します。 先輩ママたちの体験談も紹介するので、ぜひ...
2025.11.12|大橋礼
-
小学校「宿題の量が多い!」いつやる・どうやる・どうしてる?|4月の教育トピック④
最近はドリルやプリントに加えて「タブレット端末でやる宿題」もプラスされ、新しい学習方法に親が戸惑うことも少なくありません。今回の教育トピックでは主に小学校1年〜6年のお子さんがいる保護...
2025.09.10|大橋礼