算数文章題「論理的に考える子vs直感で解く子」どっちが強い!?思考タイプについて考えてみた

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
大切なのは、それぞれの特性を理解して、子どもの思考力を大きく伸ばしてあげること。
正直なところ、子どもを◯◯タイプと分けるのには無理もありそうです。でも、今回は「論理的思考」「直感的思考」の2つの傾向から、さらに広げて「子どもの思考力を伸ばす」についても考えてみましょう。
「なぜそうなるんだろう?」と子どもの思考のプロセスをのぞいてみると、意外な発見があるかもしれません!
「迷子にならない子」と「冒険に出る子」──思考タイプの違いとは?

では、まず算数の問題の解き方を例に考えてみましょう。
Aさんは、「地図を片手に道順どおりに進むタイプ」。
文章題を丁寧に読み、条件をメモに書き出し、表や図を使って一歩ずつ解いていきます。筋道を立てて考えるので、「なぜそうなるのか?」も明確に説明できます。時間がかかることはあっても、着実にゴールに向かいます。
一方、B君は「直感的に冒険するタイプ」。
文章題を見るなり「こうじゃない?」と答えを言ってくる。そこに至るまでの道筋が本人にもよくわかっていないこともしばしば。でも、時には私たち大人が思いつかないような、ユニークな方法で正解にたどり着くこともあります。

迷子にならない子の方が親としては安心な気もしますが、地図がなかったら身動きがとれないようでは、これからの時代を生き抜くのは大変かもしれないとも感じます。パパッと考え行動に移す子は、一見、積極的にも見えますが、親からすると「行き当たりばったり」で、これはこれで不安ですね……。
では、それぞれのタイプをまとめていきましょう。
論理で進む「図解派」の子
道順通りに進む“迷子”にならない子| 特徴 | 問題文の情報を図や表に整理しながら、学校で習った解法を順序立てて適用 慎重派で筋道重視 |
| 強み | 複雑な問題でもステップを踏めば解ける 友達に解き方を教えられる 記述問題で得点しやすい |
| 弱み | 「いつもの手順」から外れると混乱 発想が求められる問題で戸惑いやすい 処理に時間がかかることも |
論理派がつまずきやすい問題は
- 答えがひとつでない問題
- 立体のイメージが必要な図形問題
- 算数オリンピックのようなひらめき型の問題
論理的思考タイプの子どもたちは、定型的な解法が通用しない問題に出会うと、そこから先になかなか進めないこともあるようです。算数オリンピックのような発想力が問われる問題では、「習った公式でどう解けばいいの?」と戸惑うことも。
教科書にない発想が必要な問題に出会うと、どこから手をつけていいのか分からなくなることがあります。
ひらめきで飛ぶ「直感派」の子
地図なしでも冒険できる子| 特徴 | 問題の本質を感覚的にとらえ、型にとらわれずに素早く答えにたどり着く とにかくスピード派 |
| 強み | 柔軟な発想力 創造的なアプローチ 型にはまらない解法を思いつく |
| 弱点 | 説明が苦手 条件整理や手順の多い問題でミスしやすい テストでは部分点を落としがち |
いわゆる数学的才能とか、天才型、抜きん出ている子の話題は、時折、メディアなどで見聞きしますね。
そこまでいかなくても、頭の中に図や絵がうかんで、答えが見えてくる、そういうタイプの子どももけっこういるみたいですよ。ひらめきって、いろいろなパターンがありそうです。
直感派がつまずきやすい問題は
- 条件が多く、整理が必要な問題
- 複数のステップを経て答えにたどり着く応用問題
- 「どうやって解いたのか」を説明する記述問題
直感的思考タイプの子どもたちは、多くの条件を整理し、複数の段階を踏む必要がある問題で行き詰まることがあります。
割合の応用問題や、何段階もの計算を経て答えにたどり着く複合問題は、「なんとなく」では解きにくいもの。また、説明を求められる問題では、正しい答えを直感的に導き出せても、その過程を言葉で表現することに苦戦することがあります。
家庭でできる!論理的思考力・直感的思考力を伸ばすアプローチ

論理的思考を育てたいなら
(1)「なぜそう考えたの?」ではなく、「どうやってその答えにたどり着いたの?」と聞いてみる→考えの過程を言語化する練習になります。
(2)ボードゲームで思考力トレーニング
→「オセロ」「将棋」「ナンプレ」などは、先を読む力や条件整理の力を育てます。
オセロは親子で対決するのも楽しいゲーム。しかも、「ここに置くとこうなって、そうなると次にママがここに置くな、だったら次は…」と自然と考えるようになります。
論理的思考力は、プログラミングスクール等でも「伸ばせる力」として紹介されていますが、それはプログラミングを学ぶことで、順序立てて考えることや、プログラムがうまく動かないときに、仮説を立てて、試して、結果をみて修正する、といった体験ができるからです。
▶プログラミング教育で論理的思考力を鍛える!子どもの未来を切り開く学びとは?
直感的思考を育てたいなら
(1)正解がひとつじゃない問題にふれさせてみる→「この絵の続きを考えてみよう」「この話の別の結末を作ってみて」など、自由な発想を促す。
(2)料理や買い物を通じて“応用力”を育てる
→「塩が足りないとき、どうする?」と聞いてみると、意外なアイデアが出ることも。
(3)算数の問題も「別の解き方あるかな?」と声かけ
→固定観念から自由になる練習になります。

直感は教えてわかるものでもない、という意見もありますが、なんといっても豊かな感受性とスポンジみたいに何でも吸収する力があるのが子どもです。教えるというよりも、「こんな考え方や見方もあるかもね」の気づきを与えるイメージですね。
▶小学生向けおすすめオンライン算数塾!中学受験対策も
思考力は、日常の中でこそ育つ

そもそも、思考力とは何なのでしょうか?
思考力とは、シンプルに言えば「情報から答えを見つける力」。
でも、その「考える」には、論理的に筋道立てて考えること、パッとひらめく直感的な考え方、いろんな角度から見る多面的な考え方…など、さまざまな種類があります。
- 論理的思考
- 直感的思考
- 多面的思考
- 創造的思考
こうした思考力は見えるものではないわけですが、繰り返し「考える」ことで鍛えられ、強くなっていきます。
筋肉と似たような感じですよ!
ちょうど腕の筋肉と同じで、使えば使うほど強くなるもの。スプリンター系の筋肉とか、マラソン系の筋肉とか耳にしたことはありませんか?筋肉と同様に、思考も生まれつき持っているものや、得意・不得意もあります。
でも、自分に合ったトレーニングを続ければ、きっと伸ばすことができます。それに、特別な器具がなくても、日常生活の中でいくらでも鍛えられます(それも筋肉と似ているかも!)。
たとえば、お子さんに「おやつ300円分好きなの選んでいいよ」と言ってみると、値段を見比べるとか、小さいのをたくさん買うか、高いけど大好きなものをひとつにするか悩みます。「好み」「価格」「量」のバランスを考える、ちょっとした思考トレーニングです。
また、「日帰り旅行、どこ行く?」と家族会議をするのも効果的。「〇時に出て、△に行って、□も寄って…」と計画を立てる経験は、まさに生きた「文章題」を解いているよう。「時間」「移動距離」「予算」という制約の中で、最適解を探る本格的な思考力トレーニングになります。
何も特別なことをしなくても、意識して「考える機会」を作ってあげることが、実は一番の思考力育成かもしれません。
直感と論理、一緒に輝く瞬間

「ひらめいた!」と「ちゃんと考えた」が出会うとき、子どもの目は輝きます。
算数の問題で、直感でパッと答えを思いついた子が「どうしてそうなるの?」と考えると、自分の考えに自信が持てるようになります。反対に、いつも手順通りに解く子も、時には「こうしたらもっと早く解けるかも?」と新しい道を探ることで、思考の幅が広がります。
論理的思考と直感的思考の力が手を取り合うとき、子どもたちはもっと自由に、もっと楽しく問題に挑戦できるようになるんです。直感がきっかけを作り、論理がそれを育てる。その繰り返しが、子どもたちの「考える力」を豊かにしていきます。
直感的に「ひらめいた!」を大事にすること。 そして、それをじっくり言葉や考えで確かめていくこと。 その両方を応援していきたいですね。
正解探しより、“考える楽しさ”を

大人の私たちも、答えがひとつでない時代を生きています。正解をなぞる力だけではなく、状況に応じて「どう考えるか」を切り替える柔軟性が求められています。
だからこそ、子どもが問題に向き合うとき、解けたかどうかだけでなく、その「考える姿勢」を認めてあげることが、いちばん大事なのかもしれません。

算数の文章題は、ただの“テストのための問題”ではなく、多様な思考を育てるチャンス。 今日の「どうしてそう考えたの?」という会話が、きっと明日の思考力の土台になります。
先輩ママのおまけ体験談
「論理的思考力と直感力、算数に強いのはどっちだと思う?」そんな問いかけを、知り合いのママに投げかけると、ちょうど帰宅していた息子さんに聞いてくれました。彼女の長男は、いわゆる超難関の中高一貫校へ進み、その後、東大に合格。「中学受験くらいだと直感的な子が算数も強い印象はあるよね。でも、表向きにそう見えていても、頭の中ではちゃんと論理的思考が整っている場合が多い感じ」
「だけど実際に◯◯中に入って思ったんだけど、いるんだよね。本当にひらめくように当たり前に難問を解いていく子も。努力しても追いつかないのかなとちょっと思ったこともあった。ただ、証明問題や論述が必要になるような問題だと、頭の中で完結しちゃう子が意外と苦戦するっていうか、そこから思ったより伸びなくて悩んでいる子もいたよ。それでも、学年にひとりやふたり、こいつ天才か、ってのはいたけどね」
そして、中学受験を振り返って、「自分はコツコツ勉強して、論理的に考える方が得意だったから、◯◯中学でよかったと思う。答えだけを記入させるタイプの学校だったら、合格してなかったかもね」と続けたと言うのです。
いや、賢い子っていうのは、こんな問いかけにもきちんと返してくれるんだなぁ〜!
すると「オレはね、直感的なタイプだね!」と返ってきたので、「それって生まれつき?」と聞くと、ぶんぶん首をふります。
「オレが思うに……」
(いや、そこでわざと考えるフリしなくてもいいって!とちらりと思った母です……)
「厳しく育てられた子は、嫌でも論理的思考力が強くなるんじゃない?だって、何かする前に『親に怒られるかな』とか『怒られないためにはどうすればいいか』とか、いろいろ考えて、分析して、こうすれば怒られないぞって結論を出すわけだから」
要するに、怒られないために、順次的にどうすればいいかを考える訓練を自然としているというわけです。
なんだかなぁ、その例ってビミョーすぎる……。
私、放任主義だと思ったことないんですけども。でも、「なぜそういう考えになったのか、きちんと順を追って説明してみて」なんて、確かに言ったことないかも……。
この子の読書感想文って、すごくユニークで楽しい内容で、私はいつも褒めていたんですよね。
ただ、「読書感想文のお作法」みたいなものからは外れていて、他の人が読むと「なぜそういう感想になったのか」の説明が足りないものでした。だから一部の先生には「子どもらしい想像力や思考でいいですね」と言われたものの、一般的には評価されないタイプの感想文だったと、改めて思い出したところです。

少し話がずれましたが、皆さんのお子さんはどうですか?家庭環境と思考タイプの関係、意外と興味深いですよね。
勉強の成績ももちろん大切。でも子育ては、別の角度から見てみることも時には必要です。
「もう、なんでうちの子はこんなに回り道するの!」とため息をついていたことが、実は「そうか、こんな風に考えるタイプなんだね」という理解に変わる瞬間。子どもの思考の特性を知ることで、イライラが「なるほど!」に変わり、「うちの子、こんなところが案外すごいのかも」という新しい、楽しい発見ができるかもしれません。
子育てって親にとっては「大変」だし、正直わが子に対して「がっかり」の場面も多くあるもの。私たち「親」こそ、思考力を鍛え、柔軟で幅広い考え方で、子どもを大きな視点で見守れるといいですね!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学生とSNS「LINE・Twitter・FacebookにTikTok」との関わりを親は本当に把握してる?
小学生が今やSNSを利用する時代。SNSはコミュニケーションツールとして優れている点があると同時に、子どもが安易に手を出すと、事件性のあるトラブルに巻きこまれることもあります。 今回...
2025.09.10|大橋礼
-
子供の部屋が汚い原因は?片付けられない子の思考パターンと親のサポート方法
「なんで片付けないの!」「何度言えばわかるの!」お子さんの散らかった部屋を見て、ついこんな言葉が出てしまった経験はありませんか?片付けができないのは、単なる「だらしなさ」だけではなく、...
2025.08.26|大橋礼
-
子どもの集中力を高める方法とは?集中力が続かない子どもの勉強方法3つ|教育トピック
「うちの子は集中力がなくて困る」という声は、よく耳にします。 勉强しているかと思えば、ぼーっとしていたり、10分たっても20分たっても漢字ドリルの半分も終わっていなかったり。結果...
2025.09.10|大橋礼
-
中学生の進路選択「迷う子どもに親ができること」
「うちの子、将来のことを全然考えていなくて心配」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。しかし、中学生が進路について明確な目標を持っていないのは、実は珍しいことではありません。...
2026.01.08|大橋礼
-
KAPLA(カプラ)のメリットとは?おすすめの種類や公式直伝の遊び方もご紹介
欧米では「まほうの板」とも呼ばれる、KAPLA(カプラ)ブロック。公式サイトでは「プログラミング的思考力が伸びる」と紹介されています。4歳と3歳の息子をもつ私は、3か月前にKAPLAを...
2025.05.26|原 由希奈
















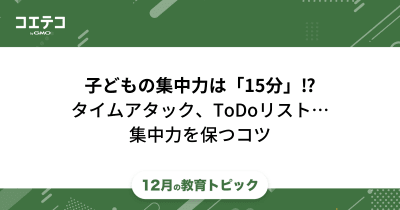
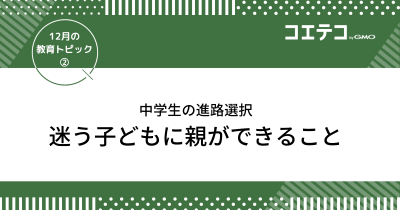

左脳思考とかクリティカル・シンキング(客観的な視点で分析する)なんて呼ばれることもありますね。
ウチの子は慎重だな〜、石橋を叩いて渡るタイプなのかな、なんて思っている方。よくよく子どもの話を聞くと、無意識にどうするべきか順番を考えていたり、こうしたらこうなるかも、と仮説を立てていたりすることもありそうですよ!