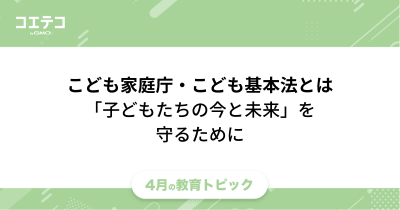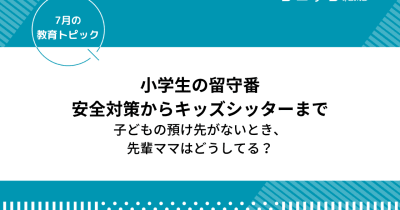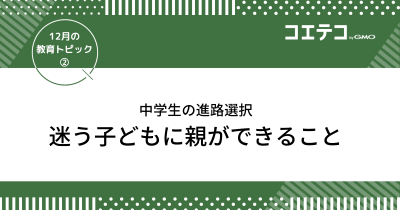中学生にインスタは大丈夫?Instagramの危険性と注意点を解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
写真投稿SNSであるInstagramは、日本でも幅広い年齢層を対象に定着してきました。
「インスタ映え」が流行語大賞に選ばれてもう2年。
中学生ぐらいの子どもの多くは、ごく普通にinstagramを使いこなしています。
でも、保護者としては、目の届かないところで子どもがInstagramをしていたら不安になるのも当然ですね。
ここでは、Instagramの基本から注意点、楽しく使う方法などをお伝えします。
Instagramとは?
そもそも、InstagramとはどのようなSNSなのでしょうか?参考:SNSとは?メリット・デメリット
写真や動画専用のSNS
InstagramとはFacebook、Tik Tok、Pinterest、Tumblrなどと並んで世界的にポピュラーなSNSの一つです。他のSNS同様、Instagramのアプリは無料で利用料金もかかりません。
Instagramの最大の特徴は、写真や動画でのコミュニケーションを目的としている点にあります。
ユーザーは、スマートフォンと専用アプリによりかんたんな操作で写真や動画をアップロードでき、世界中にシェアできます。
テキストを必要としないかんたんなコミュニケーションスタイルで若者たちを中心に人気を集めてきました。
もう一つの大きな特徴は、Instagramはスマートフォンやタブレットが中心で、パソコンからの投稿やアクセスは大幅に少ないことです。
アクティブに歩き回りながら、見たもの感じたものをスケッチできる軽快なメディアといえますね。
Instagramの歴史とは?
InstagramがApp Store(iPhoneのアプリストア)に登場したのは2010年10月6日です。その後わずか2ヵ月で100万人の登録ユーザーを獲得。翌年9月までに1,000万人を突破しました。2011年には、キーワードに#をつける「ハッシュタグ」と呼ばれるインデックス機能が追加され、写真検索がより簡単になりました。
2012年には、FacebookがInstagram社を10億ドルで買収して傘下に収めました。それからもIstragram自体は、Facebookとの連携を強化しながらも独立したサービスとして存続します。
日本語アカウントが開設されたのは2014年で、気軽にアクセスできるサービスが人気を集め、2017年には「インスタ映え」が流行語大賞に選ばれました。
2016年には全世界ユーザー数が5億人を超え、国内でも2025年1月時点で6,600万人のユーザーがいると推定されています。
Instagramは何歳から使える?
Instagramの規定では、ユーザー登録できるのは13歳以上と決められています。それ以下の年齢の人がユーザー登録をしているとわかったときには、サポートに通報するとアカウント削除が行われます。
その一方で、最初の登録時には年齢も確認されずにメールアドレスまたは電話/携帯番号とパスワードを入力すればかんたんに登録できます。
ルールを破って小学生が遊んでいないかと、保護者なら心配になるところですよね。
Instagramにはなぜ年齢制限があるの?
なぜInstagramには13歳以上という年齢制限があるのでしょうか。このような年齢制限が設けられているのは何もInstagramだけではなく、TwitterやTikTokといったSNSも、13歳以上でなければアカウントを作成することができないという制限があります。これには、まだ判断能力の発達していない青少年を保護するという目的があります。
これらのWebサービスにおいては、一般的に判断能力のあると考えられる年齢を13歳以上と考えているようです。日本でいえば中学1年生にあたりますので、確かにある程度の判断力があるとは言えそうです。親御さんの側でも、中学生になったらスマホを買い与える約束をしているという方も多いのではないでしょうか。
Instagramでできることは?
使ってみないと楽しみ方も欠点もわからないのがSNS。ここではInstagramの基本的機能を紹介します。写真や動画を投稿できる
Instagramのもっとも基本的な機能が、これ。写真や動画を撮影して、アプリから送信すると、Instagram上のじぶんのページに表示されます。また、それぞれの写真や動画にタイトルや説明文もつけられます。
写真や動画を加工したりキャプションをつけられる
Instagramのアプリには、写真を調整する機能があります。暗くて顔がはっきりしない写真でもカラーカーブの調整で見やすくできます。
セピアカラーやモノクロ写真に加工して、雰囲気のある写真に仕上げることも。
写真に額縁を付けたりデコレーションしたり、また、キャプションや吹き出しを使った演出の仕方も「インスタ映え」の一つのポイントとなっています。
写真や動画を共有できる
Instagramには、Facebookの友だち機能と同様に、フォロー機能があります。Instagramをはじめたら、友だちに知らせてアカウントをフォローしてもらえば、友だちはあなたの公開した写真を見ることができます。
ただ、Facebookとは違って、投稿を「非公開」にしておかなければ世界中から投稿が見られる状態になってしまいます。
ごく親しい友達を相手にプライベートな内容を共有するのであれば、非公開に設定しておくのをおすすめします。
ごく親しい仲間に共有するなら「非公開」設定に
初期設定の状態で投稿した写真や動画は、全世界の数億人のユーザーから「見える」状態になっています。フォロワーだけでなく、ハッシュタグ(キーワードに#を付けたもの)やあなたのIDで検索してきたユーザーにも見られます。
また、Twitterのリツイート機能にあたるリポスト機能を使えば、リポストをした人のフォロワーのタイムラインにも上がるようになります。
「それはちょっと……」と思う場合は、アカウントを「非公開」に設定しておくといいでしょう。
未公開設定をしたときには、写真や動画はフォロワー以外には見えなくなりますが、フォロワーがリポストしたときには「フォロワーのそのまたフォロワー」には見えるようになるので、あらかじめ「リポストしないでね」とお願いしていておいた方がいいでしょう。
Instagramは、さまざまなすぐれた機能があり、ユーザーなりの付き合い方ができるメディアです。アカウント削除も比較的簡単にできますので、じぶんなりの付き合い方をしたいものですね。
参考:インスタアカウント退会方法は?停止との違い
中学生にInstagramを使わせる注意点とは?
他のSNS同様に、Instagramにもさまざまなリスクが指摘されています。ここでは、子どもが使う場合の注意点をまとめます。仲間同士でのいじめ
過去には「LINEいじめ」が問題になりましたが、Instagramでも、そのリスクは存在します。たとえば、フォローはずし、秘密の暴露、挑発的なコメント、遊びに行った写真を使って仲間はずれにする、などです。
保護者として注意するすべきは、他のいじめと同じかもしれません。
子どもの態度の変化をよく見て、何かサインがあったときには見逃さず、話し合いの機会を持つ姿勢がたいせつです。
夜遊びや外泊などの誘惑の拡大
Instagramに限りませんがSNSにはダイレクトメッセージ機能があり、これを使えば友だちやまったく見知らぬ人ともコミュニケーションが取れてしまいます。スマホが解禁された直後の中学生は、人生のなかでもとくに好奇心にあふれた時期。
見知らぬ人物からのたくみな誘いについだまされて夜出かけ、後悔する結果になったら、かわいそうなのは子ども自身です。
保護者もまた、この世代になったら注意して、帰宅時間が遅くなるなどのサインを見逃さないようにしたいものです。
プライバシーの流出
残念ながら、世の中には悪意をもってSNSを閲覧する人物がいるのは否定できません。たとえば、通学途中の風景や制服の写真から学校名や通学経路を割り出してアプローチしてくるリスクも可能性としては存在しています。
日頃から、学校名や住んでいる町がわかる投稿には気をつけたいですね。
参考:ネットリテラシーとは?低いでは済まされない?意味を徹底解説
利用しすぎ、Instagram依存
SNSに依存すると、かたときも手ばなせない状態になると言われます。学習中でも夜寝てからもコメントが入るとすぐに返事しなくちゃと思ったりする強迫観念にとらわれるかもしれません。
こうなると、学習にも健康にも悪影響を及ぼしてしまいます。
その前に、早めのチェックと保護者と子どもの話し合いがたいせつでしょう。
参考:デジタルネイティブとは?意味と特徴を徹底解説
まとめ|目を配る、話し合う、頭ごなしに禁止しない、保護者もいっしょにInstagramを楽しんじゃうのがベスト
ここまでInstagramの楽しみ方とリスクについて、まとめてみました。SNSに限らず、子どもたちに人気が出ると、保護者としてはつい禁止したり制限したりしたくなるかもしれません。
でも、逆の見方をすれば、人気が出るのは楽しいからです。
さまざまな人々の生活シーンの写真を見て世界が開かれたと感じてわくわくする子どもも多いでしょう。
「いいね」がたくさんつくと、達成感もえられるでしょう。
それを頭ごなしに禁止しては、親子のコミュニーションが断絶して人間関係も悪化してしまうかもしれません。
リスクを防ぐいちばんの方法は、日頃から保護者と子どものフレンドリーなコミュニケーションではないでしょうか。
子どもを「監視」するのではなく「楽しみ方を教えてよ」とアプローチして「イヤじゃなかったら、フォローしていい?」くらいの態度で接すれば、悪い事態の回避に役立つはずです。
保護者と子どもが、お互いに「いいね」をつけあう関係になったら素敵ですよね。
Instagramでも保護者のためのInstagramガイドを用意しています。リンク先で読めるので、気になった方はチェックしてみてくださいね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
子どものスマホは何歳から持たせる?平均やいつからなのか解説
スマホを買い与えるかどうかの判断は親として悩ましいところでしょう。 「いつかは必要」「やむをえない」と思っても、どのタイミングがベストかはなかなか判断が難しいものです。 ここでは子...
2025.08.08|コエテコ byGMO 編集部
-
こども家庭庁・こども基本法とは?知っておきたい「子どもたちの今と未来」を守る権利と国の組織
2023年4月に「こども家庭庁」が発足しました。同時にこども基本法も施行されたことは、ニュースなどでご存知の方もいるかもしれません。“こども家庭庁”は「こどもまんなか」を謳っていますが...
2025.09.10|大橋礼
-
小学生の留守番「安全対策からキッズシッターまで」子どもの預け先がない時の対処法
今回の教育トピックは「子どもひとりでお留守番」の方法についてです。 預け先が見つからない急な外出や、どうしても子どもひとりで「まるまる1日過ごさせなくてはならないとき」もあるでしょう...
2025.10.29|大橋礼
-
中学生の進路選択「迷う子どもに親ができること」
「うちの子、将来のことを全然考えていなくて心配」そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。しかし、中学生が進路について明確な目標を持っていないのは、実は珍しいことではありません。...
2026.01.08|大橋礼
-
利用率急上昇中!小学生のAI活用実態と家庭でできる正しい対策
今や小学生はおろか、幼児でさえ、知らず知らずのうちに「AI」に触れています。AIについて、なんとなくはわかっていても、きちんと子どもに仕組みを説明し、正しい使い方を教えている保護者はど...
2025.09.22|大橋礼