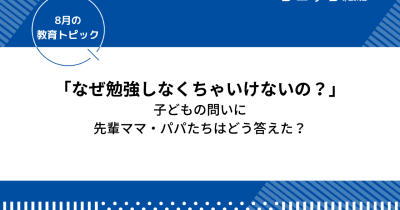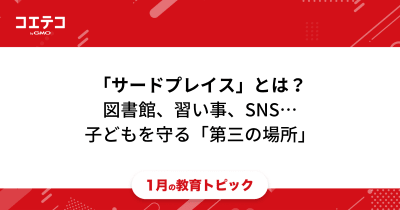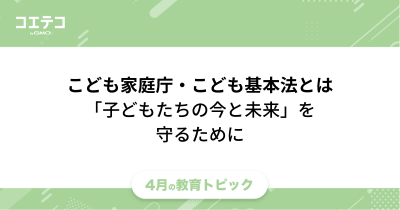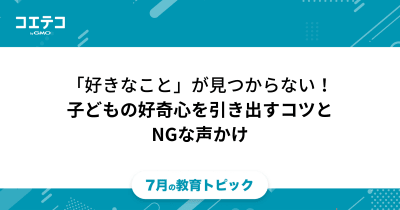勉強の仕方が分からない中学生必見!効率の良い勉強法まとめ
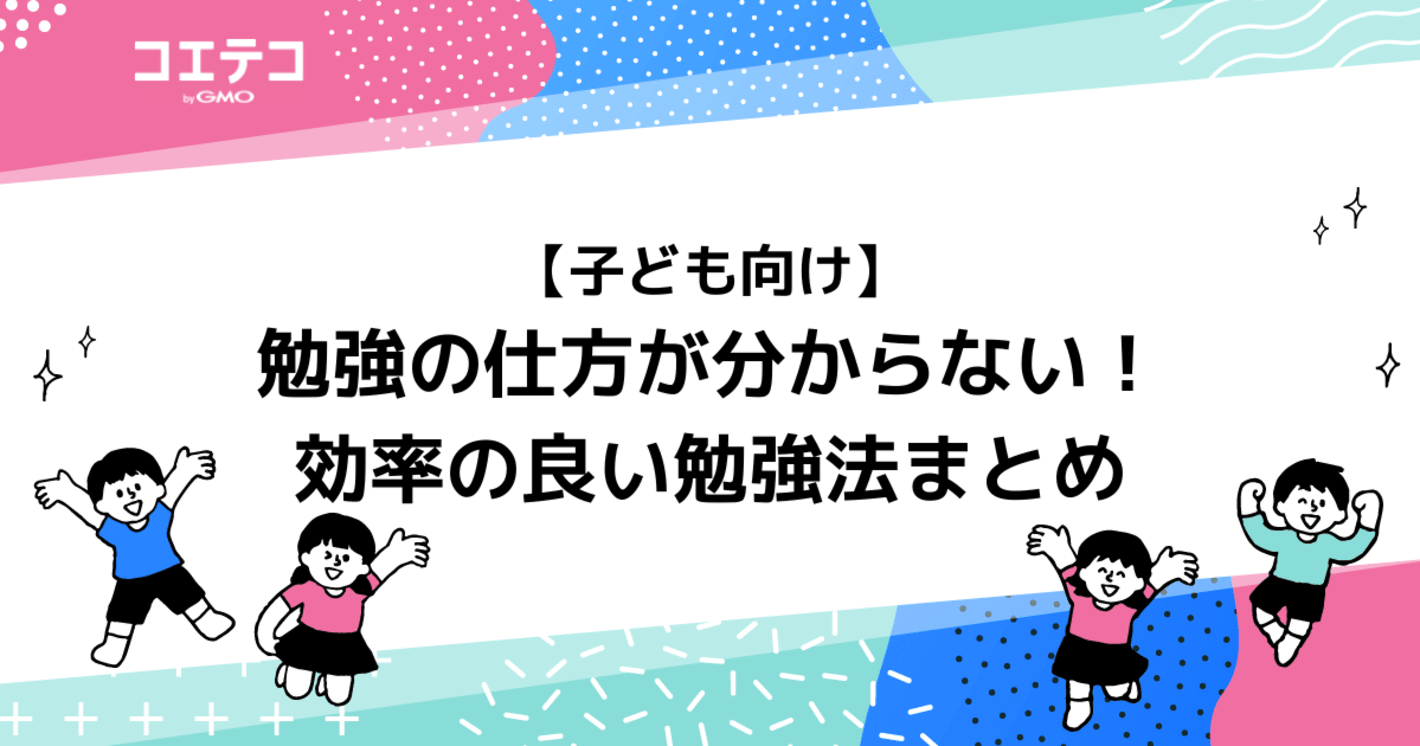
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
メモのとりかたがよくわからなかったり、復習のやりかたがよくわからなかったり。勉強に苦手意識を持ってしまう理由は、効率よく学ぶためのコツがうまく掴めないからかもしれません。この記事では、子ども向けの勉強法や、ヒントとなる情報をまとめて紹介します。
勉強の仕方が分からない中学生よく見られる傾向

1つ目は、勉強の面白さがわからずに勉強を「しない」という状態。この場合、学校の勉強に興味を持たせられるかどうかがポイントになるといわれています。
2つ目は、概念が理解できないから「わからない」という状態。例えば、「分数の割り算」(分子と分母を逆にするもの)という概念が理解できないなど。
3つ目は、どこがわからないのかが「わからない」という状態。この場合、何から手を付けたらいいのかもわからず、わからないことに嫌気がさして、勉強が嫌いになってしまうため、まずは何がわからないのかを特定し、その部分の解決を図るようにしてあげることが大切といわれています。
約半数の子どもが「勉強の仕方がわからない」
「ベネッセ教育総合研究所」が、小学1年生から高校3年生、約2万1千組を対象に行なった「子どもの生活と学びに関する親子調査」によると、学習の悩みについて「上手な勉強のしかたがわからない」という子どもが、2019年から2022年にかけて増加し、「あてはまる」という子どもが約7割になったとのことです。ベネッセ教育総合研究所は、子どもたちが学習方法について体系的に学ぶ機会は少なく、効果的な学習方法を身につけることができていないと実感している子どもが多いのではないかとの見解を示しています。
調査では、学習時間を十分に取っている子どもほど学業成績が良くなる結果が示されたほか、学習の質の重要性を示す結果も示されました。
この結果から、学習の 「量」と「成績」はある程度比例し、一定の学習時間を確保することは学力を高めるために重要な要素といえるほか、短い学習時間でも学習方法の工夫によって成果を上げることが可能になると考えられています。
では、勉強の仕方を理解し、その質を高めていくためには、どうすれば良いのでしょうか。
中学生向け効率の良い勉強法の「基本」とは?
中学生向け効率の良い勉強法の「基本」は、次の通りです。- 考えても分からないことは親や先生に聞く
- テストで間違えた問題をやり直す
- 遊ぶ時は遊び、勉強する時は集中して勉強する
- 繰り返し書いて覚える
- 友だちと勉強を教えあう
- 何から勉強したらよいか順番を考える
- 何が分かっていないか確かめながら勉強する
- 問題を解いた後、ほかの解き方がないかを考える
この中で、勉強が「嫌いから好き」に変わった子どもがより多く行っている効果的な勉強方法は、下記の3つといわれています。
- 何が分かっていないか確かめながら勉強する
- テストで間違えた 問題をやり直す
- 繰り返し書いて覚える
勉強が「嫌いから好き」に変わった子どもは、学習時間が増加し、成績も「上がった」と回答しています。
参考:タブレット学習中学生
参考:通信教育中学生
【科目別】効率の良い勉強法

ここでは、学習塾や教育情報のウェブサイトなどで公開されているノウハウをもとに、効率の良い勉強法として解説されている方法を科目別に紹介します。
参考:中学生の家庭学習
①英語
単語を覚える際は、見るだけではスペルが書けない場合があるため、単語を見るだけでなく書いて覚えることや、何度も教科書を音読しながら訳し、わからない部分の文法や単語を復習することがおすすめされています。参考:中学生向け英語塾
②国語
国語の勉強のコツは、主に「漢字」と「読解力」の2つに分かれるといわれています。漢字は、例えば、きへんやごんべんなど、漢字の意味を理解すると覚えやすくなるといわれています。その際、部首や書き順を意識することも付け加えられています。
読解力を身につけたいときに効果的だといわれているのは、読書。重要なのは、量よりも質で、わからない言葉の意味を調べながら、語彙力や読解力を養っていくことが大切とされています。
読解力は、読むだけでなく、書いたり話したりすることも欠かせません。日頃から相手にわかりやすく伝えることを意識してみたり、相手に伝わる文章を書く練習のために、日記を書くこともおすすめされています。
参考:読解力高めるためには?
参考:国語専門塾
③数学(算数)
数学(算数)は、前の単元ができていないと、次の単元もできない積み重ねの教科といわれています。例えば、中学校で習う「一次関数」は、小学校の「比例」から続いていたりと、小学校で習う算数が中学校や高校の数学に発展していくため、過去にわからなかった問題を放置しておくと後の分野に影響します。そのため、一定の演習量を確保して、繰り返し演習を行い、出来ない問題を発見して潰していくことが大切といわれています。
また、ベネッセ教育情報サイト「効率の良いおすすめ勉強法7選&効率の悪いNG勉強法4選を一挙紹介!」では、基礎の計算力が重要な科目といわれています。
参考:中学生におすすめの数学専門塾
④理科
理科の特徴は、暗記と計算の両方が求められる点です。理科の計算問題は、公式を覚えただけでは解けないため、演習問題を多くこなすことが重要視されています。問題を解いた後、解説をしっかり読み、答えに至る考え方を学ぶこともおすすめされています。
また、理科は自然や生き物、電気など、日常生活と関連が深い科目であるため、身近な好きなものに対して「どうして?」と疑問を抱く事柄があれば、どんどん実験や考察をさせていくことで理科の勉強へのハードルを下げられるのではないかともいわれています。
⑤社会
社会は、暗記が鍵を握る科目と言われています。歴史や地域、経済や政治の仕組みなど、大まかな全体像を掴んでから背景を理解すると、細かい単語も暗記しやすくなるといわれています。
また、旅行や散歩に行って地図を見たり、テレビ番組などを見て年表を広げてみたり、日常生活とリンクさせることで理解が高まるとも。
効率の良い勉強の中でおすすめ!中学生向け通信教材・塾5選
勉強の効率が思うように上がらない場合は「タブレット学習」や「オンライン塾」もおすすめです。参考:タブレット学習中学生向け
参考:中学生向けオンライン塾
東京個別指導学院・関西個別指導学院

東京個別指導学院・関西個別指導学院は、ベネッセグループが運営する個別指導塾です。
最大の特長は、「生徒一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの学習プラン」を提供している点にあります。
集団の一括指導ではなく個別のニーズに合わせた指導を受けられるため、「集団授業についていけない」「どこから手をつけていいか分からない」といった中学生でも、自分のペースで学習を進められるでしょう。
また、東京個別指導学院・関西個別指導学院では、担当講師制度を採用しており、相性の良い講師が継続して指導することで、生徒の個性や学習状況を深く理解し、きめめ細やかなサポートを実現します。
定期テスト対策から受験対策まで、目標に合わせたカリキュラムを柔軟に作成し、効率的な指導で目標達成を目指します。
さらに、自習スペースも完備されており、授業がない日でも利用可能。
学習計画の立て方やモチベーション維持についても、講師や教室長が親身にアドバイスしてくれるため、まさに「勉強の仕方」そのものを身につけたい中学生には最適な環境と言えるでしょう。
トライのオンライン個別指導塾

トライのオンライン個別指導塾は、全国どこからでも「プロの個別指導」を受けられる点が特長のオンライン塾です。
家庭教師のトライで培われたノウハウをオンラインで提供しており、自宅にいながら質の高いマンツーマン指導を受けられる点が魅力。
指導経験豊富なベテラン講師や、難関大学出身の専門分野に強い講師など、様々なニーズに対応できる講師が多数在籍しており、生徒の学力や目標、性格に合わせて最適な講師を選択できます。
さらに、オンライン指導でありながら、ホワイトボード機能を活用したり、手元カメラでノートを共有したりと、対面指導と遜色ないきめ細やかな指導を実現している点も特徴です。
また、授業時間外でも質問できるサポート体制が整っており、疑問点をすぐに解消できるのも魅力。
定期テスト対策から受験対策、さらには学習習慣の定着まで、生徒の「勉強の仕方」を根本から見直し、自立した学習者を育てることを目指します。
通塾の手間が省けるため、部活動などで忙しい中学生や、近くに適した塾がない地方の学生にも最適な選択肢となるでしょう。
東進オンライン学校中学部

英・数・国・理・社の5教科に対応しており、標準講座では英・数を、実戦力養成講座では数・国・理・社を学べるシステムです。標準講座では日々積み上げてきた力を得点につなげる学習法を習得でき、実力養成講座では90点以上を目指す一歩進んだ学習法を習得できます。
主要5教科は全学年・全範囲をいつでも学習できる、自由に復習・予習を進められるのも魅力の1つ。標準講座・実戦力養成講座・全範囲学習が全部入っても、月額2,980円~から受講できます。
進研ゼミ中学講座

タブレットで問題を解くだけでなく、ライブ授業では講師の問いかけに解答する双方向のやり取りがあり、学習内容を深く理解しやすい内容になっています。
学習する内容が自動で提案されるのも特徴です。「今日は何をしよう……」と迷うことがなくなり、スムーズに学習に取り組みやすくなるでしょう。間違えた問題や重要な問題の解き直しも提案されるため、苦手な箇所を残しません。
すらら

「すらら」では「頑張ると良いことがある」という体験を積み重ねることで、自ら勉強に取り組めるようになるトークンエコノミー方式を採用しています。目標に向けた頑張りでご褒美のトークンを受け取り、貯めたトークンを欲しいものと交換できる仕組みです。一定期間繰り返すことで、目標達成に向けて頑張ることを習慣化できるでしょう。
学習内容で分からない部分が出てきたときには、質問機能でコーチに質問することも可能です。
【科目別】勉強におすすめの参考書・ドリル
ここでは、小学生の子ども向けにおすすめの参考書・ドリルを科目別に1冊ずつ、紹介します。種類が豊富にあるため、基礎が学べるものを重点的に選びました。①英語
タイトル:「やさしくまるごと小学英語」出版社:学研プラス
価格:2640円
おすすめポイント:1冊で小学校3年~6年で学ぶ英語の内容を網羅。オールカラー&マンガ付きで、楽しく学べます。YouTubeでこの本をテキストにした動画授業も公開。付属DVDには、「効果的な英語の学習法」と「アルファベットの発音のミニ特別授業」も収録。別冊単語まるごと練習ノート付き。YouTubeの動画授業で先生がスピーキング練習を促してくれるので、慣れると自習用にも利用できるでしょう。
下記記事では、中学生におすすめの英語塾を解説しています。
②国語
タイトル:「いっきに極める国語 小学1~3年の漢字」出版社:くもん出版
価格:1320円
おすすめポイント:小学1~3年で学習する漢字440字を、学年をこえて効率的に学習可能。漢字の一字一字がとても見やすく、意味や形など漢字の特徴ごとにグループ分けされているので勉強しやすいという声も。小学4~6年のシリーズもあります。
下記記事では高校受験の対策も可能な中学生向け国語専門塾を解説しています。
オンラインの国語専門塾はなら全国どこからでも、これから求められる国語力を伸ばす指導を受けられます。しかし国語をオンライン指導で本当に伸ばせるのか不安、何を基準に塾を選べば良いか分からないという保護者も多いのではないでしょうか。本記事では中学受験、高校受験、大学受験対策もできるおすすめのオンライン国語塾や塾選びのポイントについて解説します。
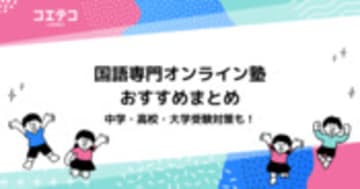

2026/01/02

③算数(数学)
タイトル:「陰山メソッド 徹底反復『百ます計算』」出版社:小学館
価格:660円
おすすめポイント:毎日同じ問題を2週間、徹底反復することで計算の基礎・基本が身に付きます。小学校全学年対象。たし算、ひき算、かけ算、わり算の各プリントが2週間分(14枚)入っています。2週間毎日同じ問題を繰り返し解くことで、前回の経験が頭の中に残り、どんどんタイムがよくなり、計算力が向上していきます。
下記記事では、オンライン受講も可能な、中学生におすすめ数学専門塾を紹介しています。
小学校のときは算数に苦手意識がなかった生徒が、中学校で数学が苦手科目になってしまうこともあります。中学校の数学でつまずかないために、おすすめなのがオンラインの数学専門塾です。この記事では、中学数学の苦手克服にオンライン塾がおすすめの理由と特色のあるオンライン塾をご紹介します。
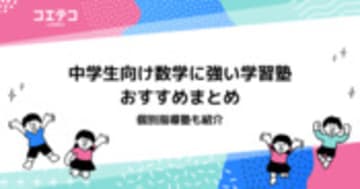

2026/01/02

④理科
タイトル:「これでわかる理科」出版社:文英堂
価格:1430円
おすすめポイント:オールカラーで図解付き。参考書とドリルと問題集がセットになっています。令和2年度からの新課程小学理科教科書に対応し、基礎から応用まで掲載。小学3年~6年生まで各学年のラインナップあり。本のはじめに、教科書の重要なポイントをまとめた「よう点チェックカード」の付録付き。テスト前にチェックができて便利です。自学自習用にもおすすめ。
中学生向けオンライン塾で理科対策が可能です。
中学生の理科対策には、オンライン塾がおすすめです。この記事では、中学生が理科に対して苦手意識を感じる理由から、中学生の理科対策にオンライン塾がおすすめの理由、さらに理科の苦手克服や入試対策に有効なおすすめオンライン塾を紹介しています。理科が苦手で悩んでいる中学生や保護者の方は、ぜひ参考にしてください。
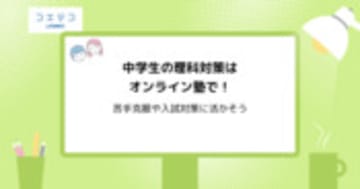

2026/01/02

⑤社会
タイトル:「?に答える! 小学社会 改訂版 (小学パーフェクトコース) 」出版社:学研プラス
価格:3300円
おすすめポイント:「?」と思ったときに子どもが自分の力ですぐに調べられる用語集。自ら学ぶ習慣がつきます。小学3年~6年の教科書の基礎から入試対策までを網羅。小学生が調べやすいように工夫されたビジュアルたっぷりの内容です。新学習指導要領対応。
勉強の効率が上がる?「ちょっと変わったおすすめ勉強法」
STUDY HACKERのコラム「東大生・京大生がおすすめする勉強法」では、こんな勉強方法も紹介されていました。参考:受験勉強は何からすればいいのか悩んでいる中学生へ
①「1冊3周」勉強法
STUDY HACKERのコラム「一冊を完璧に仕上げる! 京大生が教える「1冊3周勉強法」によると、問題集や参考書は1冊に絞って完璧にやり終えるのが、勉強法の基本だといわれています。「1冊3周」勉強法は、参考書を3周に分けて異なる方法で読み込んでいく勉強法です。1周目は参考書に目を通し、全体像を把握。読んだところや理解度に応じてマーカーなどで色分けします。
2周目は、内容を理解しながら読み、問題を解き、その内容を要約します。ページ数の横などに自分の言葉で要約を書き込みます。問題集の場合は、問題の解き方や考え方を書き込むのがポイントだそうです。
3周目は、本文を再度熟読。これまで2回読んでいるので分からないところが具体的になると言われています。マーカーなどを使いながら重要箇所の見直しを行うことで、最初に読んだ時よりも知識が定着し、効率よく勉強を進めることができると解説されています。
②ストップウォッチ勉強法
STUDY HACKERのコラム「勉強するなら絶対に用意したい「ストップウォッチ」のすごい効果」で紹介されている、ストップウォッチで時間を測りながら勉強する方法です。やり方は、ストップウォッチを使って、勉強する時間を測るだけ。それからノートに、何時間、何を勉強したのか、1日の合計勉強時間を記入します。
勉強の合計時間を記録し、努力を可視化するのがポイント。勉強時間への意識を高めてモチベーションアップにつなげ、制限時間を設けて勉強することで集中力や記憶力が鍛えられるのだとか。
勉強のやる気が出ない、すぐ飽きてしまうといった、勉強に対しての心理的な要因で勉強がなかなか進まない子どもにも、取り入れやすい方法かもしれません。
まとめ!勉強の仕方が分からない中学生はタブレット学習や塾に頼ろう!
何が分かっていないかを確かめたり、考えても分からないことは親や先生に聞いたり、やり方を工夫することで勉強が嫌いから好きになった子どもがいます。勉強が好きになれば、学習意欲が湧き、基礎学力の向上も期待できます。様々な学習方略や参考書などをうまく利用して、上手に楽しく勉強できる方法を身につけたいもの。独学が難しい場合は、習い事を利用するのもおすすめです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
「どうして?なぜ勉強しなくちゃいけないの?」子どもの問いに先輩ママ・パパたちはどう答えたか
「なぜ勉強するのか?」と問いかける子どもは実に多いものです。パパママ自身も小さい頃、親に聞いたことがあるかもしれません。 その答えはさまざまですが、今回は「なぜ勉強するのか」に先...
2025.09.10|大橋礼
-
サードプレイスとは?〜子どもに学校・家庭以外の“もうひとつの居場所”を〜
子どもだって、学校で嫌なことがあったり、友だちとうまくいかなかったり、あるいは家庭に不満を抱いたりすることもあるでしょう。そんな時に、家と学校以外にもうひとつ、子どもが駆け込める場所が...
2025.09.10|大橋礼
-
こども家庭庁・こども基本法とは?知っておきたい「子どもたちの今と未来」を守る権利と国の組織
2023年4月に「こども家庭庁」が発足しました。同時にこども基本法も施行されたことは、ニュースなどでご存知の方もいるかもしれません。“こども家庭庁”は「こどもまんなか」を謳っていますが...
2025.09.10|大橋礼
-
小学生から始める理科好きに育てる方法とは〜理科嫌い・リケジョ・文理選択を考える〜
理科嫌い・理科好きは、まだずっと先のことと思っている進路の「文理選択」にまでつながっています。 今回の教育トピックは、理科嫌い・理科好きの子どもの特徴や育った背景を探りつつ、「うちの...
2025.09.10|大橋礼
-
好きなことが見つからない!子どもの好奇心を引き出すコツとNGな声かけ(体験談)
子どもに「やりたいことはないの?」「好きなことは何?」と聞いても、「別にぃ~」「特にない」なんて薄い反応しか返ってこなくてガッカリしたことはありませんか? 親としては、子どもの好...
2025.09.10|大橋礼