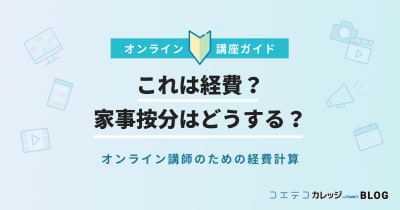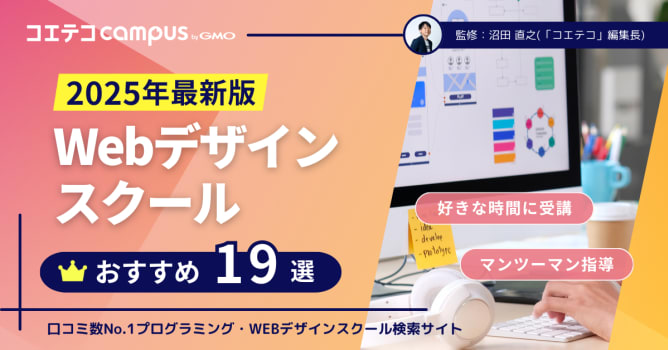開業届は出しておくべき?オンライン講師のための開業届の出し方とは
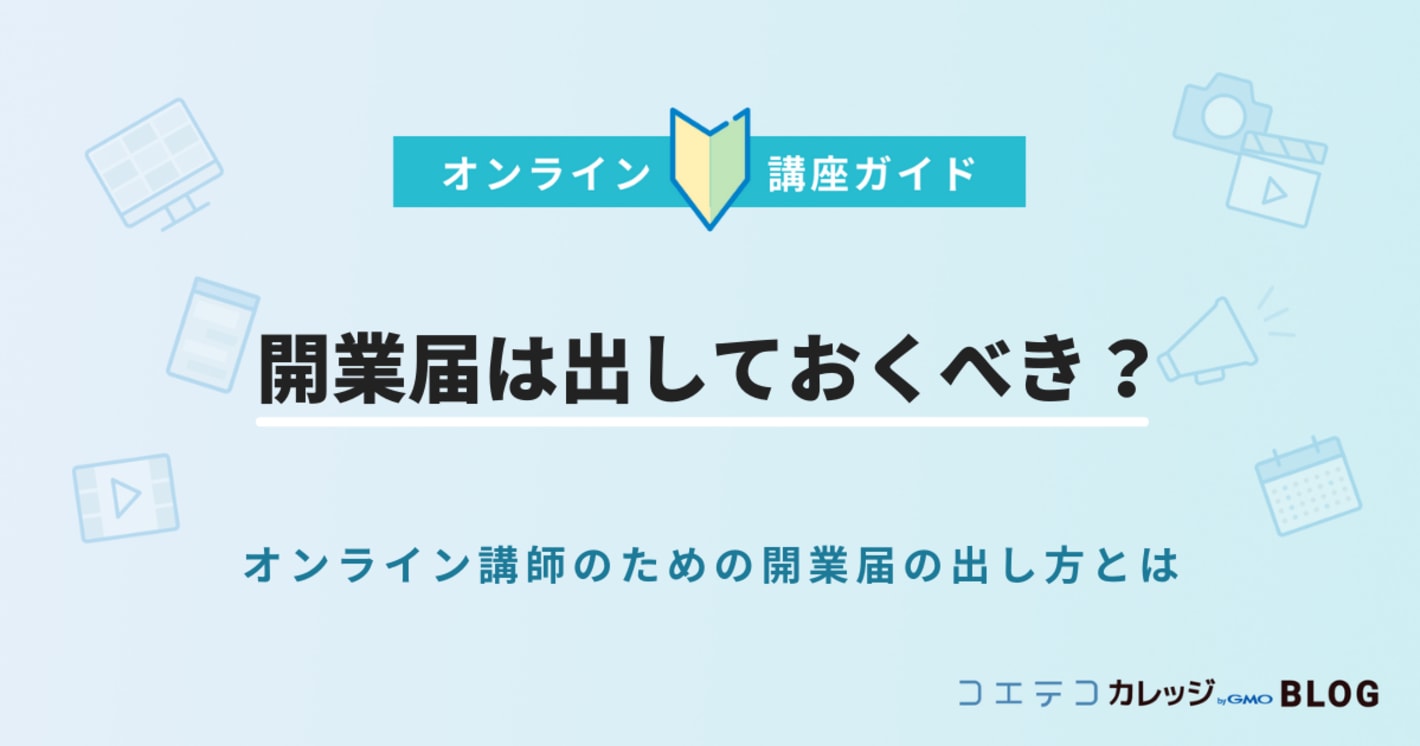
今回は、オンライン講師の方は開業届を出すメリットがあるのか、確定申告にどう関わるのか、開業届の書き方や提出方法など、詳しく調べてみました。
開業届とは
開業届とは、個人が事業を始める際に居住地の所轄税務署に届け出る書類のことで、正しくは「個人事業の開業・廃業等届出書」と言います。書類は国税庁HPからダウンロードが可能です。※参照:国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
会社員であれば所得税を給与から天引きで納めるのが一般的ですが、開業すると所得税を自分で計算し、確定申告によって納める必要があります。開業届を出すということは、税務署に対する「個人事業主として所得を報告し、所得税を納めます」という意思表示です。
ただし、確定申告が必要になるかどうかは所得によって変わります。確定申告とどう関わるの?の項を参考にしてください。
開業届の基礎知識に関しては、こちらの記事もご覧ください。
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://college.coeteco.jp/blog/archives/5516/#toc5 >
オンライン講師は開業届を出すべき?
副業でも開業届は必要
開業届を出すことは、事業を始める人にとって義務です。個人事業主やフリーランスの方だけでなく、副業を始める際も届出が必要です。出さなくても罰則はないので出さずに事業をされている人もいるようですが、開業届を出すことによってメリットも多いので、オンライン講師を始めたら開業届を出しましょう。
個人事業主として社会的に認められる
開業届を出すことで「事業を始めた証」となり、個人事業主として社会的に認められます。開業届を出すことで社会的な信用を得ているからこそ、屋号での銀行口座を開設や、補助金や助成金を申請できます。開業届と扶養や配偶者特別控除との関連は
配偶者の扶養に入り配偶者特別控除を受けられるかどうかは、所得金額によるので開業届を出す出さない、青色申告など確定申告するしないには関係ありません。ただし配偶者の会社の規定で、開業届を提出することで扶養から外され、扶養手当の支給がなくなるというケースもあるようです。扶養の範囲内で働きたい場合は、配偶者の会社の規定を事前にチェックしておきましょう。
開業届を出すメリット
青色申告で確定申告できる
確定申告には- 青色申告
- 白色申告
青色申告は、開業届と一緒に承認申請書を出すことで可能になります。青色申告の特徴として
- 所得税の控除がある
- 家族への給与を経費にできる
- 3年間赤字の繰越しが可能
確定申告する際には、青色申告にした方が良いのか、白色申告にした方が良いのかは、メリットとデメリットを考慮して決めましょう。
青色申告と白色申告について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
個人事業主として開業すると、確定申告すべきかどうか悩む人は多いでしょう。どのくらいの所得を超えたら確定申告すべきなのか、確定申告の種類はどのように選ぶのか、どのような準備が必要なのかなど、調べたり考えたりすることはたくさんあります。今回は、講師の方のために確定申告について詳しく調べてみました。
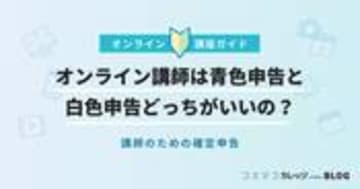
https://college.coeteco.jp/blog/archives/5879/ >
「就業」の証明に
子供を保育園に預ける際、保育が必要な理由に「親の就労」があります。就労を証明するために「就労証明書」の提出が求められますが、個人事業主の場合開業届の控えの添付を求められることがあります。開業届を出すことで、「事業をおこない就業している」という証明になります。
屋号で銀行口座を開設できる
屋号とは、国税庁によると個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。法人で言うと会社名にあたります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h27yokuaru/sosa_setsumei/nyuryokuhoho/kyotsujiko/yago.html
開業届に記入欄がありますが、必須項目ではありません。オンライン講師の場合は個人名で活動するので屋号はつけないという方も多いでしょう。
ただ、屋号を決めておくと屋号付きで銀行口座を開設できます。個人名の口座とわけて、事業用の口座を管理したい人にはおすすめです。また屋号付きの口座の方が顧客に信用を得やすい(安心感がある)ので屋号をつけたい、という方もいらっしゃいます。
補助金・助成金の申請に開業届控えの提出が条件に
個人事業主が受けられる補助金や助成金の申請時は、開業届の控えの提出を求められることがほとんどです。開業届を出すことが、実際に事業をおこなっているかどうかの証明になります。開業届を出すデメリット
開業届を出す際のデメリットはほとんどありません。開業届を記入したり提出したりする手間がかかるくらいでしょうか。ただし、開業届を出すことで
- 失業手当がもらえなくなる
- 扶養から外れる可能性がある(所得が一定額を超えた場合)
開業届を出すことでメリットは大きいので、オンライン講師を始めたいとお考えの方、まだ開業届を出していない方は、開業届を出しましょう。
確定申告とどう関わるの?
開業届と確定申告
開業届を出すと、毎年確定申告前に税務署から通知が届きます。ただし確定申告は開業届を出したら必ずやらなければいけないわけではなく、出す出さないに関わらず所得がある一定のラインを超えたらおこなう必要があります。ここでいう「所得」とは、収入(売上金)から経費を引いた残金です。オンライン講師の場合は、
1)給与所得を得ながらオンライン講師(副業)として所得を得ているか
2)フリーランスで講師業をおこない所得を得ているか
によって確定申告をおこなうべきかどうかの所得のラインが変わります。
上記1)の場合は、副業によって得られた年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
ただし給与所得を2カ所以上から得ている場合(複数アルバイトをしている場合など)は、
- 年末調整されなかった給与所得
- 副業の収入
上記2)の場合は、納税者本人の所得税の基礎控除額が48万円ですので、48万円を超えたら確定申告が必要になると覚えておきましょう。
令和7年4月1日現在法令等] 所得税 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります。 基礎控除は、納税者本人の 合計所得金額 に応じてそれぞれ次のとおりとなります。 (注1) 令和7年分の上記規定は、令和7年12月1日に施行されます。施行日前の適用関係などについては、「 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB) 」をご確認ください。 (注2) 令和7年11月30日以前に、令和7年分の所得税の死亡又は出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、令和6年分以前と同様に改正前の基礎控除の金額を適用しますので、令和7年11月30日以前に提出された準確定申告書については、令和7年12月1日以後、更正の請求により改正後の基礎控除の金額を適用することができます。 (注3) 令和7年分以後の基礎控除の金額は、居住者でない場合、58万円が最高額となります。 (注4) 令和元年分以前の基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額にかかわらず、一律38万円です。 所法86、措法41の16の2 ◆パンフレット・手引き ・ 確定申告書等の様式・手引き等 ◆各種様式 ・ 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税) ◆ 確定申告書等作成コーナー 画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。 必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、 税についての相談窓口 をご覧になって、電話相談をご利用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm >
開業届を出す前に決めておいた方が良いこと
開業届の提出の有無と確定申告は関係がありませんが、開業届を出す際には「青色申告をするかどうか」を決めておいたほうが良いでしょう。青色申告は「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、この書類を出すためには開業届を提出する必要があります。青色申告承認申請書は提出期限があり、もともと開業されている場合は原則として3月15日までに提出しなければ、翌年青色申告ができません。新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内と定められています。
青色申告承認申請書は開業届と一緒に出すこともできますし、開業届を出すときに決められない場合は開業届を出した後に提出することも可能です。提出期限が過ぎると次の確定申告で青色申告できませんので、提出時期には注意しましょう。
開業届を出すならいつ?
開業届はいつまでに出せば良いの?
提出時期は「事業を始めてから1ヶ月以内に提出」と決められています。ただ罰則がないため、事業規模が小さく確定申告の必要がないから出していない、という人もいるようです。上記の通り、確定申告は開業届を出していなくても一定の所得を超えるとおこなう必要があります。開業時に売上の見込みがわからず確定申告すべきかどうかが不明でも、開業届は1ヶ月以内に提出しましょう。
開業届を出すタイミング
Google Trendsで「開業届」を調べると、12月半ばすぎから4月頃にかけて検索件数が他の時期よりも若干増えているのがわかります。確定申告の時期になると、開業届を出した方が良いか調べる人が増えるのではないでしょうか。
開業届を書くときのポイント
届出の区分
新規の開業であれば、開業にチェックを入れて住所、氏名を記入します。所得の種類
オンライン講師であれば、所得の種類は「事業(農業)所得」です。「開業日」の考え方
法人として会社を立ち上げる場合と異なり、個人事業主には公的な「開業日」の決まりがありません。個人の考え方次第、ということになります。例えば
- 開業の準備を始めた日
- 初めて売上があがった日
- 会社を辞めた翌日
- この日に開業したい、というこだわりの日
職業欄や事業の概要はどのように書いたら良いか
職業欄と事業の概要は、決められた書き方はありません。読んでわかる書き方、一般的に使われている名称であれば特に問題はありません。講師業専門の方であれば職業欄は、講師、セミナー講師などが一般的です。教室・レッスン系の講師であれば、ハンドメイド作家、アクセサリー作家(製作者)、英語講師、ヨガインストラクターなどでも良いでしょう。
複数の職業で開業する場合は全て書くか、メインの収入を得ている職業だけでも良いようですが、確定申告する際は全ての職業を記載した方が望ましいようです。(不安があれば提出する税務署に確認してください。)
職業に変更があった場合でも、開業届の再提出や職業の申請は不要です。事業の概要は、事業内容がわかりやすく伝わればOKです。
職業によって事業税の区分が変わる
職業によって事業税の税率が変わることがあります。事業税は3〜5%に設定されており、3%はあんま・マッサージ業、指圧・はり・きゅう業など、4%は畜産業、水産業、薪炭製造業、それ以外は5%なので、講師は5%の括りに入ります。ただし所得が年間290万円以下であれば事業税の非課税対象になりますし、スポーツ選手や画家、文筆家など特定の職業の場合も非課税対象です。
職業欄の書き方で事業税率が変わることを気にされる方もいらっしゃいますが、講師の場合はあまり関係がありません。
屋号は変更できるの?
個人事業主における屋号は、法人の会社名と違い登録が必要なものではないため、後から付けることも変更することも可能です。後から付ける場合は、開業届を再度提出するか、確定申告書類に記載すれば屋号として認められます。変更する場合も同様です。
屋号付きの銀行口座開設などで書類が必要な場合でなければ、わざわざ開業届を再提出しなくても確定申告書類に記載するだけで良いでしょう。
給与等の支払の状況
ここは、自分が雇っている従業員がいなければ、記入しません。もし家族が仕事を手伝ってくれる場合、青色申告すると家族への給与は経費計上可能です。生計を共にする家族が専ら従事してくれるようであれば、「専従者」の欄に人数を記載します。家族以外は使用人欄に記入します。
「給与の定め方」は「日給」もしくは「月給」、「税額の有無」は従業員の誰か一人でも給与が月に88,000円以上になる場合は「有」にチェックして、源泉徴収しなくてはなりません。超えない場合は「無」です。
専従者がいる場合は合わせて「青色事業専従者給与に関する届出」と「給与支払事務所等の開設届出」をおこなう必要があります。使用人の場合でも給与支払事務所等の開設届出は必要です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の 提出の有無」は、給与の支給人数が10名以下の場合、所得税や復興特別所得税を年2回にまとめて納付できるという特例制度を利用するかどうかです。利用する場合は提出の有無を「有」にして、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署に届け出ます。
開業届の提出方法
必要書類
開業届の提出時に必要書類は- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告する場合は一緒に提出がおすすめ)
- マイナンバーカード
青色申告承認申請書も国税庁のホームページよりダウンロードが可能です。
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。 ※青色申告特別控除制度についてはこちらをご参照ください。 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 ...

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >
開業届に押す印鑑は認印でOKですが、スタンプ色の印鑑は使用できません。提出時に訂正箇所が見つかる場合もあるので、印鑑も一緒に持っていきましょう。
開業届の提出にかかる費用
開業届を提出する際にかかる費用はありません。無料で手続き可能です。所得税の青色申告承認申請書も同じく無料です。開業届の提出
開業届の提出方法は- 税務署に行って直接提出する
- 郵送する
- 時間外受取箱へ投函する
書類は前述の通り国税庁のホームページからダウンロードできるので、税務署で直接手続きする際もあらかじめ記入しておいてから提出した方がスムーズです。記入の仕方でわからないところがあれば、提出時に税務署で質問してから記入するか、電話で問い合わせてみてください。
郵送する際と時間外受取箱へ投函する際は
- 個人事業の開業・廃業等届出書 2部(提出用と控え)
- 所得税の青色申告承認申請書(青色申告する場合は一緒に提出がおすすめ)
- マイナンバーカードの写し
- マイナンバーカードがなければマイナンバー通知書の写しかマイナンバーがわかる書類、免許証やパスポートなど身分証明書の写し
- 開業届の控えを返送するための封筒(切手を貼り返送先の住所を記入しておくこと)

まとめ
オンライン講師に限らず、事業を始める人なら開業届を出すことをおすすめします。届出は必要書類に記入して届け出るだけですし、無料でおこなえます。この記事を参考に開業届を出す際のポイントをしっかりおさえて、スムーズに事業を始めていきましょう。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
オンライン講師は青色申告と白色申告どっちがいいの?|講師のための確定申告
個人事業主として開業すると、確定申告すべきかどうか悩む人は多いでしょう。どのくらいの所得を超えたら確定申告すべきなのか、確定申告の種類はどのように選ぶのか、どのような準備が必要なのかな...
2025.05.21|コエテコ byGMO 編集部
-
これは経費?家事按分はどうする?|オンライン講師のための経費計算
個人事業主が確定申告する際に重要になるのは、経費の考え方です。所得とは売上から経費を引いた金額のことで、経費として計上できるものは決まっており、上限額が決められているものもあります。正...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座の収入は?|増収・継続につながる講座運営のコツを解説
オンライン講座は自宅から開講できること、地域を問わず受講してもらえるメリットもあり、講師として教えられるスキルを持っていれば魅力的な働き方といえるでしょう。まずは副業で短時間からスター...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座は終わった後が肝心!講師のためのアンケートのつくり方
オンライン講座は、講座をおこなって終わりではありません。講座後にどのようなフォローがあるかでリピートされるかどうか、感想をもらってSNSなどでシェアしてもらえるかどうかが変わります。そ...
2024.04.01|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座の構成を考えよう|単発講座と連続講座それぞれのメリット・デメリット
オンライン講座の構成を決める際の重要なポイントの1つとして、どのくらいの期間でどのくらいスキルやノウハウを習得できるようにするか、という点があります。講座を単発で開催するか連続で開催す...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部