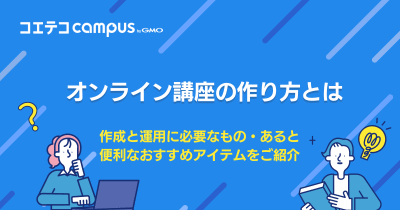オンライン講座をスムーズに開講するには|講座申し込みから、講座終了後の流れ

そこで今回はオンライン講座の開催にあたり、申し込みから講座開催までの流れを詳しくまとめてみました。
受講の流れ〜申し込みから講座開始まで〜
受講者の申し込みから受講するまでの流れは以下の通りです。
各項目について詳しく説明します。
申し込み方法①・申し込みフォームから
申し込み方法には、受講者が直接講師に申し込めるようにメールアドレスなどを表示する方法もありますが、申し込みフォームや予約管理システムを利用できるように設定した方がメリットもあり便利です。まずは申し込みフォームについてですが、講師はフォームを作成し受講者に入力してもらいます。無料で利用できるフォームも多くあります。
申し込みフォームを利用するメリット・デメリット
講師のメリット・デメリットと、受講者のメリット・デメリットにわけて見てみます。
フォームに記載した方が良い内容
申し込みフォームは、必要に応じて以下のような内容で作成しましょう。- 氏名
- 返信用の受講者アドレス
- 講座の希望日時(記入制にするかチェックボックスなどで選んでもらう)
- 複数のSNSで発信している場合はどのSNSを見て申し込んでくれたのか(今後どのSNSに力を入れたら良いか参考になる)
- メモ欄などで受講者から講師へ伝えたい内容があれば書いてもらう
- キャンセルポリシーなど利用規約があれば記述、同意を得るチェックボックスを設定
- メールマガジンを配信している場合は、メールマガジンを送信についての同意
キャンセルポリシーに関しては、消費者契約法2節9条1号の部分に、以下を超えると無効になると書かれています。
消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの平均的な損害とは講座の代金です。何日前からキャンセルポリシーを発生させるか、返金の場合の振り込み手数料はどうするかなどは、他の企業や講師等、競合相手の状況を確認して、設定しましょう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
ただしあまりにも質問が多い、記入しにくいフォームは、受講者が記入の途中で面倒になり、離脱して申し込みに至らないこともあります。受講者の立場になって記入しやすいよう記入導線をわかりやすくする、受講前にどうしても知りたい内容だけを必須にしたフォームにする、回答を選択式にして記入する際の作業負担を軽くするなど工夫しましょう。
無料で利用できるフォーム作成ツール
無料で利用できるフォーム作成ツールはいくつかあります。選ぶポイントは使いやすさもありますが、受講者の個人情報を預かることになるのでセキュリティ面、決済機能の連携や無料版でどこまで機能が使えるかなどを比較してみましょう。Googleフォームやフォームズ、オレンジフォームを例にあげるので参考にしてみてください。

申し込みの方法②・予約管理システムから
予約管理システムを利用するメリット・デメリット
こちらも講師のメリット・デメリットと、受講者のメリット・デメリットにわけて見てみます。
無料で利用できる予約管理システム
無料で利用できる予約管理システムはいくつかあります。こちらも選ぶ際にセキュリティ面のチェックはもちろん、zoom連携やフォローメールの送信などオンライン講座をおこなう上で便利な機能があるか、無料版でどこまでできるかなどチェックしましょう。RESERVA Reservation(レゼルバ予約)、STORES 予約、SELECTTYPE(セレクトタイプ)を例にあげるので、参考にしてみてください。

決済・入金管理
申し込みが完了したら、支払いのタイミングは講座受講前に設定しましょう。受講後の支払いにすると、未払いが発生することがあります。受講料の受け渡しはトラブルにつながることがあるので特に注意が必要です。講座代金は銀行振り込みにするか、PayPalなどの決済・送金リクエストサービスなどを導入し、なるべく受講者が簡単に決済できるようにしましょう。
講座参加への詳細メール・リマインドメールを送る
入金を確認したら、入金が確認できた旨と講座の詳細をメールで受講者に送りましょう。初めて講座を受講する人は、きちんと入金できているのか不安に思うこともあります。また、予約が確定した講座の日時、講座のURL、事前に用意して欲しいもの、見ておいて欲しい資料があれば資料の添付など、講座の詳細を一度メールで送ります。次に、講座の直前にリマインドメールを送りましょう。「リマインド」とは思い出させるという意味で、リマインドメールとは講座の直前にもう一度詳細な案内を送ることです。申し込みから時間が経つと忘れしまう方もいますし、覚えていてもメールを遡って探さないとオンライン受講に必要なURL等がわかりません。
講座前日か当日にリマインドメールを送ると、講座のURLなどの情報を探しやすくなり、参加しやすくなります。こうした受講者への細かな気配りはとても重要です。
終わった後こそ重要・講座を実施したら
フォローメールを送る
講座を実施したら、講座参加へのお礼のフォローメールを送りましょう。SNSのダイレクトメッセージでも良いです。まずは「ご参加ありがとうございました」とお礼を述べ、講座に関しての質問を受け付けたり可能なら感想をいただけるか聞いてみたり、受講者に対して働きかけてみましょう。講座後のフォローがあると、講座の理解度や満足度が上がります。
感想は非常に重要で、講座を受けてみたいなと思っている見込み顧客は感想をチェックし、感想が良ければ申し込みに繋がることもあります。感想をいただいたら、講師のSNSなどに掲載して良いか許可を取ってから掲載してください。
受講後アンケートに答えてもらう
講座後に感想を求める際は、受講者にフリーで書いてもらうのも良いですが、可能ならアンケートでどのように感じたか具体的に書いてもらうのもおすすめです。申し込みの動機、受講前はどんな悩みがあったか、受講後にそれが解決できたか、他の人に講座をすすめたい点など、書式を決め具体的にアンケートに書いてもらいます。
アンケートの内容から、受講者が得られた成果や他の講師との差別化、講座をどう宣伝したら良いのかが見えてきます。講座に関しての不満な点や理解できない点がわかれば、それを改善し次の講座に繋げることでより満足度の高い講座へと磨いていけます。
知り得た個人情報は公開しないなど規約を決め、承諾をいただいたうえでお願いすることが必要です。
メールマガジンやLINE公式アカウントなどで受講者と繋がる
メールマガジンやLINE公式アカウントは、プッシュ型メディアと言われメールアドレスやLINEの友だち追加で連絡先を獲得し、講師側から受講者に情報発信できます。FacebookやInstagramなどはプル型メディアと言われ、受講者の方から情報を見にきてくれるので、講師が情報を発信したタイミングで受講者に届くかどうかはコントロールできません。プッシュ型メディアを利用すると、講師の決めたタイミングで受講者に情報が届き、繋がることで既存顧客の休眠化を防ぐことができます。
申し込みフォームなどから連絡先を獲得できますが、同意なくメールマガジンを送ることはできません。フォームで同意を得ることも可能ですが、講座を通じて関係性を築いてから、メールマガジンやLINE公式アカウントを使って情報を送ってもよいか確認すると良いでしょう。
参加者が参加者を呼ぶ仕組み
講座に満足した受講者は、自分のSNSで講座の感想を投稿したり、講師に対しての思いをシェアしてくれることがあります。講座の内容に感動・共感してくれると、シェアされる確率が高くなります。この共感によるシェアは参加者が参加者を呼ぶ仕組みになり、認知の拡大に繋がります。Web集客の段階でファンになってもらうことも大切ですが、申し込みから講座後のフォローまで、気を抜かずに丁寧におこなうことで、より感動と共感を生むことができるでしょう。
講師と受講者を繋ぐサービスを利用するメリット・デメリット
講師が申し込みフォームの管理から決済の管理、受講者へのメールなど、全部自分で管理することは、かなりの時間と労力を消費します。そこで、ストアカのような講師と受講者と繋ぐサービスがあり、これらを利用するとフォームや予約管理、決済などの講師の事務的な作業負担が軽くなります。キャンセルポリシーや特商法の記述等もこうしたサービスを提供する各社が規定し、講師も受講者も確認できるようなシステムになっているので、講師が自分で設定しなくても良いのも大きなメリットです。
また、受講者のメリットとしては、講師登録に本人確認などの書類を必要とするサービスがほとんどなので、なりすましやサービス提供されないなどのトラブルに発展しにくいということがあります。他には、マンツーマンや少人数で学びたい、大勢の人と学びたいなど希望の講座のスタイルを選んだり、講師の経歴やレビューを比較したりして、検討して受講することも可能です。
講師側のデメリットとしては、全◯回などステップ式の講座を作る機能がない、サービス利用料がかかることがあげられます。
受講者側のデメリットとしては、こうしたサービスを利用する講師は個人の場合が多いので、受講できる時間帯が限られる場合があります。

ただ講師も受講生も利用するメリットは大きいので、オンライン講座を開催されるなら一度利用を検討してみると良いでしょう。
まとめ
オンラインで講座をおこなうには、ツールの他にスムーズに講座を受講できるような仕組みも必要です。申し込みからトラブルなく講座を終了できるよう、受講者のためになる心配りも惜しまないようにしましょう。受講者の立場に立って利用しやすい環境を作ることが、次の参加へ繋がります。この記事を参考に、受講者が利用しやすい仕組みを整えてください。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
オンライン講座を始めよう|コエテコカレッジで講師登録してみた
コエテコカレッジでは、講師登録をすると講座をスムーズに運営できるような機能があります。講座への申し込みから⽀払い、受講⽣へのリマインドメールなど便利な機能を利⽤でき、連続講座や動画販売...
2024.04.17|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座を盛り上げよう|スムーズで満足度の高い講座を開催するには
オンライン化が定着した現代では、オンラインでの講座やワークショップが一般的になりました。対面講座も復活していますが、オンラインは会場の確保不要や、受講者の場所を選ばない利便性で引き続き...
2024.08.29|コエテコ byGMO 編集部
-
Webセミナーはつかみが肝心?聞く人の心を掴む話し方のコツ
Webセミナーは多くの人が自宅などリラックスできる環境で参加できるメリットがありますが、反面メッセージの通知が来たり宅配便が来たり、気が散りやすい環境でもあります。対面のセミナーよりも...
2024.04.01|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座の構成を考えよう|単発講座と連続講座それぞれのメリット・デメリット
オンライン講座の構成を決める際の重要なポイントの1つとして、どのくらいの期間でどのくらいスキルやノウハウを習得できるようにするか、という点があります。講座を単発で開催するか連続で開催す...
2024.04.01|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座の作り方とは|作成と運用に必要なもの・あると便利なおすすめアイテムをご紹介
コロナ禍からの非対面サービスの需要増大に伴い、どのような業種もオンライン化が急速に進み定着しました。特に、オンライン講座は今や多くの人々にとって身近な学びの手段となっており、端末さえあ...
2024.09.03|コエテコ byGMO 編集部