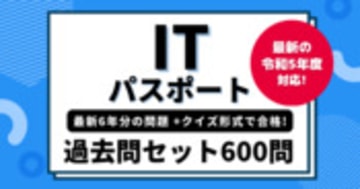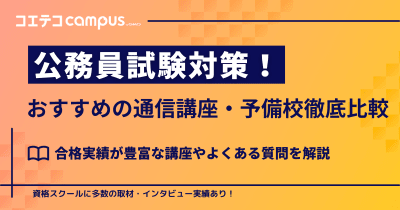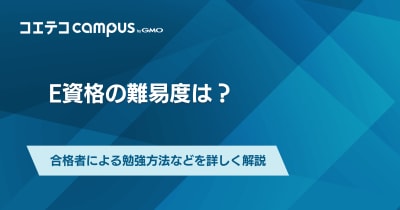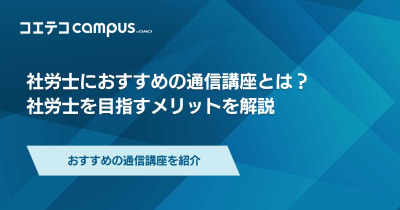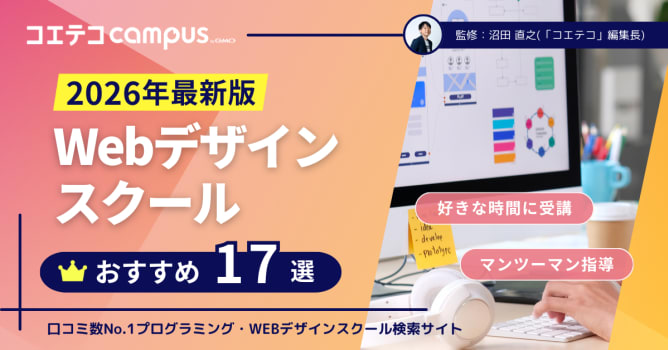ICT支援員とは | 先生の教育現場でのICT活用をしっかりサポート
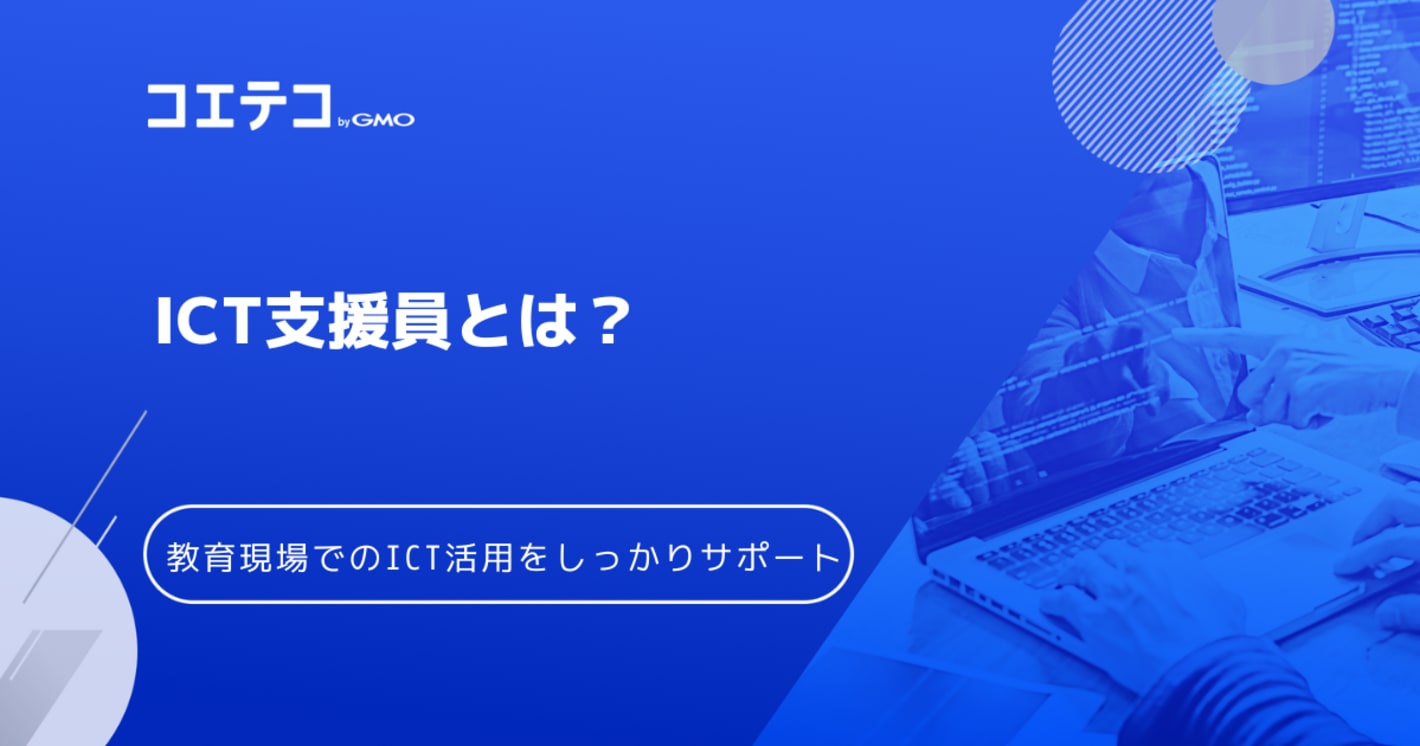
GIGAスクール構想で注目されているICT(情報通信技術)支援員も、新たに登場した職種です。いまや公立小・中学校でも児童一人に1台の端末が用意され、学校教育でのICT活用のニーズは高まっています。
この記事では、ICT支援員の仕事内容、将来性、やりがいや待遇、ICT支援員を目指す際に有利になる資格や知っておきたい事柄などを、紹介します。
ICT支援員とは
ICT支援員の仕事内容
ICT支援員とは、教員がICTを活用できるように支援する外部人材をいいます。市町村の教育委員会が各学校にICT支援員を配置し、私立学校はそれぞれでICT支援員を採用します。ICTはInformation & Communications Technologyの略で、情報通信技術のことです。ICTには、技術だけでなく、教育や医療での活用、インターネット検索やインターネット通販、SNSなど、使い方やサービス、コミュニケーションまでが含まれています。
2021年8月、学校教育法施行規則の一部改正により、ICT支援員は新たに「情報通信技術支援員」と名づけられ、職務内容が規定されました(本記事では一般に流通している「ICT支援員」の呼称を使用)。
ICT支援員は授業支援、校内研修関連、環境整備関連、校務支援など、学校でICTを活用するさまざまな場面で活動しています。ICT支援員の業務内容は教育委員会や学校によって異なりますが、一般的な業務例を紹介しましょう。
ICT支援員の業務例
- 授業中の教員の補助やトラブル対応
- 授業前に、電子黒板やタブレット端末などの機器の動作確認
- 教材作成へのアドバイス
- より教育効果を高めるためのICT機器の活用策を提案
- 教員向けにICT機器使用マニュアルを作成
- 学校紹介のウェブサイトの更新支援
- 校内文書の作成支援
- 校務システムの操作支援
ICT支援員の将来性
全ての学校がICT支援員による支援を受けられるように、文部科学省は4校で1名のICT支援員の配置を推進しています。しかし、実際のICT支援員の配置状況は、都道府県・市町村のどちらでも半数に達しておらず(※)、ICT支援員は今後も需要が大きい職業といえるでしょう。※文部科学省「令和2年度 小・中・高等学校を通じた情報教育強化事業(情報教育指導充実事業)『ICT支援員の配置促進に関する調査研究』」より
GIGAスクール構想により、児童に1台ずつパソコンやタブレットが用意されました。2019年12月に文部科学省が打ち出したGIGAスクール構想では、校内通信ネットワークと児童生徒に一人1台端末を整備して教育ICT環境の充実を目指しています。当初の整備目標は2023年度中でしたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により自宅学習のニーズが高まり、整備目標が2020年度中に前倒しされました。このGIGAスクール構想からも、ICT支援員の需要はこれからも拡大し続けることが見込まれます。
また、学校教育法施行規則の改正でICT支援員の職務内容が教員業務支援員(スクール・サポート・スタッフ)や医療的ケア看護職員、特別支援教育支援員とともに規定され、法的根拠を与えられたことにより、その地位確立も期待されています。
ICT支援員のやりがいと待遇
ICT支援員の支援対象は教員ですが、子どもとのやり取りは頻繁にあります。ICT支援員認定試験に合格するまでの体験を発信しているictsupporterさんは、ICT支援員のやりがいを、このように説明しています。
ICT支援員の給与・福利厚生は現在それほど高くないだろうが、この仕事にはやりがいがある。私も授業に入って小さな子をサポートしたときに言われた「ありがとう」の一言がとてもうれしかった。ICT支援員は、子育て中のママに魅力的な側面があります。昔からママに人気だった給食調理員のように、ICT支援員は仕事場が学校のため、休日が子どもと同じタイミングになることです。
https://ictsupporter.hatenablog.com/entry/2021/07/09/210748
ICT支援員の仕事場は学校なので、子育てや学校行事に職場からの理解が得られやすく、子どもの授業参観などに合わせて働く日を調整しやすい点も人気の理由です。
ICT支援員の採用方法は市町村によって異なり、大学生や元教員が活躍したり、ハローワークを通して募集したり、教育関連企業へ委託したりと、さまざまなケースがあります。
待遇も市町村によって異なります。市町村の教育委員会が雇用する場合は、いわゆるフルタイムの正職員はほとんどいません。業務を委託された企業でも、正社員、派遣社員やパートなど雇用形態はさまざまです。給与体系も年収、月給、時給といろいろあります。
現状では全てのICT支援員が恵まれた待遇とは言いがたいですが、ニーズは急上昇していますので今後の待遇改善を期待しましょう。
他の職種・資格との違い
ICT支援員のように、学校教育でのICT活用を支援する職種について文部科学省は以下のように紹介しています。ICT活用教育アドバイザー
国から教育委員会へ手配される職種が、ICT活用教育アドバイザーです。学校における教育の情報化に向けて専門的な知見から、情報化に関するビジョンや学校におけるICT環境整備、ICT活用に関する研修支援などを支援・アドバイスします。GIGAスクールサポーター
ICT活用のための環境整備の初期対応のために、国の補助金等を活用しながら教育委員会が配置するのが、GIGAスクールサポーターです。ICT環境整備の設計、工事・納品における事業者対応、端末等の使用マニュアル・ルールの作成などを行います。
トップ > 教育 > 小学校、中学校、高等学校 > 教育の情報化の推進 > 教育の情報化に関する外部人材 > GIGAスクールサポーターについて

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_01007.html >
教育情報化コーディネータ
学校でのICT活用を推進するための資格に、 教育情報化コーディネータがあります。この資格は教育化コーディネータ検定試験に合格すると得られるもので、ICT支援員能力認定試験も実施している教育情報化コーディネータ認定委員会が実施しています。ICT支援員としての能力や適性を評価するICT支援員能力認定試験については、詳細はのちほど紹介します。ICT支援員は教育委員会から各学校に配置されますが、教育情報化コーディネータは学校現場でICTを活用するために教育委員会を支援する人材を認定する制度です。
教育現場で実際にICTを活用するためには、ICTの活用方法をデザインしなくてはなりません。例えば電子黒板やタブレット端末などのICT機器を各学校に導入する際には、業者とのやり取りや、導入してからの管理・メンテナンスの仕組みづくりのような多くの工程があります。導入製品の選定、保管場所や電源の供給場所の決定、ソフトウェアの更新方法など、素人が一から考えることは難しいですし、非効率です。
学校現場でICT活用がスムーズに行われるように、教育委員会にアドバイスを行うのが教育情報化コーディネータです。
教育情報化コーディネータは「Information Technology Coordinator for Education」を略して、「ITCE」とも呼ばれます。教育情報化コーディネータ検定試験の難易度は、1・2・3級の3レベルです。1級は、国や都道府県レベルの長期的な計画を 設計・助言できる指導者レベルとされ、1級認定者は全国で7名います(2022年5月現在)。
以下の「ITCE 教育情報化コーディネータ検定試験・ICT支援員能力認定試験公式サイト」右上の「教育情報化コーディネータ」をクリックすると、試験の概要が表示されます。
教育情報化コーディネータ(ITCE)検定試験は、学校や高等教育機関など教育の情報化をコーディネートできる人材を認定する制度です。

https://jnk4.info/itce/aboutTEST.html >
ICT支援員になるには
ICT支援員になるために必須の資格はありませんが、採用されるために役に立つ資格や、参考になる情報を紹介します。ICT支援員能力認定試験について
ICT支援員としての能力や適性を評価するため、ICT支援員能力認定試験が2013年から始まりました。採用条件に、ICT支援員能力認定試験の合格が課せられていることも多いので、 ICT支援員を目指すなら取得しましょう。
教育情報化コーディネータ(ITCE)検定試験は、学校や高等教育機関など教育の情報化をコーディネートできる人材を認定する制度です。

https://jnk4.info/itce/aboutTEST.html >
ICT支援員能力認定試験の概要
ICT支援員認定試験は年2回、例年6月頃と11月頃にA領域とB領域の2領域の試験が行われます。A領域は、ICTの扱いに関する実践知識が36問90分のCBT方式で問われます。
B領域は、教育現場でのコミュニケーション力に関する問題分析と説明力が求められる内容です。インターネットで問題が送られてきて、自宅や職場で自撮りした説明映像を課題提示日を含めて5日以内に提出するユニークなスタイルです。
学歴や職歴などの受験資格は必要ありませんので、独学で受験することができます。過去の試験問題、高得点回答例や模範解答は公開されていませんが、問題例や評価の観点の参考情報がICT支援員能力認定試験のウェブサイトのFAQコーナーで紹介されていますので、受験勉強に役立ててください。
ICT支援員上級認定試験
ICT支援員の上級資格として、実績面、能力面で特に優秀と認められた方を認定するICT支援員上級認定試験があります。受験するには、以下の2つの条件を満たさなくてはなりません。
①ICT支援員認定試験で、A領域、B領域の両領域ともに高得点で合格していること
(4年間有効。ICT支援員認定試験に合格したときに資格を満たしていることが本人に通知されます。)
②教育現場等のICT支援に関連する実務経験が2年以上あること
ICT支援員上級認定試験は、問題解決・コミュニケーション能力に関するC領域について、課題提出と面接・口頭試問が行われます。これに合格するとICT支援員上級と認定されます。試験の実施時期は毎年2月~3月上旬頃です。
ICT支援員になるために、参考になる資料や資格
ICT支援員は歴史が浅く、ICT支援員能力認定試験の過去問も公開されていないので、ICT支援員としての知識やスキルを身につける教材探しに多くの人が苦労しています。数は少ないながらも参考となる書籍などをご紹介します。ICT支援員能力認定試験の公式サイトが参考書籍としておすすめしているのが、ICT支援員の養成に関する調査研究委員会がまとめた「ICT支援員 ハンドブック」(PDF)と、日本標準から出版されている「学校のICT活用・GIGAスクール構想を支える ICT支援員」です。
また、日本教育情報化振興会による「先生と教育行政のためのICT教育環境整備ハンドブック」では、授業や校務でのICT活用や情報セキュリティ、レンタル・リース、予算確保など幅広い内容が紹介されています。以下のリンクから最新のものをダウンロードしましょう。
https://www.japet.or.jp/publications/ict-handbook-2021/ >
このほか、ICT支援員として活躍するための参考になる知識が身につく資格として、ITパスポート(iパス)があります。ICT支援員の求人へ応募する際にも、iパスはアピール材料になるでしょう。
iパスとは、ITに関する基礎的な知識があることの証明になる国家資格で、社会人だけでなく、これから社会人を目指す学生も多く受験しています。iパスはストラテジ系(経営全般)、マネジメント系(IT管理)、テクノロジ系(IT技術)の3つの分野を、CBT方式で問われます。
合格証書の氏名において、利用者登録時に使用できなかった漢字に変更を希望する場合は、漢字表記変更の申請をしてください。試験実施日によって申請期間が異なります。2025年9月実施分の試験を受けた方は、10月15日(合格発表日)12時~10月18日(合格発表日から3日後)の23時59分、2025年10月実施分の試験を受けた方は、11月1日12時~11月4日23時59分、2025年11月実施分以降の...

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html >

まとめ
社会の変化は学校教育にも影響を与え、教育現場ではICTのより効果的な活用が求められています。ICT支援員のニーズは急速に拡大しており、今後さらなる待遇改善も期待できます。学校教育におけるICT活用を後押しするICT支援員は、未来を担う子どもたちを育てる役割の一端を担い、社会に貢献する仕事といえます。さらに、ICT支援員に求められる知識と技術は、自分自身の仕事や生活も豊かにしてくれるでしょう。あなたもICT支援員を目指してみませんか。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
ICT支援員・教育情報化コーディネータになるには|概要と資格について
コロナ禍の後押しもあって、学校教育のさまざまな場面で一人一人の児童にタブレットの配布など、ICTの活用が進んでいます。デジタル教科書の市場規模も、2019年度は30億円から6年後の20...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
公務員通信講座・予備校おすすめ7選を徹底比較【2026年最新版】
本記事では、公務員試験対策に定評のある通信講座・予備校を徹底比較し、あなたに最適な講座の選び方を解説します。 学習スタイル、目指す職種、予算、サポート体制など、選ぶ際に重視すべき...
2026.02.11|コエテコ byGMO 編集部
-
宅建通信講座・予備校おすすめランキング3選!わかりやすくて安い講座を厳選紹介
不動産の取引において、売買・仲介を行うには「宅建」の資格が必要になります。大きな会社であれば、各事務所の従業員の5人に1人の割合で「宅建士を置くこと」が義務付けられているので、宅建士の...
2025.12.31|コエテコ byGMO 編集部
-
E資格の難易度は?合格者による勉強方法などを詳しく解説
企業におけるDX化の推進などに伴って、AIやディープラーニングの知識の必要性が高まっており、これらの開発知識があることを証明する資格、JDLAのE資格(エンジニア資格)に注目が集まって...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
社労士通信講座・予備校おすすめ9選を徹底比較【2026年最新】
社労士は、会社で働く従業員の労働・社会保険に関する相談・代行などの業務を行う仕事のこと。 社労士の試験は難問と言われているので、独学で行うより「通信講座」などで効率よく勉強するのがお...
2026.02.12|コエテコ byGMO 編集部