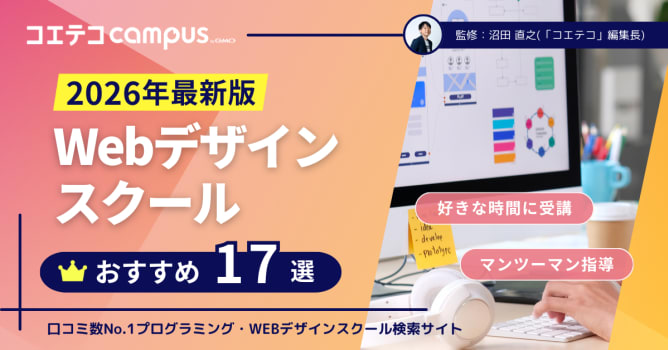オンライン講座の作り方!セミナーにも使える構成方法も徹底解説

今回は、スキルやノウハウを習得しやすく、満足度が高いリピートされるオンライン講座を作成するにはどうしたら良いのか、受講しやすい講座構成をテーマにお伝えしていきます。
講座の構成をどうするか
同業他社、ライバルを競合分析する
自分と同種の講座を開催している講師を自分と比較しながら詳しく見てみると、ヒントがたくさん得られます。教えているジャンルが違っても、構成が上手な講座は参考になります。特に、大勢の受講生を集めて回数多く講座を開催している講師が、
- どのような人をターゲットにしているか
- どんなツールでオンラインセミナーや動画配信をしているか
- どんなコミュニティを作っているか
- どのように集客しているか…など
最近はSNS集客の方法も変わってきており、FacebookやInstagramでの情報発信をはじめ、メルマガや公式LINEを使ったリストマーケティング、YouTubeやTikTokを使った動画マーケティングなどPR方法は様々です。
人気の講師がどんな媒体を使って情報発信しているかも、ぜひチェックしてみてください。
受講する対象者について研究する
講座を作成する際は、はじめにどのような人に受講してもらいたいか、ターゲット(受講者)を考えます。例えば、
- お料理やパン教室は主婦向けだけでなく、学生や男性向けもあり
- ヨガやピラティスは、ダイエットをしている人、健康になりたい人
- アンガーマネジメント、マインドフルネス、コーチングなどのセミナーは、ストレスを抱えている人やメンタルの状態を整えたい人
- ピアノなど楽器のレッスンは子供や学生、大人なら趣味で習いたい人
- ビジネス系の講座は、起業している人(個人事業主)、これから起業したい人
- パソコンやITスキルを学びたい、転職や就職希望の人
- 経営戦略を学ぶ講座は、経営者 …など
男性か、女性か、仕事をしている人か、個人事業主か、主婦や子育て中の人か…、といった性別、仕事、ライフスタイルなどを具体的に考えてみてください。
また、ターゲットが望むのは初心者向けなのか、上級者向けなのかも考えてみましょう。
例えば同じ料理系の講座でも、簡単に作りたい、品数を増やしたいので多くの時短レシピを知りたい、プロ向けのレシピでワンランク上を目指したいなど、自分がターゲットにしたい人が何を望むかによって講座の内容、到達点、講座の時間帯などが決まってきます。
受講者の到達点をどう考えるか?(講座のゴールはどこか)
次に講座を受けた受講者の、受講後の理想的な姿を考えてみます。ターゲットが講座を受講する動機や目的を想像してみてください。そこから具体的に考えます。- 1回の受講でどのくらいのスキルやノウハウを習得しているか
- 1回の講座時間はどのくらいが妥当か(何分で内容を習得できるようにするか)
- ステップアップしながらスキル習得を目指すか、繰り返し同じレッスンをおこなうか
- そのスキルやノウハウを習得すると、どのようなメリットがあるのか(最終的に受講者も講師になれる等)
この到達点の設定はとても重要で、「1回の受講でこんなにスキルが学べてメリットが多い!」と思ってもらうことが講座の受講や継続率、リピート率に影響します。
例えば、講座時間が長すぎると離脱に繋がることもありますし、ステップアップや繰り返し受講が必要ならサブスクリプション型の講座構成にするなど、構成にも影響します。
講座のゴールまでいったら受講者にはどのようなメリットがあるのかを明確にすることが大切です。ここを伝えていくことが、講座のPR活動に欠かせません。その上で構成をどうするのか考えます。
【到達点の設定例】
例1)
■教えるノウハウ:Webデザイン
■ターゲット:これから起業したい、仕事から離れてしまった主婦
→講座の到達点は、webデザイナーとして起業すること
→1回の受講は、主婦が無理なく受講できるよう1時間程度にする
→1時間で何かしらの制作物を作る
→ステップアップしながら学べるよう、全12回にする(毎週決まった時間に開催するか、動画受講を選べるようにする)
→Webデザインだけでなく、起業するのに必要なビジネスのノウハウも学べる
例2)
■教えるノウハウ:Webデザイン
■ターゲット:副業したい会社員、スキルアップを目指す会社員
→講座の到達点はWebデザインを副業としてできるようになること
→忙しい会社員でも受講しやすいよう、土日にまとまった時間を確保して受講してもらうか平日夜の時間帯に回数を分けて受講してもらう
→1回の受講で制作物を複数作り、添削してフィードバックまで完了する
→動画受講にすると忙しいのに時間を割いてまで勉強したい意欲の継続が難しいため、動画販売ではなくあえてライブ型の講座を開催することがメリットになる
同じノウハウで2つ例を挙げてみましたが、このような事例で考えていくと良いでしょう。同じノウハウを教えるにしてもターゲットによって目的も到達点も違うため、ターゲットと到達点は連動して考えてください。
例1のように主婦の方がターゲットになるなら、講座の開催時間は平日の日中や朝活のように早朝の時間帯、もしくは都合のいい時間に受講できることが望ましいでしょう。ライフスタイルに合わせた受講スタイルにする必要があります。
例2のように会社員がターゲットなら、忙しい中で時間を割く必要があるため、学ぶモチベーションを維持し離脱を防ぐことを考えることが重要です。ライブ型のオンライン講座で受講生同士が交流できるようにすると、一緒に学ぶ仲間がいるだけでモチベーションの維持がしやすくなることもあります。この場合、「志が高い仲間に出会える」など受講者同士の交流があることをメリットとしてPRするのがおすすめです。
挙げたのはほんの一例ですので、ご自身の持つスキルやノウハウ、経験をもとに具体的に考えてみてください。
具体的な構成を考える
到達点を決めたら、具体的な構成を考えます。最初に講座の目的や難易度、受講後にどのようになっているかを説明すると、わかりやすいです。目次のスライドを作って内容を最初に説明する、大まかなステージごとに、講座の最終段階までの到達点を説明すると不安なく受講できるでしょう。
講座の内容は提供するスキルやノウハウによって違いますが、先ほどの項で考えたゴールに到達できるように構成します。
英会話やヨガなど繰り返しレッスンを受ける必要があるレッスン系の講座や、入門編、応用編があるIT系の講座のようなステップアップしながら進んでいく講座は、最後に次の講座の内容を簡単に説明する、次のステップの一部を体験するなど次に繋げるような内容を最後に入れると良いでしょう。
単発で終わるセミナーでも、感想や気づきをシェアする時間を設けるのはおすすめです。次の講座の盛り上げ方の項も参考にしてください。
また講座やレッスンの内容によって、形態(マンツーマンで講座を開催するか、何人かのグループで開催するか)が変わることもあります。
例えばボイストレーニングや英会話、ピアノレッスンなどは、一人で受講した方が習得しやすいでしょう。一方でビジネス系のノウハウやコンサルティングなど、多くの人の意見やアイデアを聞く形式の方が内容を理解し習得しやすい講座もあります。プライバシーの問題も考慮して、講座の形態を決めてください。
講座の盛り上げ方
内容が決まったら、講座を盛り上げるようなコツを取り入れる工夫を考えてみましょう。例えば、
- 自己紹介タイムを設ける
- アイスブレイク(最初に場が和むような世間話などの会話)を入れる
- チャットやホワイトボード機能を使い、受講者の積極的な参加を促す
- 質問タイム、感想をシェアする時間を設けて、受講者にも発言してもらう
自己紹介タイムも、単純に名前を言ってもらうだけでなく、
- 講座に参加したきっかけや今どんなことに困っているか(講座中に話題として取り上げられる)
- 出身地や居住地(その後のアイスブレイクの話題になる)
- 講座で得たいこと(講師が設定したゴールと参加者のゴールがズレていないか確認できる)
詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
また、話し方や伝え方については、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:話し方・伝え方 | 正しくスムーズにメッセージを伝えるコツをつかもう
講座開設には何が必要?
オンライン講座や動画配信に必要な機材・ツール
講座の構成が決まったら、- ライブ講座(オンラインのセミナーにリアルで参加するインタラクティブ:双方向コミュニケーション型)
- オンデマンド講座・通信講座(好きな時に動画をみて学ぶ動画配信:eラーニング型)
ライブ講座であれば、Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなどのオンラインミーティングサービスは必須ですし、動画配信型であればYouTubeや有料のvimeoなどの動画をアップロードするツールや、動画編集ソフトなどが必要になります。
また、ライブ講座で録画しておいたものを後日販売や復習用として受講生に共有する場合、オンラインミーティングサービスによって録画方法や動画の保存先が変わるので、その辺りも確認しておきましょう。
YouTubeは無料で利用できますが、商用利用が厳しく定義されているので注意が必要ですし、限定公開は受講者側の動画の再生リストに入っていると受講者以外の人も見ることが可能になってしまうので、利用する際は慎重にしてください。
その他、webカメラや三脚、マイク、ヘッドセット、照明などは、必要に応じて準備しましょう。
こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:オンライン講座を始めるのに何が必要?|必要なもの・あると便利なアイテムをご紹介
講座の種類に合わせたプラットフォーム
有料講座・無料講座、単発講座・継続講座、動画講座+小テストなど、講座の種類は講師によって様々です。有料講座なら決済機能必須ですし、動画販売するようなら動画のアップロードも必要です。これらを全て自分で管理し、受講生がわかりやすく申し込みしやすいようにするには、講座作成に必要な機能が揃っているプラットフォームの利用がおすすめです。
代表的な日本のプラットフォームには
- コエテコカレッジ
- ストアカ
- ココナラ
それぞれ特徴があり、メリット・デメリットがあるので、利用料や機能をじっくりと比較して選んでください。
それぞれの機能の違いとして、
- 本人確認の有無
- 講座作成後、公開前に申請が必要かどうか
- 集客機能の有無
- 決済時に差し引かれる利用手数料の割合(%)
- 講師のランク付け(バッジ機能)
- 月額サービスの販売が可能かどうか
- 無料講座作成機能の有無
- 複数の受講生に開講できるか
- 受講者の管理がどこまでできるか(講座の進捗確認やLINEからの連絡機能、コミュニティを利用した相互コミュニケーションなど)
- AIを使った講座の要約や販売までのスケジュール管理
日本だけでなく、TeachableやKAJABIといった海外のオンライン講座構築プラットフォームは機能が充実しているものが数多くあります。
機能やメリット・デメリットの比較はこちらの記事を参考にしてください。
関連記事:オンライン講座を開講するならどこ?|ストアカ・ココナラ・Teachable・KAJABIとコエテコカレッジを⽐較してみた
受講料の価格設定と支払い方法、キャンセルポリシーの設定
講座の構成、具体的に教える内容等ができたら、受講料を設定します。初めは同業の講師の価格をリサーチして参考にすると良いでしょう。次に、オンラインで申し込みから決済まで完結するよう、決済機能があるツールを使って申し込みから支払いの設定を行います。
対面で直接集金するのと違い顔の見えないオンラインでのやりとりは信頼関係を築きにくく、金銭トラブルに発展しかねません。
こちらの記事も参考にしてください。
関連記事:オンライン講座をトラブルなく開催しよう|困ったときのトラブル対応
受講前に受講料を振り込んでもらう、キャンセルポリシーを設定するなど、予めルールを決めておくのがおすすめです。ただ、講座運営で忙しい講師自身が受講料の管理まで全ておこなうのは、かなりの労力がかかります。
前述のような講座運営を一括で管理できるプラットフォームを利用すれば、申し込みと同時に決済まで完結する、現金振込だけでなくカード決済が使えるなど、受講生側にも支払いが簡単になるメリットがあります。
さらに決済以外の機能も充実しており、申し込み時の自動返信メールやキャンセルポリシーの設定なども容易にできるプラットフォームもあるので、自分に必要な機能が何かを見極めて選ぶことをおすすめします。
自分でツールを使うのが苦手な人は作成代行の利用もアリ
海外の学習用プラットフォームには日本語対応していないものや、日本語対応していても海外のツールでは使いにくいものもありますので、「ツール名 作成代行」で検索すると代行してくれる人が見つかることも。日本のプラットフォームでも、出品用の説明文作成代行など調べると出てくることがあるので、自分でツールを使うのが苦手な方は作成代行の利用も検討してみてください。
受講者が参加しやすい・リピートされる講座にするには
講座の具体的な構成や開催に必要なツールの選定・レジュメができたら、どのようにしたら受講生が参加しやすいのかも工夫してみましょう。講座の時間帯を工夫する
受講者が参加しやすい講座にする工夫の1つに、講座の時間帯をターゲットが受講しやすい時間帯に設定する、ということがあります。- 主婦向けなら平日の日中、早朝、子供が寝てからの時間帯
- 働いている人向けなら平日の夜、土日などの休日、早朝、お昼休みなどの休憩時間帯
- ピアノなど音の出るレッスンは夜の時間帯を避ける
1回の講座でどのくらいの時間をかけるのかも重要です。小さい子供がいる主婦向けであれば長時間の受講が難しいでしょうし、会社員の方が対象ならこまめに受講するよりは休みの日にまとめて受講してしまった方が楽だと感じる方もいるでしょう。
ターゲットのライフスタイルを想像し、寄り添いながら講座を開催することが大切です。
講座の難易度を変える
初めて受講する方向けとリピーターの方で内容の難易度を変えることも、参加しやすく再受講者が増える工夫になります。【初心者向けの例】
最初から道具や特別な材料を揃えなくても、家にあるような道具や材料で出来るようにする。- おうちにある材料で簡単にできるパン教室
- 〇〇さえ買えば作れる石鹸教室 など
お試しで講座時間を短くし、簡単に取り組めるような内容にする。
- ヨガやピラティスの初級編
- 日常で活かせる簡単な生け花
- 15分で学べる簡単ビジネス英会話 など
このように、受講者が気軽に参加できるような工夫があると、新規のお客様にアピールしやすくなります。
一方で、リピーターの方は一度受講しているので雰囲気や講座の進め方を理解されています。
【リピーター向けの例】
ある程度道具を持っているのがわかっている、スキルが多少あることがわかっているなら- 初回よりも難しいパンにチャレンジする
- ある程度道具が必要な石鹸作り
- ヨガやピラティス、英会話は時間を長めに設けて内容を充実させる
講座に必要な材料・道具を講師が揃えて送る
普段家にあるような材料でできないレッスン(生花で作るフラワーアレンジメント、焼き型が必要なお菓子作りなど)は、受講者に材料や道具を揃えてもらう必要があります。その場合は、講師が材料や道具を手配して受講者に送るという方法もあります。どの受講者も同じ材料や道具でレッスンに参加でき、制作物の仕上がりにばらつきが少なくなり、受講者も参加しやすくなります。
送る材料や道具の代金や送料は、
- 講座代に含める
- 実費で別途お金をいただく
難易度によって講座の価格を決める
講座の難易度によって価格を変える方法もあります。難易度が上がるに連れて提供するスキルやノウハウが高度になり、講習時間が長くなるなど講師に負担がかかることも。初級、中級、上級のように難易度を変えて講座を開催する場合は、講義時間や負担も考慮して価格を設定すると良いでしょう。前述のように初級者向けは参加しやすいよう価格も抑えて設定すると、新規集客に繋がります。ただし、価格はターゲット(受講者)によって参加しやすい価格帯もあるので、同業の競合がどのような価格設定にしているのか、チェックしてみると良いでしょう。
割引制度を設ける
講座の価格に、割引制度を設けるのもおすすめです。以下、例を挙げてみます。【初回割引】
初めて受講する場合は、まずは試してみたいという方も多くいらっしゃいます。そのため講座の内容は同じでも初回限定の割引制度や、初回は講座自体の難易度を下げ、お試しで受講できるようにして価格も抑えるなど、初回割引制度を設けるのもおすすめです。【再受講の方対象の割引】
逆に、リピーターを獲得するために、決めた期間内に別の講座やステップアップ講座に申し込んだ方対象の割引制度や、再受講の方限定で割引価格にされる講師の方もいらっしゃいます。【紹介キャンペーン、紹介割引】
紹介キャンペーンで受講者からの紹介で新規の受講者に割引クーポンを発行する方法もあります。また、紹介した人、された人双方にメリットがあるような割引制度を設けると、新規の申し込みもリピーターも獲得しやすくなるでしょう。できるだけ新規集客を行いたい場合は初回割引を導入し、新規のお申し込みは多いけどなかなか次に繋がらない場合は再受講時に割引するなど、状況に応じて検討してみてください。
この他、早期割引(早めに申し込んだ方対象の割引)やリピーター割引、サブスクリプション型の講座なら初回から◯回目まで使えるクーポンの発行など、講座のターゲットが「これなら参加したい、リピートしたい」と受講するハードルが下がるような割引制度を導入するのがおすすめでず。
価格帯の違う講座を複数開催する、割引制度を設ける際の注意点
価格帯の違う講座を複数開催したり、割引制度を設けて細かく受講料を設定したりすると、請求間違いや誤入金の原因になることがあるので注意が必要です。例えば、受講生毎に割引適用金額が違う場合はメールの返信時に金額を訂正して送るなど、受講生が少ないうちは講師自身が管理できたとしても、忙しくなって請求漏れなど見落としがあるとトラブルの元になります。
オンライン講座プラットフォームを利用すれば、
- 講座作成時に講座毎の金額設定が可能
- 割引設定やクーポン発行が簡単にできる
- 割引後の金額を反映させた自動返信メールの設定が簡単にできる
また、過度な割引は「割引でお得感を出すためにわざと最初の価格を高くしている」「割引前の価格で他の講師の講座と比べると、その値段の価値がないのでは」と信用を失いかねませんし、講座の価格が低価格になると価格競争が激化して講座運営の継続が難しくなります。
あくまで、割引は「受講者が申し込むハードルを少し下げる」のが目的ですので、「割引ありきで、申し込んでもらうことに注力しすぎる」結果にならないようにしましょう。
まとめ
受講者が楽しみながらスキルを習得できるよう講座を構成し、ブラッシュアップしていくことは非常に重要なことです。実際に講座を開催してみて、受講者の反応を見ながら徐々に内容を変えていけば良いので、最初から完璧に作り込む必要はありません。開催しながら慣れてくるとわかることが多く、それが講師としての成長と成功に繋がるので、まずは始めてみましょう。
参加しやすくリピートされる講座にするには、アフターフォローも大切です。アフターフォローに関しては、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:オンライン講座はアフターフォローが大切|顧客のリピートとシェアの仕組みを整えよう
講師登録の方法はこちらを参照↓↓↓
関連記事:オンライン講座を始めよう|コエテコカレッジで講 師登録してみた
◆オンライン講座プラットフォームや講座作成に関連する記事
- オンライン講座プラットフォームとは?選び方を徹底解説!eラーニングシステムとの違い
- 動画レッスンの作成は難しい?準備と手順・ポイントを詳しくご紹介!
- オンライン講座を開講するなら国内サービスor海外サービス?|Teachable・Thinkific・コエテコカレッジの料金・機能を比較してみた
- LMSは動画教材の販売に向いている?選ぶポイントとおすすめ10選 | 国内・海外LMSを徹底比較
- Teachableで日本語でオンライン講座を作成する方法 | 日本語完全対応のプラットフォームも紹介!
- 売れるオンライン教材の販売戦略|オンラインビジネスで成功を収める方法
- e-ラーニングの最新トレンド&オンライン講座ビジネスで成功するコツを解説
- オンライン講座の収入は?|増収・継続につながる講座運営のコツを解説
- 集客はタイトルで決まる!人気講師になるための「セミナータイトルの作り方」
- オンライン教材は簡単に作成できる?制作から公開・販売までの方法をご紹介!
- オンライン講座の構成と作り方|受講しやすくリピートの多い講座とは
- オンライン講座を始めるのに何が必要?|必要なもの・あると便利なアイテムをご紹介
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
動画販売サイトおすすめ4選!始め方や高単価にするポイントも徹底解説
オンライン講座等の動画販売は、現在広く普及しています。しかし、動画レッスン等も含めた動画の販売は年々増えているため、「選ばれる動画コンテンツ」を作成することが重要となります。また生成A...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座の構成を考えよう|単発講座と連続講座それぞれのメリット・デメリット
オンライン講座の構成を決める際の重要なポイントの1つとして、どのくらいの期間でどのくらいスキルやノウハウを習得できるようにするか、という点があります。講座を単発で開催するか連続で開催す...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座は終わった後が肝心!講師のためのアンケートのつくり方
オンライン講座は、講座をおこなって終わりではありません。講座後にどのようなフォローがあるかでリピートされるかどうか、感想をもらってSNSなどでシェアしてもらえるかどうかが変わります。そ...
2024.04.01|コエテコ byGMO 編集部
-
オンライン講座プラットフォームとは?選択のポイントとLMSとの違いを徹底的に解説
コロナ禍を経て、オンラインサービスが日常の一部として定着しました。従来は対面が主流だった企業研修やオンライン講座も、LMS等のシステムを利用した動画講座やウェビナーが一般的な手段となっ...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
動画講座の販売におすすめプラットフォーム3選!動画配信システムも徹底比較
動画コンテンツは、現代の生活の中に溶け込んで子供から年配の方まで幅広い層で利用されるようになり、情報収集のための検索でもYouTubeやTikTok等の動画が上位に上るようになってきま...
2025.06.03|コエテコ byGMO 編集部