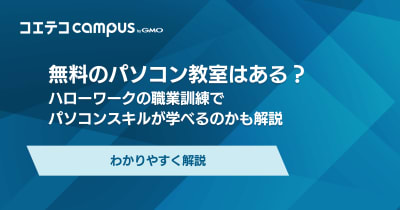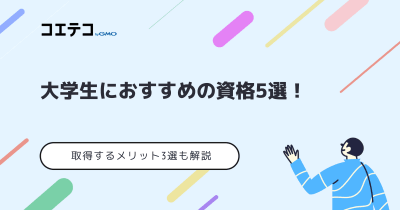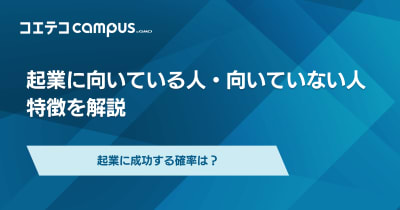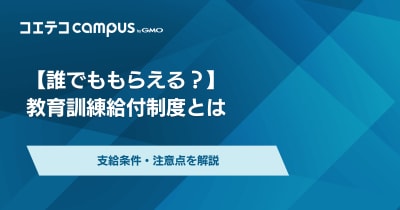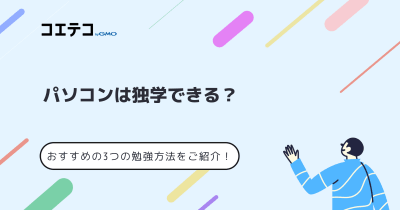主体性とは?子どもの主体性についてもわかりやすく解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。また、詳しい最新情報については公式サイトをご確認ください。
主体性とは?

主体性と言うけど、「主体性ってなんだろう?」と疑問に思いますよね?では、主体性がある人、ない人の特徴を見ていきましょう。
●主体性がある人
自分がすべき事は何かを考え、ゼロから何かを作り出すができます。いろいろなチャレンジをする分、失敗もしますがそれも糧にし、さらに成長していくことができます。
●主体性がない人
逆に主体性がない人というのは、相手に任せきりで決定を委ねる人のことをいいます。一見、協調性があると思いがちですが自分で判断せず相手に決めてもらう事は協調性とは言いません。主体性がない人は自分の意見を言わず相手に任せてしまうことで、人と衝突がなく円滑な人付き合いができると思いますが、社会で重宝されるスキルとは言えません。
主体性が社会人に重要な理由

なぜ社会に出て仕事をするようになると主体性が大事なのか?それまでの学校教育で習ってこなかった「主体性」が大事であるといくら教えられてもよくわからないのが現状ではないでしょうか。
これからの社会において、AIに変わっていくことで、多くの仕事がなくなることが話題となっていたことはご存知の方も多いかもしれません。
「なくなる」と言われている仕事は、ある程度パターンが決まっているものや、特別なスキルを必要としないことも共通点としてあげられます。
主体性に絡めて考えてみると、やることが決められていて、その目的に向かって進められる仕事が多く、逆に今後も存続する可能性が高いとされている職業については、ゼロから新しいことを作り上げるものが多く入っています。そうしたことから、今後ますますゼロから作り上げることができる「主体性」を持っていることが大事に鳴るのです。
(参考)野村総合研究所発表データ
主体性を育てるために必要なこと
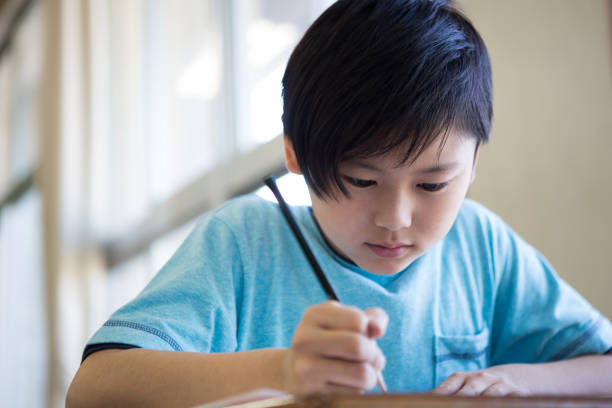
社会に出てから主体性が大事なのはわかったけど、お子さんが主体性を身につけるためにはどうするればよいでしょうか?
みなさんは、お子さんに「片付けなさい」「宿題しなさい」などと、こちらから何かをやるように働きかけてはいませんか?もしくは、お子さんのやり方が違った時に口を挟んではいませんか?
親御さんや周りの人から言われてやったことや、やり方を教えられたことで成功したことは、ほんとうの意味で「主体性」を持って動いたことではありません。前述したように、主体性とはゼロから何かを作り出せる行為です。
お子さんが創作活動に忙しそうにしていたら、可能な限りやらせてあげる、「片付けなさい」「宿題しなさい」とすぐに口に出してしまうのではなく、お子さんが自発的に行動するのを可能な限り待ってあげる。
家事や育児に追われている中で、お子さんが自分の期待している行動をしてくれないと、どうしても言いたくなってしまうかもしれませんが、そこは一旦待ってみることを心がけてみてください。
そして、もしもお子さんが困っている場面に直面したら、一方的にやり方を伝えるのではなく、「なぜこうした方がいいのか」といったように理由もていねいに伝え、子どもが主体的に考えて動ける環境を作ってあげてください。
まとめ
子どものやることに親がついつい口出しをしてしまったり、親が先にやってしまってあげたり…子どものために親心でしてしまっていることですが、それが子どもの主体性を育てることを妨げているかもしません。子どもの主体的な行動を引き出して上げるために、少し待てる子育てを心がけてみましょう。WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
無料で学べるパソコン教室のおすすめは?ハローワークも解説
ネット全盛の現代において、今やパソコンスキルは必須とも言えるでしょう。パソコンを扱えれば出来る仕事もグッと増えるため、ぜひとも身につけたいところ。パソコン教室に通って学ぶのが確実ではあ...
2025.01.15|コエテコ byGMO 編集部
-
大学生のうちに取るべき資格おすすめ6選!就職に有利?
「大学生のうちに資格を取っておいたほうがいい」という話を聞いたこと・言われたことのある人はきっと少なくないはず。しかし「どんなメリットがあるの?」「具体的に何を取ればいい?」といった疑...
2025.01.04|コエテコ byGMO 編集部
-
起業に向いている人・向いていない人の特徴を徹底解説
「自分の夢を追いかけて起業してみたい」と考えつつも、中々勇気を出せず「上手くやっていける自信がない…」「どんな人に起業は向いているんだろう?」と悩んでしまう人はきっと多いことと思います...
2024.11.30|コエテコ byGMO 編集部
-
教育訓練給付制度の支給条件とは?わかりやすく解説
スキルアップ・キャリア形成を目的とした支援制度の中でも、代表的なのが「教育訓練給付金制度」。コストを抑えつつ学ぶための手段として非常に有用である一方で「給付を受けるための条件は?」「誰...
2025.02.05|コエテコ byGMO 編集部
-
パソコンは独学できる?何から始めるのかおすすめ勉強方法を解説
パソコンを使いこなすことは、今や社会人には必須スキルといえるでしょう。これまでパソコンをあまり使っていなかった方も、これからは仕事でもプライベートでもパソコンを使いこなしたい、パソコン...
2025.01.14|コエテコ byGMO 編集部