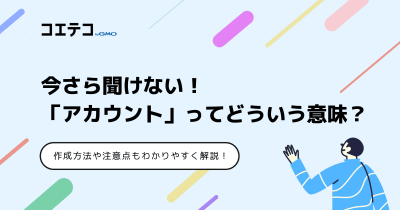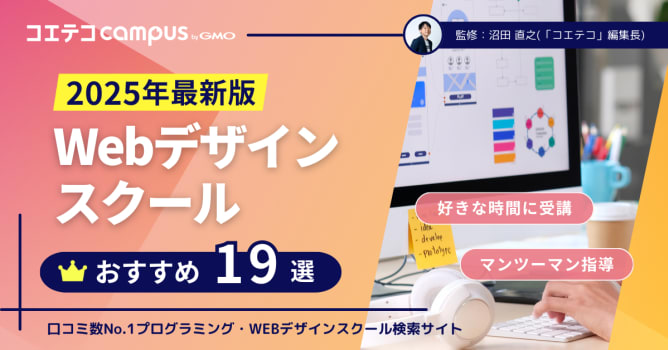ステマの意味とは?炎上しやすい理由やダイマとの違いを徹底解説
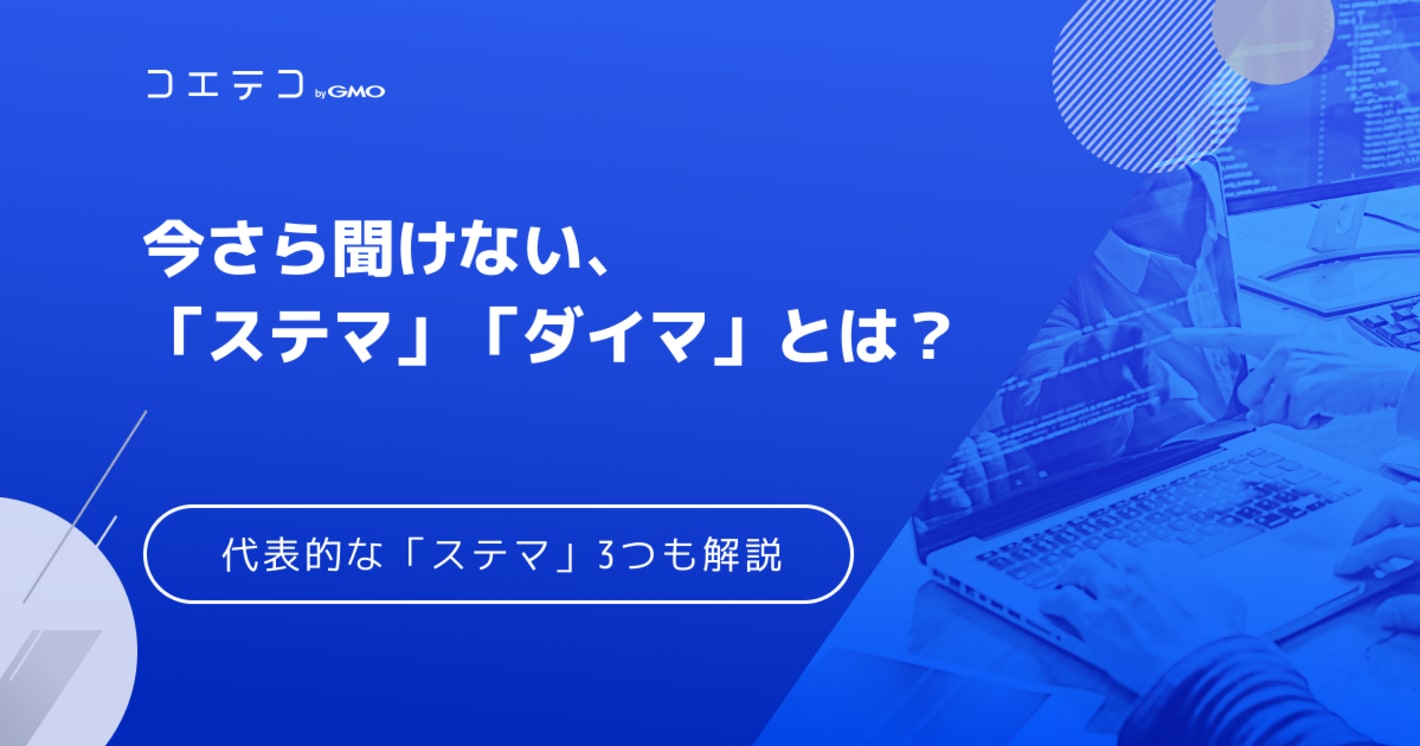
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
SNSが普及するようになり「ステマ」という言葉を耳にする機会もあるでしょう。ステマに関する事例は多々ありますが、消費者には良い印象を与えないことでも有名です。消費者としてステマに騙されないためにも、意味を正しく理解しておきたいですね。
この記事では、ステマの意味やステマが炎上しやすい理由をわかりやすく解説します。
「ステマ」の意味は?
ステマとはステルスマーケティングの略称であり、マーケティングの1つです。ステマは、芸能人やインフルエンサーが消費者に宣伝であることを悟られないよう、商品やサービスを紹介する手法のことです。商品を紹介している芸能人やインフルエンサーのファンである場合、ステマだと気づかなければ高確率で商品やサービスを利用してもらえます。つまり、ステマは消費者を欺き、商品やサービスの売り上げをアップさせようとする行為だということです。若者から絶大な支持を得ているInstagramでは、ステマが横行しているといわれています。
ステマの対義語「ダイマ」の意味とは?
ダイマは、「ダイレクトマーケティング」の略称であり、宣伝であることを隠さずに商品やサービスを宣伝することを意味します。ステマの反対の言葉として使用される言葉であり、営利目的ではなく、個人が商品レビューをするときなどにも「#ダイマ」で拡散されるケースが多くあります。消費者を騙すステマと比較して、宣伝であることを明確に宣言するダイマは消費者が好意的に受け取る傾向があります。
ステマが炎上しやすい理由
SNSを利用するのが一般的な昨今では、ステマによる炎上は後を絶ちません。ステマに騙されないためにも、ステマが炎上しやすい理由を理解していきましょう。消費者の目を欺き金儲けをしているから
ステマは商品を宣伝する芸能人やインフルエンサー、商品を販売する企業側に大きくお金が動く行為だといえます。例え、ファンであったとしてもステマによって「騙された」という事実から、不信感を持つきっかけにもなり得ます。一時は金儲けができたとしても、ステマが発覚すれば企業や宣伝した芸能人の信頼が回復することは難しいでしょう。競合他社がステマを見抜き暴露することも
ステマに気づくのは、消費者だけではありません。競合他社が商品やサービスのステマに気づくことも少なくありません。競合他社からステマが暴露されれば、消費者は競合他社へ流れることを意味します。
業界全体の信頼度が落ちる
ステマをして自社だけの責任になれば良いですが、それだけではなくステマをした商品やサービスにおける業界全体の信頼度を落とすケースも多くあります。つまり、ステマは同業者や競合他社にまで迷惑をかける行為だということです。ステマがきっかけとなり、それまで取引があった企業と縁が切れてしまうこともあるでしょう。ステマは、消費者だけではなく人脈をも失う行為であることを意味します。
炎上したステマの事例を知ろう!
炎上したステマのなかでも、有名な事件がいくつかあります。ステマに騙されないよう、これまでの事例を確認していきましょう。ぺ二オク事件
ぺ二オク事件と呼ばれるペニーオークションでは、運営側が入札を繰り返し消費者側の手数料を跳ね上げる詐欺を行っていました。さらに、多くの芸能人がこぞってペニーオークションを取り上げ「安く落札できる」などと発信していましたが、それがステマだと発覚。ぺ二オク事件がきっかけとなり、ステマという言葉と意味が広く知れ渡るようになりました。食べログ事件
2012年に起こった食べログ事件では、口コミ評価の代行業者がお金を支払うレストランに対し高評価を付けるというステマが横行していました。口コミ評価の代行業者から直接営業を受けた飲食店側が通報したことで、ステマであることがわかりました。この事件が元になり、口コミ評価の代行業者は30社以上もあったことが明らかになりました。アナ雪2漫画事件
2019年12月、全く同じ日に「アナと雪の女王2」の感想を描く漫画がTwitterで一斉に7本拡散されました。タイミングや内容を見た消費者はステマではないかと指摘していましたが、当初ウォルト・ディズニー・ジャパンはステマを否定。しかし、それから間もなくしてステマであることを、ウォルト・ディズニー・ジャパンが認め、謝罪文を公式サイトに掲載しました。ステマの意味を理解し、騙されない感覚を養おう!
日本国内の大手企業でも、ステマにより消費者からの信頼を失った企業は数多くあります。例え、インフルエンサーや芸能人のファンだったとしても、SNS上での商品のアピールは「ステマかもしれない」と一歩引いた視点から見ることも大切です。ステマが日常に潜むからこそ、ステマに騙されないよう心掛けることが重要です。ステマに騙され続ければ、大切な資産を失う可能性も否定できません。SNSを利用する以上、ステマは常に側にあるものと考えると良いでしょう。
WRITERこの記事を書いた人
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
アカウントとは?意味が分からない初心者向けに作成例も徹底解説
日常でもよく耳にする「アカウント」という単語ですが、実際にはアカウントの意味や役割がよくわかっていないという方や、メールアドレスのことと混同してしまう方も多いのではないでしょうか。今回...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部
-
Google Meet初心者向けに使い方をわかりやすく解説
Googleからリリースされているもののなかで、多くのビジネスパーソンが利用しているのがGoogle Meet。簡単に利用しやすいことから、オンライン会議に広く利用されるようになりまし...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部
-
Twitter(現X)の便利な検索コマンド14選!日付や特定ユーザー検索一覧
時代を席巻するSNSにおいて、代表的存在ともいえるTwitter(現X)。実はあるコマンドを入力することでより便利に活用することができるのです。この記事では「そもそもTwitterの検...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部
-
【2045年問題】シンギュラリティは本当にやってくるのか?
AIが人間を凌駕するといわれている「2045年問題」。コンピューターが人間を支配するようになるのでは、と心配になる人もいるでしょう。この記事では、シンギュラリティの意味や2045年問題...
2025.05.26|コエテコ byGMO 編集部
-
クラムシェルモードとは?メリットデメリット解説【MacBookデスクトップPC化】
MacBookに「クラムシェルモード」なる使い方があると耳にしたものの、具体的にどんな機能なのか知らない…という人は意外と多いのではないでしょうか。結論から言うと「MacBookがデス...
2025.11.12|コエテコ byGMO 編集部