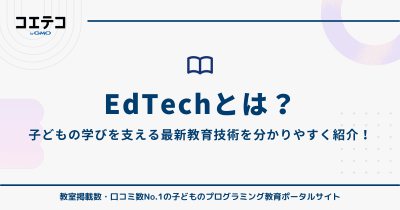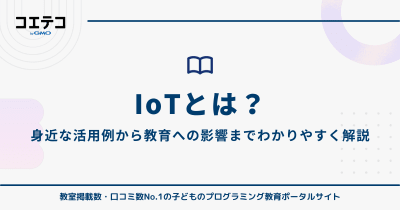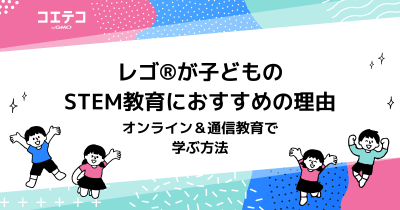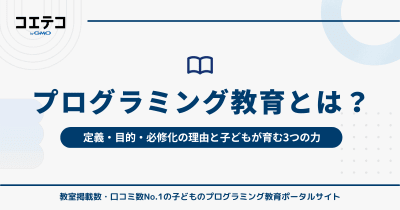STEM教育とは?特徴・メリット・家庭で始める方法をわかりやすく解説

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
科学・技術・工学・数学の学びを統合した「STEM教育」は、子どもが自ら考え行動する力を育む新しい学習スタイルです。
海外ではすでに広く導入され、日本でも注目が高まっています。
本記事では、STEM教育の特徴やメリット、家庭でできる取り組み方までわかりやすく解説します。
STEM教育とは?
「STEM(ステム)教育」とは、以下の頭文字を組み合わせた言葉であり、科学・技術・工学・数学を横断的に学び、分野を超えた問題発見と解決力を養うことを目指す教育のことを言います。- Science(科学)
- Technology(技術)
- Engineering(工学)
- Mathematics(数学)
一見、理系のみを対象にしているように見えますね。でも、決して「理系の勉強」だけを指すわけではありません。
STEM教育の特徴は、「子どもが自分で考え、発見する力」を育てることにあります。たとえば、タブレットを使って自分で調べ学習をしたり、簡単なプログラミングに挑戦したり、ロボットのキットを組み立てたり。こうした体験を通じて、子どもたちは楽しみながら「なぜだろう?」「こうしたらどうなるかな?」と考える習慣を身につけていきます。
これまでの「先生が教えて、子どもが覚える」という学習方法から、「子どもが自分で考えて、解決方法を見つける」という学び方への転換です。スマートフォンやAI(人工知能)が当たり前の時代を生きる子どもたちには、とても大切な力になるはずです。
最近では、STEMに「A(Art:芸術)もしくは(Arts:リベラルアーツ」を加えた「STEAM教育」という考え方がより主流になっています。理系の知識だけでなく、創造性や表現力も大切にしようという発想です。
「でも、うちの子は理系が苦手…」と心配する必要はありません。STEM教育の目的は、科学者やエンジニアを育てることだけではないのです。むしろ、「自分で考える力」「新しいことに挑戦する勇気」「問題を解決する知恵」を育てること。これらは、文系・理系を問わず、これからの時代を生きる子どもたちにとって、とても大切な力となるはずです。
STEAM(スティーム)教育って?STEM教育のバリエーション
STEM教育には、似た言葉で「STEAM教育」「STREAM教育」などがあります。「一体どのような違いがあるの?」と戸惑う方も多いですよね。ここではSTEM教育から派生した教育方針を順番に紹介します。
STEAM(スティーム)
STEAM(スティーム)教育は、STEM教育にA(Art(芸術)、もしくはArts(リベラルアーツ、教養))を足したもので、化学・技術・工学・数学に芸術や教養を足した教育方針になります。芸術や教養と一言で言っても、単純に絵を描くとか、楽器を演奏することではありません。芸術の本質である「何を美しいと思うのか?」「何が幸せなのか?」といった哲学をテクノロジーと融合させる。それがSTEAM教育です。
今や、われわれの生活はテクノロジーにあふれています。いろいろなモノやコトがスピードアップし、便利になってきました。
「でも、本当にそれだけでいいの?もっと人間が幸せに、心まで豊かに暮らす方法はないのかな?」
こんな風に考え(哲学)、テクノロジーを生かしていく。それがSTEAM教育の本質なのです。STEAM教育では、学んだことを現実社会の問題に生かし、解決する力が期待されています。
STEMは20世紀的(工業的)、STEAMは21世紀的(幸せ追求的)なスキルだと主張する人もいます。
STREAM(ストリーム)
STEAM教育に「R(Robotics、ロボット技術)」を足した言葉です。これからの時代にはロボットを設計したり、使いこなしたりするスキルが必須!という考えから提唱されています。
eSTEM(イーステム)
eSTEM教育は、environmental STEMの略称で、STEM教育に環境教育を足したものになります。環境教育の分野は多岐にわたっています。異常気象や森林破壊などの自然環境、近代化による公害問題など産業環境に関する分野や、人間関係や生きがいなどの生活環境の問題、IT社会におけるネット環境など、身近なものから地球規模の環境まで、あらゆる分野に広がっています。
技術の向上だけでなく、環境に配慮したよりよい社会を作れる人材の育成を目的としています。
GEMS (ジェムズ)
GEMS(ジェムズ)はGirls in Engineering Math and Scienceの略称です。女性をSTEM分野に進出させるためのプログラムとなっています。女性の社会進出や男女平等の社会づくりが求められる中、世界的にSTEM分野に進出する女性の割合が少ないことから、このような取り組みを行う国や機関が増えています。
またGreat Explorations in Math and Scienceの略称としても使われています。これはアメリカのカリフォルニア大学バークレー校で始まった取り組みです。数学や化学の分野における参加体験型のプログラムで、子供たちが自分で実験などを企画しおこないます。日本でも現在多くのプログラムが実施されています。
ジャパンGEMSセンター公式HP
【中学受験 情報センター】の公式サイトです。中学受験に関する情報リサーチやセミナーの開催、学校向け,学習塾向けコンサルティングや情報サイトの運営などを行っております。

http://japangems.org/ >
STEM教育が必要な理由
従来の教育では、ひとつの分野を深く掘り下げていくような取り組みが主となっていました。しかしSTEM教育では、科学・技術・工学・数学を横断的に学んでいきます。分野の垣根を超えて学ぶことにより、それぞれの分野にまたがるような問題を発見し、それを解決するような力を養うことを目指していくのです。複雑化・多様化する現代社会の中で、このように広い知識と視野を持つことは、仕事や研究を行う中で非常に重要な力になってくるでしょう。
また、そうした仕事や研究には、主体的に問題を発見しにいこうとする力が欠かせません。STEM教育で行われる体験的・創造的な学習によって、そうした力も鍛えられていきます。あらゆる仕事・研究は「気付き」から始まります。問題が発見されていなければ、それを解決することもできません。
STEM教育では、問題を探したり、問題に気づいたりする能力が養われます。そしてそれこそが、人工知能(AI)に代替不可能な仕事であるといえるでしょう。
STEM教育は、お子さんが今後の進路を文系とする場合でも有効です。
私たちの生活や仕事は、科学技術抜きにしては回っていきません。自分では直接それを取り扱わないにしても、どのような仕組みで世界が動いているかを知っているとことは、複雑化・高度化する現代社会を生き抜く上で重要な武器になることでしょう。
日本のSTEM教育の現状は?

ただし、この状況を改善しようと、さまざまな取り組みが始まっています。
「GIGAスクール構想」により子どもたち一人ひとりにタブレットやパソコンが配布されるようになり、プログラミング教育が小学校・中学校・高校で必修化されました。
しかし、まだいくつかの課題も残されています。
- 地域によってICT環境に差がある
- 先生方の指導力にばらつきがある
- 教育予算が海外に比べて十分とはいえない
これらの課題に対して、文部科学省や各学校での取り組みだけでなく、民間企業による教育サービスの提供なども増えてきています。埼玉大学には「STEM教育研究センター」が設置され、ロボットやプログラミングを通じた教育研究も行われています。
このように、日本のSTEAM教育は着実に前進していますが、まだ発展の余地が大きい分野といえます。保護者としては、お子さんの通う学校でどのような取り組みが行われているのか、確認してみるのもよいかもしれません。
学校の授業以外にも、地域や民間の教育機関が提供するプログラミング教室やロボット教室なども、選択肢のひとつとして考えられそうです。
参考:
STEAM教育に関係する政府等の主な方針(抜粋)/文部科学省
小学生白書Web版2022年9月調査/学研教育総合研究所
日本で実施されているSSHについて
日本では、2002年よりスーパーハイスクール(SSH)という取り組みが行われています。これは未来を担う科学技術系人材を育むことを狙った施策です。SSH指定校では、学習指導要領の範囲を超えた活動を行うことが可能です。そのため、受験勉強に使うための詰め込み教育ではない、実践的で体験的な教育を受けることができるのです。
SSH指定校はすべての都道府県に設置されており、その多くが公立校となっています。お住まいの地域から通える学校があるかどうか、SSH指定校一覧のページから確認することが可能です。
SSH指定校一覧:https://www.jst.go.jp/cpse/ssh/school/list.html
SSH指定校は年々増加傾向にありますが、一度指定校になった後に指定校ではなくなるケースもあります。進学先を考える際は、最新の情報を参照するようにしましょう。
また、以下の記事でSSHについて詳しく解説していますので、興味のある方はあわせてお読みください。
STEM教育を受けられるおすすめ教材・スクール
STEM教育は難しい勉強ばかりではありません。
初めはゲーム感覚で遊びながら学べるものや、物造りや実験など様々な体験をするものなどが主流となっています。具体的な教材と、おすすめの子ども向け教室を紹介します。
自宅でできる
LITALICOワンダーオンライン

LITALICOワンダーオンラインは、ゲームやロボットなど、子どもの「つくりたい」に合わせて必要なスキルを学べる個別最適型オンラインプログラミング教室です。
一人ひとりの個性や強み、趣味に応じて目標を決めるオーダーメイドプログラムなので、興味を持って取り組みやすい内容になっています。習い事が続かないお子さんでも、アウトプット中心の学習スタイルで試行錯誤する過程を学べます。
パソコンに触れるのが初めての子どもでも無理なく学べるよう、マウス操作のみで取り組めるプログラムも用意されています。質の高いスタッフを育てるための教育にも力を入れているため、安心して子どもを任せられます。
プログラミング教育 HALLO オンライン教室

プログラミング教育 HALLO オンライン教室では、冒険を進めながらゲーム感覚で実用レベルのコーディングを身につけられる教材「Playgram」を採用。子どもが夢中になる仕掛けが満載で、論理的な思考やプログラミングスキル・課題解決力といった将来役立つスキルを自然に学習できます。
学習においては管理システムで理解度や進捗を把握し、さらにやる気スイッチグループのノウハウを活かした個別指導をおこないます。基礎から実践まで子どもの理解のスピードに合わせて無理なく進められるでしょう。
なお、プログラミング教育 HALLO オンライン教室は2025年から大学入試科目になった「情報I」にも対応しています。カリキュラムをとおして授業内容を先取りしておけるのが魅力的なポイントのひとつです。
Groovy Lab in a Box

自宅でできるSTEAM教育なら、アメリカで大人気のSTEAM教材Groovy Lab in a Box(グルービーラボ イン ア ボックス)がおすすめ!
Groovy Lab in a Boxは月額3,980円のサブスク型STEAM教材で、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics) の素養を身につけられます。毎月送られてくるミッションは「でんきエンジニアになろう」「火星ロボットをつくろう」など種類も豊富で、実際に手先を動かしながら幅広い分野に触れられるのが魅力的です。
2020年には、世界のイノベーティブな研究者・商品に対して贈られる「エジソン賞」の2020年ファイナリストにも選出。経済産業省が立ち上げた「EdTech 未来の教室」でも紹介されており、各界での評価にも注目が集まっています。
風船で静電気を起こしたり、アインシュタインの目を光らせたり、ミニサイズのジェットコースターを作って物理を学んだり……4歳以上のお子さまなら、きっと科学の世界に興味を持つきっかけになるでしょう。

Groovy Lab in a Boxのマンスリーコースならいつでも退会OK。期間の縛りがないので、「とりあえず1ヶ月だけ」トライアルも可能です。詳細はGroovy Lab in a Boxのサイトでチェックしてみてくださいね!
NEST LAB.

NEST LAB.は「好きを究めて知を生み出す」をテーマに、小中学生の探求心や才能を伸ばすオンライン研究スクールです。NESTとは「Nature、Engineering、Science、Technology」の頭文字で、科学や技術の根幹となる自然(Nature)の理解も重視しています。
カリキュラムではサイエンスとロジックに立脚する研究者集団リバネスによって20年間培われた教育・研究ノウハウをもとに、以下5つの専攻を用意しています。
| ワンアースネイチャー専攻 |
|
| ナレッジエンジニアリング専攻 |
|
| サステナブルサイエンス専攻 |
|
| ロボットAIテクノロジー専攻 |
|
| ビジネスアントレプレナー専攻 |
|
NEST LAB.の講師は修士・博士号を取得した研究者で、小学生のうちから中高生や大学生、大人の研究者と議論する経験も。中高生のための学会「サイエンスキャッスル」などで発表する機会もあり、自宅に居ながらまさに研究者を目指せるスクールです。
世界大会出場も!モノづくり系教室
次に紹介するのは、子どもに人気のロボットプログラミングなど、コンピューターを操作するだけでなくモノづくりから行う教室です。STEM教育でのモノづくりは、自分で考えてつくり、出来上がったものを動かすまでが含まれます。
というのも、自分で考え組み立てから動かすまでの全工程を体験することにより、問題解決のための思考力や行動力など様々な技術を身に着けられます。STEM教育専門の教室のSTEMONでは、モノづくりを通して機械などの仕組みやプログラミングを学び、理系ITに強い人材育成を行っている教室で、子どもの成長に合わせて様々なコースが用意されています。
他にも最先端の物造りが体験できるLITALICOワンダー、ロボットプログラミングの専門教室のアーテックエジソンアカデミーなどがあります。
LITALICOワンダー
リンク先の情報にアクセスできますが、表示の問題でタイトルと画像を取得できませんでした。

https://coeteco.jp/brand/litalico-wonder >
ロボ団
ロボ団の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:夢見る株式会社
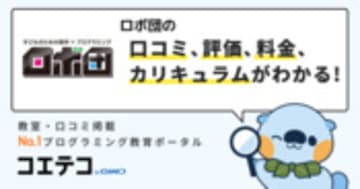
https://coeteco.jp/brand/robo-done >
プログラボ
プログラボの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:ミマモルメ
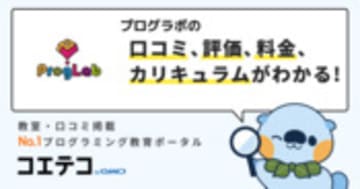
https://coeteco.jp/brand/proglab >
ヒューマンアカデミージュニアロボット教室
ヒューマンアカデミージュニアロボット教室の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:ヒューマンアカデミー
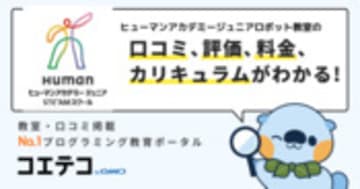
https://coeteco.jp/brand/human-robot >
STEMON
STEMON(ステモン)の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社ヴィリング
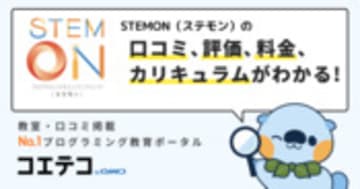
https://coeteco.jp/brand/stemon >
ロボット科学教育 Crefus
Crefus(クレファス)の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社ロボット科学教育

https://coeteco.jp/brand/crefus >
アーテックエジソンアカデミー
エジソンアカデミーの口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:株式会社アーテック
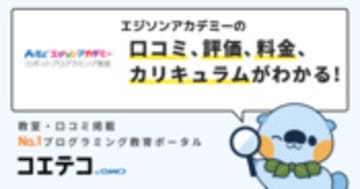
https://coeteco.jp/brand/edisonacademy >
富士通オープンカレッジ F@IT Kids Club
富士通オープンカレッジ F@IT Kids Club<ファイトキッズクラブ>の口コミや料金、カリキュラム情報をわかりやすく紹介!子供・小中学生向けプログラミング教室の特徴や体験レッスン情報も満載。Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン実施中!運営本部:富士通ラーニングメディア
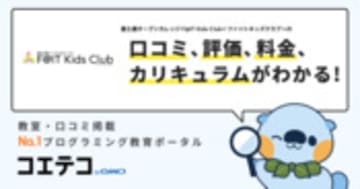
https://coeteco.jp/brand/fujitsu-opencollege >
理科実験教室
不思議な体験や経験を通じて科学への理解を深めることができる理科実験教室。大人が見ても楽しめるものが多く、楽しく科学を勉強できます。
理科実験教室のパイオニアと呼ばれるサイエンス倶楽部では、幼児から中学生までを対象にさまざまなプログラムがあり、野外実習もおこなわれています。
他にはSTEM教育の基礎となる算数などの教室などもおすすめです。
算数といっても学校の授業とは少し違っており、遊びを取り入れて楽しく学ぶことができます。たとえば算数オリンピックの数理教室であるアルゴクラブでは、パズルやブロックやカードゲームを使い、楽しみながら数理的思考力を磨くことが出来ます。


まとめ:STEM教育を念頭に置き子どもの先取り学習は早めを意識!
「子どもにプログラミングをさせるなんて、まだ早い!」と考える方もいるかもしれません。難しそうなイメージもあるし、「うちの子には無理なんじゃ……」と不安に思うかもしれませんね。しかし、ブロックを使って創造力を養ったり、タブレットで簡単な操作をさせたりと、小さいうちからできることもたくさんあります。
重要なのは、子どもが「自分で学ぶ能力を養う」ことです。自分で触れて、自分で操作して、自分で考える。そのような能力を育むことで創造力や独創性を開花させ、日本だけでなく世界で活躍する人材として成長できるのではないでしょうか。
コエテコでは今回紹介した以外にも多くの子ども向けプログラミング・ロボット教室を検索できます。お住まいの近くから探すこともできますので、お子さんにピッタリな教室をぜひ探してみてください。
STEAM教育がまるごとわかる!解説記事一覧
コエテコではSTEAM教育の基本や関連スクール・教材、有識者インタビューなど幅広いコンテンツをお届けしています。気になるSTEAM教育がまるごと分かるコンテンツをぜひご覧ください。まずは基本から。STEAM教育がわかる記事
まずはこの記事でSTEAM教育の基本をおさえましょう。用語の定義はもちろん、文科省の資料や海外の取り組み事例、実践例などを見ながらサッと理解できるコラムになっています。STEAM教育とは?STEM教育と何が違う?用語の定義や具体的な実践例を解説
STEM教育とは何が違う?
STEAM教育に似た言葉に「STEM(ステム)教育」があります。このコラムではSTEM教育の定義や海外の事情、STEM教育を実施しているスクールをまとめました。STEM教育とは?STEAM教育とは何が違う?新たな時代に必須の学び!
21世紀型の新しい教育「STEM(ステム)教育」が世界各国で導入され始めています。その具体的な内容は?STEAM(スティーム)教育とは何が違う?日本のSTEM教育の現状は?くわしく解説します。


2025/11/17

STEAMS教育との違いは?
同じく、STEAM教育に関連する言葉に「STEAMS(スティームス)教育」があります。最後の「S」とは何なのでしょうか?簡単に分かるコラムです。STEAMS(スティームス)教育とは?
プログラミング教育必修化がせまる中で『STEAMS(スティームス)』といった言葉を見かける機会が近年増えてきました。これまでには『STEM(ステム)』、『STEAM(スティーム)』などといった言葉もあり、何が違うの?って混乱する方も多いのでは?この記事を読んで基本的な意味を理解してみませんか?


2025/06/24

家庭でSTEAM教育を受けさせたい!
家庭や習い事でSTEAM教育を受けさせたい方に向け、こちらのコラムではおすすめの教材やスクールをまとめています。気になる費用もざっくり分かるので安心。習い事選びにお役立てください。
STEAM教育にかかる費用は?どんな準備物が必要?|おすすめ通信教材、費用、スクールまとめ
最近ではプログラミングの学習に加えて、各教科やロボットの組み立て方やプレゼンの方法などを横断的に学ぶことのできるSTEAM教育系のスクールや教材が増えています。 この記事ではSTEAM教育について、教材や学習法の例や費用を紹介していきます。


2025/08/21

STEAM教育が学べる通信教材「ワンダーボックス」とは?内容・料金を徹底解説
お子さんが3~4歳になると、ちらほらと通信教育をはじめる子も出てきますよね。今回は「STEAM教育」を学べる通信教育"WonderBox(ワンダーボックス)"をご紹介します。 キットの中身や得られる力、料金体系などについてまとめました。


2025/08/21

有識者インタビュー
コエテコでは官公庁を含め、さまざまな有識者にインタビューを行っています。この記事では日本人女性唯一の国際数学オリンピック金メダリストであり、内閣府STEM Girls Ambassadorを務める中島さち子さんにインタビューし、STEAM教育の意義をお聞きしました。
STEAMの「A」は未来をえがく力 ― ジャズピアニスト・数学研究者 中島さち子


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド
-
EdTechとは?子どもの学びを支える最新教育技術を紹介!
オンライン授業やタブレット学習など、教育現場で急速に広がる「EdTech(エドテック)」。これは、IT技術を活用して子どもの学びを進化させる新しい教育の形です。この記事では、EdTec...
-
IoTとは?身近な活用例から教育への影響までわかりやすく解説
IoTは「モノのインターネット」と呼ばれ、家電や車、学校の設備などがネットにつながることで暮らしや学びを便利にしています。実は教育現場でも、IoTが子どもたちの学習環境づくりに役立って...
-
ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説
2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説...

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
STEAMS(スティームス)教育とは?
プログラミング教育必修化がせまる中で『STEAMS(スティームス)』といった言葉を見かける機会が近年増えてきました。これまでには『STEM(ステム)』、『STEAM(スティーム)』など...
2025.06.24|コエテコ byGMO 編集部
-
レゴ®が子どものSTEM教育におすすめの理由 オンライン&通信教育で学ぶ方法
組み合わせや工夫次第でいろいろな物を作って遊べる「レゴ®ブロック」。知育玩具として選ぶ保護者も多く、STEM教育に最適な教材として、教育の現場でも活用されています。この記事では、STE...
2024.11.06|コエテコ教育コラム
-
ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説
2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
プログラミング教育とは?定義・目的・必修化の理由と子どもが育む3つの力
プログラミング教育が必修化されて数年が経ちましたが、子どもたちがどのようなことを学び、将来にどうつながるのか、気になっていませんか。プログラミング教育は単なる技術の習得ではなく、論理的...
2025.10.02|大橋礼
-
ロボカップジュニアで挑むロボットサッカー!競技内容と世界大会の魅力とは
1997年から開催されている「ロボカップ」の19歳以下を対象にした、ジュニア部門の大会。ノード、ブロック、日本大会を勝ち抜くと「ロボカップジュニア世界大会」 にも参加できるという本格的...
2025.05.26|プログラミング教室ガイド