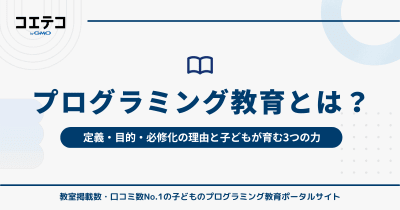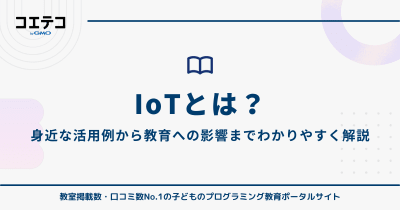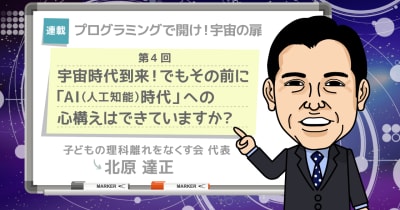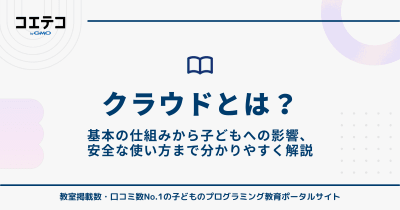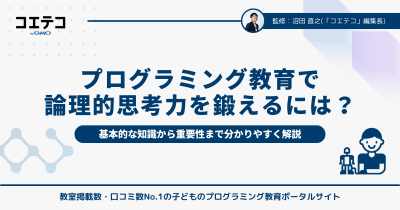プログラミングの必要性は?身近な家電で学ぶ活用例と未来

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
実はスマートフォンや洗濯機、ロボット掃除機や自動販売機など普段何気なく使っている機器にもプログラムが深く関わっています。
この記事では、身近な家電やデジタル機器を例に、プログラムの仕組みと活用例をわかりやすくご紹介します。暮らしに潜むプログラミングの力を、日常のシーンから探ってみましょう。

プログラムとは?身近な例で簡単解説
いまや1人に1台と言われるスマートフォンは、電話やメール、カメラやインターネット接続など、その他にもたくさんの機能をもった現代の便利ツールです。でもちょっと考えてみてください。スマートフォンがいくら万能でも、皆さんがしたいことを「命令」しなければ動きませんよね?
「友達とランチに行きたいけど、適当なお店ないかしら?」と思って、検索ワードを入力するからこそ、スマートフォンは答えを返してくれるのです。
決してスマートフォン自らが意志を持って、「このお店がよさそうですから、今日お友達とランチにでも行ったらどうですか?」と勧めてくるわけではありません。

スマートフォンもパソコンも機械です。
機械は電気を流せば動きますが、それだけでは何もしてくれません。
機械がわたしたちの思い通りに動くのは、そのように「プログラム」されているからなのです。
プログラムは、機械が「私たちがしてほしいように動く」ための「魔法の呪文」のようなものなのです。
AIや自動化サービスの仕組みを知ろう
いまや身のまわりにある機械のほとんどは、プログラムで動いているといっても過言ではありません。電車だって運転手が発車のタイミングや、ブレーキの指示をしていますが、その裏では、常に最適な速度を維持できるようにプログラムされているのです。

「でもAIスピーカーなんて、まるで自分で話しているようだけど…」と思う方もいるでしょう。機械そのものの意志で動いているかと思わせるほど、技術は進歩しています。
たとえばインターネットの検索サイトに文字を入力すると、その文字に続く候補が自動的に表れますよね。これは「サジェスト機能」とよばれるものです。これも一見、パソコンやスマートフォンが自分の意志で表示しているように見えますが、その裏では膨大なデータをもとにして、その言葉から連想される単語を表示するようにプログラムされているのです。
プログラミングの必要性は?身近な家電製品における活用例
全自動洗濯機

昔は画期的だった電気洗濯機も、今ではプログラムとAI技術によって便利に進化しています。
最新の全自動洗濯機はスマートフォンとの連携機能があり、外出先からの操作や洗濯状況をチェックできます。専用アプリを使えば洗濯の開始設定はもちろん、お手入れ時期などの通知も受け取れるため、忙しい日常でも効率的に洗濯を管理できます。
この便利さを支えているのが、洗濯機とアプリの動きをつなぐプログラムの力です。

また、AIを使って洗濯物の重さや汚れ具合、使用する洗剤をセンサーが検知し、最適な洗い方を自動で選べる機種も登場しています。プログラムとAI技術の進化によって、全自動洗濯機はさらに便利で使いやすい家電製品へと進化しています。
エアコン

エアコン(エアーコンディショナー)は年々進化して、さらに快適で便利なものになっています。
まわりの温度や湿度を読み取って自動で温度調節するのはもちろんのこと、部屋のどこに人がいるかを感知して、ムダなく快適な室温にしてくれます。
さらにフィルターを自動で掃除できる機種も人気で、ホコリをキャッチしたり排出したりする一連の動作もプログラム制御が支えています。

エアコンが自ら判断して動作することで、手間なく省エネや清潔感を保つ機能が実現します。
ロボット掃除機

重い掃除機を抱えて部屋から部屋へ移動するのは大変ですよね。ロボット掃除機は自分で動く機能が搭載され、壁や段差を感知するセンサーで障害物をよけながら家中を隅々までキレイにしてくれます。
また、掃除するたびに部屋の形や家具の配置を学習できるロボット掃除機もあります。最適な掃除ルートを記憶するプログラムがあるため、使うほど効率がアップするのが特徴です。

まるで自分の意志で動いているかのように見える動きも、あらかじめプログラムに書きこまれているからできることなのです。
AIスピーカー(スマートスピーカー)

スマートフォンに「明日の天気は?」と話しかけると、すぐに天気予報を教えてくれる機能を使ったことがありますか?声を認識し、質問に合った情報を回答する仕組みも人工知能やプログラムによるものです。
さらに進化したスマートスピーカーでは、声で家電を操作できます。たとえば「照明を明るくして」と言うと照明の明るさを調整したり、「エアコンを2度上げて」と話しかけると指定の温度に変更したりなど、さまざまな操作が可能です。
音声コントロール機能はさまざまな家電に使われており、最近ではリモコンに話しかけるだけで見たい番組や動画を検索できるテレビ用リモコンも販売されています。

音声を受け取り、指示を家電に伝える機能もプログラムの力で実現しています。
ゲーム

Minecraft(マインクラフト)のような広い世界を自由に冒険できるゲームも、ゲーム機のプログラム制御によってスムーズに動く仕組みです。
キャラクターがたくさん登場し、広いマップを移動したりしても快適に遊べるのは、複雑なプログラムが支えているからです。
「将来、自分でゲームを作ってみたい」と思うお子さんも多く、ゲームをきっかけにプログラミング教育を始めるケースも増えています。キャラクターの動きやゲームのルール、プレイヤーとのやり取りなど、すべてがプログラムによって作られているため、ゲーム制作にはプログラミングが欠かせません。
マインクラフト(マイクラ)が子どものプログラミング教育にぴったりなことをご存知でしたか?この記事ではマイクラが教育に最適な理由と、具体的に身につくスキル、マイクラを使ったプログラミング教室についてまとめました。
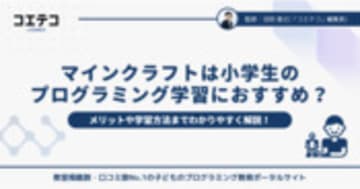

2025/11/17

自動車

自動車が安全に動くための仕組みやルールも、すべてプログラムで設計されています。
最近では車が自分で走る自動運転技術も進んでおり、目的地までの道を認識しながら安全に運転する機能も増えてきました。車に搭載されたセンサーが周囲の状況を読み取り、プログラムが障害物を避けたり、スピードを調整したりしてスムーズに運転できるよう制御しています。

プログラミング技術の進化が、自動車をますます便利で安心なものにしていると言えます。
自動改札機

今では主流になった自動改札機。ICカードやスマートフォンを機械にかざすだけで瞬時に情報を読み取り、素早く処理してくれます。
足し算や引き算などの計算はコンピュータの得意分野で、残高の確認や引き落としもあっという間に完了します。駅の混雑時でも利用者がスムーズに通過できるのは、計算処理をはじめとした制御をプログラムによって正確におこなっているからです。
自動販売機

自動販売機は、私たちがおこなう操作に応じてさまざまな仕組みが働く機械です。
たとえば100円を入れると、センサーが硬貨の厚さや大きさといった特徴をチェックして金額を認識します。その後硬貨の情報がコンピュータに送られ、購入できる商品のランプだけが点灯する仕組みです。自動販売機の一連の流れは、コンピュータとプログラムの力で制御されています。
最近の自動販売機は現金だけでなくICカードやスマホ決済にも対応しており、さまざまな支払い方法で購入できます。便利で柔軟な対応も、プログラムの力によって支えられています。
まとめ:プログラムの未来とプログラミング教育の必要性
私たちの身の回りには、コンピュータとプログラムの力によって使いやすく進化したものがたくさんあります。いったい次はどんなものが、どんなふうに進化するのでしょうか?
これからもプログラムによって、わたしたちの「こんなことができたらいいな」が次々と叶えられていくことでしょう。新しい時代に適応するためにも、子どもの頃からのプログラミング教育が必要なのです。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
プログラミング教育とは?定義・目的・必修化の理由と子どもが育む3つの力
プログラミング教育が必修化されて数年が経ちましたが、子どもたちがどのようなことを学び、将来にどうつながるのか、気になっていませんか。プログラミング教育は単なる技術の習得ではなく、論理的...
2025.10.02|大橋礼
-
IoTとは?身近な活用例から教育への影響までわかりやすく解説
IoTは「モノのインターネット」と呼ばれ、家電や車、学校の設備などがネットにつながることで暮らしや学びを便利にしています。実は教育現場でも、IoTが子どもたちの学習環境づくりに役立って...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
プログラミングで「開け!宇宙のとびら!」~第4回 宇宙時代到来!でもその前に「AI(人工知能)時代」への心構えはで...
AI(人工知能)を使ったシステムや製品がどんどん開発されている今、これからの子ども達にはAIを扱える技術力が求められています。今回は「子どもの理科離れをなくす会」で行われている、AI時...
2025.05.30|北原達正
-
クラウドとは?基本の仕組みから子どもへの影響、安全な使い方まで徹底解説
スマートフォンやタブレットが普及し、子どもたちの生活にも「クラウド」が自然に入り込む時代になりました。家庭や学校で活用される一方、仕組みや安全性がよくわからず不安に感じる保護者も少なく...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
プログラミング教育で論理的思考力を鍛える!子どもの未来を切り開く学びとは?
プログラミング教育の目的は「論理的思考力」を育てること。でも、「論理的思考力」ってそもそも何なのでしょうか?「相手を思いやる能力」でもある論理的思考力は、これからの時代に欠かせない力。...
2025.06.24|プログラミング教室ガイド