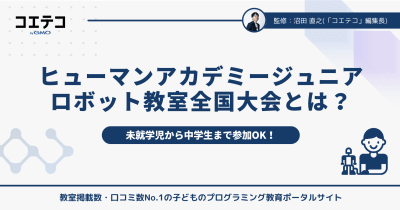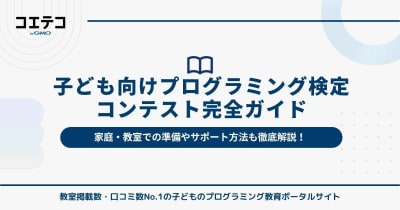小学生向けプログラミング大会一覧:ロボット・アプリ・ドローン…未来を切り開くスキルアップの場

※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
ただ淡々とスクールで授業をこなすだけではなく、さらに高みを目指すには実戦を積み、負けたくやしさや成功した嬉しさなどをバネに成長し、実力をつけていきたいですね。
この記事では、子ども向けのプログラミング大会・コンテストの種類や実際に開催されている大会について詳しく紹介します。
子ども向けのプログラミング大会・コンテストにはどのような種類がある?
子ども向けのプログラミングの大会・コンテストは、大きく分けて4つの種類があります。以下で、それぞれの大会の特徴について解説します。ロボット
アイデアに溢れた独創的な作品が求められるのは、ロボットコンテストです。子ども向けのロボットコンテストでは、テーマがなく自由に作成できるコンテストが多くあることが特徴です。ロボットコンテストにエントリーされるのは、困っている人を助けるロボットや動物を模したロボットなど、形や種類もさまざまです。
材料が決められていなければ、ストローや紙、毛糸や発泡スチロールなど、自宅にあるものを使ってロボットを制作できますね。
アプリ制作
スマートフォンには、SNSやゲーム、地図など豊富な種類のアプリがあります。アプリ制作の大会では、既存のアプリにはない、新たなアイデアが詰め込まれた作品が多数応募されます。アプリ制作の大会に参加するなら、「困っている人の役に立つ」「隙間時間を利用して楽しめる」など、目的を明確にしてアプリを制作するようにしたいですね。
プログラミング言語は、iPhone向けのアプリならSwift、Android向けのアプリならJavaが多く用いられます。学校やスクールで習ったプログラミング言語を用いて、アプリという形にできる喜びを体験してみましょう。
ドローン
ドローンの大会は、初心者向けの大会からドローンレースを体験している上級者向けの大会まで開催されています。ドローンのレースは、年齢問わず同じフィールドで戦えることが強み。決勝大会で小学生の参加者が大人と対戦し、小学生が優勝した大会もありました。指先で繊細に操縦することが必要となるドローンは、大会に出場するために地道な練習を重ねることが大切です。スピードを競い合うレースや障害物を避けるレース、ドローンのプログラミングを行うレースなど、大会によって内容もさまざまです。
その他
その他には、プログラミングのスキルを競い合う大会があります。なかには、大人顔負けの高度なプログラミングスキルが求められるハイレベルな大会も。コーディングのスキルをゲームのなかで競い合う、ユニークな大会もあります。プログラミングやコーディングのスキルに自信がある人は、腕試しに参加してみても良いですね。
プログラミングスキルを競い合える大会は、エンジニアを志す子どもからも人気を得ています。
誰でも参加できる?
子ども向けのプログラミングの大会は誰でも参加できるのか、気になるポイントですね。以下で、大会の参加資格について詳しく解説します。大会ごとに参加資格が異なるので注意
各大会によって、参加資格は異なるので注意しましょう。基本的には学年や年齢などで分けられることがほとんどですが、子どもから大人まで幅広く参加できる大会もあります。「大人と一緒だと、自分の作品が埋もれてしまう?」と不安になる参加者もいますが、上級者の作品や実力を間近で見られるメリットも。
過去には、子どもが大人顔負けの実力を発揮して優勝した大会もあるので、自身のスキルを試したいと思ったときには、是非参加したいですね。
スクール在籍生のみの大会もあれば、誰でも参加できるオープン大会もある
プログラミングスクールが主催している大会のなかには、スクール在籍生のみが参加できる大会があります。多くの大会は誰でも参加できるオープンな大会となっていますが、応募する前に参加資格を必ず確認しておきましょう。費用はどのくらいかかる?
ロボットプログラミング大会の出場費用は、出場する大会によって大きく異なります。無料で参加できる大会もあれば、数千円から数万円の参加費が必要な大会もあります。大会出場前にチーム登録料が必要なものもあるため、事前に確認しておくことが大切です。大会参加にかかる費用は、出場費用だけにとどまりません。使用するロボットキットの購入費用や、練習会場への交通費、場合によっては遠方での大会に参加するための宿泊費や食事代など、関連費用が積み重なることで、総額が高額になることもあります。
それでも、多くの人がロボットプログラミング大会への挑戦を選ぶのは、次のような多くのメリットがあるからです。
- 課題を解決する過程で、創造力や論理的思考力、プログラミングスキルが磨かれる
- チームで役割を分担し、協力してプロジェクトを進めることで、コミュニケーション能力や協調性を養える
- 努力が形になり、大会で成果を発表することで、達成感や自己肯定感を得られる
- 共通の目標に向かって取り組むことで、仲間と絆を深められ、他の参加者とも交流が広がる
- 大会での実績は進学時や将来のキャリアにおいても評価されることがある
このようなメリットがあることから、ロボットプログラミング大会への挑戦は、費用や時間をかけるだけの価値があります。得られた経験は子どもたちにとって一生の財産となり、将来の可能性を大きく広げるでしょう。
実力を試せる!全国のロボットコンテスト6選
ここでは、ロボット制作の実力を試したい方にピッタリのロボットコンテストをご紹介します。FIRST LEGO LEAGUE|ロボット制作とプレゼンスキルを試せる!
FIRST LEGO LEAGUEは、日本では2003年からはじまった小学生~高校生までが対象のコンテストです。年齢別に3つのカテゴリーに分かれています。LEGOを用いたロボットコンテストですが、チームとしての活動やプレゼンテーションを重視した内容で、日本大会を勝ち抜くと世界へも挑戦することができます。
STEMやロボットの知識を習得できるだけではなく、社会人になってから必要となるチームビルディングやプレゼンスキル力も試したい子は必見です。
ロボットプログラミングの大会といえば、世界的に有名なレゴ®︎ブロックを使用する大会「FLL(First LEGO League、ファースト・レゴ・リーグ)」。参加資格や難易度、おすすめスクールを詳しく解説します。
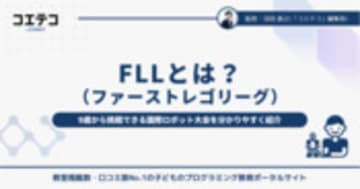

2025/05/26

WRO(World Robot Olympiad)|レゴ教材を使った国際的ロボットコンテスト
WRO(World Robot Olympiad)は、2004年から開催されている国際的なロボットコンテスト。教育的なロボット競技の挑戦を通じて、幅広い年齢層の創造性や問題解決力の育成を目的としています。2024年大会における競技種目は以下のとおりです。
- RoboMission(エキスパート競技、ミドル競技、ベーシック競技)
- Future Innovators
- RoboSports
- Future Engineers
Japan決勝大会ではベーシック競技を除く4つの競技が実施されます。さらに決勝大会で選抜されると、日本代表として国際大会への出場権を獲得できます。
大会に参加するロボットについては、チームでオリジナルのロボット戦略を考えることが条件です。ロボットを通じて世界レベルへの挑戦を考えているお子さんは、ぜひ挑戦してみましょう!
2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されるにあたって、子ども向けのプログラミング教室への関心が高まりを受け、プログラミングを習い始めるお子さんが増えていますね。 プログラミングを習っているお子さんが出場できる大会「WRO」について参加資格や難易度を詳しく解説します。


2025/05/26

スペースロボットコンテスト|JAXAのフライトディレクターが審査員!
スペースロボットコンテストは『子どもの理科離れをなくす会』主催のコンテスト。自律型ロボットでさまざまな課題をこなし、優勝者には賞金が贈られます。競技では実際に月面基地をイメージしたコースに挑戦でき、毎年変わるテーマに合わせて成功や失敗の経験を積めます。普段会わない子ども達との交流も楽しめるでしょう。
毎年、JAXAのフライトディレクターが審査と講演もしてくれるので、宇宙に興味のある子は参加してみましょう。
『子どもの理科離れをなくす会』主催のコンテスト。自立型ロボットでさまざまな課題をこなしていき、優勝者には賞金が贈られます。毎年、JAXAのフライトディレクターが審査と講演もしてくれるので、宇宙に興味のある子には必見です!


2025/05/26

ロボカップジュニア|日本で勝ち抜き世界へ挑戦!
ロボカップジュニアは1997年から開催されている「ロボカップ」のうち、11歳以上19歳以下を対象にしたジュニア部門の大会です。当日は子どもたちが設計・プログラムしたロボットを使い、3種類の競技テーマ(サッカーリーグ、レスキューリーグ、OnStageリーグ)で競います。
ノード大会(地区予選)、ブロック大会、日本大会を勝ち抜くと「ロボカップジュニア世界大会」 にも参加できるという本格的なもので、ワールドクラスのロボットを見ることができるのも魅力のひとつです。
1997年から開催されている「ロボカップ」の19歳以下を対象にした、ジュニア部門の大会。ノード、ブロック、日本大会を勝ち抜くと「ロボカップジュニア世界大会」 にも参加できるという本格的なもので、ワールドクラスのロボットを見ることができるのも魅力の1つです。
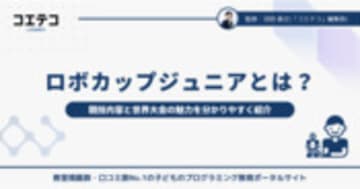

2025/05/26

全日本小中学生ロボット選手権|大会だけじゃない!最先端ロボットも登場
和歌山県御坊市で毎年開催される全日本小中学生ロボット選手権は、総じて「きのくにロボットフェスティバル」として県内外の方が集まります。小中学生向けで、市販のロボキットで参加できることが特徴です。和歌山工業高等専門学校が実行委員会事務局を務めており、高専ロボコン出場チームや最先端ロボットのデモンストレーションも開催されます。ロボット好きの子はぜひチェックしてみては?
ヒューマンアカデミーロボット教室全国大会|未就学児から参加できる!
ヒューマンアカデミー株式会社が主催するのは、ヒューマンアカデミーロボット教室全国大会です。大会では、「アイデアコンテスト」と「テクニカルコンテスト」の2部門があります。アイデアコンテストは年齢に合わせて4つの部門に分けられています。テクニカルコンテストは、アドバンスコースの受講生(18歳以下)であることが参加資格となっています。
スクールで使用しているロボットキットを使用できるため、新たに材料を用意する必要がないことが嬉しいポイント。2024年のテクニカルコンテストではロボットを使ってカップラーメンの容器に麺・具材(パーツ)を入れることが競技テーマとなっており、ユニークなテーマに子ども達も夢中になること間違いなしです。
2011年から始まったヒューマンアカデミーロボット教室全国大会は、参加者の豊かな発想力でロボットが制作されることで注目を集めています。この記事では、ヒューマンアカデミーロボット教室全国大会の特徴や過去の大会の様子などを詳しく解説します。
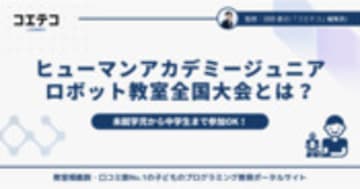

2025/06/11

アプリ制作コンテスト3選
人気の「アプリ制作」をテーマにしたコンテストも開催されています。アプリを使ったり作ったりするのが好きなお子さんはぜひチェックしてみてくださいね!全国小中学生プログラミングコンテスト|発想力・表現力・技術力を競う
全国小中学生プログラミングコンテストは株式会社角川アスキー総合研究所などが主催する、全国規模の小中学生対象コンテストです。PCやスマートフォン、タブレットで動くプログラムやアプリ、ゲームやムービー(ソフトウェア部門)、またはロボットや電子工作(ハードウェア部門)を制作・発表し、「発想力」「表現力」「技術力」 を競います。
これまでに累計3000以上の作品が応募され、AI解析やIoT、VRなど多岐にわたるテーマに触れられるコンテストです。
「全国小中学生プログラミングコンテスト」は、株式会社角川アスキー総合研究所などが主催する、小中学生対象のコンテスト。 PCやスマートフォン、タブレットで動くプログラムやアプリ、ゲームやムービー(ソフトウェア部門)、またはロボットや電子工作(ハードウェア部門)を制作・発表し、「発想力」「表現力」「技術力」 を競います。
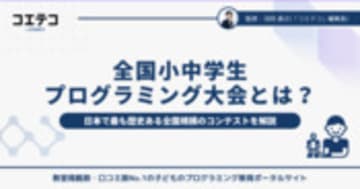

2025/05/26

PCNこどもプログラミングコンテスト|すべてのこどもにプログラミングの機会を
PCNこどもプログラミングコンテストは、PCN(プログラミング・クラブ・ネットワーク)主催の小中学生向けコンテストです。ソフトウェア部門とロボット・電子工作部門があり、オリジナルの作品であればジャンルや言語、作成ツールは自由に選べます。
2024年大会では、応募総数297作品よりノミネート作品に選ばれた25作品の紹介動画が審査の評価と共に公開されました。応募作品の名前が公式サイトに掲載されるので、ものづくりの達成感も味わえるでしょう。
アプリ甲子園|クリエイティブ力をカタチにしよう
中高校生向けのスマートフォンアプリ開発コンテストでしたが、現在は小学生も参加できるようになったアプリ甲子園。エントリーは企画書とアプリのデモ動画で行われ、審査を通過した作品は最終審査会でプレゼンテーションをおこないます。独創性や新規性、技術やデザイン、さらに消費者からの支持度も考慮して審査され、大人顔負けのアプリをプレゼンする子ども達も多い大会です。
ドローンコンテスト・大会2選
近年注目度が高まるドローン関連のコンテストについても見ていきましょう。JAPAN DRONE LEAGUE|ハイレベルなドローンレースが楽しめる
レースを行うためのミーティングも開催しているのは、JAPAN DRONE LEAGUEです。大会ではスキルに合わせて、プロクラス・エキスパートクラス・オープンクラスの3つに分けられています。レースに使用できるドローンの機体には、レギュレーションが細かく定められています。参加を検討している際には、フレームやモーターなどの規定を確認しておきましょう。
ドローンの技術とスピードを競うことで、スポーツコンテストのような雰囲気のこの大会。日本国内外からの注目を集めており、新たなドローン愛好者の育成にも繋がっています。
JAPAN DRONE LEAGUEは、日本各地からプロのパイロットが集結するハイレベルなドローンレースです。小学生が優勝を収めたことでも注目を集めている大会だといえるでしょう。参加する際には、機体レギュレーションなどをチェックしておくことが重要です。この記事では、JAPAN DRONE LEAGUEの特徴や参加資格などを解説します。


2025/08/05

(開催終了?)JDSFドローンレース|世界基準の技術で競う
JDSFドローンレースは、世界基準の日本プロドローンリーグの設立・運営をおこなうJDSF(日本ドローンスポーツ連盟)主催のドローンレースです。個人戦・チーム戦のどちらも実施され、出場した競技会で獲得したポイントの上位3戦分が最も多い選手とチームは年間チャンピオンとして表彰されます。
JDSF(日本ドローンスポーツ連盟)は、ドローンスポーツを通じてドローン業界の発展と普及、ドローン操縦技術の向上を目的として世界基準の日本プロドローンリーグの設立・運営を団体です。

https://japandronesports.com/ >
JDSF Official Cup|革新的な競技「ドローンサッカー」を楽しもう!
JDSF Official Cupでは、ドローンが球を操作するサッカーの要素を取り入れたゲームで競います。ドローンサッカーをとおして技術の進化はもちろん、エンターテインメント性の向上も期待されます。未来の技術とスポーツの融合を楽しめるでしょう。2025年10月には韓国仁川で第1回ワールドカップが開催されます。国内では日本代表チームの育成・選出に力を入れており、今注目の競技のひとつといえます。
日本ドローンサッカー®連盟の2024年度 JDSF 公式戦・認定戦スケジュールについて

https://japan-dronesoccer.com/news/game/14638/ >
その他のコンテスト6選
その他にも、全国各地ではさまざまなプログラミング関連コンテストが開催されています。興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。U-22プログラミング・コンテスト|テーマは自由!ステップアップを狙おう
小学生でも参加できるのは、U-22プログラミング・コンテストです。応募する作品は、未応募のオリジナル作品であれば、ジャンルやプログラミング言語は問いません。作品は、プロダクト・テクノロジー・アイデアの3つのカテゴリーで審査されます。テーマは自由であるため、ゲームやAIなど幅広い作品を制作することが可能です。
最高賞は経済産業大臣賞の賞金50万円が授与され、未踏事業への推薦が受けられるなど、ステップアップの道も用意されています。コミュニティに参加することで、エンジニア同士で交流を持てることもU-22プログラミング・コンテストの強みです。
HSPプログラムコンテスト|WebDish素材を上手に使おう
プログラミング言語のHSP(Hot Soup Processor)を用いて制作した作品を応募できるのは、HSPプログラムコンテストです。応募作品はすべて無料でダウンロード可能であるため、過去の作品をみることもできます。2003年から続く大会で、長年にわたってプログラミングの楽しさを広く知ってもらうことを目的に開催されています。技術の優劣を競うことが目的ではないため、上級者はもちろんはじめてHSPを使う方も年齢問わず応募できます。
応募できるプログラムは、一般プログラムとWebブラウザ実行プログラムの2部門。WebDish素材と呼ばれるアイコンやイラストなどは、作品のなかで自由に使用できることがメリットです。
全国選抜小学生プログラミング大会|小学6年生まで!自由な発想で作品を作ろう
社会課題の解決につながる作品が多数応募されるのは、全国選抜小学生プログラミング大会です。2024年度全国大会のテーマは「みんなのみらい」で、自分や大切な人、地域にとっての明るい未来に役立つアイデアが評価のポイントです。応募資格は小学6年生までで、作品に使用するプログラミング言語は限定されていません。ドローンやアプリ、映像など、さまざまなジャンルの作品を応募可能です。
作品は、発想力が40点、表現力30点、技術力30点の100点満点で審査されます。発表時間の3分間で、作品に対する思いや工夫・苦労した点などをプレゼンテーションする必要があります。
TECH KIDS GRAND PRIX|フィードバックがもらえる
直近の大会で3,122もの作品がエントリーしたのは、TECH KIDS GRAND PRIXです。小学生のためのプログラミングスクール「Tech Kids School」が大会を主催しています。エントリー可能なのは、コンピュータプログラミングを用いて開発されたオリジナル作品に限ります。小学生であれば誰でも応募可能であるため、参加しやすさが魅力といえるでしょう。参加者全員に「参加証明書」と作品に関するフィードバックがもらえることも、参加するうえで嬉しいポイントです。
「21世紀を創るのは、君たちだ。」をテーマにした2023年大会の様子は、以下のページからチェックしてみてくださいね。
日本最大級の小学生プログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2023」。大会のテーマは『21世紀を創るのは、君たちだ。』です。「プログラミングを小学生から学ぶメリットって何?」と思っている保護者の皆さん、今大会の模様をぜひご覧ください。


2025/05/30

(開催終了?)PG BATTLE|プログラミングの知識を競い合える
PG BATTLEは1チーム3名でおこなわれる企業・学校対抗プログラミングコンテストで、小学生から大人まで参加可能です。競技では出題された問題を解くプログラムを90分間に4つ書いてオンライン提出し、豊富な知識やスキル、臨機応変に対応できる力を競います。各部門、1位に入賞すると24万円が授与され、スポンサー賞や個別賞なども用意されています。直近の2023年大会では全361チーム・1,083名が集結しました。
天下一Game Battle Contest|豪華な副賞も魅力のコンテスト
年齢問わず個人でも参加できる天下一Game Battle Contestは、運営側に提供されたサーバと通信するプログラムを作成・実行し、ゲームの得点を競い合います。HTTPSによる通信ができる必要がありますが、プログラミング言語の制限は設けられていません。1位にはギフトカード100,000円分が授与されますが、発送先は日本国内のみであるため、注意しましょう。なお、直近の大会は2023年9月23日に開催しており、YouTube配信されています。
運営側がゲームAPIサーバを提供し、参加者はサーバと通信するプログラムを作成・実行し、ゲームの得点を競う形式のプログラミングコンテストです。 問題概要は github.com/KLab/tenka1-2023 にあります。 ⚠️ 重要なお知らせ ⚠️ 天下一 Game Battle Contest 2023 では、前回開催の 天下一 Game Battle Contest 2022 ...

https://tenka1.klab.jp/2023/ >
ゼロワングランドスラム|全国のキッズプログラマーが集合
キッズプログラマーが一堂に会するゼロワングランドスラムは、日本一の小学生プログラマーを決める全国規模のプログラミング競技大会です。ビジュアルプログラミング競技で使用するツールは「Scratch」で、ロボット競技では「Artec Robo」「KOOV」「SPIKEプライム」の3種類のうち好きなロボットを選んで挑戦します。1回戦はオンラインですが、2回戦以降はリアル大会になります。国内でも活気あるプログラミング大会のひとつで、参加費無料のため気軽に挑戦しやすいでしょう。
小中学生におすすめ!腕試しに大規模大会に参加しよう
小中学生のうちに大規模なプログラミング大会に出場することは、プログラミングスキルを伸ばすだけではなく、子どもにとって大きな財産となります。友人と切磋琢磨することや1つの作品を長い期間かけて制作することで、協調性や創造力なども育めるでしょう。ゲームやロボット、アプリなどさまざまなジャンルのなかから、好みの大会を選びたいですね。
自分の今のレベルにあったものを選び、今よりもさらにステップアップできるように挑戦してみましょう!


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド
-
WRO(World Robot Olympiad)とは?小中高校生が挑戦できる国際ロボットプログラミング大会
2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されるにあたって、子ども向けのプログラミング教室への関心が高まりを受け、プログラミングを習い始めるお子さんが増えていますね。 プログ...
-
ヒューマンアカデミージュニアロボット教室全国大会とは?未就学児から中学生まで参加OK!子どもの創造性を伸ばす
2011年から始まったヒューマンアカデミーロボット教室全国大会は、参加者の豊かな発想力でロボットが制作されることで注目を集めています。この記事では、ヒューマンアカデミーロボット教室全国...

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
【保存版】子ども向けプログラミング検定・コンテスト完全ガイド|挑戦する力を育てよう!
プログラミング学習を続ける子どもたちにとって、検定やコンテストへの挑戦は大きな成長の機会となります。目標を設定し、自分のスキルを客観的に測ることで、達成感や自信を得られます。本記事では...
2025.11.19|コエテコ byGMO 編集部
-
プログラミング教育市場の未来予測 多様化するプログラミング教室 ~急速に進化・展開を見せるプログラミング教育市場の実態~
近年増加している「プログラミング教室」や「ロボット教室」。最近ではプログラミング教育市場が成長拡大していく中で、様々な種類の新しい教室が生まれています。今回は、船井総研の犬塚氏が紹介す...
2025.05.26|犬塚義人
-
レゴ教材を使った国際的ロボットコンテスト『WRO(World Robot Olympiad)』
2004年から開催されている国際的なロボットコンテスト。「LEGO®MINDSTORMS ™を使うこと」が条件で、4つの競技があり対象年齢がそれぞれ異なります。毎年テーマが変わり、当日...
2025.05.26|プログラミング教室ガイド
-
小学生向けプログラミング教室12選【教室掲載数No. 1】2026年最新版
「コエテコ by GMO」は、プログラミング教室掲載数が国内No. 1ポータルサイトでもあり、 実際に利用されている風景や子ども達の声、講師へのインタビューなどを数多く行ってきました。...
2026.01.02|コエテコ byGMO 編集部
-
全国小中学生プログラミング大会とは?自由な発想を形にする子ども向け最大級コンテスト
「全国小中学生プログラミングコンテスト」は、株式会社角川アスキー総合研究所などが主催する、小中学生対象のコンテスト。 PCやスマートフォン、タブレットで動くプログラムやアプリ、ゲ...
2025.05.26|プログラミング教室ガイド