小学5年生の家庭学習ネタおすすめ!親が意識すべきポイントも解説
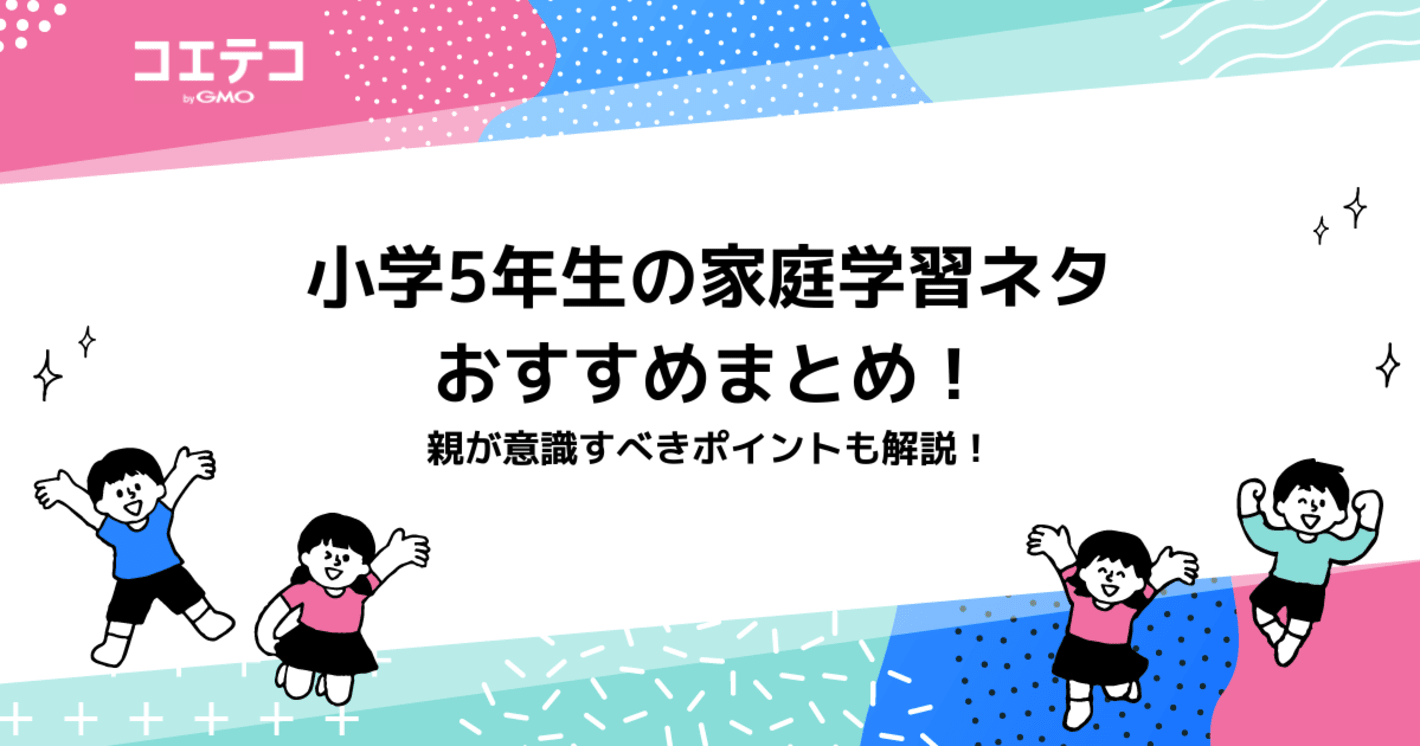
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
そんな悩みを抱える親は多いですね。「うちの子のやる気スイッチはいったい、どこにあるの!?」なんて、ついつい愚痴を言い合うのはママ友同士の会話でよくある光景です。
今回は、小学5年生におすすめの家庭学習ネタを紹介します。
「自ら勉強する気になる」家庭学習の環境づくりについて、親が意識すべきポイントもまとめているのでぜひチェックしてみてください。
小学5年生向け家庭学習教材おすすめ3選
学習習慣を身につけるには、家庭学習に役立つ通信教材を活用するのもおすすめです。ここでは家庭学習ネタになる小学5年生向けの通信教材を紹介します。
下記記事でも小学生の家庭学習方法についてご紹介しています。
おすすめ教材を知りたい方は、下記記事もあわせてご覧ください。
小学生の家庭学習方法は?おすすめ教材まとめを徹底比較
進研ゼミ小学講座

進研ゼミ小学講座は、その日に学ぶべき内容をタブレットで自動提案するのが特徴です。
学習習慣を身につけるとき、やるべきことが何か分からないと「今日は何をすればいいんだろう…」と始める前につまずいてしまいかねません。
提案は実力に合わせて行われるため、難しすぎて挫折する心配もない内容です。
学んだ内容を忘れた頃合いで提案される「とき直し」と、振り返り学習ができる「さかのぼり」も特徴といえます。
理解しにくいところは何度でもチャレンジし、苦手を残さない仕組みです。
子どもが毎日学習に取り組んでいるかは、メールでチェックできます。
励ましのメッセージで頑張りを褒めれば、学習に対する意欲アップにつなげられることも期待できます。
東進オンライン学校小学部

基礎をじっくり学ぶ標準講座と、応用力を身につけられる演習充実講座から構成されているのは、東進オンライン学校小学部です。
各教科を専門としている講師陣による分かりやすい授業で学習し、確認テストで理解度をチェックする構成で、分かったつもりを残しません。
標準講座は算数、国語、理科、社会の基礎固めができる内容です。
応用問題も解ける学力を身につけるには、算数と国語を教科書の範囲を超えて学べる演習充実講座を選びましょう。
毎日配信される算数のトレーニングもポイントです。90点以上で1ポイント獲得できる仕組みになっており、学習を継続するモチベーションにつながります。
すらら

子どものスピードに合わせて学習を進められる通信教材を選びたいなら、すららが向いています。
無学年式のオンライン教材で、学年をさかのぼって苦手な箇所に取り組み、基礎から学べるのが特徴です。
また得意な教科はどんどん先へ進むこともできます。
「頑張ると良いことがある」と実感できる、トークンエコノミー方式を取り入れているのも特徴です。
目標に向けて学習することでトークンを受け取り、トークンが貯まると欲しいものをもらえます。
分かりやすいご褒美で、自発的に勉強する姿勢が身につくでしょう。
AIによる学習サポートで、家庭教師がそばにいるかのように学べるのも特徴です。
小学5年生・6年生の家庭学習のやり方とは?環境づくりで意識したい5つのポイント
家庭学習のやり方- 勉強するスペースを決める
- やる気のでる「声かけ」を心がける
- 学習スケジュールを親子でたてる
- 学習方法を工夫する
- 褒めて褒めて感心して感激する!
「家庭学習の環境」とは、勉強に集中しやすい環境づくりという面だけではありません。
家庭学習をする子どもに影響を与えるであろう「子どもを取り巻くさまざまなこと」を意味します。
小学生の家庭学習は、大前提、習慣化するまで継続することが大切です。
今回の記事では、家庭学習を習慣化させるために重要な上記5つのポイントについて詳しく解説します。
その前に、次の調査結果を見てください。

上記は子どもの学習を見る際に実際に「親が行っていること」の回答です。
過去2年と比較して「怒るよりほめることを大切にしている」の回答がわずかながら増えています。
それ以外を見ても、親がさまざまな学習サポートを行っていることがわかります。
小学1年生の家庭学習については下記記事で詳しくまとめています。
小学1年生から家庭学習を行うメリットやおすすめ教材も紹介しているので、
小学1年生の家庭学習!おすすめ教材まとめと勉強法を徹底解説
家庭学習のポイント①勉強するスペースを決める

まずは勉強するための場所を決めましょう。
子どもの気分によって、あちこちで学ぶのが悪いわけではありません。場所を変えたほうが「暗記しやすい」「集中力が続く」ケースも確かにあります。
しかし、「ここで勉強をする」と決めておく方が習慣づけしやすいメリットがあります。
場所は、ダイニングテーブルでもいいし、リビングの一角に小さめのデスクを用意して学習スペースとしてもいいでしょう。もちろん子供部屋でもかまいません。
いずれにせよ、なるべく気が散らないように、少なくともテーブル・机の上はスッキリと片付いていることが理想。
ダイニングテーブルに、雑誌やら食べかけのお菓子やらが山盛りになっていたら、勉強する気が失せてしまうかもしれません。
教科書やドリルを置き、「その場所」に座ったら勉強モードに入ることを毎日繰り返すのがポイントです。
家庭学習のポイント②やる気のでる「声かけ」

「実際にやる気が出た言葉」のアンケート結果

上記は小学生の子どもに「実際にやる気が出た言葉」についてアンケートをした結果です。
この調査では大切なポイントとして、声がけは「笑顔で言うこと」を挙げています。
「笑顔」が見える = お母さんがこちらを向いて話しかけてくれていること。 日ごろ忙しいお母さんが手をとめて話しかけてくれることが大きなポイント!小学生にとって、身近な存在であり大好きな「家族」を笑顔にすることができた、それが大きな満足や充足になります。
何かうまくいった時にタイミングを外さずに、笑顔で褒めるのはとても大切です。
しかし、勉強をさせたい、やる気を出させたい時には「褒める」以前の段階であることも多いですね。
まずは、こんな声かけをしてみましょう。
「今日はどんな宿題が出ているの?」
「夕飯は7時よ」
「時間割をもう揃えたのね、すごい」
「勉強しなさい」のテッパンフレーズは使わずに、今の状況を子どもが確認できるように声がけをしてみます。
本人が「そろそろやるか」と勉強時間を意識するような言葉をかけてみましょう。
もっとも、これだけで勉強にとりかかってくれる子なら親も心配しませんね。
結局「勉強しなさい」と声をかけることになりかもしれません。そんな時も怒鳴らず、なるべく
「ママはお風呂の準備を始めるわ、○○ちゃんは宿題をやる時間じゃない?」
と、「〜しなさい」ではなく「〜したら?」と問いかける形にしてみましょう。
親が意識したい声がけルーティンはコレ!
子どもが「おお、それなら勉強するぞ!」とスパッとスイッチが入る魔法のコトバはありません。- 笑顔で
- 怒鳴らず
- 問いかけて
- 励まし
- 終わったら認めて褒めて褒めて褒めまくる!
上記を意識してみてくださいね!
家庭学習のポイント③学習スケジュールを親子でたてる

あるいはひとりで留守番する場合も、親の目が光っていないので「なかなか勉強しない」という声もよくあります。
下校時間や習い事などによって子どもの予定は変わるので、おおむね1週間を目安として、ざっくりでよいので学習スケジュールをたててみましょう。

今はいろいろなテンプレートが無料でダウンロードできるので、利用してみてもいいですね。
週間スケジュールはちょっと大変、という方には「今日やることリスト」がおすすめです。今日やることリストは、それこそメモ用紙に
- 算数ドリル3の①
- 漢字ドリル
- 昨日の算数ドリルの直し
- 音読(ママがハンコ)
と、書くだけです。子どもが帰宅したら、まずやることリストを書くのを習慣にします。
そして、できたことから赤ペンなどで消していきます。ひとつずつ消していくことで「これが終わった、できた」という達成感も味わえます。
スケジュールは「たてるだけ」でなく、できたかどうかを確認するのがとても大事です!
小さいうちは、キャラクターのスタンプやシールを用意して、1日の学習がすべて終わったら、親がペタンと貼ってあげると「できた!終わった!」と、やりきった満足感が得られやすいのでおすすめです。
家庭学習のポイント④学習方法を工夫する

小学校のうちは基本はまず宿題です。宿題をきちんとやることは、勉強のやり方を覚えることにもつながります。
- 今日やるべき宿題を把握する
- 順番を決めてひとつずつ行う
得意なことから始める、苦手なものから始めるなど子どもの適性を見て決める - 丸付けや直しなど、最後まで行う
ここまでが基本の基本です。さらにワンステップ進めていきましょう。
自己動機づけ方略で勉強方法を工夫する
「自己動機づけ方略」(学習に向けて自らの意欲を高めるために用いる方法のこと)の活用です。
青い棒グラフは「勉強のやり方を理解している」子どもで、グレーは学習方法が不明という子どもを対象としています。
学習方法を理解している子どもたちは、全体的に「いろいろな学習法を行っている」特徴が見えてきます。
この調査では「自己動機づけ方略」(学習に向けて自らの意欲を高めるために用いる方法のこと)を次のように分類しています。

たとえば「解き直し方略」は、間違った問題を繰り返すことで学力を定着させることが狙いです。
宿題を終えたら、前日の宿題で間違えたところやできなかったところを、家庭学習で復習すると知識が定着します。
他にも「この問題について、ママに解き方を教えて」と問いかけたり、メリハリ方略を活用して「30分勉強がんばって、その後はお風呂までゲームやる」と勉強と遊びの予定を一緒に決めたりする方法もあります。
上記を参考にして「うちでもできることはないかな?」と考えてみませんか?
家庭学習のポイント⑤褒めて褒めて感心して感激する!

しかし「そもそも褒めたくても褒められないんだから、どうしたらいいの!」という悩み、実は多くの親が経験していることです。
そこで、ちょっと視点を変えてみましょう。「褒めたくても褒められない」のは、結果を重視しているからです。
テストの結果が思わしくなかった場合、「ほらやっぱり!昨日あれほど勉強しなさいって言ったのに!」「もったいない、ちょっと復習しておけば100点とれたのに」とため息まじりの恨み節になりがち……。
でも、結果に至る過程の中に、ひとつは褒められることが見つかりませんか?
たとえば「ここのところ、毎日宿題しっかりやっていたのはよかったと思うよ」「字が丁寧に書けるようになったね」「ドリルを休まず続けてるのは偉いよね」と褒めて、「きっと次は結果に出るよ」と笑顔で励ましてあげましょう。
正直なところ「なにコレ!60点とかありえないんですけど!」とわたしも声を荒げたことはあります。
親の気持ちはよくわかります。笑顔なんぞになれるかい!?と思うけれど、ひとつ深呼吸をして、せめて怒鳴るのはやめましょう。
小学5年生・6年生の家庭学習は「学習習慣」をいかに続けるかが重要

「大人に言われなくても自分から進んで勉強する」「机に向かったらすぐに勉強にとりかかる」割合は5~6割程度で、学年が上がると割合も下がる傾向がみられる。特に小1から小2にかけて低下しており、小1での学習習慣をその後も維持する大切さがうかがわれる。小学校入学時は親子ともに「さぁ小学生になった、勉強もがんばろう!」と、やる気いっぱいでがんばるものです。ところが、早い子どもだと夏休みあたりで生活リズムが崩れると共に、家庭学習の習慣も少しずつズレてくるようです。
引用:子どもの生活リズムと健康・学習習慣に関する調査2022報告書/早稲田大学・ベネッセ教育総合研究所
学年が上がるにつれて、親の声がけも難しくなります。子どもが反抗的になったり、自らの意思を主張することが増えてくるからです。
よく「ご褒美作戦はよくない」と言われます。「これができたら○○を買ってあげる」ではなく、「これが終わったらゲームの時間」とか「今週はママが声をかけなくても、宿題や勉強をしっかりやったから、漫画1冊を特別プレゼント!」くらいのことは、いいのではないでしょうか。
モチベーションを保ち続けるのは、おとなでも大変です。あの手この手で「とにかく続けること、やがて当たり前になること」をめざして、親も忍耐強く頑張りたいところですね。
問題や課題ができずに投げ出してしまわないように
学年が上がると、学習内容がわからなくなり、やる気を失うケースも増えていきます。わからない問題を放置しておくと、次からもっとわからなくなる悪循環に陥りがちです。
宿題や問題を解くのに時間がかかっていたり、イライラしだしたりしたら、親も手を止めて「一緒に解いてみようか」と声をかけてみましょう。
ドリルによっては巻末に解説が掲載されています。また教科書を読み直すことで基本問題の解き方からヒントを得られることもあります。
最近は動画解説なども多く出ています。似たような問題を探して親子で視聴しながら「ここはこうじゃない?」と考えるのも良い方法のひとつです。
いわゆる「勉強ができる子」は、ひとりでもわからない問題を放り出さずに、自分で考えたり、調べたりして解答にたどりつきます。
とはいえ、最初はなかなかそうはいきません。ですから親が一緒に調べて、どう「わからない」を「わかった!」にしていくか、プロセスを体験させてあげることが大事です。
下記記事では中学受験に向いてる子どもの特徴について解説しています。
中学受験を検討しているご家庭や、子どもが行き詰まったときのサポート方法について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
中学受験に向いてる子の特徴!向いていなけば諦めた方がいいのか解説
親の学ぶ姿も見せる

子どもが勉強する時間を家事にあてている方も多いでしょうし、時間の都合でどうにもならないかもしれません。
それでも、もし10分時間があるなら、きりのいいところで子どもの側に行き、仕事の資料を読むとか興味のある本を読む、パソコンを広げて調べ物をする、親も「学びの姿勢」を見せられるといいですね。
確かに夕方は忙しくてそれどころでないのが現実です。まして兄弟姉妹がいれば、そのお世話もあるでしょう。
毎日が無理でも、たとえば週末だけは子どもの勉強時間に合わせて、同じスペースで落ち着いて読書や調べ物をしてまとめるといったことをしてみましょう。
「勉強ができる子は親が高学歴」は「親が学習環境の作り方を知っている」から!?
いわゆる高学歴の両親を持つ子どもは、同じように高い学歴を得られることが多いという現象について耳にしたことがあるのではないでしょうか。
引用:教育格差について考えるデータ/ベネッセ教育総合研究所
上記の調査結果では、SES(社会経済的地位)による「差」の調査結果です。
SESは、世帯年収や両親の学歴、職種などから、「H層(もっとも高い)」から「L層(もっとも低い)」で子どもを育てる環境にどのような違いがあるのかを示しています。
学校の成績を見ると、確かに両親の学歴や年収が高い層は成績上位にある子が多いですね。
- 高学歴=高収入のことが多いため、塾や文化的体験をさせる割合が高い
- 自身も受験などを通して得た「学習スキル」がある
- 勉強の大切さや進学について子どもに伝えている
- 勉強の面白さを教える(興味や関心を引き出すような働きかけをしている)
- 勉強計画の立て方など具体的に教えられる
要するに子どもの学習への関与は、学歴が高いほど自分の経験を伝えやすく、幼児期から積極的に学習環境に関わる傾向が強いということでしょう。
ただし、親の学歴が低いとか経済的な余裕がないとしても、逆に言えば上位や中位の成績をとっている子も大勢いるのだとも言えます。
特に高校生になると、その差は縮まってきます。
学歴云々の影響があるのは事実でしょう。
でも、家庭学習を習慣づけるのは、どのおうちでも少し意識して、忍耐強く子どもと向き合っていけば、不可能ではありません。
小学5年生・6年生の家庭学習を親がサポートすることは大事!
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。ずばり、親は「子どもの教育について責任がある」と法律が定めているのです。
出典:教育基本法/文部科学省
親として「子どもの教育を考える」のは当たり前のことです。
成績を良くしたいと思うのも当然ですが、まずは「自ら勉強する習慣」をつけるために親としてできる限りの環境を整えてあげたいですね。
自学自習の力を持つ子は、中学高校のみならず、勉強に限らず、生涯において学び続けられることでしょう。
やる気のない態度にイライラするのは、多くの親が経験しています。
そこであきらめてしまわずに、子どもをその気にさせて、試行錯誤をしながら「わが家の家庭学習のやり方」を作り上げていくのも、大切な親子の共同作業ではないでしょうか。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

WRITERこの記事を書いた人
塾・家庭教師ガイド
-
おすすめの塾・家庭教師一覧
-
小学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育
-
中学生におすすめの塾・家庭教師・通信教育
-
高校生におすすめの塾・家庭教師・通信教育
-
不登校の子どもにおすすめの塾・家庭教師・通信教育
RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
小学1年生の家庭学習!おすすめ教材・ドリル8選も徹底比較
小学1年生になり「勉強がんばる!」と、やる気に満ちあふれているときは、家庭学習を始めるチャンスです。この記事では、小学1年生におすすめの家庭学習教材5つとともに、教材の選び方、家庭学習...
2025.12.03|コエテコ byGMO 編集部
-
【11選】中学生におすすめの家庭学習教材とは?4つの選び方と習慣にさせるコツ
家庭学習をしていても、すぐに集中力が途切れてしまう中学生は少なくありません。そんなときには、家庭で利用しやすい教材を導入することがおすすめです。この記事では、家庭学習に集中するためのポ...
2026.01.28|コエテコ byGMO 編集部
-
進研ゼミ小学講座の評判・口コミ!意味ないのか徹底解説
小学生向けの通信教育として圧倒的な人気を誇る「進研ゼミ小学講座」。テレビやDM等で目にする機会も多いことから「うちでも使ってみようかな」と考える人もいるのではないでしょうか。その際、本...
2026.01.11|コエテコ byGMO 編集部
-
小学生の通信教育おすすめ14選【2026年最新】安い教材もランキング比較
子どもの教育には学費だけでなく、習い事や塾の費用など何かとお金がかかるもの。 小学生のうちは、家庭学習に「費用がリーズナブルで内容が充実した通信教育を取り入れたい」と考えるご家庭も多...
2026.01.28|コエテコ byGMO 編集部
-
高校生向け通信教育おすすめランキング11選【2026年最新】自宅学習比較
高校生向けの通信教育はさまざまな種類があるため「どれが良いのか分からない」という人も多いのではないでしょうか。本記事では、自宅学習にもおすすめの高校生向け通信教育ランキングを紹介します...
2026.02.01|コエテコ byGMO 編集部












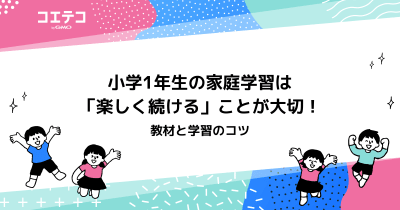
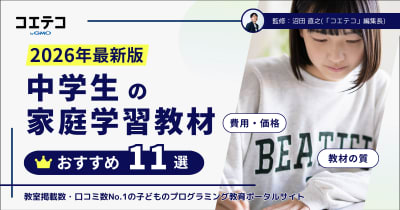

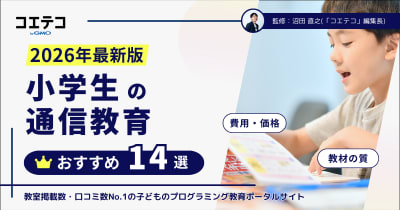
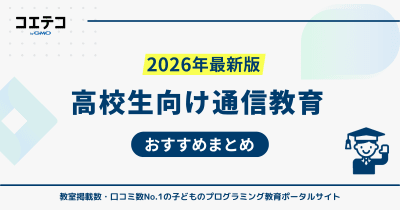
ママもパパもがんばっているんですよ!でも、子どもが「やる気」を出してくれないのが辛いところ…