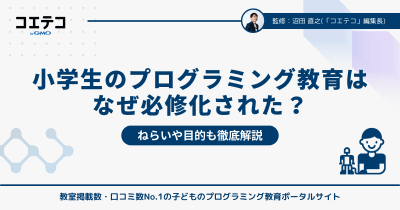世界の教育分野のICT利用率ランキング|日本の順位は?
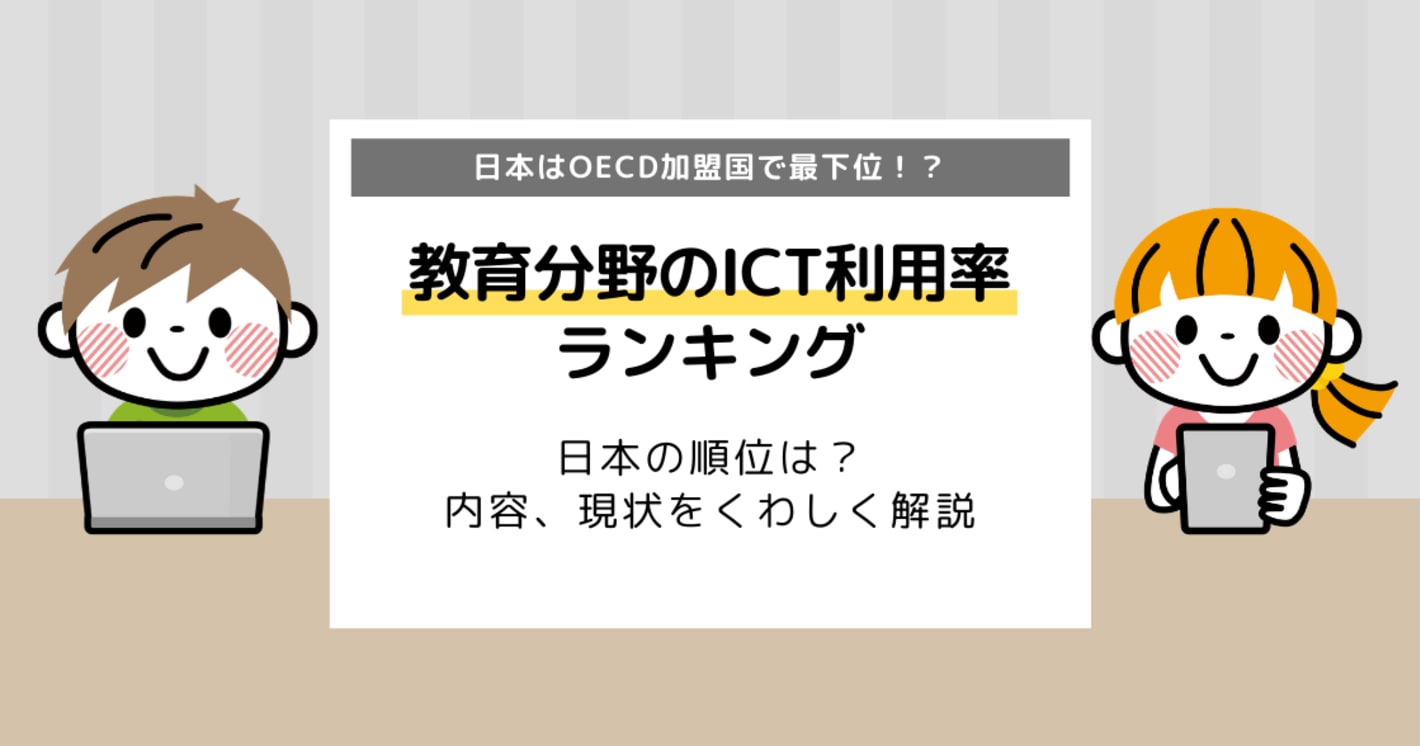
※ 本コンテンツにはプロモーション(PR)が含まれています。
海外に比べて遅れを取っていると言われる日本のICT教育ですが、実際のところどうなのでしょうか?
この記事ではOECDの調査結果を確認しながら、日本の学習環境についてまとめます。
そもそも、「ICT」って?
ICTとは、Information and Communication Technologyの略で情報通信技術という意味です。人とインターネットが繋がることや、インターネットを通して人と人が繋がることを指します。
ITという言葉も耳にしますが、ITは情報技術そのもののことで、最近ではICTという言葉の方がよく使われるようになりました。
総務省のホームページによれば、これから日本が抱える様々な問題(地域経済の活性化、社会保障費の増大、大規模自然災害)に対応するため、社会の様々な分野(農林水産業、地方創生、観光、医療、教育、防災、サイバーセキュリティ等)でのICTの有効活用が不可欠となると述べられています。
2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説します。
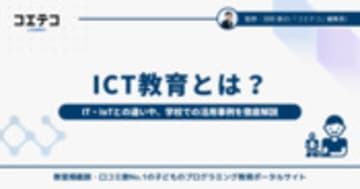

2025/05/30

ICTの活用は日本でも進んでいます。
今後の日本の問題解決や経済発展にはICTの活用は必要不可欠です。
そのために、ICTを使いこなせる人材を育てることが国の課題となっていきます。
ICTを教育に導入することにより、どのような効果が期待されるのでしょうか?
効果や普及への課題について見ていきましょう。
教育におけるICT活用
近年、世界中の教育現場で電子黒板やタブレット、パソコンなどのICT機器が導入され活用されています。これまでの教育は、黒板とノートを使用し、先生が板書したものを生徒が書き写し、内容を覚えるスタイルの一方的な授業がほとんどでした。
教科書の範囲を終わらせる事が目的のような授業ですよね。
総務省によると、ICTを教育に取り入れる意義はトリプルAにあるといいます。具体的には、このようなねらいがあります。
- Active(アクティブ) 主体的に学ぶことにより、学ぶ力を活性化する
- Adaptive(アダクティブ) AIの技術により、一人一人の習熟度が見える化し個人に合った学習が可能となる
- Assistive(アシスティブ) 学びの支援
ICTを取り入れることにより、先生から生徒への一方的な教育から、生徒たちが主体的に考え、未来に求められる力を育む教育へと変化するのです。
教育分野でICTを活用するとどう変わる?
効率化が可能
画面を通して一斉授業が可能になります。また、板書が不要な分、授業時間を有効活用できます。先生の授業準備も短縮できます。授業のための資料作成時間が省けたり、授業後は保存がきくので編集を加えながらブラッシュアップも可能です。
学習システムの中には、自分の得意や苦手を分析してくれる機能があるシステムもあります。一人一人の苦手を把握することで、先生や親の指導もしやすくなり、効果のある学習が期待できます。
授業が分かりやすくなる
タブレットと電子黒板を一緒に使用することにより、回答をすぐに表示できたり、自分の作ったプレゼン資料もすぐに表示できるので、発表もわかりやすくなります。先生の説明が分かりやすくなります。以前は紙媒体の資料や先生の図解などが主流でしたが、本物の写真や動画を映し出すことができ、ズームなども簡単にできるのでイメージしやすくなります。生徒自身が楽しく学べるのも魅力です。
ICT機器の使い方を覚える
将来的にもパソコンやタブレットが使いこなす力が必ず必要となります。小学生から授業で使うことによって、機器を使いこなしたり、ICT機器やアプリを用いて何ができるのかを理解できます。別の地域の人と交流ができる
例えば、海外の小学生と通話ができたり、専門家の先生の話を聞いたりと、実際には会うことが難しい人と話すことができます。世界の教育ICT利用率ランキング
2018年に行われたPISAのICT活用調査によると、北欧のスウェーデンやデンマークなどが上位にランクインしています。スウェーデンは特に国語、算数、理科、社会、英語においてICT機器を利用しており、1週間のうち教室の授業でデジタル機器を使う時間がもっとも長いとされています。また、オセアニア州のオーストラリアやニュージーランドも授業中の使用時間が長く、上位となっています。
日本は授業中のデジタル機器使用時間がOECD加盟国の中で最下位となり、2022年に行われた調査でもOECD平均を下回る結果となりました。
日本はなんで遅れてるの?
ICTは世界レベルで必要とされ、普及しているにも関わらず、なぜ日本は遅れをとっているのでしょうか。日本がICT化を進めていくためには様々な課題があると言われています。予算の確保が難しい
学校環境を整えるとなると、単純にICT機器を一人一台配布すればいいわけではありません。インターネットやセキュリティ対策にも予算が必要となります。
また、ICTで教育ができる人材がいなければ、予算をとっても無駄になってしまいかねません。
ICTの重要性を理解し力を入れている自治体はすでに教員へ教育から始まり、ICTを教育現場に取り入れています。しかし、そうでない自治体が多いため、地域によって格差もあります。
教員の負担が増える
ICT機器を導入し、それを効率的に勉強をするための道具として扱うためには教師が操作を覚える必要があります。しかし、現在の先生方が皆ICT機器を使いこなせるわけではありません。今の教育と並行して、ICT機器を使いこなし、授業を作り上げるためには教員の負担が大きいというのが現状です。
民間教育でのICT活用
ICT教育の推進や2020年から小学校でプログラミングが必修化に伴い、民間でもICTで楽しく学べるアプリの開発や、通信教育などが増えました。最近は、小学生のプログラミング教室も人気の習い事となっています。家庭学習の中でICT機器に触れる機会を与え、楽しく学ぶ経験が学習意欲にもつながります。
公教育でのICT活用
学校教育でも地域格差はありますが、ICTを取り入れる学校が徐々に増えつつあります。スクールタクトやロイロノートスクールなど様々な学習支援システムが開発され、使用されています。アクティブラーニングでは、タブレットを用いて自分たちで調べ、写真を撮ったり、プレゼンの資料を作成したりする際にも使われています。
教育が変わろうとしています。先生が一方的に授業をし、生徒は受け身で聞くだけ......というパッシブ(受動的)な学びではなく、生徒がみずから学ぶアクティブ(能動的)な授業に変わろうとしているのです。この記事ではアクティブラーニングについてくわしくご紹介します。
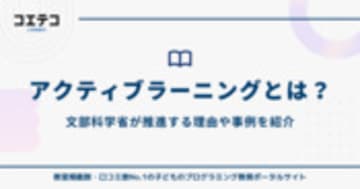

2025/11/12

ICT活用能力はますます重要に
今や、仕事の中でPCなどの情報機器を扱わないという人の方が珍しいのではないのでしょうか。一昔前まではPCを少し使うことができただけでスキルとなっていましたが、今の時代はそうもいきません。そのため、小学生のうちからICTのリテラシーを身に着けることは、未来のために非常に重要なこととなってきます。今までは対面での授業が当たり前でしたが、今後は遠隔地同士でのやり取りや、動画で学習も増えていくことでしょう。もちろん対面の授業にも良いところはありますが、ICTを活用することでより効率的に勉強を進めていくことができます。ICTの技術や知識は、子供たちがこれから勉強して成長していく過程において、土台となるスキルになるといえます。
まとめ
今後の日本を考えると、教育現場でのICTの活用は必要不可欠です。国だけでなく、自治体の協力や民間企業との連携を図りながら、ICTを用いた教育を浸透させていくことが大切ですね。


Amazonギフトカードプレゼント中!
あわせて読みたいガイド

RECOMMENDこの記事を読んだ方へおすすめ
-
日本は遅れてる?海外のプログラミング教育の現状!
日本では小学校のプログラミング教育が2020年から必修化されることになっており、中学校では2012年から「技術・家庭科」で「プログラムによる計測・制御」が必修の授業として行われています...
2025.06.24|さえ
-
ICT教育とは?ITやIoTとの違いと学校での活用事例を徹底解説
2020年、プログラミング教育が必修化します。そんな中でよく耳にするのが「ICT」という言葉。「IT」とはどう違う?学校にICT環境が整うとどんなメリットが?現状、実態は?くわしく解説...
2025.05.30|プログラミング教室ガイド
-
小学生のプログラミング教育はなぜ必修化された?ねらいや目的も解説
2020年から小学生でプログラミング教育が必修化されることになりました。プログラミング教育は本当に必要なのでしょうか?なぜ必修化されることになったのでしょうか?プログラミング教育の目的...
2025.11.17|コエテコ byGMO 編集部
-
mBotとは?STEAM教育を楽しく学べるロボットプログラミング教材
2020年4月より小学校でプログラミング教育が必修化します。それに伴い、全国各地でプログラミング教育への関心が高まっています。このページでは、初心者でもOKなSTEAM教育ロボット、m...
2025.05.30|コエテコ byGMO 編集部
-
Viscuit(ビスケット)とは?無料でプログラミング学習ができる?
2020年4月より小学校でプログラミング教育が必修化します。この記事では「コンピュータは粘土だ!!」というポリシーで開発された、対象年齢4歳以上のビジュアルプログラミング言語Viscu...
2025.11.17|プログラミング教室ガイド